- TOP
- ガーデン&ショップ
-
東京都

吉谷桂子さんのガーデン「the cloud」から学ぶ“ナチュラリスティックな庭づくり”③ 〜おすすめプランツ〜
適地適草でレイアウトを植物の性質を調べておこう 「the cloud」は西向きの庭で、背後は神宮の森がそびえて朝日がまったく当たらない。夏の太陽がもっとも厳しくなる左側のエリアは西日や乾燥に強い植物で、黄色やオレンジの花が咲くものが多い。高木の北側にあって日照時間が短い右側のエリアは、半日陰を好む日本の在来種で、ピンクや白の花が咲くものが多い。 ロングライフ・メンテナンス・フレンドリーを目標とした、今までにないガーデン制作を行っている吉谷さん。これまでの経験を活かし、高温多湿に耐えられる日本の在来種を取り入れているのもこのガーデンの特徴です。ただ、長生の植物はゆっくりと育つので、見応えと順応性が最終的に分かるのは3年後と考えて、作庭から1〜2年目は、華やかさが出る短命の宿根草や、初年度からたくさん花が咲く一年草も加えています。 上左/ややしっとりとしたエリアを彩る、ヒオウギとカラマグロスティス‘ゴールドタウ’ (7月)。上右/ベンチ+パーゴラ裏で視線が抜けるのをストップ。ルドベキア・マキシアとヒヨドリバナ(7月)。下/シードヘッドになったペンステモン‘ダコタバーガンディ’の銅葉が植栽に深みを与えつつ、引き締め役として活躍(11月)。 また、吉谷さんにとって丈夫で絶対確実な植物だけでなく、ヨーロッパなら大丈夫だけれど、ここではちょっとどうかな? というチャレンジングなものも入れています。 「全体の約2割がチャレンジプランツです。植物の魅力を知るには常にトライ&エラー。環境への順応は試してみないと分からないし、 ガーデニングは自然との共存について学べる大切なチャンスです。 失敗は決して無駄にはならないはず。いろいろと可能性を考えてトライしてみて」。 最大の合い言葉は「適地適草」まずは、植物の性質を調べておこう! 「植物のセレクトとその配置には理由があり、好きな植物をなんとなく植えてはダメ。簡単ではないかもしれないけれど、エコロジーとデザイン両面の適地適草を前提に、美を備えながら気候の変動にも耐えて長生、行儀のよい植物を見極めて」と吉谷さん。 美しい自然な風景を作るには、「植える場所の環境」と「植物の特性」を把握し、『RIGHT PLANT, RIGHT PLACE (適材適所・適地適草)』で花壇に落とし込むことが大切です。 【チェックポイント】 ・丈夫で風土環境に合っているか?(ただし侵略的でないこと)・四季を通して行儀がよいか?(暴れにくい、倒れにくい、花枯れ後の姿が汚くない・シードヘッドも魅力的であること) ① なるべく長期間生きて、その地に順応するか、花が咲くか?(翌年以降も持続して美しい草姿で、花が咲くこと)② 生物多様性、蜜源植物としても役立ち、病害虫に強いか?(命の循環、病害虫に侵されてもまあまあ復活できること。益虫もやってくるとよい) ふわっとして、エアリーなグラスや、蜜源花の代表、バーベナ・ボナリエンシス。その少し下で花後のアガパンサスやエキナセアのフォルムがアクセントに。その下方手前でアガパンサスの葉群やベンケイソウが植物の株元をしっかりガード/9月 ‘the cloud’で重宝した代表的な植物 36選 ガーデンでさまざまな役割を担った、メンバーの一部をご紹介します。ここで取り上げていない植物たちも、それぞれにいい役割を果たしています。 ■細い葉が魅力のグラス類 透け感抜群。軽やかな穂が風に揺れ、植栽の上部分(奥)で、表情豊かなナチュラル感を強めてくれます。 左/ディスカンプシア‘ゴールドタウ’ 中/ミューレンベルギア・カピラリス 右/パニカム‘ヘビーメタル’ 左/ディスカンプシア‘ゴールドタウ’イネ科草丈:約80cm特徴:穂の観賞期は初夏から。たくさん穂を上げ、細かい黄褐色となる。秋には穂が乾いて色が抜け始めるが、冬も楽しめる。ほかのグラスとは異なり多湿を好む。常緑~半常緑性。 中/ミューレンベルギア・カピラリスイネ科草丈:60~90cm特徴:夏~秋にかけて丈のあるピンクの花穂が大人気。初めはつややかだが、冬には色あせる。丈夫で大きく育つので根の張るスペースが必要。日照・風通し、根張りの場所が制限されると倒れやすく、花穂も上がりにくくなることも注意。 右/パニカム‘ヘビーメタル’イネ科草丈:約160cm特徴:葉がまっすぐに直立する姿はオーナメンタルな存在感がある。葉色は、夏まではメタリックなブルーグリーン、秋に上がる繊細な穂と葉は黄金色に変化して直立性も高い。 左/メリニス‘サバンナ’ 中/カラマグロスティス‘カールフォースター’ 右/カラマグロスティス・ブラキトリカ 左/メリニス‘サバンナ’イネ科草丈:約50cm特徴:ブルーグリーンの葉と秋に葉や穂が赤くなるのも魅力的。丈が高くならず、株もコンパクトにまとまるので狭小地でも楽しめるが、こぼれ種で増えるので、コントロールが多少必要なことも。 中/カラマグロスティス‘カールフォースター’イネ科草丈:100~150cm特徴:葉茎、穂が直立する、ナチュラリスティックガーデン代表のグラス。5月頃から上がるすっきりとしてスリムな穂が魅力。穂が出たあと徐々に黄金色に変わり、冬枯れの姿もオーナメンタルな趣がある。 左/カラマグロスティス・ブラキトリカイネ科草丈:約80cm特徴:日本名はノガリヤス。葉はグリーンで柔らかく扇状に弧を描く。羽根のように膨らむ穂は、はじめは明るいグリーンで徐々にシルバー~クリーム色へと移ろう。倒れにくく丈夫。 ■ボールドで頼りになるアガパンサス 巨大花からコンパクトものまで多種あるヒガンバナ科の球根植物。高温化の夏に負けない頼もしい植物で、‘the cloud’では8種類も植えています。美しい花を咲かせることに加え、常緑の葉が低い位置(花壇の手前)をがっしりカバーする役割も。 左/アガパンサス‘クイーンマム’ 中/アガパンサス‘サマーラブ’ 右/アガパンサス‘ポッピンパープル’ 左/アガパンサス‘クイーンマム’草丈:50~70cm花期:初夏特徴:超巨大多花性タイプで、白花を咲かせる花房は約25cmにもなる。ボリュームたっぷりに花をつけるので華やかな印象。 中/アガパンサス‘サマーラブ’ 草丈:約50cm花期:初夏~秋特徴:葉が細く花首がさほど伸びないコンパクトな品種。花色は白と青があり、春から秋まで咲く四季咲き性タイプ。 右/アガパンサス‘ポッピンパープル’草丈:30~60cm花期:初夏~初秋特徴:ほかの品種よりも株はコンパクトで半常緑性。花色は濃紫で花つきがよく、大人っぽい雰囲気が漂う。 ■日陰気味・湿り気味の場所を彩る植物 ほかの場所とは異なる、しっとりとした趣も出してくれます。 左/アネモネ‘アンドレア・アトキンソン’ 中/シュウメイギク‘パミナ’ 右/アスチルベ 左/アネモネ‘アンドレア・アトキンソン’キンポウゲ科草丈:80~120cm花期:夏~秋特徴:アネモネの仲間でシュウメイギク系のハイブリッド品種。純白の花を夏から秋と長期にわたり咲かせる。耐寒性は強く半日陰向き。土壌が肥沃すぎると徒長して倒伏する場合がある。 中/シュウメイギク‘パミナ’キンポウゲ科草丈:約80cm花期:秋特徴:華奢に見えるが花穂は高くならず、株はややコンパクトで倒れにくく丈夫。発色のよい濃いピンクの花は半八重咲き。 右/アスチルベユキノシタ科草丈:90〜120cm花期:初夏特徴:春に白やピンクの細かい花を穂状につける。夏以降に茶色く枯れた花穂をそのまま残しておくと、オーナメンタルな姿が楽しめる。 ■日本在来種、もしくは古くから親しまれてきた植物 日本の風土に合っていて、とにかく丈夫! 左/ミソハギ 中/オミナエシ 右/ヒヨドリバナ 左/ミソハギミソハギ科草丈:50~100cm花期:7~9月特徴:日本各地の湿原や田の畔などに生えている植物で、湿り気のある土地を好む。やや木質化する茎に、鮮やかなマゼンタピンクの花を穂状にたくさんつける。 中/オミナエシオミナエシ科草丈:60~100cm花期:8~9月特徴:秋の七草の一つで、黄色い小花を平らな散房状にたくさん咲かせる。低い場所で葉を広げるので、雑草が広がりにくい。 右/ヒヨドリバナキク科草丈:40~120cm花期:8~10月特徴:茎の上部の散房状花序に、白色または淡紅紫色の頭花を密につける。山地の林縁に多く自生。野趣にあふれる。 ■銅葉が美しいもの ダークな葉色がナチュラルな植栽をぐっと引き締めてくれます。 左/ベルゲニア‘ダークマージン’ 中/ペンステモン‘ハスカーレッド’ 右/ペンステモン‘ダコタバーガンディ’ 左/ベルゲニア‘ダークマージン’ユキノシタ科草丈:約40cm花期:春特徴:革のような質感で光沢のある厚い常緑葉。春~秋は葉縁に赤い縁取りが入り、晩秋以降は葉全体に赤みが濃くなる。花色はピンク。 中/ペンステモン‘ハスカーレッド’オオバコ科草丈:80~100cm花期:初夏特徴:ブロンズ色の葉がカラーリーフとして楽しめ、白花とのコントラストが魅力。春の芽吹きはより濃色で、花後は暗い緑色になる。タネもシックな印象。 右/ペンステモン‘ダコタバーガンディ’オオバコ科草丈:約60cm花期:初夏~秋特徴:光沢のある赤みがかったダークな葉に、濃ピンクがにじむ花をつける。ペンステモン‘ハスカーレッド’よりも葉が赤黒く、コンパクトな品種。 ■彩りが寂しい春先に毎年咲き続ける小球根 一度植えれば、毎年グラウンドカバーとしても活躍しながら、愛らしい花色で春の到来を告げてくれます。 左/イフェイオン‘アルバートキャスティロ’ 左/シラー・シビリカ 右/スイセン‘テタテート’ 左/イフェイオン‘アルバートキャスティロ’ユリ科草丈:10~20cm花期:早春特徴:可憐な白い星形の花をいっぱいに咲かせる。植えっぱなし可能でグラウンドカバーにも最適。細い青々とした葉は初冬から展開して花後に休眠し、地上部は枯れる。 左/シラー・シビリカユリ科草丈:10~15cm花期:早春特徴:ベルのように下垂した花は非常に可憐で房状に咲く。花色は白と青紫。緑の細い葉は開花前に展開する。 右/スイセン‘テタテート’ユリ科草丈:20cm花期:早春特徴:鮮やかな黄色の愛らしい花を咲かせるコンパクトなスイセン。早春の植栽ににぎやかさを与えてくれる。 ■シードヘッドが楽しめるもの ユニークな造形が、秋の風情を深めてくれます。 左/エキナセア‘マグナススーペリア’ 中/ヒオウギ 右/ルドベキア‘リトルヘンリー’ 左/エキナセア‘マグナススーペリア’キク科草丈:60~150cm花期:初夏~初秋特徴:ライラックピンクの花弁×赤い花心の組み合わせが鮮やか。花径が大きく、夏の植栽に元気な存在感を与えてくれる。花心が乾いて残る。 中/ヒオウギアヤメ科草丈:40~100cm特徴: 夏特長:夏の花も扇形に立ち上がる葉姿も、どちらも美しい。また、秋に風船のような種袋ができ、それが割れると中から真っ黒なタネが現れるところも非常に魅力的。万葉の昔はそれを‘ぬばたま’と呼んだ。 右/ルドベキア‘リトルヘンリー’キク科草丈:60~90cm花期:初夏~夏特徴:筒状の細長い花弁がユニークで、茶色い花心とのコントラストが愛らしい。半日陰でも咲く丈夫な小型種。蝶を呼ぶ。 ■オーナメンタルに花が楽しめる球根 細い柄に花房がつき、風に揺れる浮遊感も楽しめます。 左/アリウム‘パープルレイン’ 中/アリウム・シューベルティー 右/トリテレイア‘シルバークイーン’ 左/アリウム‘パープルレイン’ネギ科草丈:約60cm花期:春特徴:鮮やかな赤紫の星形の花を放射状につける、植えっぱなし可能な丈夫なアリウム。早咲き種。 中/アリウム・シューベルティーネギ科草丈:30~50cm花期: 初夏特徴:ネギ坊主が花火のようにパッと広がる巨大輪のピンクのアリウム。放射状に広がる花柄はそのままの形で乾いて残る。 右/トリテレイア‘シルバークイーン’ ユリ科草丈:30~40cm花期:初夏特徴:針金のように細い茎に、ラッパ形の白い花をたくさん咲かせる。掘り上げなくても毎年植えっぱなしでよく開花する。 ■暑さと干ばつにも強いストレスフリーな宿根草 昨今の酷暑を乗り越える性質を備えながら見応えがある頼もしい種類です。 左/アガスターシェ‘ブルーフォーチュン’ 中/アリウム‘サマービューティー’ 右/セダム(ハイロテレフィニューム)‘オータムジョイ’ 左/アガスターシェ‘ブルーフォーチュン’シソ科草丈:約80cm花期: 夏~秋特徴:シソの穂を細かくしたような花穂をたくさん上げ、淡いブルーの花を長期にわたり咲かせる。花後は花穂がシードヘッドになり、秋から冬の間も見応えたっぷり。 中/アリウム‘サマービューティー’ネギ科草丈:20~40cm花期:夏特徴:小型のアリウムで、球形・ピンク色の花をつける姿はチャイブに似ている。厚めの葉をたくさん展開し、グラスのよう。暑さに強い。 右/セダム(ハイロテレフィニューム)‘オータムジョイ’ ベンケイソウ科草丈:30~60cm花期:晩夏~秋特徴:丈夫な茎が立ち上がり、多肉質な葉を広げながらこんもりと育つ。花はピンクからローズピンクに移ろい美しい。ほぼ水やりは要らず、肥えていない土=貧しい栄養環境だとうまく育つ。また、西日の厳しい場所に植えるのに向いているが、少し湿り気があるところだと巣蛾(すが)でダメージを受ける場合がある。 ■グラウンドカバーで活躍する宿根草 表土を隠し、雑草防止や乾燥予防に役立ちます。 左/セラトスティグマ 中/エリゲロン・カルビンスキアヌス 右/リッピア・カネスケンス 左/セラトスティグマ(ルリマツリモドキ)イソマツ科草丈:30~60cm花期:夏~秋特徴:1~2cmのコバルトブルーの花が次々と長い間咲き続け、茎葉をこんもりと密生させながら、株は横に広がるように成長する。秋には紅葉も楽しめる。 中/エリゲロン・カルビンスキアヌスキク科草丈:10~30cm花期:春~秋特徴:小輪多花性で、長期間咲き続ける。咲き始めは花弁が白く徐々に赤みを帯びていくので、2色咲いているように見える。性質も強い。 右/リッピア・カネスケンスクマツヅラ科草丈:10~30cm花期:春~秋特徴:地面を這うように成長して広がり、各節から根を根付かせながら密に地面を覆う。また、白やピンク色の花を次々に咲かせる。 ■ふわりと間をつないでくれる一年草(一年草扱いの宿根草) 一年草や短命な宿根草は、春の庭に早くから花を咲かせます、成長が早く、しかもこぼれ種で増えるので、侵略的ではないタイプを選んで(オルラヤなどは増えすぎた場合のコントロールが大変なので場所を選ぶとよい)。 左/ニゲラ・ダマスケナ 中/セントランサス・コキネウス アルバ 右/バーベナ・ボナリエンシス 左/ニゲラ・ダマスケナキンポウゲ科(一年草)草丈:40~90cm花期:春特徴:白や青、ピンクなどの花弁のような萼片も、ふわふわとした糸状の葉も花後の風船形のシードヘッドも魅力的。一年草ながら開花前から開花後まで見頃が長い。こぼれ種から出る糸葉の新芽は雑草との見分けがつきやすいので、コントロールがしやすい。 中/セントランサス・コキネウス アルバオミナエシ科(一年草扱いの宿根草)草丈:約60cm花期:春特徴:ベニカノコソウの白花種で小花が集まって咲く。花つきが非常によく、こんもりと茂ると見応えたっぷり。宿根草で、環境に合えば温暖地の場合は常緑で冬越しする。短命だがこぼれ種で増える。 右/バーベナ・ボナリエンシスクマツヅラ科(一年草扱いの宿根草)草丈:70~100cm花期:初夏~秋特徴:強健で自立性が高く細長い茎が分岐した先に、紫の小花を咲かせる。昆虫たちにも人気が高くタネもできやすいので、適度に軽めの剪定をして、花を長く咲かせながら株の状態を保つとよい。日当たりがよく、少し乾き気味な環境を好み、条件が合えばこぼれ種でよく増える。冬越しした株は翌年も開花する。 『ガーデン・メリット』がある植物を選ぶ意味 「“花の美しさや愛らしさ”はガーデンプランツを選ぶ上で重要な選択肢となりますが、それにプラスして、芽出しの時期から枯れるまで、ずっと庭景色に魅力を与えてくれる『ガーデン・メリット』がある植物を選ぶことも大切です。 それを見極めるには、一度やってみる。失敗しながらも発見を楽しむ。“トライ&エラー”の精神で挑んでください。年を追うごとに経験値を積んでいけば、人生はきっと充実するはず。エコロジーにあった、強く美しい植物の存在を知ることは、私たちの心を癒やし、人生を豊かにしてくれる“庭”の可能性を広げてくれますよ」と吉谷さん。 連載4回目となる次回は、「ガーデン環境整備」についてご紹介します。
-
東京都

吉谷桂子さんのガーデン「the cloud」から学ぶ“ナチュラリスティックな庭づくり”②〜植栽デザイン〜
役割が決まっていれば配置しやすい! 吉谷式デザインメソッド 雲形の花壇の中に、四季を通して見応えのある『マルチプランティング』がなされている。 ■吉谷式メソッド1 自然な植栽に見せる■ ここの花壇は直線的ではありませんが、縁どりから60~90cmの幅、手前のボーダー(帯状)植栽エリア、それより花壇中央寄りの内側はマス(集合)植栽に分けられており、基本的にボーダーエリアには確実に元気に育つ植物、内側にトライアルな植物を植えています。 実際の植栽前に描いていた卓上のプランから、実際の植物の様子次第で変更も出て、描き足している。 それは、もしトライアルで植えた植物が倒れたり調子が悪くなったりしても、外側の強健な植物が確実に茂ることでカバーしてくれるから。また、花がら摘みが必要なものは手前、不要なものは奥に配してとお手入れを楽にしたのもポイントです。苗は3ポットを基本のトライアングル(三角)で連続的に植え、連鎖性(つながり)を持たせることで、自然に見えながら散らかって見えないように整然とした秩序を保っていることが植栽デザインのポイントになります。 花壇の外側は、常緑性の強健な植物がボーダー状に植えられている/2月 ■吉谷式メソッド2 安定感を生み出す■ 「ガーデンデザインは、劇場の舞台デザインがヒント」と、かつて広告美術などを手掛けていた吉谷さん。舞台では場面場面の展開があり、「床をダークで重い色に、天井は明るく軽い色にすることで軽重のバランスを取る。手前のものを大きく、奥を小さくすることで遠近感を出す」などを意識することで、景色に安定感が生まれます。これらが逆になると、景色が不自然でバランスも不安定に。ガーデンデザインも同様で、この基本を押さえて環境に合った植物を組み立てれば、景色が作りやすくなります。 植栽の下側はアガパンサスでがっしり、上側はカラマグロスティスやバーベナ・ボナリエンシスで軽くふんわりとさせて、安定感のある景色を作り出している。 【Keyword】 ■下(花壇手前):Bold・がっつり・重め 風景の下方となる花壇の手前:丈夫でしっかりとした形・質感をもつ重い印象の植物を植える。 ■上(花壇奥):Transparency・ライト・軽め風景の上方となる花壇の奥:丈のある軽やかな植物を植える。 これは軽重のバランスと遠近感を具体的に表したもので、風景の下となる花壇の手前には、しっかりとした形・質感で重い印象かつ丈夫な植物を植えます。西日や乾燥に強い『がっつり重い印象』の肉厚な葉っぱの常緑植物がおすすめ。それに対し、風景の上側となる花壇の奥には、丈があっても軽やかな植物を植えます。『ふわふわとした印象』のグラス類などがおすすめです。 こうすることで、がっつりプランツがふんわりプランツの株元を西日から守ったり、支えたりするほか、手前がはっきり・後ろがふわふわとすることで視覚的な遠近感や豊かな表情を生み出し、絵画的ともいえるランドスケープが作りやすくなります。 【がっつり・重め代表】アガパンサス、ベルゲニア、オランダセダム(オオベンケイソウ)など比較的、多肉質な葉の宿根草 【ライト・軽め代表】グラス類、シュウメイギク、バーベナ・ボナリエンシスなど比較的、背が高くて風に揺れる細長い宿根草 ■吉谷式メソッド3 植物を建築的、彫刻的に使いこなす■ 植栽は、植物の異なる色・形・質感の組み合わせの連続です。隣り合う植物は似たもの同士にならないように注意し、互いに引き立て合うものを選びます。同じようなものを並べると、ガチャガチャ散らかったように見えてしまいます。 ふわふわしたものとカチッとしたもの、また、点・線・面とさまざまなフォルムの植物を組み合わせたりすることで、「絵画的」な風景が描けます。「Using plants as an architecture(植物を建築のように扱う)」というイギリスのガーデンデザイナーの言葉が大きなヒントです。 青紫~ライトグリーンのグラデーションが幻想的なワンシーン。エリンジウム‘ブルーグリッター’などのトゲトゲとした花や、ルドベキア・マキシマの浮遊感のある細い花茎がシーンの印象を深めて/6月 まずは、フォルム・役割を考える ・アクセントプランツ……目を引いてアクセントになる植物(エキナセア、大型花のルドベキアやアリウムなど) ・フィリングプランツ……細かい花穂や葉群、間をつなぐ植物(アスター、グラスの穂など)ディスカンプシアなどのグラス類、ニゲラなど) *フィリングプランツは、アクセントプランツの間をつなぐだけでなくバックスクリーンにもなるが、背の高いグラス類は、その背景でスクリーンプランツとなる。 ・スパイクプランツ……尖った花穂などが縦の線を描き、シャープな印象を与える植物(リアトリス、アスチルベなど) ・線を描くプランツ……ラインを描き、動きや伸びやかさを与える植物(グラス類など) ・点を描くプランツ……ドットを作りリズムを生む植物(アリウムの花穂、ストケシアなど) ・面を描くプランツ……葉の面積が広く、落ち着きをもたらす植物(ベルゲニアなど) ふわふわと広がるニゲラの奥にアリウム‘パープルレイン’の丸い花穂がプカプカと浮かぶ、愛らしい風景/5月 直線的なヒオウギの葉と曲線を描くディスカンプシア ‘ゴールドタウ’の絵画的競演/9月 ■吉谷式メソッド4 レイヤーで魅せる■ 園路は風通しを確保するため、最低1.2~1.4mの幅が取られています。広すぎないほうが感覚的な親密さを感じられ、さらに目の高さに花があると五感に迫ってきます。植物が出しているエネルギーや香りなどが、見る人の感覚に訴えてくるのです。また、「the cloud」の花壇は雲形で入り組んでいるので、囲まれ感・包まれ感もたっぷり。没入感を楽しみながら落ち着きも感じられます。 ペンステモン‘ハスカーレッド’のシードヘッドの造形が、透明感のあるミューレンベルギア・カピラリスに浮かび上がっている/10月 そこで必要なのが「植栽をレイヤーで魅せる技」。手前とその後ろに来るものをどのように重ねるのか、植物が成長する前からデザインの計算をします。例えば、傘状に咲くアンジェリカや尖塔状のアスチルベの花穂を透かして見せるエアリーなグラスなど、横からの風景にも気を配っています。 植物越しに吉谷さんを撮影したスナップ。アリウム‘パープルレイン’やセントランサス・コキネウスなどの中に、吉谷さんが浮かび上がっているように撮れている。 「記念写真を撮るときに植物を背景にするのもいいけれど、植物越しに人物が写るようにアングルを選ぶと、草花と一体感のある写真が撮れます。あちこちに撮影映えスポットを設けているんですよ」と吉谷さん。 人と植物が重なる風景までも考えられています。 “美しい庭をデザインする”ために 紫がかるアンジェリカ ‘ビカースミード’のシックな花房、手前下はアスチルベ、その背景にグラスのエアリーな穂、紫の反対色となるヒオウギの黄色い花などが、重層的な風景を織り成している/7月 美しいガーデンをつくるには、植物の生態や個性を識った上で、色・形・質感の違いや醸す印象を見極め、それをどう組み合わせて活かせるかを考えることが大切です。吉谷さんは、「the cloud」で使うプランツリストに、それぞれの特徴や役割も書き込み、偏りがないかなどを確認しながらデザインをしています。 「移ろう季節と気候が景色を変えていく。『庭をデザインするということは植物を絵の具にして絵画を描くこと』と、英国の作庭家、ガートルード・ジーキル氏は言っています。100年前のジーキルの時代には想像もできなかった気候変動の中で、この考えは普遍です」。 ぜひ、吉谷さんのメソッドを庭づくりの参考にしてください。次回のテーマは、丈夫で活躍してくれる『おすすめプランツ』です。
-
東京都

吉谷桂子さんのガーデン「the cloud」から学ぶ“ナチュラリスティックな庭づくり”① 〜1年の移り変わり〜
吉谷さんが牽引する「宿根草を中心に考えた植栽による21世紀のガーデンづくり」大々的にスタート! 「the cloud」が作られたのは、JR山手線「原宿」駅から徒歩3分の「都立代々木公園」の中。原宿門から入ってすぐ右手の「オリンピック記念宿舎前広場」の右側にあります。 「東京パークガーデンアワード」は、「持続可能(サステナブル)なガーデンへの配慮がなされているか」「メンテナンスしやすいか」を考慮することが条件となっている画期的なコンテスト。モデルガーデンである「the cloud」も同様に、宿根草をメインに植栽設計がされました。ハイメンテナンス、ハイインプットになりがちな“花の満開時が見どころ”の観光ガーデンとは大きく趣旨が異なります。 光や風を感じさせる軽やかな植栽/10月 持続可能で新たな宿根草の世界に触れることができる『New Prennial Plants Movement(新宿根草主義)』。植物の植生の仕組みを理解した上で、自然の風景を手本とするこのスタイルは、特にオランダのピート・アウドルフ氏による「ナチュラリスティックガーデン」により近年注目されるようになり、欧米で主流になっています。 そしてこれが今、地球沸騰ともいわれる気候変動などを抱えた私たちを癒やしてくれる新たなソリューションとして大いに期待されています。 「干ばつがひどいイギリスでもサステナブル、エコフレンドリーであることが主流となっていますが、植物は丈夫で長もちであることが核ですね」 広い公園の中でぷかぷかと浮かぶように広がる「the cloud」。 けれど、長もちの植物を集めただけではなく、アートフォルム(デザイン性)もなくてはと吉谷さん。 「ここ代々木が、アウドルフさんが手がけたニューヨークにある高架線路跡をリノベーションした公園『ハイライン』のようになればと思っています。映える場所が好きな若い人たちや洗練された大人、そして子どもたち皆が楽しめる場所を目指しています。レアな植物が植わっていなくてもいいんです。来るのが楽しみになるガーデンになれば」 花も満開だけに注力しない、芽出しから枯れるまでのプロセスが楽しめる植栽となっています。 「the cloud」と名付けられた理由とこの形になった理由 ユニークな形をしている花壇ですが、これは吉谷さんがこの場所に初めて立ったとき、夏空に浮かぶ雲や背景の明治神宮に広がるモクモクとした森を見て、直感的に‘雲’と連想したもの。ガーデンデザインは、背景と庭が調和して一体化することを目標としていることからも、ぴったりだったと言います。 くねくねと入り組んだ形は、植物をいろいろな角度からよく観賞できるほか、手入れもしやすいという利点があります。 花が少なくても、青々と柔らかい葉が美しい植栽/3月 【ナチュラリスティックガーデン「the cloud」の6つのメソッド】 1. 自然な雰囲気、季節ごとの変化を感じられる庭。エコロジカルな機能性にデザインの創造性を感じさせるデザインですが、基本的にローメンテナンスを目指した設計です。 秋に透明感のある彩りを添えるシュウメイギクは、ヨーロッパでも注目されている。吉谷さんが自宅の庭でもずっと育てている丈夫な長生きプランツ/11月 2. 生物多様性に柔軟な植物構成(農薬不使用、チョウの好む品種などを中心にして昆虫も共存)。 チヨウやハチを呼ぶ蜜源植物、バーベナ・ボナリエンシスなどが選ばれている/7月 3. ローインプット(丈夫で長生きな宿根草や球根植物を選び、季節ごとの植え替えをせず、主に植えっぱなしの宿根草で、異なる季節の花の開花があること)を目指しています。 眺めの統一感のため、初夏から秋にかけて、下方では肉厚な葉、上に行くに従って軽やかで透明感のある植物を選んでいる/11月 4. 猛暑・大雨、逆に雨が降らず極度な乾燥の冬にも耐えうる植物の選択。対処し得る花壇の構造を設計し、21世紀の日本における存続可能な草花選び(日本原産や身近な植物にも着目)をしています。同時に装飾性も感じられる庭。庭の一部には写真映えするスポットがあり注目の草花が咲くことにも配慮していますが、それは、桜の頃やゴールデンウィーク、夏休みといった集客時期に合わせた開花品種を選んでいます。冬の枯れ姿も味わいある眺めとしたい。 左:紫と白のアガパンサスが群れ咲く。アガパンサスは、暑さや乾燥にも強く、東京なら冬も常緑で病害虫の心配もない持続可能な宿根草/7月 右:花後の花茎もオーナメンタルに楽しめるように、タネを取り除き茎を残した、夏以降のアガパンサス。 5. 宿根草により完成された根張りの植物コミュニティを形成(雑草が生えにくくなる)するには、通常3年ほどかかりますが、期間が限定されるため、初年度はなるべく土の余白を残さず、雑草の入り込む余地を与えないためと、ある程度の華やかさを補足するため、まめな花がら摘みを必要としない一年草も設計に加えています。 左:雑草防止のグラウンドカバーとして植栽されたニゲラ。雑草との見分けのつきやすい葉の品種を選んでいる/1月 右:低く伸び花後のタネも景色の一部になった/5月 6. モデルガーデン「the cloud」は、地面から10〜30cm上げたレイズドベッド(盛り土花壇)であり、水はけや風通しを確保しながら、草丈の低い植物の見栄えもよい構造です。また、花壇に個性を与えるために雲海のような膨らみの強弱のあるデザインになっていますが、これは一般のボランティアスタッフにとっても、作業・維持管理がしやすいよう配慮されたもの。花壇の幅は浅く、土に踏み込まなくても手入れがしやすい形なのです。 植え付け当初。花壇の縁がくっきりと見えていた/12月 【「the cloud」の植栽プラン】 植えられた植物数 宿根草:100種類、3,615株 球根:9種類、9,350球 東側に明治神宮の森、西側に野原が広がる代々木公園の隅に位置する「the cloud」。約40×15mの敷地の中にモクモクとした雲形の花壇が7つ設けられ、吉谷さん厳選の植物たちが配植されました。アートフォーム(デザイン性)がありつつ公園や明治神宮の森に調和し、四季折々の楽しみを提供するような植栽設計となっています。 モデルガーデン「the cloud」の初年度12カ月 【冬】例年どおりの気温で、積もる降雪はなし 11月 植え付け当日。著名なガーデンデザイナーなどメンバー8人の力を借りて、4日間で施工。土壌改良(連載第4回参照)、アイアンの仕切りを設置した後、数千株の苗を植栽。球根を植えたところに棒を立てて目印をつけている。 2月 植え込みから2カ月経ったが、まだまだ大きな変化は見られない。寒さにあたってアガパンサスの葉が黄色く、ベルゲニアが赤くなっているが、どれも順調に元気に育っている。小さな黄色いスイセン‘テタテート’が咲き始めた。 【春】例年どおりの気温、降雨 3月 まだまだ色彩の寂しい植栽に、黄色いスイセン‘テタテート’とイフェイオン‘アルバートキャスティロ’が愛らしい彩りをプラス。 4月 イフェイオンは、全部でなんと5,000球。丈夫で冬の干ばつにも耐え毎年よく花をつける小球根を植えることで、花の少ない時期の花壇がにぎやかになる。 5月 まぶしい新緑の花壇の中で、アリウム‘パープルレイン’の花穂がファンタジックな風景を描いている。 【夏】梅雨がほとんどなく、かつてない酷暑・干ばつに加え、突発的なゲリラ豪雨が数回あり 6月 ストケシアやモナルダなどが咲き始め、にぎやかさが増してきた。 7月 全体的に緑が深くなってきて、あちこちに植えたアガパンサスが満開に。 8月 干ばつのような暑さのなかでも元気に育つ、生命力あふれるたくましいガーデン。背が高くなる宿根草も少なくないが、頭が重くならず向こうが透けて見えるような品種を選んでいる。 【秋】いつまでも気温が高かったが、10月末に冬日となる日が数日あり。夏からずっと台風の到来はなし 9月 さまざまなグラスの穂が、それまでとは異なる趣を見せ始めた。 10月 秋風に揺れる、暑さを乗り越えたたくましい植物たち。 11月 晩秋はミューレンベルギア・カピラリスがピンク色に。銅葉のペンステモンもアクセントに。 「the cloud」作庭から1年を経て 吉谷さんならではの緻密な計算と抜群のセンスがぎっしりと詰め込まれた「the cloud」。 「春先の気温が高かったため、1年で予想以上に大きく育ち慌てる場面もありましたが、ライトプランツ・ライトプレイス、適地適草を見極めて、来春はもっと安定的に宿根草が楽しめるようにしていきたいです」と吉谷さん。 次回は、この美しい風景づくりに用いられた、吉谷さんによる『植栽デザイン』についてご紹介します。
-

クリスマスの寄せ植え&森の動物たちが集まるかわいいガーデンクリスマス
モミの木の寄せ植えツリー 昨年のクリスマスツリー。いつも待合室の窓からよく眺められる場所に置いています。 クリニックの庭のクリスマス演出は、患者さんたちも楽しみにしてくれている年末恒例のイベント。庭に飾るクリスマスツリーは毎年、テーマを決めてイルミネーションの色やオーナメントを変えているので、12月が近づくと、「今年はどんなふうになるの?」と聞かれるようになりました。そう聞かれたら張り切らないわけにはいきません。一緒に庭づくりをしているガーデナーの安酸友昭さんに「今年はどうするだ?」と相談すると、今年は「小さいツリーにしましょう」という意外な提案が。毎年庭には3m以上のツリーを飾ってきたので、それを小さくするのは不安でしたが、あれこれと安酸さんの指示に従って進めるうちに、いつもとは少し違う、かわいいガーデンクリスマスが出来上がりました。 大鉢に樹高150cmくらいのモミの木を植え、株元にはパンジーを植栽。その鉢の手前にいつも庭で使っている小さめのガーデンテーブルを置いて、パディントンベアを着席させました。「ほら面谷さん、パディントンから見たら、このツリーは大木ですがん」と安酸さん。庭づくりは想像の翼を広げることが大事と安酸さんはいつも言いますが、本当にそのとおり。パディントンから見たら、この庭は大きな森かもしれません。というわけで、今年のテーマは「森の動物たちのクリスマスパーティー」になりました。 パディントンたちのおかげで、冬の寂しい庭が一気に楽しい雰囲気に。患者さんも窓からたくさん写真を撮ってくれています。 モミの木の株元にはイルミネーションの色に合わせた優しい色のパンジーとアイビーを寄せ植え。 テーブルコーディネートで庭に彩りを 冬の庭はどうしても彩りが寂しくなりがちですが、ガーデンテーブルをコーディネートすると、庭に効果的に鮮やかさを演出することができます。赤のタータンチェックと緑の布は手芸店で買ったもので、雨をはじくように防水スプレーをしてあります。その上にはキャンドル入りのバスケットアレンジを置きました。アレンジも扉にかけた大きなリースも、赤がポイント。これは私がアレンジの練習に通っている東京・神楽坂の「ジャルダンノスタルジック」さんが作ってくれました。 テーブルにはハリネズミやフクロウも遊びに来ました。びしょ濡れになるとかわいそうなので、この子たちも防水スプレー済み。 夜になり、ライトアップをすると、ボックスウッドの後ろから鹿が! じつはこれ、安酸さんお手製の影絵です。防水加工をした紙に鹿を描いて、丁寧に切り抜いて作ってくれました。テーブルの下に紙の鹿を置いて、扉へ投影しています。いつも言葉数少なく「ふーん」とか「へー」とかばかり言っている安酸さんですが、その頭の中には楽しいアイデアがあふれているようです。よくこんなことを考えつくなぁと感心します。 紙の鹿は風で飛ばされないように、木の板と針金で留めてあります。室内ならもっと手軽にできるはずです。紙とライトと映し出す壁があればできますから、ぜひ作ってみてください。きっとお子さんも喜ぶと思いますよ。 クリスマスの寄せ植え 寄せ植えもクリスマスカラーで植栽しました。パンジーやガーデンシクラメン、チェッカーベリー、スキミアは赤で統一。ブルーグリーンのツンツンとした葉は、ピナス・ピネアと呼ばれるイタリアカサマツです。小さなツリーのようで、クリスマスの寄せ植えにぴったりです。赤色の寄せ植えは、夜は色が闇に沈んで見えにくくなるので、室内の明かりがこぼれる窓辺のすぐ側に置いています。 白っぽい色でまとめた寄せ植えは、夜のライトアップにもよく映えます。中央には草丈の高いキンギョソウを、周りには淡い色合いのパンジーやネメシア、白色のカルーナ、スイートアリッサムを植栽。鉢縁からは斑入りのアイビーやハツユキカズラを垂らして動きを持たせました。 ガーデンの入り口にも、大鉢のモミの木の寄せ植えを作りました。静かな森の水辺をイメージし、ブルー系のパンジーを株元に植栽しました。モミの木に吊したのは氷で作ったオーナメントで、中に庭の花を閉じ込めました。 シリコンの製氷機に花と水、吊すためのワイヤーも一緒に入れて凍らせます。いずれ溶けてしまうはかないオーナメントですが、したたる滴もきれいです。 大きなツリーはなくても、庭にちょっとしたストーリーを持たせると楽しい雰囲気が生まれます。想像の翼を広げて、ガーデンクリスマスを楽しんでみませんか。
-
東京都

「第1回 東京パークガーデンアワード 代々木公園」1年の取り組み
毎日見学者が訪れる「代々木公園」がコンテスト会場 昨年12月に作庭され、毎日公開しているコンテストガーデンとモデルガーデンがあるのは、JR山手線「原宿」駅から徒歩3分の「都立代々木公園」の中。原宿門から入ってすぐ右手の「オリンピック記念宿舎前広場」です。敷地の奥は、緑深い明治神宮の森が背景となり、右手から日が昇る日当たりがよい開けた場所。かつては陸軍代々木練兵場だったところで、その後はワシントンハイツ、東京オリンピックの選手村と時代とともに変遷ましたが、「オリンピック記念宿舎」今も保存されています。 「オリンピック記念宿舎」までの通路沿いの左右に、5つのガーデンが作られています。右奥の広場には、吉谷桂子さんによるモデルガーデン「the cloud」も公開中。11月上旬の様子。 「第1回 東京パークガーデンアワード」の最大の特徴は、主に宿根草などを取り入れた「持続可能なロングライフ・ローメンテナンス」をテーマとする点。一度植え付けて根付いたあとは、最小限の手入れで維持されること、また同時にデザイン性と植物や栽培環境に対する高度な知識が求められる、新スタイルのガーデンコンテストです。 コンテストガーデンが作られている敷地の平面図。A〜Eの各面積は約72〜85㎡ 。どのエリアでガーデンを制作するかは、2022年11月に抽選により決定しました。 ここでテーマとなる「ロングライフ・ローメンテナンスな花壇」とは、季節ごとの植え替えをせずに、丈夫で長生きな宿根草や球根植物を中心に使って、植えっぱなしで、異なる季節に開花の彩りが楽しめる花壇のこと。2022年10月に5つのデザインの作庭が決定し、同年12月上旬にはそれぞれの区画で1回目の土づくりと植え付けが完了しました。 「第1回 東京パークガーデンアワード 代々木公園」11月上旬最終審査が行われました 2022年12月に行われた5つのガーデン制作に関わった皆さん。審査委員の正木覚さんと吉谷桂子さんを囲んで。 【第1回 東京パークガーデンアワード in 代々木公園 最終審査までのスケジュール】 2022年10月20日 応募締め切り10月31日 書類による本審査 5名の入賞者決定12月5〜9日 入賞者によるガーデン制作①2023年2月27日〜3月3日 入賞者によるガーデン制作②4月 ショーアップ審査(春の見ごろを迎えた観賞性を審査)7月 サステナブル審査(梅雨を経て猛暑に向けた植栽と耐久性を審査)11月上旬 ファイナル審査(秋の見ごろの観賞性と年間の管理状況を審査)全3回の審査を踏まえ、総合評価のうえ、グランプリ・準グランプリ・特別審査委員賞の決定11月 審査結果の発表・授賞式 「第1回 東京パークガーデンアワード」は、5名の参加者決定から最終審査の結果発表まで1年かけて行われる、新しい試みのコンテストです。これまで、12月に1回目のガーデン制作、2月下旬に2回目の植え付けや手入れがされ、4月に「ショーアップ審査」、7月に「サステナブル審査」、11月上旬に秋の見ごろの鑑賞性と年間の管理状況を審査する「ファイナル審査」が行われました。酷暑を乗り越え、晩秋のガーデン風景へと移り変わったコンテスト会場をぜひご覧ください。 「第1回 東京パークガーデンアワード 代々木公園」すべての審査が終了しました! 審査委員/福岡孝則(東京農業大学地域環境科学部 准教授) 正木 覚(環境デザイナー・まちなか緑化士養成講座 講師) 吉谷桂子(ガーデンデザイナー) 佐々木 珠(東京都建設局公園緑地部長) 植村敦子(公益財団法人東京都公園協会 常務理事) 4月、7月、11月の3回の審査では、5名の審査委員による採点と協議により行われました。審査基準は、以下の8つの項目です。1. 公園の景観と調和していること 2. 公園利用者のためのデザインであること 3. 公園利用者が美しいと感じられること 4. 造園技術が高いこと 5. 四季の変化に対応した植物(宿根草など)選びができていること 6. 「持続可能なガーデン」への配慮がなされていること(ロングライフ) 7. メンテナンスがしやすいこと(ローメンテナンス) 8. デザイナー独自の提案ができていること グランプリ コンテストガーデンCGarden Sensuous ガーデン センシュアス コンテストガーデンC 季節の変化 11月上旬のコンテストガーデンC 「Garden Sensuous ガーデン センシュアス」 審査員講評緩やかなアンジュレーションと植栽との基本構成がしっかりしていて、年間を通して安心して見ていられるガーデンでした。厳しい夏を超えてなお目立ったダメージも少なく、全体としては自然風のガーデンである中で植栽配置が季節ごとにきちんと秩序を保ち、公共のガーデンにおける理想の新しい庭を見ているようでした。緑の質感と色のグラデーションが印象的で、エッジの曲線を活かした公園風景との一体感・透明感の作り方にも技術の高さを感じます。コンセプトの通り、来園者の感覚に優しく、静かに訴えかけるガーデンが見事に表現されていました。 ⚫︎コンテストガーデンCの月々の変化は、こちらからご覧いただけます。 準グランプリ コンテストガーデンBLayered Beauty レイヤード・ビューティ コンテストガーデンB 季節の変化 11月上旬のコンテストガーデンB 「Layered Beauty レイヤード・ビューティ 」 審査員講評一年中見どころの絶えないガーデンで、スタートから全力投球でのパフォーマンスに感服させられました。特に春、夏は、植物の色や質感の重厚なレイヤーが圧巻の美しさを作り出していました。確かな技術のもと引き出された多種の植物のパフォーマンスを間近で見ることができ、プロのガーデナーにとっても、今年のような酷暑にどの植物が効果的に、美しく、サスナブルに生きていけるのかを学ばせてくれる素晴らしいチャンスとなりました。思わず写真を撮りたくなる風景が四季折々に作られ、人々を惹きつける“植物の力”を再認識できるガーデンであったと感じます。 ⚫︎準グランプリを受賞したコンテストガーデンBの月々の変化は、こちらからご覧いただけます。 審査員特別賞 コンテストガーデンAChanging Park Garden ~変わりゆく時・四季・時代とともに~ コンテストガーデンA 季節の変化 11月上旬のコンテストガーデンA 「Changing Park Garden ~変わりゆく時・四季・時代とともに~」 審査員講評エントランスを飾るに相応しい、華やかなガーデンでした。色・質感がバリエーションに富んでいて、園路の際いっぱいまで活用した伸びやかな造形が公園の景色に調和すると共に、他にはない個性となっていました。慣れない東京の環境、遠方からの参加という厳しい条件の中で手入れのタイミングを逃してしまった時期も見うけられましたが、ローメンテナンスのもと最終審査の頃にはしっかりと再生させた手腕も見事で、秋には大きく育った宿根草の魅力や存在感が抜きん出ていました。年間を通じて、宿根草の豊かな表情の変化を見せてくれました。 ⚫︎コンテストガーデンAの月々の変化は、こちらからご覧いただけます。 入賞 コンテストガーデン DTOKYO NEO TROPIC トウキョウ ネオ トロピック コンテストガーデンD 季節の変化 11月上旬のコンテストガーデンD「TOKYO NEO TROPIC トウキョウ ネオ トロピック」 審査員講評明確なコンセプトのもと、他には無い珍しい植物を存分に満喫する楽しみを来園者に提供してくれました。熱帯植物の彫刻的な美しさが、高低差のある植栽配置やレイズドベッドへの寄せ植えの手法でより引き立ち、ディテールを鑑賞する楽しさや芸術性を感じながらガーデンを見ることができます。バイオネストの活用をはじめ年間を通じてのローメンテナンス、また、熱帯植物を公園のガーデンに取り入れるという実験的な視点で挑んだ点も評価が高く、今後、気候変動への対応が益々求められる中で、植栽デザインの一つの解答になり得ると感じています。 ⚫︎コンテストガーデンDの月々の変化は、こちらからご覧いただけます。 入賞 コンテストガーデン EHARAJUKU 球ガーデン コンテストガーデンE 季節の変化 11月上旬のコンテストガーデンE 「HARAJUKU 球ガーデン」 審査員講評タイトル通り、それぞれの季節に浮き上がる球状の花・植物が魅力的な、非常にビジュアルなガーデンでした。色調が統一された植栽は可愛らしさとシックさを両立しており、洗練されたお洒落さと、オリンピック記念宿舎を背景にした際のフォトジェニックさが特に際立ち、HARAJUKUという場所にマッチしています。ディテールにセンスの光る植栽デザインが垣間見えると共に、一般の庭づくりでも参考になる部分が多く見られた点も来園者に喜ばれたと評価します。デザイナーの世界観が十分に表現され、その温かな想いや愛情が伝わってくるガーデンでした。 ⚫︎コンテストガーデンEの月々の変化は、こちらからご覧いただけます。 Pick up 月々の植物 11月の植物 左から/サルビア‘アメジストリップ’(Aエリア)/ノコンギク‘夕映’(Bエリア)/アネモネ(シュウメイギク)‘パミナ’(Bエリア)/リアトリス‘フロリスタンホワイト’のシードヘッド(Cエリア) 左から/リアトリス・スカリオサ ‘アルバ’のシードヘッド(Cエリア) /パイナップルサングリア(Dエリア) /コレオプシス( Dエリア) /クジャクアスター(Dエリア) 10月の植物 左から/ペルシカリア(Aエリア)/ユーパトリウム‘羽衣’(羽衣フジバカマ)(Bエリア)/カラミンサ・ネペトイデス(Cエリア)/パンパスグラス‘ゴールデン・ゴブリン’(Dエリア) 左から/アスター・ラテリフローラス 'レディ・イン・ブラック’(Dエリア)/サルビア・アズレア(Eエリア) /カカリア( Eエリア) /アネモネ‘アンドレア・アトキンソン’( モデルガーデン) 9月の植物 左から/ミューレンベルギア・カピラリス(Aエリア)/パトリニア・プンクティフローラ(Bエリア)/アスター’アンベラータス’(Bエリア)/ガイラルディア‘グレープセンセーション’(Cエリア) 左から/ペニセタム’JS ジョメニク’(Cエリア)/ハナシキブ ‘ヒントオブゴールド’(Dエリア) /アスター’ジョリージャンパー’( Eエリア) /フロックス’オールドブルー’( モデルガーデン) 8月の植物 左から/ペニセタム‘テールフェザー’(Aエリア)/ヘレニウム’レッドシェード’(Aエリア)/バーノニア・ファスキクラータ(Bエリア)/ユーパトリウム‘レッドドワーフ’(Bエリア) 左から/リアトリス・スカリオサ ‘アルバ’(Cエリア)/ルドベキア・サブトメントーサ‘ヘンリーアイラーズ’(Dエリア) /アリウム’サマービューティ’(Eエリア) /アネモネ・トメントーサ(モデルガーデン) 7月の植物 左から/フロックス‘フジヤマ’(Aエリア)/ヒオウギ‘ゴーンウィズザウィンド’(Bエリア)/アガスターシェ‘ブルーフォーチュン’(Bエリア)/エキナセア‘バージン’(Cエリア) 左から/カンナ(Dエリア)/アメリカフヨウ(Dエリア)/エキノプス‘プラチナムブルー’( Eエリア) /ヘリオプシス’ブリーディングハーツ’ (Eエリア) 6月の植物 左から/サルビア・ウルギノーサ(Aエリア)/エキナセア‘ラズベリートリュフ’(Aエリア)/アキレア‘ウォルターフンク’(Bエリア)/フロックス‘ブライトアイズ’(Bエリア) 左から/リアトリス‘コボルト’(Cエリア)/ラティビタ ‘レッドミジェット’(Cエリア)/ポピーマロウ(Dエリア)/ポンポン咲きダリア( Eエリア) 5月の植物 左から/エレムルス‘ロマンス’(Aエリア)/クニフォフィア・シトリナ(Aエリア)/ダウクス・カロタ‘ダラ’(Bエリア)/クラスペディア・グロボーサ(Bエリア) 左から/エリンジウム‘ブルーグリッター’(Cエリア)/リクニス・コロナリア(Dエリア)/ホルデューム・ジュバタム(Eエリア)/カンパニュラ‘サマータイムブルース’(モデルガーデン) 4月の植物 左から/ユーフォルビア・ウルフェニー(Aエリア)/フリチラリア・エルウェシー(Bエリア)/ラナンキュラス・ラックス‘アリアドネ’(Bエリア)/アジュガ'チョコチップ’(Cエリア) 左から/フロックス・ピロサ(Dエリア)/エリゲロン・カルビンスキアヌス(Dエリア)/アリウム・シルバースプリング(Eエリア)/アリム‘パープル・レイン’(モデルガーデン) 3月の植物 左から/アネモネ・デカン(Aエリア)/スイセン 'ペーパーホワイト’(Bエリア)/フリチラリア‘ラッデアナ’(Bエリア)/イベリス(Cエリア) 左から/サルビア・ネモローサ(Dエリア)/ベロニカ‘オックスフォードブルー’(Eエリア)/イフェイオン‘アルバートキャスティロ’(モデルガーデン)/シラー・シビリカ(モデルガーデン) 2月の植物 左から/スイセン‘ティタティタ’(モデルガーデン)/アリウム 'シルバースプリング’(Aエリア)/ユーフォルビア ウルフェニー(Aエリア)/カレックス テヌイクルミス(Bエリア) 左から/アジュガ レプタンス(Cエリア)/リナリア プルプレア 'アルバ' (Cエリア)/ガウラ リンドヘイメリ ’クールブリーズ'(Dエリア)/アリウム ‘サマードラマー’(Eエリア) 1月の植物 左から/アネモネ(エントランス花壇)/パンパスグラス‘タイニーパンパ’(エントランス花壇)/スティパ・イチュー(Aエリア)/苗から植え付けたアリウム‘サマードラマー’(Bエリア) 左から/レモンバームやオレガノ'ヘレンハウゼン’、 'ノートンゴールド’など(Cエリア)/ユーフォルビア‘ブラックバード’(Dエリア)/エルサレムセージ(Dエリア)/ニューサイラン(Eエリア) 全国から選ばれた5人のガーデンコンセプト 「持続可能なロングライフ・ローメンテナンス」をテーマに、各ガーデナーが提案するガーデンコンセプトは、5人5様。それぞれが目指す庭のコンセプトや図面、植物リストの一部をご紹介します(応募時に提出された創作意図や植物リストを抜粋してご紹介)。 コンテストガーデンA【審査員特別賞】Changing Park Garden ~変わりゆく時・四季・時代とともに~ 【作品のテーマ・創作意図】時間や四季の移ろいと共にドラマチックに展開する宿根草ガーデンは見る人の心を豊かにします。たとえば秋の夕景は、光が植物たちの魅力をいっそう引き出してくれる、もっとも美しい時間でしょう。公園の緑花空間は、来園者に感動や癒やしを提供する場所であり、さらに植物を通してコミュニティが生まれ「共感」の時代へと変化しつつあります。人々に愛される場所であることが真の持続可能なガーデンとなるのではないでしょうか。さまざまな意味で変化する公園のガーデン≪Changing Park Garden≫をテーマに、◆Chillax (チラックス) ◆Community(コミュニティ) ◆Challenge(チャレンジ)3つの「C」をコンセプトにガーデンデザインを計画します。【主な植物リスト】サルビアネモローサ カラドンナ/ユーフォルビア ウルフェニー/エキナセア パープレア/アガスターシェ ゴールデンジュビリー/ネペタ シックスヒルズジャイアント/ヘリオプシス ブリーディングハーツ/サルビア ミスティックスパイヤーズ/アジュガ ディキシーチップ/ペニセタム ビロサム/カレックス フェニックスグリーン/ペニセタム テールフェザー/アリウム イエローファンタジー など 合計84種 コンテストガーデンA 月々の変化 【11月中旬】 ペニセタム‘テールフェザー’やミューレンベルギア・カピラリス、ペニセタム‘ビロサム’などのさまざまなグラスが隣り合う植物を透かすように穂を広げる間では、先月から引き続きサルビア‘ミスティック・スパイヤーズ’の青花やエキナセア‘ラズベリートリュフ’の鮮やかなピンクがアクセントになっています。園路にはみ出すほど匍匐して広がる黄金葉のオレガノ‘マルゲリータ’や銀葉のエリムス・アレナリウスなど葉色のバリエーションが楽しめるうえ、11月になって、サルビア‘アメジストリップ’やカンパニュラ・ラプンクロイデス(下中央)が咲き始めて彩りが一層増しています。 【10月下旬】 先月から穂を伸ばし始めたさまざまなグラス類が穂を広げ、花壇にリズミカルな景色を作っています。6月から休むことなく咲き続けているサルビア‘ミスティック・スパイヤーズ’がさらに花を増やし、存在感がさらにアップ。低い位置では、エキナセア‘ラズベリートリュフ’の鮮やかなピンク(下中央)や、アキレア‘ラブパレード’、ペルシカリア、シルフィウム・モーリー(右下)などがカラフルな花色のアクセントを添えています。 【9月下旬】 高温が続き、雨量も少ない過酷な夏を超え、6月から引き続き咲き続けているサルビア‘ミスティック・スパイヤーズ’が未だ健在。エキナセア‘ラズベリートリュフ’の鮮やかなピンクに加え、アキレア‘ラブパレード’(右下)やクニフォフィア・シトリナが再び開花。カラマグロスティス・ブラキトリカやペニセタム・アロペクロイデス(チカラシバ)など、さまざまなグラス類が穂をあげてガーデンのアクセントになっています。 【8月中旬】 7月から穂が伸び始めたペニセタム‘テールフェザー’(上写真右側)が大株に育ち存在感を発揮しています。6月から引き続き咲き続けているサルビア‘ミスティック・スパイヤーズ’(下左)やバーベナ‘バンプトン’に加え、8月は、ヘレニウム’レッドシェード’(下中)が花束のようにダイナミックに咲き、夏に切り戻したベロニカ‘ファーストキス’(下右)が再び咲き始めています。 【7月中旬】 各株が大きくなり、混ざり合って茂る真夏。6月から引き続き咲き続けるスカビオサ・オクロレウカやサルビア‘ミスティック・スパイヤーズ’などに加え、メリカ・シリアタ(写真下左)スティパ・イチュー(写真下中)、ペニセタム‘テールフェザー’(写真下右)など、さまざまなグラスの穂が伸びていて、花壇に動きが感じられます。 【6月中旬】 植物の成長が進み、一つずつの植物のボリュームが増して緑の量も増えました。6月に開花が始まったエキナセアの鮮やかなピンク色の花にペニセタム・ピロサムの穂が寄り添っていたり、5月に白花を咲かせていたバレリアナ・オフィシナリスの花がらが雲のように優しい景色を作っています。サルビアの青花、ペニセタム・テールフェザーなどが丈高い植物が背景でスクリーンのようになり、アリウムが宙に浮かんでアクセントになっています。 【5月中旬】 5月になると一気に成長が進み、まったく地面が見えないほど、どの植物もボリュームアップ。4月中旬に花壇のフレームからはみ出すほど成長していたスタキス ビザンティナ(右下)は、花穂を立ち上げ、周囲の植物と色の対比を見せています。花壇の後方では、白花のバレリアナ・オフィシナリスやエレムルスが背丈ほどに伸び、景色が立体的になりました。 【4月中旬】 3月に咲き始めたアネモネ・デカンは、まだまだ花数を増やし、他の植物も2倍、3倍と草丈が高くボリュームが増してきました。スタキス・ビザンティナ(英名ラムズイヤー、右下)は、花壇のフレームからはみ出るほどに葉を伸ばし、アリウムにはつぼみがついています。葉の形状の違いや草丈の差が出て、花壇が立体的になってきました。 【3月中旬】 アネモネ・デカンの葉が増え、白・紫・赤・ピンクとカラフルに花が咲き出しています。また、原種チューリップ‘ポリクロマ’も開花中。スタキス・ビザンティナやアリウム 'シルバースプリング’、ユーフォルビア ウルフェニーも存在感を増し、緑の量が日に日に増えています。 【2月中旬】 斑入り葉のカレックス・オシメンシスや黄金葉のカレックス‘ジェネキーが日に輝くなか、サルビア・ネモローサ‘カラドンナ’やスカビオサ・オクロレウカ、スタキス・ビザンティナなどが地面に張り付くように葉を広げています。 【1月中旬】 コンテストガーデンB【準グランプリ】Layered Beauty レイヤード・ビューティ 【作品のテーマ・創作意図】季節を感じる宿根草ガーデンを作るということは、さまざまなレイヤーを組み合わせて、美しさを構築するということだと考えています。<植物のレイヤー・時間差のレイヤー・バランスのレイヤー・地下部のレイヤー>これまで、多くのデザイナーやガーデナーとの交流の中で、どの植物がガーデンの中でどんな役割を果たしているか、また、どんな植物が耐久性があるのか、今後どういった植物を提案したらよいかなどについて蓄積してきた引き出しとアイデアがあり、それらを、今回提案できればと考えました。デザインにおいては、感性だけではなく、植物生産者としてサステナブルで、かつ美しく見える植栽の構築について理詰めでデザインする(=一般化できる)手法を取り入れ、その過程をオープンにできればと思っています。 【主な植物リスト】 <グラス類>パニカム チョコラータ/カラマグロスティス ブラキトリカ/ミスカンサス モーニングライト/ルズラ ニベア/スキザクリウム スモークシグナルなど <宿根草(高)>ユーパトリウム レッドドワーフ/パトリニア プンクティフローラ/ヒオウギ ゴーンウィズザウィンド/フィリペンデュラ ベヌスタなど <宿根草(中)>エキナセア(オレンジパッション、マグナス スーペリア他)/ヘリオプシス ブリーディングハーツ/アムソニア ストームクラウドなど <宿根草(低)>ゲウム マイタイ/アリウム(サマービューティ、イザベル、メデューサ)/ベロニカウォーターペリーブルー/カラミンサ ブルークラウドなど <日本由来の植物>イカリソウ(4-5種)/ヤマトラノオ/ノコンギク夕映/ユーパトリウム羽衣/シュウメイギク パミナなど <一年草・二年草>ラークスパー/アンスリスクス/アンミ/フロックス クリームブリュレ/タゲテス ミヌタ/クラスペディアなど <球根類>フリチラリア(ラッデアナ、ペルシカ、エルウェシー)/シラー ミスクトケンコアナ/クロッカス プリンスクラウス/ミニチューリップなど 合計142種 コンテストガーデンB 月々の変化 【11月中旬】 見上げるほど丈高く、まるで雲のようにピンク色の小花をふんわりと咲かせているユーパトリウム‘羽衣’(羽衣フジバカマ)の株元では、ノコンギク‘夕映’が紫の花を多数咲かせていたり、低い位置では茶色く色づくグラスとエキナセア‘ミニベル’がコラボレーションしているなど、花壇のあちこちでシックなカラーコーディネイトが楽しめます。ルドベキア‘ブラックジャックゴールド’のシードヘッド(花がら)が黒く残って宙に浮かび、花壇のアクセントとしても役立っています。 【10月下旬】 先月から次々と穂を伸ばしているグラス類がスモークのように穂を広げている効果で、花壇全体がやさしい印象です。人の背丈を越すほど大きくなったユーパトリウム‘羽衣’(羽衣フジバカマ)には小さな花を咲かせて赤みを添えています。ピンクの花を咲かせていたガイラルディア‘グレープセンセーション’は花びらが落ちた後、丸い花芯が残って道沿いのアクセントになっています。アガスターシェ‘ブルーフォーチュン’やヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’が引き続き咲くなか、アスター・ラテリフローラス 'レディ・イン・ブラック'やノコンギク‘夕映’など秋を感じさせる花が咲いています。 【9月下旬】 園路沿いに低く茂るグラスの間からガイラルディア‘グレープセンセーション’(左下)などが再び花を増やし、アガスターシェ‘ブルーフォーチュン’やヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’も引き続きガーデンの彩りに貢献。高低差のあるさまざまなグラスも存在感を増すなか、パトリニア・プンクティフローラ(上写真中央)やユーパトリウム‘羽衣’(羽衣フジバカマ)が人の背丈を越すほど大きくなり、デザインの変化となっています。 【8月中旬】 8月になると園路に沿ったの花壇の縁を隠すほどグラスの穂がふわふわと茂り、まるでスモークのよう。8月に咲き始めた多数のアリウム‘メデューサズヘア’(下左)やヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’(下右)、ガイラルディア‘グレープセンセーション’などが穂と混ざり合い、ユーモラスな景色が見られます。7月から涼しけなブルーの花が継続して咲いているアガスターシェ‘ブルーフォーチュン’は、突然の強い雨風や猛暑にも耐えて彩りに貢献しています。 【7月中旬】 5〜6月から咲き続けているダウクス・カロタ‘ダラ’やフロックス‘ブライトアイズ’、エキナセア‘ミニベル’に加え、7月は、ヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’やアガスターシェ‘ブルーフォーチュン’が花を増やしています。花壇の中には、秋に向けてぐんぐん成長するものや、これから咲く蕾もスタンバイしています。 【6月中旬】 6月になると、エキナセア‘イブニンググロー’や‘ブルーベリーチーズケーキ’、アキレア‘アプリコットデライト’や‘ウォルターフンク’などの暖色系の花に主役がバトンタッチして、さまざまな色彩が楽しめます。間に茂る銅葉のアンスリスクス ‘レイヴンズウィング’によって花色が際立って見えたり(左下)、ゲラニウムの黄金色の葉にエキナセアが引き立って見える(右下)など、植物同士のコラボレーションが楽しめます。 【5月中旬】 4月中旬からアクセントになっていた大小さまざまなアリウムは、次の開花を迎えるアリウムとバトンタッチしながら、咲き終わってボール状の花がらのまま残っているなか、エリンジウム(右下)やクラスペディア・グロボーサなど、新しい花色が多数組み合わさって、場所ごとに異なるカラーハーモニーが楽しめます。花から種になるもの、蕾から花を咲かせるもの、いろいろな植物の姿が一緒に見られます。 【4月中旬】 12種も植えられていたチューリップは3月から順次咲き始めて、4月中旬までバトンタッチするように咲き継ぎました。4月中旬は、ラナンキュラス・ラックスやカマシア、アリウムの彩りが加わって一層華やかに。花壇の土を盛り上げた効果で、奥に咲く花の様子もよく見えます。 【3月中旬】 花壇手前には、ピンクやブルー、白のムスカリが次々と開花し、花壇中央では、スイセン‘ペーパーホワイト’が開花。黄花のミニチューリップ・シルベストリスも花束のように咲いています。アリウム・ギガンテウムは、葉をダイナミックに繁らせ、地面を隠すほどに成長。暖かい日が続いて、多くの植物が目覚めています。 【2月中旬】 苗から植え付けたアリウム‘サマードラマー’が前月よりも2倍の高さまで伸び、スイセン‘ペーパーホワイト’(左下写真中央)はつぼみが膨らんでいます。オーニソガラムやチューリップ、クロッカスなど、あちこちで芽吹きが確認できます。ふわふわと茶色の細葉を伸ばすのは、カレックス・テヌイクルミス。 【1月中旬】 コンテストガーデンC【グランプリ】Garden Sensuous ガーデン センシュアス 【作品のテーマ・創作意図】私たちの感覚に訴えかけるガーデン、Garden Sensuous。日本の古の歌人・俳人たちは、森羅万象、感情の機微や情緒、美しい風景を歌に詠んできました。その美しさへの眼差しは自然環境への知見を踏まえた、高度に知的で文化的なものであったと考えられます。そしていま、これからの環境について考える場合、サステナブルやエシカルであることは、無視できないトピックです。サステナブルなガーデンであること、エシカルなガーデンであることが、人の感覚に訴えかける条件の一つであると考えます。また私たちの感覚に訴える美しさとはそういったものであって欲しい、という願いを込めてこの庭をデザインしました。【主な植物リスト】<Spring>アスチルベ/アガパンサス/ガウラ/カラミンサ<Summer>エキナセア/ヘレニウム/ルドベキア/ガイラルディア/アガスターシェ/ヘリオプシス/バーベナ/リアトリス<Autumn>オミナエシ/オトコエシ/フジバカマ<Ground cover>オレガノ/レモンバーム/ワイルドストロベリー<Grass 他>イトススキ/ペニセタム/フェンネル など 合計65種 コンテストガーデンC 月々の変化 【11月中旬】 カラミンサやガウラの白花と、イトススキやペニセタムの穂が花壇全体に白くエアリーな雰囲気を作るなか、アガスターシェ’ゴールデンジュビリー’と地際を覆うワイルドストロベリー 'ゴールデンアレキサンドリア’の黄金葉が明るさを添えています。その中で黒くシックなアクセントになっているのは、リアトリス‘フロリスタンホワイト’やリアトリス・スカリオサ ‘アルバ’の長い花穂のシードヘッド(花がら)です。昨年12月の作庭時に設置されたバグ・ホテルは約一年の風雨を受けて味わいが出ています。 【10月下旬】 これまで大きく茂っていた株は、剪定などの手入れで風通しよく整理され、9月よりも全体にボリュームが抑えられ、すっきりとした印象です。先月まで鮮やかに咲いていたエキナセアは花びらを落としたあと花芯が残り、リアトリス‘フロリスタンホワイト’の長い花穂のシードヘッドが9月よりも枯れ色になって、花壇に馴染んでいます。7月から咲き続けているカラミンサ・ネペトイデスは、さらに花穂を伸ばしてスモークのようにふわふわと優しい雰囲気を作っています。イトススキやオミナエシ、フジバカマといった日本で親しみのある植物も混ざり咲いています。 【9月下旬】 過酷な夏を耐えた植物たちは、隣り合うもの同士が支え合っているかのようにこんもり茂り、花壇全体に咲き続けている花が多数あります。手前では、ガイラルディア‘グレープセンセーション’が低く咲き、ペニセタム’JS ジョメニク’も穂を立ち上げています。花壇の中ほどでは、7月から引き続きカラミンサ・ネペトイデスやエキナセアが咲き、奥では丈高くバーベナ・ボナリエンシスやオミナエシが彩りに。夏の間、茂みに隠れていたバグ・ホテルが再び見えるようになり、その様子から月日の経過が感じられます。 【8月中旬】 7月から咲き続けているバーベナ・ボナリエンシスやオミナエシ、カラミンサ・ネペトイデス、エキナセアが彩る中で、花が終わったリアトリス‘フロリスタンホワイト’の長い花穂やエキナセアのシードヘッドがアクセントになっています。3月にシードボール(種団子)を播いて育ったアカジソの銅葉(上写真内右)やレモンバーム‘ゴールドリーフ’のライムグリーンの葉(下右)もガーデンの彩りに一役買っています。 【7月中旬】 5月までは場所が確認できていた4つのバグホテル(虫たちの住処になる場所)が隠れるほど各植物のボリュームが一層増して、花の彩りも豊かです。カラミンサ・ネペトイデスのような細かな花に対比して、エキナセアやガイラルディアの花が引き立ち、リアトリスやアガスターシェのような穂状の花もアクセントになっています。花壇の後方では、バーベナ・ボナリエンシスやオミナエシが丈高く開花。 【6月中旬】 各植物のボリュームが一段と増して、植物の高低差がリズミカルです。花々の中で昆虫が休んでいる様子が見られたり、花穂を伸ばす植物は風に揺れ、ワイルドストロベリーには赤い果実がなっています。この庭のテーマである「生き物たちの住処になる」ことや、風による動きや花や緑の香りを感じられたり、食べられるものも育つという「五感を刺激するガーデン」を花壇の中で実際に見ることができます。 【5月中旬】 地面がほぼ隠れるほど、どの植物も葉を増やし、ガウラやエキナセア・パラドクサ、アスチルベ、リナリアなどが開花して、花の彩りも増えています。花壇の後方では、グラスの穂が風に揺れたり、背丈より高く伸びたバーベナ・ボナリエンシスが紫の花を咲かせ、植物の高低差にリズムを感じます。2月下旬に設置されたバグホテル(虫たちの住処になる場所)が隠れるほど、周囲の植物がよく成長しています。 【4月中旬】 それぞれの植物が勢いよく成長し、イベリスの白い花とオレガノ 'ノートンゴールド’などの黄色い葉が明るいアクセントになっています。カラス除けとして刺さされていた枝は、丈高く育ってきた植物の支えに転用し、花壇の中で馴染んでいます。 【3月中旬】 2月下旬に設置されたバグホテル(虫たちの住み家になる場所)の周囲に植わるリナリア・プルプレア 'アルバ' がぐんぐん成長し、窪んだ低地では、アスチルベが存在感を出してきました。築山には、イベリスの白花やシラーの青花が彩りに。黄金葉のワイルドストロベリー 'ゴールデンアレキサンドリア’ にも花が見られます。 【2月中旬】 銅葉のガウラ 'フェアリーズソング’や黄金葉のワイルドストロベリー 'ゴールデンアレキサンドリア’、緑葉のシャスターデージー ’スノードリフト’が低く、地表に彩りを添えています。植物を守るように刺さる枝は、カラス除け。 【1月中旬】 コンテストガーデンD【入賞】TOKYO NEO TROPIC トウキョウ ネオ トロピック 【作品のテーマ・創作意図】地球温暖化と共に東京で越冬するようになった亜熱帯植物を取り入れ、花壇をつくります。また「循環型再生管理」を目指し、維持管理の過程で発生する植物の発生材は現場で更新、循環するガーデンをつくります。亜熱帯植物が力強く越冬する姿から緑のうるおいとあわせ、環境への意識「地球温暖化への警鐘」のきっかけをつくります。そして、地球温暖化による気温上昇、豪雨などの異常気象が多発するなかで、改めて「植物」や「土」の環境改善の役割を見つめ直し、緑の大切さを発信します。【主な植物リスト】<PURPLE >アンドロポゴン‘ブラックホース’ /アスター‘レディーインブラック’ /リグラリア‘ミッドナイトレディ’/アルストロメリア‘インディアンサマー’/エンセテ‘マウエリー’/ユーホルビア ‘ブラックバード’/カレックス ‘プレーリーファイヤー’/リシマキア ‘ファイヤークラッカー’/パニカム ‘チョコラータ’/ニューサイラン ‘ピンクストライプ’/トラディスカンチア ‘ムラサキゴテン’/ダリア<SILVER>ルドベキア ‘マキシマ’/リクニス‘コロナリア’/アガベ ‘姫滝の白糸’/アガベ ‘ボッテリー’/ユーホルビア/スティパ/エルサレムセージ/パンパスグラス<GREEN>ユーパトリウム‘グリーンフェザー’/トリトマ ‘アイスクイーン’/アロエベラ/ナチシダ/アガパンサス/ストレリチア/ガウラ ‘クールブリーズ’/アスパラガス ‘マコワニー’/アガスターシェ ‘ブラックアダー’<YELLOW>ワイルドストロベリー ‘ゴールデン アレキサンドリア’/ジャスミン ‘フィオナサンライズ’/カンナ ‘ベンガルタイガー’<GROUND COVER>クリーピングタイム/エリゲロン/スイセン‘チタテート’/チューリップ‘タルダ’/ハナニラ/アリウム ‘サマービューティ’/ゼフィランサス/イベリス 合計40種 コンテストガーデンD 月々の変化 【11月中旬】 5月から存在感を出していた2株のエンセテは、遠くからも存在が分かるほど一段と大株に育ち、来園者を驚かせています。アロエやエルサレムセージの銀葉、ユーフォルビア‘ブラックバード’の銅葉、カンナなどの黄金葉など、さまざまなカラーリーフが楽しめるなか、11月中旬になってもダリアやアルストロメリア、ルドベキア、エキナセア、パイナップルサングリア、コレオプシスなど多くの種類が引き続き咲き続けていて、彩り豊かです。ウィービングレイズドベッドには、ワイルドストロベリーとパッションフルーツが実をつけています。 【10月下旬】 夏に存在感があったガウラやルドベキアの花が減ってきたことと比例して、ダリアが花数を増やし、パンパスグラスやパニカム’チョコラータ’などのグラスの穂が伸びて、景色が変わってきました。紫葉のトラディスカンチアが茂るレイズドベットのそばでは、アスター・ラテリフローラス 'レディ・イン・ブラック'が無数に花を咲かせ、背景ではユーパトリウム・カピリフォリウムがふわふわと茂って、さまざまな葉色のコラボレーションも見られます。また、隣のレイズドベットに植るストレリチア・レギナエ 'ゴールドクレスト'の花芽が再び上がってきました(丸囲み内)。6月から咲き続けているアルストロメリア‘インディアンサマー’は、引き続き開花が衰えていません。 【9月下旬】 5月から存在感を出していた2株のエンセテは、カンナを越すほど丈高く成長し、花壇により一層立体感を与えています。ストレリチアが植わるウィーピングレイズドベッドで茂っていたイポメアやベンガルヤハズカズラは、つるが整理されてフレームが見えるようになりました。引き続き咲き続けている白花のガウラと紫葉のトラディスカンチア、イポメアのライムグリーンの葉色のコントラストが鮮やかです。6月から夏中咲き続けてきたアルストロメリア‘インディアンサマー’に加え、各所でダリアも次々咲き始めています。 【8月中旬】 5〜6月から咲いているガウラやアガスターシェ、アルストロメリアに加え、7月に咲き始めたルドベキアが引き続き彩りになっている8月。パンパスグラスも大きな穂を立ち上げて、さらにガーデンに立体感が出てきました。ストレリチアが植わるウィーピングレイズドベッドでは、イポメアやベンガルヤハズカズラがフレームを覆い隠すほど旺盛に葉を増やして緑豊かです。 【7月中旬】 スティパの穂が風に揺れ、5〜6月から咲いているガウラやアガスターシェ、ポピーマロウ、トリトマ、アルストロメリアが引き続き咲き続けるなか、4種のルドベキアやダリアとクロコスミアの彩りも加わって鮮やかです。丸く剪定枝を積み重ね、落ち葉などを入れて堆肥を作るバイオネストの縁に、隣から伸びてきたベンガルヤハズカズラが絡んで花壇に馴染んでいます。 【6月中旬】 各植物がより一層茂ったことで、銀色がかる葉、青みがかる葉、銅色の葉など、葉色や草姿の違いが際立ってわかるようになってきました。6月は、トリトマやアルストロメリア‘インディアンサマー’のオレンジ色の花が鮮やかに引き立っています。「Look at me!」と記された札が立つウィービングレイズドベッドには、ワイルドストロベリーの茂みの中でパッションフルーツが丸い実をつけています。夏の日差しを受けて、花壇は日に日にトロピカルな雰囲気が増しています。 【5月中旬】 花壇の中に作られた9つある「ウィービングレイズドベッド」の中の植物も、枠からはみ出るほど成長し、レイズドベッドごとに異なる景色が楽しめます。植えつけ時期の3月は、とても小さかったエンセテ(左下中央)は、赤みを帯びた緑葉を大きく広げて存在感が日に日に増し、目を惹いています。尖った葉、ふわふわ茂る葉、這って広がる緑、ワイルドに育つさまざまな草姿の違いも注目のポイントです。 【4月中旬】 スイセンやチューリップは見頃を終え、桃色のフロックス・ピロサや青花のアジュガ・レプタンス、白花のイベリス・センペルビレンスが、花を増やし彩りを添えています。メシダ‘バーガンディレース’の葉の間に咲くのは、アネモネ・フルゲンス(右下)。マルバダケブキの間から丸いつぼみを伸ばしているのはアリウム・ニグラム(左下)。 【3月中旬】 これまで姿が見えていなかったスイセン‘ティタティタ’があちこちで芽吹き、ワイルドストロベリーやアガベ、エルサレムセージなど、周囲の植物たちと面白いコラボレーションを見せています。自然素材を使った「ウィービングレイズドベッド」に植えられた植物は地面よりも高い位置にあるので、植物の様子が近くに感じられます。銀色や銅色、斑入りなど、いろんな葉色が楽しめます。 【2月中旬】 12月の植え付け時から地上部が残っているパンパスグラスやエルサレムセージ、ユーフォルビアが寒さに耐えているなか、レイズドベッドに植わる植物が少しずつ芽吹き始めています。 【1月中旬】 コンテストガーデンE【入賞】HARAJUKU 球ガーデン 【作品のテーマ・創作意図】初夏からのアリウム~秋のダリア を中心とした、球状の花の組み合わせでポップに楽しく魅せるガーデンです。アリウムはその形状が非常にユニークかつアート的で、原宿に集う人々のアンテナに触れる植物ではないでしょうか。ほかにも、エリンジウムやヘレニウム‘オータムロリポップ’、モナルダ、ニゲラの花後の球果など、観て楽しい植物で構成しました。また、秋のダリアはデスカンプシア‘ゴールドダウ’との合わせで、一見存在が浮いて見えてしまいがちなダリアを、幻想的に他の植物たちと融合させます。「球ガーデン」のネーミングは、某超有名ガーデンを原宿ならではの遊び心でもじらせていただきました。【主な植物リスト】アリウム/ダリア/エキナセア/モナルダ/ワレモコウ/ゲウム リバレ/ムスカリ/ニゲラ/カカリア/バーノニア/エリンジウム/ディアネラ/ユーパトリウム チョコレート/ヘレニウム オータムロリポップ/パニカム/ニューサイラン/カレックス/デスカンプシア ゴールドタウなど 合計88種 コンテストガーデンE 月々の変化 【11月中旬】 10月から存在感を増しているミューレンベルギア・カピラリスなどのグラス類がより一層スモークのように穂を広げ、晩秋の日差しに輝いています。10月から咲き始めていたカカリアがさらに花数を増やし、ピンクとオレンジの花が宙を浮くように咲いていたり、株を覆うように紫花が多数咲くクジャクアスターが見学者の目を惹いています。花壇の高い位置では、ユーパトリウム‘羽衣’(羽衣フジバカマ)が開花し、花が終わったバーノニア(右下)の茎先は、丸い綿毛をつけています。 【10月下旬】 ミューレンベルギア・カピラリスやディスカンプシア‘ゴールドタウ’などのグラス類が煙のように穂を広げ、周囲に咲くアスターやガウラなどが透けて見えて幻想的な雰囲気が増してきました。花壇のタイトル「HARAJUKU 球ガーデン」を表現する球形の花として多数植えられていたダリアが次々と開花し、ガイラルディア‘グレープセンセーション’の球形の花芯も花壇の景色として貢献しています。今月咲き始めたサルビア・アズレアのブルーの花色が暖色系の花々を引き立てています。 【9月下旬】 この花壇のタイトル「HARAJUKU 球ガーデン」を春から初夏に表現してきた多数のアリウムから、真夏はエキノプスやサクシサ・プラテンシスにバトンタッチしていましたが、9月からはダリアが球形を表現する花として次々開花。秋にダリアが咲いたころ幻想的に調和する効果を狙って植えられた、ミューレンベルギア・カピラリスやディスカンプシア‘ゴールドタウ’などのグラス類が穂を広げ、アンティークカラーに変わってきているものもあります。 【8月中旬】 強い日差しを受けて輝くディスカンプシア‘ゴールドタウ’の穂が煙のように花壇全体に広がり、隣り合う植物の間を繋げています。穂に浮かび上がって見える球状花のエキノプス(右下)は、花後もガーデンのアクセントとして活躍。7月から咲き続けているオレンジ花のヘリオプシス’ブリーディングハーツ’やピンク花のガイラルディア‘グレープセンセーション’などが彩りになっているなか、サクシサ・プラテンシス(左下)が球状花として仲間入りしています。 【7月中旬】 6月から咲いているポンポンダリアやヘレニウム‘オータムロリポップ’、エキノプス‘プラチナムブルー’、スカビオサ・オクロレウカがさらに花数を増やす中、オレンジ花のヘリオプシス’ブリーディングハーツ’が咲き始めてさまざまな花色が楽しめます。株間から、ディスカンプシア‘ゴールドタウ’の穂が見え始め、次の季節へと成長を進めています。 【6月中旬】 5月は、アリウム・ギガンチウムやアリウム‘グレースフルビューティー’などが、この花壇のタイトル「HARAJUKU 球ガーデン」を表現していましたが、6月は、背丈を越すほどまで伸びたアリウム ‘サマードラマー’をはじめ、ポンポンダリアやヘレニウム‘オータムロリポップ’(下左)、エキノプス‘プラチナムブルー’(下中)、アリウム‘丹頂’(下右)などが球状花として花壇を彩り、にぎやかです。 【5月中旬】 花壇のタイトル「HARAJUKU 球ガーデン」を表現する球状の花の一つであるアリウムが5月上旬に多数開花。5月中旬になると残った丸い花がらが、ホルディウム・ジュパタムやスティパ‘エンジェルヘアー’などのグラス類の上に浮いているように見え、個性的な風景を作っています。花壇の後方では、背丈よりも大きく育ったバーベナ・ボナリエンシスと競うように丈高く伸びるアリウム ‘サマードラマー’の蕾がスタンバイ。球状の花の開花リレーが続きます。 【4月中旬】 さまざまなアリウムの葉の間をつなぐようにグラスの細葉が風に揺れるほど成長してきました。アリウムの中でいち早く、白花のアリウム・シルバースプリングが開花。緑の間にオレンジや黄色のゲウム・リバレやゲウム‘テキーラサンライズ’が咲いて華やかなアクセントになっています。 【3月中旬】 この庭の特徴となる玉のような花を咲かせる多品種のアリウムも存在感を出し、ディスカンプシア‘ゴールドタウ’やホルデウム ユバツムなどグラスも葉を増やしています。花壇の縁付近では、ベロニカ’オックスフォードブルー’の紫花やムスカリも次々開花中。いろんな植物がたくましく混ざり合って育つ様子が見られます。 【2月中旬】 アリウム‘サマードラマー’やアリウム‘シルバースプリング’が勢いよく伸び出し、切り戻されていたグラスのディスカンプシア‘ゴールドタウ’は細い葉を伸ばし始めています。地面に張り付いたように葉を残す緑のニゲラや赤い葉のペンステモン‘ハスカーレッド’が彩りを添えています。 【1月中旬】 第2回参加者決定&第1回入賞者によるオンライン座談会 「第2回 東京パークガーデンアワード 神代植物園」参加者決定! 代々木公園での第1回開催に続き、第2回のコンテストの舞台は、都立神代植物公園正門手前プロムナード[無料区域](調布市深大寺)。コンテストのテーマは「武蔵野の“くさはら”」です。9月1日締切までに応募された作品から、5名の入賞者が決定しました。第2回のコンテストの様子はこちら。 第1回東京パークガーデンアワードの入賞者によるオンライン座談会 「第1回 東京パークガーデンアワード 代々木公園」の入賞者5名が登壇。応募に向けた準備や植物の調達から造園、メンテナンスまで、現場の“生”の声が聞ける座談会が2023年8月10日(木)にオンラインで開催されました。アーカイブのご視聴はこちらから。 庭づくりの舞台裏記事も公開中! 5つのコンテストガーデンは、2022年12月に第1回目の作庭が行われました。その様子をご紹介する記事『【舞台裏レポ】「第1回 東京パークガーデンアワード」5つの庭づくり大公開』もご覧ください。
-
フランス

【パリの庭】パリ市の四大植物園「パルク・フローラル」に咲くダリア
パリ市の植物園「パルク・フローラル」 ご紹介する「パルク・フローラル(花公園)」は、パリ市の四大植物園(*)の一つで、文字どおりにさまざまな植物コレクションを保有しています。1969年に同地で行われた国際園芸博覧会を契機につくられたもので、広さは30ヘクタールほど。全体的には、森林公園のような松やオークの林を抜ける散歩道の所々に、ダリア園や芍薬園などがあり、華やかな花のコレクションを見ることができます。アイリスやシダ、アスチルべなどのオーナメンタルな植物に加え、パリ盆地の自生植物や薬用植物などのコーナー、錦鯉が泳ぐ広い園池など、変化に富んだ見所もあり、どの季節も、大人も子どもも楽しめるような工夫がされています。 *四大植物園=パリ市の植物園としては、ほかに同じヴァンセンヌの森にあるエコール・デュ・ブルイユの樹木園、バラ園で有名なバガテル公園、セール・ドートゥイユがあります。 秋の森に群生するシクラメン。 色彩溢れる華やかなダリアにうっとり ダリア園の入り口、緑の中のはっとする華やかさ。 さて、今日のお目当ては、なんといってもダリア園。ダリアは7、8月から10月下旬の初霜の降りる頃までと花期が長く、少し寂しくなってくる秋の庭に華やかな色彩を添えてくれる人気者です。近年は花屋さんでも、オシャレな色合い、花姿の異なるさまざまなダリアを見かけるなぁと思っていましたが、最盛期のダリア園は、入り口に立っただけで、その華やかさに圧倒されます。 カラフルな色合いに加え、草丈は20cmほどの矮小種から2mを超すものまで。また小さな花や大きな花、一重や八重咲き、ポンポン咲き、カクタス咲き……などなど。あらゆる種類のダリアが咲き乱れる様子は、これぞ眼福です。 国際ダリア・コンクール パリのパルク・フローラルでは、野生種・園芸種を合わせて400種を超えるダリアを栽培しており、毎年8月末〜9月初めには、国際ダリア・コンクールが行われています。これには、フランス国内から60ほどの生産家がエントリー、ドイツやオランダ、リトアニア、日本など外国の生産家も参加し、一般投票と専門家の審査を経て、新栽培種の受賞品種が選ばれます。 左/Dahlia 'Hellios' (写真内手前)右/Dahlia Gryson's Yellow Spider 一般審査の参加者は、3つの好きなダリアに投票することができます。専門家の審査では、花ばかりでなく茎や葉も合わせた全体の花姿や色彩、さらに耐病性などのテクニカルな部分も対象になります。大賞、ジャーナリスト特別賞、一般審査賞、子ども審査員賞などに選ばれたダリアの一部をご紹介すると、ニュアンスカラーのバラ色のDahlia 'Dutch Delight'、黄色〜オレンジからカフェオレ色に変化するDahlia 'Hellios'、菊のような繊細なカクタス咲きで爽やかなイエローのDahlia Gryson's Yellow Spiderなど。 左/Dahlia Comet 右/Dahlia Staburadze またDahlia Cometはパステルトーンのオレンジのポンポン咲き。より柔らかでエレガントなDahlia Staburadze、シックな深いレッドのDahlia 'King Arthur'など、受賞作品は、色も形もじつにさまざま。この多様性こそがダリアの尽きない魅力と、改めて実感します。 ダリアの魅力〜多様性 もともとはメキシコやコロンビアの暖かい高地に自生するダリアは、18世紀にヨーロッパに持ち込まれ、フランスに導入されたのはフランス革命が勃発した1789年。当初は根を食用にする野菜として扱われたものの、あまり美味しくはなかったようで、ジャガイモを超える人気の食用植物にはなりませんでした。しかし、花の華やかさや、初霜まで続く花期の長さが重宝されて、庭のオーナメンタルな植物として人気となりました。植物愛好家であったナポレオン皇妃ジョゼフィーヌもマルメゾンの庭園にダリアを取り入れ、ダリアは19世紀のフランスで人気を博しました。 再び人気上昇中のダリア かつては希少な品種が高額取り引きされるなど、歴史的にも花形だったダリアですが、一時期のフランスでは、田舎の祖父母のポタジェの花のような、ちょっと時代遅れのイメージになっていました。しかし近年は現代の感性に応える色や形のバリエーションに加え、茎の強度が増し、庭での植え込みやブーケの素材として使いやすく進化してきました。また、花がら摘みが不要なように、花後には再びつぼみのような姿になるローメンテナンスなダリアも現れるなど、生産家による品種改良の努力が続けられてきた結果もあってか、ここ数年来ダリアの人気は再び上昇しています。 野生種のコーナーの一角、ポンポン咲きのダリア。 パルク・フローラルのダリア・コレクションでは、年々増える多彩な園芸品種のダリアのかたわらに、全部で40種類前後存在する野生品種のダリアの1/3ほどが栽培されています。すでに草丈は低いものから人の背丈くらいのものまで、花形も一重も八重も多種の形態がありますが、比較的クラシックなそれらのダリアに比べて、栽培種ではさらに、複雑なカラーコンビネーションで、銅葉やダークな色合いの茎までコーディネートされて、まるでオートクチュールのデザインのような完成度の高さ。 ミルキーなオレンジやカフェ・オレ・カラー、シックなレッドなど、オシャレなカラーリングにも目移りが止まりません。ダリア園を一巡りしてみると、帰りにはすっかりダリアマニアになってしまいそうです。 庭デザインにもアレンジにも大活躍 花の姿だけでなく、葉や茎も含め、さらに群生した際の姿のよさ、管理のしやすさなど、改良を重ねた園芸種のダリアの多様性は、華のある風景づくりの強い味方です。家に飾るブーケにもできる、双方向に活躍するダリアは、自宅の庭の花としても魅力的。ちなみに、ダリアの切り花は長時間の輸送には向いていないのですが、逆に地消地産といったローカルな花のサーキュラーエコノミーにうってつけであることは、サステナブル志向になってきた花屋でダリア人気が再燃している理由の一つでもあります。 さて、パルク・フローラルのダリアは、季節が終わると掘り上げられて、来春の植え付けまで大切に保管されます。また来年にはどんな新しいダリアに出会えるのか、今から楽しみになっています。
-
フランス

【フランスの庭】ル・プリウレ・ドルサン修道院の庭〜魅惑のモナステリー・ガーデン〜
中世の修道院の庭 ヨーロッパで景観への見晴らしがよい開かれた大規模な整形式庭園が発達するのは、ルネサンス期以降。中世の修道院に設けられた庭には、閉じられた空間の中に、修道士たちが自らを養う野菜や果樹のポタジェ(菜園)やベルジェ(果樹園)、また病人を癒やすためのハーブガーデン(薬草園)などがつくられていました。祈りとともに、自らの手を使って働くことは大切な修行の一環であり、庭仕事は修道士の日常の仕事の一部。自給自足という機能面と、修道院という場に相応しい、静けさと調和に満ちた美しく整った空間が、中世の修道院の庭だったといいます。 現代の感性で再現されたモナステリー・ガーデン 庭に続く、修道院の建物のエントランスのしつらいも、ウェルカム感いっぱいで期待が膨らみます。 残念ながら、現代までそのまま残る中世の修道院の庭はありません。今から30年ほど前の作庭にあたっては、装飾写本などに描かれた当時の庭の様子や文献調査から、かつての修道院の庭で行われていたように、植栽には伝統的な有用植物や象徴的な植物を選び、整形式のプランでポタジェ(菜園)、ベルジェ(果樹園)、クロワートル(回廊)がつくられ、現代のモナステリー・ガーデンが誕生しました。 ポタジェ(菜園)とサンプル(薬草園) 見学コースの始まりは、建物に一番近いポタジェから。正方形の木枠で縁取られたポタジェでは、昔からの伝統野菜が花々とともに植栽され、元気に育っています。きっちり端正に整備された構造物とのコントラストで、生き生きと茂る植物のオーガニックな動きの勢いがますます感じられます。また「プレシ Plessis」と呼ばれる小枝などを組んで作られた柵やトレリスが素敵な、魅惑のポタジェ風景が広がります。 こんなに可愛いポタジェには、なかなかお目にかかれません。ポタジェの奥は「サンプル」と呼ばれる薬用ハーブの植栽コーナーです。病人を癒やすのは中世の修道院の重要な責務であり、このハーブガーデンには、かつて王令で薬草として栽培を推奨されたハーブの数々、カモミールやメリッサ、セージ、ミント、イチョウヨモギ、アンジェリカやバーベナなども植栽されています。 プロムナード(散歩道)からベルジェ(果樹園)へ リンゴや洋ナシが規則正しく植えられたベルジェの様子。 何度でも見て回りたくなるポタジェを抜けて、芝地に並木が植栽されたプロムナードへ。緑だけのスッキリと整ったシンプルに美しいこの空間に入ると、不思議とスッと心落ち着く感じがしました。 続いて、芝地にリンゴや洋ナシといった果樹が植えられたベルジェも、穏やかな空気が流れる場所。果樹の周りを囲むように設けられたプレシ(小枝の柵)のベンチや王様の椅子を思わせるシーティングが、シンプルな空間にアクセントを添えています。 通路には、異なる空間の重なりの奥に、常にフォーカルポイントが作られていて、深い奥行きを感じさせます。 それぞれの庭のコーナーは生け垣やプレシでしっかり囲まれつつも、他の空間への見通しのポイントがそこかしこに設けられていて、こちらへ、彼方へと誘われるように、歩を進めることになります。 ラビリンス(メイズ 迷宮) さまざまな植物に彩られたラビリンス。 さらに進んでいくと、さまざまなエスパリエ仕立ての果樹や小枝の柵で構成された、ラビリンスに入り込みます。カゴ形の構造物の中に植えられたルバーブや、白を基調にした花々が揺れる仕切りの奥に、ベンチで囲まれた大きな果樹が見えるのですが、目に映るままに進んでも、意外と行きつけない、まさに迷宮になっています。 幾何学的なボリュームで構成された空間ですが、よく見ると足元の素材は木材を利用。長もちはしないかもしれませんが、温かな雰囲気です。 この迷宮は、キリスト教での“行き着くことが難しい「救済」への道”を示すものでもあるのだとか。迷路を構成する生け垣の片隅には、日陰になった休息スペースもあって、花や果樹を愛でつつ、迷うことを楽しみながら、ゴールに向かう構成です。 さまざまな小さな庭 ラビリンスの中心には、円形の洋ナシのパーゴラを被った丸いベンチが。 ラビリンスの中心には、その形を反映するように円形に刈り込まれた洋ナシと、風に揺れる花々の植栽が。イチゴやフランボワーズ、スグリなどの赤い実の小道や、残念ながらバラの季節は過ぎてしまっていたのですが、バラ園であるマリアの庭など、さまざまな小さな庭の空間が続きます。 いずれもが共通して、整形式のプランと構造に木材や小枝などの自然の素材が使われており、それでいてテーマによってそれぞれ全く異なる雰囲気を持った空間となっています。エリアが変わるたびに、ハッとするような発見の感覚があって、楽しさが尽きません。 クロワートル(回廊) クロワートルの庭の中心には、生命の象徴である水が流れています。 さまざまな小さな庭の連続の中、大きな空間を占めるのがクロワートルと呼ばれる、全体のほぼ中心に当たる庭です。修道院建築の中に必ず含まれる中庭を囲むクロワートルは、祈りと瞑想の場であり、天国を予示する象徴的な場でもあったそうです。ここでは石造りの修道院の建築の代わりに、クマシデの生け垣がクロワートルを形づくっています。その中心には静かに水が流れる噴水があり、四方は小さな葡萄畑になっています。 じつは、現在修復されている修道院の建物も、最盛期の1/10ほどだそうで、かつては石造りの建物として存在したクロワートルが、静かな散策の緑のプロムナードとなって庭に再現されているのは、デザインとしても面白いところ。 緑の生け垣の壁にくりぬかれた円形窓からの風景。どのディテールも魅力的。 作庭から30年ほどが経つという、ル・プリウレ・ドルサンの庭。現在は4人のガーデナーが維持管理を担っている3haほどの庭園は、非常によく手入れされており、本当に気持ちよく寛いで散策できます。中世の修道院の庭のさまざまな特徴を、現代の美意識でデザインに生かしたこの庭には、人の手仕事と植物たちの美しい調和が溢れていて、まさに天国のような心休まる空気が流れていました。 庭園にはショップとカフェも。昼時にはテラスか室内で、ホームメイドの塩味系のキッシュやタルトとフレッシュな庭のレタスのサラダ、ドリンクとデザートの軽いランチセットがいただけます。
-
埼玉県

素敵な発見がたくさん! 園芸ショップ探訪40 埼玉「ガーデンセンターさにべる」
お気に入りが見つかるはず!充実した苗売り場づくり 北西に連なる山々の稜線を背景に広がる田畑…その中に「ガーデンセンターさにべる(以下さにべる)」はあります。70台も収容できる駐車場には、毎日オープンからひっきりなしにお気に入りを入手するべく花好きな人々が出入りしています。 駐車場側の木戸口から入ると、ひな壇状に並べられた無数の花苗パレットがお出迎え。足を踏み入れた途端、一気にテンションが上がります。 フラワーパレットは白で統一、花の可憐さや透明感をアピールしています。なにげないこだわりがそこここに。 かつては生産農家や苗の仲卸を行っていた「さにべる」。ポットマム生産時代を合わせると50年以上の歴史があり、30年ほど前に社長の間室照雄さんが園芸店をスタートさせました。現在も野菜苗と花植えを生産直売していますが、ショップは娘で店長の間室みどりさんが柱となり、長年培った園芸のノウハウと、生産者・市場との横のつながりを大切にしつつ、時代に沿うよう進化させています。 みどりさんが仕入れる苗は、どれも新鮮。市場からの仕入れだけでなく信頼のできる生産者に依頼したものも多く、多種多様な植物を最高の状態で提供できるように力を注いでいます。「苗も雑貨も、お気に入りを見つけてもらいたいという思いで揃えています」とみどりさん。 寄せ植えやハンギングに力を入れている「さにべる」。特にパンジー・ビオラは、たくさんの生産者から取り寄せ、充実させている。 ぜひ参考にしたい!プロの寄せ植え・花合わせ 店内には寄せ植えの見本鉢が点在。植物それぞれの魅力を引き出し、お客様の花合わせの参考になるように、サンプルとして飾っています。 売り場にあった寄せ植えご紹介!手軽に楽しめる愛らしい寄せ植えを集めました 「寄せ植えを美しくまとめるのに大切なのは、色づかい」とみどりさん。じつは、みどりさんは「趣味の園芸」など、テレビや雑誌に登場する人気園芸家。カラリストの資格も持っており、常に美しく見せることを意識しながら、植物に向き合っているのだそう。「さにべる」での講習会だけでなく、出張講習会やトークショーなどでも活躍しています。 東京農業大学農学部を卒業後、デンマークで4年間切り花を学んだというみどりさん。デンマークでは「最近ヒュッゲという言葉がよく使われていますが、それは花を愛するデンマークの人々が大切にしている‘居心地のよい空間・時間’のこと。ここで、ヒュッゲな暮らしを提案できたらと思っています」。 ショップでは、寄せ植えの楽しみを提案しているみどりさんが考案した培養土が販売されています。大きな特徴は、水はけと保水性を兼ね備え、腐食酸を多く含んでいること。腐食酸(フルボ酸)は、根の働きを助けて根張りをよくし、成長につなげてくれる今注目の成分です。近いうちに、寄せ植え用の肥料も発売予定です。「季節で寄せ植えが終わったときに再利用しやすいよう、短期間効くものにしています」とみどりさん。 屋外の用土コーナーには、土壌改良材などあらゆるアイテムが揃っている。 花苗以外も見どころたくさん外売り場&店まわり 花苗売り場の奥には、樹木コーナーが展開されています。取材時の秋に最も充実していたのはオリーブ。そのほか、美しい葉や花が楽しめるものが揃っています。 ハーブなどの花壇が設けられているオリーブコーナー。 店まわりも魅力的なコーナーがたくさん。ウッドフェンスで囲まれた売り場はつる植物や多年草で覆われ、牧歌的な雰囲気が漂っています。こののどかな雰囲気が好きなファンも多いそう。 エントランスにはニセアカシアが心地よい緑陰を作っている。 フィカス・プミラが古いポストやフェンスに活着し、瑞々しいシーンに。 古い車輪のオーナメントのまわりをユーパトリウム‘チョコレート’が覆う、ノスタルジックな風景。 店内のミニガーデンは、季節の寄せ植えを飾ったり、撮影場所や子どもが遊ぶ場になったり……。自由な発想で使える空間。 屋内売り場もあらゆるアイテムが盛りだくさん! 大きなハウスを活用した屋内売り場では、季節の鉢花や観葉植物、多肉植物、園芸資材などがそれぞれ島を作っています。どれも選ぶのに困ってしまいそうな広さと品揃えです。 ドライな雰囲気たっぷりの多肉・サボテンコーナー。 秋は、あらゆる春咲きの球根植物が揃う。 照雄さんは生産農家でもあり、奥にあるハウスでは、照雄さんの作った野菜苗が大人気。最近は、農家さんも買いに来るほどの充実ぶりです。 ブロッコリーの苗(左)と隣のハウスのハーブコーナー(右)。 姉妹で作り上げる見やすく楽しい売り場 みどりさんとともに店を回しているのは、妹の2人・小枝子さんと夏実さん。それぞれに得意分野が異なる最強の仲間です。仲のよい3姉妹が一緒に考え、最近形にしたのが観葉植物コーナー。冬は加温してあたたかい空間となりますが、夏は冷房し、冷涼な気候を好む植物を管理するという特別なコーナーです。「人にとっても心地よい場所です」とみどりさん。無骨なビニールハウスの印象を払拭する、ウッディでクールなデザインが売り場の雰囲気をぐっと高めています。 コーナーの内部は、観葉植物や進物用のラン、サンセベリアなどがひしめき合い、植物園の温室さながらの雰囲気です。 シンプルなデザインの什器もおしゃれで、手書きのポップが楽しい雰囲気。 左/近年人気のビカクシダも、大きさ・種類さまざまに揃う。 右/インドアプランツ用アイテムも、一緒の場所に。 一角に設けられた雑貨コーナーも見応え十分。ここはおもに小枝子さんがディスプレイを任されている場所。かつてブライダルの世界で花を飾ることを専門にしていた能力を発揮する場となっています。 はしごでやんわりと空間を区切り、いくつものシーンを展開。あらゆるテイストのアイテムが自然になじみ、それぞれのエリアが美しく整えられています。 ボタニカルの額を背景に、花瓶などのガラス器が飾られている。 ドライフラワーのブーケやバスケットなど、温かみのあるアイテムが並ぶエリア。 テンションが上がる、おしゃれなガーデニングツールもたくさん。 「さにべる」では、照雄さんや農家が作った野菜をはじめ、地元の養蜂家の蜂蜜、コーヒーなども販売しています。新鮮な野菜は午前中に売り切れになるほどの人気。 この日販売されていたコシヒカリは、照雄さんが育てたお米。パッケージは小枝子さんがデザイン。 散策しながら見つけよう!充実の園芸資材 庭に彩りを添えるアイテムも充実した「さにべる」。広いハウス内のあちこちにアイテムごとの空間が作られ、選びやすく陳列されています。 庭の雰囲気を高めてくれる、アイアンフェンスコーナー。目隠ししたいときや、つる植物の誘引に最適。 テラコッタやグラスファイバー、ブリキなど、用途や置く場所に合わせて容器も選んで。 間室みどりさんイチオシの本格派ハンドフォーク 「こんなツールが欲しい!」というガーデナーたちのリクエストから生まれた、浅野木工所(新潟県・三条)の本格的なガーデンツール。一般的なサイズより爪の部分がやや長く、柄につながるネック部分も長さや角度など、微妙な設計が施され、使いやすいのが魅力。広い場所でもへこたれません。掘る、混ぜる、耕す、1つで何役もこなす頼れる庭仕事の相棒です。ぜひ店頭で実物をご覧ください。 上から、草取り、草取り鎌、ハンドフォーク、ハンドスコップ。ハンドフォークはSunny valeのロゴ入り。 新鮮な苗・多様なアイテムを取り揃え、地域の人々の憩いの場となっている「ガーデンセンターさにべる」。寄せ植えやハンギングバスケットなど、各種教室も充実し、気軽に花と触れあえます。「sunny:降り注ぐ光」「vale:谷」という意味を持つ「さにべる」、その名の通り、みんなの暮らしを明るく照らすスポットです。ぜひ訪れてみてください。アクセスはJR高崎線「鴻巣」駅から川越観光バス(東松山駅行き)で約10分、東武東上線 「東松山駅」から川越観光バス(鴻巣駅・免許センター行き)で約10分、どちらも「谷口」停留所下車・バス停から約300m。
-
フランス

【フランスの庭】ヴェルサイユ庭園の最新スポット「調香師の庭」
花の宮殿、グラントリアノン グラントリアノン。Andy Sutherland/Shutterstock.com ヴェルサイユ宮殿には、グラントリアノン、プチトリアノンの2つの離宮と庭園があります。ルイ14世は「ヴェルサイユ宮殿を宮廷のために、マルリー宮殿を友人たちのために、グラントリアノンを自分のために作った」といわれます。王は堅苦しい宮廷儀礼を離れたプライベートな時間を過ごすために、1668年、陶器のトリアノンと呼ばれた美しい宮殿を建てさせました。しかし、外壁を覆うデルフト陶器の脆弱さゆえに陶器のトリアノンは20年と持たず、早々に大理石のトリアノンと呼ばれる、現在まで残るイタリア風の建物に建て替えられることになります。 プチトリアノン。Ivan Soto Cobos/Shutterstock.com さて、王が親密な時間を過ごしたトリアノンの庭は、どんな様子だったのでしょうか。 当時、トリアノンの庭園の花の植栽は、その時々の王の希望に合わせて素早く変えられるよう、また、すべての花を最高の状態で見せられるよう、植木鉢に植えて花々を組み替える方法で行われていました。別名「花の宮殿」とも呼ばれたトリアノンの庭園には、香りのよい花々が大量に咲き乱れ、その強い芳香に気絶する招待客も出るほどだったとか。 ヴェルサイユと香水文化 盛夏の「調香師の庭」は、香りにまつわる植物たちが旺盛に育つ、ナチュラルかつのどかな雰囲気。 衛生面ではまだ発展途上であったともいえる17世紀、ルイ14世の時代の宮廷では、不都合なにおいを隠す目的もあって、ムスクなどの動物性の強い芳香が好んで使われていたそうです。庭園や宮殿を飾る花々も、ヒヤシンスや月下香など、芳香の強いものが好まれました。そうした背景から、17世紀から18世紀にかけて、イタリアから伝わった香水が大流行したフランスの宮廷は、数々の名調香師を生んだ、香水産業の揺り籠となったのでした。また、当時は香水を使うことができるのは王侯貴族などに限られていたゆえに、香水の香りは、豊かさと高貴さの象徴でもあったのです。 香りの花々が育つ「調香師の庭」 ダマスクローズ越しの「調香師の庭」の風景。 そうしたヴェルサイユの宮廷と宮殿、香水文化の歴史からインスパイアされて生まれたのが、新たにつくられた「調香師の庭」です。かつて「Sillage de Reine」でマリー・アントワネットの香水を復元するなどヴェルサイユと縁の深い香水のメゾン、フランシス・クルジャンがスポンサーとなってつくられた、香水の歴史に捧げられた庭園です。 シャトーヌフのオランジュリー。かつてルイ15世が、ここでコーヒーやパイナップルを栽培させたのだそう。 植物学に興味を寄せていたルイ15世がかつて造らせた、シャトーヌフのオランジュリー。「調香師の庭」は、その建物近くにある9,000㎡ほどの敷地につくられました。トリアノンの庭師たちと協力し300種以上の香水の素材となる精油に使われるさまざまな植物が集められた庭は、雰囲気の異なる3つのゾーンで構成されています。通常は非公開の場所ですが、ガイド付きであれば見学することができます。では、3つのゾーンをそれぞれ見ていきましょう。 <好奇心の庭> ルイ15世がパイナップルやコーヒーを栽培させたというシャトーヌフのオランジュリーにまっすぐ向かう通路を中心軸に、左右対称の整形式に整備されています。数百種の芳香に関連する植物が植栽された「調香師の庭」は、いわば香りのポタジェ。実際、少し前までこの敷地にはヴェルサイユの宮殿内にレストランを持つアラン・デュカスのポタジェがあったのだそう。 多数のバラの中で、わずかに咲き残りの花が見られたダマスクローズ。香水の原料の主となる香りのバラです。 この庭には、当時の植物系の香水の素材として花形的存在だったアイリスやバラ、昔から使われ続けているさまざまな香りのハーブ類、香水製造にまつわる文脈で「ミュエット(無言)」の花と呼ばれる月下香やスミレなどが植えられています。 チョコレートコスモスは、深いチョコレート色がおしゃれなばかりでなく、香りもチョコレート! また、花そのものが素晴らしい芳香を持つものだけでなく、直接的には香水の材料となる香りが抽出できず、人工的に再構成するしかない種類の花、チョコレートやパイナップルといった珍しい香りの草花など、幅広く香りに関する花々が集められています。 葉からパイナップルの香りがするハーブ、パイナップルセージ。 セージをはじめ、香りのハーブの植栽エリアも充実。 庭園全体は、17世紀のトリアノンの庭の香りのエスプリをイメージしながら、一年を通して何らかの花が咲くようにといった配慮がされています。また、ボルドーとチョコレート色、イエローからオレンジへのグラデーションというように、色彩をポイントに構成された植栽からは、オーナメンタルな庭としての心配りが大事にされているのが分かります。 晩夏もまだ花盛りのラベンダーは、青紫色の植栽コーナーの主役。 私が訪れた8月中旬は、庭の季節としては花から結実へと向かう、暑さで疲れも出ていそうな時期でした。庭の花形であるバラは、さすがに少々の花が残る程度でしたが、そこかしこで勢いよく育った草花のダイナミックな姿がワイルドで、フランスの田舎の夏休みを思わせるような、ナチュラルで心休まる風景になっていました。 かなりワイルドな、でもなぜかほっとする風景。 オランジュリーの前と通路の両脇は、レモンやビターオレンジ(橙)などの柑橘類の植木鉢で飾られています。ビターオレンジも、実は精油のネロリやプチグランの原料となり、香水の材料として活躍する柑橘です。ちなみに、さまざまな動物系の強い芳香を嗅ぎすぎたためか、芳香アレルギーになってしまった晩年のルイ14世が、唯一受け付けることができたのは柑橘系の香りだったのだそうです。 オランジュリーからの中央通路に並ぶ柑橘類を中心にしたコンテナーと植木鉢の列。 <木々の下の庭> 緑がワサワサ茂るワイルドな果樹園。 <好奇心の庭>の隣の果樹園エリアとの間には細長い桜並木があり、春には庭園の一番の見どころになりますが、8月の果樹園で目を引くのは、モモやリンゴ、洋ナシがたわわに実る果樹のほうです。かなりワイルドな感じの果樹園を抜けると、奥にはさらに、壁に囲まれた小さな<秘密の庭>が待っています。 奥に進むと、さらに壁に囲まれた扉を発見。 小さな<秘密の庭> 敷石のステップが緩やかな曲線を描き、庭の奥へと気持ちを誘う<秘密の庭>。中に立ち入って植栽などを観察することはできなかったのですが、ひっそりと静かに瞑想するのによさそうな静かな空間は、現在のところ庭師の実験ガーデンとなっているのだそう。 <秘密の庭>を覗いたところ。 見学の最後には、ワークショップスペースでアイリスの根やバラの花、パチュリの葉や茎、バニラの実など、精油の抽出には植物のさまざまな部分が使われることを学び、香りを実際に体験することができます。精油となった芳香をそれぞれの言葉で表現し、また実際の植物の香りやイメージと、精油になった香りとのギャップを発見するのは、大人にとっても子どもにとっても面白い体験。視覚と嗅覚とイマジネーションをフル活用することで、庭と植物の楽しみ方がさらに広がります。 屋根付きのワークショップコーナーでは、ガラス瓶の蓋の裏に用意された調香の基本となる香りを体験。実際に香りを嗅いで言葉にする体験は、新鮮な発見になります。 ドライのバラの花やアイリスの根などに混じって、真ん中の瓶はドライになったパチュリの茎と葉っぱ。 香水の歴史を庭のインスピレーションとして新たな空間を作った「調香師の庭」は、ヴェルサイユ庭園ならではの興味深い試みです。
-

横須賀市佐島の海が見えるサボテン&観葉植物のお店「INDIAN GREEN」のご紹介
白いラップサイディングの建物の前はアオノリュウゼツランの花が・・・ 佐島海岸沿いの道を車でしばらく走ると、右手に白いラップサイディングの建物が見えてきました。2階バルコニーのウッドデッキが自然になじんで印象的。銅管で作った緑青色に錆びたショップサインが、とってもオシャレですね。 ショップの入り口では、ちょうどアオノリュウゼツランが花を咲かせていました。「50年に1度しか咲かないんですよ」と、オーナーの堀越弓恵さん。 50年に1度だけ開花するアオノリュウゼツラン。 アオノリュウゼツランはメキシコ原産で、現地では繊維や発酵酒の原料になっています。英名では「センチュリープラント」といわれ、熱帯地方では10~20年、日本では20~50年に1度しか開花しないのです。開花期間は7月下旬から1~2週間ほどで、結実(けつじつ)すると、その株は枯れてしまいます。 多肉植物の寄せ植え。 流木の竿にはビカクシダのハンギング。 また、バルコニーの下には流木を利用した竿が。無造作にハンギングされたビカクシダが元気に葉を広げていました。ここでは屋外で冬越しができるようですが、植物も人間同様に個人差があり、寒さで枯れてしまうものもあるので、育てる環境には十分注意が必要です。 ステキな観葉植物や鉢でいっぱい 個性あふれるサボテン・観葉植物と、さまざまな鉢たち。 店内に入ると、さまざまな模様の観葉植物やお手製の鉢がありました。シンプルなものから作家が作ったような個性的なデザインまで多種多様な鉢が並びます。 鉢とともにおしゃれな観葉植物も並んでいます。葉模様がキレイなカラテア・オルビフォリアや、白い水玉のベゴニア・マクラータ。モンステラ、ユッカなど室内で楽しめる観葉植物の種類も豊富です。 とても可愛らしい白い水玉のベゴニア・マクラータ。 観葉植物のまわりはインディアンのデコレーションで 横板張りのお店サイン。 インディアン酋長の髪飾り。 水牛の頭骨とインディアンの飾り。 店の名前「INDIAN GREEN(インディアングリーン)」のごとく、酋長がかぶりそうな髪飾りや水牛の頭骨などのインディアングッズがいっぱい飾ってありました。 このインディアングッズは、堀越さんのご主人が趣味で集めたもの。たくさんの収集品のほんの一部です。 銅管を加工して植物をオシャレにディスプレイ 円形に加工した銅管。 エアプランツの銅管スタンド。 とても興味を引かれたのが、オリジナルの銅管細工です。この銅管細工は、ご主人の趣味から発展して、さまざまなグッズに展開しています。銅管を円形や不整形に折り曲げて、植物と一緒に吊り下げたり置いたりできるグッズもあり、サボテンや観葉植物がおしゃれに飾れます。 銅管を加工したグッズ。 銅管とドライフラワー。 麻縄で編んだ一輪挿し。用途はいろいろ。 テラリウムを飾って海辺風に 木の皮やヒトデなどの自然素材に合う飾りたち。 ヒトデと一緒に並んだエアプランツなど、海辺のイメージのコーディネートが素敵な店内で、一際目を引いたのがテラリウム。 テラリウムとは、ガラスなどの光が通る透明なケースの中で植物を育てる方法で、保湿と保温ができるのが特徴です。このショップでは、「オーシャンテラリウム」として海辺のイメージで海砂や貝殻が多肉植物と組み合わされており、インテリアとしての新しい魅力を感じました。マリンテイストやハワイアンな部屋によく似合いそうです。 オーナーの堀越さんは、観葉植物のリースも作っているそうなので、興味のある方はお問い合わせを。 白と青の砂でシーサイドな雰囲気満点。 貝とサボテンもオーシャンビューなイメージで。 電線ドラムもテーブルに再利用! 最近、ちまたでよく見かける電線ドラム。この電線ドラムは、ガーデンファニチャーのテーブルとしてリユースされ人気。テーブルにちょうどよい高さ70×直径75cm、サイドテーブル向きの高さ50×直径40〜45cm程度のものなど、サイズもいろいろあります。 テーブルクロスをかけて利用したり、塗装してもオシャレなガーデンファニチャーになります。 この電線ドラムは、ご主人の仕事がら手に入るとか。オーナーの堀越弓恵さんは、今後も夫婦で力を合わせてお店の発展に努めていきたいと嬉しそうに語っていました。 電線ドラムがナチュラルなテーブルやいすに。 2階はレンタルできるオープンハウスに 広くて明るいオープンハウス。 オーシャンビューがステキなウッドデッキ。 2023年6月26日にINDIAN GREEN2階がオープンしました。ここはサボテンや観葉植物だけでなく、作家鉢やキャンドル、ドライフラワー、小物などの販売、およびイベントを行うオープンハウスとして展開しています。大きな窓からの佐島オーシャンビューも最高に美しく、明るく開放感のあるスペースです。 たくさんの植物に囲まれたリビング30畳、ウッドデッキ15畳の空間は、レンタルも利用できるようです。詳細は、お問い合わせください。https://indian-green.com/ キャンドルや作家鉢などのイベントもできる。 海辺の開放的なムードと植物がコラボするショップは、新たな発見がたくさんありました。リラックスした観葉&多肉ライフのアイデアをもらいに、お出かけしてみませんか? 取材先:INDIAN GREEN オーナー:堀越弓恵 Instagram: indiangreen_hyh
-
神奈川県

宿根草とグラスの美しいハーモニーで話題のガーデン「服部牧場」を訪ねる
初夏の服部牧場を訪ねて 左から時計回りに、クナウティア、ルドベキア・ゴールドスターム(黄花)、アスチルベ、ヘメロカリス・クリムゾンパイレーツ(中央赤花)、銅葉のニューサイラン、クナウティア・マケドニカ(赤い小花)、スティパ・テヌイッシマ、ヤブカンゾウ(ニューサイラン手前のオレンジの花)、バーベナ・ボナリエンシス(淡紫の背の高い植物)。 ガーデンストーリーで服部牧場をご紹介した最初の記事は、2020年1月に公開しました(前回記事はこちら)。ついこの間くらいに思っていたら、もう3年半の月日が経っていました。前回は、晩秋から初冬のグラスや宿根草の枯れ姿が中心でしたが、今回は今年2023年6月後半に訪ねた、さまざまな花が生き生きと咲き乱れる彩り美しい服部牧場のご紹介です。 左から、ヘメロカリス・ベラルゴシ(赤花)、アキレア(白)、ベルケア・パープレア(淡いピンクの花)、ダリア・サックルピコ(ヘメロカリス上のオレンジ)が左ボーダーの彩りに。小道奥で黄色く輝く葉は、ニセアカシアフリーシア、その左で丈高く茂るのはバーノニア。右手前では、バーベナ・ボナリエンシスが咲き、奥の銅葉のニューサイランの手前で、赤花のポンポン咲きダリア・サックルバーミリオンがアクセントに。 グラスがいい仕事をするガーデン 左下から時計回りに、スティパ・テヌイッシマ、フクシア・マジェラニカ(赤花で吊り下がった形状)、銅葉のニューサイラン、アメリカテマリシモツケ‘サマーワイン’(銅葉の木)、ホルディウム・ジュバタム(中央の生成り色のグラス)、ルドベキア・マキシマ(右上背の高い黄花)、フロックス‘レッドライディングフット’(赤ピンク花)、ヘメロカリス(桃色花)。 思い起こせば、3年前の僕は“グラスを多用したガーデン”こそが新しいガーデンの形だと信じ、夕陽に輝くグラスやシードヘッドの写真ばかり追い求めていました。グラスが多数植栽されているこのガーデンにも、何回も足を運んだものです。 左下から時計回りに、バーベナ・ボナリエンシス、バーベナ‘バンプトン’(ボナリエンシスの株元のこんもり姿)、ダリア‘サックルブリリアントオレンジ’(ポンポンダリア)、ダリア‘サックルコーラル’(隣のポンポンダリアの赤)、スティパ・テヌイッシマ、アガスターシェ・ルゴサ・アルビフローラ(スティパの上に写る縦長の花穂)、フロックス‘ブライトアイズ’(ピンク)、ミソハギ(ピンクのフロックスの後ろに写る縦の紫色の花穂)、クロコスミア‘ルシファー’(ミソハギの後ろ)、カライトソウ(中央ピンクの垂れ下がる花穂)、アメリカテマリシモツケ‘ディアボロ’(右上端の銅葉の木)、フロックス‘ブルーパラダイス’(右側中段の横に広がる紫の花)。手前で2本の花穂が上がるアカンサス・スピノサス‘レディムーア’がこのコーナーを印象付けている。 秋から冬にかけてこのガーデンを訪れた際は、グラスの美しいシーンをカメラに収めることで満足していましたが、やがて季節が変わり、春から夏になると、グラス類に代わって宿根草たちがガーデンの主役になっていました。 左/上から、アリウム‘サマードラマー’、ダリア‘ミズノアール’、ユーパトリウム・アトロプルプレウム(右上)、ベロニカストラム‘ダイアナ’(白のとんがった花)、グラジオラス‘バックスター’、アスチルベ・プルプランツェ(右端のピンク花)、メリカ・キリアタ(手前下のグラス)。右/ベロニカストラム‘ダイアナ’、ユーパトリウム・アトロプルプレウム(左上)、奥の彩りは、ヘリオプシス‘サマーナイツ’(黄色)とダリア‘熱唱’(赤花)。 宿根草が生き生きと育つそのそばには、グラス類が存在しています。代わる代わる咲く宿根草の花々は、それを引き立てる名脇役のグラスが組み合わされているからこそ美しいのだと、改めてこの庭に気付かせてもらったように思います。 カメラマンを唸らせる美しいガーデン 左下から時計回りに、アガスターシェ・ルゴサ・アルビフローラ(縦の花穂)、バーベナ・ハスタータ‘ピンクスパイヤー’、フロックス‘ブライトアイズ’(ピンク)、ダリア‘サックル・ルビー’(赤いポンポンダリア)、ミソハギ(サイロの屋根の下に写る縦の紫の花)、クロコスミア‘ルシファー’、カライトソウ(中央ピンクの垂れ下がる花穂)、ヘリオプシス‘サマーナイツ’(カライトソウの後方右に写る黄花)、アリウム‘サマードラマー’、ダリア‘ティトキポイント’(いろんなダリアが重なって写っているが、一重のピンクで中央がオレンジっぽいダリア)、オレガノ‘ヘレンハウゼン’(カライトソウの手前右)、バーベナ‘バンプトン’(カライトソウ左下のふんわり姿)、カラミンサ(オレガノの手前)、ミューレンベルギア・カピラリス(手前右角に写るグラス)。 この多くの宿根草やグラス類をナチュラルに組み合わせて美しいシーンを作り、いくつも僕に見せてくれるのは、“寝ても覚めてもガーデンと植物のことが気になってしまう”服部牧場のガーデナー、平栗智子さん。僕のガーデンフォトの最良のパートナーだと、いつも感謝しています。 上左/ヘメロカリス‘ブラックアローヘッド’ 上中/下からダリア‘冬の星座’、ユーパトリウム‘アイボリータワー’、アリウム‘サマードラマー’、バーノニア 上右/エキナセア‘ミルクシェイク’ 下左/モナルダ・プンクタータ 下中/ベルケア・パープレア 下右/カライトソウとフロックス‘クレオパトラ’。 ここでご覧いただいている写真は6月の服部牧場で、伸び伸びと育った大型の植物をふんだんに使う“平栗智子流のガーデンデザイン”による、生命感溢れるシーンばかり。夕方の沈みかけた綺麗な光で、思う存分撮影してきた大満足の写真満載です。 左下から奥の順に、エキナセア‘ピンクパッション’、トリトマ‘アイスクイーン’、スタキス、アスター‘アンレイズ’(緑色のこんもり姿)、パニカム‘ブルーダークネス’(アンレイズ左のグラス)、チダケサシ(アンレイズの後ろの淡いピンクの花穂)。右側、斑入りのフロックス‘ノーラレイ’とエキナセア、株元の丸葉は、ヒマラヤユキノシタ。 そして、各写真に添えられた解説は、平栗さんがこの写真を見ながら丁寧に品種名を書き出してくれたものです。この景色を作る鍵となる宿根草の具体的な品種名の数々は、ガーデンラバーズさんにとって最良のテキストになると思います。この記事で服部牧場の魅力の秘密が伝わることを期待しています。
-
スウェーデン

【北欧の美しい暮らし】カール&カーリン・ラーションの家と庭
スウェーデンを代表する芸術家が残した家と庭 19世紀から20世紀にかけて活躍した画家カール・ラーション(1853-1919)は、スウェーデンを代表する国民的な芸術家。そして、彼が妻カーリンと7人の子どもたちと暮らした家と庭、リラ・ヒュットネース(Lilla Hyttnäs、岬の小さな精錬小屋の意)は、現代に続く北欧スタイルのインテリアデザインにも大きな影響を与えた、理想の美しい暮らしの場として知られます。 このリラ・ヒュットネースがあるのは、湖と森の風光明媚な自然に恵まれたスウェーデン中部、ダーラナ地方の小さな村スンドボーン。現在はカール・ラーション記念館となって公開されています(家の中は予約制のガイドツアーのみで見学可能)。 芸術家カップルの理想の暮らしの場 カールの妻カーリンも、もともとは画家であり、2人はフランス留学中に出会って恋に落ち、結婚。スウェーデンに戻ったのち、1888年からは、7人の子どもたちとともにカーリンの父から譲られたこの家に住まうことになります。そして、1837年に建てられたスウェーデンの伝統的な木造家屋に、コツコツとリノベーションを重ねた彼らの創造性溢れる室内装飾は、現在に続く北欧スタイル・インテリアデザインの元祖となりました。 子育てのために絵筆を置いたカーリンでしたが、伝統的な手仕事に、アール・ヌーヴォーなどの当時最新のデザイン傾向を合わせて、家族との暮らしのための家具やテキスタイルのデザインに、その才能を開花させます。 室内は、当時さながらの可愛いカーリン・デザインのドレスの女の子が案内してくれるガイドツアーで見学できるものの、写真撮影は不可なのが残念。しかしじつは、カールが家族の暮らしの様子を描き、大人気となった画集『わたしの家』から、現在も残されている家の様子をそのまま知ることができます。 『わたしの家』 1895年制作, Our Home (メシュエン・チルドレンズ・ブックス, 1976年)より。※カール・ラーション『わたしの家』オリジナルの画集は1899年出版 美しく静謐な自然に囲まれた家は芸術家の制作活動にふさわしい場所で、多くの近隣の風景が次々とカールの作品の中に描かれました。しかし、長雨が続き戸外制作ができなかったある夏、家の中を描いたら? というカーリンの発案から生まれたのが、画集『わたしの家(Ett hem/ Our Home)』でした。 1895年制作 Our Home(メシュエン・チルドレンズ・ブックス, 1976年)より。 明るい色合いで繊細に描かれた暮らしの風景は、朗らかな歌声が聞こえてきそうなほどに、あたたかな彼らの暮らしの様子を生き生きと伝えます。インテリアや服装のディテールまでが仔細な描写で描かれ、今でも家のインテリアに取り込みたいような可愛いアイデアが詰まった本です。また、スウェーデンの家庭の季節行事などの様子もうかがえ、興味深々です。 「家」と「庭」がつくる家庭 カール・ラーション《大きな白樺の下での朝食》 1896年。 画集の中には、家族全員が庭のシラカバの木の下の大きなテーブルで朝食を摂っているシーンがあります。「家庭」という語が「家」と「庭」で構成されるのには、さまざまな意味で説得力を感じているのですが、特に夏は庭で過ごす時間も長かった彼らの暮らしにとって、庭は不可欠な、大切な存在でした。 画集に描かれたラーション家のガーデナーは、妻であり母であった芸術家カーリンです。 当時の最新流行だったイギリスのコテージガーデン風をよりシンプルにアレンジした庭は、湖と森に囲まれた周囲の風景と、ファールン・レッドが基調の木造家屋を程よくシームレスに繋ぎ、子どもたちが芝の上で遊び回ったり、家族で食事をしたりお茶を飲んだりするのに、とても居心地のよい、緑の暮らしの空間だったことでしょう。 現在は記念館を運営する財団のスタッフの方々が、当時の面影をなるべくとどめるような形で庭の管理をしているそうです。 湖畔の庭のチャームポイントは、眺めとガーデン・ファニチャー 庭の最大のチャームポイントは、なんといってもダイレクトに面した湖畔の眺め。白い桟橋から眺める対岸の風景と、キラキラ輝き変化する水面の様子は、穏やかな心休まる美しさ。 また、彼ららしさが表れるのは、庭のそこかしこでフォーカルポイントにもなっているオリジナルのガーデン・ファニチャー。水辺の大きな柳の木の側には、ファールンレッドの椅子とテーブル、湖を眺める半円形の白いベンチのコーナーなど、彼らがデザインした素朴なあたたかさと機能性を併せ持った木製のガーデン・ファニチャーは、タイムレスな北欧スタイルのお手本です。 湖畔を眺める半円形のベンチ。 北欧の春は遅く、訪問した5月中旬のタイミングでは、ボーダー植栽の植物たちは、やっと芽を出したばかりといったところ。花咲き乱れる姿を見ることはできませんでしたが、柳の木の爽やかな新緑が軽やかに揺れ、リンゴやリラなど果樹や花木の花が咲き、もう、それだけでとても魅力的でした。 ファールンレッドの犬小屋もかわいい。 庭の外柵の細い丸太を斜めに使った形は、ダーラナ地方の農場などでも多く使われる、この地方特有のスタイル。 地元食材レストランのランチタイム 庭は自由に散策でき、いつまでもいることができます。これでお茶でもできれば最高! なのですが、残念ながらカフェなどは併設されておらず……と思いきや、すぐ隣にテラスのある地元の食材を使った自然派レストランを発見。 ランチタイムには、食べ放題のビュッフェ形式で、野菜豊富なさまざまな郷土料理からデザートまでがサーヴされます。テラスでいただいたお料理は、ホッとする素朴な美味しさ。シナモンロールとコーヒーでフィーカ(おやつタイム)も楽しめます。 カーリンのデザイン作品の展示 スンドボーンの村を5分ほど歩くと、ギャラリーに到着。村の中も牧歌的。 また、スンドボーン村内のラーション家の近隣に増設されたギャラリーでは、カーリンのデザイン作品の展覧会が開催中で、さまざまなファニチャーやテキスタイルのリプロダクトが展示されており、彼らの美しい暮らしの世界観にたっぷり浸ることができました。 ギャラリー入り口。 展示風景の例。 絵画に描かれていた窓辺のシェルフも展示されていました。左/1912年制作、 スウェーデンの国民画家 カール・ラーション展 (読売新聞社/美術館連絡協議会, 1994年)より。 ミュージアムショップも充実。 自然の中の、北欧の美しい暮らしの世界 豊かな自然と庭に囲まれたラーション家の丁寧な美しい暮らしの様子は、隅々まで美意識を感じる、しかし気取らず素朴な、どこか懐かしく温かな記憶を呼び覚ますよう。今でも、1世紀以上を経たとは思えないような、タイムレスな魅力に満ちています。
-
ドイツ

ドイツ・マンハイムで開催中! ドイツ最大のガーデンショーをレポート! 2
BUGA2023の体験レポート第2弾! Daniela Baumann/Shutterstock.com 現在ドイツ・マンハイムで開催中のドイツ最大のガーデンイベント、BUNDESGARTENSCHAU(BUGA)。BUGA2023は、マンハイム市とその周辺地域における持続可能な生活の質とライフスタイルを向上させることをコンセプトに行われていて、178日間という長期の開催期間中には、さまざまなテーマのガーデンが見られることに加え、フラワーショーや文化交流、レジャーやスポーツといったアクティビティーなど5,000以上のイベントも企画されています。 ちなみにBUGAは2年に1度、ドイツのどこかの街で開催されるのですが、今回BUGAの会場となったマンハイムには、BUGAのエリアのほかにも魅力的なガーデンがあります。例えばオーグステンパークのウォータータワー。今回宿泊した、BUGAの会場から徒歩10分ほどのホテルの目の前にあり、BUGAへ向かうまでにも楽しい時間を過ごすことができました。 BUGA2023のもう一つのエリア、スピネッリパークへ BUGA2023の会場には、大きく分けてルイーゼンパークとスピネッリパークの2つのエリアがあります。ルイーゼンパークをご紹介した前回に続き、第2回となる今回は、スピネッリパークをご案内しましょう。 Daniela Baumann/Shutterstock.com 印象的で魅力的なBUGAの前半部分で、大きな木々やしっかりした植物、多くの建物があるルイーゼン公園を堪能した後、ケーブルカーに乗っていざスピネッリパークへ。ネッカー川にかかるこのケーブルカーが、ルイーゼンパークとスピネッリパークを結んでいます。ケーブルカーからは市民農園やネッカー川、古い農家の建物とたくさんの野菜畑があるロマンチックな農場、本物の芝生の上に大きなサッカー場があるスポーツエリア、小麦畑などを一望でき、美しい景色を眺めながらBUGAの会場を巡ることができます。空中の旅を楽しみながら、7分ほどで広く開けた目的地に到着。遠く離れたコーナーにマンハイム・タワーが見え、他の方角には片側にネッカー川が、その反対側にはマンハイムの住人のための高層居住区があります。BUGAのケーブルカーのよい所は、乗車料金が既に入場料金に含まれていること! 歩き疲れた後にぴったりですし、ケーブルカーに乗るだけでも楽しいので、もっと時間があったら、もう一度乗りたいくらいでした。 Ingrid Balabanova/Shutterstock.com スピネッリパークの8つのエリア Daniela Baumann/Shutterstock.com スピネッリパークはかつての軍事基地、およそ80ヘクタールの跡地につくられたガーデンです。建物のいくつかは保存され、カラフルな花や展示のための場所としてリモデルして利用されています。スピネッリパークのエリアをご案内しましょう。 1.ウェルカムエリア Daniela Baumann/Shutterstock.com ここでは、シャトルバスや公共交通機関、自転車、徒歩などで南エントランスから入場してきた人々を迎えます。南ウェルカムガーデンには、気候耐性の強いムギワラギクやサルビア類、スターチス、ユーフォルビアの仲間などを生かしたボーダーガーデンがあり、ジニアやケシの花が咲くエリアもありました。 乾燥や直射日光に強く、種類豊富なユーフォルビア。Gartenbildagentur Friedrich Strauss / Vazquez, Domingo カサカサとした花弁のムギワラギクとカラフルなチガヤの組み合わせ。Gartenbildagentur Friedrich Strauss / Strauss, Friedrich カラフルな花を咲かせるケシ。日本でもよく栽培される花ですが、品種によっては日本で栽培が禁止されているものもあります。Gartenbildagentur Friedrich Strauss / Mann, Dirk 2.U-HALL Ingrid Balabanova/Shutterstock.com 21,000㎡のエリアに19の小さなホールが、アルファベットのUの形に並ぶこのエリアが、BUGAの中心部。その形から、U-HALLと呼ばれています。 フラワーショーの中でも重要なハートピースで、さまざまなテーマのホールはクリエイティブで見るべきものがたくさんあり、天気が悪い日にゆっくり楽しむのにも最適です。休憩スペースやグルメも充実していますよ。 U-HALLの周囲には、武骨な建造物をカバーするつる植物がたくさん植わり、グラス類やさまざまなサイズのワイルドフラワーも植栽されています。 クレマチスなどのつる植物は構造物のカバーにぴったり。Gartenbildagentur Friedrich Strauss / Niemela, Brigitte 細長い葉が周囲の花を引き立てるグラス類。Gartenbildagentur Friedrich Strauss / Strauss, Friedrich フラワーショーやガーデンなど屋外の空間は、天気や訪れるタイミングによって印象が大きく異なるものです。私の知人の一人、花やガーデンの愛好家が、春にBUGAを訪れたそうなのですが、彼女の感想は私のものとは全く違いました。まだ植物が小さかったため、全体に植物の量が少なく見えて、あまり満足できなかったそうです。 株がまだ小さい春の庭は、花が咲いていても少し寂しい印象。Gartenbildagentur Friedrich Strauss / Strauss, Friedrich 植物にとっては太陽光や暖かさ、十分な水と時間がパフォーマンスを発揮するために必要ですが、春はまだ気温が上がらず、水が不足することもあって、春のガーデンで生き生きとした植物たちの姿を見るのはなかなか難しいもの。そのため、彼女の印象は私とは異なるものになったのでしょう。 頼りなかった苗も、夏にはしっかりと茂ってくれます。Gartenbildagentur Friedrich Strauss / Strauss, Friedrich 幸い、私が訪れた時期は、少々暑すぎではあったものの、ベストな天候の時期。植物たちはよく管理されて最盛期の姿を見せてくれました。 3.トライアルエリア トライアルエリアでは、BUGAの4つのメインテーマである、気候、環境、エネルギー、食料安全保障をテーマにした展示が見られます。 4.SDGsガーデン いまやSDGsに配慮することはすっかり定着しましたが、BUGA2023でもSDGsは重要な課題。ここでは、17のトライアルガーデンが、それぞれSDGsの17のゴールを表しています。それぞれのガーデンルームはブナの生け垣で区切られていて、テーマとなったSDGsの目標とガーデンの解釈についての説明がイラストを用いて示されています。例えば「健康」のテーマは、ハーブガーデンで表現。時にはポイントを理解するのに相当想像力をたくましくさせなくてはいけないこともあります。 5.未来の木 ナーセリーのように長い列になって木々が並ぶエリア。これらの木は、BUGAの終了後には市全体に植えられる予定です。 6.クライメイトパーク スピネッリパークの中にある、およそ62ヘクタールの広大なクライメイトパークは、新鮮な空気が感じられる都会のオアシスでもあります。都市の気候を大幅に改善し、都市住民に広々としたオープンスペースを与えてくれるこのエリアの一角は、いわゆるステップ地帯風につくられています。この栄養の乏しい草原を再現した部分は、野生生物、昆虫、トカゲ、その他の小動物にとっても重要な場所になっています。 Gartenbildagentur Friedrich Strauss / Wothe, Konrad 7. パノラマビュースポット 川にかかる長さ81m、高さ12mの錆びた赤い展望台は、一見橋のように見えますが、じつは川の上で終わっています。そこからは、下の湿地帯と遠く離れた街のスカイラインを眺めることができる、素晴らしいビュースポットになっています。 8.遊びとウェルネスエリア Daniela Baumann/Shutterstock.com アパートとスピネッリ公園の間にある都市の住居エリアの隣には、たくさんの屋外遊戯スペースを備えた子供向けのエリアが。できたばかりなので、まだ木陰もほとんどありませんが、年々改善されて、そこに住む家庭にとっては大きなメリットになることでしょう。広々としていて空気も美味しいので、トレーニングに励むのもいいですね。 Daniela Baumann/Shutterstock.com ほかにも楽しい場所がいろいろ! こうした数々のガーデンアイデアの中で、最も印象に残ったのが、サンプルガーデンで見つけたプール! 土を掘ってつくった美しい楕円形の低いプールの周囲には、グラスを取り入れた宿根草ボーダーガーデンが広がり、温暖な気候らしい雰囲気が漂います。プールを見渡すウッドデッキには、広々とした日よけと快適なデッキチェアが備え付けられ、着替えもできる小さな可愛い小屋も魅力的です。 若者や年配の訪問者がプールに挑戦したり、水温をチェックしたりしている姿を眺めながら、何時間でも過ごせそうでした。このプールのトリッキーで面白い点は、形が正方形で均一な深さではなく、端がわずかにアーチ状になっているため、中でバランスを崩す人が続出していたこと。10 代ぐらいの少年 4 人のグループは最終的にかなり濡れてしまい、そのうちの 1 人は完全に水の中に浸かってしまっていました。天気もよかったし、引率の先生が怒る様子もなかったのでよかったです。 小さな足湯を使う人もいて、皆、とても幸せそうでした。隣にあった3つのデッキチェアもすぐに埋まり、その人たちと会話が生まれて、素敵な時間を過ごすことができました。 Daniela Baumann/Shutterstock.com BUGA2023のお気に入りのポイントは、芝生などをはじめどこにでもスチール製や木製の休憩用の椅子やベンチが豊富にあったことです。こうした場所があると、広いガーデンを歩き回った後に、ちょっと一息つくことができますね。 こうして何時間も歩いた後、スピネッリ公園のエリアを一周する小さな「パークトレイン」に乗る機会がありました。電車の中ではまたしても、スイスから来たカップルと会話が弾み、この素晴らしい場所の感想を交換することができて、楽しい時間になりました。 ガーデンショーに行ってみよう Ingrid Balabanova/Shutterstock.com こうした国立のガーデンショーは都市の発展にとって非常に重要かつ不可欠であり、植物や自然と触れるショーケースになっています。 何年にもわたるガーデン巡りの中で、すでにいろいろなガーデンショーを訪れていますが、それぞれに独自の魅力ポイントがあり、毎回、たくさんの刺激と新しいアイデアをもらうことができる場です。 ぜひ、植物に興味のある友人と一緒に訪問し、時間をたっぷり使って、会場に向かう時間から楽しんでみてはいかがでしょう。大抵のガーデンイベントは敷地が広いので、楽しむためには十分な休憩も欠かせません。また、一年の中で適切な季節、あなたの好きな季節や天候も考慮して訪れる日程を決めるのがおすすめです。 今回の私の訪問は夏のピーク。幸運にも一年で最高の季節で、この素晴らしくて幸せなイベントを堪能することができました。ぜひ皆さんも、いろいろなガーデンイベントを訪問してみてくださいね。
-
スウェーデン

北欧のドリーム・ガーデン「ローゼンダール庭園」案内
自然豊かな市民の憩いの場所 スウェーデンの首都、ストックホルムを構成する14の島々のひとつ、ユーゴルデン島は、中心から自転車やトラムで10〜15分程度とアクセス抜群の立地でありながら、水に囲まれた豊かな森の自然に触れられる市民の憩いの場所です。5月下旬、スズランの群生を足元に見ながらこの森の中を進んでいくと、北欧のドリーム・ガーデン、広い林檎園や温室、ポタジェ(菜園)が並ぶローゼンダールトレードゴード(トレードゴードは庭園の意)が見えてきます。 ローゼンダール庭園への道のり、至る所が爽やかな水と緑に彩られるユーゴルデン島の遊歩道。 小さくて見えにくいかもしれませんが、シカも散策者をお出迎え。 森の林床のグラウンドカバーは野生のブルーベリー。 歴史ある開かれた王立庭園 右のイラスト版の庭園案内図がかわいい! ショップにはトートバッグやポスターなどのグッズもありました。 19世紀までは王族の狩猟の獲物のための保護地区だったがゆえに自然がそのまま残されたこの場所に、1810年、スウェーデン王となった仏人ベルナデットが夏の離宮とイギリス風景式庭園をつくったのがローゼンダール庭園の始まりでした。森に囲まれたこの庭園は当初より市民に開放され、王族の避暑地であるとともに、市民の散策の場所にもなりました。開かれた市民のための庭という伝統は、現在に続くローゼンダール庭園の進化のバックボーンになります。 19世紀につくられたオランジュリー。手前にはバラ園とブドウ畑、ラベンダー畑が。 この開かれた庭園をさらに拡張したのは、園芸愛好家だったベルナデットの息子オスカー1世とその妻ジョゼフィーヌ王妃でした。1860年には園芸協会によって、スウェーデンで初めてのガーデナー養成学校がローゼンダールに開校し、700人のガーデナーを養成します。それは、ガーデナーの養成にとどまらず、スウェーデン全体にガーデニングを普及するムーブメントの発端となり、ローゼンダール庭園は、スウェーデンの人々にとって憧れのモデル・ガーデンの役割を果たしていきます。 庭園のコアである、1世紀半の歴史がある林檎園。不思議なほどピースフルな場所。 森の中の林檎園 ローゼンダールを訪れた際に、ひときわ印象的なのが、自然溢れる立地環境です。現在では王立公園として管理されている、苔や野生のブルーベリーがグラウンドカバーになった素晴らしい自然の森の中では、シカがゆったりと佇んでいたり、水辺をさまざまな水鳥たちが行き来するなど、その景観は都市にいることを完全に忘れてしまうほど。鳥の歌を聞きながらゆるゆると散策を続けていくと、19世紀のオランジュリーの建物や広大なポタジェ(菜園)、ベーカリーやカフェ、レストランなどの入ったおしゃれな温室、そして林檎園が見えてきます。 温室を利用したカフェやベーカリー・ショップは素朴なのにおしゃれ。 樹木のアーチをくぐると林檎園への入り口。 150年前に植えられたという400本の立派な老樹が並ぶ広い林檎園は、ローゼンダール庭園がつくられた19世紀から残る歴史的な場所。収穫されたリンゴの出来のよいものは、販売用にショップへ、またレストランとベーカリーに届けられ、それ以外のものはリンゴジュースなどに加工されるそうで、1世紀半を経たリンゴの木々は現在も活躍中です。 5月はリンゴの花盛りでした! そこかしこに設置された椅子やテーブル、ベンチでは、リンゴの木の傍で、ゆったり読書をする人、見つめ合う若いカップル、賑やかな家族連れなど、さまざまな人が思い思いの時間を過ごしています。ピースフルな空気感が溢れるこの場所には、ただいつまでもここでこのまま過ごしたい、そんな気持ちになる、マジカルな時間が流れています。 林檎園の片隅では養蜂も行われています。 この林檎園は、歴史的であるとともに庭園全体のコアになっている場所で、林檎園を囲むように、ベーカリー、レストラン、ガーデニングショップなどの入った温室と野外テラス、子どもの遊び場があり、オランジュリーの前には小さなブドウ畑とバラ園、そして広大なポタジェが作られています。 理想の庭のかたちとは? ビオディナミ農法のポタジェ 野菜の季節の到来を静かに待つ、中央の小さなガーデンシェッドがポイントの5月中旬のポタジェ。 ところで、ローゼンダールでも、20世紀初頭には庭師養成の学校が廃止され、庭園が忘れられつつある存在となった時期がありました。その後1980年代、ここで未来のための新しいパーフェクト・ガーデンをイメージしようという動きが生まれ、再びローゼンダール庭園が活性化した頃に取り入れられたのが、大地と自然のリズムを尊重するビオディナミ農法でした。 ワインのためのブドウ生産などでもよく利用されるビオディナミ農法は、ごく簡単にいえば月のリズムに基づいた自然農法。ポタジェの一角のコンポストは、土壌づくりから始まる栽培サイクルのカギとなる重要な要素です。 カフェ・レストランの風景。中央に並ぶ旬のポタジェの野菜や果物を使った日替わりのメニューは、全部食べたくなる! 花咲き乱れる美しいポタジェで採れた野菜は、採れたてが園内のレストランとベーカリーに届けられます。毎日のレストランのメニューと皿数を決めるのは、ポタジェの収穫。良質な季節の恵みをダイレクトに味わえるよう、調理はシンプルを心がけているのだそう。見ただけでも、食べたらさらに、幸せそのものを味わえそう。 温室内のテーブル席、野外のテラス席、はたまた前出の林檎園で。と、園内の好きな場所を選んで、オーガニックのランチやお茶を楽しめます。 冬が長い北欧では野外で過ごす季節が短いだけに、美しい景観も美味しい自然の食べ物もぜんぶ合わせて、心地よい庭の楽しみ方に敏感なのかもしれません。 遠足の子どもたちも楽しそう。天使の彫像の奥には、子どものためのメイズ(迷路)があります。 分かち合う庭、ナチュラルでシンプルな幸せ空間 大地と自然のリズムにしっかりと繋がった、美しいばかりでないエディブルな庭、ローゼンダール庭園は、誰もに開かれたみんなのための庭です。数十年前、2人の若い庭師ラース・クレンツ(Lars Krentz)とパル・ボルグ(Pal Bolg)が、19世紀につくられた歴史的庭園を土台に、未来の庭はこうであったらいいだろうとイメージしてつくり始めたこの庭は、訪れる人々すべてに庭の楽しみと癒やしを分かちつつ、現在も進化を続けています。
-
高知県
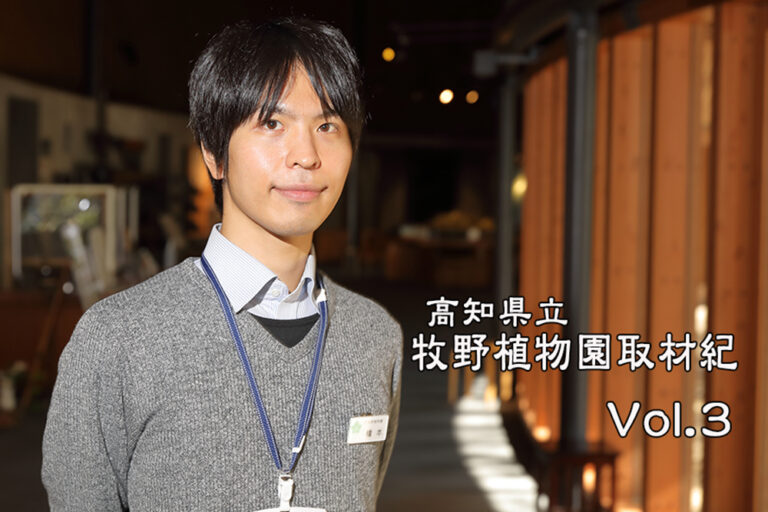
【牧野植物園広報部インタビュー】愛されキャラの牧野富太郎と博士の思いをつなぐ牧野植物園の未来
牧野植物園について 牧野植物園には、県内のほとんどの人が、子どもの頃に遠足で来たとおっしゃるんですよ ガーデンストーリー編集部(以下GS):植物園のある五台山は、牧野富太郎博士が何度か植物採集に訪れていたそうですが、そうしたことからこの地が選ばれたのでしょうか? 橋本:そうですね 牧野博士はここに限らず、高知全体をフィールドとして調査に行っています。もちろん、この植物園のある五台山にも何度か植物調査に訪れています。しかし、ここに植物園の設立が決まったのは、その調査からもっと後の話になります。 園の設立に関しては、明確に博士からの希望があったわけではなく、県民はじめ有志の働きかけによるものだと聞いていますが、牧野博士自身も「植物園」というものの建設の必要性はかねがね明言されていたことが書籍などで確認できます。計画が具体的になったのは昭和29年で、まず「牧野博士記念植物園設立準備会」ができ、昭和31年に設立が決定しました。 これは推測ですが、おそらくその準備会の中で、いくつか候補地が挙がったのではないでしょうか。地形の調査も行ったようですし。でも結局は、博士に「どこがいいですか?」と伺ったところ、「それなら五台山がいい!」という鶴の一声で、ここにつくられることが決まりました。 当時のここ五台山は、いくつかの私有地が混在していて、最終的に竹林寺の当時のご住職からご厚意をいただき、お寺の一角であった宿坊(寺院の宿泊施設)と呼ばれるエリアにつくることになったと聞いています。 北園の山頂付近に広がる「こんこん山広場」に横たわる2本のスモモの木は私有地時代の名残で、当時は無数のスモモの木が花を咲かせ、山肌を白く染めたそうだ。 GS:植物園の存在は、地元にどのような影響を与えてきたと思いますか? 橋本:当園は地元の方々に親しんでいただいており、来園のお客さま、特に県内の方に「過去に園に来たことありますか?」と尋ねると、多くの方が「子どもの頃に遠足で来た」っておっしゃるんですよ。 今でも小中高と、遠足や課外授業で来られる方も多いのですが、県民の多くの方が幼少期から学生時代に、少なくとも一度は訪れているように思います。 私どももさまざまなイベントを催していますので、大人になってからはそういった催事の話題をきっかけに再訪しようかな、という流れもあるようです。 GS:それは素敵な話ですね。幼少期にこんな素敵な植物園の思い出があるなんて、うらやましいですよ。 橋本:特に高知市内にお住まいの方は、そういった思いが深いのではないでしょうか。また、今回NHKの連続テレビ小説の題材になったことで「我が地元に牧野植物園在り!」と再認識され、再訪される方も多いですね。 GS:地元の方にとっては、今回連続テレビ小説の題材になったことは、これ以上ない誇りでしょうね。 橋本:そう思います。 牧野植物園がきっかけで、さらに植物愛が増してもらえるのは嬉しい GS:植物園が日本の園芸文化にもたらした影響についてはいかがでしょうか? 橋本:地元に対してはこのように大きな影響を持つ牧野植物園ですが、日本の園芸文化への影響というところでは、私自身の考えとしては、当園の在り方が、園芸のそれとはちょっと方向性が異なるかなと思います。しかし牧野博士の研究は、その垣根をまたいでいたものもあるため、人の手によって愛でられ栄えてきた日本の園芸文化と、自然界の植物を分類していく博士の研究とは、少なからず交わる部分もあるとは思います。GS:確かに、日本の園芸文化というと、例えば変化朝顔とか江戸菊のように、人の手によって改良を重ねられ、美術工芸品のような位置付けで楽しまれる植物が代表的ですね。 橋本:そうですね。もちろん、植物を愛する畏敬の念に隔たりはないのですが、ただ、牧野植物園に来園される方は、どちらかというと園芸植物よりも、山野草や高山植物のような人の手によるものでない野生の植物、ありのままの自然が好きな方が多い印象です。 しかし最近では、蘭が好きな方や多肉植物が好きな方が来園されたりと、割とボーダーレスでお客さまがいらっしゃるようになったと思います。 私たちとしては、きっかけはなんでもいいんです。研究としては線引きがあっても、植物を愛でる気持ちに線引きなどあろうはずもなく、お散歩がてら来ていただくのも嬉しいですし、博士のことを伝記などで読んだり、今回の連続テレビ小説を通じて興味を持たれたり、さまざまなきっかけで牧野植物園に遊びに来ていただければ嬉しいんです。 こうして、今まで植物に興味があった方も、なかったけど持ち始めたという方も、園芸というよりは、もっと大きなところで植物への興味の足掛かりに牧野植物園を使っていただければ嬉しいですね。それにより日本の園芸文化にも、植物を愛する方を一人でも多く生み出す、というフィードバックができるのではないかと思います。 GS:園を散策してみて、植物一つひとつにじつに細かくプレートが立てられていて、いかに博士が植物分類学に心血を注いでいたかがうかがえました。来園者はこのプレートからより深い植物の知識を得ることができ、関心も高まりますよね。そういった意味でも博士の研究と現在の園芸文化とのクロスオーバー的な役割を、この植物園が果たしているのだな、と思います。 私たちの生活とも関わりの深い植物などが多数植えられた薬用植物区の一部。植えられている全ての植物の側には、その植物の詳細が記されているプレートが立つ。 橋本:当園は自然風植栽を意識しているため、例えばご自身が鉢植えとして楽しまれているものが、自然の中でどのように息づいているかを見ると、よりその植物への愛も増すと思いますし、栽培のヒントにもなったりするのではないでしょうか。 博士自身も園芸文化を決して否定せず、むしろ植物を愛する気持ちに対しては心は一つ、という考えの方だったので、牧野植物園がきっかけで来園者の植物愛がさらに増すというのは嬉しい限りではないかと思います。 GS:ここは場所柄、山に吹き抜ける強風が植物の幹を太くし、強くしていると伺いましたが、言ってみればそれが自然の創り出す造形美であり、植物が健康に育つためには、いかに風が重要かも分かりました。 牧野富太郎博士について <写真提供:高知県立牧野植物園> 研究って一方通行では決して醸成されないもの GS:牧野富太郎博士は植物について並々ならぬ関心と情熱を持ち、研究や教育普及活動に生涯を捧げた方ですが、同じ道を歩まれている後進の方々から見るとどんな方ですか。 橋本:やはり植物学や植物分類学というものについて、まだ当時(明治〜昭和期)は欧米に遅れをとっていた日本のレベルを世界レベルまで引き上げたのは牧野博士なので、そのレガシーを継承し、同様の研究を進めている専門家たちから見れば、牧野博士はまさに先駆け的な存在です。 また、牧野博士は採集した植物を描いた植物図の分野でも日本では先駆者であり、そのディテールの再現性と息を呑むような美しさには、先進的だったはずの海外の植物学者も驚嘆したといわれています。 明治11年、牧野富太郎が16歳の時に描いたもの。少年の頃にすでにここまで緻密な植物図を描いていた。 GS:牧野博士は植物分類学の研究を世界水準まで高めたということですが、そもそも当時、日本の植物学は海外から注目はされていたのでしょうか? それとも、謎めいた極東の小国から、牧野博士が積極的に海外に向け情報を発信していて、それが功を奏して海外からも注目を浴びるようになったのですか? 橋本:すでに世界から注目されていたとは思いますが、当時は、文明的、歴史的な背景もあり、情報流通は極端に少なかったと思います。おっしゃるように、未知なことが多い極東の小国から、博士のほうから積極的に発信したのだと思います。そもそも研究って一方通行では決して醸成されないものなので、徐々に情報のネットワークが作られ、レベルも上がり、評価を得た、ということだと思います。 GS:一方通行だった研究を双方通行にして、日本の学術レベルを底上げした博士の功績は偉大ですね。 そもそも、牧野博士が一般常識人であったら植物分類学者牧野富太郎は生まれていなかった GS:そんなフロンティア精神溢れる博士には、ユニークなエピソードもたくさんありそうですね。 橋本:牧野博士はとにかく、どんなことにも探究心が旺盛で、凝り性だったようですね。幼少期には、実家の番頭が持つ懐中時計を借りた博士は、その仕組みが知りたくて、借り物にもかかわらず、バラバラに分解してしまったそうなんです。 GS:貸した方はさぞびっくりしたでしょうね・・・。連続テレビ小説でもそのようなシーンが盛り込まれると面白いですね!(実際に放映では、子供時代に番頭さんの懐中時計を分解しちゃったという形で再現された) 橋本:そうですね(笑)、あとは、博士は海外から大量のシリーズ物の書籍を取り寄せたりもしていたんですが、それらも抜け落ちることなく、ちゃんと全巻揃えてコンプリートしていたそうです。とにかく凝り性だったようですね。凝り性がゆえに、家計が傾いたのですが・・・。GS:家計を傾ける凝り性のことを「Rock ‘n’ Roller」というんですよ(笑)。独り身ならいざ知らず、妻君のご苦労は察して余りあります。 橋本:全財産を研究に注ぎ込んでしまうわけですから、確かに妻の壽衛さんは大変だったと思います。でも壽衛さんは、お子さんには「お父さんは世界的な研究をしている人だから、我が家は決して裕福ではないけれど、決して恥ずべきことではないんだよ」と言って、最大限の理解を示して家庭を支えていたんです。 そもそも論ですが、牧野博士が一般常識人であったら、植物分類学者牧野富太郎は生まれていなかったのではないかと思います。 若き日の牧野富太郎と妻壽衛。<写真提供:高知県立牧野植物園> GS:ある分野で突出した人は、一般常識が通じない部分が必ずどこかにあると聞きます。まさにそれですね。私の経験則では、そういう人は自己陶酔型が多いですが、牧野博士にはそれが感じられない。 橋本:そうなんです! 博士は大人、子供、老若男女の分け隔てなく、誰にでも同じように接して植物の知識を広めていった方なので、そんなところが多くの人に愛され、愛されるから支援者が現れ、親しみを持たれるからこそ、日本全国から標本が集まり、博士も知識を集積することができたんです。その結果、現在語り継がれている偉業の数々を成し遂げることができたんです。 GS:細い1本の糸が束になって、太い1本になった、ということですね。 橋本:はい。博士のお人柄のなせる業ではないかと思いますね。 出生の地、佐川町の風土も大きな影響を与えた GS:14歳のときに小学校を自主退学し、早くも植物研究の道を歩み始めている博士ですが、牧野富太郎博士が若くして植物に強く関心を持つに至ったのはなぜなんでしょうか? 橋本:牧野博士は幼少の頃に両親と祖父を亡くされて、祖母に育てられました。そんな少年時代に、肉親の愛に代わって心を満たしてくれるものが植物だったと自らも語っています。つまり、何か1つきっかけがあったというより、常に植物に寄り添い、共に日々を送っていたわけです。加えて、日本の野生植物の種類の約4割が自生しているともいわれている地元高知の自然の豊かさも大きな影響を与えたのではないでしょうか。10代〜20代前半の頃は、博士はすでに高知県の植物をくまなく調査していました。ですから影響というか、高知の自然こそ、博士の研究の源になったのだと思います。 GS:植物王国土佐の大地を駆け巡るフットワークの軽さもさることながら、そもそも学習意欲も旺盛だったのですね。 橋本:それは間違いないですね。地元でも有数のレベルの高い私塾に通い、そこで読書、天文学や物理学、英語の読み書きを学んでいました。教育に熱心に取り組み、多くの識者を輩出しているこの佐川町の風土も大きな影響を与えたのではないでしょうか。 高知は山を越えるごとに地域の特色も変わるのですが、佐川町は「佐川山分学者あり」(佐川は山も多いが学者も多いという意味)という言葉ができるほど、学問が盛んな町だったため、そのあたりも後年の富太郎を形成する苗床になったはずです。 GS:学問で肥えた土から、まさに黄金の苗が芽生えたわけですね。 橋本:いろんな要素はあると思いますが、やはり牧野富太郎を突き動かしたのは、ひとえに植物への愛ではなかったのかなと思います。 GS:歴史の必然というかなんというか、どれか1つでも欠けていたら、もしかしたら牧野富太郎は生まれなかったのかもしれませんね。 橋本:そうですね、もし両親といわずとも、どちらかの親が存命だったり、他の子どもみたいにちゃんと学校に通っていたり、場所が高知でなかったり、このどこかが異なるだけで、牧野富太郎の人生は私たちが知っているものとは違う歩みになっていたのかもしれません。 今回のドラマをフックにして、牧野富太郎の存在を広く周知したい GS:ところで、その牧野博士は昨年生誕160年を迎えましたが、博士の存在がクローズアップされている今年2023年、牧野植物園としては博士が日本の園芸に残した足跡、功績をどのように伝えていきたいですか? 橋本:牧野富太郎は、まだ全国的に知名度は低いと思うんですよ。確かにドラマのおかげで知った方も多いとは思いますが、それでもいまだに高知のパブリックイメージは、高知=坂本龍馬、だと思うんです。 我々としては、今回のドラマをフックにして、牧野富太郎という世界レベルの植物分類学者がいたんだという事実、そしてそれを生んだのが高知であるということを発信し、その結果植物に興味をもってもらい、牧野富太郎のエッセンスを当園で感じてもらう。いわば、「情報」を「体感」へと繋げていければ、と考えています。 なので、私たちとしてはひたすら牧野富太郎という人の偉業と人間性を発信していき、今までの高知=坂本龍馬が、高知=牧野富太郎というように瞬時にイコールで結びつく、そんなところを目指しています。 園内に植えられていた高知の特産品「ブンタン」。マーマレードにすると絶品! 高知は果物も豊富なのだ。 NHKの連続テレビ小説「らんまん」について ドラマ化を推進する会が結成され、署名活動が行われた経緯もあります GS:NHKの連続テレビ小説「らんまん」について、地元の方、そして植物園の皆さまはどんな風に受け止めていらっしゃるのでしょうか? 橋本:じつは以前から、ぜひドラマの題材に、というリクエストは県内の複数の箇所から出ていました。また、それを推進する会が結成され、署名活動が行われた経緯もあります。署名活動が直接的にNHK側の選考判断材料になったかは分かりかねますが、県民を挙げて牧野博士の周知を願っていたわけですから、これはあくまでも私の想像ですが、そういった活動が少なからず選考に影響を与えた部分もあるのかな、とは思います。 GS:橋本さんご自身は、テレビ化の決定を聞いたとき、どう思いました? 橋本:それは嬉しかったですよ! ここ(牧野植物園)に携わっている全ての人が、牧野博士のことを愛し、敬意を払っているので、博士の偉業と魅力が世間に、しかも全国ネットで周知されることを名誉に感じています。 GS:実際に署名活動に携わった方たちにとっては、まさに思いが報われた瞬間だったのですから、これはもうシャンパンファイトでもしたい気分だったでしょうね。こうして、ドラマの題材になったことによって、牧野植物園はどう変化すると思いますか? 橋本:そうですね、まぁ忙しくはなるでしょうね(笑)。 でも先ほども言ったように、それがきっかけで牧野富太郎に興味を持ち、植物に興味を持ってもらうことは、私たちにとっては嬉しい相乗効果です。お客さまに今後どのようなアプローチで植物に興味を持ち続けていただくのかを考えながら、牧野植物園もコンテンツをブラッシュアップしていかなければなりません。このたび、正面入り口と南門の間に植物研究交流センターという建物を新たにオープンしました。 そこでは、さまざまなワークショップやイベントを行っています。また、リニューアルしたレストランやミュージアムショップもお楽しみいただけるのではないかと思います。 牧野博士は“植物は楽しいものだ”ということを世界中の人に知らせたかったし、実際に知らせたわけですから、変化するというよりは、変わらずにその思いを継承していきたいですね。 建設中(2022年12月当時)の植物研究交流センター。 牧野植物園のこれから 牧野植物園を通じて、植物に関する正しい情報を発信していくことが私たちの使命 GS:Webマガジン「ガーデンストーリー」の読者は園芸を愛好する人たちで、さまざまな形で園芸を楽しんでいます。読者の皆さまに、牧野富太郎博士のどんな部分を知ってほしいですか? また、牧野植物園のこれからの取り組みなどを教えてください。 橋本:博士の行っていた植物研究は、基本的に人の手が加わっていない自然そのものの植物が対象であったため、人の手が加えられる園芸文化と必ずしも合致する部分ばかりではないのですが、ベースにある植物愛というところでは大きく共通していると思います。 ただ牧野博士の場合は(想いが)突き抜けてしまっていたために、研究者として偉大な功績を遺すことができたのですが、その突き抜けていた部分を、連続テレビ小説や当園を通じて、感じて、そしてファンになっていただければ嬉しいですね。なにしろ牧野富太郎は生前、自身のことを「草木の(妖)精」と言ってはばからなかったそうですから。 GS:植物への興味の有無にかかわらず、牧野富太郎という人の生き様に対して、連続テレビ小説を通じて興味を持つ方は多いと思います。 橋本:牧野博士の時代と違い、現代は情報が氾濫しているため、一つの分野を追求するのって難しいと思うんです。それがいばらの道になったら、楽な道も簡単に探せるわけですから。だからある意味、博士みたいなブレない生き方に憧れを覚える視聴者の方も多いのではないでしょうか。 そうして興味を持っていただいた方に、植物の種を本来あるべき姿で保存していくということの大切さ、そして高知県の自然の豊かさを、私たちも牧野博士のそれにならい、ブレずに積極的に発信していかなければなりません。発信する上で、この牧野植物園は重要な拠点となっているので、今後ますますその価値を高めていきたいと思います。 近年は植物の情報をネットで簡単に検索できますが、誤った情報も非常に多く見受けられます。私たちは、この牧野植物園を通じて、植物に関する正しい情報を発信していくことを使命としています。 GS:粛々と、牧野博士の偉業を紡いでいくと。 橋本:そうですね、そんなところです。すいません、答えになっているかな(笑)。 GS:いや、情報の信頼性を追求するのは、私たち園芸メディアにとってもそれは使命であるので、正しい情報を元に植物愛好者を増やしていくという形で、牧野博士を見習い、その想いを紡いでいけたら嬉しいです。今回は、いろいろお話を聞かせていただき、ありがとうございました。南園に牧野博士の立派な銅像がありましたが、博士にくれぐれもよろしくお伝えください。 橋本:伝えておきます(笑)。 南園にある牧野富太郎博士像 取材後記 35年ぶりの高知。35年も経つと、初めて来た土地のような感覚でしたが、以前のことで鮮明に覚えているのは、高知市民の親しみやすさ。すごくソウルフルで、今回の取材でお世話になった広報の橋本さんも、そんな方でした。 好青年で、時にクールに、またある時は熱っぽく語る、植物愛に溢れる橋本さんですが、牧野富太郎という人物をリスペクトしまくっているその姿を見ていて、この方は牧野富太郎と同時代に生を受けていたら、きっと牧野博士に可愛がられたのだろうな、と思いながら、お話を伺っていました。 ちなみに、この記事を作っている今(6月)、予見したとおり、連続テレビ小説効果で園内はだいぶ混み合い、忙しいらしいです。忙しいけれど、ホスピタリティー溢れる橋本さんのことだから、きっと手を抜かないのだろうな…。 話に聞く牧野博士も、それはホスピタリティー溢れる方だったそうです。今回は、そんな土佐っ子の心意気を肌で感じる取材となりました。



















