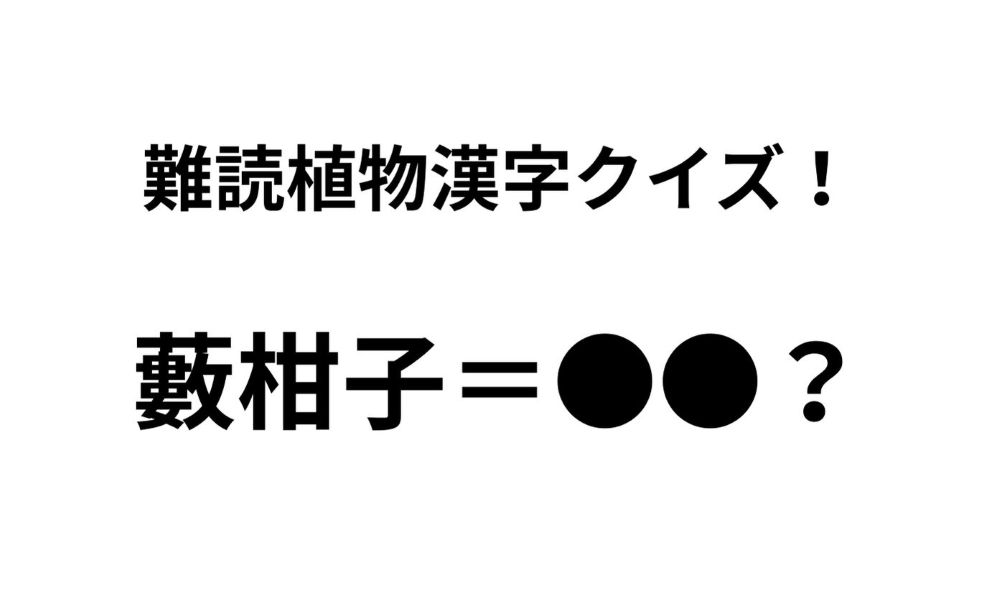- TOP
- ガーデン&ショップ
-
東京都

“ロングライフ・ローメンテナンス”で都立公園を豊かに彩るコンテスト「第4回東京パークガーデンアワード …
第4回会場となる「夢の島公園」 「東京パークガーデンアワード」は、公益財団法人東京都公園協会が主催するコンテストです。気候変動が激しい現代において、“持続可能でロングライフ・ローメンテナンス”なガーデンづくりを目指しています。デザインはもとより、植物や土壌の高度な知識が求められ、今までのものとは一線を画すコンテスト。このアワードを通じて、サステナブルガーデンの制作、普及を後押しします。 今回の舞台となる『夢の島公園』は、東京都江東区にある海辺の都立公園で、運河に囲まれた人工島の中に位置しています。「夢の島」といえば、かつてはゴミの埋め立て地として知られていましたが、その負のイメージを払拭するため、1978年に『夢の島公園』が開園しました。その後、整備が進められ、現在ではユーカリやデイゴ、ヤシなどの熱帯・亜熱帯植物が植えられた緑豊かな海辺の公園に生まれ変わりました。園内には熱帯植物館やスポーツ施設、マリーナ、広大な芝生広場があり、都心からアクセスしやすい人気スポットとなっています。 コンテストのテーマは「海辺のサステナブルガーデン」 今回ガーデンが設けられるエリアは、『夢の島熱帯植物館』西側のグリーンパークの一画で、公園のシンボルであるユーカリの樹林地に面しています。広がる波をイメージした2本のウェーブガーデン(約24㎡)に、海辺の環境に適した宿根草を植栽。背景のユーカリとも調和する、ロングライフ・ローメンテナンスなガーデンが制作されます。2025年12月、土壌改良から作庭が行われ、11月の最終審査を迎えるまで、必要に応じてメンテナンスを実施。近年の激しい気候変動、とくに厳しい酷暑への対応も重要な課題です。3回の審査を経てグランプリが決定するまで、さまざまな予測を立てながら庭と向き合っていくことになります。 「持続可能なロングライフ・ローメンテナンス」であることに加え、審査で見る重要なポイント 2025年に行われた「第3回東京パークガーデンアワード」の審査の様子。今回の審査員は、福岡孝則さん(東京農業大学地域環境科学部 教授)、正木覚さん(環境デザイナー・まちなか緑化士養成講座講師)、吉谷桂子さん(ガーデンデザイナー)、本木一彦さん(東京都建設局公園緑地部長)、植村敦子さん(公益財団法人東京都公園協会 常務理事)。 第4回も“持続可能なロングライフ・ローメンテナンス”であることが欠かせないルールです。丈夫で長生きする宿根草・球根植物(=多年草)を中心に、季節ごとの植え替えをせず、季節の花が順繰りに咲くようデザインすることが求められています。 ●公園の景観と調和していること ●公園利用者の関心が得られる工夫があること●公園利用者が心地よく感じられること●植物が会場の環境に適応していること ●造園技術が高いこと●四季の変化に対応した植物(宿根草など)選びができていること●「持続可能なガーデン」への配慮がなされていること●メンテナンスがしやすいこと●テーマに即しており、デザイナー独自の提案ができていること ●総合評価※各審査は別途定める規定に従い、審査委員による採点と協議により行われます。 第3回開催の砧公園で見られた“ロングライフ・ローメンテナンス”を実現しながら豊かに彩るための工夫 ここ数年、猛烈な酷暑が続いています。この異常な気候変動を乗り切るためには、耐暑性や耐乾性のある植物の選定、そして強くても爆発的に繁茂する種類は避けるなどの知識が必要です。またメンテナンスも欠かせない要素で、手入れのテクニックも審査の対象となります。メンテナンスはガーデナーの申請によって行うことが条件ですが、手入れの頻度(回数)も評価の参考になります。 そこで、「ロングライフ・ローメンテナンス」を実践するために、前回開催のコンテストガーデンで取り入れられた工夫をいくつか紹介します。 1. メンテナンス時の発生材(剪定枝など)をガーデン内で循環するためのバイオネストの設置 ガーデンの中央で大きなオブジェのような存在感を放っていた、印象的なバイオネスト(エリアA)。 2. ガーデンの土中に空気を送り込むための通気口の設置 直径20cmほどの穴に枝を組んで作った通気口。入り口部分にグラスの穂をあしらい、鳥の巣のような愛らしさを演出(エリアB)。 3. テントウムシを呼ぶための、バンカープランツを植栽 テントウムシがエサとして好むアブラムシが早春に集まるように植え込んだ原種のチューリップ(エリアC)。 4. 土中の微生物を活性化させるための、菌糸のステップを配置 キノコの菌床を円盤形に固めたステップ。植物の根の伸長を促すのに効果的(エリアD)。 5. シードヘッドになる植物を積極的に使う カールドン、アリウム、バーバスカム、バーベナのシードヘッドを巧み組み合わせ、秋~冬の景色に深みを与える(エリアE)。 全国から選ばれた5人のガーデンコンセプト どのエリアでガーデンを制作するかを決めるため2025年10月中旬に集合した5名のガーデナー。 コンテストのテーマとルールをふまえて制作するそれぞれのガーデンのコンセプトをご紹介します。 コンテストガーデンA花の巡り、風と大地の詩 【作品のテーマ・制作意図】 海辺という特有の環境に調和しながら、自然の力を活かした設計によって、サステナブルな公共空間のあり方を提案します。風が通り抜け、植物が揺れ、大地がそれを支える——この空間では、自然の要素が互いに響き合いながら機能します。植栽には、乾燥や高温に強く、施肥を行わずとも育つ植物を選定。水やりやメンテナンスを最小限に抑えることで、環境負荷を軽減しながら、美しさと生態系の豊かさを両立する構成としました。また、宿根草とグラス類を中心に、こぼれ種によって自発的に広がる植物を組み合わせることで、季節や年月の変化に応じて風景が移ろい、訪れるたびに異なる表情を見せるよう工夫しています。風に反応する草姿や色彩の変化は、来訪者の感覚に静かに働きかけ、風・植物・大地の関係性を通じて、自然との関わりを見つめ直す場となることを目指しています。 【植栽計画について】 海辺の環境に適応する植物を中心に構成し、自然の力を活かしながら持続的に育つガーデンを目指しました。潮風や強い日差し、乾燥といった海辺特有の条件に耐える宿根草やオーナメンタルグラスを主体とし、無施肥・最小限の水やりで維持できる植物を選定しています。これにより、環境負荷を抑えつつ、自然のリズムに寄り添う植栽管理を実現しています。 また、春から秋まで花が咲き継ぐ「開花リレー」を軸に、季節の移ろいが視覚的にも感じられるよう、色彩の重なりや草姿の変化を丁寧に計画しました。風に揺れるグラス類は海辺の風景に軽やかな動きを与え、球根植物は季節のアクセントとして景観に深みをもたらします。こぼれ種で広がる植物を組み合わせることで、植栽が自ら更新され、年月とともに自然に成熟していく仕組みも取り入れています。さらに、宿根草の間に一年草を適宜加えることで、季節ごとの彩りや変化を柔軟に補い、訪れるたびに異なる表情が楽しめる風景をつくります。こうした構成により、自然の動き・時間の流れ・生態系の豊かさが重なり合う、持続可能な植栽を目指しました。 【主な植物リスト】 宿根草:フロックス ムーディーブルー/ゲラニウム サバニブルー/アスフォデリネ ルテア/ダイアンサス カルスシアノルム/ゴリオリモン コリナム シースプレイ/エキナセア テネシーエンシス/ユーコミス ビッグボーイ/エリンジューム パリフォリウム/バーノニア レターマニー/スクテラリア インカナ/アスター アンレイズグラス類:フェスツカ エリアブルー/ブリザ メディア ラッセルズ/スティパ イチュー/エラグロスティス トリコデス/ペニセタム マクロウルム/アンドロポゴン テルナリウス/ミューレンベルギア カピラリス アルバ球根:スイセン ペーパーホワイト/ミニアイリス ペインテッドレディ/クロッカス ロマンス/ミニチューリップ ヒルデ/ダッチアイリス シンフォニー/カマシア クシッキー/アリウム シルバースプリング/アリウム ピンボールウィザード/ガルトニア カンディカンス/リコリス サンギネア コンテストガーデンB潮風に揺れるプレイフルガーデン-Playful Garden Swaying in the Coastal Breeze- 【作品のテーマ・制作意図】 ■ユーカリ樹林や公園風景を主役にする庭 ―夢の島公園の景観と調和した植物選び― ・公園の象徴であるユーカリ林を主役に、遠くからは樹林の前景として眺める花壇、入り込めばユーカリの壁を借景に、緑に包まれる植栽空間を創出。背後の樹林と庭の植栽がつながるよう視線の抜けや緑の連続感を意識し、園全体との一体感を演出します。 ・バンクシア、カリステモン、ハマゴウやメリアンサスなど、海辺の環境に耐えながら、豪州庭園を有する公園の既存植生や景観、海風の雰囲気に馴染む庭景を演出します。 ・冬季に訪れる来園者にも配慮し、花後も景観を彩るグラスや常緑樹、カラーリーフ類を混植し、季節ごとに表情が変わり、秋冬も映えるガーデンとします。 ■公園遊具・風景のきっかけとしての庭―利用者の関心を引き、居心地を生む仕掛け― ・子ども用遊具が少ない園内に、アスレチックや回遊ごっこを誘発する植栽空間を提案します。地面のウェーブ(アンジュレーション)と植栽の高低差で、歩くたびに景色が見え隠れする立体的な庭を演出し、眺めても歩いても楽しめる空間とします。 ・大人の見守りの視線は通しつつ、子どもにとっては草花のトンネルのように感じられる空間体験を演出します。園路沿いベンチを起点に、子どもの好奇心を植物へ導き、自然への関心を育む場とし、二列花壇の適所に通り抜けポイントを設けることで、アクセス性と回遊性を高めます。 【植栽計画について】 ■潮風に揺れる宿根草の庭 ―海岸環境に寄り添い、四季の移ろいを感じる庭―・バンクシア、カリステモン、ハマゴウ、シーラベンダーやコースタルローズマリーなど、耐風・耐塩・耐乾性に優れた海岸性の樹種をポイント的に配置し、庭全体に変化と海浜の雰囲気を映します。 ・海風に耐え支柱を必要としない樹種と、装飾性が高くもやや繊細な樹種を試験的に混植し、コースタルガーデンの新しい組み合わせを探ります。 ・もたれやすい草姿は、繁りやすい植栽やグラス類のそばに置き、互いに補完し合うよう計画。歩くことで植栽の色や草姿の変化を楽しめる配置とし、訪問者に発見や驚きを与えます。 ・強健種中心で単調になりやすい海辺の環境にも対応し、植栽の組み合わせや色・草姿のコントラストで多様な景観を実現し、季節や光の変化による表情も楽しめる庭を目指します。 ■微地形による環境の多様化と骨格植物の採用 ―気候変動下での持続性を生む工夫・ローメンテナンス―・アンジュレーション(微地形)を設けて排水性を確保し、乾燥に強いグラス類や低木を尾根部分に配置するなど、適所適植で植栽の安定性を高めます。 ・高低差や樹木ボリュームで異なる微気候(採光・通風・排水性の多様化)をつくり、異常気象による植物の全滅リスクを軽減。今後の気候変動(猛暑・豪雨・乾燥)を前提に、グラス類や強健種を一定割合植え込み、庭の骨格を安定化。 ・管理も容易なアガパンサス、エキナセア、グラス類や強剪定も可能な南半球由来の低木を視認性の高い要所(起伏の尾根やコーナー)に配置。マルチングやグランドカバーで乾燥防止と雑草抑制を図ります。 ・赤土を主として燻蒸したそば殻、有機物をすきこんで完熟発酵させた特製客土を用い、持込み雑草を最小化。団粒構造形成による排水性の向上とリン過多にならず、根付きもよい土づくり。あえて無肥料とすることで華美になりすぎない海辺らしい風景づくりと、オージープランツのリン酸やけに配慮。 【主な植物リスト】 宿根草:ユーフォルビア ウルフェニー/ユーフォルビア セギリアナ/トリトマ グリーンシェイド/モナルダ フィッツローザ/エキナセア ミニベル/エキナセア パリダ/シシリンチウム ストリアタム/スターチス ラティフォリウム/ホソバチョウジソウ/オレガノ マルゲリータ/アキレア マシュマログラス類:パンクスグラス プミラロゼア/ミューレンベルギア リンドハイメリ/ペニセタム アロペクロイデス/カレックス フェニックスグリーン/カレックス フラッカ低木:カリステモン ドーソンリバー/コースト バンクシア/グレビレア プーリンダ イルミナ/グレビレア ジョン エバンス/グレビレア ドーン パープル/メラレウカ タイムハニーマータル/ハマゴウ プルプレア/ギョリュウバイ ナニューム ルブルム球根: チューリップ トルケスタニカ/チューリップ シルビア/チューリップ ヒルデ/チューリップ タルダ インタラクション/チューリップ クレティカ パニア/チューリップ マーラ/チューリップ ビオレッタ/カマッシア カエルレア/カマッシア アルバ コンテストガーデンCStewardship Garden:The Way 【作品のテーマ・制作意図】 この庭は、まるで人の一生を映し出すかのような場所。最初は何も育たない砂地が、植物や小さな生き物たちのチカラ、そしてそこに暮らす人々の手によって、ゆっくりと豊かな土壌へと育っていく。それはまるで、子供が成長して大人になり、やがて成熟世代へと人生を重ねていく時間の流れと、重なり合っているかのよう。子供たちは砂のような柔らかな心で庭と遊び、自然からたくさんのことを学ぶ。大人になれば、その庭は家族や友人と収穫や語らいを楽しむ場所になり、成熟世代になれば、その成長した庭を眺めながら穏やかな、心豊かな時を過ごす。この庭は自然と人が共に成長し、砂が子供、豊かな土壌が大人へと成熟していくように、自然の再生と成熟への時、人生の旅路を映す『道』を示している。 【植栽計画について】 砂地を豊かな土壌へと育ててくれるのは植物、微生物、細菌、虫たち、そして少しの人の手。はじめに漉き込む堆肥は、その土地の土壌で作られたもの。なぜなら微生物や細菌は地域性があるからです。どこか遠くから良い資材を持ってきたとしても永続的な自然の循環は行われません。その土地だけの‘自然循環の在り方’を作り出すことが重要です。植える植物たちは潮風や乾燥に強い宿根草、そして環境に溶け込むような亜熱帯の宿根草を主軸とします。植栽は観る人々が‘思わず触りたくなるような’仕掛けを施します。それは、私が日々庭づくりで行っている‘参加型の庭づくり’に基づいています。驚きと興味は参加を促し、よき体験を生み出す。その‘関心’と’体験’こそ、サステナブルを巻き起こすものだと信じています。 【主な植物リスト】 宿根草:ユーパトリウム/トリトマ/ヘリオプシス/オミナエシ/オトコエシ/ペンテスモン/エキナセア/ベロニカなどグラス類:カールフォスター/ミスカンサス/ディプカンシア/カレックス/モリニア/コメガヤなど球根:アリウム/スイセン/ダッチアイリス/フリチラリア/カマシア/オダマキ/ラナンキュラス ラックス/ゲイソリザ/ツベロサム/シラーなど コンテストガーデンDSurFIVE Garden 【作品のテーマ・制作意図】 夏の猛暑や乾燥といった「過酷な環境を生き延びる力強さ(Survive)」×「海の波や生命のうねりを感じさせる (Surf)」を掛け、その植物のパワーが波のように広がり未来へとつながっていくイメージと、五感を刺激する植物の組み合わせを『SurFIVE』という言葉で表現しています。またガーデンのテーマカラーとしてオレンジの花色の植物を多く取り入れ、親しみやすさや太陽のもとで元気に咲く植物の生命力をアピールします。 【植栽計画について】 熱帯を思わせる個性的な形の植物をメインにして、一年を通してはっきりとしたシルエットを保つように計画しています。いくつかの同じ植物を違う場所にもリピートして植えることで、前後の花壇のつながりと、歩きながらガーデンのリズムを感じてもらえるように植物を配置しています。植え付け後は、剪定や水やりなどの手入れを最小限に抑え、人にも植物にとってもサステナブルで美しいガーデンを維持します。 【主な植物リスト】 宿根草: カンナ/クニフォフィア ルーペリ/メリアンサス マヨール/エキノプス /ロシアンセージ/アキレア/バーベナ ボナリエンシスグラス類:カラマグロスティス カールフォスター/カラマグロスティス ブラキトリカ/パニカム シェナンドア/エラグロスティス スペクタビリス球根: アリウム マジック/ミニチューリップ ショーグン/イフェイオン ウィズレーブルー/スイセン タリア コンテストガーデンE「東京サバンナ・バイ・ザ・ベイ」 〜地の記憶と環境を翻訳する庭 【作品のテーマ・制作意図】 かつて廃棄物で埋め立てられたこの島には、現在ユーカリの森を中心とした強健な植生が根づき、都市にありながら原始的で異国的な景観を生み出しています。今回、植栽地となるこの森の縁に広がる強い日射と潮風にさらされた芝生を目にしたとき、「ここは都市の果てに現れたアーバン・サバンナだ!」と直感しました。 植物を単なる装飾に限らず、この地固有の「環境を翻訳する存在」と捉え、来園者が海風・光・湿度・熱といった目に見えない環境を感覚・知覚できる場をつくります。「東京サバンナ」は景観的なサバンナの模倣ではなく、夢の島の歴史と環境条件から必然的に現れた都市の新しい風景です。都市と自然の狭間に生まれたこの庭を通じて、来園者が環境や植物との関わりを見つめ直し、都市園芸の新たな可能性を感じ取るきっかけとなることを願います。そしてこのガーデンが、見た目の美しさと維持のしやすさを兼ね備えた、持続可能な宿根草ガーデンの新しいスタンダードとして育まれれば幸いです。 【植栽計画について】 土地の過酷な条件を読み解き、徹底したローメンテナンス性、持続可能性を踏まえながら、美しく景観が維持できる計画としました。植栽計画は、強光、潮風、乾燥に耐える大型グラスをメインとした外皮構造を先に築き、その内側に小型宿根草を群植する二層構造としました。外層が強い環境要因を受け止めて微気候を生み、内層ではナース植物の効果により小型植物が守られながら安定して育ちます。 植物は侵略性が低く、かつ姿が乱れにくく支柱や過度な手入れを必要としない丈夫な種を厳選しました。内層の植栽は配置の自由度が高く、どこに植えても風景が破綻せず、誰もが維持・再現可能です。また低層種を入れ替えるだけで新たな景観を生み出せる柔軟性も持ち、さらに密植により除草の労力を軽減します。 そして、四季を通じて花や実を供給し、チョウや他の昆虫類に生息の場を与えることで都市に自然のリズムを呼び戻し、この地域の生物多様性に寄与します。「東京サバンナ・バイ・ザ・ベイ」は、美観・管理性・生態系の循環を兼ね備えた、海辺にふさわしい真のサステナブルガーデンの姿を示します。 【主な植物リスト】 宿根草:ビゲロウィア・ヌッタリー/エゾノヨロイグサ/ハマボウフウ/ヒューケラ・シャムロックなどグラス類:カラマグロスティス・カールフォスター/パニカム・ヘビーメタル/セスレリア・オータムナリス/フェスツカ・アメジスティナなど コンテストガーデンを見に行こう! Information 都立夢の島公園「グリーンパーク」内所在地: 東京都江東区夢の島2-1電話: 03-3522-0281https://www.tokyo-park.or.jp/park/yumenoshima/index.html#traffic開園時間:常時開園※サービスセンター及び各施設は、年末年始は休業。営業時間等はサービスセンターへお問い合わせ下さい。入園料:無料(一部有料施設あり)アクセス:東京メトロ有楽町線(Y24)・JR京葉線・りんかい線「新木場」下車、徒歩7分。東京メトロ東西線「東陽町」(T14)から都バス(東陽町-新木場、東陽町-若洲海浜公園)「夢の島」下車。高速湾岸線「新木場インター」より5分駐車場:有料
-
東京都

「第3回 東京パークガーデンアワード 砧公園」1年の取り組み
毎日見学者が訪れる第3回コンテスト会場は「都立砧公園」みんなの広場前 コンテスト会場となった砧公園みんなの広場前に設けられたコンテストエリアの1年間の景色の移り変わり(右上/4月 左下/7月 右下/11月)。公園の正門や駐車場からコンテストガーデンに向かうと見えてくる「東京パークガーデンアワード」の開催を示す2カ所の看板が目印。 2022年に代々木公園から始まった「東京パークガーデンアワード」。第2回の神代植物公園に続き、3回目となる今回は、成城学園、二子玉川など閑静な住宅街からほど近い場所にある都立砧公園(東京都世田谷区)が舞台です。芝生の広場と樹林で構成されたファミリーパークのほか、運動施設や遊具などが設置された広場が整備され、区民みんなに親しまれている公園でコンテストが繰り広げられました。 東京都立砧公園は、芝生が青々とした「みんなのひろば」をはじめ、バラ園、サイクリングコース、‘子供の森’など多数のエリアがあり、秋にはイチョウなどの紅葉・黄葉が楽しめます。 第3回のテーマは「みんなのガーデン」 今回のコンテストエリアは、‘みんなのひろば’前に広がるスペース。5つのガーデンは公園を訪れる多くの人の目を楽しませました。 天気のよい休日には、家族連れがお弁当を広げる光景もあちこちで見られ、地域の住民をはじめ、多くの人々に親しまれている砧公園。‘みんなのひろば’前で開催された「第3回 東京パークガーデンアワード」のコンテストテーマは『みんなのガーデン』です。「東京パークガーデンアワード」の目指す“持続可能なロングライフ・ローメンテナンス”であることはもちろん、訪れる人々の五感を刺激し、誰もが見ていて楽しいと感じる要素を取り入れたガーデンであることが求められました。植栽のメインとなる宿根草は、丈夫で長生きすることから、季節ごとの植え替えは行わず、四季ごとに花の彩りがあることも期待されました。 第3回のコンテストガーデン コンテストガーデンが設けられた敷地の平面図。A〜Eの各面積は約40㎡ 。どのエリアでガーデンを制作するかは、2024年10月に抽選により決定しました。 各コンテストガーデンは、高さ40cmの枠に囲まれた区画内に作られました。子どもたちの目線にも近い高さで、かがまずに植物を間近で観賞できるのも今回の特徴です。4月の様子。 今回のガーデンでは、通路を挟んで対に設けられた2つ1組の花壇が5つ連なっています。隣接する‘みんなのひろば’や‘ねむのき広場’からコンテストエリア全体を眺めたり、花壇に挟まれた通路を歩きながら、左右に育つ植物を観賞したりするなど、さまざまな角度からガーデンを堪能することができました。 写真手前の北から奥の南に向けて、A・B・C・D・Eの順に花壇が並ぶ。7月の様子。 2024年12月に行われた第1回作庭。5つのガーデン制作に関わった皆さん。 【第3回 東京パークガーデンアワード in 砧公園 最終審査までのスケジュール】 コンテストに挑戦する5名の入賞者が1年を通してガーデン制作に挑む「東京パークガーデンアワード」。2024年12月中旬に、それぞれの区画で1回目の作庭が完了し、2025年2月下旬に2回目の作庭日が設けられました。その後、4月は春の見頃を迎えた観賞性を審査する『ショーアップ審査』、7月は梅雨を経て猛暑に向けた植栽と耐久性を審査する『サステナブル審査』、11月は秋の見ごろの鑑賞性と年間の管理状況を審査する『ファイナル審査』が行われ、グランプリが決定しました。 2025年11月に行われた授賞式後、審査員と授賞者を囲んで、コンテストガーデンエリアに集まった東京パークガーデンアワードに関わった皆さんと記念撮影。 「第3回 東京パークガーデンアワード 砧公園」すべての審査が終了しました! 審査員は以下の5名。福岡孝則(東京農業大学地域環境科学部 教授)、正木覚(環境デザイナー・まちなか緑化士養成講座講師)、吉谷桂子(ガーデンデザイナー)、本木一彦(東京都建設局公園緑地部長)、植村敦子(公益財団法人東京都公園協会 常務理事) 4月、7月、11月の3回の審査は、5名の審査委員による採点と協議により行われました。【審査基準】公園の景観と調和していること/公園利用者の関心を得られる工夫があること/公園利用者が心地よく感じられること/植物が会場の環境に適応していること/造園技術が高いこと/四季の変化に対応した植物(宿根草など)選びができていること/「持続可能なガーデン」への配慮がなされていること(ロングライフ) /メンテナンスがしやすいこと(ローメンテナンス)/テーマに即しており、デザイナー独自の提案ができていること/総合評価 ※各審査は別途定める規定に従い、審査委員による採点と協議により行われました。 「第3回 東京パークガーデンアワード 砧公園」授賞式 2024年12月のガーデンの施工から約1年が経過し、3回目の審査となる『ファイナル審査』が2025年11月6日に行われ、入賞5作品の中より「グランプリ」、「準グランプリ」、「審査員特別賞」が決定。晴天の2025年11月22日、東京都世田谷区にある上用賀アートセンターにて授賞式が行われました。式典では、賞状とクリスタルメダルの贈呈、4名の審査員による講評、授賞者5名による喜びのコメントが発表され、参列者より大きな拍手が贈られました。 「第3回 東京パークガーデンアワード 砧公園」の受賞者と審査員。 審査員の講評 審査員 吉谷桂子さん(ガーデンデザイナー) 東京パークガーデンアワード・砧公園のコンテストに入賞されたみなさん、本当におめでとうございます。そして、過去に神代植物園や代々木公園でのコンテストに参加してくださった方々にも、心から感謝申し上げます。 このコンテストでは、造園や園芸といった枠を越え、これからの地球に必要なことを、小さな一歩から取り組み始めていると感じています。21世紀の今、新しい局面に立ち、幅広い視野で重要なテーマを探し続けているのではないでしょうか。 33年前、私はイギリスの庭に出会いました。イギリスでは100年以上前から自然主義の思想があり、庭や造園の世界で多くの草花が使われてきました。産業革命による自然破壊が進んだ1800年代末、自然保護運動が始まった国でもあります。 日本とイギリスの園芸・造園には違いがあります。 イギリスでは園芸と造園が密接で、ランドスケープデザイナーは宿根草の生態や育ち方を深く理解しています。私はそれをいつも素晴らしいと感じてきましたが、日本はまだ追いつけていない状況でした。しかし、このコンテストでは、それを覆すような躍進的な取り組みが見られたと感じています。 今回の5組のみなさんは、それぞれに素晴らしく、グランプリを決めるのは非常に難しいものでした。実際、全員がグランプリだと思っています。その中で、私が重視したのは「レジリエンスガーデン」、つまり「9月のダメージをどのように11月に乗り越えたか」という視点です。宿根草だけが生き残る庭が最良とは思いませんし、一年草を装飾的に取り入れるのもよいと思います。 私が尊敬するガーデンデザイナー、トム・スチュアート・スミスも、自宅の庭で宿根草に一年草のコスモスを取り入れています。そもそも、なぜ庭をつくるのか。それは、美しく育つ草花やその風景に、私たちが喜びを感じるからです。花が咲いている庭、咲いていない庭、どちらにも価値があります。 ちなみに、多くの人は花を見て喜びますが、私は最近、葉だけの世界が好きです。心が「気持ちよい」「癒やされる」と感じることが重要なのです。 今回のテーマ「みんなのガーデン」では、公園に訪れる小さなお子さんから幅広い世代の方々が楽しめることが最も重要でした。しかし、コンテストを重ねる中で、目に見えない部分まで審査する段階に来たと感じています。 私は土中環境を感覚的には理解していますが、数値的な詳細は分かりません。それでも、今回グランプリを獲得したガーデンは、光や風の通り方が素晴らしく、眺めているだけで生物としての喜びが広がるのを感じました。花の有無ではなく、光と風が宿根草の庭をいかに心地よく通るかが最大の焦点でした。 心と体の健康は大切です。ガーデンから「気持ちよい」と感じることは心や体の栄養になり、さらに「ここから離れたくない」と思えることが重要です。 今回のコンテストでは、5組すべてがその点で素晴らしかったと思います。順位をつけることになり、最後に「ごめんなさい!」とお伝えしたいです。 みなさん、ご参加いただき、本当にありがとうございました! 5名の授賞ガーデンと審査員講評 グランプリ コンテストガーデンCLadybugs Table 「てんとう虫たちの食卓」 ●コンテストガーデンCの月々の変化は、こちらからご覧いただけます。 審査員講評 「てんとう虫たちの食卓」というテーマがよく表現された庭でした。アブラムシを増やす植物をあえて入れてテントウムシを誘い、剪定した枝葉を作業通路に置いてナメクジなどを引き寄せ植物たちを守るなど、生態系を豊かにすることで庭も美しくするプランが成功しているようでした。プランツタグのQRコードで植物や虫たちを紹介する発信も素晴らしい取り組みです。広めに確保された作業通路が風の道となり植物が蒸れにくく、景観的にも奥行きや抜け感を生み、植物の表情をより豊かに演出していました。グラスの穂が風に揺れる姿は野原で遊んでいるような気持ちにさせ、多彩な植物たちが混み合うことなく絶妙に風を通しながら公園の風景に溶け込む様は、見るほどに引き込まれる美しい眺めでした。予測の難しい酷暑を越えた先に秋の自然な美しさが際立つことこそが、宿根草ガーデンの真骨頂だと気づかせてくれるガーデンでした。 小野雄大さん コンテストを終えた受賞者のコメント 今回、大切にして目指したのは、季節とともにガーデンの表情が変わって、植物と小さな生き物たちの営みが共存する庭です。原生地の群落を意識し、春から初夏に向けて景色が大きく変わるように植栽を工夫しました。テントウムシなどの益虫が増えるように、越冬場所を作ったりアブラムシがつくようバンカープランツを植えたりと工夫しました。また、近年の気候変動に強いレジリエントガーデン(回復力を備えた庭)というものにチャレンジし、水の流れを作ったり、土中の保水性を高めるなどして夏場の暑さに耐えられるようにしました。 印象に残ったことは、子どもたちがまわりで網を振って虫捕りをしていたこと。それがすごく微笑ましくて、虫かごに蝶々をいっぱい入れて見せあったりして楽しんでいました。たまにその網で花首が取れたり、植栽の奥まで足を踏み入れたり、ということもありましたが、それは本当に子どもたちにとっても心に残ったのではないかなと思います。この庭ができて、自然と遊ぶことができるようになったのではないかなと思っています。 準グランプリ コンテストガーデンAGathering of Bouquet 〜庭の花束〜 ●コンテストガーデンAの月々の変化は、こちらからご覧いただけます。 審査員講評 タイトル通り、花束のような素敵なガーデンでした。公園に溶け込んだ遠景は絵画的で美しく、近づいてみると、植物どうしが響き合って作る美しいシーンが随所に見られました。バイオネストはサステナブルな機能だけでなく、庭を特徴づける造形物としても効果的に働いていました。花壇の場所的に一部が松の木陰になってしまうハンディがありましたが、植物選択やメンテナンスの工夫でうまく対処されていました。厳しい夏を越えられなかった植物も見受けられましたが、春の華やかな景色は今なお強く印象に残っており、都会的で洗練された美しさが秋に至るまで展開されていました。多くの人々に楽しさや幸福感、季節の移ろいの喜びを与えてくれるガーデンでした。 保坂悠平さん コンテストを終えた受賞者のコメント 私自身、宿根草ガーデンを作る機会はこれまで非常に少なく、普段はマンションや商業施設の植栽計画を計画段階から携わっています。そうした現場では、周辺環境への配慮や在来種の使用を求められることが多いのですが、今回特に印象的だったのは、子どもたちや近隣の皆様から多くのお声掛けをいただいたことです。これまで携わった植栽計画では、なかなか直接お声掛けをいただく機会はなかったので、今回、「花の力」を強く感じました。 私は第1回の代々木公園から応募に挑戦してきましたが、当時は宿根草のことが本当に分かりませんでした。ですが、今回に至るまで、日本各地のいろいろな素敵なガーデンを訪れたり、先輩から教わったりして宿根草について学んできました。今回、私自身で剪定ばさみを持って、休日公園に通い、仲間に教わりながら剪定を行いました。こうした経験を通じ、今後は緑を通して人と人をつなぐ仕事をしていきたいと思っています。 審査員特別賞 コンテストガーデンE「みんなのガーデン」から「みんなの地球(ほし)」へ ●コンテストガーデンEの月々の変化は、こちらからご覧いただけます。 審査員講評 個性が際立つ植物を巧みに組み合わせ、まるでジャングルの中に入り込んだような感覚を味わえるガーデンでした。多種多様な植物を数多く使い、植物の可能性をとことん追及したカラフルでダイナミックな植栽デザインが特徴的で、その圧倒的な色彩の豊かさが多くの来園者の目を惹きつけていました。花壇の多角形を生かし、見る角度によって、構築的で造形的におもしろい植物、質感のバラエティ豊かな組み合わせ、多彩に変化する色合いなどを楽しめる点が印象的でした。遠くから見ても植物たちの存在感が力強く、厳しかった今夏を乗り越えた姿には感動を覚えます。写真を撮りたくなるシーンが随所に散りばめられ、見る人を自然と滞留させる魅力に富んだガーデンでした。 太田敦雄さん コンテストを終えた受賞者のコメント このガーデンは、写真や映像に映らないかもしれない「愛や他者への思いやり」という抽象的な概念を、SNSでつながった花好きなボランティアのみなさんと共に表現するという、私にとっても大きな挑戦でした。絶え間なく変化する開花のリレーを引き継ぎながら、人と植物と虫たち、人と人、そして人と環境が繋がる、美しくて尊い共存の風景を、この庭とその創作活動を通じて表現することができました。サステナビリティやメンテナンスという概念に挑戦する中で感じたのは、植物が苦しいとき、人間が愛や思いやりの手を差し伸べることで、植物は幸せに生きながらえることができるということです。園芸をする方なら分かることと思いますが、愛情を受けている植物は表情が違うのです。私たちのチームは、毎週その日に来られる人が、自分が楽しいと思える範囲で植物の手入れをしました。負担にならなければ、メンテという労働作業ではなく、仲間と会える趣味の活動になるんですよね。何かを「好き」と思う気持ちで行うことは、現代において、最もエコで尽きることのないクリーンエネルギーであり、かつ合理的なシステムだと考えています。それを、1年間かけてチームのみんなと一緒にこの庭で実践し、示すことができました。 私は、庭づくりは時間軸を伴う文脈を持った「劇」のような時間芸術であり、心から生まれ、人の心に届くものでなければならないと思っています。コンテストには順位がありますが、庭は勝負ではありません。移り行く時間や季節の中で、どれだけの感動や意義や問いを人や社会に投げかけることができるか。それが大切だと思っています。春に私のガーデンを見るために車椅子で来られたお客様が、車椅子から立ち上がって歩いて見てくださったという奇跡の瞬間。無数の蝶や虫たちが花と戯れる中で花壇の手入れする人の姿も楽園のように美しく渾然一体となった夏の日の光景。最終審査前のメンテの後、ボランティアの方がかけてくださった「青春のような1年でした」というひと言。庭とはここまで人や世界を幸せにする力があるのだ、と。この庭を通して、多くの方が愛や思いやりを受けとってくださったこと、それこそが私にとって一番の尊い賞でした。 入賞 コンテストガーデンBCircle of living things 〜おいでよ、みんなのにわへ〜 ●コンテストガーデンBの月々の変化は、こちらからご覧いただけます。 審査員講評 イチゴやイチジクなど、自分の庭に取り入れたくなるカジュアルな提案がたくさん詰まった庭でした。見ているうちに「美味しそう!」と感じ、ガーデンの先にある家族の物語まで想像させてくれます。剪定枝で作った可愛いサークルネストなど、子どもと一緒に楽しめそうな工夫も魅力的です。植栽デザインは年間を通して全体の色合いが美しく、コーナーごとに設けられたテーマカラーをぐるりと一周しながら眺める楽しみがありました。特に秋には、黄・オレンジなど暖色系の構成から、目を転じるとアスターなどの寒色系へと色調が変化する眺めが絵画のようでした。季節ごとに多彩なシーンを提供してくれ、幅広い世代の来園者が訪れる砧公園という場所にふさわしい、元気をもらえるガーデンでした。 石野夕華さん、有瀧佳実さん コンテストを終えた受賞者のコメント 私たちは、公園から自転車で 10分くらいのところに住んでいるママ友です。第3回の開催地が砧公園だと知ったとき、ぜひ地元のメンバーで応募したいと相方の有瀧を誘い、お世話になっているbajicoの母体であるNPO法人子育て支援グループamigoさんにも挑戦をしたいと伝え、これまでたくさんのフォローをしていただきました。仕入れやガーデン製作、そしてメンテナンスまで、日々仕事でお世話になっている職人さんやガーデナーの皆さんに、たくさん助けていただきました。また、砧公園入賞者皆さんの植物への思いも、たくさん知ることができ、とても勉強になりました。地元の方々にもたくさん見ていただき、ガーデンを愛してもらい、そして私たち自身も、楽しんでコンテストに参加できたこと、それだけで優勝だなと思いました。私がいま身につけているピンクのピアスやバッグは、じつは冬にカラス除けでカーデン内に張っていたピンクの水糸なんです。これを有瀧が編んで仕上げてくれました!(石野) ママ友の2人なので、夜遅くまで植え込みをした後、自転車にまたがり「今日の夕飯、何にしようか」「この後夕飯作って子どもをお風呂に入れて寝かせなきゃね」と、毎日同じような会話を繰り返しながら、メンテナンスを楽しみました。作業が終わればまた“お母さん”に戻るという繰り返しでしたが、私たちらしいコミュニケーションの取り方で、楽しんで取り組むことができ、本当に感謝しています。(有瀧) 入賞 コンテストガーデンDKINUTA “One Health” Garden ●コンテストガーデンDの月々の変化は、こちらからご覧いただけます。 審査員講評 微生物など土の中のことまでよく考えられたガーデンで、土壌改良のため取り入れた菌糸平板からツヤツヤのキノコが生えてきた様は、まるでアート作品のようにも感じられました。「土壌環境が豊かになることで植物本来の力が発揮され、豊かな景観や生態系に繋がる」という自身のコンセプトに真正面から取り組み、生物多様性の面では、実際に虫たちを多く呼び寄せることに成功していました。景観的に植物の高さのバランスに欠ける面もありましたが、できるだけ自然に任せたおおらかな景色とも言えます。メンテナンスの回数も少なく、持続可能な公園の庭づくりという点でも、今後のパフォーマンスに注目していきたいガーデンです。 高橋祐眞さん、齋藤集平さん コンテストを終えた受賞者のコメント 私たちは「ローメンテナンス・ロングライフなガーデン」をどう実現できるか、真剣に取り組んできました。メンテナンスの回数は圧倒的に少なかったと思います。そこもすごくこだわったところです。土の中に微生物をいっぱい入れた結果、勢いよく育って正直驚きましたが、私たちが目指したのは、この 1年で勝つ、 1年目がすごくよい、ということではなく、2年、3年、そして10年先まで続いていくガーデンです。じつは私たち、1回しか自分たちで散水していないんです。砧公園では、夏に雨はほとんど降らなかったと思うのですが、ほとんどの植物が枯れなかったというのは、私たちの取り組みの成果かなと思っています。(齋藤) 「みんなのガーデン」というのが何かということを考えたときに、人や植物、微性物、虫、すべて含めて、みんなを癒やすということで、One Healthという考えにたどり着きました。僕はランドスケープデザインに携わっており、いつも広い視点で見ているため、思った以上に植物が大きく育ってしまうこともありました。ほかのガーデンを見ると、そこが自分には足りていないなと思いました。ただ、僕たちの中では、微生物であったり、生態系であったり、植栽であったり、コミュニティであったりと、生態系を主軸にしながら「みんなのガーデン」を考えられたことは、とても有意義なことでした。今後、ランドスケープデザインの世界でもっと議論され、もっとみんなが考えていくべきテーマだと思います。植物に携わる人間が、先ほど太田さんが植物に対する愛ということをおっしゃっていましたように、そうしたことを、もっと真剣に考えていくべきなのではないかなと思いました。(高橋) Pick up 月々の植物の様子 11月の植物の様子 シュウメイギク‘パミナ’(Aエリア)、アスター‘パープルドーム’(Aエリア)、シュウメイギク‘雪ウサギ’(Bエリア)、アロニア(Cエリア) アスター‘シロクジャク’(Cエリア)、アメジストセージ(Dエリア)、アマランサス‘ホピレッドダイ’(Eエリア)、ダリア‘ブラックナイト’(Eエリア) 10月の植物の様子 サルビア‘ミスティックスパイヤーズブルー’(Aエリア)、アガスターシェ‘モレロ’(Aエリア)、ヒガンバナ(Bエリア)、ルエリア(Bエリア) アスター・アンベラータ(Cエリア)、シュウメイギク‘ハドスペン アバンダンス’(Cエリア)、ハギ(Dエリア)、アスター ‘ジンダイ’(Eエリア) 9月の植物の様子 アガスターシェ‘ブルーフォーチュン’(Aエリア)、ユーパトリウム・コエレスティナム(Bエリア)、オジギソウ(Bエリア)、リアトリス・スカリオサ‘アルバ’(Cエリア) アロニア‘メラノカルバ’(Dエリア)、ヒルベリー(Dエリア)、ヒビスクス・コッキネウス(モミジアオイ)(Eエリア)、 オキシペタルム・カエルレウム(Eエリア) 8月の植物の様子 ヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’(Aエリア)、カラミンサ‘ブルークラウド’(Aエリア)、コレオプシス‘ガーネット’(Bエリア)、ヘレニウム‘シエスタ’(Cエリア) エキナセア‘メローイエロー’(Cエリア)、モナルダ(Dエリア)、カンナ‘ベンガルタイガー’(Eエリア)、ルドベキア‘リトルヘンリー’(Eエリア) 7月の植物の様子 ユーパトリウム‘ベビージョー’(Aエリア)、ゲラニウム‘アズールラッシュ’(Aエリア)、ヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’(Bエリア)、エキナセア‘ブラックベリートリュフ’(Bエリア) ヘメロカリス‘クリムゾンパイレーツ’(Cエリア)、オミナエシ(Dエリア)、ネリウム(=キョウチクトウ)’ペティットサーモン’(Eエリア)、エリンジウム・ユッキフォリウム(Eエリア) 6月の植物の様子 ルドベキア ‘フラメンコ・ブライトオレンジ’(Aエリア)、ムスクマロー‘ホワイトパーフェクション’(Bエリア)、リシマキア‘ミッドナイトサン’(Bエリア)、ブリザ・メディア(Cエリア) ユリ‘リーガルリリー’(Cエリア)、ウスベニアオイ(Dエリア)、アザミ(Dエリア)、ベロニカ・ロンギフォリア‘マリエッタ’(Eエリア) 5月の植物の様子 シラー‘ブルーアロー’(Aエリア)、オーニソガラム・アラビカム(Aエリア)、チャイブ(Bエリア)、ギリア・レプタンサ(Bエリア) カマッシア・クシッキー(Cエリア)、ビバーナム・ハリアナム(Dエリア)、パパベル・コムタツム‘レディーバード’(Eエリア)、エスコルチア ピンク(Eエリア) 4月の植物の様子 スイセン‘タリア’(Aエリア)、フロックス・ディバリカタ‘メイブリーズ’( Aエリア)、アジュガ‘ディキシーチップ’(Bエリア)、チューリップ‘エデュアルトペルガー’(Bエリア) 原種チューリップ・ヒルデ(Cエリア)、フリチラリア・インぺリアス‘オレンジビューティー’(Cエリア)、ベニバナマンサク(Dエリア)、ユーフォルビア・ウルフェニー(Eエリア) 3月の植物の様子 スイセン‘テータテート’(Aエリア)、ブラックローズリーフレタス(Bエリア)、原種系チューリップ‘アルバ コエルレア オクラータ’(Cエリア)、プルモナリア‘ダイアナ クレア’(Cエリア) ユーフォルビア・リギダ(ガーデンD)、アザレアツバキ(ガーデンD)、ナルキッスス ‘ペーパーホワイト’(ガーデンE)、クロッカス ‘アードジェンク’(ガーデンE) 2月の植物の様子 シラー・シベリカ‘アルバ’(Aエリア)、シラー・ミシュチェンコアナ(Aエリア)、日本スイセン(Bエリア)、イタリアンパセリ(Cエリア) ローズマリー(Dエリア)、カレックス・オメンシス‘エヴァリロ’(Dエリア)、ナルキッスス カンタブリクス モノフィルス(Eエリア)、コルヌス ‘ケッセルリンギィ’(Eエリア) 1月の植物の様子 左から/ロータス ‘ブリムストーン・ライムゴールド’(Aエリア)、ワイルドストロベリー ‘ゴールデンアレキサンドリア’(Bエリア)、コトネアスター(Bエリア)、エリンジウム パンダニフォリウム ‘フィジックパープル’(Cエリア) 左から/庭人さんのビオラ(Cエリア)、モンタナハイマツ(Dエリア)、アロエ ストリアツラ(Eエリア)、ユッカ ‘ゴールデンスウォード’ (Eエリア) 全国から選ばれた入賞者5名のガーデンコンセプトと月々の様子 コンテストのテーマとルールをふまえて制作される5つのガーデン。それぞれのガーデナーが目指す庭を、作者の制作意図や図面、植物リストの一部を紹介しながら、月々の様子を撮影した写真とともにお伝えします。 コンテストガーデンAGathering of Bouquet 〜庭の花束〜 【作品のテーマ・制作意図】 皆さんの日常に癒やしや潤いを届けたいという願いを込め、プランツ・ギャザリングの視点で、ガーデンをひとつの大きなブーケに見立ててデザインを構成しました。動物たちが次の訪問者のために心遣いを残していく絵本から着想を得て、あらゆる世代の方が見て触れて、香りなどを楽しめるように、花の形や手触りがおもしろいものを用いた植栽計画をしています。ぜひ手に取って、お気に入りの植物を見つけてください。たくさんの感動や気づきが新たな会話を生み、笑顔になるシーンが増えますように。 【主な植物リスト】 宿根草:エキナセア‘マグナススーペリア’/ペンステモン‘ストリクタス’/アガパンサス‘ピッチュンホワイト’/クラスペディア‘ゴールドスティック’/オルレア・グランディフローラ‘ホワイトレース’ などグラス類:ペニセタム・ビロサム‘銀狐’/メリニス‘サバンナ’/ホルデューム・ジュバタム/カラマグロスティス・ブラキトリカ など低木:コルヌス・ステラピンク/ビルベリー‘ローザスブラッシュ’/ニシキギ・コンパクター/コバノズイナ など球根:チューリップ‘フレーミングピューリシマ’/レウコジャム‘スノーフレーク’/アリウム‘グレイスフルビューティ’ など コンテストガーデンA 月々の変化 11月の様子 たくさんのグラス類と季節の草花が織りなすトーンに渋みが加わり、中央に配されたバイオネストと相まって、全体にワイルドな雰囲気が漂います。シュウメイギクやアガスターシェ、オミナエシといった秋の花々が、控えめながらも確かな彩りを添えています。カラミンサやロータスのふんわりと広がる草姿が、爽やかで軽やかな印象を演出しています。 上左/夏からずっと咲き続けているアガスターシェ‘ブルーフォーチュン’と9月中旬から開花し始めたシュウメイギク‘パミナ’。午後には日陰になる場所でこっくりとした花色を見せている。上右/黄葉のホスタ‘サムアンドサブスタンス’と光沢のあるケイトウの輝きが、シーンの明るいアクセントに。下左/オミナエシやエリンジウム‘ホワイトグリッター’のシードヘッドが野趣あふれるシーンを引き立てている。下右/繊細なグラス類やカラミンサ、ロータスが、爽やかな空気を感じさせている。 10月の様子 一時は花数が減ったガーデンも、秋の訪れとともに再びたくさんの花が咲き始めました。なかでも目を引くのは、ピンクや赤、オレンジなど鮮やかな色合いのケイトウの穂。そのつややかな光沢は、シュウメイギク、ホトトギス、アガスターシェなどの花々を一層あでやかに引き立て、ペニセタムやミューレンベルギアなどのグラスの穂とともに、秋のガーデンをにぎやかに彩っています。 上左/アガスターシェ‘モレロ’やサルビア‘ミスティックスパイヤーズブルー’などの草花の合間で、ピンクやアイボリーのケイトウが目を引くアクセントに。上右/オミナエシの群生が、コルヌス‘ステラピンク’の株元でひっそりと野趣を感じさせている。下左/直立する赤褐色のワレモコウとカーブを描くイトシマススキ、ふんわりやわらかい印象のカラミンサなど、バラエティに富んだフォルムで自然な風景を織り成して。下右/ミューレンベルギア・カピラリスやペニセタム・ビロサム‘銀狐’などのグラス類や、アガスターシェ‘ブルーフォーチュン’、ケイトウなど、彩り豊かな秋風を感じるワンシーン。 9月の様子 花壇のそばに植わるマツの木が、やわらかな木陰を落とすこのガーデンには、ほかのエリアよりもひと足早く、秋の気配が訪れています。花数はかなり減ったものの、アジサイ‘アナベル’の花がらやグラス類、さまざまなシードヘッドが、ダイナミックな造作のバイオネストに寄り添いながら、季節の移ろいを感じさせています。 上左/アジサイ‘アナベル’の丸い花がらや細いイトススキ、幅が広く長い葉のシランなど、さまざまなフォルムの植物が組み合わさって、花が無くても表情は豊か。一角では、アネモネ‘パミナ’のピンクのつぼみが膨らんできている。上右/夏に伸びきった枝葉がすっきりと剪定され、バイオネストがよく見えるようになった。一定方向に組まれた枝が、植栽に規則的な流れを生み出している。 下左/グラス類が風になびくさまが、秋を感じさせる。下右/ルドベキア‘リトルヘンリー’の控えめな花が、落ち着きを見せ始めたいまの季節にピッタリ。 8月の様子 7月に主役的存在だった淡い黄花のルドベキア‘フラメンコ・バニラ’は影を潜め始めました。 代わりに鮮やかな黄花のルドベキア‘ゴールドスターム’が咲き始め、先月から咲き続けているオレンジ花の‘フラメンコ・ブライトオレンジ’やアガスターシェ‘モレロ’とともに、鮮やかさと深みのある色彩を織り成しています。また、中央のバイオネストの傍らでは、小型の西洋フジバカマや、ユーパトリウム‘ベビージョー’が、グラス類とともにワイルドな趣を演出。ホトトギスやシュウメイギクなどの秋の植物も成長し始めています。 上左/盛夏もバイオネストがオーナメンタルな存在感を発揮。上右/ユーパトリウム‘ベビージョー’の群植が印象的。中左/赤(アガスターシェ‘モレロ’)×青(サルビア‘ミスティックスパイヤーズブルー’)×黄(ルドベキア‘ゴールドスターム’)のカラフルな花色の連なりが、夏らしさを強めている。中右/カラミンサのふんわりとした草姿が植栽に涼をもたらしている。下左/ルドベキア‘ゴールドスターム’やアガスターシェ‘ブルーフォーチューン’、グラスの爽やかなシーン。下右/アジサイ‘アナベル’やエキナセア‘サンシーカーズ レインボー’の花が色褪せ始め、ミスカンサスの穂がほんのりと秋の訪れを感じさせている。 7月の様子 ルドベキアにエキナセア、アガスターシェ、アスターなどの素朴な中に、華のある草花がメインとなり、この時季の彩りとなっています。その中で、アガパンサスとアジサイ‘アナベル’の白花が清涼感をプラス。ディスカンプシアやミスカンサス、ペニセタムなどのグラス類が花の間をつなぎ、この時季ならではの風景に一体感をもたらしています。 上左/ルドベキア ‘フラメンコ・バニラ’とアガパンサス‘エバーホワイト’の涼やかな組み合わせ。コンパクトなルドベキアを選んでいるので、抜群のまとまりに。上右/アガスターシェ‘モレロ’とアスター‘ロイヤルルビー’、ルドベキア ‘フラメンコ・ブライトオレンジ’の濃厚な花色の取り合わせが印象的なシーンを描いている。中左/素朴な雰囲気のエキナセア・マグナススーペリアとディスカンプシア‘ゴールドタウ’のフォルムのコントラストの妙が味わいを出している。中右/コルヌス‘ステラピンク’の白斑の葉とアジサイ‘アナベル’の白花が離れたところで呼応し、まとまり感をアップ。下左/バイオネストのダークカラーにアジサイ‘アナベル’の白さが際立ち、他の植物も美しく映える。下右/カレックス・エラータ‘オーレア’とヒューケラの葉の明るさがアクセントに。 6月の様子 この時季は、全体的にボリュームがありながらも、デザイン的に抑制が感じられる大人っぽい雰囲気の風景となりました。数種のグラス類に、少量の赤やオレンジ、青の花の存在感が見事に引き立てられています。ふわふわとした植物群の中で、アリウムの丸いつぼみやエリンジウム・プラナム‘ホワイトグリッター’の青花が描くドットが、心地よいアクセントとなっています。 上左/植物の茂みの奥で、鮮やかなオレンジ花のルドベキア ‘フラメンコ・ブライトオレンジ’が目を引き、視線を植栽の奥へと誘っている。上右/コルヌス‘ステラピンク’の斑入り葉やエリンジウム・プラナム‘ホワイトグリッター’の青みがかった株が見せる、幻想的なワンシーン。中左/花が少ないエリアで、赤花が落ち着いた彩りを添えているアガスターシェ‘モレロ’。中右/アガパンサス‘エバーサファイア’の濃いブルーの花が、風景に深みを与えて。下左/デスカンプシア・セスピトーサ ‘ゴールドタウ’が伸ばす繊細な穂が光を透過し、軽やかさときらめきをプラス。下右/アリウム・シュベルティのシードヘッドが、オブジェのような存在感を発揮。 5月の様子 たくさんの繊細な植物が風に揺られるさまは、花に満たされた野原のよう。全体的に白・ピンク・黄・青にまとめられた花色が、この時季ならではの軽やかでやさしい雰囲気を生み出しています。ナチュラルな景色の中に大小さまざまなアリウムが球状の花穂を上げ、特にアリウム・シュベルティが造形的なデザインを添えています。 上左/ホルデューム・ジュバタムのツヤのある穂がアクセントとなりながら、シーンの切り替えにも一役買っている。上右/オーニソガラム・アラビカムやダッチアイリス、アリウム‘シルバースプリング’などの球根類を、レースのような白花のオルラヤや紫のクナウティアがふわりと優しく繋いでいる。中左/ダッチアイリス ‘ブルーマジック’ の重量感とクナウティア・アルベンシスの浮遊感が対照的。中右/そばに植わるマツの木で日陰となるエリアは、ダッチアイリス ‘ブルーマジック’がキリッとしたアクセントに。下左/バプティシア・アウストラリスの量感が、シーンの見応えを高めている。下右/つぼみを下げるコバノズイナが野趣を漂わせて。 4月の様子 数種類のチューリップが、ピンク色を軸とした色合いで一斉に咲き始めました。黄色が混ざった小ぶりの花‘ガボタ’がピリリとスパイスを効かせています。周りにはオルラヤやグラス類がふわふわとした草姿で合間を埋めつくし、まさに『ギャザリング=花束』の雰囲気が表現され始めました。 上左/前面を彩っているチューリップ‘パープルエレガンス’と‘ガボタ’。圧倒するようなボリュームで訪れた人を出迎えている。上右/チューリップ‘ガボタ’に寄り添い咲くのは、ナチュラルな雰囲気のブーケに近年よく使われているナズナ(タラスピ・オファリム)。中左/松の枝でやや日陰気味になるコーナーはオルラヤがメイン。中右/後方は明るいピンクのチューリップ‘フレーミングピューリシマ’が賑やかさをアップ。下左/アリウムの隆々とした葉が植栽に立体感をもたらして。下右/下方を軽やかに埋めているフロックス・ディバリカタ‘メイブリーズ’。チューリップ‘ガボタ’とのコントラストが素敵。 3月の様子 2月から東側のガーデンの一角で咲き始めたシラー・ミシュチェンコアナが、黄色いスイセン‘テータテート’とともに、ガーデンのあちらこちらで咲き始めました。また、対の花壇それぞれに一株ずつ植わるユキヤナギが咲き始め、植栽に立体感が出始めています。 左上/林の中の一角を切り取ったような、自然味あふれるシーン。右上/早い時点から勢いよく葉を伸ばす、瑞々しいアリウムが植栽にインパクトを与えている。左下/奔放に枝を広げるユキヤナギがデザインに動きを出している。右下/あちらこちらから顔を出すシラー・ミシュチェンコアナ。先月より花穂が伸びて存在感が増している。 2月の様子 全体的に楚々とした植物で構成されているナチュラルなガーデン。枯れた花茎を残し、頭上から落ちるたくさんのマツの葉を味方につけることで、優しい野の趣が見事に表現されています。白花の2種の球根植物が、いち早く咲き始めました。 左上/クジャクアスターなどの株間で、ひっそりと白い花を咲かせているシラー・ミシュチェンコアナ。草丈2cmにも満たない極小の球根植物。 右上/清楚な彩りを添えるシラー・シベリカ‘アルバ’。原種ならではの繊細さが、ここにはよく似合う。 左下/マツ葉の布団の下から、いくつもの球根が一斉に芽吹き始めて。 右下/1月まで咲いていたアガスターシェ‘モレロ’の立ち枯れの姿が、野趣あふれるシーンを描いている。 1月の様子 2つの花壇の中央に据えられたバイオネストは、線の細い枝で組まれているので、まだ小さく幼い植物ともよく馴染み、オブジェのような存在感を放っています。昨年からちらほらと咲いている名残の花が、高さ20cm程に芽を成長させた球根とともに冬の庭に明るさをプラス。ガーデンの上に伸びるマツから落ちる影ともよく似合い、植栽をより自然な風景に見せています。 左上/クジャクアスターやアガスターシェ‘モレロ’の残花の彩りが、冷たい空気を温めているよう。 右上/ロゼット状に広がるアキレア‘カシス’の株の合間に、球根の芽がひょっこりと顔を出して。 左下/ビルベリー‘ローザスブラッシュ’の赤褐色の照り葉が、冬の光をきらきらと反射。 右下/成長を牽引するかのように球根類の芽が勢いよく伸びて、リズミカルで楽しげ。 12月の様子 コンテストガーデンA Gathering of Bouquet 〜庭の花束〜 12月下旬、作庭後の様子。 コンテストガーデンBCircle of living things 〜おいでよ、みんなのにわへ〜 【作品のテーマ・制作意図】 季節によってカラーリングが変化する植物や、実をつけて味わい深い風景を作ってくれる植物に集まる多様な生き物たち。そして各所に配置したサークルネストはそんな生き物たちの拠り所に。命の循環というキーワードをもとに植物だけではなく生きとし生けるものたちの集まる「庭」をテーマにデザインしました。人間だけに限らず、あらゆる生き物たち「みんな」にとっても楽しめる「命を感じられるガーデン」は「みんなのにわ」となり、命を循環させてゆきます。 【主な植物リスト】 宿根草:バプティシア‘ブルーベリーサンデー’/アガスターシェ‘ゴールデンジュビリー’ /糸葉丁子草/スタキス・オフィシナリス などグラス類:カレックス‘プレーリーファイア’/メリニス‘サバンナ’/ぺニセタム・オリエンターレ など低木:ブルーベリー/イチジク/紫式部 など球根:アリウム各種/チューリップ各種 など コンテストガーデンB 月々の変化 11月の様子 多種多様な秋の花々とグラス類が自由に広がり、混ざり合いながら一体となって、この季節ならではの庭の表情を生み出しています。高低差を活かした植栽は、いまもなおガーデンに豊かな表情を与えています。4つに色分けされたガーデンでは、そのテーマカラーに沿った花々が咲き続け、訪れるたびに新たな発見がある、飽きのこない風景が楽しめます。 上左/爽やかな青花のアスター‘リトルカーロウ’と斑入りのムラサキシキブが交じり合う、見応えのあるコーナー。上右/ヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’のオレンジ花と糸ススキ‘モーニングライト’の華奢な穂が秋のぬくもりを感じさせる。下左/茂みの隙間の向こうで、陽の光を透過したグラス類が輝いて見える。下右/銅葉×シルバーリーフが広がるシックなエリアに、シュウメイギク‘雪ウサギ’と白花細弁のクジャクアスターが加わり、透明感と明るさを添えている。 10月の様子 にぎやかだったガーデンは、葉の色が少しずつ落ち着きを見せ始め、ナチュラルで愛らしい雰囲気と、シックで大人っぽい趣が混在する秋らしい風景へと変化しています。ひときわ目を引くのは、種子から育ったオジギソウの花と、静かな存在感を放つ白花のヒガンバナ。趣の異なるさまざまな草花が見事に共存し、多種多様なリーフ類とともに豊かな表情を見せています。 上左/パトリニア・プンクティフローラのライムグリーンの花後の穂がダイナミックに広がり、斑入りのニューサイランやヘリアンサス‘ブリーディングハーツ’とともに見応えのあるコーナーを演出。上右/ピンクのポンポン型の小花が愛らしいオジギソウと、ロータス‘ブリムストーン’のやわらかな緑が、ガーデンの縁をふんわりカバー。下左/ヒガンバナ(白花)とシュウメイギク‘雪ウサギ’が清楚で上品な印象。傍らでルエリアの紫色の花がほどよいアクセントに。下右/銅葉のニューサイランのまわりを、濃ピンクのケイトウやユーパトリウム’マスク‘の立ち枯れが囲み、シックな色彩に。 9月の様子 真夏の勢いを多分に残しながらも秋の気配を感じさせる、生命力あふれるガーデンです。オレンジや黄色のビタミンカラーの花々が、白い穂を出すグラス類とともに、初秋の日差しをまぶしく反射しています。春に種まきされたオジギソウの株が、花壇の縁で勢いよく生育中。 上左/ルドベキアやバーベナ、パトリニア・プンクティフローラの群生からユニークに飛び出すペニセタム・マクロウルム‘テールフェザーズ’が、植栽に躍動感をもたらして。上右/ヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’やルドベキア‘ブラックジャックゴールド’のホットな色彩が、秋の陽光に照らされたカレックスとともに、落ち着きと温かみを演出。下左/ムラサキシキブの斑入り葉が植栽のトーンを抑え、メリハリを与えている。下右/ユーパトリウム‘マスク’が、アメリカテマリシモツケ‘サマーワイン’とともに勢いよく伸びている。ペニセタム・オリエンターレの白い穂とのコントラストも面白い。 8月の様子 親しみを感じさせてきたナチュラルなガーデンは、濃厚な色彩の大人っぽい雰囲気に変わり始めました。ヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’とルドベキア‘ゴールドスターム’の赤花×黄花がつくる波が、この時期のガーデンの印象を強めています。また、ニンジンについたキアゲハの幼虫が旺盛に葉を食べており、数週間後にはたくさんのアゲハ蝶がここから旅立ちそうです。 上左/ホットな印象を与えるヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’やルドベキア‘ゴールドスターム’が、淡く素朴な花を咲かせるパトリニア・プンクティフローラと対比的な風景を創り出す。上右/ムラサキシキブの斑入り葉とコトネアスターのシルバーリーフが植栽にアクセントを添えている。中左/先月に引き続き咲き群れる白花の群れに、メリニス‘サバンナ’の白い穂が加わり、移りゆく季節を感じさせる。中右/アキレア‘ラブパレード’やコレオプシス‘ガーネット’の奥にもペニセタム・オリエンターレが加わり、装飾的な雰囲気を醸し出す。下左/ワインレッドの深みがぐっと増しているレッドコーナー。下右/ペニセタム・マクロウルム‘テールフェザーズ’の直立した細長い穂が、ガーデンの中心でユニークに揺れている。 7月の様子 強烈な存在感で人目を引いているのは、大輪の純白のユリ、オリエンタルリリー・プロポーザル。2つのガーデンの中央部でたくさんの花を咲かる姿は圧巻です。続けて印象的なのが、オリエンタルリリー・プロポーザルの手前に広がるシャスタデージーとムスクマロー‘ホワイトパーフェクション’が広がるホワイトエリア。ユリとともに、周囲の赤やピンク、黄色の花の鮮やかさを引き立てています。 上左/ユーパトリウム‘マスク’やアンジェリカ・ギガス、エキナセア・テネシーエンシス、エキナセア‘ブラックベリートリュフ’で魅せるレッドエリア。上右/シャスタデージーとムスクマロー‘ホワイトパーフェクション’が広がるホワイトエリア。中左/ヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’の赤花とアキレア‘テラコッタ’の黄花、ブロッコリーのブルーグレーの葉、ワイルドストロベリー‘ゴールデンアレキサンドリア’の組み合わせが印象的。中右/スタキス・オフィシナリスとアリウム‘ミレニアム’、バーベナ‘バンプトン’のピンクの花に、ペニセタム・ビロサムがやさしく寄り添って。下左/オリエンタルリリー・プロポーザルの周りにバーベナ・ボナリエンシスやバレリアナ・オフィシナリスがワイルドに丈を伸ばしている。下右/ブルーベリーの実がおいしそうに色づいてきた。 6月の様子 色分けした各ゾーンがいずれもボリュームが出て、見応え満点の風景となりました。春はオレンジや黄、ピンクの花で、カラフルで楽しげな雰囲気でしたが、初夏になると黄×銅葉、白花と黒花など、シックで大人っぽい色合わせに変化しています。一角では、種子から育ったブロッコリーやニンジンが発芽して育ち、傍らではネジバナも咲くなど、のどかなシーンを展開。ガーデン内にはカナヘビも棲みついているようです。 上左/アリウム‘パープルセンセーション‘や斑入りのムラサキシキブのシックな植栽に、アキレア・クリペオラータがピリリとスパイスを効かせている。上右/ワイルドストロベリー‘ゴールデンアレキサンドリア’の黄緑葉とヘリオプシス’ブリーティングハーツ’の銅葉、ブロッコリー‘スティックセニョール’のブルーグレーがかった葉で魅せる、重厚な雰囲気が漂うコーナー。中左/ピンク花のスタキス・オフィシナリスと終わりかけのアリウム‘クリストフィー’の造形的な対比がユニーク。中右/シャスタデイジーやホタルブクロの白花と、アジュガ‘バニラチップ’やムラサキシキブの斑入り葉を組み合わせた、涼やかなエリア。下左/白花のサンギソルバテヌイフォリアアルバ、黒花のスカビオサ‘エースオブスペード’など草丈のあるもので構成された、シックでワイルドなエリア。下右/ニューサイランとサニーレタスの銅葉がガーデンの印象を引き締めている。 5月の様子 2月末に植えたサニーレタスがこんもりと茂り、種子を筋まきした一角ではニンジンが芽を出し、イチゴも赤く育ち始め、実りある景色が楽しめるようになりました、この庭のコンセプトである‘命の育み’が強く表現されはじめています。一方、アリウムが咲き群れるエリアには、シックで大人っぽい雰囲気が漂うなど、眺める角度によって楽しめるシーンが大きく異なっています。 上左・上右/ギリア・レプタンサ×アリウム‘パープルセンセーション’の花が宙を浮いているように咲いていて幻想的な雰囲気。中左/2種のアリウム、スティビタツム‘ホワイトジャンアントとクリストフィー。異なる色形・高さでリズミカルに競演。中右/アキレア‘テラコッタ’の銀葉とリシマキア‘ファイヤークラッカー’の銅葉の組み合わせが、シックなアクセントを添えている。下左/サニーレタスを軸に赤褐色がにじむ植物でまとめられたエリア。下右/チャイブや実をつけるワイルドストロベリーがのどかな時間を演出。 4月の様子 西側のガーデンではピンクのチューリップの開花の盛りが過ぎ、東側のガーデンのオレンジ×黄のチューリップにバトンタッチしました。温かみのある色鮮やかな組み合わせが遠くからでも目を引き、心浮き立つ風景が広がっています。中央に植わるブルーベリーの開花がピークを迎え、収穫期の楽しい風景が待ち遠しいガーデンです。 上左/チューリップ‘バレリーナ’とスイセン‘フォーチューン’の元気が出る色合わせ。上右/こんもりと茂るギリア‘レプタンサブルー’の群生の中にチューリップ‘エデュアルトペルガー’が大人っぽいアクセントを加えている。中左/アジュガ‘ブロックスカップ’が広がる傍らで、ポツンポツンと咲くムスカリ・ラティフォリウム。中右/ピンクのチューリップ‘フレーミングピューリシマ’の株元でワレモコウのやわらかい新葉が無数に上がっている。下左/コーナーを彩る矮性のチューリップ‘ポップコーン’。 訪れた人を華やかに出迎えているよう。下右/イチゴと原種のチューリップ・ヒルデの素朴な愛らしさを漂わせるワンシーン。 3月の様子 モコモコとしたバークのマルチングの中からさまざまな小球根が芽を出し、ちらほらと花を咲かせ始めました。先月から開花し始めたニホンスイセンは花数が増え、植栽にやさしい華やぎをもたらしています。ガーデンの手前の方では、シラー・シベリカ‘アルバ’やピンクやブルーのムスカリの愛らしい姿が見られるようになりました。 左上/素朴な風情あふれる植栽にニホンスイセンがよく似合っている。右上/2月下旬に植えられたダークカラーのレタス。茶色いカレックスをクッションにして、ワイルドストロベリー‘ゴールデンアレキサンドリア’との色の対比を効かせている。左下/花壇の縁でひょっこり顔を出すムスカリ‘ピンクサンライズ’。右下/イチゴの株の中から花を上げるムスカリ・アズレウム。 2月の様子 やわらかい新葉を芽吹かせる宿根草のグリーンが、冬の日差しにまぶしく輝き、春の訪れを感じさせています。一番乗りでスイセンが咲き始めましたが、その他にもたくさんの球根類が芽を出し始め、のどかな風景が広がっています。 左上/大株のユンカス・ブルーアローがまだ寂しい植栽にボリューム感を与えている。 右上/日本スイセンが開花し始め、ほんのりと華やぎ始めた。 左下/繊細な細葉を上げるアリウム・レッドモヒカンなどの球根類の芽吹き。 右下/青みがかったルー(ヘンルーダ)の葉が、イエロートーンの植栽のアクセントになっている。 1月の様子 ふかふかとした明るい色のマルチングの中に、瑞々しくやわらかい草花の株が点在する様子は、まさに春遠からじといった風景。やわらかい葉のグラス類が風を受けて花壇に動きを感じさせています。グリーンを残すギリア ‘レプタンサブルー’やシシリンチウム ‘ストリアタム’や黄葉のワイルドストロベリー ‘ゴールデンアレキサンドリア’が表土に明るさをもたらしています。S字状の溝部分に入れたトチノキの実やその殻が愛らしく、花壇の中にストーリーを感じさせます。 左上/ギリア‘レプタンサブルー’やシシリンチウム ‘ストリアタム’の明るいグリーンが、花壇に瑞々しい景観を作り出している。 右上/数カ所に設けたサークルネストが、愛らしい鳥の巣を思わせる。左下/冬の陽光に黄金色に輝く、黄葉のワイルドストロベリー ‘ゴールデンアレキサンドリア’とブラウンがかったカレックス ‘プレイリーファイアー’の取り合わせが美しい。 右下/赤い実をつけるコトネアスターのシルエットがユニーク。 12月の様子 コンテストガーデンB Circle of living things 〜おいでよ、みんなのにわへ〜 12月下旬、作庭後の様子。 コンテストガーデンCLadybugs Table 「てんとう虫たちの食卓」 【作品のテーマ・制作意図】 砧公園で暮らす「小さな住人(虫たち)」がこのガーデンを訪れて住みやすいように生態系を意識した植栽のデザインをしています。植栽は、見る場所や角度によって印象が変わるように、カマキリなどの天敵が身を潜められるような複雑さが出るよう工夫しました。植物は、てんとう虫やカマキリの食料となるアブラムシなどが好む「バンカープランツ」や蝶やミツバチたちの蜜源となる植物を植えています。「小さな住人(虫たち)」の生活をそっとのぞき見ることができる場所を目指しています。ここでの小さな体験が、自分の身近な自然環境を考えるきっかけになってもらえたら嬉しいです。 【主な植物リスト】 バンカープランツ:へメロカリス/ユウスゲ/イタリアンパセリ など宿根草:モナルダ‘ブラドブリアナ’/エキナセア‘メローイエロー’/アスター‘オクトーバースカイ’ などグラス類:スキザキリウム‘ハハトンカ’/ぺニセタム・カシアン/パニカム‘シェナンドア’ など低木:キンカン/アロニア/コバノズイナ など球根:ダッチアイリス‘ブルーマジック’/カマシア/カノコユリ‘ブラックビューティー’ など コンテストガーデンC 月々の変化 11月の様子 中央部ではスキザキリウムが一面に穂を立ち上げ、どこまでも続くような荒涼とした風景を思わせます。視線を移すと、アスターの花が豊かに咲き群れ、景色の趣が一変するのも見どころ。グラス類やシードヘッド、名残の花々が織りなす絶妙なバランスが、秋ならではのしみじみとした情趣を美しく表現しています。 上左/スギザキリウム‘ハハトンカ’の細長い穂の赤みが増し、ガイラルディア‘グレープセンセーション’やシュウメイギク‘ハドスペンアバンダンス’とともに、ピンクがかった柔らかな風景を見せて。上右/赤い実をつけるアロニアや花後のリアトリス・エレガンス、アスター・アンベラータスが野趣に富んだシーンを織りなしている。下左/アスター‘シロクジャク’やペニセタム‘カシアン’がのびやかに広がりワイルド。下右/アスター‘オクトーバースカイズ’が花壇の縁からあふれ出るように咲く姿は、遠目からも楽しめる。 10月の様子 多様なグラス類が一面に花穂を伸ばし、吹き渡る秋風と競演するように、情趣あふれるガーデンが広がっています。自然の風景を切り取ってそのまま据えたような佇まいは、この時季も健在。先月から咲いているガイラルディア‘グレープセンセーション’に加え、シュウメイギクやリアトリス‘エレガント’のピンクの花も咲き始め、ふわりふわりとグラスに寄り添いながら、落ち着いた彩りを添えています。植栽のあちらこちらでは、カマキリの姿も楽しめます。 上左/ガイラルディア‘グレープセンセーション’、シュウメイギク‘ハドスペンアバンダンス’が静かな風景にやさしい彩りをプラス。上右/草丈の低いアシズリノジギクのシルバーリーフとフウチソウの明るい緑葉が美しく広がる、安定感抜群のエリア。下左/アジサイ‘アナベル’のドライの花がつなぐ、ぺニセタム‘カシアン’×パニカム‘シェナンドラ’のたわむれ。下右/春にチューリップが咲いていたエリアには、赤みを帯びたスキザキリウム‘スタンディングオベーション’が静かに群生。 9月の様子 先月に続き、自然の風合いや趣が楽しめるガーデンです。この時期ひときわ目を引くのは、ぺニセタムやカラマグロスティスのグラス類。どこまでも広がる草原の風景を思わせるような群生が、残暑の厳しいこの季節に、爽やかな空気を運んでくれています。 上左/先月から花壇の中央付近に広がるスキザキリウム‘ハハトンカ’が一段と草丈を伸ばし、ワイルドな魅力が増してきた。上右/カノコユリのタネが大きく膨らみ、にぎやかだった夏の風景を思い出させるような、ノスタルジックな雰囲気を漂わせている。下左/花壇全体を高台から見守るように丈を伸ばしているのは、キンカンやカラマグロスティス‘カールフォスター’。下右/花穂が乾いたユーパトリウム‘マスク’の株元で、にぎやかな黄花を咲かせているのはルドベキア‘ゴールドスターム’。 8月の様子 花数が減り、リーフで魅せる時期となりました。さまざまな色形のグラスが穂を上げ、花後の株とともに、葉の魅力を生き生きと見せています。キンカンの奥にあたる西側エリアは、開花するルドベキア‘ゴールドスターム’とヘレニウム‘シエスタ’の群生が広がり、にぎやかな雰囲気が楽しめる一角になっています。 上左/ガーデンの縁から溢れんばかりのぺニセタム‘カシアン’のダイナミックな穂が、訪れる人々を出迎える。上右/先月、モナルダやアリウムが咲き群れた花壇の中心部では、スキザキリウム‘ハハトンカ’のブルーグリーンの細い葉が風に揺れる美しい姿を見せている。中左/ペニセタム‘カシアン’と反対側の角に植わるモリニア‘エディスダッチェス’の繊細な穂が、キンカンと宿根草をうまくつなぎながら、野趣のあるエリアを作っている。中右/ホスタ‘オーガストムーン’の花後の花茎が、ライムグリーンの葉とともに、さりげないアクセントになっている。下左/ユーパトリウム‘ベビージョー’やカラマグロスティス‘カールフォスター’、ペニセタム‘カシアン’が風に揺れる野趣あふれるワンシーン。下右/キンカンとカラマグロスティス‘カールフォスター’の向こうに広がるエキナセア‘メローイエロー’やルドベキア‘ゴールドスターム’、ヘレニウム‘シエスタ’がにぎやかに花色を添えている。 7月の様子 中央に横たわる谷筋の両側に生き生きと広がる植栽は、どこか高原のワンシーンを想起させる野性味あふれる雰囲気。小川のせせらぎや鳥のさえずりが聞こえてくるよう。ガーデン内に植わる2種類のヘメロカリス。通常アブラムシだらけになりがちな花のつぼみに、まったく姿が見られないのは、テントウムシが食べてくれたから。植物が力強く育っている健康的なガーデンです。 上左/ぺニセタム‘カシアン’の白緑に輝く穂や紫ピンクのモナルダの群生が爽やかな風を感じさせている。上右/アジサイ‘アナベル ピンク’やホスタ、アスチルベ・タゲッティ‘スペルマ’のピンクがやさしい雰囲気。中左/ユーパトリウム・マスクとユーパトリウム‘ベイビージョー’やカラマグロスティス‘カールフォスター’、カマツカがワイルドに広がる谷間に咲くのは、ヘメロカリス‘クリムゾンパイレーツ’の朱色の花。ひっそりとした佇まいが目にとまる。中右/アリウム‘ミレニアム’とエキナセア‘メローイエロー’の丈の低い群植とエリンジウム・ユッキフォリウムやカラマグロスティス‘カールフォスター’の草丈の差がメリハリを生んで。下左/カシワバアジサイ‘ルビースリッパー’の赤みが差した花がナチュラルな彩りを加えている。下右/明るいアクセントをもたらすホスタ‘オーガストムーン’を軸にした、野趣にあふれるエリア。カンパニュラ‘アメリカーナ’の青い花穂が爽やか。 6月の様子 先月まで咲き誇っていたアリウム‘マイアミ’の花が終わり、茶色い枯れ穂がユニークな風景を描いています。ナチュラルなガーデンだけに、カシワバアジサイやユリ‘リーガルリリー’の白い花の豪華さが際立ち、アクセントになっています。また、庭のあちらこちらで、テントウムシの幼虫がたくさん見られるようになりました。これは、冬の内にテントウムシが棲みやすい状態に整えていたことと、バンカープランツとしての原種系チューリップやイタリアンパセリを植えたからこそ。まさにこのガーデンは、テントウムシたちの食卓となっています。 上左/アリウム’マイアミ‘の株元を、モナルダ‘ブラドブリアナ’やピンクのモナルダがカバー。上右/コバノズイナ‘ヘンリーズガーネット’が白花を咲かせる穂を下げ、ホスタ‘ファーストブラッシュ’などと共に、瑞々しいシーンを描いている。中左/カシワバアジサイ‘ルビースリッパーズ’の大きな穂が目を引き、植栽の見応えをアップ。 中右/ユリ‘リーガルリリー’が堂々と咲いて華やかな雰囲気。下左/サルビア・カラドンナの群生と数本のアロニアで作る野趣の漂うワンシーン。下右/ホスタ‘オーガストーム’や原種のジギタリス・ルテアなどがグリーンの美しいグラデーションを見せている。 5月の様子 先月開花したフリチラリア‘オレンジビューティー’の株元で静かに待機していたアリウム‘マイアミ’が一斉に開花。落ち着いた色形の品種が選ばれていることで、デザイン的な風景にまとまっています。東側のガーデンでは先月末まで咲いていたカマッシアが終わり、ダッチアイリス‘ブルーマジック’にバトンタッチ。西側のガーデンでは主役が原種チューリップからアリウム‘カメレオン’に移り変わりました。無数にあがる花後のカマッシアが、野趣を強く漂わせています。 上左/太くしっかり伸びた花茎に小さめな花が咲くアリウム‘マイアミ’。無数の花が整然と並ぶ風景は、まるでインスタレーション作品のよう。上右/ダッチアイリス‘ブルーマジック’の背後に伸びるカマッシア・ライトヒトリニ‘カエルレア’の花後の姿にも風情が。中左/谷筋にカマッシア‘クシッキー’やソテツ、ユリがワイルドに広がる。中右/原種チューリップの花後の莢のまわりに広がるのは、コンパクトな草丈のアリウム‘カメレオン’。下左/肉厚で赤い葉脈を持つホスタ‘ファーストブラッシュ’の葉が地際に広がりデザインを引き締めている。下右/プルモナリア‘ダイアナクレア’×ツワブキ×メリカ・ヌタンスと、異なる色形のリーフを組み合わせているエリア。 4月の様子 ビオラ中心の素朴だった風景に、オレンジのフリチラリアや純白のスイセンが開花し、華やかさとボリュームが加わりました。静かに眠っていたガーデンの‘目覚め’が強く感じられます。花壇の縁や通路沿いでは小さなスミレや原種のチューリップ、プルモナリアが開花。コンパクトな株姿が斜面に植わる様子はまるでヨーロッパの自生地のようです。 上左/フリチラリア・インぺリアス‘オレンジビューティー’×アリウムの葉が、動きのあるユニークな風景を創り出す。上右/プルモナリア‘ダイアナクレア’とスイセン‘タリア’の色合わせが上品な雰囲気の一角。中左/小さなビオラ・ラブラドリカとグラスのメリカ・ヌタンスの華奢な組み合わせが、眺める人の視点をぐっと寄せつけている。中右/春の日差しを愛らしく反射する、原種のチューリップ・トルケスタニカとヒルデの群落エリア。下左/エピデディウム‘ピンクエルフ’とビオラが描く、野趣に富んだ風景。下右/アシズリノジギクの上にゲラニウム・ツベロサムが咲くまでは、スイセン‘タリア’が華やぎをもたらしているエリア。 3月の様子 2月下旬の作業でビオラと数種類の苗が加わったことで、宿根草や球根の花が咲くまでのガーデンは、よりにぎやかになりました。ビオラは楚々としながらもニュアンスのある品種を用いているので、デザインに深みを感じさせます。植栽の中をよく見ると、チューリップやアイリスが広がる中で、勢いよくフリチラリア‘オレンジビューティー’の新芽が上がり始めました。 左上/パープルのビオラが広がるエリアで、フリチラリア‘オレンジビューティー’がニョキリと芽を伸ばし始めた。右上/東側のガーデンの一角でひっそりと咲くプルモナリア‘ダイアナ クレア’。左下/ダッチアイリスの群植がユニークな景色を作る。右下/原生地を思わせる咲き姿の原種系チューリップ‘アルバ コエルレア オクラータ’。 2月の様子 なだらかな丘に咲くビオラの株が少しずつ大きく育ってきました。全体的には大きな変化はありませんが、よく見ると球根類の小さな芽があちらこちらに芽吹き始め、これから先の時期への期待が高まります。 左上/ビオラの花色やモナルダ・ブラドブリアナの紫葉、グラスの赤みが、このエリアのメインカラーとなっている。 右上/腐葉土をかぶり、葉をつけたまま越冬したアシズリノジギクが、ひっそりと顔をのぞかせて。 左下/愛らしい綿毛が、晩冬の風情を高めているツワブキ。 右下/枯木立のアロニアやコバノズイナの合間に芽を出しているのは、ダッチアイリス‘ブルーマジック’。 1月の様子 花壇の中は盛土された場所や溝が掘られた場所があることで全体に起伏があり、いくつもの丘が広がるような風景を思わせます。斜面に植わる落葉した数本の灌木と冬枯れの宿根草が沢沿いのようなシーンを連想させたり、ビオラが群植する様子がのびやかに広がる丘のようなシーンを感じさせたりするなど、さまざまな素朴な風景が展開。全体にのどかな雰囲気が漂っています。 左上/落葉したアロニアやノリウツギの数本の幹が、野趣のあるシーンを演出。 右上/長い花茎の先に残るツワブキの花が、侘びと力強さを感じさせる。 左下/丘の斜面に咲き群れるように広がるビオラたち。 右下/まだ厳しい寒さを物語るほかのエリアとは異なり、青々としたイタリアンパセリとエリンジウム パンダニフォリウム ‘フィジックパープル’が明るい透明感を添えている。 12月の様子 コンテストガーデンC Ladybugs Table 「てんとう虫たちの食卓」 12月下旬、作庭後の様子。 コンテストガーデンDKINUTA “One Health” Garden 【作品のテーマ・制作意図】 ヒトの健康、生きものの健康、環境の保全を包括的な繋がりとして捉えるワンヘルス (One Health)の概念を軸に、それら3つの主体が密接に関わり合う「ワンヘルスガーデン」をつくります。土壌環境を改善し、植物や微生物を豊かに育て、鳥や虫などの地域の生きものを呼び込む。ガーデンの香りや触れ合いを通し、ヒトの健康と安らぎを生み出すガーデンをつくり、いろいろな生きものがやってくる「みんなのガーデン」を実現します。 【主な植物リスト】 宿根草(蜜源植物):ルドベキア/オミナエシ/モルダナ/アザミ/ガウラ/スミレ/チェリーセージ など宿根草(四季の移ろい):グラス類のフェスツカ/カレックス/イトススキ/フウチソウ/チカラシバ/レモングラス/ミューレンベルギア・カピラリスなど低木類(鳥類・昆虫類来訪):スモークツリー‘グレース’/ガマズミ/アロニア‘メラノカルパ’カラーリーフ:カラスバセンリョウ/カリステモン‘リトルジョン’/イリシウム‘フロリダサンシャイン’その他(季節の果実や葉):ビルベリー/コバノギンバイカ/レモンマートル コンテストガーデンD 月々の変化 11月の様子 中央に寄せられた木々が落葉しはじめ、旬を迎えた草花の生き生きとした姿を際立たせています。ピンクや紫の花を咲かせながら自由に枝を伸ばすアメジストセージやハギがふんわりと広がるグラス類とつながり、常緑のリーフ類が彩るエリアとともに、見応えのある風景を作り出しています。 上左/常緑のテンジクスゲやモンタナマツとともに、ハマギクが落ち着いた佇まいで白花を開花。上右/落葉したガマズミのまわりで思いのままにハギが咲き乱れるさまは、愛らしくありながらもワイルド。下左/ボリューム感のあるロマンドラ・ロンギフォリアや明るい葉のカレックス‘エヴァリロ’の勢いある姿がひと際目を引く。アメジストセージのあでやかさが際立つシーン。下右/ミューレンベルギア・カピラリスの赤く透ける繊細な穂が印象的。 10月の様子 勢いに満ちた若々しい植栽は、季節の移ろいとともに落ち着きを見せ始め、樹木と草丈のある宿根草がガーデンに穏やかな雰囲気をもたらしています。植栽に立体感を与えているのは、フサアカシアとユーパトリウム‘グリーンフェザー’。その合間には、紫の花が爽やかなアメジストセージやサンジャクバーベナがふんわりと咲き群れ、ドライになったアジサイやアーティチョークの風合いを引き立てています。 上左/軽やかな植栽にアジサイ‘アナベル’の枯れ色が落ち着きをプラス。上右/ライトピンクのブッドレアとダークトーンのアーティチョークの相反するバランスが絶妙。下左/イリシウム‘フロリダサンシャイン’の黄緑の葉が、シードヘッドや優しいピンク色のシュウメイギクを背後から明るく照らしている。下右/カレックス‘エヴァリロ’、ラムズイヤー、ローズマリー、ペニセタム・アロペクロイデスなどの彩り豊かなリーフ類の植栽を、紅一点のチェリーセージの花でキリリと引き締めて。 9月の様子 若々しく成長していたガーデンも、少しずつ落ち着いたトーンに変わってきました。初夏から独特なオーラを放っていたアーティチョークの花がらは褐色に変わり、ユーパトリウム‘グリーンフェザー’を背景に、より一層の存在感を示しています。 上左/ブッドレアやバーベナ・ボナリエンシスが重なる茂みが、秋の陽光に照らされ、初秋のきらめきを放っている。上右/枯れ色を帯びたアーティチョークの大きな花がらが、ワイルドな植栽の中で宙に浮かび上がり、ガーデンの表情を豊かにしている。下左/アジサイ‘アナベル’の枯れた花穂が秋の訪れを感じさせる。下右/初夏から咲き続けるバーベナ・ボナリエンシスが、いまもなお植栽にナチュラルな彩りを添えている。 8月の様子 盛夏らしく全体的にググっと大きく成長し、見上げて楽しむ風景となりました。春よりもシンプルな植栽ですが、それぞれにボリュームが増して、見応えのある植栽となっています。なかでも特に目を引くのは、ルドベキア‘ゴールドスターム’。旺盛に茂るグリーンを背景に、濃厚な黄色が効果的に映えています。 上左/シンボリックな存在感を放っていたアーティチョークの花が終わり、開花時以上に彫刻的な姿を見せている。上右/花色が少ないエリアでは、アジサイ‘アナベル’の褪せはじめた花が上品な雰囲気を漂わせている。中左/ルドベキア‘ゴールドスターム’のにぎやかな群植が、植栽のインパクトを強めて。中右/ビルベリーの実が色づき始め、風景の小さなスパイスに。下左/花を終えたウスベニアオイがさらに成長を続け、大人の背丈をはるかに超える高さに。よく見ると花茎が帯化(たいか:植物の茎や根などが帯状に平らになる現象)した姿がおもしろい。下右/思わず触わって香を確かめたくなるハーブ類もイキイキと成長。 7月の様子 宿根草が灌木類に寄り添うように大きく育ち、インパクトのある植栽となりました。とくに力強くアピールしているのは、初夏からぐんぐんとつぼみを膨らませてきたアーティチョークの紫色の花。シルバーがかった切れ込みの深いリーフとともに、彫刻的な存在感を放っています。そのほかモナルダ(赤)やルドベキア‘ゴールドストラム’などの赤や黄色の花が、若々しい夏のシーンを描き始めました。また、アロニアやビルベリーの実が色づき始めた様子も楽しめます。 上左/春の終わりから咲き続けているクナウティア・マケドニカが、まだまだ元気に咲き続けている。 上右/発色のよいモナルダ(赤)が、カレックス‘エヴァリロ’やラムズイヤーのカラーリーフに映え、鮮やかさがさらにアップ。中左/ユーパトリウム‘グリーンフェザー’が2mほどに成長し、アーティチョークとバランスを取りながら、植栽にボリューム感を与えている。中右/アーティチョークの紫花とイリシウム‘フロリダサンシャイン’の色のコントラストや、スモークツリーのふわふわとした花が印象的。下左/ルドベキア‘ゴールドストラム’が咲き始め、オミナエシとともに黄色い花が瑞々しい風景に。下右/アジサイ’アナベル‘の豊かな花房と対比して、背景ではアロニア‘メラノカルバ’が小さな紫の実をつけている。 6月の様子 6月に入り植物たちは爆発的な成長を見せ始め、爽やかな初夏を謳歌しています。4月から咲いているクナウティアに加え、ゼニアオイの紫がかった濃いピンク色の花が加わりました。そのシックな雰囲気の中でアジサイ‘アナベル’が明るさを、モナルダやブラシの木の赤花がアクセントを添えています。ところどころに置いた菌糸のステップは、朽ちて崩れ、菌糸たちは土の中の微生物とともに植物の旺盛な成長を促しています。 上左/2種のクナウティアとゼニアオイの濃いピンクの花が、瑞々しい背景につややかに映えている。上右/この時季、遠くからでも目を引く2株のアーティチョーク。間の茂みに、イリシウム‘フロリダサンシャイン’の黄金葉とアジサイ‘アナベル’の白花が、明るさを添えている。中左/向かい合うエリア同士は軽重のバランスを変え、飽きの来ない風景をデザインしているのが分かる。中右/バイオネストが顔をのぞかせ、まるでオブジェのよう。下左/植栽手前側は、カレックス‘エヴァリロ’やラムズイヤーなどのカラーリーフで色彩豊かに。下右/バーベナ・ボナリエンシス(サンジャクバーベナ)が幻想的な風景を作り出す。 5月の様子 植物の成長が全体的に進み、こんもりと茂って生命力が感じられるガーデンに。特にウスベニアオイの旺盛な成長からは、健やかな土中の状態が伝わってきます。そんな重量感のある風景に軽やかさと彩りを添えているのは、2種のクナウティア・マケドニカやアルベンシス。スモークツリーやカリステモン‘リトルジョン’、ビバーナムなどの花も咲き始め、カラーリーフが主体の庭も変化に富んだ表情を見せています。 上左/濃いピンクのクナウティア・マケドニカと紫花のクナウティア・アルベンシスが風になびく姿が、見る人の心和ませる。上右/銅葉のツツジとガウラの新芽が、シーンに深みを与えて。中左/この時季は花が少ないものの、青々と茂るウスベニアオイや黒ずんだ葉のカラスバセンリョウ、陽に透ける美しい葉のスモークツリー‘ロイヤルパープル’など、リーフのバリエーションで楽しめる。中右/ピンクの小花をつけ始めたラムズイヤーのシルバーリーフは、思わず触れたくなる質感。下左/白い粒々とした花を咲かせるビバーナム・ハリアナム。下右/大きな葉を広げるアーティチョークのつぼみが膨らんできた。 4月の様子 先月までは主に灌木が存在感を放っていましたが、4月になると数種の球根が咲き、ほんのり華やぎが加わり始めました。この時季の主役はあちらこちらに点在するピンクのチューリップ。濃緑の葉や銅葉の灌木を背景に、つややかさを際立たせています。2月末に据えた菌糸を固めたステップにオオヒラタケが生え始め、地中の活発な様子がうかがえます。 上左/カラーリーフの中でチューリップ‘メンフィス’の華やぎが際立っている。上右/冬の間からふっくら生成り色のつぼみをつけていたベニバナマンサクがようやく開花。中左/カリステモン‘リトルジョン’のホットな赤花が、他とは異なる異国情緒を漂わせて。中右/まだ銅葉のような葉色をしたヒメハマヒサカキが、植栽に陰影をプラス。下左/手前側を軽やかに埋めているのは、ユーフォルビア・リギダとフェスツカ・グラウカ。下右/ひらひらとしたオオヒラダケのキノコが、菌糸ステップからヒョコリと現れている。こんな風景もこのガーデンならでは。 3月の様子 冬の景色として残していたアスターやススキなどのシードヘッドを2月末の作業で切り戻し、すっきりとした風景となりました。ガーデン手前側のラムズイヤーやクリーピングタイムは茶色い葉が整理され、芽を出した球根類と共に、植栽の瑞々しさをアップ。茶~黄の色彩だった風景は、徐々に緑色の風景へと移ろいつつあります。 左上/つややかな緑が映えるチューリップの芽出し。右上/アザレアツバキが開花。褐色の葉がカラーリーフとして活躍し、イリシウムの黄葉やアカシアの銀葉との色の対比が楽しめる。左下/ラムズイヤー、クリーピングタイムが青々と成長し、ガーデンの色合いをグリーンに牽引。右下/ニョキリと伸びる茎の先に花をつけるユーフォルビア・リギダ。株元では新しい芽をたくさん確認。 2月の様子 冬の装いをした低木の下で、成長の早い宿根草や球根類が成長を始めています。ふわふわとした枯れ姿のノコンギクの株元には、新たな葉がびっしりと広がっています。マルチングに用いたナシのチップがキノコの菌糸と絡み合い、朽ちて土に馴染み始めました。 左上/ベルベット調の質感を持つベニバナミツマタのつぼみが日に日に膨らんでいる。 右上/まわりとの取り合わせで、朽ちた姿にも風情があるアメジストセージやフェスツカ・グラウカ。 左下/ひと足早く青々と成長しているバーベナ・ボナリエンシス。 右下/ラムズイヤーの傍らで芽吹く、赤い新芽のガウラ。奥には球根類がたくさん芽を出している。 1月の様子 落葉した灌木類と冬枯れしたススキやノコンギクなどの宿根草とのコンビネーションが、冬の日差しに反射し、きらめきのある風景を描いています。一方、常緑樹のモンタナハイマツやローズマリーの瑞々しくどっしりとした重量感が、花がないこの時期にも豊かな表情を見せてくれます。所々に配された菌糸を固めて作った平板をめくると、接地面から菌糸が広がっており、土中の微生物たちがぐんぐんと成長しているのが分かります。 左上/アーティチョークのギザギザとした葉で、空間に造形的な面白さをプラス。 右上/枯れ姿のノコンギクが風情たっぷり。フサアカシアなどの灌木同士を、ふんわりとつないでいる。 左下/赤みを帯びたユーフォルビアのユニークなフォルムが、植栽のデザインに動きをもたらしている。 右下/冬の間も楽しめる、モンタナハイマツ×テンジクスゲ×ツワブキの造形の異なる常緑植物の組み合わせ。 12月の様子 コンテストガーデンD KINUTA “One Health” Garden 12月下旬、作庭後の様子。 コンテストガーデンE「みんなのガーデン」から「みんなの地球(ほし)」へ 【作品のテーマ・制作意図】 私は「みんなのガーデン」を、来園者だけでなく、花を訪れる虫、土壌菌類などの分解者、そして庭の先につながるこの生きた星「地球」の環境といった全ての「生あるもの」をつなげる庭と捉えました。温暖化する東京の気候に合った植物を差別なく組み合わせ、虫や菌たちによる循環系の形成、見るだけでなく庭づくりに参加もできる「みんなのガーデン」。「みんな」が共に助け合いながら、末長く幸せに暮らす世界、生命共存の尊さ・美しさを伝えたい。この想いが、この庭から未来へ・社会へ・地球へと広がっていけば、と考えています。 【主な植物リスト】 宿根草:マンガベ ‘マッチョモカ’/アムソニア ‘ストームクラウド’/アガパンサス ‘ブラックマジック’ /アネモネ トメントーサ/ジンジバー(ミョウガ)斑入り/イリス・エンサタ(ハナショウブ)‘バリエガータ’/パトリニア プンクティフローラ/タリクトラム ‘エリン’ /ユーフォルビア ‘ファイアーグロー’/ユーパトリウム ‘リトルレッド’ などグラス類:カラマグロスティス ‘カールフォースター’/モリニア ‘トランスペアレント’ /アンドロポゴン ‘ブラックホークス’ /スキザキリウム ‘ハハトンカ’ /コルタデリア ‘ミニパンパス’/メリニス ‘サバンナ’/ムーレンベルギア/スティパ/ホルデウム など低木:ネリウム(キョウチクトウ)‘ペティットサーモン’/コルヌス(サンゴミズキ)‘ケッセルリンギィ’/ロロペタルム (トキワマンサク) ‘黒雲’ /ブッドレア・ グロボサ など球根:ナルキッスス(スイセン)タリアなど数種/チューリップ(原種、園芸種含めて多品種)/アリウム (開花期をずらして数種)/イキシア・バビアナ・ワトソニアなどの南アフリカ原産種 など コンテストガーデンE 月々の変化 11月の様子 のびのびと広がる多種多様な植物たちは、それぞれ個性を保ちながらも、深まる秋の寂の趣を漂わせるようになってきました。オクラやヒモゲイトウなど昔ながらの植物が植えられた一画は、民家の庭先を思わせるような秋の風情を感じさせます。アスターやシュウメイギク、アスクレピアスなどの花々がひと際艶やかに咲き誇り、情趣豊かな世界を織りなしています。 上左/カリオプテリスやミューレンベルギア・カピラリスがふんわりと広がるその傍らで、アガスターシェ‘ゴールデンジュビリー’のシードヘッドとシュウメイギク‘パミナ’、アスター‘ジンダイ’が存在感を放ち、対比の妙を演出。上右/今にも綿毛を飛ばしそうなカルドンやバーベナ‘ブルースパイヤ—’などのシードヘッドとパニカム’ダラスブルース’の組み合わせが、デザイン的でありながらのどかな雰囲気を醸している。下左/ユッカ’ゴールデンスウォード’ の直線的で硬い質感と、線が細く柔らかいグラスのスティパの質感の対比が印象的。下右/ミューレンベルギア・カピラリスから透かしてみるルドベキア‘リトルヘンリー’が秋の味わい。 10月の様子 開花のピークがひと段落したガーデンでは、花やリーフが落ち着いた色合いへと変化し、味わいを増し始めています。さまざまなシードヘッドやグラス、リーフの魅力が際立つ季節の到来です。ルドベキア・マキシマやエリンジウム・ユッキフォリウム、カールドン、バーバスカムのシードヘッドのシルエットが爽やかな秋空に浮かび上がり、彫刻のような美しさを堪能できます。たくさんのトンボたちが羽を休めている姿が楽しめるのも、この時季ならではの光景。 上左/カールドンやバーバスカムの黒褐色になったシードへッドと、アスクレピアス・チュベロサの鮮やかなオレンジの花との対比が抜群。上右/エリンジウム・ユッキフォリウムとルドベキア・マキシマのシードヘッドが、空に向かってリズミカルにシルエットを描いている。下左/カンナ‘ベンガルタイガー’の存在感ある立ち姿が、まわりの植物の秋の趣を一層際立たせて。下右/アロエ・ストリアツラ、ベスコルネリア・セプテントリオナリス × デコステリアナ、カレックス‘エバリロ’、セトクレアセア‘プルプレア’の個性的な組み合わせは、秋に入ってもつややかさを維持。茶色になり始めたグラス類との対比が、コーナーを豊かな表情に。 9月の様子 彩り豊かな植栽は、少しずつ深みのある色調に変化しながらも、まだまだたくさんの花々でにぎやかです。マンガベやユッカなど、繊細な植栽のなかで重量感のある植物、乾き始めて軽やかさが増しているグラス類、ダリアやアマランサス‘ホピレッドダイ’など植栽を引き締めている赤葉や銅葉など、それぞれの役割をもった植物が必然性のある配置で、輝きを放っています。赤いオクラや綿の花も見頃。 上左/酷暑を乗り越え、なお元気に育つ多様な草花の中で、カンナ‘ベンガルタイガー’の明るい葉が、圧倒的な存在感で花壇全体をまとめている。上右/どっしりと葉を広げるマンガベ‘マッチョモカ’と、バーベナ‘バンプトン’の霞のような株姿の重量感のコントラストが、組み合わせの妙を感じさせる。下左/パトリニア・プンクティフォリアの花後の白緑色の種穂が輝く重層的な植栽。下右/ユッカ‘ゴールデンスウォード’のまわりで開花を迎えた、ビゲロウィア・ヌッタリィとアリウム‘メデューサズヘア’。スティパ・テヌイッシマも合わせた、このガーデンの晩夏のシンボリックなエリアの一つ。 8月の様子 酷暑の真夏も引き続き多種多様な花が咲き続けています。個性的な色彩とフォルムの対比をさまざまなグラス類が巧みに繋ぎ、混沌しているようでありながら、植物と人、虫たちまでもが見事に一体化された生命の空間を感じられます。グラス類や線の細い植物に対し、カルドンやエリンジウムなどのシードヘッドの彫刻的フォルムが対照的で魅力的。 上左/中央部分では大人の背丈を超える高さにまで植物が生育。アリウム‘サマードラマー’やルドベキア・マキシマのシードヘッドの間で、ヒビクス・コッキウス(モミジアオイ)が赤い花を咲かせている。上右/赤紫葉のアマランサス‘ホピレッドダイ’を引き立てるように、煙のような穂をつけているのはグラス、エラグロスティス・スペクタビリス。中左/線の細い植物を支えるように、ピクナンセマム・ムティクム(広葉マウンテンミント)の白い苞葉が広がっている。中右/日本で古くから育てられていて懐かしさを感じるムラサキゴテン(セトクレアセア・パリダ)と細かい穂のグラス、エラグロスティス・スペクタビリスの組み合わせや、エリンジウム・ユッキフォリウムの丸いシードヘッドが、幻想的な風景を描く。下左/ダウクス‘ブラックナイト’やルドベキア・マキシマのシードヘッドと黒葉のダリア‘ブラックナイト’のシルエットが個性的な風景を演出。下右/強烈な印象を放つカンナ‘ベンガルタイガー’とソフトな草姿のシルフィウム・モーリーや斑入りのグラス、ミスカンサス‘モーニングライト’との取り合わせが好対照。 7月の様子 花壇の中央部の草花は人の背丈を超え、見上げる景色になりました。この時季でも多種多様な花が咲き続けて、日々大きく変化する絵画的シーンとの一期一会の場になっています。あえて無造作に見せるカッティングと目立たないよう支柱を添えることで、整いすぎない植栽の野生みを楽しみながら、植物の生命力まで感じることができます。 上左/にぎやかに咲くコレオプシス’ガーネット’の濃いピンクや、その背後から顔を出すエキナセア’マーマレード’、赤紫葉のアマランサス’ホピレッドダイ’などのこっくりとしたカラーを、スティパのエアリーな褪せた穂がひと際あでやかに引き立てている。上右/エリンジウム’ブルーグリッター‘やアキレア’ヘラ・グラショフ‘などさまざまな色形の植物が、一幅のタペストリーのようなシーンを描いて。中左/リリウム・ライヒトリニィ(=コオニユリ)やフロックス‘ハーレクイン’、モナルダ’ファイアーボール‘のビビッドな花色が、強烈なインパクトを放つ。中右/リアトリス‘コボルト’とダリア‘ブラックナイト’など比較的コンパクトな品種で安定感を出したエリア。下左/ニューサイランの縦ラインを中核に、ブロンズフェンネルやダウクス‘ブラックナイト’などセリ科の花特有の水平感を対比させ、そこにアリウム‘サマードラマー’の球状のシードヘッドがふわりと浮かぶシーンはどこか幻想的。下右/ヘレニウム‘モーハイムビューティー’の花に、ニュアンスある銅葉のクロコスミア‘ソルファタラ’ が寄り添う。その黄〜濃オレンジ花の色彩と、奥に咲くバーベナ・ボナリエンシスやサルビア・グアラニチカなどの青紫花との補植対比が風景にリズムを加えて。 6月の様子 春に引き続き、初夏の花がにぎやかに開花しています。パレットのように豊かな色彩が展開し、花姿・草姿もじつに多種多様。グラス類のメインはホルデウム・ユバツムからスティパに移行しています。中でも繊細でいて堂々とした存在感を放つのは、大型種のスティパ・ギガンテア。ニューサイランやカールドン、エルムルスとともに、造形的でありながら野趣のある風景を織り成し、観る人の関心をぐっと引き寄せています。 上左/ダイアンサス・カルスシアノルムの濃いピンクの花とペルシカリア‘ゴールデンアロー’の黄金葉のコントラストが、シーンの印象をぐっと高めて。上右/さまざまな草姿・花姿の植物が美しいレイヤーをつくり、重層的な風景を紡ぎ出している。中左/ダリア‘ブラックナイト’やバーバスカムなどの多様なリーフの中で、アキレア’アプリコットディライト’、シシリンチウム・ストリアツムが効果的に彩りを添えている。中右/ニューサイランやスティパ・ギガンテア、カラマグロスティス‘カールフォースター’で魅せる、独創的なシーン。すらりと伸びるアリウム‘サマードラマー’のつぼみがユニーク。下左/アロエ・ストリアツラの手前側に合わせられたピンク花のマツバギクと黄葉のカレックス‘エヴァリロ’。ガーデンの入り口にふさわしいウェルカムコーナーとして存在感を放っている。下右/アルストロメリア‘サマーブリーズ’ のオレンジ×黄の花が、灰紫色の葉とともに植栽の表情を豊かに演出。 5月の様子 4月まで個々の形が際立っていた植栽もすくすくと成長し、様々な花が風に揺れる野原のようなナチュラルな風景に様変わりしました。主役はチューリップから、バリエーションもさまざまなアリウムにバトンタッチ。ガーデンのあちらこちらでユニークな花姿が楽しめます。色形のバラエティ豊かな植栽のなかで、特に目を引くのは、ピンクのエスコルチアやパパベル’レディーバード’の花とホルデウム・ユバツムのキラキラした穂。風に揺れる花がビビッドなスパイスとなりつつ、牧歌的・幻想的な光景を演出しています。 上左/目にも鮮やかなピンクのエスコルチアとトラディスカンティア‘スイートケート’、ロロペタルム’黒雲’の配色取り合わせ。アリウム・シューベルティがシーンに形のリズムも添えて。 上右/パパベル’レディーバード’の真っ赤とネペタ’ウォーカーズロウ’の青紫の花色対比が遠目からでも色鮮やかに映える。 中左/ホルデウム・ユバツムの穂が陽光に輝いて描き出す幻想的な野の風景。 中右/花壇中央、ボリュームのあるバプティシア’キャロライナムーンライト’のクリーム色の花穂とアリウム’グラディエーター’と紫色の球形花序で色形のコントラストを表現。 下左/サルビア‘カラドンナ’の深みのある暗紫花がシーンの色彩をぐっと引き締めてより印象を強化。 下右/やわらかく軽やかな色・質感の植物の中、個性の強いアロエ・ストリアツラやベスコルネリアが、優しい表情に溶け合いつつ同時に重量感のあるフォーカルポイントに。 4月の様子 グラベルガーデンのような趣から一転! スイセンやチューリップ、フリチラリアなどの球根に加えてラナンキュラス・ラックスも満開を迎え、一気に華やぎのある風景となりました。 花色の美しさに加え、楽しませてくれるのが個性豊かな春咲き球根の開花リレーやリーフの鮮やかな芽吹き。独創的、かつ景色の移ろいと生命の歓喜を堪能できる季節です。 上左/コーナーで満開を迎えたロロペタルム’黒雲’の濃厚な銅葉と濃赤花が目を引く。黄金葉のトラデスカンティア‘スイートケイト’、青紫花のシラー・シベリカとのコントラストが挑発的。中央のアンティーク調の一輪はチューリップ‘ラ・ベルエポック’、その左、細い外弁に緑色がのる咲き方がユニークな白半八重チューリップは‘ホワイトバレイ’。 上右/ピンク花で黒軸のチューリップ‘ライトアンドドリーミー’やスイセン‘タリア’、銅葉のアスチルベ‘ダークサイドオブザムーン’の濃厚な対比がやわらかい葉群の中で際立っている。中左/ペルシカリア‘ゴールデンアロー’の黄金葉とチューリップ‘ハッピーフィート’の明暗の対比が鮮やか。 中右/大型で彫刻的な姿・不穏な花色のフリチラリア・ペルシカがシーンをぐっと劇的に引き締めて。下左/ユッカ‘ゴールデンスウォード’の株元を軽やかに彩るアスフォデリネ・ルテアの細葉とベロニカ‘ジョージアンブルー’の紫花。下右/原種系のチューリップ ‘ジャイアントオレンジサンライズ’。独特な葉模様と巨大花が個性的なフォーカルポイントに。 3月の様子 グラベル仕上げの地面で個性を放つ植物たち。それら一つひとつにフォーカスして楽しめるのは、地上部が少なく隙間があるこの時季ならではの見どころです。さまざまな芽が小さな景色を織り成す中、今春の一番手で花をつけているのはスイセンとクロッカスの2種。このガーデンでは真っ白い花が見られるのは春の初めだけで、これからカラフルに色づく植栽の静かなイントロダクションとして、清楚な彩りを添えています。 左上/世界の多種多様な植物が、健やかに成長できるよう配慮して植えられたガーデン。右上/ベタっと広がるアリウム ‘マイアミ’。アリウムだけでも大小・姿形さまざまに展開する多様な種類が用いられている。左下/透明感あふれるナルキッスス パピラケウス。右下/白花の外側の花弁が紫色のクロッカス ‘プリンスクラウス’。自然界で見られる“コロニー(群生)”のように、ぎゅっとまとめて植えている。 2月の様子 中央のニューサイランを軸にして渦を描くように設けられた花壇に、早くも植物たちが色形の異なる個性を見せ始めました。現在は、造形的なフォルムのアロエやエリンジウム ‘フィジックパープル’、黒葉のベルゲニア ‘レッドスタート’、ペンステモン ‘ダークタワーズ’などの植物が、他にリードして存在感を放っています。その間では小さな宿根草や球根が愛らしく芽を伸ばして。 左上/芽出しから独特な姿を見せるチューリップ ‘ジャイアントオレンジサンライズ’。 右上/葉の縁が赤く色づくチューリップ シルベストリスと黒みがかる繊細なダイアンサス カルスシアノルム、そしてベタっと大きめの葉を広げるフロミスなどが植わるエリア。どこを切り取っても組み合わせの妙が感じられる。 左下/ユッカの傍らに植わる、クルクルと渦を描く姿がユニークなアスフォデリネ ルテア。個性的だがブルーがかるやわらかい質感が、ユッカの強烈な雰囲気を和らげている。 右下/マットな革質の黒葉ならではの質感で存在感を放っているのはベルゲニア‘レッドスタート’。 1月の様子 化粧砂利のような明るい表土とアールを描く通路のデザインは、植物が小さなこの時期の大きな見せ場の一つとなっています。見下ろした風景はまるでノットガーデンのよう。常緑性のニューサイランやアロエなどのほかは、冬季落葉性の宿根草や低木類で、地上部がとても小さかったり枝のみだったりしますが、冬越しのロゼット葉の造形やカラーステムがとてもユニーク。それだけに、これからの成長と風景の変化も大きな見どころです。 左上/幹立ちして展開するアロエ ストリアツラと、カレックス ‘エヴァリロ’のライムイエローの葉が、植えたてのため不織布を被せて防寒養生中のベスコルネリアをやんわりと目隠し。右上/鹿沼土と軽石をブレンドした明るい表土をトキワマンサク ‘黒雲’の照りのある黒葉で引き締めている。左下/細い葉をふんわりと広げるルッセリア エキセティフォルミスやカレックス ‘プレイリーファイアー’、ロドコマ カペンシスに矮性のネリウム (キョウチクトウ) 、ネリウム ‘ペティットサーモン’を組み合わせた、植物の多様な面白さが感じられるシーン。右下/多くの植物が冬季落葉中のなか、放射状に葉を広げるエリンジウム ‘フィジックパープル’が、目を引くアクセントとして活躍しながら空間を埋めている。 12月の様子 コンテストガーデンE 「みんなのガーデン」から「みんなの地球(ほし)」へ 12月下旬、作庭後の様子。 「第4回 東京パークガーデンアワード 夢の島公園」の参加者募集! ※締め切りました 2022年にスタートしたガーデンコンテスト「東京パークガーデンアワード」が、代々木公園・神代植物公園・砧公園での開催を経て、2025年、夢の島公園で始まります。第4回のコンテストの舞台は、夢の島公園「グリーンパーク」内(東京都江東区)。コンテストのテーマは、「海辺のサステナブルガーデン」です。応募の締め切りは、2025年8月31日(日)18時必着。応募方法など詳細は、以下のバナーをクリック! 5月25日(日)「入賞者イベント」開催! ※終了しました 第3回東京パークガーデンアワードの入賞ガーデナー5組によるガーデンイベントを5月25日(日)に開催しました。入賞ガーデナーが案内する「ガーデンツアー」や「たねダンゴづくり」、「微生物観察ワークショップ」など、子どもから大人まで楽しめるガーデンイベントで当日は賑わいました。 ■日 時:2025年5月25日(日)10:00~15:10(雨天中止)■会 場:都立砧公園(東京都世田谷区)コンテストガーデンエリア(みんなのひろば前)■参加費用:無料 第3回 東京パークガーデンアワードの入賞者によるオンライン座談会イベント 都立砧公園にて開催中の第3回コンテストガーデン入賞者5名によるオンライン座談会を2025年8月1日(金)15:30~17:00に開催しました。座談会では、入賞者それぞれの応募書類の紹介、植物の調達から造園、メンテナンスまで、参加したからこそ分かる”ナマ”の声をお届けしました。 11月9日(日) 「ガーデンフェスティバル@砧公園」開催!※終了しました 「東京パークガーデンアワード」のコンテストをより深く知ってもらうためのイベント「ガーデンフェスティバル@砧公園」を11月9日(日)に開催しました。入賞ガーデナーが案内する「ガーデンツアー」や「生き物クイズ」、「ミニブーケづくり」など、秋の花咲く庭を眺めながら過ごす特別な1日。人気のキッチンカーもやってきて、大人も子どもも楽しめるイベントとなりました。 ■日 時:2025年11月9日(日)10:00~16:00(雨天中止)■会 場:都立砧公園(東京都世田谷区)コンテストガーデンエリア(みんなのひろば前)■参加費用:無料 5つの花壇のコンセプト・作庭・審査様子の詳しいレポートはこちらをチェック! コンテストガーデンを見に行こう! Information 都立砧公園「みんなのひろば」前所在地: 東京都世田谷区砧公園1-1電話: 03-3700-0414https://www.tokyo-park.or.jp/park/kinuta/index.html開園時間:常時開園※サービスセンター及び各施設は、年末年始は休業。営業時間等はサービスセンターへお問い合わせください。入園料:無料アクセス:東急田園都市線「用賀」から徒歩20分。または東急コーチバス(美術館行き)「美術館」下車/ 小田急線「千歳船橋」から東急バス(田園調布駅行き)「砧公園緑地入口」下車/小田急線「成城学園前駅」から東急バス(二子玉川駅行き)「区立総合運動場」下車駐車場:有料
-
東京都

グランプリ決定!「第3回東京パークガーデンアワード砧公園」の『ファイナル審査』を迎えた11月の庭と審査…
年3回審査を行うガーデンコンテスト「東京パークガーデンアワード」 制作が始まってから約1年が経過するコンテストガーデン。「最終審査」では、今回のテーマである『訪れる人々の五感を刺激し、誰もが見ていて楽しいと感じる要素を取り入れた‘みんなのガーデン’が表現されているか』に加え、『秋の美しい風景が楽しめる健やかなガーデンとなっているか』という観点から評価が行われました。これまでに実施された「ショーアップ審査」(4月)と「サステナブル審査」(7月)の結果も踏まえ、総合的に判断されます。審査日:2025年11月6日※年によって気象条件が変わるため、開花の時期がずれていても評価に影響しません。 審査員は以下の5名。福岡孝則(東京農業大学地域環境科学部 教授)、正木覚(環境デザイナー・まちなか緑化士養成講座講師)、吉谷桂子(ガーデンデザイナー)、本木一彦(東京都建設局公園緑地部長)、植村敦子(公益財団法人東京都公園協会 常務理事) 【コンテスト審査基準】丈夫で長生きする宿根草・球根植物(=多年草)を中心に季節ごとの植え替えをせず、季節の花が順繰りと咲かせられること/公園の景観と調和していること/公園利用者の関心が得られる工夫があること/公園利用者が心地よく感じられること/植物が会場の環境に適応していること/造園技術が高いこと/四季の変化に対応した植物(宿根草など)選びができていること/「持続可能なガーデン」への配慮がなされていること/メンテナンスがしやすいこと/テーマに即しており、デザイナー独自の提案ができていること/総合評価※各審査は別途定める規定に従い、審査委員による採点と協議により行われます。 11月の審査時期を迎えた5名の授賞ガーデンと一年の振り返りコメントをご紹介 コンテストガーデンA 【準グランプリ】Gathering of Bouquet 〜庭の花束〜 【審査員講評】 タイトル通り、花束のような素敵なガーデンでした。公園に溶け込んだ遠景は絵画的で美しく、近づいてみると、植物どうしが響き合って作る美しいシーンが随所に見られました。バイオネストはサステナブルな機能だけでなく、庭を特徴づける造形物としても効果的に働いていました。花壇の場所的に一部が松の木陰になってしまうハンディがありましたが、植物選択やメンテナンスの工夫でうまく対処されていました。厳しい夏を越えられなかった植物も見受けられましたが、春の華やかな景色は今なお強く印象に残っており、都会的で洗練された美しさが秋に至るまで展開されていました。多くの人々に楽しさや幸福感、季節の移ろいの喜びを与えてくれるガーデンでした。 開花期を迎えていた植物 サルビア‘ミスティックスパイヤーブルー’、アガスターシェ‘モレロ’、アガスターシェ‘ブルーフォーチュン’、アネモネ・フペンシス‘パミナ’、ノコンギク‘夕映’、クジャクアスター‘紫八重’、ヘリオプシス‘ブリーティングハーツ’、カラミンサ、チョコレートコスモスほか 【今回の庭づくりを振り返って】 季節ごとの草丈・開花期・色彩の変化を踏まえつつ、視覚的な彩りと空間の広がりを備えた「庭の花束」を表現しました。限られた面積を鑑みて、小さな配植を丁寧に重ね、グラス類は緩やかに束ねることで、配植の繊細さを際立たせています。夏の開花量を抑える切り戻しを行い、植物の体力を温存させることで、秋まで開花期を延ばす工夫を実践。その結果アガスターシェ、ヘリオプシス、アネモネなどは再び蕾を上げ、秋の構成美においても重要な役割を果たしてくれました。また、子供から大人まで楽しめるように、目線の高さに配慮した多層的な花壇構成を目指しました。宿根草に柔らかな日陰を提供するバイオネストを中心に据えることで、植物の生育特性に応じた配置に多様性を生むことが出来たと考えています。その結果、ガーデン全体に奥行きが生まれ、来園者の視線や動線を自然に誘導してくれる花壇構成が実現しました。 ガーデンにバイオネストがもたらした機能と可能性が、新たな気づきとなりました。管理作業で発生した植物残渣はすべてここに収めることができ、廃棄物の削減と土壌循環の促進に貢献。また、景観要素としても機能し、冬は構造物としての存在感を、春以降は宿根草を始めとする草花の背景として視覚的なアクセントを担ってくれました。ナチュラリスティックな場の質を高めると同時に、来園者の興味を引く造形として、ガーデンに物語性を添える存在となってくれたことは思わぬ発見の1つです。 年間を通しての最大の成果は、ガーデンを介して来園者のまわりで生まれる交流です。植物単体の美しさだけではなく、風景としての調和を大切にしながら「このガーデンがみんなの記憶の中で輝きますように!」と想いを込めて管理に取り組みました。 コンテストガーデンB 【入賞】Circle of living things 〜おいでよ、みんなのにわへ〜 【審査員講評】 イチゴやイチジクなど、自分の庭に取り入れたくなるカジュアルな提案がたくさん詰まった庭でした。見ているうちに「美味しそう!」と感じ、ガーデンの先にある家族の物語まで想像させてくれます。剪定枝で作った可愛いサークルネストなど、子どもと一緒に楽しめそうな工夫も魅力的です。植栽デザインは年間を通して全体の色合いが美しく、コーナーごとに設けられたテーマカラーをぐるりと一周しながら眺める楽しみがありました。特に秋には、黄・オレンジなど暖色系の構成から、目を転じるとアスターなどの寒色系へと色調が変化する眺めが絵画のようでした。季節ごとに多彩なシーンを提供してくれ、幅広い世代の来園者が訪れる砧公園という場所にふさわしい、元気をもらえるガーデンでした。 開花期を迎えていた植物 シュウメイギク‘雪ウサギ’、ヘリオプシス‘ブリーティングハーツ’、ルエリア、アスター‘リトルカーロウ’、クジャクアスター、ケイトウ、青花フジバカマほか 【今回の庭づくりを振り返って】 来園者の興味を引く野菜類やオジギソウなど、みんなのガーデンというテーマに沿った独自のチョイスができました。なかでもオジギソウはとても吸引力があり、子どもだけでなく大人も足を止めて楽しんでもらえていたと思います。また、テーマカラーで分けたりガーデン内でも見所を点在させたりすることで、どの角度からでも楽しめるガーデンになりました。 自分たちで考案した、メンテナンス時の発生材を利用したサークルネストは、生き物の拠り所になるだけでなく季節感の演出にも一役買いました。シンボリックな姿ですが植物の邪魔をせず、ガーデンともよくマッチしたと思います。一年という期間もあり、当初のアイデアの中にあった「たくさんの生きとし生けるものたち全てがやってきてくれる」、というところまで辿り着くことはできませんでしたが、今後も管理事業者によるメンテナンスが続いていくなかで、その姿に徐々に近づいていくことはできるだろうという手応えは感じることができました。 私達の住む世田谷の地の親しみある砧公園で、地域でつながった仲間たちとコンテストに挑戦し、ガーデンをつくり上げ、管理しながら見守ることができました。今後も地元を盛り立てたツールとして、このガーデンが区民の憩いの場になることを期待しています。ガーデンは人と植物だけではなく、人と人とのつながりを生み出すコンテンツ。メンテナンス中などに、来園者にガーデンの説明や見所、今後の楽しみなど、ガーデンの意図を直接伝えることの重要性に気づきました。 コンテストガーデンC 【グランプリ】Ladybugs Table 「てんとう虫たちの食卓」 【審査員講評】 「てんとう虫たちの食卓」というテーマがよく表現された庭でした。アブラムシを増やす植物をあえて入れてテントウムシを誘い、剪定した枝葉を作業通路に置いてナメクジなどを引き寄せ植物たちを守るなど、生態系を豊かにすることで庭も美しくするプランが成功しているようでした。プランツタグのQRコードで植物や虫たちを紹介する発信も素晴らしい取り組みです。広めに確保された作業通路が風の道となり植物が蒸れにくく、景観的にも奥行きや抜け感を生み、植物の表情をより豊かに演出していました。グラスの穂が風に揺れる姿は野原で遊んでいるような気持ちにさせ、多彩な植物たちが混み合うことなく絶妙に風を通しながら公園の風景に溶け込む様は、見るほどに引き込まれる美しい眺めでした。予測の難しい酷暑を越えた先に秋の自然な美しさが際立つことこそが、宿根草ガーデンの真骨頂だと気づかせてくれるガーデンでした。 開花(結実)期を迎えていた植物 アスター‘シロクジャク’、アスター・アンベラータス、アスター‘オクトーバースカイズ’、ガイラルディア‘グレープセンセーション’、シュウメイギク‘ハドスペンアバンダンス’、リアトリス・エレガンス、キヨスミシラヤマギク、アロニアほか 【今回の庭づくりを振り返って】 原生地で見られるような群落を意識し、季節──とくに春から初夏にかけて──の移ろいによって雰囲気が大きく変わるように植栽を構成しました。ネスト通路を挟んで各エリアがレイヤーをつくるよう工夫しており、立つ位置によって奥行きが生まれ、印象や見え方が変わったのではないかと思います。 テーマは「昆虫などの小さな生きもの」。そのため、越冬のための枝を敷いたり、春先にアブラムシがつきやすい“原種系チューリップ”を植えたりと、ガーデンの象徴となったテントウムシが早い時期から活動しやすい環境づくりを行いました。その結果、アブラムシなど特定の虫が過剰に増えることもなく、ガーデン全体の生態系をバランスよく保つことができたと感じています。 「バンカープランツ」の手法は予想以上に効果的で、初夏にアブラムシで真っ黒になるはずのヘメロカリスが、ほぼ無傷だったのには驚きました。今回もっとも食害が多かったのはマメコガネでしたが、コガネムシの幼虫に寄生するツチバチが多く飛来していたので、来年の変化が楽しみです。8月の時点で観察できた昆虫はおよそ120種類。ガーデンの存在が、砧公園の生態環境に少しでも寄与できたのではないかと感じています。 一年を通して華やかさを保ちながらローメンテナンスを目指すことは、やはり反比例の関係にあると実感しました。広大ではない1つのガーデンで“見どころ”とのバランスをとる難しさは、大きな学びになりました。 また、施工から約3年後に全体がよく馴染む景観になるよう意識してデザインしましたが、土壌改良(微生物・空気・水の流れを意識)を丁寧に行ったことで、一部の植物がまるで3年の風格をまとったかのように成長し、驚かされました。今後はその部分をさらに深めていけたらと思っています。 コンテストガーデンD 【入賞】KINUTA “One Health” Garden 【審査員講評】 微生物など土の中のことまでよく考えられたガーデンで、土壌改良のため取り入れた菌糸平板からツヤツヤのキノコが生えてきた様は、まるでアート作品のようにも感じられました。「土壌環境が豊かになることで植物本来の力が発揮され、豊かな景観や生態系に繋がる」という自身のコンセプトに真正面から取り組み、生物多様性の面では、実際に虫たちを多く呼び寄せることに成功していました。景観的に植物の高さのバランスに欠ける面もありましたが、できるだけ自然に任せたおおらかな景色とも言えます。メンテナンスの回数も少なく、持続可能な公園の庭づくりという点でも、今後のパフォーマンスに注目していきたいガーデンです。 開花期を迎えていた植物 アメジストセージ、ハギ、チェリーセージ、ハマギク、ブッドレアほか 【今回の庭づくりを振り返って】 子どもたちの遊び場であり、天気のよい日には老若男女が思い思いに過ごす場所。そんな“日常の延長にある公園”の中で、ガーデンを「眺める」「触れる」、時には「花や葉を持ち帰る」など、さまざまな行動を通して、人と人、生き物、植物、微生物が自然に交わる世界を表現したいと考えました。宿根草の花色や種類の配置、低木との高低差などを工夫することで、2つの花壇でありながら統一感と自然な広がりを両立した空間を表現することができました。それぞれの植物の特性を活かしながら、ナチュラルな景観を形成できたと感じています。また、「生き物との共生」をテーマの一つとして掲げ、普遍的なチョウやウグイスなどの小鳥だけでなく、オオセイボウといった珍しい昆虫も観察され、多くの来園者に楽しんでいただけました。 ガーデンは1年間を通してローメンテナンスで維持。刈り込みや枝の更新をしない剪定管理、季節ごとの補植をするのではなく、最初に植えた植物たちが育ちたいように育てました。 今回のコンテストに使用した原産地もバラバラで多種多様な植物たちは、限定的な植栽帯の中でコミュニティを作り生存競争をしています。昆虫や鳥などの生き物は上手くその空間にニッチを見つけて入り込みます。人はガーデンにより五感を刺激され、微生物を浴びることで、心身の本質的な健康を享受しています。この環境、ヒト、微生物の連関こそが“One Health”を体現しています。 さらに、イベントでの案内やメンテナンス、写真撮影などを通じて出会った方々には、「生態系のぬか床」といった取り組みも紹介し、微生物の世界にも関心を持っていただくことができました。私たちの目指す“One Health”の視点からガーデンを体感してもらえたのではないかと感じています。このメンバーで、“One Health”のガーデンを砧公園で提案できたことは、最大の成果だと思います。 コンテストガーデンE 【審査員特別賞】「みんなのガーデン」から「みんなの地球(ほし)」へ 【審査員講評】 個性が際立つ植物を巧みに組み合わせ、まるでジャングルの中に入り込んだような感覚を味わえるガーデンでした。多種多様な植物を数多く使い、植物の可能性をとことん追及したカラフルでダイナミックな植栽デザインが特徴的で、その圧倒的な色彩の豊かさが多くの来園者の目を惹きつけていました。花壇の多角形を生かし、見る角度によって、構築的で造形的におもしろい植物、質感のバラエティ豊かな組み合わせ、多彩に変化する色合いなどを楽しめる点が印象的でした。遠くから見ても植物たちの存在感が力強く、厳しかった今夏を乗り越えた姿には感動を覚えます。写真を撮りたくなるシーンが随所に散りばめられ、見る人を自然と滞留させる魅力に富んだガーデンでした。 開花期を迎えていた植物 アネモネ・フペンシス‘パミナ’、カンナ‘ベンガルタイガー’、アスター‘ジンダイ’、アスクレピアス・チュベロサ、ルドベキア‘リトルヘンリー’、オキシペタラム・カエルレウム、ダリア‘ブラックナイト’、ルドベキア‘ブラックジャックゴールド’、サルビア・レウカンサ‘フェアピンク’ほか 【今回の庭づくりを振り返って】 この庭には、私自身にとっても初めての挑戦や試み、そして心からのメッセージをたくさん盛り込んでいます。単に「きれいで気持ちのよい場所」ではなく、「人に力や学び、芸術的な希望を与える場」を目指して、深い思索と実践を重ねた一年でした。ほかでは見られない多種多様で個性的な植物を組み合わせ、審査の時だけでなく常に美しい開花リレーを織り成し、絶え間なく、そして常に変化し続ける美しさを保つことができました。その風景の変化には、私が追い求めてきた“漸進的な生命の美”が宿っていました。世界中の植物を混沌と調和させながらも、日本の夏冬の気候を生き抜ける植物選び。オクラやミョウガなど、どこか懐かしい日本の「民家の庭」の情景へとつながる—そんな新しい都市生態系を示す試みでもありました。 経験値やバックグラウンドの異なるボランティアの方々と心を一つにすることも難しい課題でしたが、皆が庭を心から愛し、活き活きと動いてくださる姿に何度も胸を打たれました。ボランティアの方々と互いをリスペクトし合いながら、人間も植物も共に成長していくこのプロセスは、気候変動により、個人でガーデンを作ることがますます難しくなる現代において、とても心優しく美しい行為でもあり、人と人を結ぶ社会的・コミュニティ的な意義においても大きな希望を与える取り組みであると実感しました。 春、車イスでいらした方が、「私の庭を背景に写真を撮りたい」と車イスから立ち上がり歩いてくださったその時、植物と人との間に底知れないパワーが生まれているのを感じました。愛と思いやりをもって接すれば、植物にも人にも力が宿る。ガーデンは勝負ではない。庭を造る者の情熱や優しさ、心の美しさを映す鏡・器なのだと学びました。「あなたはその時ひとつの奇跡に気づくだろう。愛の報酬は愛であるということを」(リチャード・カールソン)
-
神奈川県

【2025年秋で見納め】67年の歴史に幕。市民が守り抜いた「生田緑地ばら苑」再整備前の最後の一般公開へ
春は約800品種、秋は約620品種のバラが咲き誇る「天空のばら苑」 1958年(昭和33年)に開苑して以来、67年もの長きにわたり、憩いの場として市民に愛されてきた「生田緑地ばら苑」は、かつて「向ヶ丘遊園」閉園の危機を乗り越え、市民の声によって守り抜かれた歴史を持っています。モダンローズや希少なアーリーモダンローズなど、約800品種3,300株のバラが植栽されている「生田緑地ばら苑」の歴史をまずは振り返ります。 神奈川県川崎市「生田緑地ばら苑」は、1927年(昭和2年)、小田原急行開通と共に、川崎市多摩区の山の上に開業した「向ヶ丘遊園地」の中に、戦争を経て開業から31年後の1958年(昭和33年)に「向ヶ丘遊園ばら苑」として開苑しました(現住所:神奈川県川崎市多摩区長尾2丁目8-1)。 ばら苑は、緩やかな坂道と階段の上に広がり、「天空のばら苑」と称されます。 春は、約800品種、約3,300株のバラが開花。秋は、四季咲き性、返り咲き性のバラを中心に、約625品種、約2,900株のバラが開花します。 2023年9月2日に放送されたテレビ東京【アド街ック天国「登戸・向ケ丘遊園」 】の Best20では、「生田緑地ばら苑」が堂々の第1位に選ばれました。番組内では、「地元のひとたちで守ったばら苑」と紹介されました。 歴史のあるばら苑だけに希少な品種が多い一方、最近では病気や老化で衰えが目立つ株も見受けられることから、川崎市は、市民ミュージアムの武蔵小杉からの移転計画と合わせ、「生田緑地ばら苑」全体の再整備を含む管理運営方針を制定中とのこと。今年度内に方針をまとめ、2026年度から整備事業が始まるため、この2025年秋の一般公開をもって、しばらくの間休苑となることが決まりました。 これを機に、市民をはじめ、近郊の人々にとっても、67年もの長きに渡って憩いの場として親しまれてきた、多摩区を象徴する「生田緑地ばら苑」の歴史と魅力について振り返ってみたいと思います。 「生田緑地ばら苑」の歴史 開苑時の時代背景 ZaQeL/Shutterstock.com 遡ること、1958年5月23日「向ヶ丘遊園ばら苑」として開苑したその年の日本国内の主な出来事を調べてみると、1958年は、第二次世界大戦後の“日本の敗戦から復活を目指す”高度急成長期を象徴する出来事がたくさんあった年でした。 3月9日:山口県下関市と福岡県北九州市を結ぶ海底トンネル「関門トンネル」が開通。 4月5日:長嶋茂雄プロ野球デビュー。 11月1日:特急「こだま」が運転開始。 11月27日:皇太子明仁親王(現・上皇様)と正田美智子様(現・上皇后様)のご婚約発表。 12月1日:新1万円札(聖徳太子)発行。 12月23日:東京タワー完成。 12月27日:国民健康保険法公布。他。 この年の出来事を振り返ると、日本国内だけでもこんなにさまざまなことがあり、時代が大きく新しい時代に移行している様子が伺えます。 1977(昭和52)年に、朝日新聞社より寄贈された「フローラの像」のある「ロイヤルコーナー」。 「ばら苑」ができる前の「向ヶ丘遊園」でも、平和や豊かさを象徴する娯楽施設が次々と創られていました。「動物園」(1950年)、「プール」及び、「天然スケート場」、遊園地の入り口から園内山頂を結ぶ関東初の「空中ケーブルカー」(1951年)、「鑑賞用温室(オランジェリー)」(1955年)などが設置されました。 そしていよいよ、日本では明治維新以後「文明の花」の象徴とされ、世界大戦以後は「平和の花」の象徴となったバラが、「向ヶ丘遊園ばら苑」に集められ、1958年5月23日に開苑の日を迎えました。 開苑間もない5月27日と翌年の1周年記念には、秩父宮妃殿下がご来訪されました。 開苑時に携わった人々 「向ヶ丘遊園ばら苑」開苑には、当時の園芸やバラの専門家たちが携わっていました。 ばら苑の設計には、東京大学農学部園芸学教授の横山光雄氏、ばら苑の植栽と管理には、新宿御苑苑長の福羽発三氏、バラの品種については、海外の留学経験もあり、海外のバラに関する書物を日本に紹介し、バラの普及に貢献し、日本に於ける初めてのバラの会「大日本薔薇協会」{1927(昭和2)年3月25日設立}や、「ひらかた大バラ園」(現・ひらかたパーク・ローズガーデン){1955(昭和30)年開園}の誕生に深く携わった岡本勘治郎氏などが、「向ヶ丘遊園ばら苑」の誕生にも深く携わっていました。 戦中~戦後と、園芸やバラ栽培を続けることが困難な時代に、日本での園芸文化やバラ文化を守りぬいた当時の専門家達の知識と経験が、「向ヶ丘遊園ばら苑」の誕生に注がれたことを思うと感慨深いものがあります。 開苑後の様子 「向ヶ丘遊園ばら苑」の開苑後は、1963(昭和38)年に、第1回フラワーショー「日本の花・世界の花」ほか、さまざまな花に関するイベントが開催されるなど、しばらくの間、遊園地と共に大変人気を博しました。 1990年代のばら苑の様子。 1977(昭和52)年に、朝日新聞社より寄贈された「フローラの像」のある「ロイヤルコーナー」。こちらには、‘クイーン・エリザベス’や‘プリンセス・アイコ’、‘プリンセス・ミチコ’ほか、皇室や世界のロイヤルにちなんだバラが今も植栽されています。 1990年代のばら苑の様子。 当時は、水の豊富なばら苑として、噴水や水面に映るバラの美しい風景を楽しむことができました。 「向ヶ丘遊園」の閉園と「ばら苑」のその後 長い間、人々に愛された「向ヶ丘遊園」でしたが、時代の流れと共に、他の大型テーマパークの台頭などにより、徐々に来園者数に影響が見られるようになりました。そして2002年3月31日に、「向ヶ丘遊園」は惜しまれながら閉園となりました。 「向ヶ丘遊園」は閉園となりましたが「ばら苑」の存続を強く希望する市民の声を受け、川崎市が「ばら苑」とその周辺の土地(7.4ha)を購入し、「生田緑地ばら苑」として存続することになりました。 ボランティアの作業風景。 2005年には、「生田緑地ばら苑ボランティアの会」が発足し、20年間に渡りバラの育成管理や苑の維持管理などに協力してきました。また、春と秋の一般公開時には、ボランティアによる苑内ガイドツアーなども行われました。 続けて2007年からは、日本ばら会による講習が始まり、2008年には、ばら苑開苑50周年記念として「イングリッシュ・ローズコーナー」が増設されました。 「イングリッシュ・ローズコーナー」に咲く‘リッチフィールド・エンジェル’(S)(2006年、英、D・オースチン作出) ‘アン・ブリン’(S)(1999年、英、D・オースチン作出) 2011年頃には、「オールドローズガーデン」が増設されましたが、このエリアは、小田急向ヶ丘遊園園芸部に入社され、1977年から約6年間「向ヶ丘遊園ばら苑」の責任者を務められた村田晴夫さんと、ボランティアが中心となって創り上げたものでした。 春の「オールドローズガーデン」の様子。 木々にボランティアが誘引したランブラーローズ‘ポールズ・ヒマラヤン・ムスク’の様子。 左/‘ピース’(HT)(1935年、仏、フランシス・メイアン作出)中/‘ピース’の枝替わりとされる‘シカゴ・ピース’(HT)(1962年、米、ジョンストン発見)右/‘ピース’の枝替わりとされる‘クローネンブルク’(別名:‘フレーミング・ピース’)(HT)(1965年、英、マグレガー発見) 苑内には、モダンローズを中心に、野生種のバラやオールドガーデンローズも見られます。 また香りのバラや、殿堂入りのバラも紹介されています。特に、アーリーモダンローズ*の希少種が植栽されていることも、こちらのばら苑の魅力の一つです。 *アーリーモダンローズとは、モダンローズ第1号‘ラ・フランス’が作出された1867年から、約50年の間に誕生したモダンローズの総称とされています。 モダンローズ第1号‘ラ・フランス’(HT)(1867年、仏、ギヨー作出) アーリーモダンローズの‘マダム・エドワール・エリオ’(HT)(1913年、仏、ペルネ・デュシェ作出) 左/アーリーモダンローズの‘オフェリア’(HT)(1912年、英、ポール作出)右/‘オフェリアの枝替わりとされる’マダム・バタフライ’(HT)(1918年、米、ヒル発見) ぜひ、ばら苑にいらした際は、これらの古い時代のバラを探して、それらのバラが誕生した時代背景に想いを巡らせてみてください。バラの美しさだけでなく、バラの背景に広がる物語が見えてくるかもしれません。 バラ咲く季節に開催されたイベントの思い出 2024年10月20日に行われた「近接バラ園とのミニ・シンポジウム」の様子。 昨年2024年の秋の一般公開時には、「川崎市政100周年及び全国都市緑化かわさきフェア記念」のイベントがさまざまに企画・実施され、そのなかでも、2024年10月20日には「生田緑地ばら苑」にて「近接バラ園とのミニ・シンポジウム」が開催されました。 登壇者には、神代植物公園園長の松井映樹氏、京成バラ園副園長の佐々木猛氏、練馬区立四季の香ローズガーデンガーデナーの小河紀子氏、横浜イングリッシュガーデンガーデナーの黒田智史氏、オブザーバーとしてバラの育成に取り組んでいらっしゃる企業から住友化学園芸(現KINCHO園芸)の牛迫正秀氏、そして会場である川崎生田緑地ばら苑苑長の有賀眞由美氏。私は司会進行役を仰せつかり、シンポジウムではバラに関する興味深い意見が交換されました。 2024年11月3日には、「ブルガリアデイ」が開催され、駐日ブルガリア共和国マリエタ・アラバジエヴァ大使、ブルガリア共和国大使館文化部のクツアロヴァ・エレナさんがいらっしゃり、川崎市藤倉茂起副市長がお出迎えされました。大使からは温かいご挨拶を賜り、クツアロヴァ・エレナさんによる「ブルガリア文化とバラ散歩」と題したトークショーがありました。その後、ブルガリアンダンスの公演、最後は皆で踊り親交を深める貴重なひとときとなりました。 2024年11月4日は、日本ばら会講師によるトークショー、演奏やワークショップが開催され、私も「いにしえから続くバラと人との物語」と題したトークショーをさせていただきました。 2025年秋バラが咲く苑内で11/1(土)~11/3(祝・月)「ファイナルイベント」開催 今年2025年秋の一般公開は、現存の「生田緑地ばら苑」の最後の一般公開となります。 開苑期間:10月16日(木)~11月3日(月・祝日)*期間中休苑日無し開苑時間:平日は10時~15時30分、 土、日、祝日は9時~15時30分*最終入苑時間はいずれも14時30分まで アクセスなど詳細は、生田緑地ばら苑公式HPをご覧ください。 https://www.ikuta-rose.jp/ 11/1(土)~11/3(祝・月)のファイナルイベント開催時には、ばら苑コンサートやトークセッション、園芸講習会が行われるほか、11月2日(日)12時30分~13時30分には、元木はるみと「Garden Story」倉重香理編集長による「スペシャルトークショー」を開催し、バラの歴史や日本で親しまれるバラ、そして未来像などをお話しする予定です。会場は芝生広場、雨天時は屋内。事前申し込み不要。ご参加費無料。 現存のばら苑での最後のイベントになりますので、ぜひお越しください。 今回、この記事をまとめるうえで、『ばら苑物語』(企画発行:生田緑地ばら苑ボランティア会)が大変参考になりました。昨年2024年10月、ばら苑が変化の時を迎える前に、記念誌として、生田緑地ばら苑ボランティア会によって発行されました。 これから、しばらくの間、「生田緑地ばら苑」は再整備のために休苑となりますが、ばら苑物語は、きっとこれからも続いていくことでしょう。 バラが咲き誇る、よりよい未来を心より願っております。
-
フランス

【一度は行きたい】花好きを魅了するフランス「シュノンソー城」王妃たちの庭園を巡る旅
フランス王妃たちの庭園、花々が溢れるシュノンソー城 フランスの中央部を流れるロワール川の支流、シェール川のほとりに位置するルネサンス様式の優美な古城シュノンソー。古くは王室の居城であり、歴代女城主によって守られてきたことから、貴婦人たちの城とも呼ばれてきました。 フランス国王アンリ2世の王妃カトリーヌ・ド・メディシスと美貌で知られた寵妃ディアーヌ・ド・ポワティエのこの城をめぐる確執は有名です。そして現在のシュノンソー城では、歴史的な面影に新たな見どころが加わり、さらに魅力的になった庭園が見逃せません。 シェール川の水景を生かしたディアーヌの庭 ディアーヌの庭全景。 16世紀中葉、アンリ2世は最愛の寵妃ディアーヌ・ド・ポワティエに、王室所有であったシュノンソー城を与えます。ディアーヌはルネサンス様式の城をさらに整備し、美しい庭園をつくらせました。洪水対策として川面よりも高い位置につくられ、石壁で囲まれた構造を当時のままに残す12,000㎡ほどの「ディアーヌの庭」には、穏やかなシェール川の水景を生かした景観設計がなされています。外の景観を取り入れ、建物と調和したエレガントな庭園です。 ディアーヌの庭のポイントにはスタンダード仕立てにしたムクゲなども使われている。中央は芝生とミネラル素材で形づくられたアラベスク模様。 城から庭を見下ろした時に最もよく映える、芝生の上に描かれた端正な幾何学模様は、19~20世紀の著名な造園家アシール・デュシェンヌ(1866-1947)によるものです。 カトリーヌの庭 カトリーヌの庭。バラやラベンダーが使われたクラシカルで優雅なフォーマル・ガーデン。 城の建物を挟んで反対側には、アンリ2世が逝去するとすぐ、ディアーヌからシュノンソー城を奪回した王妃カトリーヌ・ド・メディシスがつくらせた「カトリーヌの庭」があります。かつては川向こうまで広がっていた庭園ですが、現在残る部分は約5,500㎡と、こぢんまりとした親密な雰囲気のあるルネサンスの整形式庭園です。 カトリーヌの庭正面のシェール川の向こう側にも森が広がる。 イタリアの庭園芸術の流れを汲んで、城の建築と一体化したシンメトリーな整形式のデザインは、城の景観を見事に引き立てています。庭園に動きを与える中央の噴水を囲み、リズムよく配置された壺などの彫刻を用いた装飾も、やはりイタリアの影響を受けたもの。 カトリーヌの庭から見たシュノンソー城。ロワールの古城の中でもひときわ優雅。 こうした整形式庭園の構成要素は、17世紀のフランス絶対王政の時代に、ル・ノートルによって完成されるフランス整形式庭園に引き継がれていきます。 スタンダード仕立てのバラや、ラベンダーなどが多用された植栽には、シュノンソー城らしい女性的でロマンチックな雰囲気が醸し出されているように感じます。 城内の窓から見た、穏やかに流れるシェール川と、川に面したカトリーヌの庭。城の周りは御伽話の世界にトリップしそうな、こんもりとした森に囲まれています。 ラッセル・ページの庭 ラッセル・ページ記念庭園。シンプルな洗練された緑の空間に、ラランヌの羊の彫刻が点在してユーモラス。 カトリーヌの庭から少し離れると、かつてカトリーヌが動物小屋や鳥小屋を作らせていた、現在はさまざまな木々が主体となった「緑の庭」があります。その先には、20世紀を代表するイギリスの造園家ラッセル・ページ(1906–1985)へのオマージュの庭があります。 全体にシンプルなシンメトリー構成のラッセル・ページの庭。庭を囲む壁に沿って、イギリス風のボーダー植栽が。 現代の造園家によって十数年前につくられたもので、城の建築に隣接した歴史的庭園空間とは異なり、モダンな美意識が感じられる、グッとシンプルに洗練された庭です。ページのモットーであった「自然と建築の調和」に則りつつ、シンプルな緑を生かした構成に、フランスの彫刻家フランソワ=グザビエ・ラランヌによるアート作品が彩りを加え、現代アートと庭園の融合を楽しめる空間でもあります。 フローリストの庭 フローリストの庭。 さらに、現在のシュノンソーの城と庭園の新たな魅力になっているのが「フローリストの庭」です。かつてルネサンス期には、実用のためのハーブ園やポタジェ(菜園)はあったにしても、 花々はあくまでも庭園の装飾要素、またはポタジェの一部であったに過ぎなかったようです。 訪れた9月はダリアが盛り。城内のアレンジメントの花々が花畑でも見られるので、散策するのもとても楽しい。 現在のシュノンソー城のポタジェはまさに「花のポタジェ」で、敷地内のレストランでも利用されるさまざまな栽培野菜とともに、リンゴの木やバラで仕切られた12区画の植栽エリアは、城内のフラワーアレンジメントに切り花として使うための季節の花々を提供する花畑になっています。ここで栽培された食用花は敷地内のレストランのシェフが料理に利用することもあれば、フローリストたちが野菜をアレンジに使うこともあり、さらなるクリエイティビティの可能性に貢献する庭にもなっているといいます。 庭の中には19世紀の農家を移築したフローリストのアトリエがあります。ここではワークショップなども行われるとのこと。 訪れた時には盛りは過ぎていてあまり目立っていませんでしたが、フランスのポタジェの野菜の定番であるアーティチョークは、じつはカトリーヌがフランスにもたらしたものの1つだそうで、そうした歴史的背景も考慮した城内のフラワーアレンジメントによく登場するのだとか。 フラワーガーデンと城内を飾るアレンジメント 城内のフラワーアレンジメントはどれも素敵で、この部屋ではランとケイトウ、ヨウシュヤマゴボウ、枝垂れるアマランサスなど、花器からこぼれるようなアレンジが。ヒストリカルな室内の雰囲気をさらに盛り上げている。 「フローリストの庭」が作られたのは2015年頃からと近年のことで、シュノンソー城は、ロワールの古城の中では唯一、自前のフローリストチームを抱える城でもあります。ヨーロッパ・ジュニア・チャンピオンで国家優秀職人賞を受賞した経歴をもつフローリスト、ジャン=フランソワ・ブーシェ氏率いる3名のフローリストチームが、城内19の各部屋を飾るフラワーアレンジメントを毎週作り変えています。 この時期、フローリストの庭で煙のような穂をつけていたグラス類の隣には、赤や黄色のケイトウやカンナも開花。 フローリストの庭では、毎年6万本以上の切り花用の植物が栽培されていますが、材料としてはそれだけではとても足りないそうで、毎朝アレンジメントの状態をチェックして、花材の発注をしたり、市場が休みの月曜の朝は、自然の中にグラス類などの花材を探しに出るのだとか。ブーシェ氏によれば、野生の素材はアレンジに命を与える点が素晴らしいのだということですが、これも自然に囲まれた城という環境ならではの贅沢でしょうか。 城内のアレンジメントは、シンメトリーを基本とした優雅でゴージャス、非常にオーナメンタルで、家具類やタペストリー、美術品のコレクションが飾られたルネサンスの城の各部屋に華を添え、次はどんなデコレーションに出会えるかと、歩を進めるのが楽しくなってくるほど。 また、非常に華やかなアレンジの中にも、シャンペトルな自然の雰囲気、季節感が強く感じられるのは、フローリストたちの美意識に加えて、庭や近隣の自然に結びついた素材の力も大きいのかもしれません。 大輪のダリアにヨウシュヤマゴボウが動きを添えるアレンジメント。 城の中も外も、見どころが尽きないシュノンソー城。オランジュリーはレストランとサロン・ド・テになっており、食事もゆっくりできます。花々に囲まれ、昔日の貴婦人になった気分で、一日ゆったりと過ごしてみたい場所です。 庭園内のかつてのオランジュリーはレストランとサロン・ド・テになっています。優雅な気分で食事やお茶を楽しめます。
-
神奈川県

【秋バラが本格的に開花!】煌めくクリスマスの雰囲気を先取り「横浜イングリッシュガーデ…PR
秋バラが次々開花し、色濃く輝くオータム・ガーデン 秋バラが満開の横浜イングリッシュガーデン(2025年10月下旬)。 横浜イングリッシュガーデンでは、今年も10月中旬から秋バラが見頃を迎え、11月になってさらに開花が増えていきます。日毎に涼しくなる気候の下でゆっくりと花開く秋バラは、春バラと比べ色合いが鮮明で、ふっくらとした大輪の花を咲かせる傾向があります。 左上から時計回りに/ラ・マリエ/イージー・ダズ・イット/ニュー・ウェーブ/アンゲリカ/サザンホープ/シスター・エリザベス/ベルエポックフェアリー・ボタン 秋バラが満開の横浜イングリッシュガーデン(2024年11月上旬)。 花数こそ春と比べて少なくなるものの、一輪一輪の品質が高く重厚感があるのは秋ならではの魅力です。病害虫の発生しやすい日本の気候条件の下で夏を越し、秋バラを美しく咲かせるには、適切な管理が必要。横浜イングリッシュガーデンが自信を持ってお届けする美しい秋バラを、じっくり見て香りを嗅いで、堪能してください。 秋バラが満開の横浜イングリッシュガーデン(2024年11月)。 ⚫︎横浜イングリッシュガーデンのインスタグラム yokohama_eg_official や各種SNSでは、河合伸志さんの品種解説が書き添えられた見頃の花や庭の様子も毎日発信中! バラのほかにも、秋らしい植栽がいっぱいです。22品種ものコスモスやシュウメイギク、穂が美しいオーナメンタル・グラス、カラーリーフのコリウスなど、秋を代表するさまざまな植物が競演中。夕日に長く伸びる花影さえも目を見張る美しさです。 11月4日(火)からは一年を締めくくる装飾イベント「クリスマス・ディスプレイ」にお色直し つるバラの緑が森のような雰囲気を演出するローズトンネルの下に、ゴージャスなツリーやクリスマスモチーフなどが飾られ、ガゼボもクリスマス色に。芝生広場ではソリのフォトスポットなどが登場し、園内が煌めく「クリスマス・ディスプレイ」2025年の様子。 2025年11月4日(火)~12月25日(木)は、イベント装飾「クリスマス・ディスプレイ」に園内はお色直し。今年は8mのモミの木のクリスマスツリーも登場し、季節を先取りしてクリスマスの雰囲気をいち早く楽しめます。11月中旬ごろまで咲き続ける多数の秋バラとともに、煌めくクリスマスの雰囲気に満たされた期間限定の素敵なガーデンを散策しましょう! 秋色の植物が大集合! 第13回ハンギングバスケットコンテスト 2023年のコンテスト展示の様子。 11月9日まで出展作品募集中 毎年11月に開催するハンギングバスケットコンテストの開催は、2025年で第13回目。全国から個性の光る魅力的なハンギングバスケットの作品の数々が一同に会し、その技術力とセンスを競います。多数の作品がずらりと並ぶ、見応えのある展示をお見逃しなく。*11月9日(日)までエントリー作品を募集中。詳しくは、HPをご覧ください。 「第13回 横浜イングリッシュガーデン ハンギングバスケットコンテスト」 展示期間:11月29日(土) ~12月7日(日) 10:00~18:00 ※最終日は15時までコンテストの種類 :① 壁掛けタイプ(募集数/80作品)作品テーマ「冬を彩るハンギングバスケット」② 吊り下げタイプ(募集数/20作品)作品テーマ「街を彩るハンギングバスケット」表彰式:12月7日(日) 13:30開催予定主催 :(一社)日本ハンギングバスケット協会 神奈川支部、横浜イングリッシュガーデン ハロウィンの起源を知ってお祭りを楽しもう 初夏は無数のバラが咲いていたローズトンネルの下が、ハロウィン・ディスプレイで賑やかな雰囲気に一変する秋の横浜イングリッシュガーデン(2025年)。 日本でも毎年恒例のイベントとなった10月31日のハロウィン(Halloween)は、キリスト教の諸聖人に祈りを捧げる祝日、11月1日の「諸聖人の日」「万聖節」(All Hallo)の前夜祭(All Hallo Eve)。先祖の霊をお迎えするとともに悪霊を追い払い、秋の収穫を祝うというヨーロッパが発祥のお祭りです。日本では「仮装の日」というイメージがありますが、本来の意味は「秋の彼岸」に似ているかもしれませんね。 横浜イングリッシュガーデンのハロウィン・ディスプレイの様子(2025年)。 ハロウィンの起源は、古代ケルトのドルイド教で行われていた「サウィン祭」といわれています。古代ケルトの暦では新年を11月1日とし、前日にあたる10月31日の大晦日の夜に先祖の霊が帰ってくると信じられていました。ところが、悪霊も一緒にやって来て、収穫した作物に悪影響を与えたり、子どもをさらうなど悪事をはたらくといわれていたのです。そこで人間は、悪霊から身を守るために仮面を被ったり、仮装をして悪霊の仲間に扮し、魔除けの焚き火をしていたといわれます。これがハロウィンにお化けの仮装をする由来です。 ハロウィンに欠かせない「ジャック・オー・ランタン」とは 横浜イングリッシュガーデンのハロウィン・ディスプレイの様子(2025年)。 ハロウィンで欠かせないのがシンボルとして使われるカボチャ。目・口・鼻の形をくり抜いて中にキャンドルを灯してランタンに仕立てたものを「ジャック・オー・ランタン」と呼びますが、そのジャックとは、アイルランドの物語に登場する男性の名前です。 横浜イングリッシュガーデンのハロウィン・ディスプレイの様子(2025年)。 ジャックは生前、悪いことを繰り返し、魂を取ろうとやってきた悪魔さえも騙すような行為をしたことから、地獄に堕ちることすらできず、死後もランタンに火を灯して闇夜をさまよい続けたという物語に由来します。愉快で可愛い印象のオバケカボチャですが、そのじつ業の深い人間の姿だったというわけです。ジャックはいまだ闇夜をさまよい続けているのでしょうか…。 写真撮影が楽しい! と毎年好評の「ハロウィン・ディスプレイ」 横浜イングリッシュガーデンのハロウィン・ディスプレイの様子(2025年)。 年々、素敵な仮装をした来園者も増え、楽しさも倍増している恒例のハロウィンをテーマとしたディスプレイは、10月31日(金)まで開催。今年は、秋の植物とともにたくさんのカボチャや大小さまざまなジャック・オー・ランタンを並べ、オレンジを基調とした明るくカラフルなフォトスポットが登場! 秋の植物とハロウィンのアイテムがコラボする横浜イングリッシュガーデン(2025年)。 また、芝地にはセメタリーガーデンをイメージした、モノクロのシックなディスプレイなど、ハロウィンとガーデンの植物がコラボレーションしています。賑やかでワクワクする秋の庭演出の数々を、ぜひ散策をしながら見つけてください。カラフルなコリウスや美しい穂を揺らすグラス類など、秋の庭演出も参考になりますよ。 芝生のエリアもハロウィン・ディスプレイ。周囲の木々のフォルムの違いもハロウィンの雰囲気を盛り上げています。 お見逃しなく!(2025年) 園内に入ってすぐに驚きがあり、園内のあちこちに映えるフォトスポットがあります。秋の植物も彩りに加わる、この時期ならではのガーデン散策をぜひお楽しみください。 10月24日(金)〜26日(日)3日間限定のライトアップイベント! 輝く「ハロウィンナイト」開催 ※本年は終了しました 期間限定公開の、横浜イングリッシュガーデン「ハロウィンナイト」の様子(2025年テスト点灯時)。 10月24日(金)〜26日(日)の3日間限定で、ハロウィン装飾のライトアップを楽しめる夜間イベント「ハロウィンナイト」を実施します! 通常、日没後の園内はご覧いただけませんが、ハロウィン装飾のランタンに明かりを灯し、営業時間を20時まで延長して開園いたします。夕闇に浮かび上がる数々の照明でハロウィンらしさを演出します。普段は味わえない、幻想的な夜のガーデンをお楽しみください。 【「ハロウィンナイト」イベント概要】 期間限定公開の、横浜イングリッシュガーデン「ハロウィンナイト」は、秋に見頃の植物や咲き始めた秋バラのライトアップも見どころ(2025年テスト点灯時)。 開催日:2025年10月24日(金)・25日(土)・26日(日)開催時間:17:30~20:00(最終入園19:30)イベント入園料:大人1,000円/小中学生500円/未就学児無料 ●10/24~26の「ハロウィンナイト」イベントチケットは、10月6日午前10時からネット予約システム(楽天・アソビュー)にて販売中。※当園窓口での販売予定はございません。ご入園前に電子チケットをお求めください。 ※「ハロウィンナイト」開催日は、通常営業は17:00(最終入園16:30)で終了します。当日の通常営業時間にご入園された場合は、「ハロウィンナイト」イベントチケットをお求めの上、17:30以降に再度ご入場ください。※悪天候の場合は、状況により中止または順延となる場合がございます。当日公式HPにてご確認ください。※「ハロウィンナイト」開催日当日は、無料送迎バスを延長して運行します。時刻表等詳細は、公式HPにてご確認ください。 期間限定公開の、横浜イングリッシュガーデン「ハロウィンナイト」の様子(2025年テスト点灯時)。 芝生が広がるエリアも周囲の木々がハロウィンナイトの雰囲気を盛り上げます(2023年)。
-
フランス

【フランスのバラの楽園へ】アンドレ・エヴが遺した「香りのナチュラルガーデン」を訪ねて
アンドレ・エヴのバラの庭へ アンドレ・エヴ(André Eve 1931-2015年)はフランスの著名なバラの育種家です。数々の名花を作出し、またモダンローズの全盛だった1980年代から、現在に続くオールドローズの人気復興に貢献した人物としても知られます。彼が作り育てたプライベートなバラの庭、また現在も後継者たちが見事な育種を行うバラのナーセリー、アンドレ・エヴ社の育種場兼展示ローズガーデンなどの素晴らしいバラの庭は、フランスのロワレ地方にあります。 ロワレのバラ街道。loskutnikov/Shutterstock.com この地域は、バラの生産が盛んであると同時に、見所の多い植物園や庭園を擁する土地であることを生かし、近年には「ロワレのバラ街道」なる、フランスのバラと庭園を訪ねる観光ルートが立ち上げられているほどです。 バラの最盛期である6月初めに、このバラの庭を訪れる幸運に恵まれました。 1969年発表の‘シルヴィ・ヴァンタン’。Alexandre Prevot/Shutterstock.com アンドレ・エヴは、ベルサイユ園芸学校で造園を学んだのち、造園家として活躍するうちにバラ園芸に魅せられて育種家となります。彼が作出した最初のバラは、1969年発表の‘シルヴィ・ヴァンタン’でした。70年代から80年代には、どちらかというと派手めなモダンローズが流行の傾向にありましたが、そうした中でオールドローズの魅力をいち早く再発見したのも彼でした。 バラと宿根草のナチュラル・ローズガーデン アンドレ・エヴのナーセリーは、育種家ジェローム・ラトゥーらに引き継がれ、現在もフランスきってのバラのナーセリーであり、メゾン・ディオールのためのバラ‘ジャルダン・ド・グランヴィル’などの名作を次々に作出し続けています。 2016年に社屋を移転したシリュール=オ=ボワの地では、創設者のエスプリを大切に作庭された「アンドレ・エヴの庭(Le jardin André Eve ® )」で、100近いオリジナル品種のバラとともに、オールドローズをはじめとするバラのコレクションが、宿根草や灌木類、小型の果樹など、バラの「コンパニオン」と呼ばれる草花とともに植え込まれ、洗練されたナチュラル感溢れるバラの風景を作り出しています。 バラを活かす庭デザインの秘訣 白樺などナチュラル素材を仕切りに用いて自然な雰囲気を心がけたボーダー植栽。 さまざまな姿形で咲き誇るバラたちで賑やかな庭に入って気がつくのは、まずその香りです。バラの季節の雨上がりの庭、一歩足を踏み入れた途端に、繊細なバラの香りに包まれ、さらに園路を散策しながら一つひとつのバラの香りを呼吸すれば、もうそれは至福の心持ちに。ようやく我に返って、バラ栽培に重要な日当たりを確保するため、敢えて大木は避けた空間がのびのびと広がっているのを気持ちよく眺めます。 バラと宿根草、灌木類がミックスされた植栽がポイント。 美しいばかりでなく、無農薬の自然な栽培に向く耐病性・耐久性の高いバラを目指したアンドレ・エヴの庭は、デザインにも洗練された素朴さ、ナチュラル志向が表れています。構成はフォーマルな左右対称ではない自然風。よくイギリス風のコテージガーデンに見られるような、きれいに刈り込まれた芝生のライン、または白樺などの木材で区切られたバラと宿根草の植栽の間には、緑地になった曲線の園路が設けられ、ゆったりと散策しながら間近で植栽された植物を観察できます。 パーゴラも丸太を利用し、全体のトーンをナチュラルに統一。 また、丸太のパーゴラやアーチ、壁面に盛大に這い上るつるバラの姿がそれは見事です。 それぞれのバラの個性を魅せつつ、ヒューケラやホスタ、デルフィニウムやシャクヤクなど、バラと共存しやすいコンパニオン・プランツを組み合わせて、全体として自然な風景が創り出されているのが大きな魅力の1つ。庭づくりの参考になる見所が随所にありました。 庭を案内してくださったアンドレ・エヴ社のドニーズ・フランソワさんによると、バラを庭に植え風景を創るときのポイントの1つは、3本以上同じ品種をまとめて植えること。ボリュームを出すことによって、そのバラの存在感が遺憾なく発揮される、その目安が3本以上なのだそう。 芝地に緩やかな曲線をベースに配置された植栽グループ。 1本ずつぽつんぽつんと植えるのでは、この存在感が出にくいのです。また、多少空間がありすぎるように見えても、成長は早いので、それぞれに必要な間隔はあらかじめ空けておくこと、アーチなどに這わせる際の注意点など、具体的にバラを庭に取り込むために役立つアドバイスが満載です。 「結婚の部屋」バラ育種の現場 「結婚の部屋」ビニールハウスで、案内してくださったフランソワさん。 さらに興味深かったのが、実際に新品種開発のための交配を行っている場所の見学です。そこは、将来の新品種の父と母となるべく選出されたバラのポットが並ぶ、フランス語で「結婚の部屋」と呼ばれるビニールハウスです。 不純物が混じらないように、あらかじめ父となるバラの開花前に雄しべを取っておき、母となるバラの雌しべの開花の準備ができたところで人工交配が行われます。秋まで待って、成熟した実から種子を採取し、12月まで冷蔵ののち播種して隣の「育児所」ビニールハウスで栽培していくという、とてもベーシックな方法で育種が行われています。 「育児所」となるビニールハウスの中。札に示されている写真のバラを両親として生まれた新種のバラたちの花姿を見比べると、色も形も性質もさまざまあって興味深い。 面白いのはその子どもたち。ひとつとして同じ姿形がない、じつに変化に富んだバラが生まれるのです。育種家は、それぞれのバラの姿形や香り、花数や返り咲き性の高さなどを日々つぶさに観察し、新品種候補のバラが選ばれます。 同じ両親を持つバラの子どもたち。見た目からそれぞれに全く違うのが面白い 。 現代の新品種作出時の最重要項目としては、姿形や香り、返り咲き性もさることながら、強い耐病性や乾燥への耐性などが欠かせません。農薬などを使わない自然栽培に向き、天候不順にも適応できる耐久性を併せ持ったバラが求められるのは、現在の庭園の在り方の流れを反映しているといえるでしょう。 庭に隣接した野外の販売コーナー。 3万粒ほどの種子を播き、9年ほどをかけた栽培ののちに、実際に新品種としてデビューするのは、年間に3~5点とごく僅か。自然の驚異と育種家のバラへの情熱と深い造詣に裏打ちされた日々の努力、生み出される新品種のバラそれぞれの姿が、ますます魅力的に見えてきます。 ガーデニングをしていても、バラは敷居が高い、難しいと感じている方は結構いらっしゃるのではないかと思います。じつは私もその一人なのですが、やっぱり挑戦してみたいと思わせられて、カタログを眺めてはあれこれ想像の翼を広げる日々です。
-
大阪府

素敵な発見がたくさん! 園芸ショップ探訪41 大阪「NOAH(ノア)」
園芸を楽しむすべての人のためにメーカーとの間を橋渡し 入り口に立ててある、木製の小さな看板が目印。 大阪花き園芸地方卸売市場など植物関連の業者が集まるエリアに位置する、ガーデニング資材やナチュラル雑貨の問屋「NOAH(ノア)」。センスのよいものが揃い、園芸やフラワー関係のバイヤー、ガーデンまたはインテリアのコーディネーターなど、さまざまな業界の人たちに頼りにされている問屋です。オープンから20年経った今年、多くの声に応えられるようにと、一般の方々も買えるようになりました。 店舗の造りは倉庫そのもの。約300坪もの広大なフロアに1万点以上ものアイテムが並ぶさまに圧倒されます。 商品はメーカーごとに並んでおり、多様な商品が次から次へと展開されていきます。「取引メーカー数は200社ほどあります。さまざまな要望に応えるために、雰囲気・好みに偏りなくあらゆるテイストのものを置くように、多くの業者から仕入れています」と代表の山野井良夫さん。 以前、ガーデンストーリーでベランダガーデンの演出の記事にご登場くださった奥様のRIKAさんとともに、ガーデニングのショップ『みどりの雑貨屋』を兵庫や大阪、京都に5店舗も展開している山野井さん。 現在のRIKAさんのベランダガーデン。ほとんどの鉢はNOAHで入手できる。 RIKAさんがコーディネートするこの店舗は一般の方向けで、ナチュラルなコーディネートに定評があります。「『みどりの雑貨屋』で扱うアイテムは、当然ながらカラー(雰囲気)が統一されています。それ以外の雰囲気のものが欲しいという方のために、NOAHに一般の方にも買えるようなシステムを設けたんです」と山野井さん。 基本的に各メーカーの担当者が自分の商品をディスプレイしており、ブースごとに雰囲気は異なります。「私たちが行うといつも同じようになってしまうので、可能な限りメーカーさんそれぞれに飾ってもらっています。これならイチオシや旬の商品が分かりやすく陳列され、いつも新鮮な売り場になるからです」。そのほか什器も多様で、パーゴラにカゴを吊したり、ポテトボックスを積んで鉢を並べたりと、飽きがこないよう展示にもこだわっています。 あんなものも、こんなものも!広い店内をフロアごとにご紹介 多数の商品が所狭しと並ぶ店内から、一部のコーナーをピックアップしてご紹介します。一般店舗とは異なる問屋の雰囲気も楽しんで。 【1F】 1Fは、基本的にガラスや陶器など、割れ物の鉢や雑貨、重量感のある大物がメイン。ガーデニングをするのに、あると嬉しいアイテム(土や肥料、ペイント材、リボンなど)も揃っています。 ■寄せ植え向きコンテナ グレイッシュなカラーの鉢が今人気。どんな植物とも相性抜群。 ■素焼き等コンテナ 昔ながらのスタンダードな素焼き鉢もたくさん。 ■大型コンテナ ビックリするほど大きなコンテナも。インテリアにこだわりのある男性に人気。 ■コンテナ(素材いろいろ) 軽くて便利な樹脂製の器。観葉植物や多肉植物にもピッタリ。 ロングヒットのモスポット。什器として使われているポテトボックスとの相性抜群。 ■インテリア用コンテナ(陶器タイプ) どんな空間にも馴染みやすいモノトーンの器は、ショップやレストランなどで人気。 ■ミニコンテナ コーヒーのテイクアウト容器形のミニコンテナ(上)と、動物の顔形の陶器のミニコンテナ(下)。遊び心あふれるアイテムもずらり。 ■インテリア用花器 落ち着きのある色・質感の花器。オーナメントとして飾ることもできるデザイン。 ■ガラス瓶 空間に透明感ときらめきを添えてくれるガラス瓶。見ているだけで楽しい。 ■ガーデニング雑貨 人気のオーナメントやアイアンフェンスなども充実。 ■インテリア雑貨 室内に素敵な彩りを添えてくれるアイテムもいっぱい。 ■カゴ類 籐製に見えるバスケットは、じつはポリプロピレン・ポリエチレン製。寄せ植えの器としても活躍してくれる。 アルファベットパーツ(左)やマクラメ(右)など、空間づくりを楽しくしてくれるアイテムも充実。 ナチュラルな仕上がりが魅力の“ミルクペイント”など、人気の塗料も販売。 【2F】 1Fの半分ほどのスペースの上に、2Fの売り場が設けられています。ここには比較的軽いアイテムとガーデン雑貨類が並べられています。 ■ガーデン雑貨 シーンに味わいを添えてくれる、ブリキなどの雑貨類。庭に挿したり、アーチにかけたりと、使い方いろいろ。 ■軽量コンテナ 軽量で耐久性抜群のグラスファイバーポット。デザインもエレガント。 気持ちがほっこりと和むような、ユニークなデザインのものも。 ■流木 なにかと便利な流木。サイズはいろいろ。 ■アンティーク イギリス・フランスのアンティークアイテムが2F奥のエリアに並ぶ。庭のシーンの雰囲気を高めるのにぴったり。 【SALEコーナーとSDGsコーナー】 NOAHでは地球環境・資源に配慮し、半端もの、型落ち、壊れなどの訳アリ商品をお得な価格で積極的に販売しています。販売タイプは2種類で、「SALEコーナー」は、各メーカーが型落ちや製造終了のものを、各ブースで販売。それに対し「SDGsコーナー」は、主に壊れてしまったもの、古くなったもの、部品が足りないものなどを2Fの一部エリアにまとめて並べています。どちらも掘り出し物が見つかる確率大! 各ブースで行っているセール。赤いSALE・値下げマークが目印。 木の棚に並ぶたくさんのアイテム。動かなかったり欠けたりしていても、庭に飾るだけなら問題なし。屋外でも惜しみなく使える。 園芸関連資材とナチュラルな雑貨の問屋として、プロの仕入れのみならずガーデニングを楽しむすべての人をサポートする「NOAH(ノア)」。1万点もの厳選されたアイテムの中からお気に入りを見つけ出す時間は、まるでプロの気分。当日登録・購入が可能です。ぜひ訪れてみてください。アクセスは阪急宝塚線「服部天神」駅より徒歩20分、阪急バス「上津島バス停」より徒歩5分。車の場合、名神高速道路・豊中IC(池田方面出口)より約5分、阪神高速道路「豊中南IC」より約5分。
-
東京都

【参加者募集中!】都立公園を花で彩るコンテスト「第4回 東京パークガーデンアワード 夢の島公園」応募方…
東京パークガーデンアワードとは 写真(上)は、「第1回 東京パークガーデンアワード 代々木公園」のコンテストが開催される以前の様子。オリーブなど既存の樹木はそのままに、芝地が整地されてコンテストの花壇エリア(写真下)が作られました。コンテスト期間中、東京の最新ガーデンが見られるスポットとして多くの人々が訪れました。 2022年にスタートした「東京パークガーデンアワード」は、都内の公園を舞台に、新しい発想を活かした花壇デザインを競うコンテストで、2022年には代々木公園、2023年は神代植物公園で開催。今年は、砧公園を舞台に開催中です。東京都が主催し、12月の作庭から翌年11月のファイナル審査まで約1年かけて行われているガーデンコンテストです。 「第2回 東京パークガーデンアワード 神代植物公園」で開花した多数の宿根草。ロングライフ・ローメンテナンスをテーマに選ばれた植物は、3月から11月の間、バトンタッチをするように花壇を彩りました。なかには3〜4カ月もの期間咲き続けた種類も。 このコンテストの最大の特徴は、宿根草を活用した「持続可能なガーデン」をテーマにしていること。デザインに加え、植物や土壌に関する確かな知識やノウハウが求められる、今までのものとは一線を画すガーデンコンテストとして注目されています。 「第2回 東京パークガーデンアワード 神代植物公園」でグランプリを受賞した「Grasses and Leaves, sometimes Flowers ~草と葉のガーデン〜」季節の変化。 書類審査を通過した5名の入賞者には、抽選によって割り当てられた区画に、それぞれのガーデンを制作いただきます。そして、植物が成長をスタートした4月中旬に「ショーアップ審査(春の見ごろを迎えた鑑賞性を審査)」を、7月中旬には「サステナブル審査(梅雨を経て猛暑に向けた植栽と耐久性を審査)」を、11月上旬には「ファイナル審査(秋の見ごろの鑑賞性と年間の管理状況を審査)」という、3回の審査を経てグランプリが決定します。 第4回コンテスト会場とテーマ コンテストの舞台となる東京都江東区にある夢の島公園は都心から近く、東京湾に浮かぶような立地の都立公園です。 かつてのごみの埋め立て地を緑豊かな海辺の公園へと変貌させた「都市再生のモデル」となる公園でもあります。 園内にはユーカリ、デイゴ、ヤシなど熱帯・亜熱帯植物が生育し、熱帯植物館やスポーツ施設、マリーナ、広大な 芝生広場を備え、訪れる人々に南国リゾートの雰囲気を感じさせてくれます。 今回のテーマは「海辺のサステナブルガーデン」です。 東京パークガーデンアワードが実施されるエリア(熱帯植物館西側の グリーンパークの一画)は、公園のシンボル樹であるユーカリの樹林地に面しています。ユーカリの木々を背景に広がるウェーブガーデン(波をイメージしたダブルボーダーの花壇)に、海辺という環境に適した宿根草を使い、持続可能なガーデンを制作していただきます。 ガーデン制作費として最大180万円支給 「第2回 東京パークガーデンアワード 神代植物公園」2023年12月作庭時の様子。 書類審査を通過した5名の入賞者には、植物代などガーデン制作にかかった材料費として最大180万円が支給されます。今年は花壇面積が約24㎡と、例年に比べ小さく、ご参加いただきやすくなっています。 【審査基準】公園の景観と調和していること/公園利用者の関心を得られる工夫があること/公園利用者が心地よく感じられること/植物が会場の環境に適応していること/造園技術が高いこと/四季の変化に対応した植物(宿根草など)選びができていること/「持続可能なガーデン」への配慮がなされていること/メンテナンスがしやすいこと/テーマに即しており、デザイナー独自の提案ができていること/総合評価※各審査は別途定める規定に従い、審査委員による採点と協議により行われます。 「第3回東京パークガーデンアワード砧公園」審査の様子。第4回の審査員は、福岡孝則さん(東京農業大学地域環境科学部 教授)、正木覚さん(環境デザイナー・まちなか緑化士養成講座 講師)、吉谷桂子さん(ガーデンデザイナー)、本木 一彦さん(東京都建設局公園緑地部長)、植村敦子さん(公益財団法人東京都公園協会 常務理事) 「第4回 東京パークガーデンアワード 夢の島公園」応募方法 【申込者について】 ・一般市民、企業・団体、学生などを含め、プロ・アマ、国籍を問わず応募できます。・グループでの応募の場合は、必ず代表デザイナー1名を決めてください。・応募は1名(1団体につき)1件までとします。・定められた期間にガーデン制作やメンテナンスを行なっていただきます。 【ガーデン制作について】 ・ガーデン制作エリアは、「グリーンパーク」内です。 ・ユーカリの樹林地を背にしたエリアです。・ 重機の使用はできません。・ 植物代などガーデン制作にかかった材料費について180万円(税込)を上限に支給します。 ・ガーデン制作は2025年12月15日(月)〜12月19日(金)の5日間の中で行っていただきます。 以降、メンテナンスを行う中で補植も可能です。 【応募に必要な書類】 ・申込書・平面設計図・デザイン画(様式不問) 過去のコンテストガーデンをチェック!
-
東京都

猛暑に負けない花壇!「第3回 東京パークガーデンアワード 砧公園」の『サステナブル審査』を迎えた、5人…
年3回審査を行うガーデンコンテスト「東京パークガーデンアワード」 “グランプリ”、“準グランプリ”、“審査員特別賞”と、最終的な結果が決まるまでに4・7・11月の3回に渡り審査が行われますが、ガーデンの施工から8カ月ほどが経過した今回、2回目となる『サステナブル審査』が行われました(梅雨を経て猛暑に向けた植栽と耐久性を審査します)。審査期間:2025年7月10日~16日。 審査員は以下の5名。福岡孝則(東京農業大学地域環境科学部 教授)、正木覚(環境デザイナー・まちなか緑化士養成講座 講師)、吉谷桂子(ガーデンデザイナー)、本木一彦(東京都建設局公園緑地部⻑)、植村敦子(公益財団法人東京都公園協会 常務理事) 【コンテスト審査基準】丈夫で長生きする宿根草・球根植物(=多年草)を中心に季節ごとの植え替えをせず、季節の花が順繰りに咲かせられること/公園の景観と調和していること/公園利用者の関心が得られる工夫があること/公園利用者が心地よく感じられること/植物が会場の環境に適応していること/造園技術が高いこと/四季の変化に対応した植物(宿根草など)選びができていること/「持続可能なガーデン」への配慮がなされていること/メンテナンスがしやすいこと/テーマに即しており、デザイナー独自の提案ができていること/総合評価※各審査は別途定める規定に従い、審査委員による採点と協議により行われます。 今回の評価のポイントは主にガーデンの耐久性で、「梅雨を経て、猛暑に向けた植栽がなされ、秋まで庭が維持されるような持続性が考えられているか」。しかし、単に猛暑に耐える庭であることだけが重要ではなく、「植物個々の特性・魅力がしっかり見せられているか」、「葉や花の組み合わせがデザイン的に美しいか」、そして今回のテーマ、「訪れる人々の五感を刺激し、誰もが見ていて楽しいと感じる要素を取り入れた“みんなのガーデン”が表現されているか」などの項目も含めて評価されています。※年によって気象条件が変わるため、開花の時期がずれていても評価に影響しません。※今回行われた審査結果の公表はありません。 7月のショーアップ審査を迎えた5名のガーデンをご紹介 コンテストガーデンAGathering of Bouquet 〜庭の花束〜 【作品のテーマ・制作意図】 皆さんの日常に癒やしや潤いを届けたいという願いを込め、プランツ・ギャザリングの視点で、ガーデンをひとつの大きなブーケに見立ててデザインを構成しました。動物たちが次の訪問者のために心遣いを残していく絵本から着想を得て、あらゆる世代の方が見て触れて、香りなどを楽しめるように、花の形や手触りがおもしろいものを用いた植栽計画をしています。ぜひ手に取って、お気に入りの植物を見つけてください。たくさんの感動や気づきが新たな会話を生み、笑顔になるシーンが増えますように。 【7月中旬(審査当日)の様子】 審査時の見どころ マツやケヤキなどが作る日陰などの外的要因によく合わせられた植栽。美しくまとめられた配植のバランスは絵画的。春に引き続き、絶妙な足し算と引き算でまとめられたガーデンからは高い技術力が伺える。 開花期を迎えていた植物 ユーパトリウム‘ベビージョー’、ルドベキア ‘フラメンコ・ブライトオレンジ’、ルドベキア ‘フラメンコ・バニラ’、アガパンサス‘エバーホワイト’、エキナセア・マグナス‘スーペリア’、アジサイ‘アナベル’、アガスターシェ‘モレロ’、ヘリオプリス ‘ブリーディングハーツ’、エキナセア ‘サンシーカーズ レインボー’ など コンテストガーデンBCircle of living things 〜おいでよ、みんなのにわへ〜 【作品のテーマ・制作意図】 季節によってカラーリングが変化する植物や、実をつけて味わい深い風景を作ってくれる植物に集まる多様な生き物たち。そして各所に配置したサークルネストはそんな生き物たちの拠り所に。命の循環というキーワードをもとに植物だけではなく生きとし生けるものたちの集まる「庭」をテーマにデザインしました。人間だけに限らず、あらゆる生き物たち「みんな」にとっても楽しめる「命を感じられるガーデン」は「みんなのにわ」となり、命を循環させてゆきます。 【7月中旬(審査当日)の様子】 審査時の見どころ 土壌の栄養がよいのか巨大な葉が見られるなど、整いすぎていないワイルドさが魅力。生物多様性を意識した自然に親しむことができるガーデンは、自然のエネルギーを感じさせ、見ているだけで元気が出てくる。やや日陰を好むアンジェリカ・ギガスがうまいところに植わっていて、形のおもしろさや色彩を際立たせている。 開花期を迎えていた植物 ヘリオプシス‘ブリーディングハーツ’、エキナセア‘ブラックベリートリュフ’、エキナセア・テネシーエンシス、ムスクマロー‘ホワイトパーフェクション’、ユーパトリウム‘マスク’、アンジェリカ・ギガス、バーベナ‘バンプトン’、バーベナ・ボナリエンシス など コンテストガーデンCLadybugs Table 「てんとう虫たちの食卓」 【作品のテーマ・制作意図】 砧公園で暮らす「小さな住人(虫たち)」がこのガーデンを訪れて住みやすいように生態系を意識した植栽のデザインをしています。植栽は、見る場所や角度によって印象が変わるように、カマキリなどの天敵が身を潜められるような複雑さが出るよう工夫しました。植物は、てんとう虫やカマキリの食料となるアブラムシなどが好む「バンカープランツ」や蝶やミツバチたちの蜜源となる植物を植えています。「小さな住人(虫たち)」の生活をそっとのぞき見ることができる場所を目指しています。ここでの小さな体験が、自分の身近な自然環境を考えるきっかけになってもらえたら嬉しいです。 【7月中旬(審査当日)の様子】 審査時の見どころ 高低差やレイヤーで魅せる美しいバランスが印象的。開花させることだけを目的とせず、葉形や幹、茎が全体的にマッチするよう形をうまく生かした配植は、多様な表情を見せ、自然の風景を存分に楽しめる。それぞれの植物の特性に合わせた配置も機能的に考えられている。 開花期を迎えていた植物 ユーパトリウム・マスク、ユーパトリウム‘ベビージョー’、アリウム‘ミレニアム’、アリウム‘サマービューティ’、アリウム‘イザベル’、エキナセア‘メローイエロー’、カノコユリ‘ブラックビューティー’、アンジェリカ‘ビガーズミード’、ペニセタム・カシアン、モリニア‘エデュスダッチェス’、エラグロディス・スペクタビリス など コンテストガーデンDKINUTA “One Health” Garden 【作品のテーマ・制作意図】 ヒトの健康、生きものの健康、環境の保全を包括的な繋がりとして捉えるワンヘルス (One Health)の概念を軸に、それら3つの主体が密接に関わり合う「ワンヘルスガーデン」をつくります。土壌環境を改善し、植物や微生物を豊かに育て、鳥や虫などの地域の生きものを呼び込む。ガーデンの香りや触れ合いを通し、ヒトの健康と安らぎを生み出すガーデンをつくり、いろいろな生きものがやってくる「みんなのガーデン」を実現します。 【7月中旬(審査当日)の様子】 審査時の見どころ 土壌のバクテリアを育てるなど、実験的な取り組みがおもしろい。自然を意識した植栽は、藪の中にいるような気分にさせる。昆虫も多く見られ、“生物多様性”の目標に達成していることが伺える。時間の経過でまとまってくると感じられる絶妙なバランス。 開花期を迎えていた植物 アーティチョーク、オミナエシ、ウスベニアオイ、モナルダ(赤)、ルドベキア‘ゴールドストラム’、クナウティア・マケドニカ、アジサイ‘アナベル’、スモークツリー など コンテストガーデンE「みんなのガーデン」から「みんなの地球(ほし)」へ 【作品のテーマ・制作意図】 私は「みんなのガーデン」を、来園者だけでなく、花を訪れる虫、土壌菌類などの分解者、そして庭の先につながるこの生きた星「地球」の環境といった全ての「生あるもの」をつなげる庭と捉えました。温暖化する東京の気候に合った植物を差別なく組み合わせ、虫や菌たちによる循環系の形成、見るだけでなく庭づくりに参加もできる「みんなのガーデン」。「みんな」が共に助け合いながら、末長く幸せに暮らす世界、生命共存の尊さ・美しさを伝えたい。この想いが、この庭から未来へ・社会へ・地球へと広がっていけば、と考えています。 【7月中旬(審査当日)の様子】 審査時の見どころ カラフルでダイナミック、ポップでパワフル。植物の種類をたくさん入れることを恐れず、植物の可能性を追及するあくなきチャレンジ精神に拍手。つい写真を撮りたくなる見栄えのするパートがいっぱい。人を長時間滞在させる、飽きの来ないガーデンです。 開花期を迎えていた植物 カンナ‘ベンガルタイガー’、ヘレニウム‘モーハイムビューティー’、ネリウム(キョウチクトウ)‘ペティットサーモン’、エリンジウム・ユッキフォリウム、コレオプシス‘ガーネット’、アガスターシェ‘ブルーフォーチュン’、エリンジウム‘ブルーグリッター’、フロックス‘ハーレクイン’、モナルダ‘ファイアーボール’、バーベナ‘バニティ’、サルビア‘ロッキンディープパープル’、バーベナ‘バンプトン’ など <News> オンラインイベント開催&第4回参加者募集 第3回 東京パークガーデンアワードの入賞者によるオンライン座談会イベント開催 現在、都立砧公園にて開催中の第3回コンテストガーデン入賞者5名によるオンライン座談会を2025年8月1日(金)15:30~17:00に開催します。座談会では、自身の応募書類の紹介、植物の調達から造園、メンテナンスまで、参加したからこそ分かる”ナマ”の声をお伝えします。ご視聴のお申し込み(無料)は、以下のバナーをクリック! 「第4回 東京パークガーデンアワード 夢の島公園」の参加者募集! 2022年にスタートしたガーデンコンテスト「東京パークガーデンアワード」が、代々木公園・神代植物公園・砧公園での開催を経て、2025年、夢の島公園で始まります。第4回のコンテストの舞台は、夢の島公園「グリーンパーク」内(東京都江東区)。コンテストのテーマは、「海辺のサステナブルガーデン」です。応募の締め切りは、2025年8月31日(日)18時必着。応募方法など詳細は、以下のバナーをクリック! コンテストガーデンを見に行こう! Information 都立砧公園「みんなのひろば」前所在地: 東京都世田谷区砧公園1-1電話: 03-3700-0414https://www.tokyo-park.or.jp/park/kinuta/index.html開園時間:常時開園※サービスセンター及び各施設は、年末年始は休業。営業時間等はサービスセンターへお問い合わせください。入園料:無料アクセス:東急田園都市線「用賀」から徒歩20分。または東急コーチバス(美術館行き)「美術館」下車/ 小田急線「千歳船橋」から東急バス(田園調布駅行き)「砧公園緑地入口」下車/小田急線「成城学園前駅」から東急バス(二子玉川駅行き)「区立総合運動場」下車駐車場:有料
-
近畿

憧れの【バラに包まれたロマンチックガーデン】大原邸に学ぶ、小さな庭のつくり方
たくさんの人の心に響き渡る奏でるようなバラの庭づくり レンガの住宅を背景に、ロマンチックなバラが咲き誇る大原邸。階段脇でこんもりと咲き群れるバラに玄関の壁を駆け上がるバラ、フェンスに絡むバラなど仕立て方はさまざまで、道行く人たちの目を奪っています。 こんもりと茂るバラが一体となり、ピンクを軸とした美しいグラデーションを描いている大原さんのガーデン。この家を建てたのは約22年前。今ではこんなにもバラに包まれた夢のような庭ですが、当時はあまりバラには興味がなかったという大原さん。玄関のエントランス部分と庭の端に小さな花壇を設けた以外は、コンクリートを打ち、花壇に季節の草花とコニファーを植えて、バラは取りあえず加える程度でした。 大原さんのお気に入りのバラ、ほんのりグレーがかる波打つ花弁の‘カミーユ’と、コロンとしたピンクの中輪咲きの‘アントニオ・ガウディ’が控えめながらも存在感を発揮。フェンスには‘レイニー・ブルー’、レンガのウォールには‘ファイル・フェン・ブラウ’が広がっている。 丸いトピアリー仕立てのツゲ類や、ペチュニア‘アマゾナス’など季節の花を植えたコンテナで、エントランスに彩りをプラス。 「この家を建てた当時は下の子がまだ3歳で、植えたバラの世話が大してできませんでした。けれど、子育てに少し余裕ができ始めた頃からその魅力に取りつかれるようになり、徐々に本数が増えていったんです」 和バラ‘あおい’のこっくりとしたピンクの花が、デルフィニウムの青花とともに、あでやかなシーンを描いている。 とはいえ、植えることができるスペースはほんの一部。地植えできる場所にはバラと草花を植えつつ、それ以外ではコンテナを用いたり、コンクリートの上に土をのせたりして、失敗も繰り返しながら、バラ×草花で彩られる空間づくりにシフトチェンジしていきました。 左/コンクリートの上に土をのせてレンガで土留めした小さな花壇。 右/コンテナ植えと地植えを交えて庭を構成。 こんなにもバラに包まれた空間ですが、2/3以上が鉢植えというから驚きです。コンテナは大きくすると管理も大変なので、10号サイズ程度までにとどめています。「小さい庭に合った程よい大きさに育つほか、移動もしやすく模様替えも容易になります。植え替えは様子を見ながら部分的に行っています」。 北側の玄関と南側のメインガーデンをつなぐ通路からの眺め。突き当たりにアーチを配し、アイストップの効果を生んでいる。 現在、約50種類ものバラが5月上旬から次々に開花。大原邸の最大の見せ場である南側のメインガーデンでは、中央の白いパーゴラにランブラーローズ‘メイ・クイーン’と‘群星’、つるバラの‘玉鬘’が咲き乱れ、柱まわりに添わせたフェンスとともにロマンチックな空間を作り出しています。 パーゴラの下でくつろげるように、小さなテーブルとイスをセッティング。この空間ができたことで、ガーデンの立体感や見栄えがぐっと高まり、過ごす時間が格段に増えたのだそう。この麗しい空間は、いまや大原家のシンボリックな風景になりました。 パーゴラの半分ほどを占めているのは、ピンクのランブラーローズ‘メイ・クイーン’。「花付きのよい枝はしなやかで、下を向いてこぼれるように咲いてくれるので、パーゴラにピッタリなんです」と大原さん。今年は昨年より多めに枝を剪定したので、パーゴラ下の空間が明るくなりました。「枝をたくさん残せば、花は見事だけど庭が暗くなってしまう。この分量が最適だということが分かりました」。 デルフィニウムが美しかった2023年の庭。今年は苗の入手が遅れたため、成長が遅れている。 「結婚当初に訪れた信州で草花に感銘を受けたのが、ガーデニングに目覚めたきっかけです。以前の家では、寄せ植えやハンギングバスケットづくりのほうが好きで、好きが高じて雑誌のコンテストで入選したこともありました。しかし、今では我が家はバラでいっぱいに。ご近所のバラ好きや、お庭をされる方々と情報交換をしたりして、お世話になりながら楽しんでいます」 自宅でピアノを教えている大原さん。バラが見えるリビングでピアノを弾くことは至福の時間で、生徒さんやそのご家族にも好評なのだとか。「音楽も庭づくりも分野は異なりますが、どちらも“どう作り上げるか”が大切です。音楽にはいろいろな音があり、音色や強弱のコントラストなどを意識して演奏します。庭づくりも、たくさんの色彩などが交じり合って流れを作っていく。曲を奏でることと庭をつくることは、同じなんだなと感じています」。 リビングからの眺め。豊かなフリルが美しいカーテンと相まって優雅さにあふれている。「早朝が最もきれいに見えるんですが、1日が終わって夕方に庭に出る時が、一番ほっとする時間です」。 ロマンチックなシーンがそこかしこにある大原さんの庭。バラがひとしきり咲いた後は、アジサイとヤマボウシの花にバトンタッチ。庭はしっとりとした趣に変化していきます。 雑貨のあしらいも控えめながら、アクセントとして効果的に配されている。 バラを美しく咲かせるためには? バラが本格的に増え始めて10年あまり。バラ栽培については、故村田晴夫さんの本をはじめ、さまざまな書籍やインターネット、SNSなどを参考にしながら、自分なりに試行錯誤を繰り返してきました。今現在も庭づくりは進行形で、良いと思えることはいろいろ取り入れていっています。 バラを美しく咲かせるためには、冬に有機肥料+2~3回有機化成肥料を施しています。オールドローズは肥料をやりすぎるとボーリング(つぼみのまま開かない現象)しやすかったり、うどんこ病も出やすくなったりするので、冬だけに限定。害虫はなるべく捕殺にとどめ、どうしても取り切れないときや病気が出たときは、スプレーの殺虫・殺菌剤をまいています。 【フェンス使いのヒント!】 限られた空間を有効に使うには、フェンスやトレリスの導入が欠かせません! 大原さんの秀逸なフェンス使いの数々をご紹介します。 玄関正面にはしっかりしたフェンスを3連使いで見栄えよく。絡んでいるバラは‘レイニー・ブルー’。 隣家との境には、華奢なラインが美しいアイアンフェンスを。色は黒で統一し、バラ×クレマチスを引き立てる。絡むのはバラ‘マダム・アルディ’や‘フィリスバイト’、クレマチス‘マダム・ジュリア・コレボン’など。 南側のメインガーデンで使われているのは、手づくりの白い木製フェンスと数枚を並べたアイアンフェンス。絡んでいるのは、バラ‘ローラ・ダボー’ とクレマチス‘ブルー・ライト’。 メインガーデンの入り口で中を一望できないように目隠ししているのは、バラ‘ロココ’と白いアイアンフェンス。メダルタイプのオーナメントを下げて、ワンポイントをプラス。 はすかいに続く建物の壁を覆うように白いウッドフェンスを設置し、雑貨類を合わせてディスプレイコーナーに。扉付きのミラーが空間を広く見せながら、きらめきを生んでいる。 左/リビングの掃き出し窓の横の壁を、白い小さなフェンスでカバー。台にのせた鉢植えのバラは‘リナルド’。 右/テーブルセットの脇にも華奢な白いフェンスを立てて。ピンクのバラ‘レーヌ・デ・ヴィオレット’とクレマチス‘カシス’を合わせて可憐なワンシーンに。 西側の細い通路もウッドフェンスで隣家から目隠しし、コンテナでバラを楽しんでいる。勝手口前には細いフェンスを配置して、‘ジ・オルブライトン・ランブラー’ を誘引。奥のアーチには‘クープ・デペ’で華やかさを出して。 【スモールガーデンを彩るバラ&クレマチス】 ここでは、庭を彩る美しいバラとクレマチスの品種を一部ご紹介します。 左から/‘オデュッセイア’、‘カーディナル・ド・リシュリュー’、‘シャルル・ド・ミル’、‘ファイルフェンブラウ’ 左から/‘ザ・プリンス ’、‘あおい’、‘フランボワーズ・バニーユ’、‘クープ・テペ’ 左から/‘レイニー・ブルー’、‘ローラ・ダボー’ 、‘メイ・クイーン’ 、‘ファンタン・ラトゥール’ 左から/‘ウイリアム・モリス’ 、‘ スペクタビリス’ 、‘ペッシュ・ボンボン’、‘ロココ’ 左から/‘ジ・オルブライトン・ランブラー’、‘群星’、‘スノー・グース’、‘マダム・アルディ’ 左から/‘ジョセフィーヌ’、‘カシス’、白万重、‘アラベラ’ 2022年フォトコンテストで編集長賞を受賞 受賞時にガーデンストーリーサイトでもご紹介した受賞写真は、パーゴラに優雅にバラが絡み咲く風景でした。 まるで一服の絵画を思わせる写真に心奪われました。パーゴラにつるバラが優雅に絡み、視線の先で隣家を隠すフェンスにも何種かのバラが咲き、手前ではラベンダー色のバラが枝垂れ咲いています。寒さが厳しい冬につるバラのトゲと格闘しながら剪定や整理をされて、この時を待ちわびて訪れたベストシーズン。庭主さんがブルーの椅子に座ってバラの香りに包まれ、至福の時間を過ごされている光景が目に浮かびます。太陽光を受け止めて透ける葉色と影の色、その中に浮かび上がる愛らしい花色。咲かせすぎず、目に心地よい風景づくりに好感を持ち、編集長賞に選ばせていただきました。取材に行くのが楽しみです! 編集長 倉重 ガーデンストーリーでは、今年も、フォトコンテストを開催中です。詳しくは、下記をご覧ください。
-
東京都

【都会の秘境】目黒天空庭園へ! 高速道路の上に広がる驚きの空中庭園
首都高速道路の真上の庭園 黒川の氷川橋付近から見た大橋ジャンクション外観。屋上が天空庭園となっていて、階段を上ると庭園に至るエレベーターがある。右手のクロスエアタワーの9階からもアクセスが可能だ。picture cells/Shutterstock.com 東急田園都市線で、渋谷の次の駅、池尻大橋の近くに要塞のような外観の建物がある。これは、地上~35mの高さにある首都高3号渋谷線と地下約35mにある中央環状線を結ぶ大橋ジャンクション。天空庭園は、このジャンクションの屋上に2013年につくられたもので、約7,000㎡の都市緑地だ。ジャンクションがループ状なので、庭園も外寸175×130mのドーナツ形となっている。植栽は高木・中木・低木を合わせて約4,000本、地被類は73種、約3万株を数えるという。 庭園の案内図、現在地が分かるように何カ所かに設えられている。Henry Saint John/Shutterstock.com 庭園内の高低差は約24m、幅16~24mで、1周は400m。10のゾーンに分かれ、少しずつ趣が異なっている。バリアフリーで、四阿(あずまや)やパーゴラのほか、至る所にベンチが設置されているので、散策に疲れたら座って木々や草花を眺めることもできる。昼食時には、そこかしこでお弁当を広げる人の姿が見られた。 左/空から見た目黒天空庭園の全景。右/ゾーン別に色分けされた見取り図。(写真提供/目黒区) ブドウ棚での収穫祭 管理棟側から見た「西口広場」。 庭園には、4カ所の出入り口が設けられている。池尻大橋駅に近いアクセスを行くと、竹林の見えるアプローチから管理棟のある「西口広場」に至る。ここは低木植栽と花壇が主体の場で、信楽焼のブルーの縁石が印象的だ。 3つのブドウ棚が並ぶ「コミュニティスペース」。 「西口広場」の隣の「コミュニティスペース」では、ブドウ棚に葉が茂り始めていた。栽培されているのは、赤ワインに適した‘マスカット・ベーリーA’という品種で、9月に果実が収穫される。これに、山梨県のワイナリーで採れたブドウを加え、年間300 本のワインが醸造されるという。ブドウ棚は「目黒天空庭園栽培ガーデンクラブ」というボランティア団体のメンバーで管理され、収穫祭なども実施されている。 「コミュニティスペース」の野菜畑 収穫時には子どもたちの歓声が響く、野菜畑。 「コミュニティスペース」にはブドウ棚のほか、暮らしの中で親しまれている花木、そして野菜畑もある。畑には季節ごとにネギやエンドウマメ、ジャガイモなどが植えられ、こちらも前述のボランティア団体の管理区域で、有機栽培を学ぶ場、子どもたちが収穫に訪れる食育の場となっている。 モッコウバラの咲くパーゴラ「くつろぎの広場」 モッコウバラ、スイカズラ、ツキヌキニンドウなどのつる性植物が生い茂るパーゴラ。 散策路を行くと、つる植物に覆われた巨大なパーゴラが目に入る。4月末~5月初旬には、白色モッコウバラのほか、赤とオレンジ色の鮮やかなツキヌキニンドウの花を見ることができる。すっぽりと緑に覆われたパーゴラの下は陽射しの強い日でも快適で、テーブルにお弁当を広げる家族の姿が見られた。 左/パーゴラに咲いていた白色モッコウバラ。中・右/ツキヌキニンドウ。 「くつろぎの広場」の四阿と「あそびの広場」 左/散策路の途中にある四阿。右/紫蘭の咲く道の先に続く「あそびの広場」。 高低差のある庭園だが、木々に囲まれているので、400mを1周するのがそれほど苦にはならない。疲れたら屋根のある四阿でゆっくり休める。その手前ではハナカイドウが開花していた。 四阿(あずまや)脇の紫蘭(シラン)の花の先に広がるのが「あそびの広場」。歩道の左右にある5つの小さな盛り土は「五山の築山」という日本庭園の造園様式だという。撮影の日には松の木の剪定が行われていて、手入れの行き届いた庭園であることが納得させられた。芝生を囲む西洋式庭園と、松やカエデの葉が茂る日本庭園が混在しているのも、この場所ならでは。 庭園では植栽の手入れが丁寧になされている。見事な日本庭園の佇まいだ。 染井吉野とほぼ同じ頃に開花するハナカイドウ。 富士見台から富士を望む 屋上庭園とは思えないほど、濃い緑の木々が茂る「四季の庭」。 「四季の庭」の木々をくぐると「東口広場」に至る。ここは庭園の中で最も高い位置にあり、タワーマンションと目黒区の施設を併せ持つ、クロスエアタワーの9階からもアクセスが可能だ。 「東口広場」の入り口付近。クロスエアタワーのエレベーターで9階をめざすと、屋上とは思えない景色に遭遇する。 エレベーターホールの正面付近に設えられた富士見台からは、晴れた日には富士山を望み、大橋から三軒茶屋方面が一望できる。9階には目黒区立大橋図書館があるので、散策と読書の両方を楽しむ人もあるという。 ここから見える田んぼや池のある空間は、換気所の屋上に作られた「おおはし里の杜」。多様な生き物が生息する緑地で、かつての目黒川周辺の自然を復元したものだという。年に数回、一般公開される。 桜の開花リレー 左から時計回りに、染井吉野、シズカ桜、スルガ桜、オムロ桜、御殿場桜。開花リレーは、ほぼ1カ月続く。 庭園では季節ごとに咲く花が移り変わる。中でも4月の桜の開花リレーは、見ごたえがあるものだ。染井吉野から始まり、シズカ桜、スルガ桜、オムロ桜、御殿場桜(表記は庭園の名札から)と、約1カ月にわたり楽しむことができる。遅咲きのオムロ桜の前で記念撮影するイタリアからの観光客は、桜の季節に間に合ったと、満面の笑みを浮かべていた。 京都の仁和寺の桜として知られる、遅咲きのオムロ桜。半八重の花姿が華麗だ。 染井吉野が咲く頃は、すぐ隣の目黒川沿いの桜も満開なので、中目黒駅から川沿いに20分ほど歩いて、近所の店で買い入れたお花見弁当をここで広げるというのも、おすすめのコース。氷川橋通路からのアクセスが便利だ。 四季を彩る花々 左から時計回りに、信楽焼の大鉢に植えられたオオデマリ、アセビ、ハクサンボク、トサミズキ。 芝生が広がる散策路の両側には、さまざまな木々や花が植栽されていて、人々が木陰のベンチでくつろいでいる。 左/「あそびの広場」に咲く、ハナズオウとオムロ桜。右/「くつろぎの広場」に咲く、源平しだれという名前の2色のハナモモ。 目黒区のホームページや、天空庭園のパンフレットには、季節の花カレンダーが掲載されている。 木々や花には名札が付いているので、散策しながら珍しい植物に出会うことができる。桜、ハナカイドウ、ハナウメなど、4月の開花は見ごたえのあるものだった。初夏の庭園のこれからの開花も楽しみだ。 目黒区のホームページや目黒天空庭園のパンフレットに掲載されている花カレンダー。(写真提供/目黒区) 都市緑化の大きなプロジェクト 国道246号線側出入り口からのアプローチ空間。 高速道路の真上に7,000㎡の緑地を作り出したプロジェクトは、高い評価を得ていて、技術、緑化、デザインの各分野のコンクールで入賞している。周辺地域の環境対策と同時に、誰もが憩える場が提供されたこと、まちづくりの一環として、地域住民の参加がなされていることなど、称賛に値する事業だろう。ビルの屋上での緑化が進んでほしいと願っている身にとって、「天空庭園」散歩は、貴重な体験だった。 管理棟横の小部屋には、天空庭園の航空写真のほか、築庭の過程が分かるパネルが展示されている。
-
フランス

年間75万人が訪問するフランス「モネの庭」 なぜ人々は心奪われる? 復元された魔法の庭
ジヴェルニー「モネの庭」の魅力を深掘り 5月になるとバラの香りに包まれるモネの家。 睡蓮の連作などで知られる印象派の画家クロード・モネ(1840-1926年)の庭は、フランス、ノルマンディー地方の入り口、人口500人ほどの小さな村ジヴェルニーにあります。ひっそりとした佇まいを想像したくなりますが、じつは年間75万人もの人々が訪れる、モン・サン=ミシェルに次ぐ、ノルマンディー地方第2の大人気観光スポットです。 家の前には赤とピンクのペラルゴニウムが、かつてのモネの庭と同じように群れ咲いています。 さらには日本にも「モネの庭」が再現されているほどで、庭好きさんはもとより、多くの人々を魅了するこの魅力とは、どんなものなのでしょうか。モネの庭の2025年の様子をお伝えします。 画家の夢の庭 「水の庭」の太鼓橋。4~5月には紫と白のフジの花が咲き継ぐ見どころです。 画家モネが、家族とともにジヴェルニーの家に移り住んだのは1883年、彼が43歳の頃。戸外の自然の風景を描き続けてきたモネにとって、川の流れや林、牧草地に囲まれたこの地の自然は格好の画題となります。そして新たな情熱となったのが、庭づくりでした。方々に写生旅行は続けながらも、園芸雑誌を熟読し、園芸仲間と情報や種苗を交換し合って没頭した庭づくりは、50歳になる頃にはさらに大々的に進められます。 食堂はクロームイエロー、台所はブルーと白など、大胆な色づかいの内装もモネ自身が考えたものだそうで、とても可愛らしい空間になっています。壁を飾る浮世絵を見ると、モネのコレクションの様子が分かります。 ようやく画家として認められて財を成し、借家だった家と土地を買い取れるまでになったのです。庭師を何人も雇い、珍しい種苗を取り寄せて、理想の庭をつくり上げます。かつて農家だった建物とその敷地は、鮮やかな色彩が溢れる夢のような庭となり、亡くなるまでの43年間をここで過ごした画家の終の住処となったのです。 「花の庭」と「水の庭」 「花の庭」5月の中央園路の様子。アーチにはつるバラが咲き、その足元にはアリウムをはじめパープル系の花々が。 モネの庭は、大きく雰囲気の異なる2つの庭で構成されています。まず家の裏に広がるのは「クロ・ノルマン」(クロは囲まれた土地の意味)と呼ばれた「花の庭」。家屋の中央から庭の正面を貫く幅広い中央園路が印象的です。かつては並木道だったそうですが、モネは家の近くにある一対のイチイの大木を残して、すべて取り去ってしまい、モネの庭のシンボル的な存在でもある、バラが絡むアーチが続く明るいトンネルを作りました。 同じ中央園路の4月の様子。まだ閑散とした早春の庭では、チューリップをはじめとする春先の球根花たちが大活躍。 幾何学形の花壇がリズムよく並ぶ全体の構成はポタジェ(菜園)のようですが、これでもか、というほどにぎっしりと、さまざまな草花が植栽された花の園です。 「水の庭」の5月、白花のフジが咲き残る緑色の太鼓橋の上は、いつも人がいっぱいです。 そして道路を挟んだ向こう側のエリアは、後になって土地を買い足し、近くを流れるエプト川支流の流れを変えて、睡蓮の池とフジに縁取られた緑の太鼓橋をポイントにした、日本風の「水の庭」をつくりました。 「花の庭」の5月、枝垂れるスタンダード仕立てのバラと、足元のアイリスなどが満開に。 モネ没後、最後の直系の遺族だった息子の死に際して、残されていた作品や家と庭はフランス芸術アカデミーに遺贈されます。その頃の庭はすでに、手入れもされず元の形は失われかけていたのですが、1970年代から1980年代にかけて最初の復元プロジェクトが始まります。そして、庭を描いた作品や写真、モネの手紙や種苗の注文書などの資料をもとにした復元作業によって、輝くような本来の姿を取り戻しました。元どおりというばかりでなく、世界中から訪れる観光客に配慮して、一年中見どころがあるようにと、復元を超えて季節をくまなくカバーするような植栽計画がなされています。 「花の庭」花々が咲き継ぐ春から秋へ 4月の「花の庭」の様子。注意深く見ると、しっかりと区画分けされた花壇のそれぞれがテーマカラーを持っています。 現在のモネの庭の開園は、毎年4月初めから10月末まで。季節の花々が主役の庭ゆえに、冬季は閉園になります。4月といえばフランスではまだ早春ですが、庭を訪れてみると、スイセンやフリチラリア、色とりどりのチューリップをはじめとする、華やかなスプリングエフェメラルたちの饗宴に、思わず目を奪われます。この時期はまだ花壇の構造もはっきりと見えているので、それぞれの花壇ごとに色調がまとめられているのがよく分かるのですが、全体を眺めようとすると、それはまるでパレットに並べた絵の具の色彩が一度に目の中に飛び込んでくるようで、圧倒されます。 リンゴや洋ナシなどの果樹の花々は、この時期ならではのフランスの田舎らしい早春の風景。 そして5月、ひと月経つか経たないかの間に、すっかり様変わりした庭の、満開に近づくバラの下にアイリスやシャクヤクが咲く花風景は、まさにゴージャス。自然な風景を好んだモネのバラの好みは、白やピンク系のオールドローズ、白モッコウバラや野バラなど。当時から栽培されている品種だけでなく、例えば当時は存在しなかったイングリッシュローズ、デヴィッド・オースティンの‘コンスタンス・スプライ’など雰囲気の合う現代のバラも植栽に加えられています。 バラが咲き出す5月の風景。たった1カ月の違いで、緑も花もどんどん育ってまったく違う様相に。 そして夏から秋にかけては、ダイナミックにダリアやヒマワリが咲き、オレンジのナスタチウムが中央の園路を覆うというように、また違った花風景が展開します。いつの季節も豊かに咲き乱れる花々に囲まれて、うっとりと幸せな気持ちになってしまう、魔法がかかっているかのようです。 庭のそこかしこから、思いがけない花風景が広がって、息をつく暇もないほど。でも気持ちはウキウキ、そしてゆったりと庭を散策。 日本を意識してつくられた「水の庭」 「水の庭」4月の様子。睡蓮は夏になってからが出番なので、まだ姿は見えないけれど、池の周りにも変化に富んだ色彩の華やかな植栽が施されています。 幾何学構成の花壇の花々があふれ、その色彩に埋もれてしまいそうな「花の庭」に比べると、「水の庭」は、常に微妙な変化を見せる水面と空と植物とが織りなす、ぐっと落ち着いた空間です。 モネは浮世絵のコレクターで、家のなかには収集した浮世絵がたくさん飾られていたそうですが、池の外周を囲う竹林や、緑にペイントされた太鼓橋にフジの花や睡蓮の花という、和を感じる植物のチョイスには、当時流行したジャポニスムの影響が見られます。 「水の庭」の4月は、ヤエザクラや早咲きの紫のフジなどの花木が春らしい彩りを添える。 自然風景のなかにある、特に光や色彩、天候や時刻による変化を捉えようとしたモネにとって、睡蓮池の水景は刻々と表情を変える光、水、空気までもを捉えるための、描き飽きることのないモチーフとなりました。晩年には白内障を患い、視力を失いつつあるなかで描き続けた睡蓮の連作は、抽象絵画の先駆けとして現代美術への扉を開くことになります。 5月の池の周りでは、ボルドー色の紅葉の隣に紅のツツジが華やかに咲き、少し進むと白花と紫の爽やかな組み合わせが。 モネの息子から遺贈された作品はマルモッタン美術館に所蔵され、この庭とアトリエで制作された最後の大作はフランス政府に寄贈されて、現在パリのオランジュリー美術館に特別に誂えられた展示室で観ることができます。 池の外周を囲む竹林で一気に雰囲気が変わります。近年ではフランスの庭でも竹を使うところは多いですが、当時はまだ珍しかったそう。また、垣根にも竹垣を用いるなど、和風へのこだわりが感じられます。 画家の庭の魅力 芸術家の庭は、造園家が設計するのとはまた違った自由な着想が魅力であることが多いのですが、モネの庭もその1つ。シンプルな構成のうえに、画家としての色彩感覚と、たっぷりの植物愛をこめて配置された過剰なまでの花々。庭師たちの手間暇惜しまない維持管理が、モネの庭を特別なものにしているのでしょう。また、モネの愛したノルマンディーの絶え間なく変化する空と光と空気感も、この空間を輝かせている重要な要素なのだと思います。 ジヴェルニーの村を散策するのもおすすめ ジヴェルニー印象派美術館のカラフルな庭園。Alex_Mastro/Shutterstock.com 小さな村のなかには、土産物を売る店やら、かつて芸術家たちが集ったレストランなどが幾つかあるほか、モネの家と庭からほど近くには、庭付きのジヴェルニー印象派美術館があります。印象派の歴史やその後の展開を紹介する美術館ですが、地元の星付きシェフがプロデュースする付属のレストランには庭に面したテラス席もあり、人混みを離れて緑のなかで昼食を楽しむにもおすすめです。繁忙期には予約したほうがよいでしょう。また、食事のあとに村を散策する時間があれば、教会やモネのお墓を訪れることもできます。 モネの庭から徒歩15分程度の場所にある、ロマネスク様式のサント=ラデゴンデ教会。モネの墓もここにある。Alex_Mastro/Shutterstock.com ジヴェルニー印象派美術館(英語) https://www.mdig.fr/en/レストラン・オスカーOscar(英語) https://www.mdig.fr/en/plan-your-visit/restaurant/ ジヴェルニーへの行き方 ・公共交通機関利用の場合は、パリのサン=ラザール駅より電車で50分ほど、最寄りのヴェルノン=ジヴェルニー駅下車、のちバス(所要30分ほど)かプチ・トランかタクシーでジヴェルニーの村へ移動。繁忙期には混み合ってすぐにバスに乗れないこともあるので、時間には余裕を持って移動するのがよさそう。 ・車の場合はパリから1時間強。駐車場は村のなかのモネの家と庭の向かい側の他にも、外側に大駐車場があります。 ・入場券は現地でも購入できますが、入口には常に長蛇の列ができているので、個人で見学に行く場合は事前にオンライン予約購入が無難です。オンライン購入済みの場合の入口は団体入口になりますので要注意です。 ・パリからの日帰り観光バスツアーも多く出ているので、そちらを利用することもできます。
-
神奈川県

【見頃到来】バラとアジサイの共演! 横浜イングリッシュガーデンで出会う初夏の限定絶景PR
首都圏屈指の300品種のアジサイが主役になる季節 遅咲きのバラと早咲きのアジサイが一緒に楽しめる2024年5月下旬の横浜イングリッシュガーデン。 2,200品種、2,800株ものバラが4月下旬から咲き継ぎ、2025年も多くの人を魅了してきた横浜イングリッシュガーデン。5月下旬からは、主役が遅咲きのバラから早咲きのアジサイへとバトンタッチして、景色が日々変わっています。 左/ホルトノキに10株のつるバラ‘ローゼンホルム’を絡め、所々にクレマチスやホタルブクロも競演するバラのシーズンのフィナーレを飾る演出。右/8mのオウシュウナラに赤バラ‘ゾマーアーベント’ が咲くダイナミックな風景。5月下旬。 ‘ローゼンホルム’や‘ゾマーアーベント’など最晩生のバラが咲く頃になると、庭のあちこちで存在感が出てくるのがアジサイです。空のように爽やかなブルーや燃えるような真紅、チャーミングなピンク花など、個性溢れる300もの品種が日毎に色づいています。 5月下旬は、遅咲きのバラと咲き始めのアジサイが同時に楽しめる貴重なタイミング。 一度訪れたことがある方は、「あんなにバラが咲いていた、同じガーデンとは思えない!」と驚くほど。日ごとに存在感を増すアジサイは、6月中旬に最盛期を迎えます。 オレンジ色の‘ラ・ドルチェ・ヴィータ’の二番花とクレマチス‘アフロディーテ’がアジサイとコラボする景色(左)や、ライラック・ピンクの‘シスター・エリザベス’の二番花とアジサイがコラボする景色(右)が美しい6月下旬。。 その頃になると、再び花を咲かせるのはバラの二番花です。ひたすらゴージャスだった一番花に比べると少し控えめながら、ガーデンに彩りを添えています。バラからアジサイに主役が移り変わる5月下旬〜6月上旬と、バラの二番花が咲き始める6月中~下旬は、バラとアジサイが一緒に楽しめる贅沢なとき。多くの植物が生き生きと育つ横浜イングリッシュガーデンならではの景色に出会えます。 花の名にも注目したい個性あふれるアジサイの競演 ローズ・トンネルの下に植るアジサイの一つ、‘恋物語’は、白に赤の覆輪が美しい八重手鞠咲き。早咲きで、花付きがよく、育てやすい。完成度の高い品種。 花弁の縁をくっきりと紅に染めるのは‘恋物語’。 花の中に青い十字が浮かび上がる‘水凪鳥(みずなぎどり)’、そして名前のとおり! と言いたくなる花姿の‘ポップコーン’など、どのアジサイも美しく、花名も魅力的。歩を進めるたびに出会う個性あるアジサイの数々をじっくり楽しんでください。 左/花弁(萼片)の縁が丸くカールする‘ポップコーン’。右/花(萼)の中心に青い十字が浮かび上がる‘水凪鳥(みずなぎどり)’。 横浜イングリッシュガーデンに咲くアジサイたち。左上から時計回りに/‘モナリザ’、‘泉鳥’、‘ギャラクシー’、‘てまりてまり’、‘小町’、‘星花火’、‘レッド・エース’、‘メルティ・ラブ’。 夏のガーデンフラワーと咲き競う最高品質のアジサイ 全国各地のアジサイの名所とはひと味違う花景色が評判の横浜イングリッシュガーデン。その理由は、「庭園」という空間でアジサイが咲いているからです。アジサイだけが咲く名所も圧巻ですが、ここでは例えば、6月中旬からデイ・リリー(ヘメロカリス)、ユリ、アカンサスなど、さまざまな花とアジサイの奏でるカラーハーモニーを楽しむことができます。 庭園の権威ある世界大会で優秀庭園賞を受賞している横浜イングリッシュガーデンのガーデナーたちは、アジサイの栽培技術に長け、独自の技術で花を咲かせています。 そのため、ほかでは見られないようなビッグサイズのアジサイが、園内を進むごとに出現。その大きさとともに、圧倒的な花の数にも驚かされます。 映えスポットが出現! 期間限定のアジサイ・ディスプレイ 「アジサイ・フェスティバル」期間中は、毎年“映えフォトスポット”として人気の高いディスプレイがローズトンネルに出現。今年は、虹のようなグラデーションが映えるアンブレラが頭上を彩り、色とりどりのアジサイが園路を飾ります。雨にも色が冴えるアジサイの花風景を、ぜひ園内でご覧ください。 庭散策の後は、冷たい花モチーフのスイーツでクールダウン! 花々の美しさで癒やされたら、併設するカフェ「YEG Original CAFE」でクールダウンがおすすめ。アイスコーヒーやサンドイッチなどのカフェメニューのほか、特に人気なのが、見た目も可愛い「フラワーソフト」。バラとバニラのミックスソフトに、エディブルフラワーをカラフルにトッピングした、ここでしか味わえない美味しさです。パラソルの陰で花々の香りに包まれながら、ガーデン散策の余韻に浸るティータイムを過ごせます。 日が傾く夕方も庭散策におすすめの時間帯です。日陰のベンチに腰掛けて花々に囲まれる贅沢な時間をお過ごしください。左上に雲のようにふわふわの花穂をつけるのは、花木のスモークツリー。 本格的な夏に向けて、アジサイに混じってスモークツリーやヘメロカリス、ユリ、アカンサスが咲き継ぎ、訪れるたびに発見のある名園「横浜イングリッシュガーデン」。庭づくりの参考に、花知識を深めるために、また、大切な人と過ごす癒やしのデートスポットとして、ぜひお出かけください。
-
広島県

【今が絶景】7,000本のバラが咲き乱れる!福山市ばら公園がまるで花の海に
福山市とバラの歩み ― 公園に込められたまちの物語 花盛りの福山市「ばら公園」。 現在、「第20回 世界バラ会議福山大会」が開催中(5月24日土曜日まで)の広島県福山市。市内のあらゆる場所が満開のバラで彩られており、中でも「ばら公園」はその見どころのひとつとして、連日多くの来場者でにぎわっています。 「ばら公園」開園当初に植えられていたと思われるバラ‘ヴォーグ’。 福山市とバラの関係には深い歴史があります。第二次世界大戦で大きな被害を受けた福山市では、1950年代半ば「荒廃した街に潤いを与え、人々の心に和らぎを取り戻そう」と、近隣住民がバラ苗、約1,000本を植栽。それが「ばら公園」の始まりです。リニューアルした「ばら公園」にも、開園当初から植えられていたと思われるバラを一部残したコーナーや、平和への願いを込めて名付けられたバラのコーナーがあり、人々の記憶と思いが大切に受け継がれています。 福山城下の福山城公園もバラの盛り。 市民が育て、守り続けたバラは、今や福山市のまちづくりの象徴となり、「100万本のばらのまち」を目指すプロジェクトにも発展しています。そして今回、世界バラ会議の開催を機に、「ばら公園」は次の時代へ向けて大きな一歩を踏み出しました。 “バラのある”美しいガーデンへ。新たな混植デザインが見どころ 19基のつるバラ ‘マニントン・モウブ・ランブラー’のアーチとスタンダード仕立ての白バラ‘アイスバーグ’、紫の宿根草ネペタが織りなす見事な花の大回廊。アーチは王冠をイメージ。 今回のリニューアルにあたり迎えたのは、これまでハウステンボスなど多くのローズガーデンを手がけてきたランドスケープアーキテクトの白砂伸夫さん。アーチなどの構造物やスタンダード仕立てのバラを取り入れることで立体的なバラ空間を生み出しています。周囲を住宅や道路に囲まれた立地にもかかわらず、ひとたび公園に足を踏み入れると、花の世界に没入できるのは白砂マジックとも言えます。そして、「バラ+草花」の混植も今回のリニューアルでの大きな変化の1つ。これまでは主にバラが中心の公園でしたが、宿根草や灌木類など多様な植物と組み合わせることで、季節ごとの彩りや立体感がぐっと増しました。 見事な花付きの‘マニントン・モウブ・ランブラー’。 左/スタンダード仕立ての‘アイスバーグ’の株元をネペタとサルビアがさざ波のように彩る。右/一重咲きの‘キューガーデン’とネペタの組み合わせもロマンチック。 特にネペタやサルビア・ネモローサ、アイリスなどブルーの草花とバラとの共演は見事。バラの美しさがよりいっそう引き立ち、草丈や花形の違いを生かしたデザインは、ガーデナーにとって学びと刺激に満ちています。 真紅のバラ‘ムンステッドウッド’とサルビア・ネモローサがドラマチックなワンシーン。 ゆるやかな傾斜とカーブする小道、アーチなどの構造物によって、歩みを進めるたびに新たな景観がドラマチックに展開し、園内のあちこちで小さな歓声が上がります。犬の散歩をする地元の人に話を聞くと、「バラだけじゃなくいろんなお花が入ったおかげで、どこを見ても最高にきれい。ゆっくり歩きたいから、前よりお散歩の時間が長くなりましたね。この景色は街の誇りです」と話していました。 金メギの明るい葉色やネペタの淡い紫花がバラを引き立てる植栽。 約670品種・7,000本!“歩くバラ図鑑”のような公園へ ‘ヴァイオレット’や‘ギスレーヌ・ドゥ・フェリゴンドゥ’が彩るつるバラの小道。 リニューアルを経て、バラの品種は約670種、本数は約7,000本に拡充。以前の約280品種・5,500本から大幅にスケールアップし、アーチやフェンスに誘引されたつるバラやシュラブローズを生かした立体的な演出により、空間全体が奥行きとリズム感のある構成に。視線が自然に誘導され、どこを切り取っても絵になる風景が広がっています。 一重咲きで花心がビビッドピンクになる‘シー・ユー・イン・ピンク’と‘メアリー・レノックス’のロマンチックな共演。 それぞれのバラが持つ個性的な花形・香り・枝ぶりを実際に見て確認できるのも、この公園の大きな価値。プロや愛好家にとっても、品種選びや庭づくりの参考になる“生きたカタログ”ともいえます。 ‘ルイーズ・オディエ’や‘クーペ・デベ’などオールドローズを集めたコーナー。 福山市のバラのコーナー。左上から時計回りに/‘ウルヴァリンFUKUYAMA’、‘ローズ ふくやま’、‘プリンセス ふくやま’、‘アニバーサリー ふくやま’、‘福山城’、‘ビューティフル ふくやま’ 世界に誇る“ばらのまち”から未来へ バラがあふれる福山の街中。 福山市が開催地となる「世界バラ会議2025」は、世界のバラ研究者や愛好家たちが集う一大国際イベント。開催地に選ばれたことは、バラを通じたまちづくりが世界に認められた証でもあります。 その関連イベント「Rose Expo FUKUYAMA2025」(5月17日〜19日、福山通運ローズアリーナにて開催)は豪華なゲストを迎えるステージもあり、連日大盛況。そのほか、市内各所で多彩な展示や催しが行われており、「ばら公園」も中心スポットとして注目の的に。今しか体験できない特別な景観が、来園者を迎えています。 今こそ「ばらのまち福山」へ 国内外からの来園者でにぎわう「ばら公園」。入場は無料。 バラの美しさを超えて、ガーデンの芸術性・育てる楽しさを体感できる場所へと進化した「ばら公園」。景色を堪能できるのはもちろん、「この品種を庭に植えてみたい」「こんな組み合わせ、マネしてみたい」――そんな気づきと発見のある場所です。 バラが最も輝く季節に合わせて今こそ、この特別なバラのまちを訪れてみてください。 公園内に用意された可愛らしいフォトスポット。 【Information】 ばら公園 住所/福山市花園町1-5 営業時間/常時 利用料/無料 アクセス/JR福山駅北口から中心部循環バス・まわローズ青ルートで「ばら公園前」下車 トイレ設備/多目的トイレあり,おむつ交換台あり