ガーデンストーリー編集部

ガーデンストーリー編集部の記事
-
ガーデン&ショップ

【お出かけ情報】新しい仲間が加わった春のムーミン谷をのんびり散策しませんか?
ゆったりリラックスした一日を過ごせる「メッツァ」 ムーミンバレーパークは埼玉県飯能市の宮沢湖畔にある「メッツァ」の一部にあります。「メッツァ」とはフィンランド語で、森。北欧をお手本にしたライフスタイル提案型の複合型施設で、北欧のライフスタイルを感じられるマーケットやアクティビティが体験できる「メッツァビレッジ」と、ムーミンの物語をテーマにした「ムーミンバレーパーク」の2つのゾーンから構成されています。どちらもペットと一緒に入場ができ、お散歩や食事(テラス席)、ショッピングを楽しむことができます(※入場可能な施設・店舗はHPをご確認ください)。 フィンランドの陶器ブランド「ARABIA」の食器で提供されるカフェレストラン「nordics」。湖を望みながら食事ができる。 入り口からほど近い「メッツァビレッジ」は入場無料のエリア。季節ごとに移り変わる森と、野鳥が訪れる湖の景色を眺めながら、ゆったりと一日を過ごすことができます。湖のほとりに広がる芝生の広場にはデッキチェアが点在し、寝そべってキラキラ輝く湖面を見ているだけで、心も身体もリフレッシュ。もっとアクティブに過ごしたい人には、カヌーやクリアカヤック、アイランドボートなどのアクティビティがおすすめ。パラソル付きのアイランドボートにはテーブルが設置されており、湖上のピクニックが楽しめます。湖の周囲にはカフェやレストランが設けられているので、ランチもおやつも持たずに手ぶらでお出かけOKです。 カヌーはレンタルのほか、カヌー作り体験もできる。 北欧のヴィンテージアイテムなどが並ぶ「森と湖のマルシェ」 2023年4月22日(土)・23日(日)、メッツァビレッジで北欧のアイテムと自然が楽しめる「森と湖のマルシェ」が開催されます。北欧のヴィンテージアイテムや植物店、伝統料理を販売するキッチンカーなどが出店します。湖のほとりでゆったりショッピングを楽しみませんか? 第19回森と湖のマルシェ 開催日時/2023年4月22日(土)・23日(日)10〜16時場所/メッツァビレッジ特設会場*雨天中止 物語の世界を堪能できるムーミンバレーパーク 湖のほとりを歩いてメッツァビレッジの奥へと進むと、「ムーミンバレーパーク」にたどり着きます。「本」の形をしたウェルカムゲートをくぐり抜ければ、ムーミンの物語の舞台、ムーミン谷が待っています。フィンランドの作家トーベ・ヤンソンによるムーミン・シリーズは、ムーミン一家と個性的な仲間たちが、美しい自然に囲まれ平和でのんびりとした日常生活を過ごしながらも、冒険を通じて成長し自立していく姿が描かれています。 ムーミン一家と仲間たちが暮らすムーミン屋敷。素朴で上品なインテリアは必見。 ムーミンパパの作った水浴び小屋。 戦いやアクションといった派手な展開はない代わりに、日常の暮らしの喜びと厳しくも豊かな自然と対峙する方法や他者との調和、自立といった、どの時代にも普遍的なテーマで人々を魅了し、世界中で愛されている物語です。舞台となるムーミン谷は、海と山に囲まれ、春にはムーミンママが丹精する庭が花いっぱいになる美しい場所です。 春の花がいっぱいのムーミン屋敷の庭。 この物語が生まれた北欧フィンランドでは、人々は幼い頃から自然と共生し、自然から多くのことを学んで暮らしています。春のイベント「スプリングフェスティバル」では、植物採集が好きなヘムレンさんをムーミンバレーパークの新しい仲間として迎え入れ、フィンランドのような身近に「学び」を体験できる「Hemulen‘s academy(ヘムレンズアカデミー)」を行っています。アカデミーでは湖畔の周りを彩る季節の植物や水辺を訪れる野鳥の観察など、ムーミンバレーパークの自然や生き物を学ぶことができるフィールドワークに参加できます。 植物学者のヘムレンさん。デスクの上に並ぶのはヘムレンさんの収集物?©︎Moomin CharactersTM 夢いっぱいのアトラクションとかわいいムーミングッズ ©︎Moomin CharactersTM 園内では、若き日のムーミンパパたちの冒険を一緒に体験できる「海のオーケストラ号」や、ムーミンやムーミン谷の仲間たちによる歌とダンスのエンターテイメントショーなど、夢いっぱいのアトラクションが待っています。ほかにも、ここでしか買えないリトルミイのグッズが集合した「リトルミイの店」や、約400冊のムーミン関連書籍がずらりと並ぶ「ライブラリー カフェ」、売り場面積・商品数が世界最大級のショップ「ムーミン谷の売店」など、ショッピングの楽しみも満載。 おしゃれな「ライブラリー カフェ」。ムーミンのマシュマロを浮かべたキュートなラテ。 豊かな自然の中で、のんびりそれぞれのペースで過ごせて、かわいいムーミンたちにも出会えるメッツァへ、春のお散歩に出かけてみませんか。 メッツァ ■住所/埼玉県飯能市宮沢327-6■HP https://metsa-hanno.com■アクセス/西武線飯能駅から「メッツァ」行き直行バス、または「メッツァ経由武蔵高萩駅」行き路線バスで13分 メッツァビレッジ ■営業時間/平日10:00〜18:00 土日祝10:00〜19:00■入場料/無料 ムーミンバレーパーク ■営業時間/平日10:00〜17:00 土日祝10:00〜18:00※お正月、お盆休み、GWなど、施設が指定する日において営業時間が異なる場合があります。HPでご確認ください。■入場料/1デーパス 【2023年4月30日までの料金】大人(中学生以上):前売り販売3,000円 通常販売3,200円子ども(4歳以上小学生以下):前売り販売1,800円 通常販売2,000円【2023年5月1日からの料金】大人(中学生以上):前売り販売3,400円 通常販売3,600円子ども(4歳以上小学生以下):前売り販売2,000円 通常販売2,200円
-
季節のおすすめイベント

約2万株の花々が咲き広がる大人気イベント! 横浜赤レンガ倉庫「FLOWER GARDEN 2023」
横浜の春の風物詩「FLOWER GARDEN」とは 明治末期から大正初期に国の模範倉庫として建設された横浜赤レンガ倉庫は、長い歴史を経て1989年に倉庫としての役割を終え、2002年に文化・商業施設として生まれ変わりました。その後、5 周年記念イベントとして2007年に初開催されたのが「FLOWER GARDEN」。以来、横浜港を望む広場に咲き誇る花は “横浜の春の風物詩”として親しまれ、2023年で開催17回目を迎えます。 2023年のテーマは“WELL-BEING”! 花に包まれ心地よい空間を体験 今年のテーマは、幸福で身体的・精神的・社会的にも良好な状態を意味する“WELL-BEING”。リラックス効果のある青や紫を基調とした花が広がる「Sleeping Area」や、食欲増進効果のある赤やオレンジの花に囲まれて食事を楽しめる「Picnic Area」など、フラワーセラピーに基づいて設計された、エリアごとに配色の異なる多彩なロケーションを楽しむことができます。 「Sleeping Area」 鎮静効果があり、リラックスできる青と紫を基調としたネモフィラやビオラ、ペチュニアなどが咲く花壇の中央に、屋外用のチェアが設置されています。落ち着いた空間で、ゆったりとくつろぐことができるスペース。 「Picnic Area」 食欲増進効果のある赤やオレンジといったビタミンカラーのペチュニアとマリーゴールドが一面に広がるエリア。キッチンカーでは、横浜市産の食材を使用したフードや、オーガニックハーブティーなどが提供され、会場でもひときわ目を引く巨大なシンボルツリーの下、木製パレットのテーブルを囲んで食事を楽しむことができます。 【キッチンカー】フード・ドリンク A:ランチボックス横浜市の地産地消サポート店提供の、ローストビーフサラダとフレンチトーストのランチボックス。市内で採れた野菜と卵を使用し、食べられる花「エディブルフラワー」も添えられた彩り豊かな一品。税込1,200円/SHINMEI CAFE B:ピクニックボックス全粒粉のパンと鎌倉ハムのサンドイッチ&三浦野菜を使用した具だくさんのミネストローネスープのセット。税込1,200円/kitchen macaroni C:湘南ゴールドのジンジャーエール自家製ジンジャーシロップに湘南ゴールド(神奈川県が開発した黄色の柑橘)を漬け込んだ、オリジナルのジンジャーエール。税込780円/kitchen macaroni D:オーガニックハーブティーレモングラス、レモンバーム、ミント、ローズマリーなどをブレンドしたハーブティー。税込500円/kitchen macaroni 「Working Area」 記憶力と理解力を高める効果が期待できる黄色や白の花畑の中に、パーゴラが設置されたフォトジェニックなエリア。海風を感じながら空想にふければ、素敵なアイデアを思いつくかも? オージープランツが咲くウェルカムガーデンなど、フォトスポットが満載! 新港中央広場側から見て正面には、可憐な草花と近年人気が高まっているオージープランツを組み合わせたおしゃれなウェルカムガーデンが。両サイドに赤レンガ倉庫1号館と2号館が写り込むベストポジションでの撮影は、順番待ちになりそうな予感。 ライスフラワーやフランネルフラワー、ウエストリンギアなど、個性的でユニークな花姿が魅力のオージープランツが多種植えられたウェルカムガーデン。流木などのオーナメントもセンスよく配置され、庭づくりの参考に観察するのもよいでしょう。 他にもガーデンベンチや切り株、花のトンネルなどのフォトスポットが多数散りばめられ、友人同士やファミリーで、花に囲まれた記念撮影を思う存分楽しめます。 【ドッグフォトスポット】各所に設置された大小の切り株をステージに、色彩豊かなガーデン風景をバックにした愛犬の写真を撮影できるスポット。 また、夜のライトアップも、例年より装飾をパワーアップして開催。会場を訪れる時間によって、異なる表情を楽しむことができます。 土日限定でさまざまなコンセプトのマルシェを開催 会場内中央エリアでは、会期中の土日限定で週替わりのマルシェが開催。観葉植物やハーブなどを販売する「グリーンマルシェ」や、オーガニックのコスメやスキンケア用品を取り揃える「ウェルネスマルシェ」など、各週でコンセプトの異なるショップが並ぶので、毎週足を運んでも楽しめます。 植物の自家生産・輸入販売を手掛けるショップ「Willing plant」のブース(4月2日で終了) 「FLOWER GARDEN 2023」開催初日の3月31日(金)から4月2日(日)は、近年ファンが急増し注目を集めているアガベを中心に、多肉植物や塊根植物を取り揃えた8つのショップが集う「アガベマルシェ」を開催。午前11時のマルシェオープンと同時に多くの来場者で賑わい、男性を中心にショップ厳選のアイテムを吟味する姿が見られました。 マルシェ開催日程 「ローカルマルシェ」:4月8日(土)〜9日(日)地産地消や地場の新鮮食材、地元店舗が出店。地元ではお馴染みの横浜開港黒カレーをはじめ、フードロス対策になる食品などを販売。 「ウェルネスマルシェ」:4月15日(土)~16日(日)オーガニックなコスメやスキンケア、環境に優しい日用品や雑貨などを取り揃えるセレクトショップや、“食べられるバラ”を使用した食品の販売など、ナチュラルで健康に配慮したショップが集う。 「グリーンマルシェ」:4月22日(土)~23日(日)観葉植物や生花などを中心としたマルシェ。人気のシダ植物や珍しい樹種も用意され、豊富なラインナップに。花苗、ハーブ苗、野菜苗なども販売。 会場の花の100%再利用を目指す! 花の無料配布も 例年、会場内で使用した資材や花の再利用を行ってきた「FLOWER GARDEN 2023」。今年も、イベント最終日には花畑の花の無料配布を実施し、花の“100%再利用”を目指します。サステナブル活動を推進するとともに、多くの来場者に笑顔を届けてくれた花を、今後は自宅で育てて楽しむことができます。 花の無料配布 ■開催日時:4月23日(日) 13:00~18:00■場所:「FLOWER GARDEN 2023」 会場内特設ブースにて受付■花の種類(一例)・ワスレナグサ・ムルチコーレ・アリッサム・マリーゴールド・ペチュニア・ビオラ・ネモフィラ※予告なく変更となる場合があります■注意事項・雨天決行・荒天中止・先着4,000名限定、一人1袋(1ポット入り)。または時間になり次第終了・花の種類は選択不可 「FLOWER GARDEN 2023」は、美しい港の風景や街並みを背景に表情豊かな花々を楽しめる「みなとエリア」や、里山と柔らかな色合いの植物が織りなす「里山ガーデン」を中心に、横浜市内各所が花で彩られる催しが行われる「ガーデンネックレス横浜 2023」の連携イベントです。春の花が咲き誇る、見どころ満載なみなとみらい地区の散策とともに、ぜひ「FLOWER GARDEN 2023」に足を運んでみてはいかがでしょうか。 「FLOWER GARDEN 2023」開催概要 ■開催期間:2023年3月31日(金)~4月23日(日) 計24日間※ライトアップ 17:30~20:00※フードトラック、週末マルシェは11:00~18:00※4月23日(日)は18:00でイベント終了※雨天決行。荒天時は一部エリアを休業することがあります。■入場料:無料※飲食・物販・ワークショップ代は別途■場所:横浜赤レンガ倉庫イベント広場231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1■URL:https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/77■主催:横浜赤レンガ倉庫(株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)■協力:横浜市(ガーデンネックレス横浜実行委員会)
-
イベント・ニュース

無料会員登録で抽選で200名様にプレゼント! 「ガーデンストーリー」サイトをリニューアル
より使いやすく見やすいサイトになりました! ご愛読いただく皆さまに使い勝手がよいサイトへとリニューアルいたしました。4つの主な特徴をご紹介します! 日々上がる記事や検索で見つけたあなたのお気に入り記事を保存できる機能や、メールマガジンの購読サービスが利用できる無料会員制度を開始しました。 編集部がおすすめする季節の話題やタイムリーな記事一覧をページ上部など見やすい位置に配置しました。 ガーデニングビギナーさんに読んでいただきたい初心者向けハウツー記事への誘導枠を、分かりやすく配置。アクセスしやすくなりました。 ガーデンストーリーに関連するWebショップや動画サイト、関連サイト、各種サイト内ページへのリンクを分かりやすく並べたメニューを上部に配置しました。 無料会員登録してプレゼントキャンペーンに応募! ※終了いたしました 今回新たに開設する無料会員制度では、これまで読者の皆さまからもご要望の多かった「記事のお気に入り追加」機能を設けました。無料会員にご登録いただくと、気になる記事や何度も読み返したい記事を「お気に入りに追加」ボタンを押すことでマイページに保存できます。 また、ご希望の方には、季節ごとの人気記事などを掲載したメールマガジンをお届けいたします。 そして、今回のサイトリニューアルを記念して、無料会員登録をしてくださった方を対象にプレゼントキャンペーンを開催中! 抽選で200名様に、下記8種類のプレゼントのいずれかをお贈りいたします。ぜひ奮ってご応募ください! ■賞品のご紹介 ● A賞:春から秋まで楽しめる寄せ植え花苗セット【エム・アンド・ビー・フローラ】 3名様 ※こちらの賞品の抽選は先行して終了いたしました。 ガーデンストーリーの人気連載「1鉢で華やか!寄せ植えブーケ」の講師であるエム・アンド・ビー・フローラ 難波良憲さんセレクトの、春から秋まで楽しめる寄せ植え花苗セットです。 ※写真はイメージです。実際にお届けする賞品とは異なりますのでご了承ください。 ※こちらのA賞のみ、花の開花時期にあわせて先に抽選をさせていただき、4月中のお届けとなります。 ●B賞:小さな寄せ植えツール3点セット【浅野木工所】 5名様 白い塗装にブロンズの留め金、なめらかな木製の持ち手というおしゃれなデザインが目を引くスコップ、熊手、ピック(根ほどき)の3点のガーデニングツールセット。素材はすべて錆びにくく丈夫なステンレス製で、世界的に有名な刃物の産地、新潟県燕三条の職人の粋を集め、細部にこだわり設計されています。 賞品詳細はこちら→https://gardenstory.jp/gardening/59402 ●C賞:ガーデニング前掛け【grn GENERAL LIFE】 5名様 アウトドアシーンで長年愛されてきたファブリック、6040クロスに撥水性・防汚性に優れたテフロン加工を施した生地を使用した「ガーデニング前掛け」です。ベージュ、オリーブ、グレー、インディゴの4つのカラー中のいずれかをお届けいたします(写真はグレー)。 賞品詳細はこちら→https://www.gardenstory.shop/shopdetail/000000000085 ●D賞:ヘンプソープ【MOONSOAP】&オーガニックマルチバーム【PIANTE FELICI(ピアンテフェリーチ)】の2点セット 5名様 コールドプロセス製法で仕込んだオールハンドメイド、天然素材100%、合成化学成分不使用の石けんで、洗顔、メイク落とし、ボディーソープ、シャンプーと1つで4役をこなす「ヘンプソープ」と、ヘアにもボディにもマルチに使える高保湿バーム「オーガニックマルチバーム」の2点セットです。 賞品詳細はこちら: 「ヘンプソープ」→https://www.gardenstory.shop/shopdetail/000000000116 「オーガニックマルチバーム」→https://www.gardenstory.shop/shopdetail/000000000053 ●E賞:ガーデンストーリー書籍【KADOKAWA】2冊セット 10名様 2021年3月の発売以来大好評をいただき、9刷重版となっているガーデンストーリー書籍『花や実を育てる飾る食べる 植物と暮らす12カ月の楽しみ方』【KADOKAWA】と、第2弾として2023年3月に発売後、2週間ですでに重版となった新刊『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』【KADOKAWA】の2冊セットです。 書籍詳細はこちら: 『花や実を育てる飾る食べる 植物と暮らす12カ月の楽しみ方』→https://gardenstory.jp/events-news/54116 『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』→https://gardenstory.jp/events-news/79092 ●F賞:『ガーデンストーリークラブ』2カ月お試しクーポン 10名様 全国の花ファン、ガーデニングファンが集う有料会員制度『ガーデンストーリークラブ』を2カ月間無料でお試しいただけるクーポンです。会員限定オンラインサロンにご参加いただいたり、投稿やコメントでほかの会員さまと交流を図るなど、会員特典をお楽しみいただけます。 『ガーデンストーリークラブ』の詳細はこちら→ https://gsc.gardenstory.jp/about ●G賞:ガーデンストーリーウェブショップで使える2,000円クーポン 12名様 ガーデニンググッズやオーガニックコスメなど、こだわりの商品をそろえるガーデンストーリーウェブショップ(https://www.gardenstory.shop/)にて、6,000円以上の商品に使える2,000円割引クーポンです。 ●H賞:オリジナルハンドタオル 150名様 スタイリッシュな花柄をあしらった、ガーデンストーリーオリジナルデザインの今治産ハンドタオルです。 サイズ:20cm×20cm 素材:綿100% ※写真はイメージです。実際にお贈りする賞品と色合いなどが異なる場合がございますので、ご了承ください。 ■キャンペーン期間 2023年5月31日(水)まで ※A賞の「寄せ植え花苗セット」のみ、花の開花状況にあわせて先に抽選させていただき、4月中の発送とさせていただきます。 ■お申し込み方法 「ガーデンストーリー」の無料会員にご登録いただいた後、自動返信メールにてお送りするキャンペーン専用フォームからお申し込みください。 無料会員登録はこちらから→ https://gardenstory.jp/login/ ■プレゼント発送 A賞は2023年4月中、B〜H賞は2023年6月上旬ごろを予定しています。 ※無料会員登録にはメールアドレスのご登録が必須です。 ※当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。 ※プレゼントの内容をお選びいただくことはできません。 皆さまのご応募、お待ちしております!
-
ガーデン&ショップ

NHKの連続テレビ小説「らんまん」で話題の牧野植物園を取材! 牧野博士と植物園の全てを教えちゃいます!
牧野植物園を訪ねて、牧野博士の足跡をたどる 明治から昭和の時代、日本の植物学界に偉大な功績を残した植物学者「牧野富太郎」をご存じでしょうか? 彼は幼少期に植物に興味を持ち、以来独学で研究を続け、“日本の植物分類学の父”といわれるまでになりました。今年2023年は、数々の名作を生み出してきたNHKの連続テレビ小説で牧野富太郎をモデルとした物語「らんまん」が放映されることになり、今、その生涯に注目が集まっています。 高知県立牧野植物園とは 今から遡ること65年、1958年(昭和33年)に、高知県の五台山に、驚くべきスケールの植物園が開園しました。その名も「高知県立牧野植物園」。 日本の植物学界に偉大な功績を残した牧野富太郎博士を顕彰し、博士の故郷高知県に作られました。 世界にはいくつもの植物園がありますが、個人の名を冠し、それを顕彰する目的で作られた植物園は日本はもちろん、世界でもおそらくこの牧野植物園のみ。約8ヘクタール(東京ドーム約2個分)にも及ぶ園内には3,000種類以上の植物があり、そのほとんどが番号入りのタグで管理されています。 植物園のある高知県は「植物王国」 高知県といえば、鰹と坂本龍馬をまず思い浮かべる方が多いでしょう。しかし意外と知られていないのが、植物の宝庫という側面。日本で確認されている約7,000種にものぼる維管束植物(根、茎、葉、のある一般的な植物のこと)のうち、なんと40%に相当する3,170種が高知県に自生しているんです。日本の本州ほどの広さを持つ園芸大国イギリスでさえ、確認されている総数は約3,300種ほど。つまり高知県だけでイギリスの総数に近い植物が自生していることになります。豊かな日本の植生に改めて驚くとともに、3,000種以上の植物を擁する牧野植物園がいかにスケールの大きい植物園であるかが分かります。 【維管束植物数値データの参照元】 各国:OECD(経済協力開発機構) Environmental Data Compendium 高知県データ参照元:高知県植物誌 植物園内を歩いてみる 高知県の自然が再現されたエントランスまでのアプローチ 牧野植物園のスケールを物語る上で欠かせないのが、正面玄関からエントランスまでの約100mのアプローチ。ここでは「土佐の植物生態園」として、高知県の豊かな植物生態を、山→川→海辺と、段階的に体感することができます。ここだけで半日過ごす人もいるそうですが、それだけの価値と魅力にあふれたアプローチなのです。 建築家・内藤廣が牧野博士の偉業に彩りを添える 「土佐の植物生態園」で高知県の植物たちの出迎えを受けたら、エントランスのある本館に。そこで建屋が不思議な形をしていることに気づきます。 本館と展示館の建物を設計したのは、多くの公共建築や文化施設などを手掛ける、日本を代表する建築家の内藤廣氏。 スタイリッシュなデザインに目を奪われますが、設計した内藤氏は「この建物の主な目的は建築ではなく、牧野さんの生涯と、牧野さんがどのくらい興味深い人物だったかをプレゼンテーションすることです」と語ります。その意図は、建物が持つ機能を紐解くことで理解できます。 台風銀座と揶揄されるほど台風の通り道となっている高知県。植物園のある五台山頂付近は風が特に強くなるため、建屋にはその衝撃を分散する機能をもたせながらも、山の稜線美に溶け込むようなデザインが採用されました。木材は全て県産のものを使用しています。 屋根の急傾斜は、効率よく雨水を取り込み、それを再活用するためのもの。集められた雨水はいくつもの受け鉢や水盤に貯められ、その上を風が渡ると気化熱効果で周囲の空気がクーリングされるという仕組みです。受け鉢や水盤には水生植物も育ち、循環する生態系が生まれています。昨今巷でSDGsが高らかに唱えられていますが、ここではずっと前から“持続可能な循環型社会”が実現されています。 内藤氏の建築は、高知の自然を愛し、いつも人の1歩2歩先を行く牧野博士の姿を、入園者に体感という方法でプレゼンするものなのです。 展示館のスケジュールは要チェック 展示館では期間限定の展示やイベントが随時開催されているので、訪れる予定がある方は、牧野植物園のイベントカレンダーは要チェックです。 【牧野植物園イベントカレンダー】https://www.makino.or.jp/event/ 私が取材に赴いた12月は、牧野富太郎生誕160年特別企画展「牧野博士と図鑑展」が開催されており(現在は終了)、展示館内では牧野博士ゆかりの品々を見ることができました。 建物を一歩出ると、まるで絵画の中を歩いているよう 建物を一歩出ると、そこには絵画のような光景が広がっています。春はパステルカラーに、夏は涼感を呼ぶ緑に、秋は燃えるような赤にと、季節ごとの色彩で楽しませてくれます。 【春】 【初夏】 【夏】 【秋】 【冬】 【植物園と竹林寺の深〜い関係】 牧野植物園のある五台山には、もともと四国霊場第31番札所の五台山竹林寺がありました。しかし「牧野博士のご人徳から、その敷地の一部を譲り受け、無事に開園することができた」そうです。そのため、園内には現在もお遍路道があり、園を散策していると、時折お遍路さんに出くわすことも! 牧野博士にゆかりの深い植物たち 開花している植物が少ない冬の園内でも、大変貴重な植物が出迎えてくれました。それは、園のシンボルマークにもなっているバイカオウレンの花と、牧野博士の夫婦愛がこめられたスエコザサ。 【バイカオウレン】 牧野博士が幼少期を過ごした生家の裏山にはバイカオウレンの花がたくさん咲いていました。牧野博士にとってバイカオウレンは、自分を育んだ高知を想起させる花として、大人になってからも特別な存在であり続けました。晩年、病床にあった博士は、お見舞いでもらったバイカオウレンを、顔をこすりつけるほど喜んだそうです。 【スエコザサ】 スエコザサは、1927年(昭和2年)に牧野博士が仙台で発見した新種の笹。翌年に他界した愛妻壽衛に感謝の意を込めて、和名をスエコザサ、学名をSasa suwekoanaと名付け、これを発表しました。 この2つ以外にも、園内には至る所に牧野博士が命名した草花があり、それらには全て説明が記載されたガイドプレートがついています。 広大で起伏も激しい園内は、歩きやすい靴で 2Dの案内図では分かりづらいのですが、実際の園内は起伏がとても多いので、スニーカーなどの歩きやすい靴と、動きやすい服装で来園されることをおすすめします。 園内にはカフェやレストラン、売店も 園内はとにかく広いので、歩き疲れたらカフェで休憩しましょう。 園内にはお腹を満たしてくれる場所も充実しています。本館にはレストラン「アルブル」、展示館にはカフェ「アルブル」があり、レストランでは本格的な料理とティータイム、カフェではくつろぎの時間が歩き疲れた体を癒やしてくれます。 スタッフのイチ推し「まきのロール」。大納言あずきの入ったロールケーキで、「の」の字に巻いてあるので「まきのロール」という名前がつきました。シンプルながらも、スポンジ生地のやさしい風味と、ふわっと軽いクリームが絶品! レストラン及びカフェで食べられるほか、テイクアウトも可能です。(写真提供:レストラン&カフェ「アルブル」) 売店では、食品からグッズまで、バラエティに富んだ牧野グッズが選べます。どれもここでしか買えない貴重なものばかり。 牧野富太郎博士について学ぶ ①偉業 さてここからの2章は、牧野富太郎博士について解説します。 まずは牧野博士の偉業をわかりやすく解説 日本の植物学界に偉大な功績を残した牧野富太郎博士。彼の代表的な功績として、以下の7つが知られています。 【牧野富太郎の代表的な功績】 独学で植物を研究し、新種、新品種合わせて約1,500種類以上にも及ぶ植物を命名。 94歳で亡くなる直前までに、約40万枚にも及ぶ植物標本を収集。 出版物や講演活動などを通じて植物の教育普及に尽力。 画才にも秀でていた牧野博士が描いた植物図は「牧野式植物図」と呼ばれ、美しさ、正確性、緻密性、その全てにおいて圧巻のレベルだった。 植物の世界を一般大衆に啓発するために『日本植物志図篇』を自費で刊行。 『植物研究雑誌』を創刊。博士亡き現在も発行され続けている。 これらの業績が高知県立牧野植物園を作る礎を築く。 【今でも読める『植物研究雑誌』】 株式会社ツムラが隔月刊に発行している『植物研究雑誌』を、J-STAGE(電子ジャーナルプラットフォーム)上で読むことができます。 株式会社ツムラ『植物研究雑誌』https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjapbot/-char/ja すべてがアナログな時代に、圧巻のクオリティでこれらを成し遂げた牧野富太郎博士。その才覚とバイタリティは、現代にあっても人々の心を揺さぶるさまざまなエピソードで伝えられています。 牧野富太郎博士について学ぶ ②歩み 生誕から学者になるまで 世は幕末の1862年、生誕の前日 5月21日は京都で寺田屋事件が発生という動乱の時代に、牧野富太郎は造り酒屋を営むとても裕福な商家の一人息子として生を受けました。少年富太郎は幼少期にすでに英才ぶりを発揮し、12歳で入学した小学校の授業に飽き足らず、わずか2年で退学。その後15歳で、なんと退学した小学校で代用教員として教鞭をとることになりました。 後世に繋がる転機が訪れたのは、富太郎17歳の時。高知市の中学校教員・永沼小一郎と出会い、西洋の植物学や江戸時代の書物『本草綱目啓蒙(漢方医学の本)』に触れ、植物への知識をより本格的に深めていきました。この永沼先生との出会いこそが自分の原点であると、後年上梓する自叙伝にも記しています。 富太郎に影響を与えた『草綱目啓蒙』は国立国会図書館に保存されている。 国立国会図書館『本草綱目啓蒙』https://dl.ndl.go.jp/pid/2555472/1/1 22歳になった時に東京の植物学者・矢田部良吉教授を訪ね、植物研究を本格的に始めました。『植物学雑誌』や『日本植物志図篇』の刊行に携わるなど、若き研究者は持てる情熱の全てを自らの理想に注ぎ込みました。しかし研究のために財産をも使い果たすその金銭感覚は、後年結婚する妻にとっては頭痛の種でした。 学者になってから晩年まで 1889年(明治22年)、27歳の牧野富太郎は、矢田部教授の門弟・大久保三郎と共に地元高知で発見した新種の植物にヤマトグサと命名し、これを『植物学雑誌』第三巻に発表。国内で初めて日本人により植物に学名がつけられるという快挙を成し遂げました。 ところでプライベートでは、青年らしく、ちゃんと恋もしています。富太郎は大学への道中にある菓子屋の娘、小澤壽衛に恋をし、程なくして結婚しました。 こうして、公私共に順風満帆かと思われた矢先、自費出版していた『日本植物志図篇』が矢田部教授の逆鱗に触れ、発行中止になるばかりか、大学にも出入り禁止に。やむなく研究の場をロシアに移そうとするも、頼りにしていたロシア人植物学者の急死でこれも頓挫。負の連鎖はこれだけにとどまらず、祖母の逝去、実家の倒産など、富太郎は山あり谷ありの青年期を過ごすことになったのです。 しかしタダでは起きないのが富太郎。日本で初めて発見した水生の食虫植物のムジナモの論文が世界的な評価を受け、30歳を過ぎた頃には『大日本植物志』を発行。また、現在も薬品メーカー「ツムラ」に受け継がれて発行が続いている『植物研究雑誌』を発行するなど、持てる力と財の全てを植物研究に注ぎ込みました。 そして50歳にして東京帝国大学理科大学から講師として迎えられます。学歴を持たず権威にも無頓着だった学者が、最高学府の要職に就くことは当時としては極めて稀なことで、いかに日本の植物学界が牧野富太郎を必要としていたかがうかがえます。 1927年(昭和2年)、65歳で論文「日本植物考察」を発表したのを機に、東京帝国大学から理学博士号を授与されます。 植物学者として絶好調! 人生ようやく安泰か、と思われた矢先の翌年2月、最愛の妻壽衛に先立たれてしまいます。享年54歳でした。富太郎は亡き妻に感謝をこめて、前年に発見した新種の笹に、妻の名にちなみ「スエコザサ」と名付けました。 晩年 戦中戦後と、激動の昭和に晩年を送った牧野博士は、老いてもなお植物研究に情熱を注ぎ込み、その結果数々の栄誉称号を受けました。 75歳:各分野で傑出した業績と社会貢献を上げた人に授与される「朝日文化賞(現朝日賞)」を受賞。 78歳:植物研究と教育普及の集大成である「牧野日本植物図鑑」を刊行。 86歳:皇居に参内し、昭和天皇に植物学を御進講。 88歳:学術上顕著な功績を上げた科学者のための国の特別機関「日本学士院」の会員に選定。 89歳:文部省に「牧野博士標本保存委員会」が組織され、初代の「文化功労者」に選定。 91歳:「東京都名誉都民」に選定。 没後:従三位勲二等を叙任。また旭日重光章と文化勲章を追贈。 晩年に得たものとはいえ、これらの栄誉や称号は、先立った妻への最高のプレゼントになったのではないでしょうか。 そして1957年(昭和32年)に、牧野富太郎は妻壽衛のもとへと旅立ちました。享年94歳、まさにドラマ化にふさわしい激動の人生でした。 その翌年、高知県立牧野植物園が開園し、牧野博士の業績は今も語り継がれています。 【晩年の牧野博士に会える!?】 展示館では、晩年の牧野富太郎が「繇條書屋(ようじょうしょおく)」と名付けた書斎が再現されています。5万冊余の蔵書に囲まれ、日夜机に向かい研究に没頭していた牧野博士の姿を見ることができます。 NHKの連続テレビ小説「らんまん」 牧野富太郎の生涯をモデルにしたNHKの連続テレビ小説『らんまん』が、4月3日(月)よりスタートします。物語はオリジナルストーリーのため、主人公を務める神木隆之介さんの役名も牧野富太郎ではなく槙野万太郎となっており、ヒロインを務める浜辺美波さんの役名も富太郎の妻、牧野壽衛ではなく槙野寿恵子となっています。 物語は、真っ直ぐで純粋な槙野万太郎の人生が、幕末から明治、そして大正、昭和という激動の時代の渦中を、植物への愛と共に駆け抜ける様子を描きます。愛に満ち溢れた彼の人生が、主題歌を唄うあいみょんさんの歌に乗ってどのように描かれるのか、とても楽しみです! 【放送予定】2023年4月3日(月)より放送開始 【作】長田育恵 【音楽】阿部海太郎 【主題歌】あいみょん「愛の花」 【語り】宮﨑あおい 【出演】神木隆之介、浜辺美波、ほか 【植物監修】田中伸幸 取材後記 起伏の激しい植物園を歩き、牧野博士にゆかりの草木を見ながら思いました。もし私が同時期に生きていたら、牧野博士の好奇心に生で触れてみたい! 好奇心というのは誰しもが何かしらに抱くものですが、自分を制御せずに好奇心の赴くままに生きるというのは、誰もができるものではありません。皆がどこかで理由を作って置いてきてしまう好奇心に、生涯向きあい続けた牧野博士。そのエネルギーは凄いものだな、と、そう感じさせてくれた牧野植物園でした。 次回は、牧野植物園の内部をさらに深掘りし、園内のぜひ訪れてほしい場所を詳しくご紹介します。 おみやげプレゼント!※応募受付を終了いたしました。 取材途中に立ち寄った売店で人気No.1を誇る商品、バイカオウレンの葉を模ったスタンプを抽選で1名様にお送りします。 牧野博士にとって郷里土佐を思い起こさせる特別な植物バイカオウレンの葉は、牧野植物園のロゴマークにもなっています。このスタンプはその売れ行きから一時的に販売休止になっていて、多くの方が再販を望んでいましたが、今回偶然にも復刻版を手に入れることができました! 【応募方法】 応募受付を終了いたしました。 【応募締切】 2023年4月10日(月)23:59まで 【当選通知】 ご当選の方には別途メールでご当選の旨をお伝えし、送付先情報をうかがいます。
-
観葉・インドアグリーン

今、カラテアが熱い! 一鉢置けばそこはもう熱帯アメリカ、プロが選んだ推しのカラテア4選|観葉植物基礎講座 Vol.7
カラテアってどんな植物? カラテアは、グアテマラやホンジュラスなど7つの小国からなる熱帯アメリカを原産地とするクズウコン科の植物。品種ごとに異なる葉の模様を持っており、そのエキゾチックな美しさは世界中の観葉植物ファンを魅了しています。 いくつかの品種は、夜になると葉を折りたたむ休眠運動をすることでも知られており、この動作が手を合わせて祈る姿を想起するため、Prayer plants(祈りの植物)とも呼ばれています。 カラテアという名の由来は諸説ありますが、古代ギリシャや古代ローマで使われていたkalathos(カラトス)というユリの花のような形をした網籠に花穂が似ているため、という説が一般的です。 カラテア属は、かつては300以上の種類がありましたが、2012年に行われたDNA検査により、そのうちの約250種がゲッペルティア属、残る約60種類がカラテア属として分類されました。そのどれもが葉の色や形が異なるためコレクターも多く、集める楽しみがあるところは、前回特集したポトスにも似ていますね。 しかし育て方に関しては、ポトスよりやや難度が上がります。カラテアが枯れる原因として最も多いのは、乾燥。美しい葉の模様を楽しみながら健康な株に育てるためには、頻繁に葉水を行って株周りの湿度を保たなければなりません。多少放置していても葉が劣化しない品種が多い観葉植物の中にあって、カラテアは日々のケアがとても大切な種類なんです。 カラテアは、クロカータやオーガスタなど、種類によっては美しい花を咲かせます。ただ残念なことに、日本では沖縄など亜熱帯に近い環境以外で観葉植物として育てた場合、素人が開花させるのは難しいとされています。しかし、クロカータのように、比較的開花しやすい品種も出回っているため、関東以南の太平洋側にお住まいの方はチャレンジしてみる価値はあります。 【カラテアってウコンの仲間なの?】 カラテアはクズウコン科の植物ですが、二日酔いに効くとされるウコンとは関係ありません。ただ、クズウコンは地下茎から澱粉が取れ、それが食用になることから、コロンビアのヌカク族という先住民は、自生するカラテアになんらかの薬効性があるかどうかと考え珍重しています(薬効成分があるかは実際のところ不明)。また、ヌカク族のハンターは、大きく成長したカラテアの葉を狩猟用の矢を入れる筒にするなど、工芸品としても活用しています。 カラテアのプランツデータ 植物名:カラテア 和名:品種ごとに異なる和名がある。 学名:カラテア+○○(品種ごとに異なる) 科目:クズウコン科 属名:カラテア属 原産地:熱帯アメリカ 分布域:亜熱帯地域、熱帯雨林地域 葉の観賞期:通年 カラテアの特徴と魅力 一つひとつの品種が個性的な葉の模様を持つことで知られるカラテア。 カラテアは品種によって葉の模様がまったく異なるため、同じ属仲間には見えないほど個性豊かなのが特徴です。美しい模様はまるでアートのようで、一目惚れで買う方も多く、中には海外までレア物を探しに行く熱狂的なコレクターもいます。 ポトスやへデラのように、どの園芸店に行っても置いてあるというものではないため、欲しい方は事前に園芸店に確認することをおすすめします。ちなみにオザキフラワーパークでも入荷に波があり、また入荷しても種類によってはその日のうちにすぐに売れてしまうため、事前の在庫確認が望ましいです。 カラテアは入手したらSNSに投稿するファンも多く、インスタグラムで「#カラテア」と検索してみると2.9万件ものMyカラテアが投稿されており、学名の「#calathea」と入れると、投稿数はなんと86.1万件にまで跳ね上がります。そこでは、世界中の人々が自分流にカラテアを楽しんでいる様子が見られるため、これからカラテアを買う方も、買ったけれどインテリアコーディネートに迷っている方も、よい参考になるのではないでしょうか。 カラテアの育て方 置き場所 カラテアにとって最適な置き場所は、レースのカーテン越しの優しい光が入る窓辺や、同程度の明るさが確保できる場所。窓から離れた部屋の中心あたりに置いても問題はありませんが、日中の2〜3時間は前述の場所に置いてあげると葉の模様もくっきりした健康な株に育ちます。直射日光は葉焼けの原因となるため、絶対にNGです。 カラテアは耐陰性が強いため、日陰でもしっかりと育ちます。ただし、極端に暗い場所で栽培すると、最大の魅力でもある葉の模様が薄くなったり消えてしまうなどの影響が出ます。また、劣化した葉は株の勢いも弱めてしまいます。 最も注意してほしいのが、エアコンの風。冷暖共に、風が直接当たる場所は避けてください。エアコンの風が直接当たる場所に長時間置いておくと、葉が気孔から水分を蒸発させる代謝活動(蒸散)ができなくなり、株が弱る原因になります。 これらのことから、カラテアの置き場所は「明るすぎず、暗すぎず、エアコンの風があたらず」を念頭に管理してください。 【カラテアはペットOK】 観葉植物の中にはペットに有害な種類のものも数多くあります。しかし、カラテアはペット(犬及び猫)に対して安全な観葉植物なので、安心して室内に置けます。ただし、猫の中には猫草と間違えて葉をかじってしまう子もいるので、猫がいるご家庭では特にご注意ください。 観葉植物のペットに対する安全性は、下記「アメリカ動物虐待防止協会」のANIMAL POISON CONTROL/Toxic and Non-Toxic Plants List (ペットに対する有毒無毒リスト)を引用しています。 ASPCA/Toxic and Non-Toxic Plants List 夏の管理温度、冬の管理温度 【夏】 カラテアの栽培に最適な温度は20〜30℃です。しかし年間を通して蒸し暑い熱帯アメリカが原産のため、耐暑性はとても強く、室内の温度が35℃くらいにまで達するような猛暑日が続いても枯れる心配はありません。むしろ寒さに弱いため、冷房の冷たい風が当たらないよう十分に注意してください。 【冬】 カラテアは数ある観葉植物の中でも特に寒さに弱いため、冬は15℃を下回らないように管理してください。15℃を下回ると葉がしおれたり、株の健康状態によっては枯れてしまう場合もあります。また、冬は暖房を効かせていても、陽が落ちるにつれ窓辺の気温も急激に下がっていくため、カラテアを窓辺で管理している場合は、夜間は部屋の中心に移動してあげるのがおすすめです。 【サーキュレーターを活用しよう】 夏と冬は窓を閉め切っていることが多いので、自然界に少しでも環境を近づけるために、サーキュレーター(送風機)の使用をおすすめします。 天井(直上)に向けて風を送れば、サーキュレーターの風は直進する性質があるため、天井で四方に分散し、壁にぶつかった後は下に向かい、部屋の中でぐるぐると回ります。こうして部屋の空気をまんべんなく循環させることにより、病害虫も発生しにくく、健康な株に育つことが期待できます。 水やり 春~秋の間は土の表面が乾いたら、鉢底穴から流れ出るくらいたっぷりと水を与えます。冬は土の表面が乾いて3日ほど経過したら、同様に鉢底穴から流れ出るくらいたっぷり水を与えます。受け皿に溜まった水は必ず捨ててください。 肥料 春~秋の間は、窒素が多い観葉植物用の液体肥料を週1回のペースであげてください。使用法はメーカーにより異なるため、必ず商品ごとの使用法に従い、適切な量を与えてください。 固形(錠剤)肥料の場合は、置肥(おきひ)といって、鉢の縁付近に規定個数を置いておけばOKです。こちらも必ず商品ごとの使用法に従い、適切な量を与えてください。 カラテアは、根の機能が弱まる冬の間は基本的に施肥は不要です。液体肥料は冬になったら止め、固形(錠剤)肥料は、冬に入る前にまだ鉢に残っている場合は撤去して、冬場は完全に無肥状態にしてください。 葉水の方法など、日常のお手入れ カラテアは極度に乾燥に弱いため、空中湿度を高く保たないと葉が丸まったり、先端から変色するなど葉のコンディションが急速に悪くなり、最終的には枯れてしまいます。このため、葉水は春夏秋冬、毎日あげてください。極端な話、気づいた時にスプレーするなど、一日に何回あげても構いません。むしろそうすることで、害虫が発生するリスクを抑えることができます。 ただし、冬場の葉水は必ず日中に行うようにしてください。カラテアは寒さに弱いため、夜間に行うと株の体温を下げてしまい、弱らせる原因となってしまいます。 植え替え 株の成長を促すために2~3年に1回、春~秋の間に1〜2回り大きい鉢に植え替えてください。 病害虫 【害虫】 カラテアの葉や茎が乾燥すると、高い確率で発生するのがカイガラムシとハダニ。発生すると葉を弱らせるため、葉の美しさが売りのカラテアにとってはまさに天敵です。 カイガラムシは、一度発生すると急速に広がり患部も深くなります。しかし効果的な薬剤が少ないため、見つけ次第ピンセットや歯ブラシを用いて物理的に駆除します。 ハダニの場合は、市販の殺虫剤を散布して駆除してください。 前述のように、害虫予防に最も有効なのが葉水なので、“気づいた時の葉水”を習慣にすることをおすすめします。 【病気】 カラテアは空中湿度を高めにして育てるため、春~秋に、湿度を好む黒斑病、斑点病が出る場合があります。 黒斑病/初期症状は白い小さな斑点ができ、やがてその名の通り黒い大きな斑点に成長していきます。 斑点病/初期症状は褐色の小さな斑点がいくつかでき、やがてそれらが拡大していきます。 黒斑病も斑点病も、初期症状の段階で総合殺菌剤(『STダコニール1000』等)を用いて治療すれば高い確率で治りますが、発見が遅れると殺菌剤も効かずに枯れてしまうこともあります。 人間の体同様、病気は早期発見が第一。手遅れにならないように、日頃の葉水のときなどに株の状態に目を配ることが大切です。 オザキフラワーパーク後藤さんが選んだ、推しのカラテア4選 ランキフォリア 【写真の商品】高さ(以下全て鉢含まず)20cm 店頭価格:1,680円(税込) 品種の名がラテン語で槍の(lancea)葉(folium)に由来するように、シャープで波打つ形の葉に水彩絵の具で描いたようなアート感溢れる模様が印象的。 ポップな現代アートを思わせるこの模様、とても自然の物とは思えません。表の模様に反して、裏は綺麗なパープル1色。表と裏で全く違う表情を楽しめるのも、ランキフォリアの魅力です。 成長が早いランキフォリアはすぐに生い茂ってきます。葉が古くなって傷んできたなと思ったら、躊躇せずに剪定をしてください。剪定をすることにより新しい代謝を促し、株の健康状態を良好に保つことができます。それ以外は一般的なカラテアの育て方と変わりありません。 写真の商品は高さ20cm(鉢含まず)ですが、自生地では1mを超える株も多いため、明るい場所で基本通りのケアをしていけば、現状の倍以上の40〜60cmまで伸びると思います。 ドッティー 【写真の商品】高さ20cm 店頭価格:1,680円(税込) まるで黒いキャンバスにホットピンクの模様を一筆書きで入れたような葉が特徴の‘ドッティー’。漆でも塗ったかのような光沢を帯びたエキゾチックな葉の雰囲気は、部屋でも独特の存在感を放ちます。 ‘ドッティー’は1998年にAnne E. Lamb氏によりフロリダで作出された園芸品種です。2000年に米国で特許が出願され、市場に出た途端に大人気になり、今では最も売れているカラテアの一つです。オザキフラワーパークでもとても人気で、中にはカラテアと知らずに、その存在感に惹かれて買っていかれるお客様もいます。 耐陰性の強いカラテアの中でも‘ドッティー’は最も耐陰性があり日陰でもよく育つため、カラテア初心者にはおすすめです。 ムサイカ 【写真の商品】高さ15cm 店頭価格:2,680円(税込) 葉の表面の模様がモザイクみたいなことから、モザイクという異名を持つムサイカ。欧米ではカラテア・ネットワークという商品名でも販売されています。擬態の一種でもあるかのようなこの模様の葉が自然に生えてくるというのは、摩訶不思議なものです。遠目にはなんの変哲もない緑の葉に見えますが、近くに寄るとこのモザイク模様なので、お客様が思わず足を止めて見入ってしまう光景を店頭でもよく目にします。 コンテンポラリーな見た目から近年作出された品種かと思われますが、オリジナルの品種は1875年にブラジル南東部で英国の園芸家ウイリアム・ブル氏により発見され、最初はマランタ・ベラ・ウイリアムブルと名付けられました。 それ以降、カラテアの1品種として世界中で愛されてきましたが、2012年に行われたDNA調査により、カラテアではなくゲッペルティア属に分類されたため、正式にはカラテアではなくなりました。でも、今だに世界中でカラテアの1品種として販売されているというのは面白いですよね。 ちなみにムサイカは、カラテアの中でも出会えたらラッキーなレア物として知られていますが、オザキフラワーパークには割と頻繁に入荷します。ただし、すぐに売り切れてしまうことが多いため、購入される場合は、事前に在庫状況をお問い合わせください。 オルナータ(サンデリアーナ) グリーンの下地にピンクのラインという、まさに熱帯ならではの奇抜な配色が目を引くオルナータ。海外ではサンデリアーナの名のほうが通っていますが、その見た目からピンストライプ・カラテナという別名もあります。 【写真の商品】高さ45cm 店頭価格:2,980円(税込) よく見ると、ペンで描いたようなライン模様はピンク1色ではなく、葉の外側に行くにしたがって色が薄くなるグラデーションになっているんです。おしゃれですよね! 初見のインパクトが強いためか、オルナータを一目見たお客様の多くが、そのまま衝動買いしていかれます(笑)。 自生地では3m近くまで伸びますが、観葉植物として室内で育てた場合は、高くても1mくらいが最長です。写真の45cm(鉢含まず)という高さの商品は、どんなお部屋にもマッチする大きさだと思うので、僕個人的にはおすすめです。しかし、成長が遅い品種のため、大きくしたいと考えている方は、最初から大きめの株を検討されたほうがよいと思います。 自生地では5〜8月に、上の写真のような小さなオレンジ色の花を咲かせるので、自生地に近い環境の沖縄周辺地域にお住まいの方は、地植えしたら開花を体験できるかもしれませんね。 取材後記 独特な模様を持つ葉が印象的なカラテアですが、皆さんは後藤さんのピックアップしたこの4種類のうち、どれが気に入りましたか? ここまで葉の模様が異なると、どれを選ぶかで性格診断などもできそうですね。 ランキフォリアを選ぶ人は情熱的で、‘ドッティー’を選ぶ人はポジティブ思考、ムサイカを選ぶ人はこだわりが強く、オルナータを選ぶ人は社交的。もちろん、論理的な根拠はなく、私の勝手な解釈ですが、皆さんはどう思われますか? それぞれに個性が際立つので、贈り物にする場合、あの人にはどのカラテアがいいかな、って考えるのも楽しそうですよね。私個人的にはムサイカのシンプルな中にも存在感のある葉が気に入ったので、ちょっと変わったものが好きな友人の誕生日に贈ろうかなと考えています。 オザキフラワーパークの企画、次回も乞うご期待です!
-
ガーデンデザイン

造園のプロ直伝! 苗木の植え付けテクニックを学ぼう 〜はまだんの「ステキなお庭をつくろう!」企画Vol.8〜
プロのアドバイスのもと苗木の植え付けにチャレンジ これまで一年草の花や野菜栽培を楽しんできたはまだんですが、今回は庭デザインに関わる本格的な植栽作業を行います。今回植え付ける低木類や宿根草は、これまで植えた一年草の花苗や野菜類とは異なり、一度植えたら基本的に移動せずにその場所で長く育つもの。庭の骨格を作る大事な要素でもあるため、植物のセレクトや配置を吟味する必要があります。そこでプロにアドバイスをいただきます。建築・エクステリアの企画事務所「エムデザインファクトリー」主宰・松下高弘先生、横浜市内で造園業を営む貝塚造園の岸聡志さんと、LEA GARDENの佐久間勇太さんをはまだんハウスにお招きし、植裁の指導をしていただきました。 庭の骨格を作る低木類と宿根草 初心者でも比較的育てやすいことを考慮し、岸さんが以下の植物をセレクトしてくれました。 ■低木類 ①カシワバアジサイ/ピラミッド状の大きな花はもちろん、柏の葉に似た大きな葉は秋に真っ赤に紅葉し美しい。 ②あじさい‘アナベル’/真っ白な大輪の花が存在感たっぷり。他のアジサイに比べて剪定が簡単なので、初心者向き。 ③マホニアコンフューサ/艶やかな緑の葉を一年中茂らせる常緑低木。 ④ローズマリー/葉に良い香りがある常緑低木。ハーブとして料理や暮らしの中で使われる。冬から早春にかけて小さな青い花を咲かせる。 ⑤ブルーベリー/春は白い花、夏は実の収穫、秋は紅葉と楽しみが多く育てやすい果樹。⑥コニファー‘ゴールデンモップ’/黄金の葉が這うように伸びグラウンドカバー的にも使える常緑低木。 ⑦ハクチョウゲ/夏に白い小さな花を株を覆うように咲かせる常緑低木。 ■宿根草 クリスマスローズ(左)/「冬の貴婦人」と呼ばれ、多くは早春2〜3月に花を咲かせる。 ギボウシ(右)/黄金葉や斑入りなどバリエーション豊富な葉を楽しむカラーリーフの代表。夏に咲く白や紫の花も美しい。 SDGsを実践できる「はまっ子ユーキ」で土壌改良 苗木を植え付ける前に、まずは土に堆肥と化成肥料を加えて耕し、土の状態を整えます。今回使用する堆肥「はまっ子ユーキ」は、横浜市内の公園や街路樹、公共施設などから発生する剪定枝を原料としており、横浜市グリーン事業協同組合による「緑のリサイクル事業」から生まれたもの。この事業では、市内で回収された剪定枝・刈草・幹材を原料に堆肥やチップを製造・販売することで、横浜市のゴミの低減や緑化推進に貢献しています。 横浜市南区にある清水ケ丘公園を管理する横浜緑地株式会社では、SDGsの取り組みの一つとして、はまっ子ユーキを花壇作りに活用しています。SDGsとは、持続可能でよりよい世界を目指すために、国連加盟国が貧困、環境問題、経済成長やジェンダーなどの課題に対して掲げた、2030年までに世界共通で達成すべき17の目標のこと。環境負荷低減への取り組みで生まれた製品を調べて選択することは、SDGsを意識して消費者ができる身近な行動の一つです。こうしてガーデニングや暮らしの中でできることを少しずつ実践して、地球環境の保全につなげたいですね。 苗木のレイアウトを決める 主役となるカシワバアジサイは、今回植裁を行うコーナーの中心後方に設置。常緑で立性のローズマリーは背景として最後部に、低木で這うように広がるコニファー‘ゴールデンモップ’は手前に、暑さが苦手なクリスマスローズは日差しを避けるためにカシワバアジサイの足元に置くなど、植物の性質を考慮してレイアウトします。 カラフルな一年草をプラスし庭を鮮やかに 彩りをプラスするために、一年草も取り入れます。明るく元気なはまだんをイメージして、夏は赤・ピンク・オレンジ・黄・白と色とりどりのジニアをセレクト。冬から春はパンジー&ビオラなど、季節ごとに植え替えます。地植えだけでなく鉢植えも配置することで高低差をつけ、庭に立体感を出します。 今回植木鉢に使用するのは、リサイクルペットボトルと天然素材から作られた不織布製の「ルーツポーチ」。通気性と排水性に優れ、健康な根が育ちやすく、高温になる夏の時期も鉢が熱くなりにくいという特徴があります。植物に優しく環境にも配慮された植木鉢で、カジュアルでおしゃれな見た目も、はまだんのお気に入りポイントです。 ルーツポーチに培養土を入れ、苗を植え付けます。今回岸さんと佐久間さんから教えていただいた、ジニアの苗を鉢に植え付ける際のポイントは2つ。1つ目は、花の正面を見極めること。花苗を360°回してみると、花がこちらを向いている! と思うポイントがあります。そこが花の正面であり、その面が前を向くように配置すると見栄えがよくなります。 2つ目のポイントは、苗を斜めに傾けて植えること。真上を見上げるようにまっすぐ植えるのではなく、やや外側に傾けて植えることで、全体的に丸いフォルムになり可愛らしく仕上がります。 実際にはまだんも苗を確認してみると、「あ! 花と目が合った!」と、花の正面がどこか分かるようになりました。正面を見極めることで花の顔が見えやすくなり、より魅力的な仕上がりになるのは、鉢植えだけでなく、フラワーアレンジメントやブーケ作りでも大事なポイントと言えますね。 必見! プロ直伝の苗木の植え付け手順 では、本題の苗木の植え付けに移ります。今回はブルーベリーの苗木を使って植え付けの方法をレクチャーしていただきました。 まず植えるための穴を掘りますが、掘り上げた土はまた戻すので、植え穴の周辺に積んでおきます。園芸初心者のはまだんは、「根鉢の体積を考えると、ある程度土は余りそうだけど…?」と、疑問に思いました。やんちゃ坊主のようなりゅりゅは、掘り上げた土を勢いにのってポーンと遠くに投げてしまいそうなところですが(笑)、それは待った! この土を残しておく重要性はこの後分かりますよ! そして、ジニアを鉢に植え付けた時と同様に苗木の正面を確認して穴の中に置き、深植えにならないよう高さを確認してみて、必要であれば土を戻して調整します。 最後に、周辺に積んでおいた土を植え穴へ戻しながら苗木の周囲にドーナツ状の土手を作ります。この「土手」を作る理由は何なのでしょうか? それは、植え付けた苗木にしっかり水を行き渡らせるため。「周りの土を地表より高く盛っておくことで、水が周囲にこぼれにくく苗に水がいきやすくなるんです。この土手のことを業界では“水鉢(みずばち)”と言うんですよ」と佐久間さん。なるほど、さすがはプロの技。ガーデニングを始めたばかりではなかなか知ることができないテクニックです。 その他の苗木や、地植え用のジニアとバーベナの花苗も手分けして植え付けます。おしゃべり好きなはまだんは、ふざけ合いながら楽しそうに庭作業を進めていきます。家族や仲間と一緒にガーデニングを楽しむ方も多いかと思いますが、植物を通して人とコミュニケーションを深められることもガーデニングの良さと言えますね。みんなで協力して作業することで、はまだんのチームワークもさらに高まったことでしょう。 水やりでフィニッシュ 植え付けたばかりの苗木への水やり方法も見てみましょう。先ほどのブルーベリーの苗木に水をやってみると、土手の内側の苗木周りに大きな水たまりができます。そしてある程度水が溜まったら幹を優しく揺すって隙間の空気を抜き、根鉢に水がしっかり行き渡るようにします(スコップや棒でつつくこともあります)。水が引いてきたら土手にしていた土を中心へ被せて整地し、終了です。 「ここまでレクチャーした植え付け・水やりの方法は“水極め(みずぎめ)”と言うんですよ」と佐久間さん。またいただきました、業界用語! 今回は、造園のプロに教えていただきながら苗木の植え付けや水やりについて学びました。苗木が根付いて健康に育つための基礎として、ぜひプロが行うテクニックを庭木や果樹を植え付ける際の参考にしてみてくださいね。 庭づくりの様子はYOKOHAMA男子公式YouTubeチャンネル「はまだんTV」にて公開しています。こちらもチェックしてみてくださいね。 動画のご視聴はこちらから https://youtu.be/XyLR16FmXrw YOKOHAMA男子プロフィール 2017年11月、「音楽の力で横浜そして神奈川を元気にしよう!」というコンセプトのもと結成。 神奈川県内のお祭りやイベントに積極的に参加、さらには横浜市内での路上ライブにも力をいれて活動しているほか、「神奈川県犯罪防止応援アイドル」として神奈川県警の詐欺防止運動にも取り組んでいる。今後は地域の食や文化そしてSDGsなど、アイドルの枠組みにとらわれずに視野を広げて、よりよい社会作りに貢献できるグループを目指す。 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbF2EyAywVpiReWvTqQgFlA Instagram: https://www.instagram.com/hamadan065/ Twitter: https://twitter.com/hamadan_11 Official Site: http://hamadan.yokohama/
-
観葉・インドアグリーン
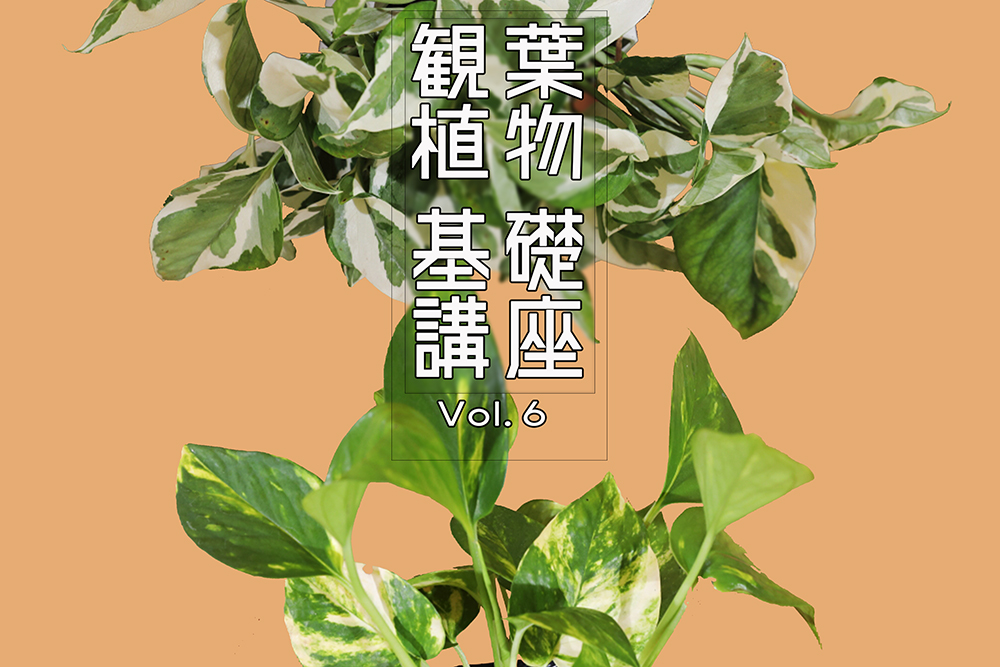
今イチ推しのポトス、プロが教えます! ポトスで始める観葉植物|観葉植物基礎講座 Vol.6
ポトスは定番中の定番 数ある観葉植物の中でも定番の人気を誇るポトス。オーソドックスなビジュアルは、決して主張しすぎることなく、瑞々しい存在感があり、住宅はもちろん、飲食店、オフィス、公共施設など、さまざまな場所で手軽に加えられるインドアグリーンとしても重宝されています。 ポトスという名称はスリランカの公用語シンハラ語の「potha(ポサ)」に由来しています。しかし、ポトスの原産地はフランス領ポリネシアのモオレア島と考えられています。名前の由来とされる言葉が原産地の言語ではないのは、一体なぜなのでしょう? その謎を、スリランカ駐日大使館が解決してくれました。 じつはスリランカもポトスの自生地であり、古くは有毒な雑草(確かにポトスには毒がある)という扱いだったそう。しかし今ではスリランカ国民もポトスを観葉植物として好んで育てている、とのことでした。スリランカでは、ポトスが雑草みたいに生えているなんて驚きですね! 日本ではポトスは明治時代から観葉植物として親しまれており、和名では黄金葛(おうごんかずら)と呼ばれてきました。現在は、ほとんどの園芸店がポトスの名前で販売していますが、この「黄金葛」という和名がいかにも富を呼んでくれそうだということから、縁起物としても知られており、風水的な見地でポトスを購入する方もいます。 多くの方がハンギングで楽しんでいるため、ツルが下垂する印象が強いポトスですが、原産地では薄暗いジャングルの地表あたりに自生し、気根と呼ばれる幹や茎から出た根を他の樹木に巻き付かせながら、上方向に伸びていきます。 【ポトスに花が咲く!?】 あまり知られてはいませんが、じつはポトスは花が咲く植物なんです。といっても、それは原産地で自生しているポトスの話で、それも10年に1度というタイミングで咲きます。しかし観葉植物として流通しているポトスの開花例は、かつて名古屋で1例あるといわれていますが、それも物証がなく生産者間での伝説というレベルの話なので、もしも花を見られたら、それはもう奇跡!! これが現地で確認されたポトスの花。何やらトウモロコシのようですが、サトイモ科特有の黄色い花軸に密集した肉穂花序(にくすいかじょ:肥厚した花軸の周囲に多数の小さな花が密生している状態)と、茶色く枯れた仏炎苞(ぶつえんほう:肉穂花序を包むために葉が変形したもの)が確認できます。 ポトスのプランツデータ 植物名:ポトス 和名:オウゴンカズラ(黄金葛) 学名:エピプレムナム・ピナツム 科目:サトイモ科 属名:ハブカズラ属 原産地:ソロモン諸島及び東南アジア 分布域:亜熱帯地域、熱帯雨林地域 葉の観賞期:常緑多年草なので通年 ポトスの特徴と魅力 ポトスは、主に東南アジアのソロモン諸島などの熱帯地域に自生するサトイモ科のツル性の植物です。光沢を放つ瑞々しい葉を付けたツルが、鉢から旺盛に垂れ下がる姿がとても印象的。多くの方がハンギングにしたり、棚やスツールに置いた鉢植えからツルを垂らして楽しんでいます。また、成長も早く、育て方が簡単なため、観葉植物初心者にはおすすめです。 ポトスには多くの園芸品種があります。最も多く目にするのは、葉にクリームイエローの不ぞろいな模様が入った‘ゴールデン’という品種。このほかにも、濃いグリーン1色の葉が特徴の‘パーフェクトグリーン’や、葉が縮れたタイプの‘テルノシャングリラ’など、園芸店で購入できる品種だけでも20以上あるため、「ポトス推し活」で園芸店めぐりをする人もいるほど、今人気の観葉植物なんです。 価格は500円以内で買えるものや、1,000円前後で買える吊り鉢タイプのものなど、さまざまです。レアな品種であったり、作り込んであるようなものだと値段も高くなりますが、それでも3,000円を超えるというのは稀で、とてもコスパのよい観葉植物でもあります。 ポトスの育て方 置き場所 ポトスは耐陰性の強い観葉植物です。これは、前述の自生地での環境に由来するもので、観葉植物として地下のレストランやカフェに置かれても、枯れずに生きていけるのはそのためです。逆に、遮るものもなく直射日光が長時間当たるような環境では、葉焼けを起こし、枯れてしまいます。 元気に育ってもらうために最適な置き場所は、レースのカーテン越しの優しい光が入る窓辺や同程度の明るさが確保できる場所。それが難しい場合は、前述のように耐陰性があるため、窓から離れた部屋の中心あたりに置いても問題ありません。 ただし、四季を通してエアコンの風が直接当たる場所は避けてください。そのような場所に長時間置いておくと、葉から水分を蒸発させる蒸散活動を阻害し、株がダメージを受けるからです。 【ポトスは幼児やペットの手の届かないところで育てましょう】 ポトスの葉や茎には毒素(不溶性のシュウ酸カルシウム結晶)が含まれており、大人はさほど気にかける必要はありませんが、万一幼児がそれらを口にした場合、呼吸困難に至る場合があります。また、ペットを飼っている方も同様に注意が必要です。それ故か、英語圏ではDevil's Ivy(悪魔の蔦)とも呼ばれています。 夏の管理温度、冬の管理温度 夏場の最適な温度は25〜26℃です。耐暑性が強いため30℃くらいまでは問題なく育てられます。しかし、窓を閉め切っていることの多い夏場は自然界に少しでも環境を近づけるために、天井にサーキュレーター(送風機)の風を送るなどして、部屋の空気を循環させてあげるのが望ましいです。 冬は10℃を下回らないように管理してください。耐寒性が弱いので、8℃を下回ると葉がしおれたり、落ちたりする場合があります。しかし、元来が丈夫な植物のため、10℃以上の環境に戻せば徐々にまた生えてきます。 水やり 春~秋の間は土の表面が乾いたらたっぷり与えます。冬は土の表面が乾いてから1日おいて、たっぷり与えます。受け皿に溜まった水は必ず捨ててください。 肥料 肥料は本来、決められた時期に決められた量をあげるものですが、ポトスは肥料との相性が大変よいため(肥料焼けを起こしにくい)、春~秋の間は、窒素が多い観葉植物用のタブレット肥料を2カ月に1回程度、やや多めに与えると葉の色艶がよくなります。 このほか、観葉植物用の液体肥料もあり、その場合は春~秋の間に週1回与えてください。ただし、タブレット・液体肥料共に、成長が鈍化する冬はあげないでください。 葉水の方法など、日常のお手入れ ポトスは空中湿度が高いほうが喜ぶので、葉水は毎日あげてもOKです。また、葉水はポトスにつきやすいカイガラムシやハダニの予防にもなります。 葉が旺盛に茂った株は、一部の葉が黄色くなり枯れることがありますが、枯れた葉は株の代謝維持のために、見つけ次第カットしてください。また、日焼けした葉も同様にカットしてください。 植え替え 株の成長を促すために2~3年に1回、春~秋の間に1〜2回り大きい鉢に植え替えてください。 特筆すべき栽培ポイント 【剪定と水挿し、挿し芽】 ツルが特徴のポトスですが、長くなりすぎたツルや葉は切って剪定しても大丈夫です。また剪定は株の形をこんもりとさせたいときにも有効です。こんもりとさせたい場合は、ツルを根元から10〜15cmほど残してカットし、そこから新しいツルが伸びて、3〜4枚の葉がついた頃に先端をカットします。こうしていくうちに、どんどん枝分かれしていき、やがてこんもりとした形になります。 水を張った容器に切ったツルを挿せば(水挿し)、水耕栽培を楽しむことができ、用土を入れた植木鉢に挿せば(挿し芽)、株分けをすることができます。 ただし、水挿しや挿し芽を目的としてツルを切る場合は、新芽が出ている節を残してカットしてください。節には成長点があり、これがないツルを挿しても発根しないので注意が必要です。また、残したツルに葉が多く残っている場合は、葉からの水分の蒸散を抑え、エネルギーを発根に集中させるために、葉は1〜2枚のみ残してあとは切ってください。 【病害虫】 定期的に葉水をして株を潤わせていないと、カイガラムシやハダニが高頻度で発生します。カイガラムシは残しておくと、どんどん広がり、患部も深くなるため、見つけ次第早急な駆除が望ましいです。効く薬剤が少ないため、歯ブラシやピンセットを用いて物理的に駆除します。ハダニの場合は、市販の殺虫剤を散布して駆除してください。 オザキフラワーパーク後藤さんが選んだ、推しのポトス6選 パーフェクトグリーン 【写真の商品】高さ15cm 店頭価格:680円(税込) 葉に斑(ふぞろいの模様)が入ったイメージが強いポトスにあって、‘パーフェクトグリーン’はその名の通り、潔いぐらいパーフェクトなグリーンの葉が持ち味。 ゴールデン 【写真の商品】高さ15cm 店頭価格:398円(税込) ポトスのアイコン的存在ともいえる‘ゴールデン’。一般に、ポトスといえばこの‘ゴールデン’を指します。一般的とはいえ、クリームイエローの斑とグリーンの織りなす美しい葉は、ずっと見ていると時間の経つのを忘れてしまいます。 斑の入り方は光の状態によって左右されます。明るいところで育てれば斑が多く入り、暗いところで育てると新芽に斑が入らず、‘パーフェクトグリーン’のような緑一色の葉になる傾向にあります。明治時代から日本に入っており、とても生命力が強いため、観葉植物初心者にもおすすめの品種です。 写真の商品は500円でお釣りの来る手乗りサイズですが、成長も早くあっという間に生い茂るため、コスパも最高なポトスです。 テルノシャングリラ 【写真の商品】高さ12cm 店頭価格:398円(税込) 巻き巻きの葉にびっくりする‘テルノシャングリラ’。これらの葉はこれから展開するわけではなく、この巻き巻きのまま成長していく、ちょっと珍しい品種です。 愛知県の育種家、伊藤輝則氏が作出した品種で、オザキフラワーパークでも入荷したらすぐに売れてしまう人気商品です。 名の由来を考えてみると、伊藤輝則氏(テルノ)の作り出した理想郷(シャングリラ)なんて、とてもロマンチックですね。ちなみに、伊藤輝則氏の作出した品種は、その名前を取り「テルノシリーズ」として、愛好家に人気なんです。 珍種のわりには価格も安いので、普通のポトス(ゴールデン)と一緒に育ててみるのも面白いですね。育て方は、通常のポトスの育て方と同様です。 テルノハナハナ 【写真の商品】高さ12cm 店頭価格:398円(税込) ‘テルノシャングリラ’同様、伊藤輝則氏が作出したテルノシリーズの‘テルノハナハナ’。淡く黄緑色の斑が入っていて、濃淡2色のグリーンを楽しめます。 全体的に爽やかな印象なので、写真のようにウッディーなインテリアや白壁映えのする、とてもおしゃれなポトスです。 テルノシャンゼリゼ 【写真の商品】高さ20cm 店頭価格:1,380円(税込) こちらもテルノシリーズ。ポトス・ライムというポトスの人気品種の枝変わり品種(元の植物の枝の部分の成長点が突然変異し、新たな品種となったもの)で、原種のライムより葉が肉厚で色も濃く、とても育てやすい品種です。 他のテルノシリーズよりも大きめの株で、ハンギング仕立てにして販売しています。ハンギング鉢も込みの値段なので、初めてのポトスにいかがですか? エンジョイ 【写真の商品】高さ15cm 広がり幅30cm 店頭価格:2,480円(税込) 斑の入り方が迷彩模様のような‘エンジョイ’は、オザキフラワーパークでも人気のポトスです。一鉢置くだけでお部屋の雰囲気が楽しげになり、品種名もハッピーな雰囲気なので、新築や引越しのお祝いとしても喜ばれます。 ‘エンジョイ’は、そのルーツもユニーク。もともとはインドの栽培農家が偶然発見した突然変異種でした。それがオランダに持ち込まれて商標を獲得し、その後アムステルダム郊外の街で毎年開かれる世界最大規模の花の品評会「アールスメールフラワーオークション」で、2007年のロイヤルフローラホラントアワードを受賞した品種なんです。 ちなみにこの賞は、世界の花市場の6割強を占めているオランダで、最も権威のあるロイヤル(王室)の名を冠した賞。そんなルーツを持つ‘エンジョイ’を贈ったら、贈られた人も喜ばれることと思います。もちろんご自宅にもおすすめです! 取材後記 この取材をしたあと、どこでどんなポトスに出会えるか、改めて自宅付近の店舗を歩いてチェックしてみました。 まず駅ビルのスイーツショップとスタバ、薬局、駅前の都市銀行、カレーチェーン店、不動産屋2軒、メガネ店、皮膚科、形成外科、整骨院、ジェラート専門店、パン屋、台湾料理屋、、、さすがにここでやめました(笑)。 ちなみにカレーチェーン店とジェラート専門店が‘ゴールデン’、それ以外は皆‘パーフェクトグリーン’でした。この調査でポトスが最もメジャーな観葉植物であるということを改めて実感しました。もしも、カツカレーを食べながら「あ、あそこにあるのパーフェクトグリーンだ。」とつぶやく人がいたら、それは完全に推し活中のポトスオタクです。 あなたも推しポトスを見つけて、推し活してみませんか?
-
園芸用品

家庭菜園におすすめの大人気プランター! 保育園での食農教育にも活躍する「ベジトラグ」
「ベジトラグ」とは? ベジトラグとは、イギリス生まれの菜園プランター。高さのあるレイズドベッド式になっていて、かがまずに水やりや雑草抜きなどの日頃のお手入れがラクにでき、車イスに座ったままでも作業ができるので、「バリアフリーガーデニング」を楽しめるアイテムとしても人気があります。 作業のしやすさだけでなく、植物にとっても、高さがあることで風通しと日照を確保しやすく、排水性・通気性にも優れ、プランター内が高温多湿になりにくいというメリットがあります。 また、プランター底部がV字形状になっているので、深い部分には根菜類、浅い部分には葉物野菜、というようにいろいろな野菜やハーブが混植できる点も魅力です。 ベジトラグには、さまざまなタイプとサイズが揃っているので、庭やベランダ、玄関先など、置き場所に合わせて選ぶことができます。 食農教育にベジトラグを取り入れた「アスク」保育園 そんなベジトラグが、最近とある場所で活躍しています。それは子育て支援事業最大手の(株)JPホールディングスのグループ会社、(株)日本保育サービスが運営する保育園です。 「ベジトラグで植物とともにある豊かな暮らしを多くの人に広めたい」という販売メーカーの株式会社タカショーの想いと、「自分たちで植物を育て、収穫して食べるという食農教育を実現したい」というJPホールディングスの想いが一致し、プロジェクトがスタートしました。 プロジェクトは、保育園にベジトラグ本体と土、肥料、野菜やハーブ・花の苗やタネが季節ごとに届くというもの。連作障害を防ぐために、使い終えた土を送り返すための「土回収キット」もついていて、植え替えの時期になったら、次の植物とともに新しい土・肥料が保育園へ届くという仕組みです。 保育園では、植え付けや日頃のお手入れを子どもたちと一緒に楽しみ、育った植物を観賞したり、収穫して料理やクラフトに活用したりなど、さまざまな形での食農教育が実現しています。 ベジトラグを活用中の保育園を訪問! 実際に保育園の現場ではどのようにベジトラグを活用しているのでしょうか。編集部は東京都西東京市にあるアスクひばりヶ丘保育園を訪問しました。 玄関先でベジトラグがお出迎え 門を入るとすぐに2つのベジトラグが目に入ってきました。一つは、奥にハクサイ、手前にオレガノとチャービルがたっぷり植わって、ベジトラグが緑でこんもり! そしてもう一つは、タネから植えて間もない小松菜が可愛く顔を出し始めていました。 ベジトラグは2021年夏頃に1台目、続いて2022年4月に2台目が導入され、以来、セットで届く野菜やハーブ、花を絶やさず植えて育てています。 「ベジトラグの置き場所は、日当たりがよく、子どもたちや保護者の方々が必ず通る玄関先と最初から決めていました。毎日みんなが利用する場所なので、保護者の方にも日々の変化を見て感じていただけます。行き帰りの時間に、植えられた植物について親子で会話しているのを見ると嬉しくなります」と語るのは園長の仲順明子さん。 スタッフと協力して試行錯誤しながら、植物を園の活動に活かし続けています。 「3〜5歳児クラスには苗やタネを植えるところから一緒にやってもらい、5歳児さんには日頃のお手入れも手伝ってもらっています。1〜2歳児さんも収穫のときに参加して、子どもたちも、自分たちが育てて大きくしたものを収穫できる楽しさを感じていると思います」(仲順さん) 収穫した野菜やハーブを給食に活用 アスクひばりヶ丘保育園では、ベジトラグの収穫物の活用方法について栄養士さんが中心になって考えています。ベジトラグで育てた新鮮な野菜やハーブは給食の食材として大活躍だそう。 「特にピーマンは採っても採ってもなくならないくらいの豊作で、色も緑や赤、オレンジなどカラフルで、子どもたちもとても喜んでくれました」と栄養士の花田絵里さん。 植物の植え方、育て方などの知識がないなかで、はじめは枯らしてしまう失敗もあったものの、失敗からの学びも多く、子どもたちと一緒に育てた食材を、子どもたちと一緒に収穫し、食べるという一連の流れは、とても良い「食農教育」になっていると言います。 「5歳児のクッキング保育では、収穫したバジルを使ってピザを作ったり、おままごとのように包丁でニンジンを切る練習をしたりもしました」(花田さん) 口にする以外にも、ハーブの香りを観察、にじみ出る汁で色をつける、型を取ってスタンプを作るなど、「自然科学」に触れる機会にも活用しています。 ベジトラグ活用の幅を広げていきたい ベジトラグを活用した食農活動の大きな魅力は、季節ごとに植える植物が土や肥料とセットで園に届くところ。季節に合った野菜やハーブの苗が適期に定期的に届き、栽培に必要な土や肥料も自動的に必要な分だけ届くため、迷うことなく植え付け作業が進められます。常に何かを育て続けることができ、ガーデニングライフを導いてくれる嬉しいシステム。ガーデニング初心者も安心して、1年で一通りの野菜やハーブ栽培の体験ができ、あっという間に初心者卒業です。 最後に、今後ベジトラグで挑戦してみたいことを伺ってみました。 「届くハーブの中には、あまり日常で料理に使ったことがない種類もありますので、活用方法をもっと知りたいと思っています。レシピの幅を広げていきたいですね」(花田さん) 「野菜やハーブは収穫した後にいろいろと活用できていますが、花は今のところ観賞用になっています。今後は花もアレンジメントなどに活用し、あらゆる形で子どもたちが植物と触れ合える機会を増やしていきたいと思います」(仲順さん) ベジトラグで楽しい菜園生活を! 保育園でのベジトラグ活用例をご紹介しました。機能的にもデザイン的にもこだわりを持って作られたベジトラグ、ご家庭でもお子さまと一緒に野菜や果物づくりを楽しむことができます。 ぜひこの春は、ベジトラグで楽しい菜園プランター生活を始めましょう! 取材協力 株式会社日本保育サービス https://www.nihonhoiku.co.jp/ アスクひばりヶ丘保育園 https://www.nihonhoiku.co.jp/blog/hibari/ Credit ガーデンストーリー編集部 ベジトラグ販売ページ https://aoyama-garden.com/shop/c/c1701/
-
イベント・ニュース

ガーデニングビギナーの男性アイドルが「グリーンアドバイザー」資格取得に挑戦! 結果は…?
グリーンアドバイザーとは? グリーンアドバイザーとは、公益社団法人 日本家庭園芸普及協会が認定する資格で、植物の栽培に関する正しい知識を持ち、園芸の魅力・楽しみ方を伝えられる人に与えられる資格です。ガーデニング人気が高まる中、園芸・ガーデニングに関する適切な指導やアドバイスができる人材が広く求められており、2023年現在、全国に約11,000人いる有資格者は、園芸相談員やセミナー講師、園芸店の販売員、造園業、学校・研究機関、園芸関係の地域活動など、さまざまな分野で活躍しています。 グリーンアドバイザーの資格については、過去の記事でも詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。 初めてのガーデニングにチャレンジしながら勉強に奮闘 ガーデンストーリーの「庭づくり企画」をきっかけにガーデニングをスタートしたはまだん。メンバーの中から、戸田健太さん(通称たっつん)と富田慧太郎さん(通称けいたる)の2人がグリーンアドバイザーの受験を決意しました。 受験に当たっては、認定講習・試験の申し込みと受験料の振り込み手続き完了後、協会が独自に作成した認定講習テキストが届き、このテキストとインターネット配信による講習動画の視聴を通じて学習を進めます。 「テキストは大ボリュームで、園芸にまつわる幅広い知識が網羅されています。僕たちのようにまだガーデニングの経験が少なかったり、知識に不安がある人は、早めに申し込みをして勉強をスタートするのがおすすめです」と富田さん。 また、戸田さんは「アイドル活動と並行して勉強を進めるのはハードに感じることもありましたが、講習動画は受講期間中ならいつでも視聴が可能なので、移動中にスマートフォンで視聴するなど自分の都合に合わせて学習しやすい点がよかったです」と、猛勉強した約4カ月間を振り返りました。 はまだんの庭づくりに関する記事はこちら きっかけは、グリーンアドバイザーの資格を持つ先輩のアドバイス グリーンアドバイザーを知ったきっかけは、彼らが庭で育てる花や野菜のタネを探しに行った、サカタのタネ ガーデンセンター横浜でのこと。店内を案内してくださった、サカタのタネの清水俊英さんが「植物の正しい知識を身につけてガーデニングを深く楽しみたい! と思ったら資格を取得するのもおすすめ」と紹介してくれたのです。そんな清水さんも、グリーンアドバイザーの資格を持つ先輩の一人です。 グリーンアドバイザーを認定する公益社団法人 日本家庭園芸普及協会は、「フラワー&ガーデンショウ」や、学校緑花、たねダンゴ普及をはじめとするさまざまな事業の企画や運営に携わっています。グリーンアドバイザーの資格を取得すると、これら協会主催のガーデニングの楽しさを伝えるイベント活動への参加機会が得られるのです。 いざ受験! 結果は…? 2022年度の試験は9月に全国で行われ、横浜住まいの彼らは東京の会場で試験に臨みました。そして受験から1カ月後、ついに緊張の結果発表です。 その結果は…… 2人とも見事合格! 猛勉強の努力が実を結びました。フラワーデザイナーとしてプリザーブドフラワーのアレンジメント作品の制作・販売で全国の百貨店を飛び回るリーダーの戸田さんは「ガーデニングの知識が深まったことで、園芸が好きなお客さまとのコミュニケーションの幅が広がったり、より意欲的にガーデニングを楽しめるようになりました。今後は園芸に関するイベントやセミナーに積極的に参加したい!」と話してくれました。彼らの今後の活動にも注目です。 CBT方式導入で受験しやすい! グリーンアドバイザー試験の特徴 2023年度からはCBT方式(全国のテストセンターに設置されたコンピュータ端末を使って受験する試験方法)が導入され、地方在住の方も受験がしやすくなりました。2023年9月1日~30日の期間内で都合の合う日時と、全国300カ所以上あるテストセンター(試験会場)の中から1カ所を選んで受験します。試験予約日の3日前までなら、受験会場と日時を無料で何度でも変更可能なので、仕事が忙しい方や引っ越しを控えている方も、安心して受験することができますよ。 園芸関連の資格として30年以上の歴史があるグリーンアドバイザーは、園芸業界で働く方はもちろん、趣味でガーデニングを楽しむ方など、幅広い層の方々が受験されています。ガーデニングの知識を深めるだけでなく、園芸にまつわるさまざまな分野での活動に生かすことができるグリーンアドバイザー。興味がある方は、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか? 4月3日から申し込みスタート! 2023年度グリーンアドバイザー講習・試験概要 講習・試験の申し込み期間 2023年4月3日(月)~8月31日(木) 試験実施期間・会場 2023年9月1日(金)~9月30日(土) ※期間中の1日を選んで受験 全国47都道府県の合計約300カ所のテストセンターから会場を選んでオンラインで予約。 ※試験予約日の3日前まで、受験会場・日時は何度でも無料で変更可能。 受講・受験料 ◯一般:40,700円(税込) ◯学生:20,350円(税込) ◯再受講・受験:29,700円(税込) 申し込み方法 オンラインのみ。申し込み専用ページは、公益社団法人 日本家庭園芸普及協会のウェブサイトにて2023年4月3日(月)以降公開。 詳細はhttps://www.kateiengei.or.jp/greenadviser/examinationをご確認ください。 合格発表 グリーンアドバイザー認定審査会が合否判定を行った上で、2023年10月17日(火)正午に受験者マイページにて発表予定。 詳細・お問い合わせ 公益社団法人 日本家庭園芸普及協会 電話:03-3249-0681 メール:ga-work@kateiengei.or.jp ウェブサイト:https://www.kateiengei.or.jp/greenadviser/examination グリーンアドバイザーになろう! 資格取得を目指す方であれば、誰でも受験できるグリーンアドバイザー。園芸業界で働く方だけでなく、一般の方で「園芸の知識を深めたい」「自身の活動や交流を広げて、園芸の仲間を増やしたり地域活動に参加したい」という思いを持つ方にもおすすめの資格です。 2023年度の受講・受験申し込みは4月3日(月)から。受験を検討される方は、ぜひ協会ウェブサイトをご覧ください! YOKOHAMA男子プロフィール 2017年11月、「音楽の力で横浜そして神奈川を元気にしよう!」というコンセプトのもと結成。 神奈川県内のお祭りやイベントに積極的に参加、さらには横浜市内での路上ライブにも力をいれて活動しているほか、「神奈川県犯罪防止応援アイドル」として神奈川県警の詐欺防止運動にも取り組んでいる。今後は地域の食や文化そしてSDGsなど、アイドルの枠組みにとらわれずに視野を広げて、よりよい社会作りに貢献できるグループを目指す。 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbF2EyAywVpiReWvTqQgFlA Instagram: https://www.instagram.com/hamadan065/ Twitter: https://twitter.com/hamadan_11 Official Site: http://hamadan.yokohama/
-
ガーデニング

アイドルが家庭菜園に初チャレンジ! 栽培レポート〜はまだんの「ステキなお庭をつくろう!」企画Vol.7〜
イギリス生まれの家庭菜園プランター「ベジトラグ」の植物 夏のベジトラグ菜園の主役は、もりもりに育ったピーマン! ベジトラグに植えた2つの苗は、初夏から一気に生長していき、プランターに覆い被さるまでに大きくなりました。 撮影時の7月中旬頃には、ぷっくりと膨らんだピーマンが軽く20個は収穫できたほど。隠れていた赤ちゃんピーマンたちもその後次々に大きくなり、最終的には一苗から40〜50個実り、はまだんハウスの庭で一番の収穫量となりました。 ピーマンは家庭料理で使いやすい食材なのも嬉しいポイント。定番の肉詰めや野菜炒め、青椒肉絲などはもちろん、パリパリピーマンといったおつまみ系でも活躍しますが、採れたてのピーマンで作る料理は格段の美味しさだったと喜んでいました。 こちらは、同じくベジトラグに植えていたローズマリー。常緑のローズマリーは、料理の香り付けやハーブティーなど、使いたい時にいつでも収穫できます。料理の他にも、リースにして楽しむなどさまざまな活用法があります。 ハーブにはあまり馴染みがないはまだんでしたが、メンバーのたっつんとけいたるは、グリーンアドバイザーの受験勉強にローズマリーを活用しました。ローズマリーに含まれる成分には、頭をすっきりとさせ集中力を高める作用があるので、ローズマリーの葉を擦ってかたわらに置き、勉強に励みました。 ちなみに、2人のグリーンアドバイザー受験の合否については改めて発表いたしますので、どうぞお楽しみに! 地植えや鉢植えの花 地植えと鉢植えでは、タネからの栽培にチャレンジしました。まず、地植えのコーナーの足元には、平弁の八重咲きマリーゴールド‘サファリ’が黄色とオレンジの元気な花を咲かせました。開花期が長く、ビタミンカラーが鮮やかなマリーゴールドは、庭に彩りを加えるだけでなくコンパニオンプランツとしても活躍してくれます。今回は虫を駆除するための薬剤は使用せずに自然の姿も観察しながらガーデニングを楽しみました。そんなわけで写真にも写っている通り、バッタが花の上に鎮座する姿が見られましたが、メンバーのりゅりゅは「花もバッタも可愛いなぁ〜」としばし観察。そして、そんなりゅりゅが一番の期待を込めて育てたアサガオの‘ヘブンリーブルー’は… 8月中旬頃に、爽やかな花を咲かせてくれました。りゅりゅ、やったね! 夏場の暑い中、こまめに様子を確認して世話をした努力が実を結びました。 また、同時に育て始めたアサガオの‘フライングソーサー’も、花ごとに少しずつ異なる模様を見せて楽しませてくれました。一日花であるアサガオは、タイミングを逃すとその花姿を拝むことができません。それぞれイベントやレッスンなど外出が多いメンバーは、アサガオが咲いたのを発見すると、スマホで撮影して見せ合いながらアサガオの花を楽しんでいました。 アサガオと並んで夏の花の代表格であるヒマワリは、ゆうだいがセレクトした大輪咲きの‘ロシア’。タネまきから約1カ月後の6月には30cm〜1mほどに生長し、支柱を立てて誘引を開始しました。7月にはゆうだいの身長ほどに生長し、地上部が倒れないよう上部も誘引。どこまで大きくなるんだ?! と思うほどダイナミックなヒマワリにメンバーたちは大興奮でした。 そして7月下旬には草丈は頭上を大きく超え、ヒマワリははまだんハウスのほうを向いてニッコリと笑うように元気に開花。「エネルギーにあふれるその姿を見てパワーをもらえた!」とゆうだい。 さて、花を楽しんだ後に収穫したタネはというと、編集部員の愛ハム(?)が美味しくいただきました。普段、カロリーの高いヒマワリのタネはなるべく控えているこちらのハムスター君、差し出された数粒のタネを嬉しそうに頬張っていました。食いつきがよかったので、やはり好物なんだな、と実感する飼い主でした。 地植えの野菜 地植えの野菜は、エダマメとインゲンを栽培。育苗している間はややヒョロヒョロしていて心配だった早生種のエダマメですが、7月の上旬頃から収穫できるように。このエダマメは、3粒莢になる確率が高いと言われている‘いきなまる’という品種ですが、コンパクトな草姿ながら立派な莢のエダマメが次々となり、何度も収穫を楽しむことができました。 そんなエダマメには、虫の痕跡が。葉が網目状に透けた状態になったのを見て「これはコガネムシの仕業だよ」と教えてくれた住友化学園芸の牛迫さん。 葉を食害するのはコガネムシの成虫です。見た目には多少食い荒らされた印象ですが、実の収穫にはあまり影響がないため、特別な防除はせず見守りながら栽培を続けました。これには、「害虫に関する知識が増えて勉強になった!」と、グリーンアドバイザー受験に向けて勉強中のたっつんとけいたる。 そして最後。始めはタネが発芽せずに二度目の種まきチャレンジをしたインゲンは、6月に立てた支柱を伝ってつるがグングン伸び、「多分、この支柱では収まりきらないくらい伸びるよ」と、牛迫さんに助言された通り、最終的にはつるが行き場をなくすほどに生長! こちらは早どりの品種のため、タネまきの約50日後から最初の収穫がスタート。地際から実がなり始め、1カ月ほどは収穫が続きました。気がついたらたくさんなっていた! なんてこともしばしばで、写真のように莢がパンパンになることもありましたが、メンバーで美味しく、楽しみました。 フラワーアーティストで手先が器用なリーダーのたっつんは、料理もお手のもの。収穫したインゲンで作ったパスタをお披露目してくれました。インゲンの食感がほどよく、美味しく仕上がったそう。Instagramでたびたび野菜を取り入れた料理配信を行っているたっつんは、「自分で一から野菜を育てて、収穫、調理まで体験できたのは貴重な経験。今度は、大好物のトマトを栽培してみたいです」と語ってくれました。 庭づくりの様子はYOKOHAMA男子公式YouTubeチャンネル「はまだんTV」にて公開しています。こちらもチェックしてみてくださいね。 動画のご視聴はこちらから https://www.youtube.com/channel/UCbF2EyAywVpiReWvTqQgFlA YOKOHAMA男子プロフィール 2017年11月、「音楽の力で横浜そして神奈川を元気にしよう!」というコンセプトのもと結成。 神奈川県内のお祭りやイベントに積極的に参加、さらには横浜市内での路上ライブにも力をいれて活動しているほか、「神奈川県犯罪防止応援アイドル」として神奈川県警の詐欺防止運動にも取り組んでいる。今後は地域の食や文化そしてSDGsなど、アイドルの枠組みにとらわれずに視野を広げて、よりよい社会作りに貢献できるグループを目指す。 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbF2EyAywVpiReWvTqQgFlA Instagram: https://www.instagram.com/hamadan065/ Twitter: https://twitter.com/hamadan_11 Official Site: http://hamadan.yokohama/






















