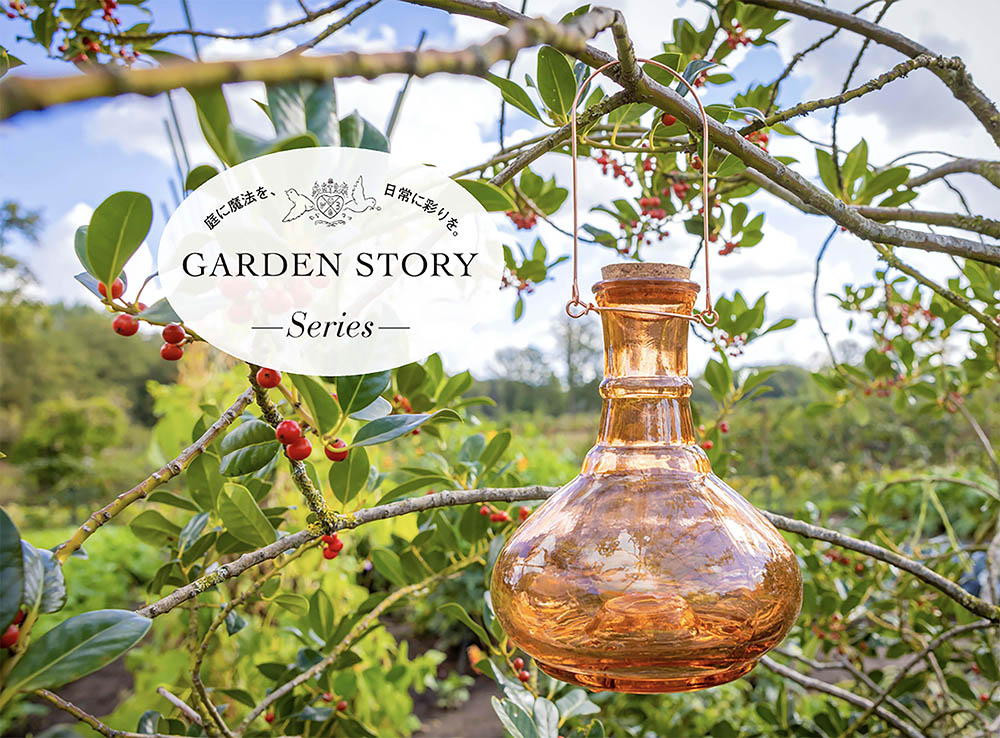- TOP
- 花と緑
- おすすめ植物(その他)
- マストバイ“こぼれ種(こぼれだね)・神7” 植えっぱなしで、よく増え、かわいい!
一度植え付けたら、タネがこぼれて毎年咲く “こぼれ種”の植物。これといって特に世話をしなくても、勝手に発芽し年々増えてくれるので、ローメンテナンスかつコスパも最高! なかには、こぼれ種から思いもよらない花を咲かせてくれるものも。楽しみがたくさんあるこぼれ種の植物の中から、ガーデナーがおすすめする厳選7種をご紹介します。
目次
こぼれ種とは
植物のほとんどは花の後にタネをつけます。そのタネから次世代が育つわけですが、どれも勝手に大きくなるわけではありません。ある種類の植物は意図的にタネを採り、その植物が好むよう栽培環境を整えたうえで、苗床に改めてタネを播き、日々世話をしないと育たないものもあります。一方、地面に落ちたタネから勝手に発芽し、勝手に育つ種類もあります。後者の勝手に増えるタイプを「こぼれ種で増える植物」といいます。勝手に増えるため、英語では「self-sowing(勝手に種まき)plants」とも呼ばれます。基本的に丈夫で、育てるのにも手がかかりません。
こぼれ種のメリット

前述の通り、特に世話をしなくても勝手に発芽して育ち、また再びタネがこぼれて発芽する、ということを繰り返し、どんどん増えてくれるコスパのよさが、こぼれ種の植物の最大のメリットです。加えて、雨風で運ばれたり、虫たちによって移動されたりして、思いもよらないところから芽を出しナチュラルな庭風景を作ってくれるのも大きな魅力。レンガの隙間や小径の脇などに繁茂すると、何年も経た庭のような雰囲気が生まれます。
- よく増えてコスパがいい
- 丈夫でローメンテナンス
- ナチュラルな雰囲気になる
という3つがこぼれ種のメリットです。
ガーデナーがおすすめする“こぼれ種”の植物
ここからは、庭で多くのこぼれ種の植物と上手に付き合っている面谷ひとみさんに、その魅力とおすすめの7種を紹介していただきます。
ワスレナグサ/一年草扱い/開花期3〜5月

春に水色の小さな花を咲かせるワスレナグサ。原生地では多年草ですが、暑さに弱く日本では夏に株がいったん枯れるので、一年草扱いです。しかし、こぼれ種でよく増える植物の代表選手で、毎年、どんどん増えていきます。春の初めの頃から咲き出し、スイセンなどの球根花のそばで彩りを添えてくれる名脇役です。咲き始めは小さく愛らしい姿ですが、季節が進むにつれて勢いを増し、草丈が高くなっていきます。
「バラなどよく肥料をあげる植物の側では、1株が上の写真の5〜6倍に大きく育ち膝丈くらいにまでなります。増えるのを喜んで何もしないでいたら、庭がある年真っ青になってしまって、ほかの花が全然育たなかったことがあります。それ以来、春の芽出しのまだ小さな頃に掘り上げて間引いたり、移植するなどしています」(面谷ひとみさん)



「ちなみに、こちらはワスレナグサによく似たオンファロデス‘スターリーアイズ’、宿根草です。かわいいので増やしたいのですが、この花はこぼれ種では全く増えないので、大事にして株を太らせ、毎年、少しずつ増やしてきました。こんなふうに、植物の全てがこぼれ種で育つわけではないので、毎年様子を見ながら特性に合わせて上手に付き合うようにしています」(面谷ひとみさん)
セントランサス/宿根草/開花期5〜6月

英国ではコンクリートの割れ目や屋根の上にも生えている丈夫な花。宿根草なので、毎年同じ株から咲くのに加え、こぼれ種で庭の思いがけないところからも咲きます。白花と赤花があります。
「草丈50〜60cmで、ちょうどバラの開花期に咲いてくれて、レースのような繊細な花がバラと相性ぴったりです。こぼれ種であちこちから生えてくるので、白花は白いバラの側など、咲かせたい場所に移動して育てています」(面谷ひとみさん)
シャーレーポピー/一年草/開花期5〜6月

色も花形も豊かなバリエーションがあり、赤の一重から八重、ピンクや覆輪など、咲いてみるまでどんな花か分からないサプライズ感が楽しいポピーです。根が真っ直ぐに下に生える直根性で移植を嫌うので、移動したい場合は、ごく小さいうちに根を傷つけないように深く掘り上げます。こぼれ種から発芽して11月くらいに幼苗ができている場合があるので、よく観察しましょう。
ニゲラ/一年草/開花期4月下旬〜7月

「Love in a mist(霧の中の愛)」というロマンチックな別名を持つニゲラ。糸状の葉っぱの中にブルーの花を咲かせ、爽やかな彩りが魅力です。草丈は50〜60cmで、4月から7月まで次々に花を上げます。病害虫被害もほとんどなく、非常に丈夫。花後、小さな風船のようなタネ袋ができますが、そのタネ姿も愛らしいです。そのまま刈り取らずにいると、風船が弾けて中からタネがこぼれ、翌年も発芽します。
「ちょうどバラと開花期が重なり、ふんわり柔らかな雰囲気で咲いてバラを引き立ててくれます。バラにはブルーの色がないので、合わせるととても素敵です。繊細な花の雰囲気とは裏腹に、とても丈夫で、こぼれ種で駐車場のコンクリートの隙間からもたくさん生えてきています」(面谷ひとみさん)

イングリッシュデージー/多年草/開花期3〜5月

ヨーロッパに自生する原種のデージー。花径2cmほどの小さな花で、ヒナギクとも呼ばれます。丸い黄色の花心に白い一重の花弁が野原のような素朴な雰囲気。こぼれ種でよく増え広がっていきますが、草丈が10〜15cmと低いので、増えても邪魔になることはありません。むしろグラウンドカバーのように地面を覆い、雑草が生えるのを防いでくれます。

オキナグサ/多年草/開花期4〜5月

赤紫のうつむいて咲く花と銀葉の草姿が美しい多年草。花後はふわふわとした綿毛のようなタネができ、風で飛んで増えていきます。園芸では山野草にも分類され、風に揺らぐ自然な花姿が魅力。落葉樹の下など、少し日陰になるところを好んで増えていきます。
セリンセ・マヨール/一年草/開花期4〜5月

シルバーがかった青緑の葉に、青紫のグラデーションの花が不思議な魅力の一年草。茎の先がくるっと曲がる花姿もユニークで、派手さはないのに庭で目を引く存在です。

「小さな1株が、こぼれ種で増えてこんなに大きな群生になりました。バラの肥料が効いているせいか、草丈も70cmくらいまで大きくなります。増えすぎた分は株が小さい芽出しの頃に掘り上げて、寄せ植えなどに利用しています」(面谷ひとみさん)

こぼれ種はコントロールしよう

こぼれ種はよく増えるがゆえに、増えすぎて困るケースがあります。庭中がこぼれ種の植物でいっぱいになってしまうと、ほかの植物がその陰になったり、栄養を取られて育たなくなることも。そんな場合は、間引くなどの引き算のコントロールが必要です。発芽したばかりの幼苗のうちなら、シャベルで根っこごと掘り起こして別の場所へ移植することもできます。咲かせたい場所に移動したり、間引いたりして、こぼれ種の植物と上手に付き合いましょう。
Credit
アドバイス / 面谷ひとみ - ガーデニスト -
おもだに・ひとみ/鳥取県米子市で夫が院長を務める面谷内科・循環器内科クリニックの庭づくりを行う。一年中美しい風景を楽しんでもらうために、日々庭を丹精する。花を咲き継がせるテクニックが満載の『おしゃれな庭の舞台裏 365日 花あふれる庭のガーデニング』(KADOKAWA)が好評発売中!
- リンク
写真&文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!
- リンク
記事をシェアする
新着記事
-
育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR
今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…
-
ガーデン&ショップ

【秋の特別イベント】ハロウィン色&秋バラも開花して華やぐ「横浜イングリッシュガーデン…PR
今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、10月31日(金)まで「ハロウィン・ディスプレイ」…
-
イベント・ニュース

まちづくりを支える花とみどり…みつけイングリッシュガーデン、一人一花運動、中之条ガーデンズの事例 〜…
40年以上の歴史を持つ老舗業界専門雑誌『グリーン情報』最新号から最新トピックスをご紹介! 2025年9月号の特集は、「まちづくりを支える花とみどり」。そのほかにも、最新のイベント紹介はじめ園芸業界で押さえて…