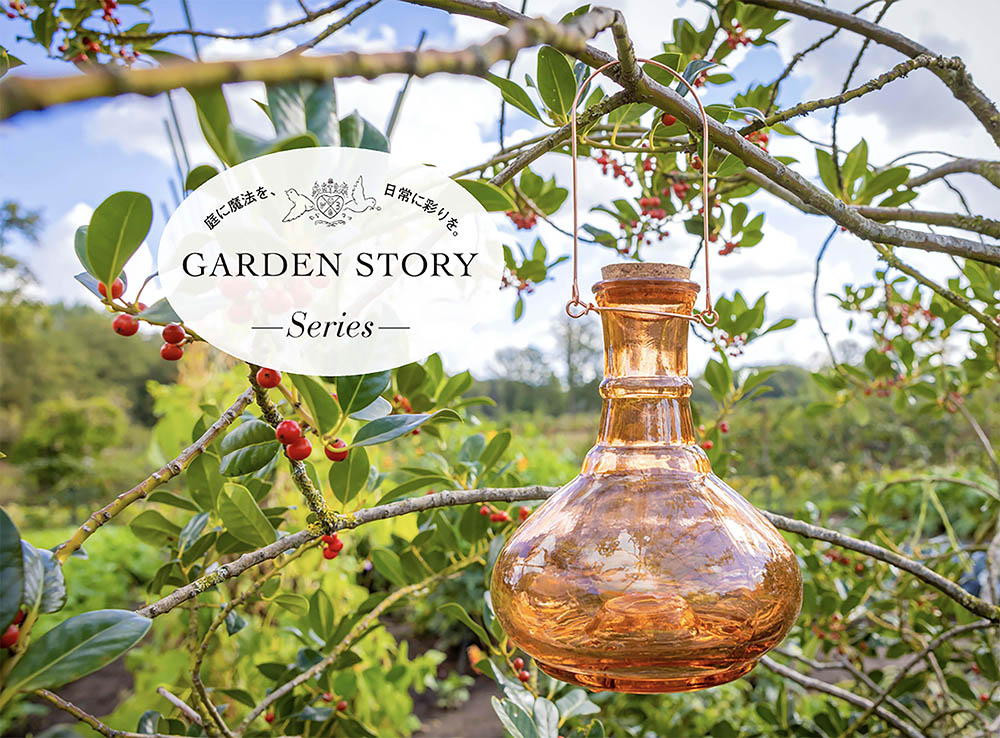- TOP
- 花と緑
- 観葉・インドアグリーン
- 【観葉植物】フィカス・ウンベラータの育て方! 上手な栽培のコツを大公開
【観葉植物】フィカス・ウンベラータの育て方! 上手な栽培のコツを大公開

patchii/Shutterstock.com
フィカス・ウンベラータという植物をご存じですか? 近年、インドアプランツとして多くの人から親しまれている樹木タイプの観葉植物で、薄く軽やかな可愛いハート形の大きな葉を茂らせます。さまざまなサイズや樹形に仕立てることができるので、部屋の大きさや雰囲気に合わせてお気に入りを選べること、そして何より丈夫で育てやすいことが人気の理由。この記事ではフィカス・ウンベラータの育て方について徹底的に解説します。
目次
フィカス・ウンベラータってどんな植物?

フィカス・ウンベラータは、アフリカ熱帯雨林気候地域原産のクワ科の植物です。自生地では樹高10m程度にまで育ちますが、日本でインドアプランツとして購入できるのは、50cmから1.8m程度のものが一般的です。
ゴムノキに似た雰囲気がありますが、ゴムノキもウンベラータと同じクワ科フィカス属の植物です。ベンジャミン(フィカス・ベンジャミナ)などと比べると葉が大きくて薄く、ツヤがありません。また、表面にはしっかりとした葉脈があり、よりナチュラルな樹木のたたずまいがあります。
シーグレープというインドアプランツの葉とも似ていて混同されがちですが、シーグレープの葉が丸くうねりがあるのに対して、ウンベラータはより幅広でハート形をしているので区別できます。
明るい場所でももちろん育ちますが、耐陰性があるため少し暗い場所に置かれてもすぐに適応し、問題なく育てられます。自生地では常緑ですが、置かれた環境、特に気温が低いと葉を落とすことがあります。しかし、もし冬に葉を落としても枯れてしまったわけではなく、暖かくなれば再び新芽を出してきます。2週間に1回程度、土の表面が濡れる程度にサッと水やりをして春を待ちましょう。
フィカス・ウンベラータの基本情報

ウンベラータはクワ科イチジク属の樹木で、学名をフィカス・ウンベラータ(Ficus umbellata)といいます。
大きな葉っぱがまるで「日傘(umbella)」のように見えることが名前の由来となっています。
もともとはアフリカの熱帯雨林地方に自生し、暑さには強いのですが、寒いのはちょっと苦手です。成長速度が非常に速く、自生地では樹高10mにも及びますが、前述のように日本では50cm〜1.8m程度の樹高のものがよく販売されています。
よく育つので、いらない枝を剪定して好みの樹形を作ることも比較的簡単です。それほど強い光を必要としないため室内でも楽しむことができます。
花言葉は「永久の幸せ」「すこやか」「夫婦愛」など、平穏な幸せを感じさせるものばかりです。
風水では恋愛運上昇とリラックス効果があるとされます。
日本では流通量も多く、3,000〜20,000円で買い求めることができます。
フィカス・ウンベラータが好む環境

フィカス・ウンベラータは置かれた環境に順応しやすく育てやすい植物ですが、ポイントを押さえることで、より失敗なく育てられることでしょう。ここでは、ウンベラータが好む環境について解説したいと思います。
フィカス・ウンベラータの栽培温度

フィカス・ウンベラータの自生地は、中央アフリカを中心とした熱帯雨林の森です。
そのため本来は高温多湿の環境を好みますが、周囲の環境になじみやすい性質があり、日本の環境下でも冬を除いて問題なく育てることができます。
熱帯原産ということもあり、寒さには弱いという一面があるため、温度の低下に伴って葉を落とし、休眠する場合もあります。枯死の危険を避けるために、冬期の温度管理については5℃を下回らないようにしましょう。
春から秋は戸外で育てることもできますが、肌寒さを感じる時期(最低気温が15℃程度)になったら、室内に取り込みましょう。
屋内管理の場合、リビングのようにできるだけ暖かくて寒暖差の少ない場所に移動するなどの工夫をすることで、休眠に入らず成長を続けることができます。もし葉を落として休眠してしまったら、できるだけ暖かい場所に置いて休眠が明ける気温になるのを待ちましょう。
フィカス・ウンベラータが好む日当たり・置き場所

フィカス・ウンベラータは適度に明るい場所を好みます。
屋外であれば、冬期を除いて問題なく育てられます。ただ日光が強すぎると葉焼けを起こしてしまうので、真夏の直射日光にさらすことはやめましょう。夏の間は午前中だけ日が当たる場所や日陰に移したり、30~50%程度遮光できる寒冷紗をかけるとよいでしょう。冬は室内や保温できる環境に移動します。
ウンベラータは多少の暗い場所でも育てることができるため、インドアプランツとして人気が高いです。
屋内で丈夫に育てる際のポイントとしては、レースのカーテン越し程度の明るさのある風通しのよい場所に置くことです。屋外同様、直射日光が当たる場所は、やはり葉やけの心配があるので避けましょう。耐陰性があるため、蛍光灯の明かり程度でも育てることができます。ただその場合でも、日中はできるだけ明るいところに移動させたほうが徒長の心配もなく、丈夫に育ちます。
フィカス・ウンベラータを育てる用土

自生地は熱帯雨林のため多湿の環境を好みます。用土は保水性のあるものを。すでにブレンドされた観葉植物の土などでもよいでしょう。しかし保水性が高すぎる、水はけの悪い用土を使うと屋内では特に根腐れを起こしやすいので注意しましょう。
生育環境に合わせて赤玉土や鹿沼土を混ぜ込み、水はけを調整しましょう。ただし、腐葉土などがブレンドされているとコバエが発生する場合があります。土の表面を赤玉土や鹿沼土、化粧砂など無機質の用土で覆うと見た目もよく、コバエなどの発生予防にもなるのでおすすめです。
フィカス・ウンベラータに必要な水やり

春から秋の成長期の水やりは、表土が乾いたタイミングで鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えてください。根がしっかりと育っている株であれば乾燥にもある程度耐えることができるので、神経質になることはありません。結構乾いてしまったなというくらいでも問題ありません。むしろ室内管理の場合は、特に水やりのしすぎによって根腐れしやすいので注意。常に用土が濡れているという状態は避け、鉢内の空気を入れ替える意味でも、用土内の水分をすべて入れ替えるイメージで、鉢土が乾いたのを確認してからたっぷりと与えてください。またウンベラータは多湿の環境が好きなので、葉水をすることでより健全に育てることができます。大きな葉には埃がたまったり、ハダニが発生したりするので、葉水のときには表面だけでなく裏面にもしっかりと水を吹きかけましょう。秋以降葉を落とし、休眠してしまったら水やりの頻度を減らし、乾燥気味に管理しましょう。
フィカス・ウンベラータに必要な肥料

肥料を与えることで小さな鉢でも大きく育てることができます。施肥の時期は春から秋の成長期ですが、2カ月に1度を目安に、緩効性肥料を与えていれば問題ありません。成長が活発になる夏などは、併せて2週間に1度程度、規定の倍率に薄めた液体肥料を与えるのもよいでしょう。生育スピードの低下に合わせて施肥も減らしていきましょう。また市販の用土は肥料が混ざっている場合もあるので、植え替え時には肥料過多にならないよう確認しましょう。
フィカス・ウンベラータ栽培、その他のポイント

フィカス・ウンベラータは環境の変化に順応しやすく、日向でも日陰でも育てることができます。反面、屋内から屋外、屋外から屋内などのように急に環境を変えると、変化に耐えられず葉が傷んでしまったり、落葉したりすることがあるので注意が必要です。ただ丈夫なのでそれで枯れることはほとんどなく、しばらくすると新しい葉が展開してくるので、慌てずに様子を見てください。
屋外、屋内共にその場所をおしゃれに、そして素敵に彩ってくれるフィカス・ウンベラータですが、フィカス属の樹液には有毒な成分が含まれているので、ペットや幼児の誤食、また肌の弱い人が素手で触ることなどには注意が必要です。ペットや幼児の手が届かない位置に置いたり、剪定の際などにはゴム手袋をして、樹液を直接触らないように気をつけましょう。
【お手入れ編】フィカス・ウンベラータの育て方

ここまではフィカス・ウンベラータの基本的な育て方について解説してきました。ここからは、より具体的に日々のお手入れ方法について解説したいと思います。
フィカス・ウンベラータの剪定

フィカス・ウンベラータの成長期は春から秋です。その間は旺盛に葉を展開し、茎を伸ばします。枝葉が重なってしまうと通気が悪くなり、病気や害虫の発生源になることがあるので、バランスを見て剪定するとよいでしょう。また、新しい葉の展開と共に古い葉が落葉することがあります。そのため下部の葉が黄色くなってきても心配ありません。黄化した葉は早めに処分しましょう。また枝が伸びてきたら、節の少し上の位置で切ると脇芽が出てきます。剪定した枝は適切な処置をすれば挿し木として利用できたり、花瓶などに活けてインテリアグリーンとしても活用できます。
剪定時に注意することは、前述のように樹液には人体に有毒な成分が含まれているので、できるだけ触らないようにすること。もし触れてしまったときは流水でよく洗い流すようにしましょう。
フィカス・ウンベラータの増やし方

フィカス・ウンベラータの増やし方は「挿し木」と「取り木」が基本です。挿し木をする場合は枝の先端から2〜3枚目の葉の下5cmくらいのところで切り、葉は全部落とすか、半分に切ります。
これは、必要以上に枝の内部にある水分が蒸散するのを防ぐためです。
切り口から出る樹液を流水でよく洗い、挿し木用の用土や鹿沼土に挿しましょう。
挿し木の適期は5~6月です。直射日光は避け、半日陰で用土が乾かないように管理しましょう。取り木をする場合は、根を出させたい場所の節の皮を剥ぎ、剥いだ部分を濡らした水苔で巻きます。さらに保湿のためビニールなどを巻き付け様子を見ましょう。数カ月してビニール越しに根が見えてきたら切り取り、用土に植え付けます。
●フィカス・ウンベラータの取り木の方法は『観葉植物が伸びすぎた! 剪定して増やす簡単な方法』でご紹介しています。
フィカス・ウンベラータの植え替え

フィカス・ウンベラータは根張りが旺盛なため、長期間植え替えをしていないと根詰まりが起きます。根詰まりとは、鉢内が根でいっぱいになってそれ以上伸びることができず、水の通りが悪くなり、用土内が乾燥、加湿、酸欠などの状態に陥ってしまうことです。葉が落ちたり、空中に根が出たり、なんとなく元気がなくなったように見えたら植え替えが必要です。
植物や鉢のサイズにもよりますが、おおむね1~2年に1度は植え替えたほうがよいでしょう。植え替えの適期は5~6月。そのタイミングに合わせて枯れた根を取り、すっきりさせておくと、その後の経過もよく育ちます。また植え替え時の鉢のサイズは今の鉢より一回り大きくしましょう。
植え替える際は、鉢のサイズに合わせて適切な鉢底石と湿らせた新しい培養土を入れ、フィカス・ウンベラータの根鉢が新しい土から外に出ないように高さを調整しながら用土を足していきましょう。このとき鉢を叩くなどして空気を抜き、割り箸などを使って根鉢と用土の間に隙間ができないようにつつきながら土を入れます。用土は鉢の縁ギリギリまで足すのではなく、3cm程度のウォータースペースを取りましょう。植え替え後は鉢底から濁った水が出なくなるまでしっかりと水やりを行ってください。
植え替え後は直射日光などには当てず、徐々に元の環境に慣らしてください。20日前後で新しい葉が展開してきたら、根の調子もよくなってきた証拠です。通常の管理に戻しましょう。
病気・害虫

フィカス・ウンベラータのかかりやすい病気の一つに「うどんこ病」があります。葉の表面にうっすらと白い粉のようなものが広がるのが特徴で、原因はカビです。一年を通して発生する可能性があり、特に空気が乾燥する時期や室内の風通しの悪い場所で管理していると発生リスクが高くなります。放置しておくとカビに覆われた葉は枯れ、全体に広がっていきます。最終的には他の植物にうつしてしまったり、枯れてしまったりするので、うどんこ病だと判断したら早期の対応が必要です。初期段階であれば発生した葉をちぎり、ビニール袋などカビを封じ込められるものに入れて処分しましょう。あるいは重曹水を葉に吹き付けることでも広がりを抑えることができます。それでも広範囲に広がってしまった場合は薬剤散布が有効です。葉の表と裏にまんべんなく吹き付けましょう。
フィカス・ウンベラータには害虫が付くこともあります。主にハダニ、アブラムシ、カイガラムシです。これらの害虫は日照不足や乾燥、風通しの悪い場所でより発生しやすく、また植物体が根腐れなどで弱っているときに被害が出やすいです。アブラムシやカイガラムシは歯ブラシなどでこすり落として捕殺しましょう。ハダニであれば、付いている葉ごと処分しましょう。数が多く捕殺しきれない場合は、薬剤散布が有効です。
カビや害虫が付く場合、基本的には環境に何らかの問題がある場合が多いので、日当たり、風通し、灌水頻度などをもう一度見直しましょう。また毎日の葉水なども予防に効果的です。
ウンベラータを育てておしゃれな空間を作ろう!

今回はフィカス・ウンベラータの育て方について解説してきました。丈夫で環境への適応力もあり、とても扱いやすい植物なので、特にインドアプランツとしての活用が注目されています。これまで解説した気を付けるポイントをしっかり守って、元気なウンベラータを育ててください。
Credit
文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!
- リンク
記事をシェアする
新着記事
-
育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR
今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…
-
ガーデン&ショップ

【秋の特別イベント】ハロウィン色&秋バラも開花して華やぐ「横浜イングリッシュガーデン…PR
今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、10月31日(金)まで「ハロウィン・ディスプレイ」…
-
イベント・ニュース

まちづくりを支える花とみどり…みつけイングリッシュガーデン、一人一花運動、中之条ガーデンズの事例 〜…
40年以上の歴史を持つ老舗業界専門雑誌『グリーン情報』最新号から最新トピックスをご紹介! 2025年9月号の特集は、「まちづくりを支える花とみどり」。そのほかにも、最新のイベント紹介はじめ園芸業界で押さえて…