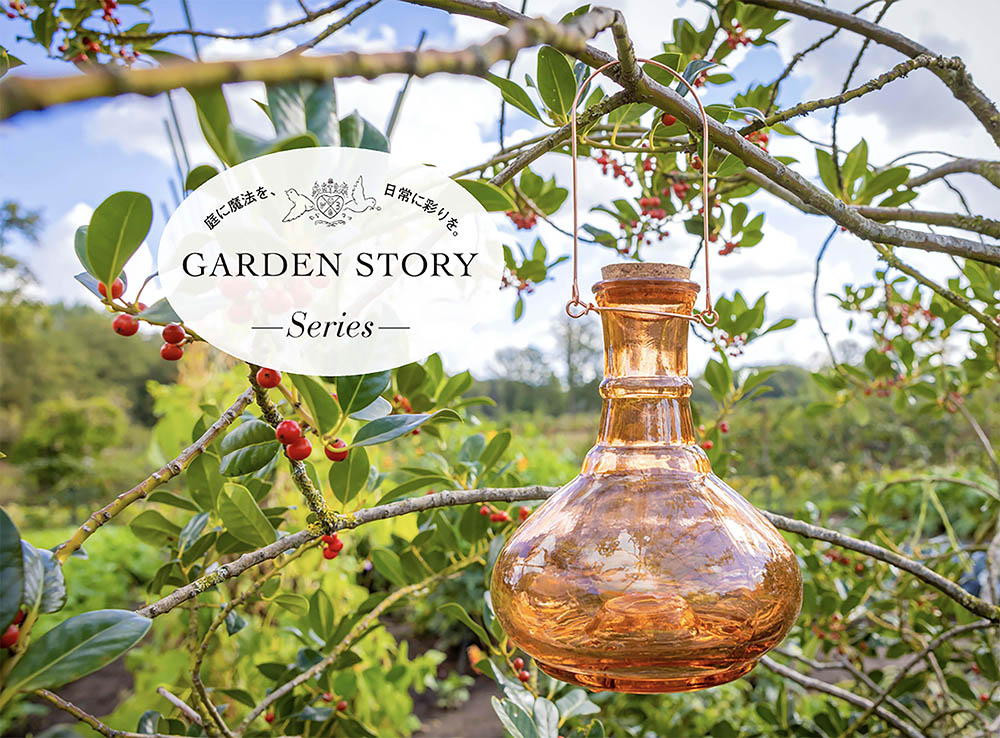千変万化の個性を競い合う個人育種パンジー&ビオラ最先端レポート③

2018年2月に宮崎のフラワーショップ「アナーセン」で開催されたパンジー・ビオラ作品展にて花を解説してくれた川越ROKAさん。
色も姿も多彩に広がる個人育種のパンジー&ビオラの世界。宮崎県を中心として個人育種が広がり、劇的な進化を遂げているその理由は、川越ROKAさん、その人に源泉があります。川越さんご自身のパンジー&ビオラの育種のきっかけを伺いました。
(『千変万化の個性を競い合う個人育種パンジー&ビオラ最先端レポート②』より続き)
編集部)
一方で、育種の世界には閉鎖的な面もあるかと思います。これまでにない形質を持ったものを発見したとき、それを他の人に渡したくないという思いとか、専売特許的な権利を持ちたいとか。でも、川越さんはどんどん人に新しい花のタネを配っていらっしゃいますよね。そのおかげで、宮崎県では新しいパンジー・ビオラが次々と生まれています。



川越さん(以下敬略)
それはですね、そもそも私がパンジー・ビオラの育種を始めたきっかけが関係しているかもしれません。私はアナーセンに入社する前に、知的障害者の方の授産施設に勤めていました。授産施設というのは、障害のある方の就労を支援する施設で、生産活動が行われ、その売り上げが利用者の賃金に還元されます。その中に花苗の生産部門があり、そこの担当でした。私は利用者の方と一緒に種苗会社から購入したタネを播いて花苗を生産し、それを市場に出荷していたわけですが、技術力の面で、どうしてもプロの生産者さんにはかなわない部分があったんですね。でも一生懸命育てた苗の値段が低くなってしまうのが残念で、生産技術以外の何か別の付加価値を付けられないかなと、ずっと考えていました。
そんなある日、育てていたパンジーの中にたった一株だけ、白色地でパープルが細く花弁を縁取っている「覆輪」が出たのです。今は覆輪品種ってたくさんありますが、25年前ぐらいでしょうか、当時はそういう花はなかったので、すごくキレイで驚きました。けれど、そういう一つだけ違う個性を持ったものは、市場には出せないんですね。市場出荷は「揃い」が重要、出荷の際には「色組み」といって同じ色の花をケースに入れるんですが、白にパープルの覆輪はどこにも当てはまらなかったんです。いわゆる「はねもの」というものです。ですから、それだけ外して大事にしていたら、そこにタネができたんです。で、それを播いてみたら、次の年に咲いた花にも覆輪という形質が伝わったんですね。それを見て「これだ!」と思いました。たくさん種を播けば「はねもの」は出ます。それを拾っていけば、それが私たちの生産する花苗の付加価値になると思ったのが、私のパンジー・ビオラの育種の始まりなんです。だって、タネを売っていない、どこにもないものなんですから。

編集部)
なるほど。そもそも個人的な欲求や利益を追求したものではなくて、授産施設の生産品に付加価値をつけることが目的で始まったんですね。
川越)
そうなんです。それで、たくさん育てる中に覆輪の他にも絞り咲きなどが出て、次第にいくつかの系統ができ上がっていって、異なる系統同士を交配したら、また面白いものが出てきて…。そんな風にして、私はどんどん交配に夢中になって、それに比例して花のバリエーションもどんどん広がって。そうやって次々に新しい花が生まれていったわけですが、それらの花や施設の様子を老舗園芸通販の改良園さんの会報誌(園芸世界・平成10年1月号)に掲載していただいたんです。そしたら、それを高知県の見元一夫さんがご覧になって、わざわざ7時間もかけて施設まで来てくださったんです。
編集部)
野うさぎミーモなど、オリジナルのパンジー・ビオラで有名な見元園芸さんですか。
川越)
ええ、そうです。当時、メロンなどの野菜がメインだったと思います。それで、私のところにあった系統のほとんどをお渡ししたのが、実は見元園芸さんのビオラの始まりなんです。ですからルーツは私のところにあるわけですが、大事なことは、それらがさらに交配や選抜を繰り返して見元さんらしい特徴に変わっていったところにこそあるんですよ。私は見元さんの世界ができ上がっていくのを見るのが面白かったし、福祉施設で頑張っている私たちの花が、見元さんを通じて世の中に広がっていくということがとても嬉しかったのです。ですから、最初に苗をお渡しするときにも、「ぜひ、障害者施設でつくっている花だと一言添えて販売してほしい」とお願いした記憶があります。それだけで十分でした。その後、お付き合いはずっと続いて、今年はこのパンジー・ビオラ作品展の10周年の記念に、見元さんが特別講演をしてくださいました。
編集部)
ところで、その25年前の覆輪の花には、名前をつけたんですか。
川越)
ジャム&クリームという名前をつけました。最初は白にパープルの覆輪だったのが、タネを取り続ける中で覆輪がローズになったり、今度は地色が黄色になったものなど、バリエーションが広がって、それをジャムとクリームに見立てた訳です。実はこのタネをあるところに託したことがあるのですが、それを入手して育てたことがあったのが、なんと平塚弘子さん、ご本人と知り合う前のことです。この品種がすでにご縁を繋いでくれていたのですね。当時珍しかった覆輪の花とネーミングにいたく感激されたということが、知り合った後に分かって、お互いにビックリでした。それからさらに育種にはまり込んでいく訳です。私は小さいころからタネ播きが好きで、ハナショウブやツバキのタネなんかを播いていたんですね。ですから、ある程度の育種の知識があって、花をもっと多様化させるには、違う原種の血を入れればいいということが分かっていました。そこで、その当時、イギリスからビオラの原種のタネを全部買ったんですが、その中に1㎝程度のとても小さい花を咲かせる、アルベンシスという原種があったんです。

あまりにも小さくて目立たない花なので、正直使えないなと思ったのですが、市販品種のビオラと交配したところ、たまたまできたのが、極々小輪の系統なんです。1㎝程度の大きさの花を極々小輪と呼んでいます。ですから、極々小輪系はほぼアルベンシスの血を引いているんですね。バニーと呼ばれる細弁系もアルベンシスの血を引いています。極々小輪も細弁も日本でできた花形です。小さいものは日本人は大好きですし、野に咲くスミレのイメージもあるので受け入れられたんだと思います。で、一つの花形が登場すると、デザイン的にも洗練が始まるんですね。例えば、バニーを見たコウロギノブコさんが、自分なりの細弁を追求した結果が、人気の‘碧いうさぎ’のようなシャープな細弁のラビット形になるんです。今は石川園芸さんや秋田緑化農園さんでも極々小輪の花を作出されていて、寄せ植えの素材としてもとても人気です。


編集部)
川越さんは、これまで何人くらいの方にタネを差し上げているんですか。
川越)
うーん、数えたことはないですが、少なくとも10年くらい前からはブログでタネの配布をご案内して、毎年100人くらいの方から応募があるので、すでに1,000人以上になりますかね。生産者さんからも希望があります。そうやって、あちこちでタネを配ると、みなさんの感性がそれぞれに違うので、いろんな花が登場するんですよ。もしも私が一人で抱え込んじゃっていたら、できない広がりです。
編集部)
‘エボルベ’をつくった大牟田さんが、川越さんがいなかったら、パンジー・ビオラの発展は確実に10年以上は遅れていたとおっしゃっていました。変な質問ですが、川越さんが配ったタネから、他の人がすごい綺麗な花をつくって大流行したりしたら、悔しくなったりしませんか。
川越)
あははは、ちっとも悔しくないです。むしろその逆ですよ(笑)。私は人にタネを配ったおかげで、予想もつかなかったこんな美しい世界を、いま見せてもらって、本当に幸せです。多くの人が関わることによって、世界はこんなに豊かになるっていうことを、この小さな花は私に教えてくれたんです。本当に素敵な世界ですよ。だから、まだまだたくさんの人にこの育種という世界に参加してほしいんです。いまどきの若い方はSNSとかでビジュアルセンスに長けているじゃないですか。そういう若い感性で花をつくったら、どんなふうになるのか、ぜひ見てみたいと思います。

川越)
ぜひ、みなさんもタネを播いてみませんか。誰でも参加できますよ。ベテランも新人も、手にしているタネは同じですから、同じスタートラインから出発できるところも、パンジー・ビオラの育種の面白さです。必ずしも経験年数がすべてじゃなくて、初心者がすごい花を生み出す可能性が十分にあるってところが素敵だと思いませんか。それにタネから育ててみれば、一つの花の背景にあるいろんな人の苦労や喜びにも思いを馳せることができるようになるんですよ。ここまで花を完成させるのは大変だったろうなとか、この花がどういう経緯を辿ってここまで来たのかなとか。キレイだっていうだけで終わらない世界が広がるんですよね。
ぜひ、タネを播いてみてください。この世界がどんなに豊かで美しいか、感じられるはずですよ。
Information
Andersen アナーセン
宮崎県宮崎市跡江1380−9
TEL & FAX 0985-48-2668
OPEN 10:00 – 18:00
月曜定休
http://andersen-flower.com
Credit

写真&文/3and garden
ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。
新着記事
-
育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR
今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…
-
ガーデン&ショップ

【秋の特別イベント】ハロウィン色&秋バラも開花して華やぐ「横浜イングリッシュガーデン…PR
今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、10月31日(金)まで「ハロウィン・ディスプレイ」…
-
イベント・ニュース

まちづくりを支える花とみどり…みつけイングリッシュガーデン、一人一花運動、中之条ガーデンズの事例 〜…
40年以上の歴史を持つ老舗業界専門雑誌『グリーン情報』最新号から最新トピックスをご紹介! 2025年9月号の特集は、「まちづくりを支える花とみどり」。そのほかにも、最新のイベント紹介はじめ園芸業界で押さえて…