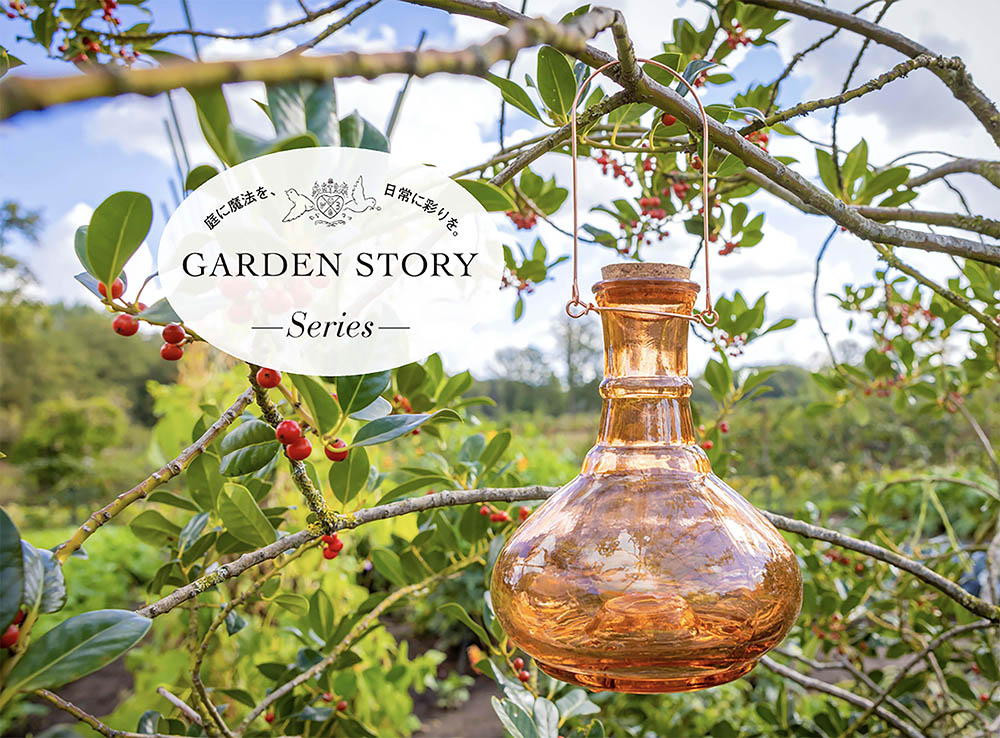東京・根津美術館で「燕子花図屏風」を見て、庭園のカキツバタと出合う

東京・青山にある「根津美術館」では、尾形光琳作の国宝・「燕子花図屏風」の公開時期に、庭園にはカキツバタが見事に咲きます。これまで、国内外に咲く季節の花々にカメラを向けてきた写真家でエッセイストの松本路子さんが、今、見頃を迎えた庭園のカキツバタを撮影すべく「根津美術館」を訪問。尾形光琳が手がけた「燕子花図屏風」の見どころを、水辺のカキツバタの群生が優美に咲く様子とともにレポートします。
目次
カキツバタの記憶

10年近く前に、友人に誘われて東京・青山にある根津美術館に、尾形光琳筆の「燕子花図屏風(かきつばたずびょうぶ)」を観に出かけたことがある。その折の屏風の佇まいもさることながら、庭園に咲くカキツバタが見事だったことが記憶に残っていた。

屏風は毎年、カキツバタが咲く4月から5月にかけての約1カ月間公開される。今年(2023年)はいつになく開花が早いという花便りが届き、改めて国宝・「燕子花図屏風」と庭園のカキツバタを見てみたいと、根津美術館を訪ねた。
展示室にて

美術館の1階の広い空間の中央に置かれた「燕子花図屏風」はひときわ輝いて見えた。屏風の公開に当たっては、毎年テーマが決められ、今年は「光琳の生きた時代1658-1716」という切り口で構成されている。宮廷や幕府主導の文化の時代から、町人が担い手となって花開いた元禄文化の時代へと、尾形光琳が生きた約60年間の江戸の美術史を切り取る試みだ。
光を放つ、燕子花図屏風

総金地に描かれた群青色の花と緑青色の葉。リズミカルで大胆な構図は、現代に生きる私たちにとってもモダンで斬新に感じられる。屏風を数える単位は隻(せき)で、1隻の中に縦長の画面を6枚つなぎ合わせたものが6曲屏風。6曲屏風が2隻で1組みになっているこの屏風は6曲1双とされる。

右隻には根元からすっくと立つ花の群生が描かれ、左隻では根元をほとんど見せていない。写真家の眼からは、右隻は広角レンズでやや下から仰ぎ見た図、左隻は望遠レンズでやや上から見た図、とも思える。この対照的な構図によって、燕子花は躍動し、空間は無限に広がっている。

金箔の部分は光を反射し、見る角度によって艶めかしくも、冷淡にも見える。2色の岩絵具の濃淡だけで燕子花の生気を描き出すという色彩感覚もまた驚異的だ。
尾形光琳の生涯

江戸時代を代表する絵師のひとり、尾形光琳(1658-1716)は、伝統的な大和絵に斬新な構図を取り入れ、のちに琳派と呼ばれる画派を確立した人物として知られる。
1658年に京都でも有数の呉服商の家に生まれ、幼い頃からさまざまな絵画や工芸に触れて育った。30代前半から絵師の道を志し、本格的に活動を始めたのは40代になってから。「燕子花図屏風」は40代半ばの代表作とされる。その後、「紅白梅図屏風」(国宝)、「風神雷神図屏風」(重要文化財)などを制作。1716年に没するまで、わずか十数年の制作期間であった。

燕子花図屏風に描かれた花の群生は、一部に染め物で使う型紙の技法が使われ、同じ形が反復されている。これは子どもの頃から着物の意匠に接してきた光琳ならではの発案だろう。燕子花図は、平安時代前期に書かれた『伊勢物語』第九段「八橋」に想を得ているという。光琳が好んで描いた花の背景には、彼が思いを馳せた和歌や物語があることを知ると、鑑賞の趣もまた変わってくる。
根津美術館の庭園

根津美術館を訪ねる楽しみの一つが、庭園散歩。広さ2万㎡の起伏に富んだ庭園をめぐると、都会にいることを忘れるほど、深山幽谷の気配を感じることができる。美術館は実業家初代根津嘉一郎氏の古美術コレクションを保存し、展示するために作られたが、庭園もまた彼の意向に添ったもので、いわば自然が生み出す芸術といえるものだ。その最たるものが、水辺のカキツバタの群生だ。庭内には灯籠や仏像などの石造物が100体ほど配され、薬師堂の竹林、初夏に色づく紅葉など、印象的な景観が展開する。



カキツバタの群生

カキツバタは、庭園の中央部に位置する池の一角に群生している。開花の最盛期に訪れることができたのは幸運だった。池をぐるりと巡り、違った角度から見ると、花の趣もまた変わってくる。私が訪ねた日にはサギが園内を悠然と散歩し、池には水鳥が遊んでいた。どこからか飛来してくるのだという。

カキツバタはアヤメ科アヤメ属の植物で、乾燥した場所を好むアヤメに対して、カキツバタは湿地を好む。カキツバタのほうが葉幅が広く、また花弁の付け根に網目模様があるのがアヤメで、カキツバタには1本の白い筋が見られる。

庭園のカキツバタが池の水に映る様は、たとえようもなく優美。さらに尾形光琳の屏風絵を見たあとの散策には格別なものがある。この時期ならではの贅沢な時間を味わうことができるのだ。
Information

根津美術館
特別展「国宝・燕子花図屏風 光琳の生きた時代1658-1716」
2023年4月15日(土)~ 5月14日(日)
住所:107-0062 東京都港区南青山6-5-1
電話:03-3400-2536
開館:10:00~17:00(入館は16:30まで)、
5月9日~5月14日は19:00まで開館(入館は18:30まで)
休館:月曜日(祝日の場合は開館し、翌日休)、展示替期間、年末年始
入館料:[特別展] 一般1,500円、学生1,200円(オンライン日時指定予約)
当日券 一般1,600円、学生1,300、小・中学生以下は無料
(*混雑状況によっては当日券を販売しない場合もあります)
アクセス:地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線、表参道下車、徒歩約10分
HP:https://www.nezu-muse.or.jp
取材・写真協力
根津美術館
Credit
写真&文 / 松本路子 - 写真家/エッセイスト -
まつもと・みちこ/世界各地のアーティストの肖像を中心とする写真集『Portraits 女性アーティストの肖像』などのほか、『晴れたらバラ日和』『ヨーロッパ バラの名前をめぐる旅』『日本のバラ』『東京 桜100花』などのフォト&エッセイ集を出版。バルコニーでの庭仕事のほか、各地の庭巡りを楽しんでいる。2024年、造形作家ニキ・ド・サンファルのアートフィルム『Viva Niki タロット・ガーデンへの道』を監督・制作し、9月下旬より東京「シネスイッチ銀座」他で上映中。『秘密のバルコニーガーデン 12カ月の愉しみ方・育て方』(KADOKAWA刊)好評発売中。
- リンク
記事をシェアする
新着記事
-
育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR
今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…
-
ガーデン

【スペシャル・イベント】ハロウィン色で秋の庭が花やぐ「横浜イングリッシュガーデン」に…PR
今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、9月13日(土)から「ハロウィン・ディスプレイ」…
-
ガーデン

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【秋の到来を知らせる9月…
新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストが、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台にスタートし、春の花が次々と咲き始めています。…