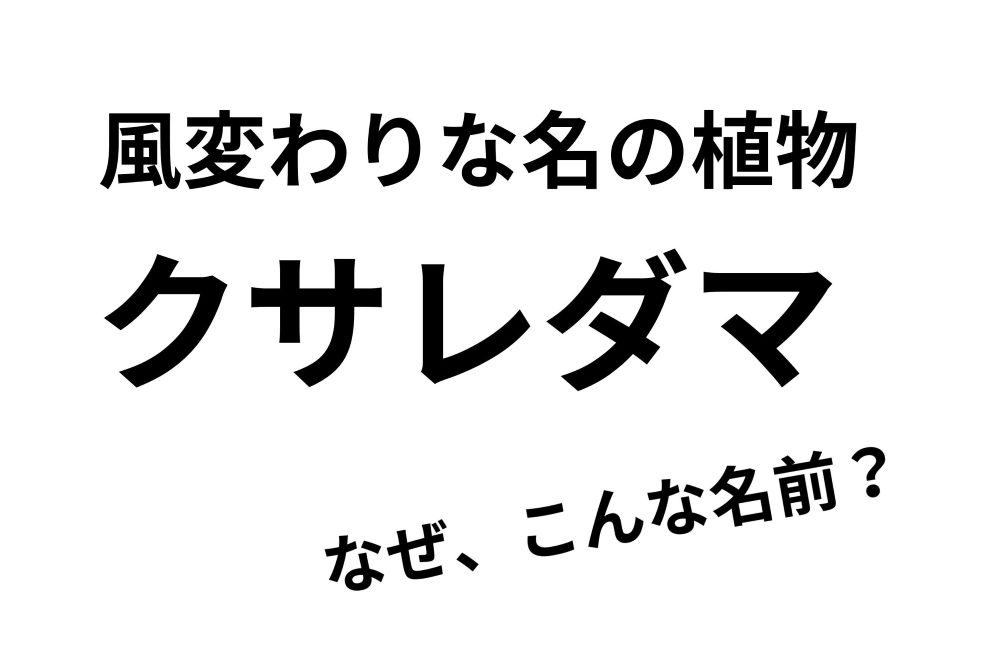えんどう・ひろこ/東京出身。慶應義塾大学卒業後、エコール・デュ・ルーヴルで美術史を学ぶ。長年の美術展プロデュース業の後、庭園の世界に魅せられてヴェルサイユ国立高等造園学校及びパリ第一大学歴史文化財庭園修士コースを修了。美と歴史、そして自然豊かなビオ大国フランスから、ガーデン案内&ガーデニング事情をお届けします。田舎で計画中のナチュラリスティック・ガーデン便りもそのうちに。
遠藤浩子 -フランス在住/庭園文化研究家-

えんどう・ひろこ/東京出身。慶應義塾大学卒業後、エコール・デュ・ルーヴルで美術史を学ぶ。長年の美術展プロデュース業の後、庭園の世界に魅せられてヴェルサイユ国立高等造園学校及びパリ第一大学歴史文化財庭園修士コースを修了。美と歴史、そして自然豊かなビオ大国フランスから、ガーデン案内&ガーデニング事情をお届けします。田舎で計画中のナチュラリスティック・ガーデン便りもそのうちに。
遠藤浩子 -フランス在住/庭園文化研究家-の記事
-
ガーデン&ショップ

フランスも庭シーズン! ショーモンシュルロワール城・国際ガーデンフェスティバル〜前編〜【フランス庭便り】
アートと自然が出合うロワールの古城、ショーモンシュルロワール城 15世紀以来の歴史をもつフランス王家に縁の深いショーモンシュルロワール城に、現在に続く英国風の庭園が作られたのは19世紀になってから。この城の面白いところは、歴史的であるばかりでなく、現代においてもどんどん進化している点です。 城館は現代アートセンターとなって、若手や国際的な巨匠の作品制作や展示の場になり、庭園にも数多くの一流の現代アートのインスタレーション作品が設置されます。 また、毎年春から秋にかけての約7カ月にわたり、フランス最大規模のガーデンフェスティバルが開催されるなど、アートと自然を結ぶクリエイティブな活動が常に注目される、非常に魅力的な場所なのです。 30周年を迎えた老舗国際ガーデンフェスティバル 今年で30周年を迎える、ショーモンシュルロワール城の国際ガーデンフェスティバルは、多い年には約53万人もの入場者を集める人気のガーデンショーです。毎年異なるテーマに沿って公募された、300件を超える応募作品の中から選ばれた二十数個の庭デザインが、それぞれ約200㎡強の区画のショーガーデンとして作庭・展示されます。 城の庭園の一角に位置するショー会場は、敷地の庭園や森林とシームレスにつながっており、自然な雰囲気の中でのどかな散策を楽しみつつ、ショーガーデンの見学ができるのも大きな魅力です。 若手庭園デザイナーの登竜門 応募書類は匿名で審査されます。フランスでは若手の庭園デザイナーの登竜門として定評あるガーデンショーで、また庭園デザイナーや造園家ばかりでなく、アーティストや建築家など他分野のクリエーターたちとの混合チームでの作品なども多く見られるなど、開かれた雰囲気のショーでもあります。 今年の出展者の顔ぶれは、フランス、イギリス、ベルギー、ドイツ、オランダ、イタリア、チェコ、スロバキアのほか米国からも。コロナ禍以前には毎年、日本や中国、韓国などアジアからの出展もありました。ヨーロッパ地域が多いながらも国際色豊かです。 出来上がったガーデンデザインには、さらなる審査があり、全体的なクリエイションのクオリティ、アイデアの斬新さ、植栽のハーモニーなど、さまざまな基準で選ばれるいくつかの賞が用意されており、授賞式は6月に行われます。 国際的な著名造園家の招聘 また、30周年という節目の年ゆえ、ショーガーデンにカルト・ヴェールと名付けられた自由裁量の招聘枠が加えられ、キャスリーン・グスタフソンやジャクリーヌ・オスティといった、国際的な大御所ランドスケープ・アーキテクトがデザインした小さな庭が見られるのも、今年の面白いところです。 今年のテーマは「理想の庭」 さて、毎年異なるフェスティバルのテーマは、時代のトレンドを反映したものが多いように思われます。30周年を迎える今年のテーマは、ズバリ「理想の庭」。 都市化がこれ以上ないほど進み、地球温暖化が目前の問題となっている現在、人と自然の関係性から見た「理想の庭」とはどんなものなのか? 癒やしの空間、または安心安全な野菜や果物を育てるポタジェ、あるいはアートと同じような価値を持つ空間かもしれない? 「理想の庭」からインスパイアされる、新たな演出方法や素材や技術を用いて表現する庭とはどんなものだろうか? みなさんなら、どんな庭を想像しますか? 季節を追って変化する植栽デザイン さて、このガーデンショーの大きな特徴は、長期にわたる開催であること。春から晩秋にかけて約7カ月にわたって開催されるため、ロンドンのチェルシーガーデンショーなど、数日間の開催期間中に最高に完成された姿のガーデンを演出するガーデンショーとは異なり、季節の変化に合わせて、成長し変化する植栽を工夫しなければなりません。 春先と盛夏、または晩秋では、同じショーガーデンでも植栽次第でその表情が大きく変わっていくのも面白いところです。訪れる園芸愛好家にとっては、変化していく植物の姿をそのまま見られるので、自宅の庭づくりの参考にしやすいという利点もありそうです。ちなみに園内のガーデニング関連のショップでは、植物の種子や苗を購入することもできます。 見学を充実させる豊かなアメニティ このように、ガーデンショーの展示をゆっくり眺めるだけでも軽く半日は楽しめますが、隣接するイギリス式庭園や、城や旧厩舎の展示、ポタジェ、クレマチスなどのプランツコレクション、さらには隣接するグアルプ公園の異文化からインスパイアされたさまざまなガーデン……などなど、全部を見て回ろうとしたら、一日では足りないほど。幸い素敵なレストランやカフェも充実しており、丸一日、大満足で過ごすことができます。 敷地内のほかのガーデンについても、また次の機会にご紹介できたらと思います。 ●ショーモンシュルロワール城・国際ガーデンフェスティバル(後編)は近日公開!
-
ガーデン&ショップ

フランスの城で春のガーデニングフェア開催! ポタジェにも注目の「サン=ジャン=ド=ボールギャール城」【フランス庭便り】
専門ナーサリーが一堂に集まる貴重な機会 年2回、春夏の週末に城の庭園内で開催されるこのガーデニングフェアには、フランス内外の各種ナーサリーや園芸ツールなどを扱う200を超える専門店が出展します。タイミングによって花の咲く様子が見られる草花もあれば、そうでないものもありますが、出展ナーサリーの扱う植物は安定的に質が高く、信頼して買い物ができると園芸愛好家の人々に好評。 特に、各地に散らばっているナーサリーをそれぞれ訪ねるのは園芸ファンといえどもなかなか大変。また、バラに限らず、シャクヤクやアジサイ、アイリス、アリウム、ダリアあるいはハーブ類、果樹類や紅葉する樹木類など、さまざまな異なる得意分野を持った地方の専門ナーサリーが一堂に集まるガーデニングフェアは、その場での買い物はもちろん、気になった植物やナーサリーをメモして後日の注文にも生かせる、貴重な機会となっています。 リラックスした心地よい雰囲気が魅力 また、このガーデニングフェアの魅力は、なんといっても会場が城の庭園の中であること。ゆったりとした木々や草地といった緑に囲まれた中でのガーデニングフェアは、そぞろ歩きをしているだけでもエネルギーチャージができる場所。自分の庭の一角に置いた時の雰囲気を容易に想像できるガーデンツールの展示など、見ているだけでも楽しいものです。 春のガーデニングショーの注目株は? 今の時期、バラやシャクヤクは、展示用に早く咲くようにハウスで栽培されたもの以外は、基本的にはようやく葉っぱが出始めているところ。でも春からのガーデニングの仕事始めに、早速定植することができるので、苗木選びもリアリティがあって楽しいものです。ハーブ類の栽培もこれからがベストタイミングですし、ダリアの球根なども、夏に向かってこれからが植えどきです。逆に秋のフェアでは春球根が主になるなど、季節によって品揃えは変わりますが、それは季節感の味わいでもあります。 ちょっと休憩、ランチどころは? ガーデニングフェアといえば、フード・トラックやレストランも欠かせません。いつもは青空レストランが城の敷地の裏側に設置されるのですが、今年は悪天候の日もあったため、レストランスペースはテントの中に。しかし、通常もっともよく見られるのが、サンドイッチなどをフードトラックで購入し、あるいは自宅からランチを持参して、城館の正面の絶景を眺めながら食べたり、ポタジェ(菜園)でピクニックをする人々の姿です。この、人気のピクニック・スペースにもなっているポタジェのほうも覗いてみましょう。 17世紀のデザインを伝える、花咲く歴史的ポタジェ ガーデニングフェアの絶好のランチスペースにもなっているポタジェ。じつは17世紀のフォーマルガーデンスタイルの姿を今日に伝える、貴重な歴史的庭園でもあります。 かつては城内に暮らす数十名の人々の自給自足のための野菜・果物、そして花々を栽培する場であったこのポタジェ、現在は、昔野菜などの一般的には栽培されなくなった希少種を中心とした野菜や、季節を通じて次々と入れ替わり咲き乱れる花々が栽培され、「花咲くポタジェ」として愛され続けています。 こうした、実用(野菜果樹栽培)とオーナメンタル(花々)がバランスよく組み合わされた姿は、まさにフランスのポタジェガーデンの魅力といっていいでしょう。 クレマチスやバラが這う石壁に囲われた約2ヘクタールほどの面積の中央部分が、フランスの昔ながらの野菜など、希少種を栽培する野菜畑。真ん中の丸い池の水は、ポタジェの散水にも利用されます。 中央の野菜畑は、リンゴや洋ナシといったエスパリエ仕立ての果樹で区切られ、また春先のチューリップやスイセンに始まり、アリウムやシャクヤクやバラ、アイリス、と季節を追って次々と入れ替わり、3月から11月までさまざまな花が咲き乱れるボーダーに囲まれています。庭園内とポタジェを合わせて、全体で10万球もの球根が植えられているのだそう。 緑が瑞々しい果樹園コーナーと珍しいブドウの温室 ポタジェの一画を占めるデザインも素敵な温室は、ブドウ栽培用の珍しいもの。その奥にはリンゴなどの果樹が植えられた草地が広がります。ガーデニングフェアが開催されている昼どきには、果樹園の草地や、南向きの日差しが暖かい温室近くに、ピクニックする人々がどんどん集まってくるのが微笑ましい。 私もピクニックしたい気持ちはやまやまながら、諸事情によりこの日は叶わず。絶景ポイントで風に吹かれながら、ノルマンディー風タルトとカフェをいただいたのみ(しかも写真は撮り忘れ)でした。それでも十分ほくほく満足してしまうガーデニングフェアです。 どの季節にもそれぞれの良さがいっぱいの歴史的ポタジェの散策が楽しめて、かつ、フランスの日常生活の中に根付くガーデニング周りの様子がダイレクトにうかがえるのが、このフェアの一番楽しいところです。
-
ガーデン&ショップ

早春の「ポタジェ・デュ・ロワ(王の菜園)」を訪ねて【フランス庭便り】
ヴェルサイユの隠れた憩いの場 ルイ14世は美食家であり、野菜や果樹の栽培への関心も高かったことから、王自らが宮殿から馬に乗ってポタジェまで散策に出ていたのだそうで、「王の門」と呼ばれる立派な鋳造の門が現在も残っています。王にとって、公の場である宮廷を離れてほっと一息つく、憩いの場であったのかもしれません。古の「ポタジェ・デュ・ロワ」は王家の食卓に上がる多種多様な野菜や果実が栽培されていましたが、もちろん単なる菜園・果樹園ではありません。王の散策の場にもふさわしい美観を備えつつ、王家の食卓ならではの贅沢を満足させるスペシャルな菜園だったのです。 フレンチ・フォーマルなスタイル ポタジェを訪れてまず驚くのが、徹底的なフォーマル・ガーデン・スタイルの構成です。9ヘクタールの敷地全体が壁で囲われた沈床型のウォールド・ガーデンになっています。グラン・カレと呼ばれる正方形の中央区画には、円形の噴水を中心に、エスパリエ仕立てのリンゴや洋ナシなどの果樹で仕切られた、野菜栽培のスペースが整然と並びます。その周りには、伝統品種や新品種などバラエティに富んだ果樹が、さまざまなエスパリエ仕立ての独特な樹形で栽培されています。 エスパリエ仕立てとは、フランスの果樹栽培のための伝統的な剪定方法。現在でもリンゴや洋ナシを中心に4,000本ほどを栽培するポタジェ・デュ・ロワは、これだけの規模でその様子が見られる、世界でも唯一の貴重な場所です。 ウォールド・ガーデンとエスパリエ仕立ての効用 ところで、沈床型のウォールド・ガーデンをぐるりと囲む厚い土壁にも、壁に沿わせるエスパリエ仕立ての剪定にも、じつはスペシャルな果樹栽培のための理由がありました。土壁は果樹が外部からの冷風に直接晒されるのを防ぐとともに、日中の太陽の熱を蓄え、夜間の急激な温度の降下を抑えて、果樹栽培に好都合の微気候を作り出します。また、平面的なエスパリエ仕立てには、果実に満遍なく日光が当たるように、また収穫がしやすいようにという配慮から生まれたものです。 17世紀にも野菜の促成栽培 贅を尽くした王宮の食卓には、例えば3月にイチゴ、6月にイチジク、12~1月にアスパラガスが並んだといいます(ちなみにイチゴもイチジクもルイ14世の大好物だったそうです)。現代であれば何ら驚きもないのですが、ハウス栽培などなかった時代です。通常の露地栽培の収穫期に大幅に先駆けて現れるこれらの野菜や果実は、まさにミラクル。宮廷人たちにとっても大変な贅沢でした。 では、どうやって実現したのか? ルイ14世の命を受け、ポタジェの造園と管理を行ったのは、庭師で果樹栽培の専門家として名高かったラ・カンティニ。彼は当時最新の栽培技術の開発に余念がなく、宮殿の厩舎から出る馬糞を用いた堆肥の発熱を利用した促成栽培術で宮廷を驚かせ、称賛を集めたのでした。 伝統そして革新 創始者ラ・カンティニのイノベーション精神は後世に受け継がれ、フランス革命などさまざまな時代の変遷を経て現在に至ります。「ポタジェ・デュ・ロワ」のモットーは、歴史の伝承とともに常に革新的であること。世界的にも希少な17世紀のフレンチ・フォーマル・ガーデンの姿を留めたポタジェでは、フランスの昔ながらの固有種を多く栽培し、また伝統的な園芸技術であるエスパリエ仕立ての剪定など、技術の伝承が行われています。そうした伝統の継承を自らの使命として大切にする一方で、今の時代に対応する新たな試みが次々と行われているのも、このポタジェの大切な側面です。 アグロエコロジーへ フランスでは、オーガニックの食材が一般化しているだけでなく、2016年から公共の緑地での薬剤散布が法律で禁止されるなど、人の健康や環境保護が社会的に重大なテーマになっています。先駆精神に富んだこのポタジェでは、2000年代には無農薬の自然農法への切り替えが始まり、パーマカルチャーの手法を取り入れるなどして、できる限り無農薬、栽培品種によっては完全無農薬栽培へと移行してきました。 特に土壌や生態系といった自然環境を保護しつつ、サステナブルな方法で人間と自然の共存を目指す未来の農業、アグロエコロジーへの取り組みが積極的に進められています。また、一般の来場者の見学に門戸を開き、園芸講座や各種イベントが行われ、歴史的庭園の姿やサステナブルな都市農業のあり方を人々に伝える教育普及も現在のポタジェの大事な役割です。 春を待つポタジェの魅力 庭園を訪れる際には、どの季節が見頃なのか、という問いが常にありますが、「ポタジェ・デュ・ロワ」は年間通じて見学が可能です。春にはモモやリンゴの花が咲き、夏は緑が溢れ、秋には黄葉とともに、カボチャ類など秋の収穫物がコロコロと畑を彩る…と季節による変化を追うのも、興味深く楽しいものです。 冬の間は果樹類の葉っぱも落ちて、若干寂しいのではと思われがちですが、じつは自慢のエスパリエ仕立ての木々のグラフィックな魅力を十二分に堪能できる、特別な時期でもあります。この機会に、変化に富んだポタジェの四季の表情を皆様に楽しんでいただけたら嬉しいです。 遠藤浩子さんが案内する「ポタジェ・デュ・ロワ」オンラインサロン開催※終了しました 記事でご紹介したフランスの「ポタジェ・デュ・ロワ」と中継をつなぎ、この時期しか見られない春のポタジェの様子を、庭園文化研究家、遠藤浩子さんがご案内するサロン。開催は、2022年4月14日(木)18:30スタート(フランス時間11:30)。 サロンへのご参加には、ガーデンストーリークラブへのご入会が必要です。
-
ストーリー

ローマ時代の庭園にタイムスリップ! 古代ローマ時代に描かれたリウィア荘の庭園画
古代ローマ、リウィア荘の庭園画 ローマ国立博物館マッシモ宮。Takashi Images/shutterstock.com 旅先で立ち寄ったローマ国立博物館マッシモ宮で、庭園を描いた古代ローマのフレスコ壁画に出会いました。このリウィア荘の庭園画が描かれたのは紀元前40~20年、今から2,000年ほど前のこと。ところが、この庭園画の前に立った途端、2,000年の歳月を忘れてしまうほどにその風景は瑞々しく、時空を超えてローマ時代の庭園に迷いこんだかのようでした。 リウィア荘壁画の展示室の入り口。 リウィアは初代ローマ皇帝アウグストゥスの妻で、この庭園画はローマ郊外、フラミニア街道北のティベリス川を見下ろす高台プリマ・ポルタにあった彼女の別荘から出土したものです。壁画は、夏の季節の暑さを避けて、食事や宴に用いられたのであろうと推測される、半地下状の窓のない部屋の四方を囲む形で庭の風景が描かれたものです。描かれた庭とはいえ、この壁画に囲まれた空間に入ると、まるで本当に庭園の中にいるような心持ちがしたことでしょう。というのも、20世紀間を隔てた現代でも、本物の庭にいるときのような、ふうっと落ち着く心地よさに包まれるのです。さらにはその静謐な空気感の中に、不思議なワクワクする感覚が湧いてきます。 写実と幻想のワルツ 中央にはモミの木と白い鳥、フレスコ画のマットな質感がなんともよい。 描かれた庭にさらに近づいてみます。よく見ると、私たちも知っているような、モミやマツ、イトスギなどの針葉樹やオークなどの大きな樹木、またツゲやギンバイカ、ゲッケイジュがあり、ザクロやカリンやサクランボなど、さまざまな果樹の姿が浮かび上がってきます。それぞれがはっきりと識別できるほど写実的に描かれています。 果樹と小鳥たち。 木々の樹冠にはさまざまな種類の鳥が集まり、小枝にとまって果実を啄(ついば)んでいます。描き込まれた植物は23種、鳥は69種もいるそうです。季節の異なる果実が一度に実り、同様に花々が一斉に咲いている様子は、架空の絵画ならではの、時なしの桃源郷の庭のよう。バラやマーガレットなどの花や果実の色合いで、瑞々しい空の青色と木々の緑色に鮮やかな色彩のタッチが加わります。 ヨーロッパのフォーマル・ガーデンの左右対称の配置は、古い伝統に根ざした感覚なのだろうなと思わされる構成。 そして木々の足元、下方前景には、丁寧に編み込まれたトレリスの柵が庭を囲み、ツタやアカンサスの葉っぱが茂り、さらにその奥にも、凝った文様の仕切りの壁が回してあるのに気付きます。現代の庭にもそのまま使えそうなフォルムの柵は、不思議な遠近感とともに、架空の庭の空間をより庭らしくしています。木々の姿はどちらかといえばナチュラルな自然樹形ながらも、メインの木々や植物の配置はシンメトリーなフォーマル・ガーデン風。ヨーロッパのフォーマル・ガーデンへの嗜好は、もともとの伝統的な感覚に根差しているのかと納得したりもします。 ほぼ実物大なので、本当に庭園を眺めているような感覚になってきます。 全体として実に写実的に描かれている、にもかかわらず、夢の中のような雰囲気が醸し出されるのは、不思議な遠近表現から来るのか、絶妙なリアルと幻想のミックス感からか、またはところどころが剥げ落ちているような絵画のテクスチャーの経年変化のゆえなのか。 古代ローマのバラとゲッケイジュ バラの花でしょうか。塀の描写もリアル。 ところで、壁画に描かれた樹木と花々は、それぞれにギリシア・ローマ神話や伝説などで親しみ深いものばかり。例えばギンバイカは愛と不死、純潔を象徴し、愛と美の女神ウェヌスに捧げられ、結婚式の飾りなどにも使われた花。一番目を引くのはバラですが、アウグストゥスの子孫にあたる古代ローマ皇帝ネロは大のバラ好きで知られます。晩餐会を催す部屋にはバラを降らせて埋め尽くし、バラ水を土砂降りのように注ぎ、その重みで窒息死する来客まで出たのだとか。かなり怖い。 さまざまな樹種の木々が小鳥たちとともに描かれています。 また、オリンピックの勝者の冠として使われていたゲッケイジュには、リウィア荘とも関わる伝承があります。アウグストゥスとの結婚を控えたリウィアが別荘にいた時に、不思議な出来事が起こりました。どこからともなく飛んできた鷹が彼女の膝元に落としていった獲物が、ゲッケイジュの枝を咥(くわ)えた白い鶏だったのだそうです。宣託にしたがって植えたその枝からは、別荘を取り囲むゲッケイジュの森が育ちます。その森のゲッケイジュで凱旋する歴代のローマ皇帝の冠が編まれ、使った枝から再び挿し木をして育ち、別荘は白鶏荘と呼ばれるようになりました。ゲッケイジュの木は皇帝の死期が近づくと立ち枯れ、王朝最後の皇帝ネロの死期には、森全体が枯死したのだそうです。 古代ローマの邸宅の壁画の例、花飾りの模様も定番でした。 描かれた庭の魅力 この夢のような庭園風景の中に佇むと、時が止まったような空気に包まれ、ずっとそのまま座っていたいような気がしてきます。この感じはどこかに似ている……そう、パリのオランジュリー美術館のクロード・モネの睡蓮の部屋に座った時の感じを思い出しました。 モネが自分の庭の睡蓮池の風景を描いた、楕円の展示室の壁を覆う絵画は、二次元のタブローという感覚を超えて、観る人を包み込んでしまうインスタレーションアートのように圧倒的。庭の描写というより、そのエッセンスから生まれた庭の風景のよう。 鳥籠も描かれています。 この古代ローマの庭園画は、昔日の庭園の様子を知るという意味でも興味深いですが、何よりも、時を超えた生命が宿る幻想の庭のごとき、描かれた庭ならではの独特の庭園空間を堪能できるのが素晴らしいです。 [作品] リウィア荘の壁画 ローマ国立博物館(マッシモ宮)MUSEO NAZIONALE ROMANO所蔵
-
ストーリー

バレンタインのギフトはサステナブルな「スローフラワー」で【フランス花便り】
バレンタインは「スローフラワー」を選ぼう スローフラワー、って聞いたことありますか?日本ではまだ馴染みが薄いかもしれませんが、近年パリでは「スローフラワー」を扱うおしゃれな花屋さんが増えて、人気を集めています。ところで、そのスローフラワーとは? これは、スローフードなどからインスパイアされた呼称で、ローカルにサステナブルな方法で栽培される季節の切り花が「スローフラワー」です。 エコロジーやサステナビリティは、もはや日常の生活に欠かせない選択基準。そんななか、バレンタインに花束を贈るのならば、ぜひスローフラワーを選んでほしい、という環境意識の高いフローリストや生産者たちの声が広く聞こえるようになってきています。 フランスのバレンタインデーのギフトのベーシックは? さて、恋人たちのためのバレンタインデーは世界共通なれども、祝い方には国によってちょっとした違いがあるようです。日本では女性から男性にチョコレートを贈るのがスタンダードですが、フランスではむしろ男性から女性に赤いバラなどをプレゼントする日なのだそうです。花をはじめ、香水やランジェリーなど、ロマンチックな贈り物が定番です。 バレンタインの赤いバラ なかでも赤いバラの花言葉は、愛情や情熱、アイラブユーとまさに愛の告白で、バレンタインデーやプロポーズに“愛する人に贈る花”、とされてきました。ところがバレンタインデーの2月14日は、立春も過ぎたとはいえ、まだ真冬。それは日本とほぼ同じ四季のサイクルのフランスでも同じこと。たとえばパリと近辺のイル=ド=フランス地方のバラの季節は、だいたい4月から11月頃まで。2月の庭にバラが咲くことは、まずないのです。 では、この赤いバラはどこからやって来るのでしょうか。遠くエクアドルやケニアなどの温室で安価な労働力を使い管理栽培された切り花が、オランダの生花市場などを経由して届きます。見た目は端正だけれども、多大なCO2を消費して届けられる、かつ目には見えないけれど大量の農薬や殺菌剤でコーティングされた赤いバラなのです。 バレンタインデーは切り花販売の最盛期だそうですが、特に人気が集中するバラは、自然のサイクルを全く無視した方法で遠い外国で栽培され、調達されていることがほとんど。ちなみにフランスでは切り花市場の花々の8割以上が、こうした生産サイクルで外国から運ばれて来ているのだそうです。 近年は食卓に上がる野菜や果物に限らず、肌に触れるものなど、日常生活のあらゆる場面で安心安全なオーガニック、環境に優しいサステナビリティが選択基準の大事なポイントになってきました。野菜や果物に対して、地産地消で季節のものを大切にしたい、と思う人は多いことでしょう。それはじつは、切り花にとっても同じなのです。 スローフラワーで季節の花を愛でる このような切り花市場の事情を知ると、あえて季節外れのバラでなくても、この時期に美しい季節の花を選びたい、と思うのは、今やごくナチュラルな感覚になりつつあります。この時期のフランスだと、ハウス栽培にはなりますが、アネモネ、ラナンキュラス、チューリップやミモザなど冬から早春のフレッシュな可愛らしい季節の花々が選べます。花を愛でることはその季節を愛でること、今しかないこの季節を表現する花束を贈るのは、なかなかに素敵なことではないでしょうか。 ちなみに、万が一どうしてもバラがいい、という場合は、フランスでは南仏の生産地で、光エネルギーを利用するなど環境に優しい方法で栽培された、輸送距離も短くクオリティの高いバラを選ぶという選択肢もあるのだそうですが、あまりおすすめではありません。できる限り季節の花を大切にする、という発想が素敵だと思います。 パリのフローリストにて そんな訳で今回覗いてみたのは、パリの人気フローリスト「デジレ」。パリの中でもおしゃれなインテリアショップやパティスリー、バーやレストランなどが集まる地区にある、スローフラワーを扱う花屋さんの老舗的な存在。 環境に配慮したオーガニック栽培の国産の花々を専門に扱う「デジレ」の店頭を見ると、今の季節の花が分かります。寒い季節にはパリと近郊の露地栽培ものはお休みになりますが、もっと温暖な気候の南仏の生産地から届けられる花々があり、バラはなくともとてもバリエーション豊か。見ているだけでワクワクしてきます。 また、ガラス壁で仕切られたショップの隣には、小さな可愛いカフェが併設されており、すべて手作りされたオーガニックのランチや軽食メニュー、美味しいスイーツ類がいただけます。おしゃべりに興じる友人同士やラップトップを持ち込んで仕事をする人、ちょっとコーヒーブレイクに寄ったらしい近所の人など、それぞれが自分のリズムで楽しんでいる、普段着のパリジェンヌのライフスタイルを垣間見るようなリラックスした雰囲気も素敵。 スモールバジェットのためのアイデア、思い切ってシンプルに ところで、オーガニック生産の花は割高なのでは? とか、花を贈りたいけれど、花束にするには予算が心配、という迷いがあるかもしれません。例えば大輪の赤いバラなら一輪でもさまになるけど、ほかはどうなの、という声もありそうです。でも、心配無用。スモールバジェットでも花の楽しみ方はさまざまです。 例えばラナンキュラスやアネモネは、一輪挿しで飾るだけでも、じつは大いに存在感があり、かえって大勢でワイワイと花束になった時よりも、花の個性を感じることができます。幾枝かのミモザや、1種類のチューリップのみ、などのブーケは潔く、花種の選び方次第でグッとスタイリッシュにもなります。 さて、バレンタインデーにも、チョコレートの代わりに季節の花を贈るのはいかがでしょうか? 花が私たちに伝えてくれる今の季節を一緒に楽しむことを大切に、ちょっとした贈り物に、もちろんご自宅用、ご自身へのプレゼントにも、ぜひ気軽にローカルな季節の花を活用してみませんか。 Information
-
宿根草・多年草

冬の庭の宝物「スノードロップ」の花風景【フランス庭便り】
早春の球根花、スノードロップ フランス語ではペルスネージュ(perce neige)、和名では雪待草などとも呼ばれるスノードロップ。ヨーロッパ~コーカサス山脈が原産地ですが、ヨーロッパ~西アジアに20種弱が広く分布し、フランスでは庭園の植栽に限らず、森の中や野原などにも自然の群生が見られます。学名はGalanthus nivalis、スズランなどと同じヒガンバナ科で、球根には毒があるので、取り扱いには注意です。 春の先駆けの魅力 森の林床や庭園や公園の芝生など、さまざまな場所で、時には積もった雪の下からも、この時期になるとむくむくと顔を出すのがスノードロップです。地方にもよりますが、冬のパリやイル=ド=フランス地方は、基本的に曇ってて暗くて寒いイメージです。そんななか、例えば冬枯れのヴェルサイユの庭園を囲む森の中を歩きつつ足元に目をやると、何やらシュッとした新鮮な緑の葉っぱがたくさん元気そうに育っている。さらによく見ると、小さなティアドロップのような可憐な花が咲きかけている。しかも1本、2本ではなく、あちこちに群生している姿には、宝物を見つけたような高揚感があります。 名前の由来 スノードロップという呼び名は、涙形の花の形から。17世紀にヨーロッパで流行したティアドロップ形の真珠のイヤリングのドイツ語呼称に由来するそうです。フェルメールの絵画の少女が耳につけていた、あのイヤリングです。可憐なイメージにぴったりの由来ですね。 小さな花の一つひとつも可愛らしいのですが、冬の終わりの林床を埋め尽くすように咲く満開のスノードロップは、さながら白い絨毯のようで、感動的といってもよいほど。 昔の人々も、はっとするようなスノードロップの白い絨毯に、きっと大感動したに違いありません。花言葉は主なところで「希望」や「慰め」とされているこの花には、じつにさまざまな伝承があります。 さまざまな伝承 キリスト教では聖母マリアの花とされているスノードロップは、イエス・キリストの奉献、聖母マリアの御清めの祝日である2月2日の聖燭祭に関わりが深く、この日にスノードロップを集めて持ち帰ると家が浄化されるといわれています。ちなみに少々脱線しますが、フランスでの聖燭祭(フランス語ではシャンドルールと呼ばれます)の日は、クレープを焼いて食べる日でもあります。 ほかにも、エデンの園を追われたイヴが初めて地上で迎えた冬の日、一面雪で草花が何もなくなってしまったのを嘆くイヴを慰めるために、天使が降る雪をスノードロップに変えたという伝説もあります。そこから花言葉の「希望」や「慰め」に繋がるのでしょうか。 ドイツでは、雪にはもともと色がなかったので、花々に色を分けてほしいと頼んだものの、唯一応じてくれたのはスノードロップだけだった、だから雪は白いのだという伝承もあります。 いずれのエピソードにも、優しさがこもった可憐なスノードロップらしさが感じられるようです。 寒さに強いスノードロップ 雪の日や寒い朝は、白い水滴のようにしっかりと花を閉じて、日中暖かくなってフワッと目一杯花を開いた姿は、ウサギの耳みたいに見えて、これもまた可愛らしい。夜間や寒い時に花を閉じるのは、昼間吸収した暖かい空気をしっかりキープするためなのだそうですが、さすが寒さに負けず花咲くには、それなりの工夫が備わっているものです。 開花シーズンは2~3月 聖燭祭は2月のはじめですが、暦通り、イル=ド=フランス地方では、例年2月に入ってからがスノードロップの開花シーズンです。開花が始まってから2~3週間は、花咲く姿を楽しめるのも嬉しいところ。 花期の後半には、クロッカスやスイセンなどのスプリング・エフェメラルが追いついて咲き始めます。庭園の芝生や大木の足元に、スノードロップとともに、またはその後に、さまざまな球根花がカラフルに咲き乱れる姿からは、しっかりと季節がどんどん春に向かって進んでいるのを実感できます。 森の魔法のような白い絨毯 とはいえ、ちゃんと春が来るのか少し疑わしいほどに寒々とした時期に、林床に広がるスノードロップの花の存在感、その白い絨毯は、本当に圧巻です。背丈も低いので、花の時期が過ぎると、どんどん後から育ってくる他の植物の陰に隠れて、すっかり存在感がなくなってしまいます。それゆえなおさら、花の時期には特別感があるのでしょうか。 一種類の花の群生には、たとえ一つひとつは派手でなくとも、全体力で印象深い風景をつくる力が備わっているのを感じます。例えば、ヒマワリ畑やポピーの群生、梅林や桜並木、ツツジやアジサイなど、その時期の風物詩になるような、また特別な場所のイメージに繋がるような花の風景がいろいろ思い浮かぶのではないでしょうか。 スノードロップの白い絨毯から思い浮かぶのは、森に束の間の魔法がかけられたみたいな、ヨーロッパのお伽話のシーンのようなイメージです。妖精が潜んでいても不思議じゃない、そんな気がしてくるほどです。この白い絨毯の風景に出逢ったら、1鉢のスノードロップに感じる魅力もまたさらに倍増する違いない。そんなことを思いつつ、寒さのなかを進む自然とともに春を待つ日々です。 ●スノードロップの育て方。コツとお手入れ、植え替えや寄せ植えを一挙紹介
-
ガーデン&ショップ

珠玉のプロヴァンススタイル・ガーデン「ラ・ルーヴ庭園」
プロヴァンス・スタイルの「ラ・ルーヴ庭園」 太陽がいっぱいの南仏プロヴァンスのガリーグと呼ばれる灌木林には、自生のタイムやローズマリーの群生が広がり、西洋ウバメガシやカシの木、ツゲなどの自生樹種が山野を彩ります。リュベロンの小さな村ボニューにある「ラ・ルーヴ庭園」は、そうしたローカルな自然を取り込んだ、元祖コンテンポラリーなプロヴァンス・スタイルのガーデンです。 フレンチ・シックなガーデンデザイン リュベロンの山を望み、岩壁を這うようにつくられた庭園のテラスに入ると、さまざまな常緑灌木が球形または大刈り込みのように繋がり、立体的な緑の絨毯が広がるような姿に驚かされます。フレンチ・フォーマル・ガーデンというとシンメントリーで幾何学的な、整ったイメージですが、それとも違うのだけれども、大変シックに美的に整っており、同時に庭の生きた魅力に満ちているのを感じます。歩を進める度に微妙に庭の眺めが変わり、細長い庭園の園路を進んでいくと、ラベンダー畑やブドウ畑からインスパイアされたのであろうプロヴァンス風景のコーナーがあったりと、決して広くはない庭園なのに、変化に富んだ散策が楽しめます。 土地の自然を取り込む自生樹種をチョイス トレードマークともいえるツゲやローズマリーなどをはじめとするすべての刈り込みの灌木類は、庭を遠巻きに囲む山々にある自生樹種が選ばれています。土地の風土に適した、手入れがなくとも育つ丈夫な木々が庭に取り込まれ、それぞれの緑のトーンやテクスチャーの違いが豊かな表情を見せます。それはまた、プロヴァンスの明るい透明な光の具合によって、さらに輝きを増すのです。刈り込みの常緑樹木には変化が少ないように思われるかもしれませんが、季節によって、また朝昼晩の光の違いによって、生き生きと変化する絶妙な庭の風景を作り出しています。プロヴァンス独特の自然の産物である樹木の緑や太陽の光が最大限に生かされ、独自のスタイルとなっているのが、このガーデンの特筆すべきところです。 ラ・ルーヴとの運命の出会い この庭をつくったのは、元エルメスのデザイナーでもあった女性、ニコル・ド・ヴェジアン(Nicole de Vésian/1919~1999)。南仏プロヴァンスの土地の魅力に魅せられ、ラ・ルーヴ(仏語で狼のこと)と名付けられた村外れの邸宅と土地を購入したのは1989年、70歳の時でした。山の眺めに向かって大きく開かれた3,000㎡ほどの土地がたちまち彼女を魅了し、建物の中も見ずに購入を即決したのだとか。そして、70歳にして彼女の最初の庭づくりが始まったのです。 70歳にして初めての作庭 当初は庭づくりの知識などなかったので、何人かの庭師を雇って作庭を始めました。植物の知識はなくとも、このような庭にしたい、という絶対的なイメージがあって、そのクリエーションを庭師たちの職人技が支えていく、そんな感じだったのでしょう。その作庭の方法はデザイナーとしては独特で、「図面も描かないし、長さも測らない」。すべて現場で、植栽前に植物の配置を何度も並べ替えて、徹底的に目視で確認して決定するというやり方です。庭師たちにとってはたまったものではなかったことでしょう。しかし、一緒に仕事をしていくうちに、あうんの呼吸が生まれ、後に、彼女の庭を訪れたセレブたちから次々と庭園デザインの仕事が舞い込むようになった時には、必ずお気に入りの庭師たちとのチームで仕事を受け、海外からの依頼を受けた際にも自分の庭師たちを連れていったのだそうです。 フランスのみならず、特に英米からの来訪者が多かったそうですが、ある美術評論家は彼女の庭を美術作品のごとき「傑作」だ、とたたえ、ニコルには音楽での絶対音感のような、絶対的な空間造形の感覚があるのだろうと評しています。 ローカルな素材への愛着 見事な刈り込みの緑の造形の他にも、庭の主たる構成に見えるのは、ローカルな石への愛着。ルネサンス庭園にあるような非常にシンプルな球形の石造彫刻や、地元の廃墟となった庭園や建物からリサイクルした石がふんだんに使われています。 日本庭園への憧憬 ところで、石と刈り込みの緑といえば、日本庭園にも共通するアイテム。プロヴァンスの自然と彼女の感性から生まれたであろうデザインでありながらも、日本人から見たら、どこか日本庭園に通じる雰囲気も感じられるのも、この庭の不思議な魅力です。その背景にある哲学や美学は異なるものであろうとも、アシンメトリーな構成や、シンプリシティや自然へのリスペクトを追求する庭づくりには、伝統的な日本庭園を彷彿とさせる完成された美観と静けさが満ちています。ニコルはデザイナーの仕事で何度も日本を訪れており、日本庭園も見ていたはず。何らかの形でインスパイアされた部分があるのかもしれません。 80歳の時、ニコルは次の庭をつくるべく別の土地を購入し、そのためラ・ルーヴ庭園を売却しています。残念ながら新たな庭を完成する前に世を去ってしまうのですが、その次作には、なんと日本風の庭園を作る構想を立ていたのだそう。つくられなかった庭がどんなものになったのか、興味深いところです。 生き続けるラ・ルーヴ庭園 その後のラ・ルーヴ庭園の所有者は何代か変わり、現在は、やはりこの庭園に魅了された元ギャラリストの夫妻が所有者となっています。庭は生き物なので、継続的な手入れが欠かせません。長い年月の間には、庭の木が成長しすぎてバランスが崩れたり、あるいは枯死したりといった事態も起こります。また、作庭当時に比べて夏の暑さが一層厳しくなるなどの気候の変動に対応し、一部植物のチョイスを変えるなど、常に調整が必要です。所有者はニコルがつくり上げた庭園のエスプリを尊重しつつ、今も大切に庭を育て続けており、見学も可能です。 何歳からでも庭づくりを 70歳からの作庭で、いくつもの名園をつくり上げたニコル・ド・ヴェジアン。デザイナーとしての素養と慧眼のうえに、晩年の彼女に目覚めた自然への愛、庭づくりへの情熱が生んだ、彼女独自のプロヴァンス・スタイル・ガーデン。そうして生まれたガーデンは、彼女が亡くなってからも、多くの人々を魅了し、世界中に影響を与え続けています。
-
ストーリー

オリーブの収穫期を迎えた南仏プロヴァンス便り
南仏プロヴァンスのオリーブの木々 プロヴァンスの風景の象徴、オリーブの木々。 世界で栽培されているオリーブの樹種は1,000種以上あるそうですが、大きく分けると果実加工用とオイル加工用の2種類になります(両方兼ねる場合も)。太陽がいっぱいのプロヴァンス地方ですが、冬場は氷点下となることもあるので、栽培に向く樹種としては耐寒性が高いことが必須です。 収穫されたばかりのオリーブの実。 例えばプロヴァンス地方、ヴォークリューズ県で最も多く栽培されているのが、オイル加工用のアグランドー種。喉越しがピリリとするフリュイテ・ヴェール(Fruité vert)と呼ばれるオイルになります。そのほか、ピショリーヌ種、レロナック種、グロサンス種なども多く栽培されています。また、オリーブの木は自家結実性が低いので、受粉用に2種類以上の樹種を植えるのが通常です。 オーナメンタルと実用を兼ねるオリーブの木 プロヴァンス地方のオリーブの木は、オーナメンタルと実用を兼ねた植栽樹として選ばれていることが多いのが特徴です。アマチュアのオリーブ栽培家たち(専業農家ではない)がたくさんいることも、その理由の一つに挙げられると思います。シンボルツリーとして植えられるのはもちろん、広い敷地であれば、周囲の景観と調和させるために、庭がオリーブの木々を何千本と植えたオリーブ畑になっているのを目にするのも珍しくありません。 オリーブの栽培には、もちろん施肥や消毒、剪定などの定期的な手入れが必要です。しかし、例えばブドウ畑を作ってワインを醸造するのは素人にはかなり難しいことですが、比べてオリーブ栽培はだいぶハードルが低く、自家製オリーブオイルを味わうことができるのが大きな魅力にもなっています。 みんなが集まってオリーブ収穫祭り 友人知人が集まったオリーブの収穫。 そしてプロヴァンス地方のオリーブ栽培の隠れた魅力は、なんといっても収穫のとき。集約農業のオリーブ畑の収穫は、機械化されトラクターで行われていますが、アマチュア栽培家の景観重視のオリーブ畑は機械が入れないような地形になっていたり、また、個人宅ではそこまでは必要ない規模であることも多く、収穫は手作業で行います。たくさんオリーブの木があれば人手も必要ということで、家族や友人・知人が集まって、ワイワイと収穫作業を行う絶好のお祭りイベントになるのも、プロヴァンスの特徴かもしれません。 テラスの太陽の下、長いテーブルでわいわいとランチタイム。 午前中から集まって収穫を始め、ランチをしっかり楽しんだ後は、また暗くなるまで収穫作業。といっても、この時期は日暮れも早く、午後17時にはすでに暗くなるので、そのままお開きだったり、さらにディナーが用意されていることも。 オリーブの収穫はどんな風に? ラトー(熊手またはレーキ)かペーニュ(櫛の意味)と呼ばれる道具を使って収穫します。 収穫作業に活躍するのがラトーと呼ばれる小さなプラスチックの熊手です。地面にはネットを敷いて、この熊手でオリーブの枝を梳かして実を落とします。背が高い木は、梯子を使ったり、木に登ったり、それでも手の届かない場所は枝をググッと引っ張って(よくしなって滅多に折れない)たわわになった実を梳かし、地面のネットの上に落としていきます。 ネットの上に落ちたオリーブの実を集めているところ。まるで地引き網のよう。 全体にくまなく実を落としたら、次は地面のネットを引っ張って実を1カ所に集め、ケースに移していきます。手作業の収穫は人出も時間も必要ですが、機械よりはずっと木に優しいという利点もあります。 オリーブの搾油所(ムーラン) 「O comme Olive」というお洒落な名前のオリーブ搾油所。地元の人々が次々と訪れます。 さて、収穫したオリーブの実は、その日のうちか、遅くとも翌日にはムーランと呼ばれる搾油所に運びます。というのも、搾油するまでの酸化度が、オリーブオイルのクオリティーの違いの重要なポイントになるのです。収穫した実の酸化が進まないうちに、できる限り迅速に搾油工程に入るのが美味しいオリーブオイルを抽出する秘訣です。 オリーブ搾油の工程。洗浄ののち粗砕・撹拌に向かうたくさんのオリーブの実。 洗浄ののち、粗砕・撹拌されてペースト状になったオリーブの実は、加熱などの加工をせずにそのまま遠心分離機にかけ、オイルを抽出して、エクストラ・ヴァージン・オイルが出来上がります。 また、若いグリーンのうちに収穫した実のオイルは、喉越しが辛口のパンチが効いた味、黒っぽくよく熟した実は、まろやかな味のオイルになるのだそう。どちらがよいかは好みですが、オリーブオイル愛好者には、前者の角の立った味が好まれる傾向があるのだとか。 アグランドー種のグリーンの実。 オリーブ10kgから採れるオイルはおよそ5ℓ。収穫量が少ない場合、一般には搾油の際に他の畑のオリーブとのミックスになってしまうことが多いのですが、こちらは他とは混ぜずに、オリーブ50kgと小ロットからオリジナルのオリーブオイルを作ってくれるので、アマチュア栽培家たちに人気の地元のムーラン。最盛期の週末の夕方~夜には、日中収穫したオリーブを持ち込む客が列を作ることも。 夕刻、収穫したオリーブのケースを運び込む人々。最盛期には長蛇の列ができることも。 ちなみに、大きなオリーブの木からは、1本で70~80kgほどの実が収穫できることもあるそうですが、オリーブ50kgというと、通常でも10年くらいの木から平均10kgのオリーブの実を収穫したとして5本あれば到達する量で、ハードルはそれほど高くないといえます。畑とはいわないまでも、しっかりしたオリーブの木が自宅の庭に何本かあれば、オリジナルの自家製オリーブオイルを楽しむことができるなんて、なかなかに素敵です。 ピクチャレスクなオリーブの木々。 自家製オリーブオイルは、収穫場所からのアクセス圏内に搾油所がないとなかなか実現が難しいですが、オリーブの木々が南仏プロヴァンスの風景に、また人々のライフ・スタイルに深く根付いているのだなあと改めて感じるのがこの収穫の季節です。プロヴァンス料理では日常的にオリーブオイルをよく使いますが、温かいお米にも塩胡椒を振ってオリーブオイルを混ぜてメインの肉や魚への付け合わせにしたり、冷えたお米はサラダにしたりします。美味しいエクストラ・ヴァージンのオリーブオイルは、加熱せずに生で使うのもポイントです。 小さな若木はまだ実が少なく、ネットを敷くほどでもないのでカゴで収穫。ちなみに長靴は「日本野鳥の会」で販売している折りたためるタイプ。フランスの人々にも好評です。 鉢植えでも育つオリーブの木 オリーブオイルは栄養豊富なばかりでなく、抗酸化作用が高いことでも知られていますが、葉っぱにも抗酸化作用があり、花にはリラックス・癒やしの効果があるそうです。また生命力の象徴ともいわれるオリーブの木、じつは鉢植えでも十分育てることができるので、果実加工用の樹種などを選んで自宅でトライしてみるのもよいかもしれません。 プロヴァンスの白っぽい石壁の色合いが、オリーブによく似合う。 併せて読みたい Credit 写真・文/遠藤浩子 フランス在住、庭園文化研究家。東京出身。慶應義塾大学卒業後、エコール・デュ・ルーヴルで美術史を学ぶ。長年の美術展プロデュース業の後、庭園の世界に魅せられてヴェルサイユ国立高等造園学校及びパリ第一大学歴史文化財庭園修士コースを修了。美と歴史、そして自然豊かなビオ大国フランスから、ガーデン案内&ガーデニング事情をお届けします。田舎で計画中のナチュラリスティック・ガーデン便りもそのうちに。 blog|http://www.hirokoendo.cominstagram|moutonner2018
-
家庭菜園

本場フランスでも再注目の家庭菜園「ポタジェ」を解説
ポタジェって何? SNHF(全仏園芸協会)のポタジェ大賞(2016年)を受賞したシャトー・コルベールのポタジェ。18世紀のポタジェをリノベーション。 「ポタジェ」や「ポタジェガーデン」という言葉、耳にしたことがあるでしょうか。ポタジェ(Potager)という呼称はフランス語のポタージュ(Potage, スープのこと)からきたもので、スープの材料となる野菜を育てる場所、つまり菜園のこと。野菜だけでなく、果樹やハーブや花なども栽培する美観を備えた庭を意味します。 「ポタジェ・ガーデン」の魅力 サン・ジャン・ド・ボールギャール城のポタジェで見られるエスパリエ仕立て。 実用的な野菜や果実を栽培するにしても、いわゆる畑とは違った、オーナメンタルなガーデンとして景色に馴染むのがポタジェのよさ。植栽の仕切りには果樹のエスパリエを仕立てたり、レイズドベッドにも野菜や花を取り混ぜてみたりと、自由な発想で庭づくりの楽しさと収穫の喜びの両方を満喫できるのが嬉しいところです。 ポタジェの歴史 秋のポタジェ・デュ・ロワ。さまざまなエスパリエ仕立ての果樹が並ぶ。 「ポタジェ」の歴史は古く、果樹や花々が美しくあふれる聖書のエデンの園もポタジェの祖先といわれます。中世の修道院ではすでに薬用や食用になる植物を育てるハーブ園があり、17~18世紀のフランスの王侯貴族の城館の庭には、必ず「ポタジェ」がありました。 ポタジェ・デュ・ロワ。グラン・カレと呼ばれる中心部は野菜栽培が中心。 もっとも名高いポタジェは、17世紀、太陽王ルイ14世の食卓のために野菜や果樹を栽培したヴェルサイユの「王の菜園(ポタジェ・デュ・ロワ)」でしょう。完璧なフレンチ・フォーマル・スタイルで構成されたこのポタジェは、果樹栽培に関心を寄せていた王自らがしばしば散策に訪れ、お気に入りの庭師と語らったという場所。当時最先端の栽培技術でさまざまな珍しい野菜や果樹を生産するばかりでなく、散策が心地よいものになるような美観を備えた場所でした。さすが美オタクのフランス人の矜持を感じさせる「ポタジェ・デュ・ロワ」ですね。 秋のポタジェ・デュ・ロワ、手前は多年草のフェンネル。 もちろん、ポタジェが営まれた城館や宮殿はヴェルサイユにとどまりません。現在もフランス各地の城館にポタジェがありますので、庭園見学の際にはぜひ覗いてみたいものです。実用と装飾を兼ねた、まさに用の美ともいえるガーデニングは、美オタク的かつケチケチ精神もたくましいフランス人の性格にしっくりきたのでしょうか。この習慣はブルジョワ階級に受け継がれ、広く一般化していきます。 フランスでも「ポタジェ」がブーム 春秋にはガーデニングショーも開かれるサン・ジャン・ド・ボールギャール城のポタジェ。 このように伝統あるフランスのポタジェですが、じつはこのところ特にフランス人たちの間で、再び「ポタジェ」人気が高まっています。きっかけは、コロナ禍による数カ月のロックダウン。自宅に引きこもらざるを得ない厳しい外出制限下で、フランス人の10人中6人、なんと人口の半数以上がガーデニングに勤しんだという調査結果があります。 パリのカトリーヌ・ラヴレ公園の一角にあるポタジェ。夏には水着で日光浴をする人も。 ロックダウンの中で、期せずして、庭で、あるいはテラスやバルコニー、キッチンの窓辺でも、とにかく植物を育てて親しむ人が増えました。そして、それは植物との触れ合いが生活にいかに潤いを与えてくれるかということに多くの人々が気付き、深く実感するきっかけになったのです。 南仏にある田舎家のポタジェの初夏。手前はコンパニオンプランツとしても優秀なナスタチウム。花はサラダに入れたりして食べられます。 じつは何を隠そう、フランスの田舎にある我が家でも、やはり2年前のロックダウン中に、パートナーが突如としてポタジェづくりを始めました。試行錯誤を重ねつつ、2期目に入ろうとしているところです。 また一方で、温暖化対策の一環としてパリなどの大都市では都市緑化が推進され、都会暮らしのパリジャン・パリジェンヌの間でも、ガーデニングへの関心が高まっています。オーガニックへのこだわりも一般化していることから、初心者ガーデナーたちにとっても、自宅でガーデニングを始めるにあたり、安心して食べられる緑を育てられれば一石二鳥。満足度も高く、子どもの教育にもよい、と「ポタジェ」ブームがどんどん広がっています。 さまざまなポタジェ 毎年春から秋にかけてガーデンショーも行われる、ショーモン・シュル・ロワール城のポタジェ。アーティチョークの花はポタジェのオーナメンタルとしても優秀。 例えば庭がなくとも、バルコニーやテラスの限られた空間でも、コンテナや植木鉢を上手に使って小さなポタジェを楽しむことができます。最近、パリの街中では、市民のためのシェア・ガーデンとしてのポタジェを方々で見かけるようになりました。シェア・ガーデンでは、隣り合う人々の間でコミュニケーションが生まれ、人の繋がりが自然と育まれていく、そうしたことも都会では貴重な収穫と捉えられています。また、ある有名百貨店の屋上には社員の福利厚生目的でつくられた、とってもお洒落なポタジェがあったりもします。ちょっと羨ましいかも。 最近オープンした、ホテル・グランドコントロール内のアラン・デュカスのレストランテラスとポタジェ。お客さんはポタジェも見学できます。 一方、ポタジェが大ブームになる以前から、ガストロノミーな高級レストランの間では、こだわりの採れたてオーガニック野菜を使った料理という最高の贅沢を追求するために、自前のポタジェを持つのが流行っていました。そんな訳で、ミシュラン星付きレストランのポタジェというのも、珍しくないほどになっています。 ポタジェはオーガニックが基本 ショーモン・シュル・ロワール城のポタジェ。 これらのポタジェに共通するのは、いわゆるオーガニックな栽培です。なるべく環境に負荷をかけない自然な方法を志向するガーデニングが当たり前になっているフランスでは、食卓に直結する食物を育てるポタジェではことさら、化学肥料や農薬を使わないナチュラル・ガーデニングが主流。自然素材のマルチングを使ったり、コンポストを利用したり、廃品パレットでアウトドア・ファニチャーを作ってみたり。ポタジェは、さまざまな創意工夫の場でもあります。 昆虫ホテル。 ところで、ポタジェで目にするアイテムの一つに、昆虫ホテルなるものがあります。受粉を媒介する昆虫たちは、ポタジェの植物にとって大切な存在。ポタジェでは、植物たちの美観と実用のみならず、その周りの昆虫やらさまざまな自然の働きにも目が向くようになってきます。ひいては生き物の多様性やエコロジーの大切さに思いを馳せるきっかけにもなる、まさに人と自然をつなぐ、日々の癒やしの場がポタジェ。収穫の後の食卓の料理に思いを馳せながら、あなたの「ポタジェ」を、さっそく始めてみませんか?
-
ガーデン&ショップ

シャンティイ城のガーデニングショー【フランス庭便り】
シャンティイ城のガーデニングショー 秋は暖かな季節の名残を惜しみつつも、来春の植栽などを考え始める、ガーデナーにとってある意味心躍る季節ではないでしょうか。そんな時期、フランスの園芸好きの人々が心待ちにしている年中行事の一つが、ジュルネ・デ・プラント(プランツデー/植物の日)。毎年春と秋に開催されるシャンティイ城のガーデニングショーです。 なぜお城でガーデニングショー開催? シャンティイ城といえば、ルーヴル美術館に次ぐほどレベルの高い美術コレクションや、ル・ノートル設計のフォーマル・ガーデンがあることでも有名なお城です。パリから車で1時間ほど。電車でもアクセスできるので、観光スポットとしても人気です。 そんな場所で、なぜガーデニングショー? と思われるかもしれませんね。このガーデニングショーの発端は、30年以上前に遡ります。最初はクルソン城という別のお城で、全仏植物園協会の会合が開かれた際に、その余興として植物の交換会をやろうという計画が立ち上がります。会員の中にはナーサリーを営む人もいて、最終的には植物の販売会が開催されることになりました。すると、隣国イギリスでしか売っていないと思われていた植物をフランスのナーサリーでも扱っていたなど、さまざまな嬉しいサプライズがあって大成功! これがきっかけとなって恒例開催されることになったのだそう。その後、庭好き・植物好きのクルソン城の城主夫妻が主導して32年続いたガーデニングショーは、シャンティイ城に引き継がれ、この城での開催は2021年で6年目となります。 会場そのものが魅力的 ちなみにフランスのお城は、仏文化省に文化遺産として登録されているものだけでも11,000件。登録されていないものも含めれば45,000件ほどと推測されています(その8割以上は個人所有)。膨大な面積の森と広い庭園に囲まれたフランスのお城は、じつは豪華な結婚式や企業イベントなどに最適な場所として利用されることが多くあります。このガーデニングショーの会場でも、お城の建物や庭園、森の木々を背景に、販売スタンドやショーガーデンが立ち並ぶ風景には、自然の美しさばかりではない非日常感があって、ウキウキ度も倍増です。 遠方のナーサリーの植物を一度に見られる 毎年、春秋の週末3日間に行われるこのガーデニングショーには、いつも2~3万人の来場者があるそうです。まずその魅力の一つは、普段はなかなか見て回ることができない遠方のナーサリーが一堂に集まること。フランス国内だけでなく、ベルギーやドイツなど近隣諸国からも国境を越えて出展者が集まり、全部合わせると180ほどにもなります。 また、ナーサリーの出店資格は専門家コミッティーによって厳正に審査されるので、その質の高さも折り紙付き。普段あまりお目にかかれないバラ専門、アジサイ専門、多年草専門、カエデ専門などさまざまな専門ナーサリーが集まるうえ、おしゃれかつ実用的なガーデニング道具やウェアなどのショップも並びます。 最近はパリ市内でもおしゃれなガーデニングショップが増えてきましたが、季節の植木苗などを購入するのには、一般的なチェーンのガーデニングショップやホームセンターが一番近い、ということも多いのが実情です。そうした一般的なショップでは見つかりにくい珍しい植物がその場で選べるのは、本当に魅力的。そんな訳で財布の紐もゆるゆるになりがちな、大変危険な場所でもあります。 生産者や専門家たちと直接コミュニケーション 遠方のナーサリーが集まっているガーデニングショーは、植物好きの交流の機会であることも大きな魅力です。業界人の間でのコミュニケーションもあれば、顧客側にとっても、直接生産者に質問をしたり、育て方のアドバイスを聞いたりというコミュニケーションの中で仕事への姿勢が分かり、その後彼らの通信販売をなども安心して利用することができます。また、会場では「果樹の剪定の仕方」など、さまざまなワークショップや講演、親子向けのアクティビティなどもプログラムされていますので、ずっと気になっていた植物を入手したり、新しい品種を発見したり、興味のある項目を学んだり、と飽きることなく丸一日楽しむことができます。 シャンティイ城の隠れ名物デザート「クレーム・シャンティイ」 会期中はお城の敷地内、英国式庭園部分の広い芝生のエリアがショー会場となり、出店スタンドのテントなどのほかに、軽食を販売するトラックがいたり、休憩所などが設けられていたり。青空の下でのランチやおやつも完備されています。なかでも有名なシャンティイ城の名物デザートは、元祖クレーム・シャンティイ。 クレーム・シャンティイとは、生クリームを泡立てた、つまりホイップクリームのことなのですが、この城で17世紀コンデ公に仕えた有名な料理人ヴァテールが考案したのが始まりといわれています。すでに18世紀には、シャンティイ城を訪れた海外の王族をはじめ多数のゲストが、庭園内の田舎家風の園亭で軽食の際にサーヴされるクレーム・シャンティイの美味しさに感動の言葉を残していて、その噂は国境を越えて広がっていたとか。 毎回、このガーデニングショーを訪れるたび、植物探しに熱中するあまり、その味を知らずに終わってしまいます。今回は、ぜひこの元祖クレーム・シャンティイを味わってみなければと心に決めていました。ショー会場を少し離れて、アングロ=シノワ風と呼ばれる自然風の庭園の中を歩いて行くと、マリーアントワネットの王妃の村里にあるような田舎家風の園亭が見えてきます。内部は現在レストランになっており、天気のよい日には、庭で食事やお茶を楽しめます。 期待のクレーム・シャンティイは………ボリューム満点、通常のホイップクリームよりさらにしっかりどっしりとした感じで、味が濃くて美味しかったです! 甘みをつけるにはバニラ風味の砂糖を混ぜる。ポイントは極限までホイップすること。それ以上ホイップするとクリームが分離してバターになってしまうという、その直前までホイップするのがポイントなのだそう。定番は、イチゴやフランボワーズなどの赤い果実や、シャーベット、アイスクリームなどに添えて出されるのですが、冷静になってカロリーを考えると、ちょっと恐ろしくもあり。でも、今日はたくさん歩いたから、まぁよしとしよう! と心の中でかなり言い訳をしてしまいました(笑)。 ちなみに私の今回の主な戦利品は、これからが植え時のスイセンなどの春の球根類と巨大なアガパンサス。それに大好きなワイルドチューリップの球根も見つけて大満足です。