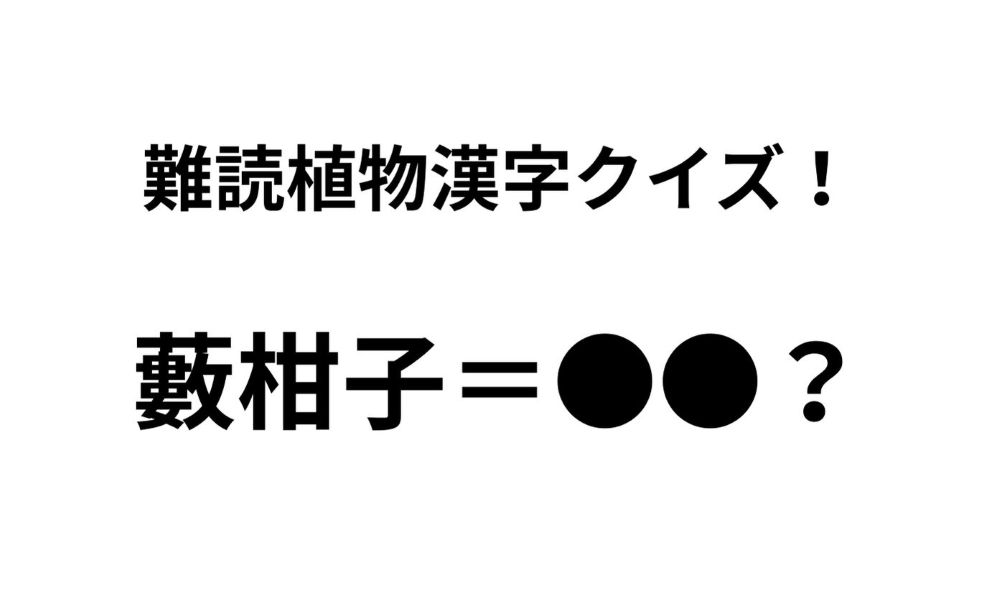おかざき・ひでお/早稲田大学文学部フランス文学科卒業。編集者から漫画の原作者、文筆家へ。1996年より長野県松本市内四賀地区にあるクラインガルテン(滞在型市民農園)に通い、この地域に古くから伝わる有機栽培法を学びながら畑づくりを楽しむ。ラベンダーにも造詣が深く、著書に『芳香の大地 ラベンダーと北海道』(ラベンダークラブ刊)、訳書に『ラベンダーとラバンジン』(クリスティアーヌ・ムニエ著、フレグランスジャーナル社刊)など。
岡崎英生 -文筆家/園芸家-

おかざき・ひでお/早稲田大学文学部フランス文学科卒業。編集者から漫画の原作者、文筆家へ。1996年より長野県松本市内四賀地区にあるクラインガルテン(滞在型市民農園)に通い、この地域に古くから伝わる有機栽培法を学びながら畑づくりを楽しむ。ラベンダーにも造詣が深く、著書に『芳香の大地 ラベンダーと北海道』(ラベンダークラブ刊)、訳書に『ラベンダーとラバンジン』(クリスティアーヌ・ムニエ著、フレグランスジャーナル社刊)など。
岡崎英生 -文筆家/園芸家-の記事
-
育て方

タネから花を育てよう! 種まきの適期・失敗しないコツ・発芽後の管理を分かりやすく解説
花のタネはどこで買えばいいの? 花のタネは信頼できる園芸店で買いましょう。自宅近くにいい園芸店がないときはネットを利用して、「サカタのタネ」(横浜市)、「タキイ種苗」(京都市)などの大手種苗会社の通販サイトから購入することもできます。 タネは、いつ播けばいいの? 花のタネを播くのに適している季節は、春と秋の年2回。春は3月中旬頃からが播き時となります。発芽に必要な温度は、通常、15〜20℃。種類によっては、もっと高い25℃前後を必要とするものもあります。発芽適温はタネ袋の裏面に必ず書いてありますので、タネを買ったら、その説明をよく読むようにしましょう。 どんな用土に播けばいいの? サカタのタネのジフィーピートバン。 市販の種まき専用土を使います。ただし、あまり安価なものは避けましょう。 「サカタのタネ」からは「ジフィーシリーズ」という種まき用グッズが各種販売されています。大きめのタネを播くのに適しているのは、小さなポット型の「ジフィーセブン」。発芽後、植え替えなしで、ポットごとそのまま定植することができます。 細かいタネを播くのに適しているのは、同シリーズの「ピートバン」。ピートモスを固めて薄い板状にした製品で、水でふくらませて使います。発芽した苗の初期生育に必要な肥料が入れてあり、酸度も調整済み。発芽率がとてもいいので、種まき初心者にもオススメできるすぐれものグッズです。 その他、必要な種まきグッズは? 上記以外にもタネを播けるものはいくつかあります。3号ポット(径3cm)をいくつか用意し、その中に種まき専用土を入れて、苗床をつくります。イチゴの空きパックなどを種まき用のトレイとして使うこともできます。その場合は、空きパックの底に水抜き用の小さな穴をいくつかあけ、種まき専用土を入れて苗床をつくります。 タネはどんなふうに播くの? まず苗床にたっぷりと水をやり、用土を十分に湿らせます。 指でつまめる程度のタネは、ひとつのポットに2〜3粒ずつ播きます。播いた後は、タネを指で用土に押しつけ、しっかりと密着させましょう。 細かいタネは用土を入れたトレイや、前記の「ピートバン」にバラ播きします。播き終えたら、タネを用土に押しつけ、しっかりと密着させます。 タネに土をかける? かけない? 花のタネには、発芽に光を必要とするタイプと、光に当たると発芽しないタイプがあり、このような性質のことをそれぞれ「好光性」と「嫌光性」といいます。 好光性なのか、嫌光性なのかは、タネ袋の説明に書いてありますので、それによって播いたタネに土をかける(覆土する)か、覆土しないかを決めます。 種まき後の水やりの方法は? K.Decha/Shutterstock.com 覆土した場合も、覆土しない場合も、ジョウロなどで一度にドッと水をやると、タネが動いたり、流れて一カ所に偏ってしまったりする恐れがあります。なので、いずれの場合も、霧吹きで丁寧にたっぷりと水やりをしましょう。 発芽するまで、この霧吹きによる水やりを続け、苗床が乾かないようにします。 直まきもOK? 花の中には、苗のときに移植されるのを嫌うので、コンテナや花壇に直まきしたほうがいい種類もあります。タネ袋の説明をよく読み、専用土にまくか、直まきするかを決めましょう。 タネを播いた後の置き場所は? 種まきをしたポットやトレイは、屋外ではなく、室内のなるべく日当たりのいい窓辺に置きましょう。日当たりのいい窓辺はポカポカ陽気。15〜20℃程度の発芽適温を確保することができます。 発芽までの日数は? 早いものは3〜4日で発芽します。通常は1週間から10日程度。もっと長く、14日前後かかるものもあります。それまで霧吹きでの水やりを続けながら、気長に発芽を待ちましょう。 「発芽発見」に大感激! ある日、苗床から緑色の小さな芽が顔をのぞかせているのを発見したときの喜びと感激! そして、その瞬間、ガーデニングは買ってきた苗を育てるより、種まきから始めたほうがずっと楽しいということに気づくのです。「発芽発見!」の瞬間の喜びと感激を知らないなんて、本当にもったいない! 発芽後の管理は? 発芽後は、しばらくそのまま水やりをしながら育苗を続けます。その後、本葉が2〜3枚、あるいは3〜4枚になった頃に、一回り大きなポットに植え替えたり、コンテナや花壇に定植したりします。 種類によっては、生育のよい苗だけを残す「間引き」の作業も必要となります。タネ袋の説明をよく読んで、植え替えや定植、間引きなどの作業を行いましょう。 苗が小さいうちは固形肥料を与えると、効き目が強すぎて、枯れてしまうことがあります。 肥料を与える場合は、200倍以上に希釈したごく薄い液肥にしましょう。ただし、可愛がっているつもりの与えすぎはNG! 2〜3週間に1回程度にしましょう。 タネから育てる花・おすすめ5選 タネから育てるおすすめの花1インパチェンス NANCY AYUMI KUNIHIRO/Shutterstock.com 初夏から晩秋になって霜が降りる頃まで咲き続けてくれる春播きの一年草。 播き時は4月上旬から5月下旬。先にご紹介した「ピートバン」に播くと、後の作業が楽です。タネは好光性なので、覆土はしません。 発芽後、本葉2〜3枚の頃に3号ポットに仮植えし、雨風に当てないようにしながら育苗します。本葉8枚ぐらいになったら定植の時期。日向よりも半日陰を好みます。夏の猛暑の時期にはちょっとお休みしますが、涼しくなると再び旺盛に花を咲かせてくれます。 さまざまな品種がありますが、「タキイ種苗」が販売している「F1アテナ・レッド」は、真っ赤なミニバラのような花が咲く八重咲き種。ハンギングにすると素敵です。 タネから育てるおすすめの花2ジニア(百日草) ShaikhMeraj/Shutterstock.com 多くの品種があり、花色も豊富。違う色をいくつも組み合わせて群植すると、素晴らしい景観をつくり出してくれます。 種まきの適期は4月の上旬、気温が20℃になった頃から。ポットに3〜4粒ずつ間隔をあけて播くか、あるいはトレイにやはり間隔を十分あけて播きます。 ジニアのタネは嫌光性なので、薄く覆土します。4月にタネ播きをすると、6月末頃から咲き始め、晩秋まで長く花を楽しむことができます。 草丈が40〜50cm以上になる高性種もあります。高性種を植えたときは、手前に草丈の低い草花を組み合わせると、美しさがより引き立ちます。 タネから育てるおすすめの花3アサガオ(朝顔) ruiruito/Shutterstock.com 朝顔は日本の夏を象徴する代表的な草花の一つ。江戸時代には栽培が大ブームとなり、さまざまな新品種がつくり出されました。 タネは外皮が固いので、一晩水につけて十分に吸水させてからまきましょう。このとき水に浮いているタネは除き、容器の底に沈んでいるタネだけを播きます。発芽適温が20〜25℃とやや高めなので、播き時は5月中旬から下旬にかけて。3号ポットに2〜3粒ずつ播き、タネを用土に密着させた後、1cmほど覆土します。 発芽までの日数は通常4〜5日。そのまま育苗を続け、最も生育のいい苗だけを残し、その他は間引きます。そして2枚の子葉が水平になったら、ピンセットなどで根を切らないように丁寧に掘り上げ、鉢やコンテナ、あるいは庭に定植します。 花が咲き始めるのは7月中旬頃から。一日花なので翌日にはしぼんでしまいますから、花がらを摘み取りましょう。摘み取らないと、やがてタネができます。そのタネを保存しておいて、翌年また播く場合は、花がら摘みはしません。だだし、こうしてできたタネからは、前年と同じ花が咲くとは限りません。 「西洋朝顔」は夏の終わりから咲き始め、秋遅くまで咲き続けるタイプ。大輪の空色の花が咲く‘ヘブンリーブルー’などがおすすめです。 タネから育てるおすすめの花4ペチュニア Job Narinnate/Shutterstock.com 多花性で、夏の暑さに強く、花期も長いので、多くの人に愛されている草花です。春先にさまざまな種類の花苗が販売されますが、ぜひタネから育ててみましょう。発芽適温が20〜26℃と高めなので、種まきの適期は3月中旬から5月中旬にかけて。ソメイヨシノが散った頃が、一つの目安となります。 前述の「ピートバン」に1粒ずつ、間隔をあけて播くと、発芽後の作業が楽。ペチュニアのタネは好光性なので、覆土はしません。発芽後、本葉3〜4枚の頃にポットに植え替えて育苗し、一番花のつぼみが見え始めた頃、鉢やプランター、コンテナなどに定植します。 長雨には弱いので、梅雨時は雨が当たらない場所に置きましょう。 しぼんだ花はそのままにしておかず、こまめに花がらを摘みましょう。また、伸びすぎた枝や枯れかけている枝は少し切り詰め、再生を促します。月に1度程度、薄い液肥を与えましょう。 タネから育てるおすすめの花5ナスタチウム(金蓮花) Shutova Elena/Shutterstock.com 赤、黄色、オレンジ色などの大きな花が咲き、黄緑色の葉も美しい春播きの一年草。ハーブの仲間で、花や葉にはピリリとした爽やかな辛みがあり、サラダに使うと彩りがよく、風味もアップします。 タネの播き時は3月下旬から5月上旬にかけて。3号ポットに1粒ずつ播き、1cmほど覆土します。本葉2〜3枚になった頃が定植の時期です。あるいは、用土を入れたプランターやコンテナ、庭に直まきします。直まきでも、よく発芽します。 ナスタチウムに多肥は絶対NG! 肥料をやりすぎると、葉っぱばかり繁って花が咲かなくなります。水やりも控えめにして、乾燥気味に育てましょう。春から夏にかけて次々に花を咲かせ、次第に大株になっていきます。7〜8月の猛暑の時期はちょっとお休み。涼しくなると再び花が咲き始めます。そして晩秋、霜が降りると一夜にしてしおれてしまいますが、それまで数カ月間、花と美しい葉を楽しむことができます。 パクチー、タイム、カモミールハーブの種まきにもぜひ挑戦してみよう! PPMeth/Shutterstock.com タイム、カモミール、セージなどのハーブ類も発芽率がよく、鉢やプランター、コンテナなどで栽培すれば、狭いベランダにもミニ・ハーブガーデンがつくれます。とくに、独特の香りで女性に人気のパクチー(コリアンダー)は、発芽率抜群! 種まき初心者におすすめのハーブです。
-
野菜

お手軽家庭菜園! 秋が植えどきのニンニクとラッキョウ
種球を購入して植えよう ラッキョウの種球。 ニンニクもラッキョウも、どちらも秋になると「種球(たねきゅう)」という球根がホームセンターなどに並ぶようになります。栽培する際は、この種球を植えて育てます。種球は一見すると、ニンニクそのもの、ラッキョウそのものの姿をしていますが、土に植えた際にウイルス病にならないよう薬品が施されているので、これを食べたりはしないようにしましょう。栽培過程でこの薬品はなくなり、収穫物は安心して食用できます。一方、スーパーで食用として販売されているニンニクは、このような薬品処理がされていないので、種球として植えてもウイルス病にかかってきちんと育たない可能性があります。また、食用のものは、芽や根が伸びてしまうと商品価値が下がるため、多くは「芽止め」や「根止め」という処理がされており、植えても生育しない可能性が高いです。家庭菜園で栽培する際には種球を植えましょう。ニンニクもラッキョウも、葉を伸ばして光合成し、葉で作られた栄養が種球に戻って分球し、増えていきます。 病害虫を寄せつけないための土づくり ニンニクもラッキョウも、植え付ける予定地を植え付けの1〜2週間くらい前に耕しておくことをおすすめします。雑草を抜いて牛フン堆肥、苦土石灰、有機化成肥料を施し、よく耕しておきます。それぞれの量は1㎡あたり、 <ラッキョウ> 牛フン堆肥 200g苦土石灰 80g有機化成肥料 80g <ニンニク> 牛フン堆肥 400g苦土石灰 100g有機化成肥料 100g が目安です。ニンニクは「肥料食い」といわれ、肥料をたっぷり施す必要があります。分量はきっちり計る必要はなく、だいたいで大丈夫。牛フン堆肥200gは手で2掴みくらい、軽く1掴みが他2つの80g相当です。 さて、これらを土に混ぜる理由は、土を柔らかくしてよく育つようにという意味ももちろんありますが、ウイルス病を防ぐ意味もあります。これはどんな野菜にもいえることですが、最初にしっかり土づくりをしておくと、病害虫に強く育ちます。病気は土中のカルシウム分が不足すると発生しやすくなりますが、牛フン堆肥や苦土石灰、有機化成肥料の中にはその要素が含まれているので、最初にこれらを混ぜて土づくりをしておく必要があるのです。プランター栽培の場合も、小粒の赤玉土にこれらを混ぜて、1〜2週間ほどおきます。1〜2週間というのは、それぞれの成分がよくなじむのに必要な期間です。しかし、あらかじめこれらの成分が混ざった野菜用培養土を使う場合は、すぐに植え付けしても問題ありません。 ラッキョウの植え付け方 幅約70cm、高さ約20cmの畝(うね)をつくり、そこに20cm間隔くらいで種球を植え付けていきます。深さは球根の頭頂部が少し土の上に見えるくらい。年内には発芽して細い緑色の葉を茂らせ、11月頃に紫色の可愛い花を咲かせますので、秋の花壇の彩りとして育ててもいいかもしれません。植え付け後は、基本的に水やりはせずに、土中の水分と自然の降雨のみでOK。地域によって、よほどカラカラに乾燥するようなら水やりをします。 春になって周りに雑草が生えるようなら抜く。 翌年の2月頃に1回、株元を軽く耕して追肥(有機化成肥料)を施す必要がありますが、それまでは何もやることがないので、この追肥作業を忘れてしまわないようにカレンダーやスマホのリマインドに入れておくとよいでしょう。収穫は翌年の6月頃。つまり、ラッキョウは収穫までに植え付けから約8カ月ほどを要します。じっくり気長に収穫を待ちましょう。春になって、ラッキョウのエリアに雑草が生えてきたら抜きましょう。雑草を生えっぱなしにしていると、そちらに土の栄養分がとられて球根が太らなくなってしまいます。 ラッキョウは1年採りと2年採りがある ラッキョウは9月頃に種球を植え付けて、翌年の6月頃に収穫できますが、もう1年寝かせる2年採りという方法もあります。待った分だけラッキョウは太って立派になりますが、1年目でも1個の種球が3〜4球に分球し、食するのに十分問題なく育ちます。ちなみに私はすでに今年、34個のラッキョウの種球を植え付けたので、100〜130球は収穫できるのではないかと楽しみにしています。 mimi-TOKYO/Shutterstock.com 栽培期間は長いのですが、他の野菜に比べたら本当に手間なしのお手軽野菜です。例えばナスは2週間に1回追肥をしたり、トマトは脇芽を摘んだりと、いろいろ面倒を見てやる必要がありますが、ラッキョウは植え付けたらあまりすることもなく、害虫もこないし、花が可愛いので気に入っています。以前、フレンチレストランでこのラッキョウの花を散らした一品が出てきて、とても素敵でした。 ラッキョウの美味しい食べ方 ラッキョウは収穫した後にも生育を続けるため、採ったらすぐに食べるか調理保存することをおすすめします。食べる前には薄皮をむく必要がありますが、これが、結構時間がかかる地道な作業なので、ゆっくり台所仕事ができる日を選んで収穫することをおすすめします。採れたてのラッキョウは甘くねっとりとしていて、その奥にわずかにピリッとした辛さがあり、そのまま味噌をつけてかじるのが一番美味しいと思っています。辛いといっても、保育園の孫娘もパリパリ食べていたくらいですから、爽やかな軽い刺激です。もちろん、収穫した全部は生で食べきれないので、私は塩漬けにします。この塩漬けは、私の飲み友達から教わったものです。以前私には、私よりずいぶん若い福岡出身の飲み友達がいて、彼女が「酒のあてに最高!」と、この塩漬けを教えてくれました。私の住む関東では甘酢漬けはよく売られていますが、九州では焼酎をつくった後の空いた大きなカメに、ラッキョウを塩で漬け込んでおくらしく、塩漬けがよく食べられているということでした。確かにラッキョウの塩漬けは、酒豪の彼女のおすすめ通り、酒のあてに最高です。 ラッキョウの塩漬けの作り方 Thu_Truong_VN/Shutterstock.com 8パーセントくらいの塩水を作って、その中にラッキョウを入れ、冷暗所で1カ月ほど漬けます。だんだん発酵してきてガスが発生するので、2〜3日に1回フタを開けてガス抜きをします。しないとフタが飛んで危険なので、忘れずに。食べる時は水にしばらくさらして塩抜きしてからいただきます。我が家では塩抜きしたものを甘酢漬けにしたり、味噌漬けにしたりしています。 ニンニクの種球は安くはないが実りは大きい! 9月になるとホーセンターや園芸店に、いろいろな種類のニンニクの種球が出回ります。私がいつも選ぶのは、青森県産の「ホワイト六片」という品種です。粒が非常に大きく立派で味もよいので気に入っていますが、種球は500gで約2,500円と、安価とはいえません。ですが、1個が5〜6個に分球するので、結局は安上がりになります。種球は調理に使うときと同様に、1片ずつバラバラにして皮をむいておきます。 ニンニクの植え付け方 geoBee/Shutterstock.com 幅約70cm、高さ約20cmの畝(うね)をつくり、そこに20cm間隔、5cmくらいの深さで種球を植え付けていきます。ニンニクの場合は地温が高いほうがよく育つので、マルチングをするのもおすすめです。マルチングというのは地面を覆うことで、稲わらなどを用いる方法もありますし、植え穴のあいた黒いビニールのマルチング材がホームセンターで販売されているので、それを使っても便利です。植え付け時も植え付け後も、水は基本的に土中の水分と自然の降雨で十分ですが、地域によって、よほどカラカラに乾燥するようなら土を水で湿らせてから植え付けます。植え付けから約1〜2週間で発芽します。その後、特にすることはなく、翌年の2月頃に株元を軽く耕して有機化成肥料を追肥します。もし脇芽が出てくるようであれば手で引っ張って抜き、茎は1本で育てます。 ニンニクの収穫と保存方法 ニンニクもラッキョウと同じで、収穫は翌年の6月頃です。できるまでじっくり待つ必要がありますが、栽培には手間がかかりません。収穫の前、4〜5月になると、株の中心部から硬い真っ直ぐな茎が伸びて花を咲かせようとします。それを「トウ立ち」といいます。この花茎を放っておくと、アリウム・ギガンチウムのような薄紫色のきれいな花が咲きます。しかし、花を咲かせるとそちらに栄養分が取られてしまって土中のニンニクが太らなくなるので、花茎が上がってきたら株元から切り取りましょう。緑色の葉っぱが黄色くなって枯れ始めた頃が収穫時です。ニンニクはカビが生えたり腐ったりしやすいので、晴天続きの日を狙って収穫しましょう。 gardenfairy/Shutterstock.com 収穫後は根を切り、5〜6株ずつ茎を束ねて日の当たらない風通しのよい日陰で、よく乾燥させましょう。 我が家のニンニクの美味しい食べ方 私の父は、冬になるとニンニクの味噌煮をよく作っていました。今、私も時々、それを作ります。父が亡くなって五十数年。レシピを教わったわけではないので、今やっているのは私なりの作り方ですが、味噌を酒と水で溶き、砂糖を加え、それに皮をむいたニンニクを投入し、弱火でゆっくりコトコトと煮詰めてゆきます。煮上がったニンニクは柔らかく、ホクホクとした食感。美味しいので、つい一度に2つも3つも食べてしまうけれど、生ニンニクと違って胃に負担がかかることもありません。 elena moiseeva/Shutterstock.com おろしニンニクを使った、韓国料理の定番ソース「ヤンニョムカンジャン」もよく作ります。これは、おろしニンニク、刻みネギ、すりごま、粉唐辛子、醤油、胡麻油を混ぜ合わせて、冷蔵庫で少し寝かせておくだけ。このソースで食べる焼き肉は絶品。そのほかにも、いろんなふうに使えて、とても重宝します。 ラッキョウもニンニクも植え付けから収穫までに時間はかかりますが、どちらも手間はほとんどかからず、じっくり待てば充実した実りが待っています。ぜひチャレンジしてみてください!
-
野菜

袋栽培でベランダ家庭菜園でもOK! 秋ジャガイモ
植え付けから2カ月で収穫! ベランダでもできる秋ジャガイモ ジャガイモは春に植えるのが一般的ですが、関東地方の南部やそれ以西の温暖地では夏の終わりから秋にかけて植え付け、11〜12月頃に収穫することができます。これを秋ジャガイモといいます。ジャガイモは植え付けから2カ月ほどで収穫ができるので、家庭菜園初心者の方にもおすすめです。また、畑などの広い栽培地がなくても袋をプランター代わりにしてもきちんと実ります。袋栽培する際は、しっかりしたビニール袋や麻袋などで30ℓくらい土が入る容量の丈夫な素材を選んでください。30ℓで種イモ2つ分くらいがちょうどいいです。袋の側面や底面には穴を開けておきましょう。この方法ならベランダなど場所が限られるところでもジャガイモ栽培が可能ですからぜひチャレンジしてみてください。 袋をプランター代わりにしたジャガイモ栽培。Angela Lock/Shutterstock.com ジャガイモにはさまざまな品種があり、私はこれまで‘キタアカリ’や‘男爵’、‘インカのめざめ’などを育ててきましたが、今回選んだのは‘アンデスレッド’という品種。本当はジャガイモの中で一番好きな‘キタアカリ’にしたかったのですが、‘キタアカリ’や‘メークイン’、‘男爵’などは、秋の栽培には向かないのです。というのは、ジャガイモには休眠期間というものがあり、これらの品種は、秋は休眠から目覚めておらず、土に植えても発芽しないからです。 Cora Mueller/Shutterstock.com ジャガイモは品種によってかなり食感が異なり、‘キタアカリ’はしっとり、ねっとりといった感じで、肉じゃが、カレー、ポテトサラダなど、何に使っても濃厚なジャガイモの旨味が感じられるのです。我が家では「ヤンソン」という料理にすることが多いのですが、これも絶品。後ほどレシピをご紹介しますね。‘男爵’はより粉っぽく、‘メークイン’は煮崩れしないので料理によって重宝しますが、煮崩れてもやはり私は‘キタアカリ’の味が大好き。しかし、これは春の栽培向きです。 長年育てているお気に入りの‘キタアカリ’。 さて、今回栽培する‘アンデスレッド’は果皮が赤く、中は鮮やかな黄色をしています。この品種は初めて栽培します。レシピサイトでも‘アンデスレッド’という品種名でたくさんのレシピが掲載されており、ひと通り眺めてみると、ポテトサラダやソテーなどシンプルな調理で食べられていることがほとんど。おそらくイモの味そのものが美味しいジャガイモだと思われます。うーん、楽しみ! 栽培には「種イモ」を使おう! ジャガイモの植え付けには、ホームセンターなどで販売されている「種イモ」というものを使います。「種イモ」は一見、スーパーで売っているジャガイモと何ら変わりありません。だったら、スーパーで売っているジャガイモを土に植えればいいんじゃない? と思われるかもしれませんが、それはおすすめしません。土の中にはイモが育つためのたくさんの微生物が棲み、栄養分も含んでいますが、同時に病気にさせるウイルスも棲んでいます。種イモにはウイルスにかからないようにあらかじめ薬品処理されているものが多いので、そうした種イモを使ったほうが健全に育てることができます。この薬品は栽培過程でだんだんなくなっていくようにできているので、収穫したジャガイモは安心して食用にできます。しかし、薬品処理された種イモ自体は食用ではないので、これを料理して食べるのもおすすめしません。 秋植えの種イモは切らずにそのまま植える 秋植えの種イモは切らずに植える。Sezamnet/Shutterstock.com しばしば、種イモを植え付ける際には、半分に切って、切り口に腐敗防止のために消石灰や草木灰を塗りつけて植えます。半分に切るのは、春植えに向く品種の種イモのサイズが割と大きく、1個の中にたくさん芽があるので、切って植えればそれだけたくさん芽ができ、収穫量もあがるからで、別に切って植えなくても育ちます。ですから、春植えの場合は切っても切らなくてもいいのですが、しかし秋植えに限っては、切って植えてはいけません。これは種イモの腐敗を防ぐためです。秋といっても残暑が続き、土の中で温度が上がると、切り口から腐敗しやすいので、秋は切らずに植えます。それに、今回私が選んだ‘アンデスレッド’は種イモが比較的小さめの品種なので、春植えするにしてもそのまま植えたほうがよさそうです。 最初の土づくりが病害虫に強くするカギ プランターで栽培する際も、土と肥料分を混ぜて1〜2週間寝かせておくとよい。 まず、植え付ける予定地を、植え付けの1〜2週間くらい前に耕しておくことをおすすめします。雑草を抜いて牛フン堆肥、苦土石灰、有機化成肥料を施し、よく耕しておきます。それぞれの量は1㎡あたり、 牛フン堆肥 200g苦土石灰 80g有機化成肥料 80g が目安です。といっても、料理のようにきっちり計る必要はなく、だいたいで大丈夫。牛フン堆肥200gは手で2掴みくらい、軽く1掴みが他2つの80g相当です。さて、これらを土に混ぜる理由は、土を柔らかくしてジャガイモがよく育つようにという意味ももちろんありますが、ウイルス病を防ぐ意味もあります。これはジャガイモに限らず、どんな野菜もそうなのですが、最初にしっかり土づくりをしておくと、病害虫に強くしっかり育ちます。病気は土中のカルシウム分が不足すると発生しやすくなりますが、牛フン堆肥や苦土石灰、有機化成肥料の中にはその要素が含まれているので、最初にしっかり土作りをしておく必要があるのです。プランターや袋栽培の場合も、小粒の赤玉土にこれらを混ぜて、1〜2週間ほどおきます。1〜2週間ほどおくのは、それぞれの成分がよくなじむのに必要な期間です。しかし、あらかじめこれらの成分が混ざった野菜用培養土を使う場合は、すぐに植え付けしても問題ありません。 ジャガイモの植え付け方法 Kletr/Shutterstock.com 幅約70cm、高さ約20cmの畝(うね)をつくります。そこに20cm間隔くらいで、5〜8cmの深さで種イモを芽が上になるように並べて土をかぶせます。種イモは腐りやすいので、植え付け後に水やりはしません。この後の栽培でも地植えの場合は土中の水分と降雨のみで十分です。発芽したら追肥(有機化成肥料)を株元に施します。袋栽培の場合は、豪雨などによって袋の中に水が溜まってしまうのが心配なので、雨の当たらない場所に置いて、葉っぱが下がって元気がなくなってきたのを目安に水をあげる程度で大丈夫です。土の表面だけでなく、土の中までしっかり乾いた状態になってから水やりをすることが大切。常に湿った状態にしておくと、イモが腐るので乾かし気味で管理しましょう。 Kalinin Ilya/Shutterstock.com 1個の種イモから大体3〜4本の芽が出るので、しばらく様子を見て元気のいい1本だけを残して他の芽は取ります。これを「芽かき」といいます。 ジャガイモ栽培で大事な「土寄せ」 Kalinin Ilya/Shutterstock.com 芽かきとともに、株元に土を寄せておきましょう。これを「土寄せ」といいます。土寄せは1回だけでなく、こまめに畑を見回ってイモが表面に出そうになっていたら行います。ジャガイモは1個の種イモが茎を伸ばし、葉を繁らせて光合成し、その栄養分を根のほうに戻すことで子イモが生まれ、それが太っていくという成長過程をたどります。その成長過程で子イモは割と土の表面のほうにでき、土から顔を出してしまうことがあります。イモは成長過程で日光に当たると、そこが光合成で緑色に変色し、毒を持ってしまいます。ジャガイモを料理するとき、芽を取りますよね。あれは芽の部分に毒があるので、それを取り除いて料理をするのですが、それと同じ毒が日光に当たった部分にも生まれてしまうのです。 これは天然の有毒成分で、グリコアルカロイド(主にα-ソラニンとα-チャコニン)が含まれています。 緑色に変色した部分は毒があるので、皮を厚く剥いて利用する。FotoHelin/Shutterstock.com じつは小学校などの学校栽培で、この「土寄せ」が不十分だったためにイモが土の上に出てしまい、それを知らずに収穫して調理実習に使い、集団食中毒が発生する事態が意外と少なくありません。小さく未成熟なジャガイモも、グリコアルカロイド含有量が多いといわれているので注意が必要。ジャガイモはきちんと土寄せしながら栽培し、十分に育ってから収穫することが大事です。株間の間隔の目安なども、ジャガイモが十分に育つためのスペース確保のために考えられているのです。 ジャガイモの害虫「ニジュウヤホシテントウ」 CreelShutterStock/Shutterstock.com ジャガイモにはまれに、「ニジュウヤホシテントウ」、通称「テントウムシダマシ」という、テントウムシによく似た害虫が発生します。葉っぱの裏側について葉をかじり、ボロボロにしてしまうのです。そうすると、葉っぱが光合成できずに、栄養が送られなくなり、土中の芋が育たなくなってしまいます。この虫はナス科の植物を食草としており、ジャガイモの他に、同じナス科のトマトやナス、トウガラシ、花ではニコチアナにもつきます。トウガラシの葉は、とても辛いのですが、以前我が家の畑のトウガラシの葉を食べまくっていたのをみると、テントウムシダマシには辛いという味覚がどうやらないようです。さて、これがついたらどうするかというと、消毒という選択肢もありますが、家庭菜園程度の規模なら手でとれば十分対策できます。 ジャガイモに禁物な「連作」 ナスを植えた後に続けてジャガイモは植えられない。PHILIPPE MONTIGNY/Shutterstock.com 前述したような、同じナス科の野菜を作った後にジャガイモを栽培すると、著しく収穫量が激減したり、病気で育たないことがあります。これは連作障害というもので、同じ科の野菜を続けて同じ場所で栽培すると発生します。ですから、夏にトマトやナスを栽培した跡地でジャガイモを栽培してはいけません。再びナス科の野菜を植えるには3年空ける必要があります。ですから、畑のローテーションを考えておかなくてはなりません。ローテーションできるほど広さがない! という方には、連作障害を防ぐ資材もあります。 ジャガイモの収穫にはコツあり! Kalinin Ilya/Shutterstock.com ジャガイモは白や紫色の可愛い花を咲かせます。人によってはジャガイモを太らせる目的で摘むこともあるようですが、さほど花に栄養を取られるわけでもないので、我が家ではそのまま咲かせていますが、なんの問題もなくたくさんのジャガイモが収穫できています。収穫は葉が黄色くなって、枯れ始めた頃が目安です。晴天が2日以上続いた日をねらって行います。前の日が雨でびちゃびちゃ湿っていると、当日が晴れでもイモが湿っていて、収穫後に病気になることがあります。1個病気になると次々ダメになるので、注意が必要です。収穫したら新聞紙などを敷いて、風通しのよい場所で1日乾燥させます。途中、イモを裏返して、全体を万遍なく乾燥させましょう。 おすすめジャガイモ料理 ある時、北海道の人たちが茹でたジャガイモにイカの塩辛を乗せて食べているのをテレビで見て、「美味しそうだな〜」と思ったことがありました。でも、生憎、我が家の近くのスーパーでは、あまり美味しい塩辛を売っていません。そこで、ふと思いつき、アンチョビをのせて食べてみたところ、これは抜群に美味しかった! アンデスレッドが実ったら、茹でジャガにアンチョビのちょい乗せを、ぜひまたやってみたいと思います。 そして、我が家で最も食べられるジャガイモ料理が「ヤンソン」。正式には「ヤンソンの誘惑」という料理名です。これは作家で料理研究家の丸元淑生さんの本に掲載されていた料理で、スウェーデン発祥だそうですが、もう20年以上前から作っている定番料理です。失敗しないようアレンジした我が家風レシピをご紹介します。アンチョビの塩気がアクセントになります。シンプルですが「ヤンソン牧師」がつい誘惑に駆られて食べてしまったというエピソードから名前がついたほど、美味しいです。 スウェーデンのジャガイモ料理「ヤンソンの誘惑」 maroke/Shutterstock.com <材料> ジャガイモ、玉ねぎ、アンチョビ、生クリーム、塩、コショウ、バター(or サラダオイル) <作り方> 玉ねぎを薄くスライスし、バターかオイルで炒めます。ジャガイモは細切りにして耐熱皿に入れてラップをし、電子レンジで熱を通しておきます。1に2を入れ、塩・コショウ少々をふり、焦げ付かないよう中弱火で炒めます。この段階で、ほとんどジャガイモに火を通しておくと失敗がありません。耐熱皿に3の半分を入れて、アンチョビをちぎって散らします。残りの半分をかぶせ、材料の8分目あたりまで生クリームを注ぎます。200〜220℃に予熱したオーブンで、表面がキツネ色になるまで焼けば完成。 *元々のレシピでは、生のジャガイモを使い、オーブンで焼くとありましたが、ジャガイモの種類によってかオーブンの性能の違いかで、ジャガイモに硬さが残ることがあったので、最初にジャガイモにレンジで熱を入れ、さらにフライパンでほとんど火を通してしまうことで、失敗しなくなりました。 ジャガイモの保存方法 収穫したジャガイモはよく乾かした後、涼しくて風通しがよく、直射日光の当たらない場所で保存します。しかし、今回選んだ‘アンデスレッド’は生命力が非常に強く、割と短期間で発芽してしまうので、長期保存には向かない品種です。ですから、食べ切れる分だけを栽培することにしました。収穫が楽しみです!
-
ガーデニング

酷暑・猛暑を有効利用しよう! 暑い夏だからこそできる庭仕事
猛暑を有効活用した古土の再生 Mountain Cubs/Shutterstock.com プランターやコンテナの中で、古い土がそのままになっていませんか? プランターで一度植物を育てた土は、そのままでは使えません。目には見えませんが、一度使った土の中には害虫の幼虫や卵、病原菌が潜んでいたり、土の団粒構造が崩れて微塵(みじん)になっていたりするため、そのまま使うと次の植物が健全に生育しないからです。しかし、土は再生することができます。その再生の方法をご紹介しましょう。 [日光消毒] 晴天の日を選んで作業します。ビニールシートの上に土を広げ、目立った枯れ葉や前の植物の根、肥料のカスを取り除きます。鉢底石も分別しておきましょう。土はふるいにかけますが、ふるいの目には荒目、中目、細目があります。最初に荒目でふるい、細かい根やゴミを取り除きます。次に中目と細目を重ねてふるうと「微塵(みじん)」という砂のように細かい土が落ちます。これは根詰まりなどの原因となるので処分し、ふるいに残った粒状の土だけを再利用します。 土にジョウロで水をかけて全体を湿らせ、黒いビニール袋に入れて口をしばります。1日おきくらいに袋の上下をひっくり返して太陽が全体に当たるようにします。この方法で、真夏なら1週間ほどで土の日光消毒ができます。 [再生剤・腐葉土・完熟堆肥を混ぜる] 消毒した土に、市販の古土再生剤を1〜2割ほど混入し、さらに腐葉土、完熟堆肥、苦土石灰を加え、よく混ぜます。このとき、モミガラ燻炭を混ぜるのも効果的。通気性がよく、水はけのよい土になります。 [液肥] 上記の要領でブレンドした土に、ごく薄い液肥を回しかけ、よくかき混ぜます。そして、そのまま3週間〜1カ月ぐらい寝かせておきます。 [再生完了] 3週間〜1カ月経ったら、再生完了。自家製培養土の出来上がりです。草花も野菜類も、こうして再生させた土で、とてもよく育ちます。 Pong Wira/Shutterstock.com 古くなった土を捨ててしまうなんて、もったいない。そして、都会では土を捨てるのにも一苦労するので、この暑さを利用して夏の間に土の再生をしましょう。秋からは球根や宿根草、冬野菜の栽培がスタートします。それまでにぜひ、土の準備を済ませておきましょう。 猛暑を有効活用した干し野菜作り Rimma Bondarenko/Shutterstock.com 晴天と気温の高い日が続く夏は、干し野菜を作るのに適した季節。家庭菜園で採れすぎた野菜やまとめ買いした野菜は、太陽と風の力を借りて干し野菜にしましょう。干すことで野菜の旨味が凝縮し、生とは食感も変わるので、いろいろな料理に使えるようになります。 作り方は? [大根] kariphoto/Shutterstock.com 長さ5mmほどの千切りにし、ザルや網に乗せて天日で乾燥させます。真夏の晴天なら、3〜4日で自家製切り干し大根の完成! 市販の切り干し大根よりずっと風味豊かです。 [切り干し大根レシピ(4人分)] 材料/豚コマ200〜300g(一口大)、切り干し大根2つかみ(水で戻す)、A(水200cc、酒大さじ1、砂糖大さじ1、しょう油大さじ1/2) つくり方/材料をすべて鍋に入れ、中弱火で汁気がほとんどなくなるまで煮て完成。豚コマを油揚げ(短冊切り)に代えてもよい。 *ご飯の惣菜によし、お酒のおつまみによしの、お箸がとまらない美味しさです。 [ゴーヤ] Trum Ronnarong/Shutterstock.com ゴーヤは1株育てるとやたらとできて、食べるのが追いつかないくらい。ドライにすれば保存がきき、苦味が減るのも魅力です。厚さ1cmほどの輪切りにして、ザルや網に乗せて天日で乾燥させます。真夏の晴天なら1〜2日でゴーヤチップのでき上がり! ジッパー付きの保存袋に入れて冷蔵庫へ。 K321/Shutterstock.com 使うときは水で戻し、炒め物などにすると、生のときとは違う食感とゴーヤ独特の苦みが楽しめます。定番のゴーヤチャンプルや味噌汁など、何にでも使えます。 [ナス] schankz/Shutterstock.com 縦に厚さ7〜8mmほどの薄切りにし、酢水に20分つけてアクを抜きます。こうすることで、干したナスが黒っぽく変色するのを防ぐこともできます。 アク抜きしたナスをザルや網に乗せて天日で乾燥させます。真夏の晴天なら2日ほどで水分がほとんどなくなります。ジッパー付きの保存袋に入れて冷蔵庫へ。 [切り干しナスレシピ] 使うときは、水から茹でて、沸騰したら火を止め、そのまま一晩おきます。 干しナスの料理は山形の郷土料理の一つで、他の野菜やちくわと炊き合わせたり、油炒めや白和え、枝豆をすりつぶして砂糖と塩などで味をつけた「ずんだ」和えなどにして食べます。 [トマト] Giuseppe Piazzese/Shutterstock.com 夏の完熟トマトは美味しいものですが、そんなトマトで作ったドライトマトの美味しさも格別。ミニトマトなら半分にカットして、切り口の水気を一度キッチンペーパーに吸わせます。切り口を上にして軽く塩を振り、晴天で4日以上乾かします。 KristinaSh/Shutterstock.com [ドライトマトレシピ] 自家製ドライトマトはセミドライの状態のことが多いので、そのまま保存するよりオリーブオイルに漬けておくと長もちします。 殺菌した瓶にドライトマト(50gくらい)とニンニク(2かけ)、粒黒胡椒(10粒くらい)、ローリエ(2枚)ドライオレガノかタイム(少々)を入れ、オリーブオイルを注ぎます。そのままおつまみとしても、またパスタの具材に合わせても、旨味が凝縮した美味しいソースになります。 *完全にドライになっている場合は、いったんドライトマトをお湯(酢を大さじ1ほど入れる)で3〜4分煮戻してからオリーブオイルに漬けます。 [干し野菜作りのポイント] どの野菜も、干している途中で雨にあたると、カビが発生します。雨にあてないように注意しましょう。もしも途中で天候が崩れてしまったら、低温のオーブンで水分を飛ばし、カビの発生を防ぎましょう。干し野菜や自家製の干物などを作るときに便利な干しカゴが市販されています。3段重ねや5段重ねなので、大量に干すことができ、しかも上からも下からも風があたるので、早く乾燥させることができます。ぜひ干しカゴを利用しましょう。
-
家庭菜園

種から育てよう! 夏の料理にヘビロテ必至のハーブ3種【動画解説付き】
世界に多くの品種があるバジル バジルは、世界に60以上の品種があります。ヨーロッパで主に料理に使われるのは、スイートバジルと呼ばれる品種。風味が豊かでピリッとした辛味と甘味が同居しています。一方、アジアでもバジルは料理に欠かせないハーブの一つで、こちらでは主にホーリーバジルを使います。スイートバジルよりも香りが強いのが特徴で、ガパオライスなどの代表メニューがあります。また、タイではタイバジルをアイスクリームやチョコレート菓子に添えることもあり、種子を水に浸してゼリー状にしたバジルシードは、ドリンクやシャーベットなどでも活躍します。 Jirik V/Shutterstock.com 誰でも料理上手にしてくれる魔法のハーブ「バジル」 j.chizhe/Shutterstock.com バジルは、フランスのシェフたちに「エルブ・ロワイヤル(ハーブの王様)」と称賛されるキッチンハーブの代表。料理に入れれば、たちまち味をグレードアップさせてくれる魔法のハーブなのです。ペストソースと呼ばれるバジルを使った緑色のソースは、イタリアでもフランスでも、よく作られます。昔ながらの方法は、ニンニクとパルメザンチーズ、松の実、オリーブオイルとバジルをミキサーで混ぜて作りますが、このペストソースを作っておけば、パスタはもちろん肉や魚の料理、サンドイッチなどが「混ぜるだけ」、「かけるだけ」で美味しさが格段にアップします。 ●バジルを使った世界の料理レシピ【キッチンガーデンレシピ】 バジルの種まき方法 バジルは地温が十分高くなってから種まきをすると、発芽率が高くなります。種子袋の裏などにしばしば発芽適温は20〜25℃、適期は4〜6月と記載されていますが、私の経験上、6月になってからのほうが格段に発芽率は上がります。 1.土づくりをしておく 畑に直播きする場合は、2〜3週間前に土づくりをしておきましょう。バジルは酸性土を嫌いますが、日本の土は放っておくと酸性に偏りがちなので、苦土石灰をまいて中和します。また、堆肥も混ぜておきます。堆肥は土中の微生物を増やしてその活動を活発化させるので、土がフカフカに柔らかくなり、植物の根に新鮮な空気や水を送りやすくなります。さらに、化成肥料も混ぜておきます。化成肥料は植物の初期生育に必要な栄養素を与える役割です。プランターで栽培する場合は、これらの成分があらかじめ配合されている専用の培養土を使うと便利です。 2.播き溝をつける 畑にタネを播くための播き溝をつけます。シャベルで土の表面をなぞって溝をつけますが、あまり深くなりすぎないように注意。約1cmの深さくらいにしたら、播き溝に沿ってたっぷり水をかけ、土に十分水分を吸収させておきます。 3.タネをすじまきにする バジルのタネは非常に細かいので、1粒ずつ播くのは効率的ではありません。片方の手のひらにバジルのタネをまとめてとり、もう片方の指で適当な量をつまんでパラパラ播いていきます。この時、なるべく重ならないようにずらしながら播きます。でもあまり神経質にならなくても、発芽後に2〜3回間引きをして、重なった分は抜きながら育てていくので大丈夫です。 4.タネを土と圧着させる バジルのタネの上から拳(こぶし)を押し付け、タネと土をよく圧着させます。ささいな作業ですが、タネが流されたりしないようにする大事なポイントです。 5.土をかける 上からごく薄く土をかけます。シャベルなどを使って埋めるというより、手で土をつまんでパラパラとまく程度です。あまり厚く土をかけすぎると発芽しないので、ごく薄くかけるようにします。種子の中には「好光性」と「嫌光性」という2種類のタイプがあり、「好光性」は発芽に光を必要とするため土をかけません。バジルは「嫌光性」で発芽に闇を必要とするので、上からごく薄く土をかけます。 6.もみ殻をまく もみ殻をまくと水の蒸散が抑えられるので、まいておくと安心ですが、なくてもOK。もみ殻は、ホームセンターやガーデンセンターなどで入手できます。 7.水をまいて完了 水をやって完了です。水はタネが流されないように、はす口のついたジョウロかホースのシャワーでごくやさしくふんわりとやるようにします。天気のよい日が続く時は、タネが乾かないよう毎日水やりします。発芽までは乾かさないことがポイントです。 パクチーの種まき Dream79/Shutterstock.com パクチーはコリアンダーやシャンツァイとも呼ばれ、アジアンテイストの料理には欠かせないセリ科のハーブ。独特の味と香りがあり、麺料理や海鮮・肉料理などで活躍します。 パクチーの種まきも、おおむねバジルと同様ですが、パクチーの種子は少し大きいので、すじまきではなく、点まきにします。点まきとは1カ所に3〜4粒種子を播くやり方です。10cm程度離して点まきにしていきます。そして、パクチーの場合は発芽して混み合っていても、間引きません。しばらくの間はそのまま混み合った状態で育てます。セリ科の植物は倒れやすく、何本かが一緒に育つことで互いを支え合うからです。一株ひと株が大きくなって、いよいよ窮屈だなと思う段階で間引けばOKです。 大葉の種まき optimarc/Shutterstock.com 大葉は日本でも古くから利用されてきた和ハーブです。冷奴やそうめんなど、夏の食卓で薬味として活躍してくれますね。大葉も順調に育てば大株になり、薬味として2〜3枚使う程度では消費しきれなくなってくるので、ジュースにするのがおすすめです。ジュースの作り方は、大株になる頃に改めてご紹介しようと思います。大葉の種子は外皮が固いので、播く前の晩から水に浸けておきます。こうすることで発芽しやすくなります。その後の作業はバジルとほぼ同じですが、タネの上から土をかけないのが大きな違いです。大葉のタネは好光性で発芽に光を必要とするので、土ももみ殼もかけず、土の上に播いたタネを拳で押し付けたら作業完了です。大葉も、生育過程で2〜3回間引きながら大きくしていきます。 自分で種子から植物を育てるのはとても面白い作業です。種まきの成功の最大のポイントは、適期に播くということ。今なら地温が十分に上がって、とても発芽率がよいはずなので、ぜひチャレンジしてみてください。
-
植物の効能

ガーデニングのトラブル時に 薬として愛用されてきたラベンダーオイル
薬として愛用されてきたラベンダーオイル 野生のラベンダーが豊富に自生していた南仏プロヴァンス地方では、古くから農家の人たちが家庭用の小型の蒸留器でラベンダーのエッセンシャルオイルを抽出し、傷薬や虫刺されの時の薬として使っていました。また、お酢とオイルをブレンドしてラベンダービネガーをつくり、捻挫や打ち身への湿布薬としても利用されてきた歴史があります。 今日では、ラベンダーオイルには強い抗菌力と抗ウイルス性、鎮痛の効力があることが科学的に確かめられています。こうしたエッセンシャルオイルの効能はヨーロッパでは代替・補完医療として医療の現場で活用され、「メディカルアロマセラピー」は一般の人々の間でも常識となっています。近年は日本でも専門知識を学んだ看護師やアロマセラピストによる施術を取り入れている病院もあります。 岡崎さんのガーデン救急箱。左のボトルは北海道富良野産の100%天然の「ラベンダーオイル」(50ml・5,652円 /ファーム富田)、右の小さなボトルはフランス産のオイルでアロマ環境協会認定精油「GAIA オーガニック エッセンシャルオイル ラベンダー・トゥルー」(5ml・1,620円/GAIA NP) ガーデニングのトラブルにラベンダーオイル 私はガーデニング中のトラブルでラベンダーオイルを使うことが度々あります。庭仕事をしていると、トゲが刺さったり、ちょっとした切り傷ができたりすることがあります。最近も、こんな出来事がありました。 庭に出て、剪定バサミであちこちチョキチョキやっていた時のこと。ハサミを持つ手に力が入り過ぎたのか、いつのまにか小指の爪が裂けて出血。市販の消毒薬で一応の処置はしたものの、嫌な感じの痛みがずっと続くようになってしまいました。 この時私が一番恐れたのは、傷口が化膿してしまうのではないかということでした。庭仕事でしょっちゅう土に触れている私の爪先には、ブラシで洗い落とせない泥が入っていて、その爪先に傷ができてしまったからです。 ラベンダーオイルの抗菌・鎮痛作用 そこで、以前からよく使っている北海道富良野産のラベンダーオイルを傷口に1〜2滴。それで痛みはほぼおさまったのですが、翌朝もまだほんの少し嫌な感じが残っていたので、ラベンダーオイルを傷口にさらに1〜2滴。すると痛みはその日のうちに消え、4〜5日経つと、裂けていた爪が自然に癒着し、化膿することもなくキッチンで水仕事ができるようになりました。 また、ある日妻がレッドカラントを収穫していた時、腕をアシナガバチに刺されてしまいました。私は小さい頃から何度も色々な種類のハチに刺されているのでよく知っているのですが、ハチに刺されると直後から強烈な痛みと腫れが出て、その後しつこくかゆみが続くのです。そこで、刺された箇所をよく洗った後、ラベンダーオイルを塗布したところ、「あ、痛みがスッと引いてく」と妻。その後、1〜2時間ほど保冷剤で冷やしておいたところ、腫れもかゆみも残ることなく翌日には完治してしまいました。 必ず天然100%のラベンダーオイルを というわけで、私の庭の救急箱にはラベンダーオイルが常備されています。ただし、オイルは必ず天然100%のラベンダーオイルでなければなりません。ブレンドオイルや合成香料でつくられたものには、本来の効用がないので切り傷に使うのはNGです。 ちなみに、芳香浴に使えるのも天然のオイルだけで、合成香料製のオイルは肌トラブルを引き起こすこともあるので使ってはいけません。 Credit 文・岡崎英生/ラベンダー栽培史研究家。 ラベンダーの原産地の一つ、フランス・プロヴァンス地方や北海道富良野地方を訪れ、ラベンダーの栽培史を研究。日本のラベンダー栽培の第一人者、富田忠雄氏に取材した『富良野ラベンダー物語』(遊人工房刊)や訳書『ラベンダーとラバンジン』(クリスティアヌ・ムニエ著、フレググランスジャーナル社)など、ラベンダーに関する著書を執筆。自らも長野の庭でラベンダーを栽培し、暮らしの中で活用している。
-
野菜

秋の家庭菜園・葉酸たっぷりのビーツを育てよう!【コスパ最高のタネから栽培】
葉酸たっぷりの野菜ビーツ 鮮やかなルビーレッドの野菜、ビーツ。赤いカブのような形をしていますが、カブはアブラナ科なのに対し、ビーツはホウレンソウと同じアカザ科の野菜です。ビタミンやミネラル、葉酸が豊富で、スーパーフードとしても注目されています。日本ではあまりなじみのない野菜かもしれませんが、ロシアの家庭料理「ボルシチ」はご存じの方も多いのではないでしょうか。ボルシチはビーツを使った赤いスープで、トロトロに煮込んだ牛すね肉とビーツの素朴な甘みがなんとも身体にやさしく、ホッとする味なのです。我が家では近年、作るようになった料理ですが、簡単で失敗することがなく、とても美味しく、栄養もたっぷりなので、早くも定番料理になっています。きっかけを作ったのはうちの奥さんで、フィギュアスケートの大ファンである彼女がロシア大会へ出かけて行って、現地で食べて感激したことからです。とにかくこの料理にはビーツが欠かせない…そこでビーツを探し回ったのですが、日本のスーパーの店頭にはほとんど並んでおらず、ネットで取り寄せようとしたところ、生のビーツは2~3個で「800円+送料1,700円」。うわぁ、高い! と驚いてタネを探したところ、タネは280粒も入って200円前後で販売されていました。これは育てるしかないということで、ビーツが家庭菜園の仲間入りをしたわけです。ちなみに缶詰の水煮もありますが、栽培したものと比べると、私はやはり生ビーツを使った味のほうが好きです。 発芽率がよく初心者でも育てやすい野菜 栽培してみたところ、ビーツは発芽率がとてもよく、非常に丈夫で簡単に育つので、初心者にもおすすめの野菜です。栽培適期は春と秋の2回で、秋は10月いっぱいくらいまで種まきができます(関東地方以西の暖地)。タネはとてもたくさん入っているので、播く時期を少しずつずらして育てると、長い期間、少しずつ収穫ができます。いっぺんにたくさん播くと、いっぺんにたくさん採れてしまって、家庭で消費するのには大変苦労することになります。ビーツはある程度は保存ができますが、ジャガイモやタマネギのような保存性はないので、1回の収穫で7~8個採れるくらいに調整して種まきをするといいでしょう。あ、タネはおそらく余るでしょうけれど、有効期限の1年を過ぎると極端に発芽率が落ちてしまうので、余った分はあきらめて改めて買い直しましょう。 さて、タネの播き方を説明する前に、畑の準備について少しお話ししておきます。 とにもかくにも土の準備が上手に育てるコツ まず、植え付ける予定地を、植え付けの2週間くらい前に耕しておくことをおすすめします。雑草を抜いて、牛フン堆肥、苦土石灰、有機化成肥料を施し、よく耕しておきます。それぞれの量は1㎡あたり、 牛フン堆肥 200g 苦土石灰 80g 有機化成肥料 80g が目安です。といっても、料理のようにきっちり計る必要はなく、だいたいで大丈夫。牛フン堆肥200gは手で2掴みくらい、他2つは軽く1掴み(80g相当)です。さて、これらを土に混ぜる理由は、土を柔らかくしてビーツがよく育つようにという意味ももちろんありますが、ウイルス病を防ぐ意味もあります。これは、どんな野菜もそうなのですが、最初にしっかり土づくりをしておくと、病害虫に強く育ちます。病気は土中のカルシウム分が不足すると発生しやすくなりますが、牛フン堆肥や苦土石灰、有機化成肥料の中にはその要素が含まれているので、最初にしっかり混ぜておく必要があるのです。プランター栽培の場合も、小粒の赤玉土にこれらを混ぜて、2週間ほどおきます。2週間ほどおくのは、それぞれの成分がよくなじむのに必要な期間です。しかし、あらかじめこれらの成分が混ざった野菜用培養土を使う場合は、すぐに植え付けしても問題ありません。 ちなみに、ジャガイモをベランダなど限られたスペースで栽培する際、麻袋などを利用した袋栽培がありますが、ビーツもこの栽培方法が可能です。 種まきの方法 タネは播く前に一晩水につけておきます。 幅30cm、高さ20cmくらいの畝をつくり、中央にタネのまき溝をつくります。溝はシャベルの先端で深さ1cm程度くらいの線を引くようにしてつくります。そこにジョウロにハス口をつけて水をたっぷりやります。 なるべく間隔があくように、すじまきにします。点まきにする場合もありますが、すじまきのほうが簡単です。 ●すじまきなど、種まきの方法についてはこちらの記事を参照。 『正しいタネのまき方とは? すじまき・点まきなど野菜に合った種まきを!』 軽く土をかけ、手で上から押さえて、よくタネを土に圧着させます。このとき、あれば、籾殻をかぶせてから水をまくと、籾殻に保水性があるため乾燥を防ぐことができます。発芽までは乾燥しないように、水やりを欠かさないようにします。種まきから発芽まで1週間ほどです。発芽後は、よほど乾燥が続くようなことがない限りは、水やりはしません。 発芽した苗が3cmくらい伸びたら、混み合っているところを間引きします。これが1回目の間引き作業です。なるべく生育のよさそうなものを残します。 本葉が3~4枚になったら、2回目の間引き作業を行い、最終的に株間が10cmくらいになるようにします。このとき、追肥として有機化成肥料をやります。 直径8cmくらいになったら収穫どきです。上から見ると、首が少し見えているので、だいたいの大きさを判断できます。種まきから収穫までは40~50日ほどです。晴天が続いているときに収穫するとよいでしょう。 ビーツのおいしい食べ方 ビーツはサラダなど生でもおいしくいただけますし、アルミホイルに包んでオーブンで30~40分焼くベイクドビーツもホクホク甘い味がやみつきになります。ビーツの代表的料理「ボルシチ」はロシアの家庭料理ですが、これもとても簡単に美味しく作れます。牛すね肉を柔らかくするのに、圧力鍋を使うと短時間でできますよ。 <ボルシチの材料(4人分)> ニンジン 1本 タマネギ 1/2個 牛すね肉(一口大) 300g ビーツ 1個 トマト缶 1/2個 コンソメ 2個 ベイリーフ 1枚 サワークリーム 大さじ4 <作り方> ニンジン、タマネギを適当な大きさに切り、牛すね肉とともに適度に焼き色がつくまで炒めます。 牛すね肉を圧力鍋に入れ、トマト缶、ベイリーフ、かぶるくらいの水を加えて15~20分ほど加圧します。 ニンジン、タマネギ、ビーツ、コンソメを入れて、さらに3分ほど加圧します。 火を止め、圧力が抜けたら皿に盛り付け、サワークリームを大さじ1のせたら完成。 Credit 文・写真(表記外)/岡崎英生(文筆家・園芸家) 早稲田大学文学部フランス文学科卒業。編集者から漫画の原作者、文筆家へ。1996年より長野県松本市内四賀地区にあるクラインガルテン(滞在型市民農園)に通い、この地域に古くから伝わる有機栽培法を学びながら畑づくりを楽しむ。ラベンダーにも造詣が深く、著書に『芳香の大地 ラベンダーと北海道』(ラベンダークラブ刊)、訳書に『ラベンダーとラバンジン』(クリスティアーヌ・ムニエ著、フレグランスジャーナル社刊)など。
-
育て方

【春の種まき】コスパ良好で丈夫に育つ種まきガーデニング!失敗しないコツとは?
タネは発芽するようにできている! 花や野菜をタネから育てるなんて難しそう……。あなたは、そう思っていませんか? でも、タネを播いて発芽させるのは、じつは意外に簡単。というのも、花や野菜のタネには素晴らしい力が秘められているからです。タネの中には生物が成長していくもととなる「胚(はい)」と、成長の養分となる「胚乳(はいにゅう)」があり、水をやったり光に当たったりすることで休眠から目覚め、発芽し生育するシステムを持っているのです。 そして、種まきから数日後、可愛い緑色の芽が出ているのを発見したときの感動といったら! 一度でもその感動を味わえば、種まき大好きになること間違いナシ! さあ、この春はぜひ、花や野菜の種まきに挑戦してみましょう! 3月になったら種まきを始めよう 3月上旬から4月~5月上旬にかけては、春播きの花や野菜の種まきの適期です。 桃の節句(3月3日)が過ぎたら、種まきの準備を始めましょう。 春の種まきカレンダー(一般地) [花] ジギタリス 3月上旬~4月、5月中旬 アグロステンマ(麦なでしこ) 3月中旬~4月 インパチェンス 3月中旬~5月中旬 フラックス(宿根アマ) 3月中旬~4月 ニコチアナ(花たばこ) 4月~5月中旬 ジニア(百日草) 4月中旬~6月上旬 ナスタチウム(金蓮花) 4~5月 [野菜] レタス 3月下旬~ トマト 3月中旬~5月 ズッキーニ 3月中旬~5月上旬 ホウレンソウ 3月中旬~5月下旬 小カブ 3月下旬~ 青ジソ 3月下旬~7月上旬 春大根 5月下旬~ タネ袋の説明をよく読もう 種まき栽培で失敗しない大切なコツ──。それはタネの袋の裏面の説明をよく読むことです。地域ごとの種まきの適期、タネの播き方、発芽適温、発芽までの日数、発芽率、発芽後の管理の仕方など、タネ袋の裏面には大切な情報がいろいろと記されています。その説明を読み、記されている通りにタネを播けば、失敗することはありません。 タネを一晩水につける ナスタチウム、朝顔、ホウレンソウなどはタネの外皮が硬いので、一晩水につけてから播くと、よく発芽します。 ナスタチウムのタネは、水につける前、カッターなどで外皮に軽く傷をつけておきましょう。 覆土する? 覆土しない? 花のタネの中には、発芽するときに光を必要とするものと、光を嫌うものがあります。これを「好光性」と「嫌光性」といいます。 [タネが好光性の草花] ジギタリス インパチェンス ペチュニア フラックス(宿根アマ) ニコチアナ(花たばこ) [好光性のタネの播き方] 種まき用土に、まず水をたっぷりとやります。 その湿らせた用土にタネを播き、指でタネを用土に押しつけ、圧着させます。 覆土はしません。 その後は発芽まで乾燥させないように、霧吹きで水やりを続けましょう。または水を入れたトレイにタネを播いたポットを入れ、底面吸水をさせましょう。 [嫌光性の種] 野菜のタネは、ほぼ全てが嫌光性。覆土を必要とします。 草花では、ナスタチウム、ジニア(百日草)、朝顔などが嫌光性。覆土を必要とします。 [覆土の仕方] 種類によって、タネが隠れる程度に薄く覆土するものと、タネの2~3倍の厚さに覆土するものがあります。 覆土の仕方はタネ袋の裏面に記されていますから、それをよく読み、説明の通りに覆土をしましょう。 ポットやトレイに播く 花や野菜のタネの多くは、用土を入れたポットやトレイの苗床に播いて発芽させ、苗を育てます。そして、ある程度成長したら、プランターやコンテナ、花壇、家庭菜園などに植え付けます。 [必要なグッズ] ポットで育苗するときは、次のようなグッズを用意しましょう。 3号ポット 直径3cmのビニールポットです。 鉢底網 ポットの大きさに合わせてカットして使います。 種まき専用土 粒子の細かい種まき専用土が市販されています。花や野菜用の培養土に播いても発芽しますが、発芽率の向上を目指すなら種まき専用土を使うようにしましょう。 霧吹き タネを播いた後、乱暴に水をやるとタネが流れてしまいます。霧吹きで丁寧に水やりをしましょう。あるいは、タネを播いたポットを水が入ったトレイの中に置き、底面吸水をさせましょう。 [トレイの苗床] たくさん苗をつくりたいときは、種まき用のトレイや連結ポットを利用するとよいでしょう。イチゴの空きパックなどを利用することもできます。容器の底に小さな穴をあけ、種まき専用土を入れて苗床をつくり、種まき用トレイとして代用することもできます。 タネを直播きすると強い苗が育つ 野菜のタネの多くは、家庭菜園や用土を入れたプランター、またはコンテナに直播きして発芽させ、苗を育てます。春以降、園芸店には野菜の苗が多数並びます。苗を買ってくればより手軽に野菜を育てられますが、苗はそれまで育てられていた場所から、あなたの庭や畑へと栽培環境が変わるため、その変化に対応し慣れるための期間中に、病害虫被害を受けるリスクがあります。そこで、時間はかかるものの、種まきから育てたほうが病害虫に強く育つというメリットがあります。 [タネを直播きする野菜] レタス ホウレンソウ 小カブ 大根 人参 ズッキーニ カボチャ トマト [トマトのタネの直播き] トマトは、通常はポットやトレイにタネを播いて苗を育成します。しかし、家庭菜園に直播きすることもできます。その場合は、5月初旬頃、気温が高くなり、地温も十分に上がってから播くようにします。トマトは菜園に直播きすると、病虫害に強い苗が育ちます。キュウリやナスも同様に直播きで栽培できます。 [タネの直播きができる草花] ポピー ラークスパー(千鳥草) ジギタリス ニゲラ(クロタネソウ) ナスタチウム 花壇をよく耕し、腐葉土、完熟堆肥、苦土石灰、化成肥料などを施し、たっぷり水やりをしてから播きます。ラークスパー、ジギタリス、ニゲラは花が終わった後、タネを採取し、すぐに播きます。あるいはタネを保存しておき、9~10月頃に播きます。翌春に開花します。 点播きと条(すじ)播き タネの播き方には、点播きと条(すじ)播きという2つの方法があります。どちらの方法が適切かは、タネの袋の裏面に記されていますので、それに従うようにしましょう。ジギタリスのタネは非常に細かいので、トレイの苗床などにバラ播きします。 [点播き] ペットボトルのフタなどを用土に押し付けて深さ1cm程度の播き穴をつくり、そこにタネを3~4粒ずつ播きます。播き穴と撒き穴の間隔、覆土の厚さは、タネの袋に説明されている通りにします。 [条(すじ)播き] 用土に深さ1cmほどのまっすぐな播き溝をつくり、そこにタネを播いていきます。 タネとタネの間隔、播き溝の幅や間隔、覆土の厚さは、タネの袋の説明に従います。 ●植物に合わせた3つの「種まき」の方法 発芽後の管理は? [間引き] 発芽後、本葉3~4枚になった頃、成長が最もいいものを残して他は間引き、1本立ちにします。 間引きの時期についてもタネの袋に記されていますので、それを参考にしてください。 [植え替え] 苗の成長に合わせて1~2回り大きいポットに植え替え、さらに育苗を続けます。 植え替えを2度ほどした頃から、ごく薄い液肥を与えましょう。頻度は2週間に1回程度とします。 小さなポット苗に顆粒状の化成肥料を与えるのは禁物です。顆粒が溶け始めると、急速に肥料分が効き、苗を枯らしてしまいます。 [植え付け前の土づくり] 苗が成長し、植えつけの時期が近づいてきたら、土づくりをしましょう。 プランターやコンテナ用の土=赤玉土(小粒)6、腐葉土3、完熟堆肥1の割合で混合し、苦土石灰をひとつかみ加えます。 以上をよくかき混ぜ、3週間ほど寝かせておきましょう。 花壇や家庭菜園は、苗を植え付ける3週間前によく耕し、腐葉土、完熟堆肥、苦土石灰、化成肥料などを施しておきます。 [植え付け] 苗が十分に成長したら、プランターやコンテナ、花壇、家庭菜園などに植えつけます。植え付け後は、たっぷり水をやりましょう。 トマトの場合=ポットやトレイにタネを播いて育てたトマトの苗は、一番花が咲き始めた頃に家庭菜園に植え付けます。 タネには消費期限があります タネには食料品などと同じように消費期限があります。おおよそ1年間がその期限で、それを過ぎると発芽率がとても悪くなります。なかにはもっと消費期限が長いものもありますが、いずれもタネ袋に記載されているので、よく読んで期限内に播きましょう。
-
ハーブ

精油の価格の正しい見極め方「ラベンダーの場合」
ラベンダーの主要な系統とは? 安眠やリラックスなどの効果があることで人気のラベンダーオイル。愛用している方も少なくないと思いますが、日常的に使うならちょっとでも価格の安いものを、と思いがちです。実際、ネットなどで調べてみると、同じラベンダーのオイルでも、かなり価格に違いがあります。私は北海道のラベンダーオイルを愛用していますが、試しにネットで価格の安いものを買ってみたところ、その中身が「ラバンジン」であることが分かり、なるほど、とその安さに合点がいきました。ラバンジンもラベンダーの一種ですので、そのオイルをラベンダーオイルといっても間違いではありません。けれども、ラベンダーとラバンジンの間には、かなりの違いがあります。どこがどう違うのか? まずは、ラベンダーには以下の3つの主要な系統があることを覚えておきましょう。 (1)トゥルー・ラベンダー トゥルー・ラベンダーは学名「ラヴァンデュラ・アングスティフォリア」、または「ラバンデュラ・オフィキナリス」。アングスティフォリアとはラテン語で「小さな葉の」という意味、オフィキナリスとは「薬用の」という意味です。英名は「トゥルー・ラベンダー」、仏名は「ラバンド・ヴレ」。いずれも「本当のラベンダー」という意味です。この系統は、数あるラベンダーのエッセンシャルオイルの中でも最もよい香りとされ、現在でも香水や化粧品の重要な原料の一つとなっています。 また、「オフィキナリス」という学名が示すように、かつては薬用としても珍重されました。トゥルー・ラベンダーのエッセンシャルオイルに強い抗菌力と抗ウイルス性の働きがあることは、今日では医学的にも確かめられています。アロマテラピーに使用されるのも、このオイルです。 (2)スパイク・ラベンダー スパイク・ラベンダーは、学名「ラヴァンデュラ・スピカ」、または「ラヴァンデュラ・ラティフォリア」。ラティフォリアとはラテン語で「大きな葉の」という意味で、草姿がトゥルー・ラベンダーとは異なることを示しています。 花穂はトゥルー・ラベンダーよりも長く、主枝の下方に2本の小さな花茎ができ、その先端にも花穂をつけるのが特徴。 スパイク・ラベンダーのエッセンシャルオイルは、カンファー(樟脳)のような臭いが強く、しかもアルコールにも溶けにくいため、香水や化粧品には利用できません。従って、栽培もオイルの生産も行われていません。 (3)ラバンジン トゥルー・ラベンダーとスパイク・ラベンダーの自然交雑種が「ラバンジン」です。つまり、ミツバチなどがトゥルー・ラベンダーとスパイク・ラベンダーの花粉を花から花へと運んだことにより、自然に交雑が起きて誕生したハイブリッド種が「ラバンジン」なのです。従って、ラバンジンにはトゥルー・ラベンダーに近い性質を持つものや、スパイク・ラベンダーに近いもの、またその中間の性質を持つものなどがあります。 ラバンジンはスパイク・ラベンダーの性質を受け継いでいるため、どの種類も主枝の下方で分枝し、そこにも小さな花穂ができます。従って、その分枝があるかないかが、トゥルー・ラベンダーとラバンジンを見分けるときのポイントとなります。 ラベンダーは野生の植物だった!! ラベンダーは、もともと野生の植物で、トゥルー・ラベンダーもスパイク・ラベンダーも、乾燥した冷涼な気候の高原や山岳丘陵地帯に自生していました。 フランスのある作家は、1920年代のアフガニスタンでラベンダーの大草原を見て感激したことを、晩年近くになって出版した自伝の中に記しています。 今から80年ほど前には、サハラ砂漠中央部のアハガール台地で「ラヴァンデュラ・コロノピフォリア」と「ラヴァンデュラ・アンテナーエ」という古いラベンダーの生き残りが発見されました。このことから、サハラが砂漠化する以前は北アフリカのほぼ全域が野生のラベンダーの大草原に覆われていたのではないかと推定している学者もいます。 自然交雑はどこで起きた? トゥルー・ラベンダーは耐寒性が非常に強く、標高600m以上の場所で繁殖し、高い所では標高1,400m前後の高山地帯にも自生していました。一方、スパイク・ラベンダーは標高600m以下の丘陵地の南斜面などに自生していましたが、そこにも野生のトゥルー・ラベンダーが繁茂していました。そのため、ミツバチなどの活動によって交雑が起き、トゥルー・ラベンダーとスパイク・ラベンダーの性質を併せ持つハイブリッド種「ラバンジン」が誕生したのです。 ラバンジン「発見」!! ラベンダーの原産地の一つである南仏プロヴァンス地方では、農民たちが野生のラベンダーを刈り集め、エッセンシャルオイルを生産していましたが、彼らは野生種の中にひときわ大きなラベンダーがあることに早くから気がついていました。 人々はそれを「でっかいラベンダー」「太っちょラベンダー」などと呼び、さらにバゲットよりも短くて太いパン、バタールにちなんで「バタール・ラベンダー」とも呼んでいました。それがまさに「ラバンジン」だったのです。 ラバンジンの特徴とは? ラバンジンはラベンダーよりも生育がはるかに旺盛で、非常な大株に育ちます。そして気象条件にも土壌の条件にも、強い適応力を持っています。また、大株になるためエッセンシャルオイルの収油量がきわめて多い(トゥルー・ラベンダーの10倍!)のも大きな特徴の一つです。また、トゥルーラベンダーにはほとんどない、カンファー(樟脳)臭が含まれており、少し刺激的でシャープな香りです。逆にトゥルー・ラベンダーの香りの主要な香気成分であるリナロールなどの含有量が少ないため、トゥルー・ラベンダーのオイルのような甘く強い芳香は持っていません。ラバンジンはハイブリッド種なので、花が咲いても種子をつくることができません。従って、繁殖は挿し木増殖によって行われています。 ラバンジンにはどんな種類があるの? ラバンジンの主な種類は次の4つです。 (1)ラバンジン・アブリアル エッセンシャルオイルの収油量が非常に多い品種。南仏プロヴァンス地方では1930年代から盛んに栽培されました。名称は、このラバンジンを品種として固定した農学者アブリアル教授にちなんでいます。 (2)ラバンジン・シュペール トゥルー・ラベンダーに近い性質を持つ品種。プロヴァンス地方では一時は「アブリアル」をしのぐ勢いで栽培されましたが、現在は他のラバンジンに取って代わられ、エッセンシャルオイルの生産量も減少しています。 (3)ラバンジン・グロッソ 南仏プロヴァンス地方ヴォークリューズ県在住のグロッソ氏によって育種が行われ、品種として固定された種類。強健で、エッセンシャルオイルの収油量も多いため、プロヴァンス地方では1970年代半ばに劇的に栽培面積が増えました。現在、日本の宿根草専門店などで販売されているのも、ほとんどがこの「グロッソ」です。 (4)ラバンジン・オルディネール ラバンジン栽培の初期に主流となっていた品種。オルディネールとは、フランス語で「普通の」「ありふれた」という意味です。日本でこのラバンジンを見かけることはまずありません。 気になるオイルのお値段は? トゥルー・ラベンダーは収油率が低いため、エッセンシャルオイルの価格はどうしても高くなります。現在は50ml入りボトル、4,000~5,000円といったところが平均的な価格でしょう。それに対し、ラバンジンは収油量が非常に多いので、エッセンシャルオイルはきわめて安価です。 ただし、前述したようにトゥルー・ラベンダーのオイルのような甘く爽やかな香りは期待できません。ラバンジンにはトゥルー・ラベンダーにはないカンファーという成分が含まれているため、リラクゼーションよりはリフレッシュというイメージで使うとよいでしょう。使い道に応じて、また2つを比較してみて好みのほうを選ぶとよいでしょう。 併せて読みたい ・安眠効果あり!「ラベンダーピロー」の作り方 ・富良野ラベンダー物語1〜海を越えた友情が咲かせた花〜 ・ラベンダーの育て方。コツとお手入れ、植え替えや寄せ植えを一挙紹介します Credit 文/岡崎英生(文筆家・園芸家) 早稲田大学文学部フランス文学科卒業。編集者から漫画の原作者、文筆家へ。1996年より長野県松本市内四賀地区にあるクラインガルテン(滞在型市民農園)に通い、この地域に古くから伝わる有機栽培法を学びながら畑づくりを楽しむ。ラベンダーにも造詣が深く、著書に『芳香の大地 ラベンダーと北海道』(ラベンダークラブ刊)、訳書に『ラベンダーとラバンジン』(クリスティアーヌ・ムニエ著、フレグランスジャーナル社刊)など。
-
育て方
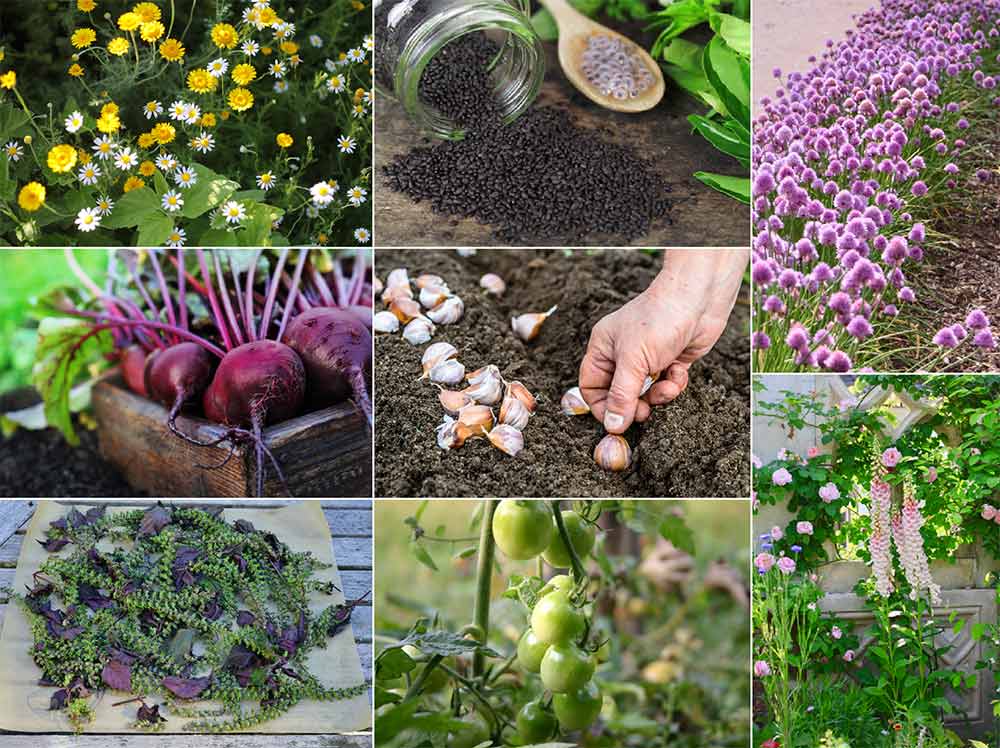
10月の庭仕事 収穫物の利用・植え付け・種まき5つの作業
作業①バジルのタネでダイエット ダイエット食品として注目されているのがバジルシード、つまりバジルのタネ。10月になると、夏から家庭菜園で育ててきたバジルには花穂が伸び、タネができ始めます。タネが完熟するのを待って収穫し、ダイエットに大いに利用しましょう。 バジルシードの効果とは? バジルシードは水を注ぐと、約5〜10分で30倍に膨らみます。そのまま食べたり、ヨーグルトやジュースに加えて摂取したりすると、かなりの満腹感が得られ、ダイエットにつながります。 腸内環境を整え、肥満も改善! また、バジルシードは約50%が不溶性食物繊維なので、腸内環境を整えるのに役立ちます。さらに、青魚に多いDHA(ドコサヘキサエン酸)と同じタイプの不飽和脂肪酸が含まれているので、肥満改善の効果が期待できます。 バジルシードの食感は? プリプリ、ツルッとしていて、タピオカのような食感。体型維持に気を遣うモデルたちに大人気で、東南アジアではデザートとしてよく食べられています。 バジルシードの収穫法は? 花穂にできるタネがしっかりと硬くなり、充実してきたら収穫し、タネを軸から外して軽く水洗いします。その後、風通しのいい日陰で乾かし、完全に水気がなくなったら煮沸消毒したガラス瓶などに入れて保存しましょう。 使う時は適量をスプーンですくい取り、水を注いでそのまま食べたり、ヨーグルトやジュースに加えたりします。クッキーを手づくりする時に加えるのもおすすめです。 通販でも バジルシードは通販でも手に入れることができます。 作業②シソの実の塩漬けをつくる シソも10月になると花穂を伸ばし、タネをつけ始めます。花穂を収穫し、シソの実の塩漬けをつくっておくと、シソのいい香りがいつまでも楽しめます。 [シソの実の塩漬けの作り方] 花穂を収穫し、シソの実を軸から外す。 それを一晩水に浸けてアクを抜く。 一晩経ったらザルに上げて水を切り、さらにキッチンペーパーで水気をよく拭き取る。 シソの実の重さの8%の粗塩を振り、よく混ぜる。 梅酢を小さじ1〜2加える。 梅酢を加えることでシソの実の色変わりを防ぐことができ、保存性も高まる。 煮沸消毒したガラス瓶などに入れて、冷蔵庫で保存する。 こうしてつくったシソの実の塩漬けは1カ月ほどすると塩辛さの角が取れて、風味も増します。おにぎりに混ぜたり、冷や奴の薬味にしたりして楽しみましょう。 炊きたてのご飯で作るシソの実ご飯もおすすめです。 [シソの実ご飯の作り方] ・炊きたてのご飯 ・シソの実の塩漬け ・ミョウガ(みじん切り) ・ちりめんじゃこ ・その他お好みの具 炊きたてのご飯に上記の材料(それぞれ適量)を加えて、軽く混ぜるだけ。さわやかな秋の朝にピッタリの美味しいご飯のでき上がりです。 作業③青いトマトをヌカ漬けにする 家庭菜園ではトマトが今も実り続けていますが、朝夕の気温が下がってくると、次第に赤くなることができなくなります。でも、青いトマトを捨ててしまうのはもったいない。 半分に切ってヌカ床に入れ、ヌカ漬けにしましょう。3〜4日ほどすると、えぐみが抜けて、ちょっと酸味のある美味しいヌカ漬けになります。 作業④ニンニクの植え付け 10月はニンニクの植え付けの適期。プランターでも栽培できるので、ぜひ挑戦してみましょう。 用意するものは? ・ニンニクの種球(園芸店、ホームセンター、通販などで購入) ・深さ25cm以上のプランター ・野菜用の培養土 ・完熟堆肥(牛糞堆肥など) ・苦土石灰 ・化成肥料 植え付け前の準備は? 植え付けの3週間前に、培養土に完熟堆肥、苦土石灰、少量の化成肥料を混ぜ、そのまま寝かせておきます。 こうして土づくりをしておくと、植え付け後の生育がよくなります。これは他の野菜でも、また草花類でも同じ。いわばガーデニングの基本なので、ぜひ覚えておきましょう。 植え付け方は? 種球をほぐして、ニンニクの鱗片を1片ずつにします。 薄皮は剥いても、剥かなくてもOK。ただし、剥いたほうが水分や肥料分の吸収がよくなり、生育が早まります。 プランターに3週間寝かせておいた土を8分目ほどまで入れます。 ニンニクの鱗片を一つずつ、15cm間隔で植え付け、4〜5cmくらい覆土します。 たっぷり水やりをして、植え付け完了です。 その後の作業は? [芽かき] 植え付け後30日ほどで発芽します。1株から2本芽が伸びていたら、生育のよいほうを残して、芽をかき取りましょう。この時、残すほうも抜けてしまわないように、株元をしっかり手で押さえておくことが必要です。 [追肥] ・1回目……12月頃、株元に完熟堆肥一つかみと少量の化成肥料を散布します。 ・2回目……2月中旬。上記と同様に追肥を行います。 [トウ立ち] 4〜5月頃、まっすぐな花茎が伸び始めます。これをトウ立ちといいます。花を咲かせてしまうと地中のニンニクに養分が行かず、大きくならないので、花茎を引き抜きましょう。手で引っ張るとスポッと簡単に抜けます。この花茎は、ニンニクの芽として炒め物などにして食べられます。 収穫は? 6月、葉が黄色くなり始めたら収穫期です。作業はなるべく晴天の日に行いましょう。 保存法は? しばらく日向に置いて乾燥させ、茎が乾いたら2〜3束ずつ束ねて、雨の当たらない軒先などに吊るして保存します。 作業⑤秋まき野菜、秋まき草花などの種まき 10月は秋まき野菜や秋まき草花の種まきの適期です。 播き方などは、前回、「9月の庭仕事」で紹介したので、今回は種まきができる植物名だけを挙げておくことにしましょう。 [野菜] パクチー、ビーツ、春菊、ほうれん草、リーフレタス、葉大根など。 [草花] ペチュニア、ニゲラ(クロタネソウ)、カンパニュラ、ジギタリスなど。 [ハーブ] タイム、カモミール、チャイブなど