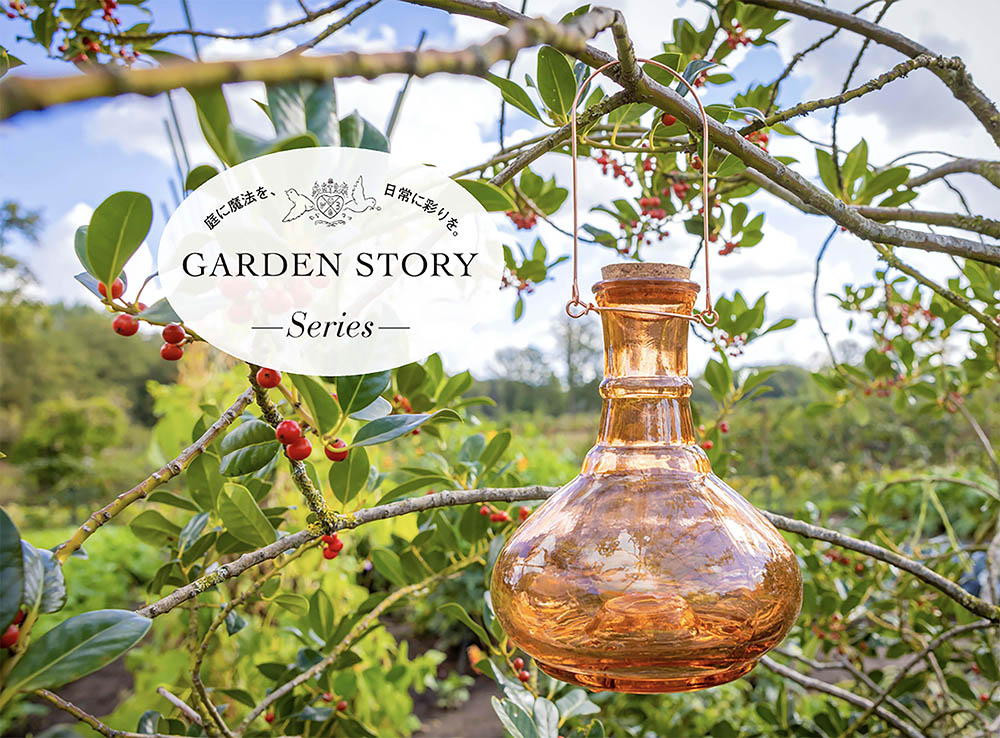シルバーリーフが魅力! アサギリソウ(朝霧草)の育て方とお手入れ方法

Roollooralla/Shutterstock.com
細かい切れ込みが入る葉が、ふんわりと繊細なイメージをもたらすアサギリソウ。産毛に覆われているため光を受けるとシルバーグリーンに輝き、美しいカラーリーフとして活躍します。この記事では、アサギリソウの基本情報や特徴、名前の由来や花言葉、種類、育て方などについて詳しく解説します。
目次
アサギリソウの基本情報

植物名:アサギリソウ
学名:Artemisia schmidtiana
英名:silvermound
和名:アサギリソウ(朝霧草)
科名:キク科
属名:ヨモギ属
原産地:北陸以北~北海道、樺太、千島
形態:宿根草(多年草)
アサギリソウは漢字で「朝霧草」と書き、学名はArtemisia schmidtiana(アルテミシア・シュミドティアナ)です。キク科ヨモギ属の多年草で、原産地は日本の北陸以北〜北海道、樺太、千島。高温多湿がやや苦手で、寒さに強い性質をもっています。草丈は20〜30cmほどです。落葉性で、冬は地上部を枯らして休眠し、翌年の成育期に入ると新芽を出して再び生育します。
アサギリソウの葉や花の特徴

園芸分類:草花
開花時期:8月〜9月上旬
草丈:20〜30cm
耐寒性:普通
耐暑性:普通
花色:黄
アサギリソウの茎葉はびっしりと白い産毛に覆われています。光を受けると輝くようなシルバーリーフが大変美しく、主に茎葉を観賞するカラーリーフプランツとして人気があります。線のような細い葉は長さ4〜5㎝で、羽状複葉で細かい切れ込みが入る繊細な表情が魅力的。ふわふわとした軽やかな質感でドーム形にまとまり、思わず触ってみたくなる草姿をしています。
アサギリソウの開花期は8月〜9月上旬で、小さな黄色い花を咲かせます。花よりも茎葉に観賞価値があるとされ、つぼみのうちから切り取って株姿の勢いを保つのも一案です。
アサギリソウの名前の由来や花言葉

アサギリソウという和名は、光を通して輝く繊細な白い葉が朝霧を連想させることから名付けられたとされています。アサギリソウの花言葉は「喝采」「慕う心」「脚光」「光」などです。
アサギリソウの仲間
アサギリソウが属するヨモギ属にはいくつかの種類があり、カラーリーフとしてガーデニングで人気のものもあります。主なものを取り上げてご紹介します。
シロヨモギ

本州中部から北に分布し、海岸の砂地や斜面などに自生。茎葉はびっしりと白い産毛に覆われてふかふかと厚みがあり、白く見えます。葉はアサギリソウほど細くはなく、羽状に中裂するのが特徴です。地下茎を伸ばして増えていきます。草丈は20〜50cmほど。
チシマアサギリソウ
南千島産のアサギリソウで、より葉が繊細です。草丈は15〜30㎝ほどで、コンパクトにまとまります。暖地では多湿に弱いため、長雨などに当てないように管理しましょう。
サマニヨモギ
北海道や東北地方に分布し、高山の岩場や乾いた草地などに自生。新芽の頃は産毛に覆われていますが、開花する頃には薄くなります。小型種で、草丈は30〜50cmほどです。
アルテミシア‘ポウィスキャッスル’

ニガヨモギの交配種で、イギリス、ウェールズにあるポウィス城の名を冠した園芸種。丈夫ですが、ニガヨモギよりも小さめの草姿にまとまるので扱いやすく、人気が高い品種です。
アルテミシア・ルドビシアナ

高さ90cmほどまで垂直に伸びる立性の草姿と、‘ポウィスキャッスル’に比べ葉幅がより広く、より明るいシルバーグレーになるのが特徴です。高温多湿への耐性はやや低め。
アサギリソウの栽培12カ月カレンダー
開花時期:8月〜9月上旬
植え付け・植え替え:3月下旬〜4月
肥料:4月下旬〜6月下旬、10月〜11月上旬
適した栽培環境

日当たり・置き場所
【日当たり/屋外】日当たりがよく、風通しのよい場所を好みます。日当たりが悪い場所では、ヒョロヒョロとか弱い茎葉が茂って草姿が間のびするので注意しましょう。
【日当たり/屋内】一年を通して屋外での栽培が基本です。
【置き場所】真夏の高温多湿の環境をやや苦手とするので、水はけのよい場所で風通しよく管理します。
耐寒性・耐暑性
寒さには強く、耐寒温度はマイナス15〜25℃くらいなので、戸外で越冬できます。蒸れに弱いので、夏は風通しよく管理しましょう。
アサギリソウの育て方のポイント
用土

【地植え】
植え付ける1〜2週間前に腐葉土や堆肥、緩効性肥料を植え場所に投入し、よく耕して水はけのよい土壌をつくっておくとよいでしょう。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。
【鉢植え】
草花の栽培用に配合された園芸用培養土を利用すると便利です。自身で培養土をブレンドする場合は、赤玉土と鹿沼土を等量で混合し、さらに元肥として緩効性肥料を施しておくとよいでしょう。
水やり

アサギリソウは細かな産毛を株全体にびっしりとまとっています。そのため、茎葉に水がかかると蒸れやすくなるので水やりの際には注意してください。株全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えるようにしましょう。
真夏は昼間に水やりすると水の温度が高いため株が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。反対に、真冬は気温が十分に上がった日中に行います。夕方に水やりすると凍結の原因になるので避けてください。
【地植え】
植え付け後にしっかり根づいて茎葉を伸ばすようになるまでは、水切れしないように管理しましょう。根付いた後は地中の水を吸い上げるのでほとんど不要です。ただし、雨が降らずに乾燥が続くようなら、水やりをして補います。
【鉢植え】
日頃から水やりを忘れずに管理します。ただし、アサギリソウは多湿を嫌うので与えすぎには注意し、いつもジメジメしている環境にならないようにしてください。
土の表面が十分に乾いてから、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。茎葉がややだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。特に真夏は高温によって乾燥しやすくなるため、水やり忘れに注意します。冬は休眠しますが、カラカラに乾燥させることのないように控えめに与えるとよいでしょう。
肥料

【地植え、鉢植えともに】
土づくりの際に、元肥として緩効性肥料を施しておきます。追肥は4月下旬〜6月下旬と10月〜11月上旬の真夏を除いた生育期に、液肥を2週間に1度を目安に与えて株の勢いを保ちましょう。
注意する病害虫

【病気】
アサギリソウが発症しやすい病気は、軟腐病、炭疽病などです。
軟腐病は細菌性の病気で、高温時に発生しやすくなります。特に梅雨明けから真夏が要注意。
球根や成長点近くの茎、地際の部分や根が腐って悪臭を放つので、発症したのを見つけたら、周囲に蔓延しないようにただちに抜き取り、周囲の土ごと処分してください。予防としては、連作(同じ科に属する植物を同じ場所に植え続けること)を避け、水はけをよくしていつもジメジメとした環境にしないこと。また、害虫に食害されて傷ついた部分から病原菌が侵入しやすくなるので、害虫からしっかり守ることもポイントになります。
炭疽病は、春や秋の長雨の頃に発生しやすくなります。カビが原因で発生する伝染性の病気で、葉に褐色で円形の斑点ができるのが特徴です。その後、葉に穴があき始め、やがて枯れ込んでいくので早期に対処することが大切です。斑点の部分に胞子ができ、雨の跳ね返りなどで周囲に蔓延していくので、被害を見つけたらすぐに除去して土ごと処分しておきましょう。密植すると発病しやすくなるので、茂りすぎたら葉を間引いて風通しよく管理してください。水やり時に株全体に水をかけると、泥の跳ね返りをきっかけに発症しやすくなるので、株元の表土を狙って与えるようにしましょう。
【害虫】
アサギリソウに発生しやすい害虫は、アブラムシ、ナメクジなどです。
アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、植え付け時に土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。
ナメクジは花やつぼみ、新芽、新葉、果実などを食害します。体長は40〜50mmで、頭にツノが2つあり、茶色でぬらぬらとした粘液に覆われているのが特徴。昼間は鉢の下や落ち葉の底などに潜んで姿を現しませんが、夜に活動します。植物に粘液がついていたら、ナメクジの疑いがあるので夜にパトロールして捕殺してください。難しい場合は、ナメクジ用の駆除剤を利用して防除してもよいでしょう。多湿を好むので風通しをよくし、落ち葉などは整理して清潔に保っておきます。
アサギリソウの詳しい育て方
苗の選び方
苗を購入する際は、節間が間のびしておらず、がっしりと締まって勢いのあるものを選びましょう。
植え付け・植え替え

植え付けの適期は3月下旬〜4月です。適期以外に花苗店などで苗を購入した場合は、早めに植え付けてください。
【地植え】
土づくりをしておいた場所に、根鉢よりもひと回り大きな穴を掘って苗を植え付けます。複数の苗を植える場合は30〜40cmの間隔を取っておきましょう。植え付けた後に、たっぷりと水やりします。
庭で育てている場合、環境に合えば数年は植え替える必要はありません。大株に育って込み合ってきたら掘り上げて株分けし、植え直して若返りを図りましょう。
【鉢植え】
苗を単植するなら、鉢のサイズは、6〜7号鉢を準備します。
用意した鉢の底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから培養土を半分くらいまで入れましょう。苗を鉢に仮置きし、高さを決めたら、軽く根鉢をほぐして植え付けましょう。水やりの際にすぐ水があふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取っておいてください。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底からたっぷりと水が流れ出すまで、十分に水を与えましょう。寄せ植えの素材として、大鉢にほかの植物と一緒に植え付けてもOKです。
鉢植えで楽しんでいる場合、成長とともに根詰まりして株の勢いが衰えてくるので、1〜2年に1度は植え替えることが大切です。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から株を取り出してみて、根が詰まっていたら、根鉢をくずして古い根などを切り取りましょう。根鉢を1/2〜1/3くらいまで小さくして、元の鉢に新しい培養土を使って植え直します。もっと大きく育てたい場合は、元の鉢よりも大きな鉢を準備し、軽く根鉢をくずす程度にして植え替えてください。
日常のお手入れ

【切り戻し】
草姿が乱れてきたら、適宜切り戻します。草丈の半分くらいまでを目安に、深めにカットしましょう。梅雨前に行うと、株が蒸れやすくなるのを防ぎ、風通しよく管理することができます。
【つぼみの除去・花がら摘み】
アサギリソウは小さな黄色い花を咲かせますが、どちらかというとシルバーリーフの茎葉を主に観賞します。花を咲かせると株が消耗してしまうので、茎葉の観賞を重視するならば、つぼみがついたら早めに摘み取りましょう。
また、花を楽しむなら、終わった花は適宜摘み取りましょう。まめに傷んだ花を摘んで株まわりを清潔に保つことで、病害虫発生の抑制につながります。また、いつまでも終わった花を残しておくと、種子をつけようとして株が消耗し、老化が早まってしまうので注意しましょう。
増やし方

アサギリソウは、株分けと挿し芽で増やすことができます。ここでは、それぞれの方法について解説します。
【株分け】
アサギリソウの株分けの適期は3月下旬〜4月です。
アサギリソウの株を植え付けて数年が経ち、大きく育ったら株の老化が進むので、「株分け」をして若返りを図ります。株を掘り上げて数芽ずつつけて根を切り分け、再び植え直します。それらの株が再び大きく成長し、株が増えていくというわけです。切り分ける際は、あまり小分けにしない方がよいでしょう。
【挿し芽】
挿し芽とは、茎葉を切り取って地面に挿しておくと、発根して生育を始める性質を生かして増やす方法です。植物のなかには挿し芽ができないものもありますが、アサギリソウは挿し芽で増やせます。
アサギリソウの挿し芽の適期は、4月下旬〜5月です。新しく伸びた茎を10〜15cmほど、切り口が斜めになるように切り取り(挿し穂)、水の吸い上げと蒸散のバランスを取るために下葉を半分くらい取ります。黒ポットを用意して新しい培養土を入れ、十分に湿らせておきます。培養土に穴をあけ、穴に挿し穂を挿して土を押さえてください。明るい日陰に置いて適宜水やりをしながら管理し、発根して十分に育ったら植えたい場所へ定植しましょう。挿し芽のメリットは、親株とまったく同じ性質を持ったクローンになることです。
ふわふわの見た目が可愛いシルバーリーフ「アサギリソウ」を育ててみよう

美しいシルバーリーフを持つアサギリソウは、こんもりと茂るので色の塊となって主張しつつも、葉姿が繊細なので軽やかさも併せ持っています。カラーリーフとしても、華やかな花々との調和役としても重宝するアサギリソウの栽培に、チャレンジしてみませんか?
Credit
文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!
- リンク
記事をシェアする
新着記事
-
育て方

秋のバラ苗予約スタート! 夏バテバラの回復におすすめのプロ推奨資材&作業ポイントも詳し…PR
今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…
-
ガーデン&ショップ

【スペシャル・イベント】ハロウィン色で秋の庭が花やぐ「横浜イングリッシュガーデン」に…PR
今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、9月13日(土)から「ハロウィン・ディスプレイ」…
-
ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【秋の到来を知らせる9月…
新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストが、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台にスタートし、春の花が次々と咲き始めています。…