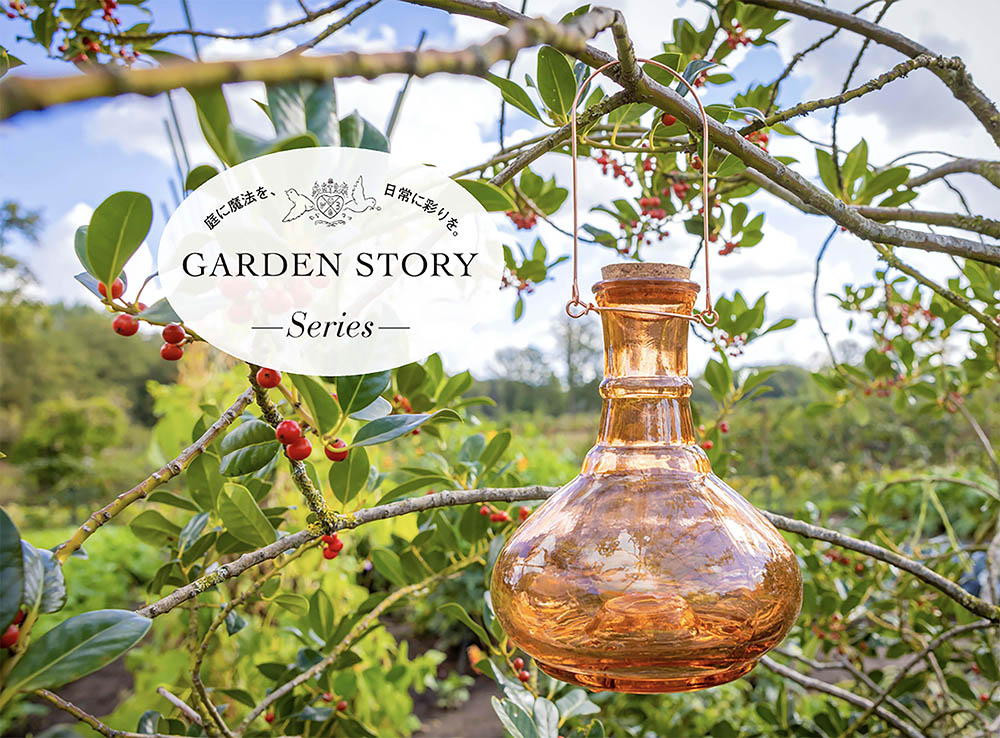植物にやっかいな被害を与える代表的な害虫10種! 特徴や対処法をご紹介

Jiggo_Putter Studio/Shutterstock.com
植物の栽培では害虫がつきもの、といってもいいかもしれません。見た目に不愉快なだけでなく生育も著しく阻害され、最悪の場合枯れてしまうこともあるため、対策が必要です。害虫にはさまざまなタイプがいるので、相手をよく知ることも大切。この記事では、植物につきやすい10種の代表的な害虫を取り上げ、特徴や対策などについてご紹介していきます。
目次
植物につく害虫の種類

植物につく害虫は、大きく「食害性害虫」と「吸汁性害虫」に分類されます。
「食害性害虫」は、主に昆虫の幼虫が葉、芽、茎、根などを旺盛に食べて穴をあけたり、新芽をことごとく食べてしまって、植物の生育を阻害します。食害した傷から菌などが入り、病気を発症してしまうこともあるので注意が必要です。食べられた部位やあいた穴の形状によって、ある程度害虫を特定することができるので、ガーデニング上達への第一歩は、害虫の特性を知ることからとなります。
「吸汁性害虫」は、植物の体内にある汁液を吸う害虫で、アブラムシ類やコナジラミ 類、昆虫、ダニ類などが挙げられます。小さな虫がほとんどで、ダニ類などは肉眼では見えないこともあり、気がついたら大発生していた、というケースも。また、吸汁によってウイルス病を媒介することもあるので、放任せずに早めに駆除しておきましょう。食害性害虫とは異なり、穴があくなどの分かりやすい状況判断はできませんが、葉が巻いていたり、排泄物が原因となってすす病が発生したりという植物の状態から、発生を疑うことができます。
害虫が発生する要因

ガーデニングでは、害虫対策に頭を悩ますことになりますね。でも、「害虫が発生しやすい環境」とは何かを知っておくと、害虫を呼ばない環境づくりを心がけることができます。では、害虫が発生しやすい要因とはなんでしょうか。
害虫が発生しやすいのは、菜園では特に連作を繰り返したケースが挙げられます。連作とは、同じ科の植物を同じ場所に植え続けること。例えばアブラナ科のコマツナを栽培した同じ場所に、アブラナ科のダイコンを栽培することを繰り返すと、土壌の栄養バランスが崩れてしまい、病害虫が発生しやすくなって健全に生育できなくなります。菜園を楽しむ場合は、同じ科の植物を続けて同じ場所に植えないように場所を区分けし、ローテーションする菜園計画を立てることで、病害虫発生を抑えることができます。
庭などではどうでしょうか。害虫が好む環境とは、次のようなケースです。「雑草が生い茂っている」「落ち葉や枯れ枝、落ちた花が散乱している」「植物が密集していて、株間が狭く風通しが悪い」「生け垣や樹木が手入れされずに伸び放題で密に茂りすぎている」など。このような環境は害虫の棲み処となり、越冬場所として好条件。翌年の春になるとターゲットとなる植物に移っていきます。まずは枯れた葉や枝、花がらなどはまめに整理して清潔に保つこと、そして植物が密生しないように、風通しよく剪定管理することが、害虫を呼ばない環境づくりの基本です。
植物に被害をもたらす害虫10種の特徴と対処法
ここからは、ガーデニングで発生しやすい害虫10種についてピックアップし、その特徴と対処方法について解説します。
アザミウマ

アザミウマは花や葉につき、吸汁する害虫です。別名はスリップス。体長は1〜2mmと大変小さく、色は緑や茶、黒の昆虫で、群生して植物を弱らせるので注意しましょう。針のような器官を葉などに刺して吸汁する際にウイルスを媒介するので、二次被害が発生することもあります。被害が進んだ花や葉は傷がついてかすり状になる異変が見られるので、よく観察してみてください。花がらや枯れ葉、雑草などに潜みやすいので、株まわりを清潔に保っておきます。土に混ぜるタイプの粒剤を利用して防除してもよいでしょう。
アブラムシ

アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目にも悪いので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、シャワーではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、植え付け時に土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。
カイガラムシ

カイガラムシは、ほとんどの庭木に発生しやすい害虫で、体長は2〜10mm。枝や幹などについて吸汁し、だんだんと木を弱らせていきます。また、カイガラムシの排泄物にすす病が発生して二次被害が起きることもあるので注意を。硬い殻に覆われており、薬剤の効果があまり期待できないので、ハブラシなどでこすり落として駆除するとよいでしょう。
カメムシ

カメムシは、新芽、葉、鞘、果実などについて吸汁する害虫で、体長は10〜12mm。触ると嫌なにおいを発生させます。アオクサカメムシ、ホソヘリカメムシは野菜に寄りつきやすく、特にエダマメでは被害が大きくなりがちで、サヤについて中の豆の汁を吸い、吸汁されたサヤは黄色く変色して落下するので、収穫量が減ってしまいます。成虫は見つけ次第捕殺し、除草をまめに行いましょう。果樹類には、果実に袋がけをして対策します。
グンバイムシ

グンバイムシは葉に寄生して吸汁する害虫です。体長は幼虫が2mm、成虫が3mmほど。羽はなく、トゲのようなものが体中についているのが特徴です。被害にあうと、葉の緑色が抜けて白っぽいかすり状になるので、葉に異常を感じたら葉裏などを入念に観察してください。葉裏には黒い排泄物が見つかります。風通しの悪い環境で発生しやすいので、枝葉が込んでいたらすかすように剪定をしておきましょう。越冬場所にならないように、落ち葉や雑草を除去しておきます。大発生したらスプレータイプの適応薬剤で駆除しましょう。
コナジラミ

コナジラミは、植物の葉裏について吸汁する害虫です。体長は1mmほどで大変小さいのですが、白いので意外と目にとまりやすいです。繁殖力が旺盛で、短期間で卵から幼虫、成虫になり、被害が拡大しやすいのが特徴。吸汁によってウイルスを媒介するほか、排泄物にすす病が発生しやすく、二次被害を呼びやすいので要注意。冬は卵やサナギの状態で雑草の中に潜み、春になると周囲に移動して活動を始めるので、雑草や枯れ葉を残さずに処分しておきましょう。大発生した時はスプレータイプの適応薬剤を散布して対処してください。
ハダニ

ハダニは、葉裏に寄生して吸汁する害虫です。体長は0.5mmほどと大変小さく、黄緑色や茶色い姿をしています。名前に「ダニ」がつきますが、クモの仲間。高温で乾燥した環境を好み、梅雨明け以降に大発生しやすいので注意が必要です。繁殖力が強く、被害が大きくなると、葉にクモの巣のような網が発生することもあります。ハダニは湿気を嫌うため、高温乾燥期に葉裏にスプレーやシャワーなどで水をかけて予防するとよいでしょう。
ケムシ

ケムシ類は蛾の幼虫。いも虫のような姿で多数の細かい毛に覆われています。ケムシの種類は多様ですが、主に体長は20〜30mm。葉裏などに幼虫が大発生することがあり、見た目も悪いので見つけ次第駆除しましょう。ケムシの中でもドクガ類はやっかいで、毒を持っています。最も知られているのはチャドクガで、毒をもつ毛に触れるとかぶれて皮膚炎を起こします。ツバキやサザンカに発生しやすいので注意してください。見つけたら早々に駆除しましょう。毛が皮膚につかないように、長袖、長ズボン、手袋を着用し、枝ごと切ってビニール袋に入れて処分してください。
コガネムシ

コガネムシは、幼虫が根を、成虫が花、つぼみ、葉を旺盛に食害します。成虫の体長は20mm前後で、緑、茶色などの甲虫です。幼虫は土中に潜み、根を食害します。目には見えないので発生が分かりづらいのですが、地上部の茎葉が何の原因も見当たらないのに黄色く枯れ込み始めたら、地中の異変を疑ってください。鉢栽培では特に、放置すると枯死してしまうこともあるので注意。毎年発生するようになった場合は、地中に混ぜるタイプの粒剤を利用して防除しましょう。
ナメクジ

ナメクジは花やつぼみ、新芽、新葉、果実などを食害します。体長は40〜50mmで、頭にツノが2つあり、茶色でぬらぬらとした粘液に覆われているのが特徴。昼間は鉢底や落ち葉の下などに潜んで姿を現しませんが、夜に活動します。植物に粘液がついていたらナメクジの疑いがあるので、夜にパトロールして捕殺してください。ナメクジ用の駆除剤を利用して防除してもよいでしょう。多湿を好むので風通しをよくし、落ち葉などは整理して清潔に保っておきます。
殺虫剤以外の対処方法
野菜やハーブ、果物など、収穫を楽しむ植物には、薬剤を使いたくないという方も多いことでしょう。害虫は薬剤を使用せずに対処することもできるので、おすすめの方法をご紹介していきます。
防虫ネットを使用する

家庭菜園で、野菜を無農薬栽培したい場合には、園芸用資材を上手に利用する方法があります。用意するのは、防虫ネットと園芸用支柱です。防虫ネットはなるべく網目の細かいものを選んでください。
園芸用支柱を畝の両端と中央あたりにアーチ状にして深く差し込み、防虫ネットを被せます。畝の両端で防虫ネットを結び、四方の裾に土を盛ってしっかりと固定。畝の両端の結び目は、Uピンを上から刺してとめるとよいでしょう。これで物理的に虫の侵入を抑えられるというわけです。キャベツやハクサイ、ブロッコリー、ダイコン、コマツナなど、特に葉を食害されやすいアブラナ科の野菜などに有効です。株がしっかり育って、ネットの天井につかえて邪魔になるほど大きくなったら外します。虫が苦手な方は、園芸用資材を上手に使って防除するのがおすすめです。ただし、ヨトウムシなど地中に潜んで、主に根を食害する害虫には対策にならないので注意してください。
おとり資材の活用

おとり用の資材を利用して、守りたい植物に近づけないようにする方法もあります。おとりとは、害虫が好む色やフェロモンを使って誘引し、植物から遠ざける対処法です。
まず、粘着テープのおとり資材について解説しましょう。黄色はアブラムシ類やコナジラミを引き寄せる色で、資材として販売されている黄色の粘着テープを守りたい植物の近くに設置すると、そこに虫が集まります。すると粘着物質によって身動きが取れなくなり、植物に近づく害虫が減るというわけです。一方、青い粘着テープにはアザミウマを引き寄せる効果があります。
次に、フェロモントラップの利用について。これは市販されているキットで、メスのフェロモンを入れた容器を設置しておくと、中にオスが誘い込まれます。容器は一度入ると脱出不可能な仕掛けになっているので、そのまま駆除できるというわけです。
コンパニオンプランツの活用

コンパニオンプランツは、「共栄作物」と訳されています。相性のいい植物を一緒に植えることによって、収穫した果実などの味がよくなったり、病害虫の発生を抑えたりすることを利用するものです。代表的なコンパニオンプランツは、ミント類などのシソ科のハーブ。野菜などの周囲に植えると、カメムシ類やカミキリムシを寄せつけないとされています。また、アフリカンマリーゴールドは、土中に潜むセンチュウを抑制し、コナジラミを近づけないとして、これらの被害が出やすい植物の周囲に植えられることが多い草花です。
相性のいい組み合わせとしてよく知られるのは、トマトとバジル。一緒に植えることでお互いの味、香りをよくし、アブラムシ類の被害が少なくなるとされています。また、ネギとキュウリの組み合わせは、ウリハムシの被害が少なくなり、つる割れ病が発生しにくくなるようです。
逆に、相性の悪い組み合わせもあります。キャベツとボリジ、ジャガイモとローズマリー、ピーマンとツルインゲンは相性の悪い組み合わせです。
植物が害虫の被害にあわないよう、しっかり対策を行おう

害虫の被害から植物を守るためには、害虫が発生しにくい環境に整えるのが第一の手段です。日頃から植物の状態をよく観察し、異常を発見したらすぐに対処して、被害が広がらないようにしましょう。スプレータイプの薬剤は手軽に利用でき、効果も高いですが、それらを使わずに対処する方法にもトライしてみてはいかがでしょうか。
Credit

文/3and garden
ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。
参考文献/
『だれでもわかる病害虫防除対策』監修/草間祐輔 発行/万来舎 発売/エイブル
『植物の病気と害虫 防ぎ方・なおし方』著者/草間祐輔 発行/主婦の友社
新着記事
-
育て方

秋のバラ苗予約スタート! 夏バテバラの回復におすすめのプロ推奨資材&作業ポイントも詳し…PR
今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…
-
ガーデン&ショップ

【スペシャル・イベント】ハロウィン色で秋の庭が花やぐ「横浜イングリッシュガーデン」に…PR
今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、9月13日(土)から「ハロウィン・ディスプレイ」…
-
ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【秋の到来を知らせる9月…
新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストが、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台にスタートし、春の花が次々と咲き始めています。…