えんどう・あきら/30代にメルボルンに駐在し、オーストラリア特有の植物に魅了される。帰国後は、神奈川県の自宅でオーストラリアの植物を中心としたガーデニングに熱中し、100種以上のオージープランツを育てた経験の持ち主。ガーデニングコンテストの受賞歴多数。川崎市緑化センター緑化相談員を8年務める。コンテナガーデン、多肉植物、バラ栽培などの講習会も実施し、園芸文化の普及啓蒙活動をライフワークとする。趣味はバイオリン・ビオラ・ピアノ。著書『庭づくり 困った解決アドバイス Q&A100』(主婦と生活社)、『はじめてのオージープランツ図鑑』(青春出版)。
遠藤 昭 -「あざみ野ガーデンプランニング」ガーデンプロデューサー-
えんどう・あきら/30代にメルボルンに駐在し、オーストラリア特有の植物に魅了される。帰国後は、神奈川県の自宅でオーストラリアの植物を中心としたガーデニングに熱中し、100種以上のオージープランツを育てた経験の持ち主。ガーデニングコンテストの受賞歴多数。川崎市緑化センター緑化相談員を8年務める。コンテナガーデン、多肉植物、バラ栽培などの講習会も実施し、園芸文化の普及啓蒙活動をライフワークとする。趣味はバイオリン・ビオラ・ピアノ。著書『庭づくり 困った解決アドバイス Q&A100』(主婦と生活社)、『はじめてのオージープランツ図鑑』(青春出版)。
遠藤 昭 -「あざみ野ガーデンプランニング」ガーデンプロデューサー-の記事
-
おすすめ植物(その他)

「植物が私の人生を変えた」庭づくり30年の記録と感動のベスト・フラワー22選を一挙公開
我が家のザ・ベスト・フラワー・オブ・ザ・イヤー22年間 私がガーデニングを始めて、気がつけばもう30年になります。この期間に、数えきれないほど多くの植物を育て、その花たちから、たくさんの歓びと感動をもらってきました。「感動の数ほど人生は豊かになる」と言いますが、まさにそのとおりで、植物のおかげで私は幸せな時間を積み重ねてこられたのだと思います。 40代でのオーストラリア、メルボルン駐在から帰国した頃、ふとユーカリをはじめとするオーストラリア原産の植物たちが懐かしくなりました。そこで、種子を個人輸入して育ててみたことが、オージープランツとの本格的な出会いです。趣味だったガーデニングは、気がつけば退職後の仕事となり、プロとしても15年が過ぎました。植物の魅力が、私の人生の流れそのものを変えてしまった──そう言っても過言ではありません。 ガーデニングとほぼ同じ時期に始めたインターネットでの情報発信もかれこれ25年以上、毎朝のルーティンとなっています。そして年末には、毎年「我が家のザ・ベスト・フラワー・オブ・ザ・イヤー」と題し、その年もっとも心を動かしてくれた花を選んできました。 必ずしも“育てるのが簡単だった花”ではありません。その年の庭の主役であり、私に最も大きな感動を与えてくれた植物です。当時まだ日本では珍しかった種類も多く、いま振り返ると、時代の流れや自分自身の関心の変化も映し出しているように思います。 デジタル写真として高解像度の記録が残っているのは2004年以降ですので、今回はその22年間を振り返って、22品種の花を一挙にご紹介します。すでに当サイトの連載記事で紹介した植物もありますので、併せてアーカイブ記事もご覧いただければと思います。 2004年から2014年に育てた11種の植物 さて、ここからはいよいよ、年ごとに「我が家のベスト・フラワー」を振り返っていきたい。写真がしっかり残っている2004年から2025年までの22年間は、私の庭づくりにとっても、日本のガーデニングの変化にとっても、節目がいくつもあった時期だった。 その最初のページを飾るのが、2004年の“ダリア・天涯”。私にとっても忘れられない1年の象徴となった花だった。 2004年 ダリア『天涯』──私のガーデニング人生を押し出した花 見事な大輪花が咲いたダリア‘天涯’。 2004年は、私にとって特別な年だった。浜名湖花博のガーデニングコンテストでグランプリを受賞し、前年の園芸雑誌のコンテストに続いての二冠。副賞としてハワイ、そしてニュージーランドへと旅する機会にも恵まれた。ガーデナーとしての自信と可能性が、一気に広がった時期だった。 その勝負どきの応募写真に使ったのが、超巨大輪ダリア『天涯』だった。当時、ダリアはまだ今ほどブームになる前で、庭で存在感を放つ“勝負花”でもあった。 コンテスト応募に撮影した、ダリアが庭のアクセントになっている2階からの眺め。 超巨大輪ダリアとは、花径30cm以上の迫力あるダリアを指す。私はその規格に挑戦し、何とか30cmの壁を越えようと、肥培管理から支柱の立て方まで、これでもかというほど手をかけた。咲き上がった花は、まさに天にも届くような圧倒的なスケールで、写真に収めた瞬間、思わず息を呑んだことを覚えている。 私の“花の年表”の最初を飾るにふさわしい、力強い一輪だった。 2005年 アガパンサス──メルボルンの記憶を運ぶ花 2005年の主役は、鉢植えで10年以上育ててきたアガパンサス。今でも健在。私がこの花を育て始めたきっかけは、メルボルン時代の通勤の道の記憶だった。中央分離帯いっぱいに咲き誇るアガパンサスが、青空の下で揺れる光景は、今でも鮮明に思い出せる。 ほとんど手をかけなくても、鉢植えでも毎年よく咲く。私にとっては“オーストラリアの風景そのもの”を連れてきた花だ。 2006年 フリンジド・リリー──旅が連れてきた、野生の感動 2006年に咲いたのは、フリンジド・リリー。その2年前、西オーストラリアのワイルドフラワーを巡る旅で、野生のフリンジド・リリーに出会った瞬間の衝撃は忘れられない。 パースのナーセリーで手に入れた種子を播き、2年越しでようやく1株だけ咲いたその姿は、旅の記憶と重なってまさに“感動の再会”だった。当時、日本では入手できない品種だった。 2007年 アマルクリナム──花は思い出を咲かせる この花は「花なかま」というサークルの交換会で譲り受けた株。数年育てての開花は、贈り物を開くような喜びがあった。花にはそれぞれ思い出が宿る。 だから、花はいつも美しいのだと感じる1年だった。その後も毎年、咲いてくれる。この花を見ると、当時のメンバーを思い出す。 2008年 ヘメロカリス──知らない世界を開いた花 2006年、メルボルン・インターナショナル・フラワーショーで出会ったヘメロカリス。当時はこの花を知らず、ヘメロカリスの専門店に並べられた膨大な品種の数に圧倒された。これは育ててみたい、と未知の球根を2つ購入し、2年後に見事に咲いてくれた。 日本でも普及すると感じたが、いまも大きな波は来ていない。しかし、私にとっては“世界の広さを教えてくれた花”だ。 2009年 エキウム──3年越しの塔の花 はじめてエキウムを見たのもオーストラリア。化け物のように大きな塔を立ち上げる姿に驚き、名前も知らず、ただ見惚れと。 2006年にメルボルンで種子を入手し、3年かけてようやく開花。何本か芽生えたうち、最後まで育ったのは1本だけ。その1本が咲いてくれた瞬間は“エキウムの奇跡”だった。 2010年 ストレリチア──庭に咲く極楽鳥という衝撃 ストレリチア(極楽鳥花)は熱帯植物のイメージが強いが、じつは南アフリカ原産で、意外に耐寒性もある。メルボルンの住宅街で、庭に普通に植えられている姿を見たときは、本当に驚いた。 日本では切り花のイメージだったストレリチアが、庭で風に揺れている……。その光景は私の園芸観を揺さぶった。そして横浜の我が家でも開花した。 2011年 ユーカリ──私の人生を変えた木 オーストラリア駐在中に出会ったユーカリは、私の人生を変えた植物だと思う。広い庭で週末にBBQを楽しむ豊かなライフスタイル。その象徴のような存在だったユーカリ。 帰国後、日本では入手できなかったので、ピンクの花の咲くユーカリの種子を海外から取り寄せて4年後にやっと開花。たくさん咲くようになったのは、ちょうど私が定年退職しプロのガーデナーになった頃だった。このユーカリは、いつも“原点”を思い出させてくれる。 2012年 ボトルブラシ(ピンクシャンペーン)──鳥を呼ぶ花木 ピンクのボトルブラシは、5月・7月・9月・11月と、ほぼ年に4回咲く働き者。オーストラリアでは“鳥を呼ぶ木”としてお馴染みで、我が家でもメジロが蜜を吸いに来る。 花木と小鳥の組み合わせは、オーストラリアの庭の原風景。それを日本の庭でも楽しめることが嬉しかった1年だ。 2013年 ピメレア・スペクタビリス──青白い光を放つ花 西オーストラリアのワイルドフラワーの旅で見た花が、日本でも流通するようになった。低木で、青みがかった葉と繊細な花姿が印象的。日本では春に咲き、独特の透明感がある。 この年は「オージープランツの奥深さ」を再認識した年だった。 2014年 プチロータス──風に揺れる羽毛の花 プチロータス・ジョーイは、ふわふわとした羽毛のような穂を立ち上げる、西オーストラリア原産の多年草。種子は国内でも入手出来て、種子からたくさんの株が育った。 乾燥に強く、銀緑色の葉とピンクの花が風に揺れる姿は、砂漠の中の光を思わせた。庭に育っているだけで、オーストラリアの空気が流れ込むような花である。 2015年から2025年に育てた11種の植物 2015年 アガベ「白糸の滝」──15年目の奇跡 ついに咲いた、15年育てたアガベ「白糸の滝」。父の日に妻から贈られた小さな苗が、こんなにも大きく育ち、ついに開花した。 アガベは“命を懸けて咲く花”。リューゼツランの仲間は花後に枯れる。花弁だと思っていた黄色は、実は雄しべ。花を初めて見たときは、鳥肌が立つほど感動した。 2016年 キンギアナム──20年育てた株の誇り 桜と同じ頃、満開を迎えるキンギアナム。20年以上育てて大株になり、毎年見事な花を見せてくれる。 2004年に訪れた西オーストラリアで野生蘭を見て以来、この花には特に思い入れがある。旅が、今の私の園芸を形づくっていることを実感した年だった。 2017年 ピメレア(Qualap Bell)──繊細さの極致 ピメレア・フィソデスの可憐さは、オージープランツの中でも群を抜く。重なり合う苞が鐘のように見え、その色合いは複雑で奥深い。 育てるのは難しいが、咲いたときの喜びは格別だった。 2018年 アガベ・ベネズエラ──命を懸けた開花 知人からいただき、10年育てた株が突然のつぼみ出現。百年に一度咲くと言われる、センチュリープランツ。 アガベは開花すると枯れる“命の花”。 家で観賞するだけではもったいないと、勤務先の植物園に展示したところ新聞にも紹介された。多くの人に見てもらえたことも嬉しかった。 2019年 ブラック・キャット──ようやく咲いた黒い猫 地下に肥大した地下茎をつくるタロイモ科の多年草で、黒花が魅力のブラック・キャット(Tacca chantrieri)。 数年育てて、株分けで増えても、なかなか咲かず苦労したが、植物園の温室で越冬させたところ、ついに開花した。 この花は“温度がすべて”だと実感した年だった。 2020年 プルメリア──娘の結婚式の思い出とともに このプルメリアは、2009年に娘のハワイ挙式で買った挿し木用の枝が“原点”。それを子株にして育てて、5年目にようやく咲いた。 親株は枯れてしまったが、この花が咲くと、あの日の青空が蘇る。コロナ禍のステイホームの憂鬱を吹き飛ばしてくれた。 2021年 ダーウィニア・タキシフォリア──静かな気品と情熱 この年もコロナ禍で、ガーデニングがちょっとしたブームだった。華やかさはないが、見るほど味わいが深まるダーウィニア。 細い葉と控えめな花が、オーストラリアの乾いた空気を思い出させる。“派手さよりも趣”。園芸観がまた一歩成熟した年だった。 2022年 バンクシア・バースディキャンドル──刹那の憧れ 憧れ続けたバンクシア。基本的に、「ザ・ベスト・フラワー・オブ・ザ・イヤー」は、自分で育てて開花させた花から選ぶと決めていたが、この年だけは、開花株を“自分へのご褒美”として購入した。 しかし一年で枯れてしまった……。刹那の輝きだったが、憧れは確かに手の中にあった。 2023年 黒法師──花の合間から顔を出す“新発見” 黒法師は長年、育てていたが、黒法師の花が初めて咲いた年。驚いたのは、花後に花の間から小さな“赤ちゃん株”がいくつも顔を出していたこと。 長年園芸をしていても、まだまだ初めて見る現象がある。これこそが園芸の醍醐味だ。 2024年 ハーデンベルギア──春を告げる古い友人 30年ともに歩んできたのが、つる植物のハーデンベルギア。我が家のAlex’s Garden の春は、アカシアと、この花が告げる。 小さな花が集まって生み出す鮮やかさは、毎年見ても飽きない。長年の間に、我が家の雨どいや、アーチに絡み、なかなかの貫禄。 2025年 ジャカランダ──4株目の執念が咲かせた青い花 25年以上ジャカランダを育てて、幾度も失敗。18年育てた大木が咲かずに枯れたこともある。 そしてこの4株目。接ぎ木苗を地植えし、寒冷紗で冬越しを工夫し、ようやく5年目に、見事に開花した。植物にも気持ちは通じる——そう思わせてくれた年だった。 人生の深みを教えてくれるガーデニング 振り返れば、ガーデニングを始めてからの30年余り、私はいつも「花とともに」生きてきたように思います。四季の移ろい、咲いては散る花々の姿に、その年その時の自分の暮らしや感情が重なり、庭は私にとって人生そのものの写し絵のようです。メルボルンの道路脇で見たアガパンサス、乾いた大地に強く咲くワイルドフラワー、広い空の下で揺れるユーカリの銀葉──。 海外で出会った植物たちは、私のガーデニング観を大きく変え、人生の針路までもそっと押し出してくれました。 花は、育てる者の努力や知識だけでは咲いてくれません。「気まぐれ」と言ってしまえばそれまでですが、むしろ私は、花には“意思”のようなものがあると感じています。 その意思と向き合い、ときに失敗し、ときに長い年月をかけてようやく一輪が咲く──そんな体験の積み重ねこそが、園芸の醍醐味であり、人生の深みを教えてくれました。 この回想録に綴った花々は、どれも一つとして同じものはなく、咲いた背景や心に宿した記憶も異なります。けれど、いずれの花も私にとって「その年の自分の姿」を映し出す宝物でした。 これからも、未来をイメージして庭に種子をまき、水をやり、新しい花と出会い、新しい驚きと感動を受け取る日々が続いていくことでしょう。年齢を重ねるほどに、庭の時間はゆっくりと、しかし確かな喜びとして胸に刻まれていきます。 2026年、みなさんはどんな花を咲かせるでしょう。新年も楽しみですね。 長い文章にお付き合いくださった読者の皆さま、そして30年もの間、私を支えつづけてくれた数えきれない花たちに、心から感謝を込めて。
-
おすすめ植物(その他)
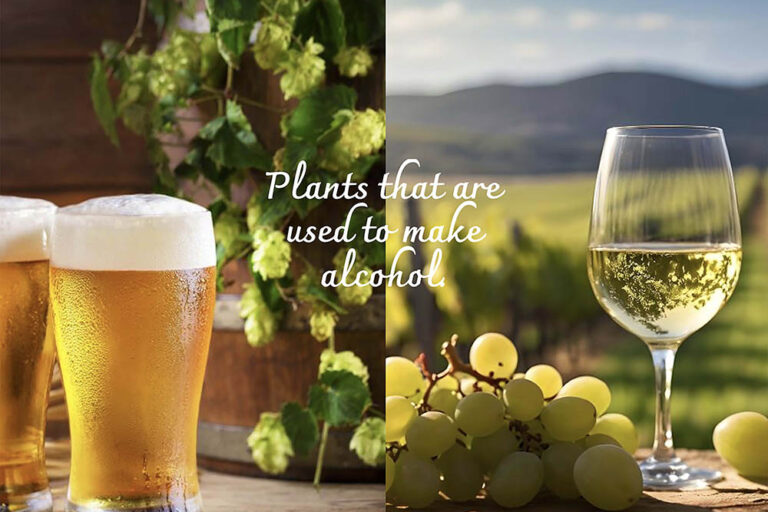
お酒の原料は全部“植物”? ビール・日本酒・ワインなどを生む8種の植物の秘密
お酒の原料1…大麦― ビール・ウイスキー・麦焼酎のベースになる穀物 allstars/Shutterstock.com ビールやウイスキー、そして麦焼酎は麦からつくられることは誰もが知っていますが、さて、それはパンやケーキを作る小麦粉の原料と同じものでしょうか? 結論からいえば、そうではありません。小麦粉の原料は小麦ですが、ビールやウイスキー、麦焼酎などをつくるのは、「大麦」で、その中でも「二条大麦」という種類が原料となっています。 左が大麦、右が小麦。Jenya Smyk、artifex.orlova/Shutterstock.com 大麦と小麦は、どちらもイネ科の穀物で「麦」の仲間ですが、大麦はイネ科オオムギ属、小麦はイネ科コムギ属と分類から異なり、さまざまな点で違いがあります。 以下に、大麦と小麦の違いを比べてみましょう。 左が大麦、右が小麦。kungfu01、maxbelchenko/Shutterstock.com 大麦小麦外観穂の形:穂が長く、芒(のぎ)と呼ばれる針のような突起が目立つ。粒の形:粒が丸みを帯び、粒の中央の溝(腹溝)がはっきりしている。穂の形:穂が短く、芒も短いか、またはない。粒の形:粒が細長く、粒の中央の溝(腹溝)は浅め。成分タンパク質:グルテン(タンパク質)含有量が少ない。食物繊維:小麦よりも食物繊維を多く含む。タンパク質:グルテン(タンパク質)を多く含む。食物繊維:大麦よりも食物繊維は少ない。用途麦ごはん、麦茶、ウイスキー、ビール、焼酎、味噌、醤油などの原料として利用。パン、麺類、お菓子などの原料として利用。食感麦ごはんにすると、プチプチとした食感。パンや麺類にすると、もちもちとした食感。栄養価食物繊維が豊富で、血糖値の上昇を抑える効果がある。タンパク質が豊富で、筋肉や体の組織を作るのに役立つ。栽培方法比較的寒さに強い。温暖な気候を好む。種類二条大麦と六条大麦がある。硬質小麦と軟質小麦がある。 続いて、ビール・ウイスキー・麦・焼酎などの原料として使われることが多い二条大麦の特徴を見てみましょう。 <二条大麦の特徴> 粒が大きい:六条大麦に比べて粒が大きく、デンプン含有量が多い。 発芽しやすい:発芽が均一に進みやすく、麦芽製造に適しています。 酵素力価が高い:酵素を多く生成するため、糖化やアルコール発酵を効率的に行えます。 これらの特徴から、二条大麦はビール・ウイゥキー・麦・焼酎などの醸造に適しているとされています。 ビール・ウイスキー・麦焼酎の違いを生む製造工程 AntAlexStudio、jazz3311、evgeeenius/Shutterstock.com ビール・ウイスキー・麦焼酎は、同じ大麦が主原料。しかしながら、製造工程が大きく異なるため、それぞれ全く異なる風味を持つお酒になります。ただし、ビールにはホップが加わることも風味の違いの大きな要因になります。 この3つのお酒に共通する最初の工程が、麦芽づくり。原料として最も重要な大麦麦芽は、大麦を水に浸して発芽させ、乾燥させたものです。この過程で、大麦に含まれるデンプンを糖に変える酵素がつくられます。この麦芽が、ウイスキーやビールでよく耳にするモルトです。 工程ビールウイスキー麦焼酎① 麦芽づくり大麦を発芽・乾燥させて、糖化酵素を含む麦芽(モルト)をつくる。② 糖化・麦芽を粉砕し、温水と混ぜて麦汁をつくる。麦芽に含まれる酵素がデンプンを糖に分解。・主に麦汁を煮沸する工程でホップを添加。麦芽を粉砕し、温水と混ぜて麦汁をつくる。麦芽に含まれる酵素がデンプンを糖に分解。蒸した麦に麹菌を繁殖させ、麹菌がデンプンを糖に分解。③ 発酵麦汁に酵母を加えて発酵。麦麹に酵母を加えて発酵。④ 蒸留行わない。発酵液を蒸留してアルコール度数を高める。⑤ 熟成貯蔵タンクで熟成。樽で熟成。貯蔵タンクや甕で熟成。⑥ 製品化ろ過 → 瓶詰または缶詰。ろ過・加水 → 瓶詰。 <製造工程の主な違い> 糖化方法: ビールとウイスキーは麦芽の酵素を利用しますが、麦焼酎は麹菌の酵素を利用します。 蒸留: ビールは蒸留を行いませんが、ウイスキーと麦焼酎は蒸留を行います。 熟成: ビールは貯蔵タンクで熟成させますが、ウイスキーは樽で熟成させ、麦焼酎は貯蔵タンクや甕で熟成させます。 これらの製造工程の違いにより、ビール・ウイスキー・麦焼酎はそれぞれ異なる風味を持つお酒になります。 豆知識:「whisky」と「whiskey」の違いとは Kyle J Little/Shutterstock.com ウイスキーのスペル「whisky」と「whiskey」の違いは、主に産地による慣習的なものです。 whisky: スコッチウイスキー、カナディアンウイスキー、日本のウイスキーなどで使われることが多いです。 whiskey: アイリッシュウイスキーやアメリカンウイスキー(バーボンウイスキーなど)で使われることが多いです。 大麦の産地と育て方 Iv-olga/Shutterstock.com 大麦は世界中で栽培されており、その産地は多岐にわたります。主な産地は、ロシア、ウクライナ、オーストラリア、ドイツ、トルコ、カナダなど。日本国内では、愛媛県、香川県、大分県などの瀬戸内海周辺地域や九州北部で主に栽培されています。 大麦の育て方は、品種や栽培地域によって異なりますが、基本的な手順は次のとおりです。 1. 品種選び 大麦には二条大麦と六条大麦の2種類がありますが、ビール・ウイスキー・麦焼酎には二条大麦が多く使用されます。 2. 種まき 秋まきと春まきがあります。 秋まきは9月下旬~10月上旬。 春まきは3月下旬~4月上旬。 種まき前に、畑を耕し、肥料を施しておきましょう。 3. 栽培管理 発芽後は、適切な間隔になるよう間引きを行います。 雑草が生えてきたらこまめに除草を。 追肥は生育状況に合わせて行います。 病害虫が発生したら、早めに対処しましょう。 4. 収穫 収穫時期は、一般には5月下旬~6月上旬です。品種や栽培地域によって異なります。 穂が黄色く色づいたら、収穫のサインです。 収穫後は、乾燥させて保存しましょう。 その他 大麦は連作障害を起こしやすいので、同じ場所での栽培は避けましょう。 日当たり・水はけのよい場所を好みます。 大麦は比較的育てやすい作物ですが、病害虫には注意が必要です。 branislavpudar/Shutterstock.com それぞれのお酒の製造に使われる大麦の品種は、その風味や特性に大きく影響するため、各醸造所はこだわりを持って慎重に選んでいます。品種を組み合わせたり、独自の栽培方法を採用したりすることで、数々の個性的なお酒が生み出されています。 お酒の原料2…米―日本酒・米焼酎・泡盛をつくる穀物 ABCDstock/Shutterstock.com 米からつくられるお酒といえば、日本酒が代表的ですが、米焼酎や泡盛なども米を原料としています。 日本酒の主な原料には、特に酒米と呼ばれる品種が用いられます。酒米は、デンプン含有量が多く、タンパク質含有量が少ないことが特徴。代表的な酒米の品種は、山田錦、五百万石、美山錦などが挙げられます。 Watthana Tirahimonchan/Shutterstock.com 日本酒づくりは、大まかな工程は下記のとおりです。 工程内容目的・ポイント① 原料米の準備精米:玄米を磨き、糠を取り除く。・タンパク質・脂肪を除き、雑味を減らす。洗米・浸漬:精米した米を洗い、浸水。・ムラができないよう米全体に吸水させる。蒸米:洗米後の米を蒸す。・麹づくりや仕込みに使う蒸米を準備。② 麹づくり蒸米に麹菌を繁殖させ、「麹」をつくる。・麹菌の酵素がデンプンを糖に変える。・日本酒の風味や味わいを大きく左右する重要工程。③ 酒母づくり蒸米・麹・水・酵母を混ぜ、「酒母(しゅぼ)」をつくる。・「酒母」は優れた酵母を大量に培養したもので、糖を分解してアルコールを生み出す。・健康な酵母を育み、日本酒の発酵の源となる重要要素。④ 仕込み蒸米・麹・酒母を3回に分けて加える(三段仕込み)。・酵母の活性を高め、安定した発酵を促進。仕込みタンク内で発酵が進む。・酵母が糖分をアルコールと炭酸ガスに分解。⑤ 搾り・濾過発酵後のもろみを搾り、酒と酒粕に分ける。必要に応じて濾過を行う。・透明度・味を調整。⑥ 火入れ・貯蔵搾った酒を加熱殺菌(火入れ)。・微生物を殺菌して品質を安定化。種類によって、火入れ後一定期間貯蔵タンクで熟成。・熟成で味をまろやかに。⑦ 割水・瓶詰め必要に応じて水を加え(割水)、アルコール度数を調整。・飲みやすい度数(約15%前後)に調整。瓶詰めして出荷。 オーナメンタルグラスを取り入れた庭。Chiyacat/Shutterstock.com ガーデンではなかなか登場しないイネですが、イネ科の植物は庭を彩るオーナメンタルグラスとしても美しいものが多いですね。インテリアとしてガラス容器などに入れて水耕栽培すると、根の成長も楽しめます。 インテリアとして楽しむグラス類(左)とイネの花(右)。studio_24、tamu1500/Shutterstock.com お酒の原料3…トウモロコシ― バーボンウイスキーのベースになる穀物 baona/Shutterstock.com トウモロコシは、じつは麦や米よりも世界的な生産量が多い穀物です。日本では野菜として扱われることが多いですが、全世界で主食のほか飼料や工業用にも使用されている、世界三大穀物の1つです。そして、このトウモロコシは、バーボンウイスキーの最も重要な原料でもあります。 Rullexio Studio/Shutterstock.com アメリカ合衆国の法律では、バーボンウイスキーの原料の51%以上がトウモロコシでなければならないと定められています。とはいえ原料となる植物はトウモロコシだけでなく、通常トウモロコシに加えて、ライ麦、小麦、大麦麦芽なども使用されます。これらの穀物の配合によって、バーボンウイスキーの風味は大きく変化します。 また、バーボンウイスキーの製造には、良質な水が不可欠。ケンタッキー州の石灰岩で濾過された水は、バーボンウイスキーづくりに最適な水として知られています。 原料を糖化、発酵させて蒸留し、内側を焦がしたオークの新樽で熟成させることで、バーボンウイスキー特有の風味と色が生まれます。 ElenaVah/Shutterstock.com お酒の原料4…ホップ― ビールに独特の風味や泡もちを与えるつる植物 ホップの花。PanSvitlyna/Shutterstock.com ビールの原料として欠かせないのが、ホップです。ホップはアサ科のつる性植物で、ビールづくりには雌株の花(毬花)を使用します。 ビール製造におけるホップの役割は多岐に渡り、ビールに独特の風味や香り、苦味を与える上で非常に重要な役割を果たしています。またホップに含まれる成分がビールの泡立ちをよくし、泡もちを向上させるほか、抗菌作用によりビールの腐敗を防ぐ効果もあります。 ホップは主に麦汁を煮沸する工程で添加され、ホップの種類によって、ビールの風味は大きく変わります。 ホップの産地と育て方 ドイツのホップ畑。Wolfgang Hauke/Shutterstock.com ホップはビールの原料として欠かせない植物で、世界中で栽培されています。日本では東北地方を中心にホップ栽培が行われ、岩手県、秋田県、山形県などが主な産地です。 比較的冷涼な気候を好み、日当たり・水はけのよい場所で栽培する必要があります。ホップの基本的な育て方は下記のとおりです。 1.植え付け 植え付け適期は3月下旬~4月上旬。 苗は間隔をあけて植え付けます。 ホップはつる性の植物なので、支柱やネットなどを用意しましょう。 2.栽培管理 日当たり・水はけのよい場所で栽培します。 乾燥に弱いので、土壌が乾いたらたっぷりと水を与えましょう。 肥料は生育状況に合わせて与えます。 病害虫が発生したら、早めに対処しましょう。 3.収穫 収穫時期は8月下旬~9月上旬。 毬花(ホップの実)が十分に成長し、黄色く色づいたら収穫のサインです。 収穫後は、乾燥させて保存します。 お酒の原料5…ジュニパーベリー―ジンの核となる風味を与える針葉樹 doroninanatalie4/Shutterstock.com ジュニパーベリーという名前には、あまり聞き覚えがないかもしれません。これは、カクテルのベースなどとしても親しまれているジンに欠かせない原料です。 セイヨウネズ。l.glz.ttlphotos/Shutterstock.com ジンは、その独特な風味で知られる蒸留酒ですが、針葉樹であるセイヨウネズ(Juniperus communis)の果実ジュニパーベリーが、その風味の源。ジンの風味の核となる成分であるピネンやその他の精油成分を豊富に含むこの実によって、特有の爽やかな風味が生まれます。 豆知識:ジンの香りは松ぼっくり由来 ブルーベリーに似た深い紫色のジュニパーベリーは、一見ベリー類のような見た目をしていますが、じつは松ぼっくりと同じ球果。鱗片が木質化せず多肉質になるという特徴があります。 5PH/Shutterstock.com ジンは、ジュニパーベリー以外にもさまざまな植物由来の原料(ボタニカル)を使って香り付けされます。 代表的なボタニカルとして挙げられるのは、コリアンダーシード、アンジェリカルート、オリスルート、レモンピール、オレンジピールなど。そのほかにも、カルダモン、シナモン、ナツメグ、ショウガなど、多種多様なボタニカルが使用されます。 これらのボタニカルの組み合わせや配合割合によって、ジンの風味は大きく変化します。 お酒の原料6…サトウキビ―黒糖酒・ラム酒・黒糖焼酎などをつくるイネ科の植物 Photoongraphy/Shutterstock.com サトウキビから絞った汁をそのまま煮詰めて作る黒糖。サトウキビはイネ科の多年草で、温暖な気候で育つため、日本では主に沖縄県や鹿児島県の南西諸島で生産されています。黒糖は、精製された白砂糖に比べてサトウキビ由来のミネラルやビタミンが多く残り、豊かな風味があります。そんな黒糖を原料としたお酒には黒糖酒、ラム酒、黒糖焼酎があります。 ○黒糖酒 黒糖酒の製法は、大きく分けて以下の2つの方法がありますが、ラム酒との違いは「米麹の有無」です。 1.黒糖を原料とした蒸留酒 黒糖を水で溶かし、酵母を加えて発酵させます。 発酵した液体を蒸留して、アルコール度数の高い蒸留酒をつくります。 蒸留タイプの黒糖酒は、ラム酒に似た風味を持つことがあります。 2.黒糖を原料とした醸造酒 黒糖を水で溶かし、酵母を加えて発酵させます。 発酵した液体を蒸留して、アルコール度数の高い蒸留酒をつくります。 蒸留タイプの黒糖酒は、ラム酒に似た風味を持つことがあります。 ラム酒 サトウキビの搾り汁や糖蜜を原料とした蒸留酒ですが、黒糖を原料としたラム酒もあります。 カクテルや料理に使われることが多いです。 黒糖焼酎 黒糖を原料とした日本の蒸留酒です。 鹿児島県の奄美群島でのみ製造が認められています。 ロックや水割りで飲むのが一般的です。 Marian Weyo/Shutterstock.com お酒の原料7…ブドウ―古代から愛飲されるワインをつくるつる性果物 シャルドネの実。Chiyacat/Shutterstock.com 世界で最も多くの地域で飲まれているお酒の1つ、ワイン。その原料となるのは、言わずと知れたブドウです。日本語で「葡萄酒」ともいわれるとおり、ブドウ果汁を発酵させた醸造酒で、白ワインも赤ワインも、それぞれに使われるブドウの品種は非常に多種多様ですが、ここでは代表的な品種4種と、その特徴について簡単にご紹介します。 ソーヴィニヨン・ブランの畑。Shch/Shutterstock.com 1. シャルドネ(Chardonnay) 特徴:白ワインの王様とも呼ばれる品種で、世界中で栽培されています。中立的な味わいで、栽培地や醸造方法によってさまざまなスタイルに変化します。 味わい:冷涼な地域: リンゴや柑橘系の爽やかな酸味とミネラル感温暖な地域: トロピカルフルーツや蜂蜜のような豊かな風味 2. ソーヴィニヨン・ブラン(Sauvignon Blanc) 特徴:シャルドネと並ぶ人気品種で、ハーブや柑橘系の香りが特徴です。 味わい:冷涼な地域: グレープフルーツやハーブの爽やかな香り温暖な地域: パッションフルーツやグーズベリーのような甘酸っぱい香り カベルネ・ソーヴィニヨン。barmalini/Shutterstock.com 3. カベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon) 特徴:赤ワインの王様とも呼ばれる品種で、世界中で栽培されています。タンニンが豊富で、力強く、長期熟成に向いています。 味わい:カシスやブラックベリーのような黒系果実の香りが特徴 3. シラー(Syrah) 特徴:南フランスやオーストラリアのワインなどに多く見られ、小粒で果皮が厚いのが特徴。タンニンが豊富で、長期熟成に向いています。 味わい:ブラックベリーやスミレなどの香りに黒コショウのようなスパイシーさが特徴 オーストラリアではシラーズと呼ばれるシラーの畑。Claudine Van Massenhove/Shutterstock.com お酒の原料8…アガベ―世界で親しまれるメキシコの地酒テキーラをつくる多肉植物 Igor Normann/Shutterstock.com テキーラは、メキシコを代表する蒸留酒で、その独特な風味と歴史から世界中で愛されています。俗に「サボテンからつくられる」などといわれることがありますが、正確にはアガベ(リュウゼツラン)からつくられるお酒です。飲み方としては、ストレートで、岩塩とライムを添えるスタイルが有名。ただし、テキーラはアルコール度数が高いため、飲みすぎには注意が必要です。 German Zuazo Mendoza/Shutterstock.com 豆知識:テキーラに利用されるアガベの品種 テキーラを名乗るためには、 メキシコ国内のハリスコ州とその周辺の指定された地域で栽培された、アガベ・テキラナ・ウェーバー・ブルー(Agave tequilana Weber var. azul)という特定のアガベ植物を原料としていること。 メキシコの公式規格(NOM)に沿って製造されていること。 アルコール度数が35~55%であること。 が条件となっています。 多肉植物とアガベを合わせたロックガーデン。Parilov/Shutterstock.com アガベの仲間は、近年注目が集まっているガーデンプランツ。ドライガーデンにも向き、耐寒性の高い品種を選べば地植えでもローメンテナンスで栽培できるため、大株に育ててシンボリックに植栽されている光景も見ることができます。 8種のアルコール飲料の原料となる植物をご紹介してきましたが、いかがでしたか? 今日の1杯を味わうときは、ぜひ「どんな植物から生まれたのか」を思い浮かべてみてください。きっと、また違った味わいの美味しい“1杯”が楽しめるはずです。酒は百薬の長といわれますが、まあ、ほどほどに楽しみましょうね。
-
おすすめ植物(その他)

【収穫の喜びも!】子どもと孫と一緒に楽しむガーデニング「家族の思い出を作る植物」7選
子どもとガーデニングの趣味を共有してみよう! 私がガーデニングを始めて今年で30年。 ガーデニングが流行して「流行語大賞」に“ガーデニング”という言葉がエントリーしたのが1997年で、早29年。29年といえば、ほぼ一世代が入れ替わる年数ですね。当時、ガーデニングブームを牽引していた世代の多くは、今還暦を超え、孫のいる世代になっているはず。僕自身もその世代で、自分がガーデニングに興味を持った頃は、子どもと共通の趣味を持ち、一緒に楽しみたいという願望がありました。しかし、その頃は自分も仕事が忙しく、子どもたちは塾通いの年齢で、それどころではなかったのです。 オーストラリアに駐在した経験から、帰国後多くのオージープランツ(オーストラリア原産の植物)を育てることに夢中だった。 今、自分が孫を持つ年齢になり、自分自身の子育てでは叶わなかった“子どもとのガーデニングの趣味”の共有が、孫とならできそうな気がして、孫が我が家に来たときには実際に実践しています。そこで今回は、小さなお子さんやお孫さんが喜ぶとともに、大人にとっても楽しめる植物をセレクトしてご紹介します。 大人も子どもも喜ぶ“珍しくて可愛い植物”おすすめ7選 おすすめ1 ミッキーマウスの木 ご覧のとおり、実のフォルムがミッキーマウスに似ているところから、この名前がついています。写真を見ると、なるほど! と思いますね。僕が初めて出会ったのは、かつて相談員として勤務していた植物園の温室でしたが、来園する子どもたちに説明すると、目をキラキラ輝かせて喜んでいました。植物にキャラクターの名前が付くのは珍しいことですね。 これは、たまたま東欧のチェコを旅行していて、レドニツェ城の温室で撮影した写真です。 「ミッキーマウスの木」と呼ぶのは日本だけかと思っていたのですが、チェコで出会い、この国でも「Micky mouse tree」の名に驚き、感動しました。 もともと、南アフリカのオクナ科という、あまり日本では親しみのない科の植物ですが、近年「ミッキーマウスの木」として急に知られるようになり、通販サイトでも苗が買えるようになりました。ミッキーさんが実るなんて、夢いっぱいですね。 鉢でも育てやすい低木で、樹高が1~2mとされていますが、現地では6mに達することもあるようです。耐寒温度が日本では10℃程度とされていましたが、近年は暖地なら露地で越冬するという説もあります。まだデータが少ないので断言はできませんが、南アフリカ原産で、オーストラリアやニュージーランドでも改良品種が栽培・販売されていますから、オージープランツ並みに、もう少し寒くても越冬できそうな気がします。 南アフリカでは9~11月(つまり春)に開花し、日本の温室でも1月に開花。2~3月には、ミッキーマウスに似た赤と黒の実が楽しめます(写真は1月に温室で撮影)。 花弁は5枚で、いい香りがします。 温室でない場合には、開花は3月頃からで、実が黒くなるのは6月頃からです。比較的長期間、次々と咲き続けます。 温室栽培の2月末の状態です。花と実が両方見られます。 2月の内は、実がまだ緑色ですが、だんだんと黒く色づきます。開花から3カ月間、観察を楽しめるので、子どもへの花育にも適しているのではないでしょうか。 和名:ミッキーマウスノキ学名:Ochna serrulataその他の名前:ミッキーマウスツリー、オクナ・セルラタ英名:mall-leaved plane, carnival ochna, bird's eye bush, Mickey mouse plant or Mickey Mouse bush科名 / 属名:オクナ科 / オクナ属原産地:南アフリカ この写真では、実の1つはまだ緑色ですね。これがほかの実のように次第に黒く色づきます。 たくさん咲くと賑やかで楽しい雰囲気です。 【育て方】 基本的に鉢植えで育てます。4月頃からは屋外の日当たりのよい場所で育てます。一般の鉢物同様に夏の直射日光や西日は避け、真夏は半日陰で風通しのよい場所での栽培が適しています。土の表面が乾いたら、たっぷり水やりをします。日当たりが悪いと開花しにくくなるので注意しましょう。11月頃からは、屋内の日当たりのよい場所に移します。屋内で育てる場合の注意として、ガラスの窓際や暖房器具の近くなど、温度変化の多い場所は避けます。 次に、子どもや孫が喜ぶ植物は、実のなる果樹です。トマトやキュウリなども喜ばれますが、果樹のほうが、収穫の歓びを感じるようです。余談ですが、ガーデニングに興味を示さないご主人やお子さんに庭に目を向けさせるには、私の長い経験上、ブルーベリー、レモン、ミカンなどの果樹はとても効果的です。子どもも男性も、果物が好きなようです。そして果物の最大の魅力は、「ブルーベリーが実ったから、ブルーベリー狩りに来ない?」あるいは「ミカン狩りに来ない?」と誘う「強力なネタ」になるのです。 おすすめ2 ブルーベリー 果物の中でも特に、背の低い子どもが手軽に摘んで親しめるブルーベリーがおすすめNo.1です。1粒が小さい点でも、小さなお子さんには摘みやすいです。また、ブルーベリーは鉢植えでも育てられるので、手軽に始められるのも魅力です。 そして、果実を楽しむのはもちろんですが、5月に咲く鈴のような白い花も愛らしく、秋の紅葉も楽しめます。 【育て方】 3つの大切なポイントは 酸性土を好む 2株以上植えると受粉しやすい 日当たりのよい場所で育てる ことです。 多くの植物は、pH5.5〜6.5の用土で育ちますが、ブルーベリーの場合、酸性の用土を好むのでpH5.0が最適とされています。ですので、お手持ちの培養土にピートモスを混ぜて調整するか、ブルーベリー専用の土を利用すると失敗がありません。 今年購入して実が色づき始めた「ティフブルー」。 そして、苗を購入する際に覚えておくとよいのが、系統です。 ブルーベリーには、大きく分けると3つの系統があります。ラビットアイ系、ハイブッシュ系、サザンブッシュ系ですが、同じ系統の中から異なる2品種を選ぶと実つきがよいです。 初心者の方におすすめなのは、育てやすく実つきがよいとされるラビットアイ系の組み合わせ。ラビットアイ系のおすすめの組み合わせは、「ティフブルー」と「パウダーブルー」で、どちらも育てやすく、収穫量も多い品種です。 採取してすぐ新鮮な果実を食べられるのもブルーベリーの魅力。 枝ぶりが華奢で扱いやすいので、鉢植えにしてマンションのベランダでも育てることができます。鉢増し(1回り大きい鉢に植え替えること)は1~2年に1度、2月頃に行います。肥料は3月と9月に施します。 おすすめ3 レモン この20年ほどで、レモンが家庭の庭木としてすっかり定着しましたが、レモンの“お洒落感”は小さな子どもでも分かるようで、ミカンの栽培より楽しいようです。 何より、採りたてのレモンは、紅茶蜂蜜レモン、レモンスカッシュ、レモンソルト、そしてレモン胡椒など、さまざまな料理やお菓子にも使用できて、とても重宝するうえ、豊かさを運んでくれる果樹です。その喜びを、ぜひ子どもやお孫さんと共有してください。 苗木は、年中見つかりますが、秋から年内に数個ほど実のなっている10号鉢程度の苗を購入して育て始めれば、数年で大量に収穫できます。我が家では、毎年100個ほど収穫して20年以上になります。そして子どもや孫が成長しても「思い出」のレモンの木は寿命が長いので、次の世代も楽しめるというのも大きな魅力です。 おすすめ4 ミカン 最も親しみのある果物で、柑橘類は本当に種類が多いですね。我が家で育てているのは、「温州ミカン」。私の果樹栽培歴25年間に、柿、桃、梅、梨、巨峰など、いろいろ挑戦してきましたが、木が大きくなりすぎたり、虫がついたり、病気になったり……。そのなかでも、ほぼ放っておいても毎年確実に収穫できているのが、レモンとミカンなのです。 比較的低い所に実るので、子どもも直にもぎ取る体験が自宅でできます。一度経験したら忘れられないのか、孫は毎年ミカンの収穫時期になると遊びにくる恒例行事となっています。 ここまで花木と果樹を紹介してきましたが、もっと簡単に、手軽に、短い期間で育てることができ、学べるのが草花です。 草花のなかで小さな子どもに人気なのは、やはり学校の教材で扱う、ヒマワリ、アサガオ、チューリップの3種が圧倒的です。学校で育てたり学んだりする前に、自宅で栽培を経験しておけば得意科目になります。 おすすめ5 ヒマワリ 学校花壇の代表ですね。誰にもヒマワリを育てた思い出はあるのではないでしょうか? 大人にとっても、元気の出る花ですね。そして、ある世代の人々には、映画の『ひまわり』が思い出かもしれません。ヒマワリといえども最近は進化していて、大きな花からコンパクトな品種、シックな花色などバリエーションが豊富で、大人も栽培を楽しめます。 おすすめ6 アサガオ アサガオも、学校の夏の教材や宿題の定番ですね。種まきから発芽、つるが伸び、花が咲き、種子ができるまでの植物の一生を短期間で観察できるという、花育にぴったりの植物です。また、プランターで育てられるので、栽培が手軽に始められるという点や、早朝に鮮やかな花が咲くことは、家族でも話題にしやすいという利点がいっぱいです。 雨樋を伝って2階まで伸びて咲くアサガオ。 大人は子どもの頃の記憶をたどりながら、改めて家族でアサガオを育ててみるのはいかがでしょうか。 おすすめ7 チューリップ チューリップほど、小さなお子さんから大人まで、咲いたときの喜びを得られる、バラエティ豊かな植物はほかにはないのではないでしょうか? 私自身、幼稚園生の頃、母と初めて植えた球根がチューリップだった記憶があります。「咲いた、咲いた、チューリップの花が♪」 庭に咲いた花を部屋に飾るのも贅沢な楽しみです。 小さい時の思い出は、いつか蘇り、大人になって、チューリップの球根を「大人買い」して、思う存分、育てたことがあります。それはそれは楽しい体験でした。 大人買いしたチューリップ栽培のレポートは、下記の記事をぜひご覧ください。 庭で過ごした家族との思い出が未来につながる 子どもや孫と一緒に育ててみたい種類は見つかりましたか? 今回は7種をご紹介しましたが、決して子どもや孫とだけではなく、どれもどんな世代が育てても楽しい思い出ができる魅力的な植物です。子どもの頃に植物と触れ合う喜びを感じた体験は、きっと大人になって、いつか記憶が蘇り、植物に触れ合う豊かな人生へと導いてくれるでしょう。実体験した私が保証します。
-
おすすめ植物(その他)

狭い庭を有効活用! ベテラン園芸家が語る【つる性植物】の魅力と落とし穴
バリエーション豊かなつる植物 夏の定番つる植物といえば、アサガオ。irina_raduga/Shutterstock.com 一口に「つる性植物」といっても、じつにたくさんの植物がある。美しい花で人気のつるバラやクレマチスに始まり、ノウゼンカズラ、藤などの花木類から、アサガオ、ゴーヤなどの一年草、さらにはクズ、ヘクソカズラなどの厄介な雑草まであり、数えきれない。そんな多彩な植物グループであるがゆえに、その活用方法も魅力に溢れており、また逆に注意点も多い。 私は30年近い園芸生活で、限られたスペースの狭い庭ではあるが、じつに多種多様なつる植物を育ててきた。その経験から、魅力と注意点について振り返りながら書いてみたいと思う。 つる植物をどう仕立てるか 壁面にフジを誘引した例。もし塗装をし直す場合、植物を撤去しなくてはならない。 つる植物の最大の魅力は、長いつるを上や横へ広げて伸ばして育てることができるので、狭い庭を立体的かつ効率的に活用できることだ。壁面利用、空間利用は、狭い庭づくりには欠かせない。 壁面利用は、擁壁や建物の壁面を利用するわけだが、建物の壁面の場合、10年に1度程度、ペンキの塗り替えがあるので、そのようなケースが想定できる場所にはおすすめできない。 空間利用は、アーチ、オベリスク、トレリス、フェンス、支柱仕立て、カーテン仕立てなどなど、構造物を用意することで仕立て方や見た目が変わる。さて、それぞれの仕立て方に対して、どんな植物が適しているだろうか? 壁面利用に適したつる植物 我が家の場合、庭は道路面よりやや高台にあり、コンクリート擁壁の広い壁面がある。西日の当たるエリアだが、歩道との間数十センチの部分はコンクリート仕上げになっており、植物は植えられない。そのため、上の庭からフェンスに絡ませると同時に下に垂らすことになる。 30年の間に、じつにいろいろな植物を「壁面緑化」に活用してきた。 壁面緑化に使う植物の条件は、常緑であることや、早く緑化したいので成長が早いこと、丈夫であることなど。これらをポイントに、植物を選んだ。 ① ナニワイバラ 白い一重の花が清楚な薔薇である。期待に応えて、すくすく成長してくれた。しかし、数年経つと、かなり暴れ者の様相を示し、つるも太く、トゲも太い。もしも台風が来た際にこの塊が歩道に落ちたら……と心配になって処分した。 丈夫さと美しさ、成長の速さでは優等生だったのだが、庭に植えて垂らした状態で、きちんと壁面に固定できなかったのが失敗の要因だったと反省。下方の地面に植えて、太くトゲのある硬いつるをしっかり壁面に固定し、きちんと管理できれば、広いスペースにはおすすめの品種だ。 ② クレマチス・アーマンディ 上記のナニワイバラの次に育てようと思いついたのは、色合いの似た、クレマチス・アーマンディ。成長が早く、トゲや太いつるかどうかの点で心配はなかったので植えてみた。かれこれ20年くらい経つが、未だに健在。3月の中旬から一斉に開花し、芳香を放ち、通りがかる人に、「この花、なんですか?」とよく尋ねられる。 上写真が15年前。下が今年2025年の写真。 20年くらい、元気に育ち続けている要因は、思い切った剪定だと思う。1年で2~3mは伸びる暴れ者ではあるものの、花後に新芽が伸びたタイミングでバッサリ剪定すればよいだけだ。高枝バサミで比較的楽に切れる。 ③ ツルハナナス ツルハナナスは、比較的早い時期、つまりナニワイバラとほぼ同時期に植えて、今も健在。丈夫で長もちで、最近の暖冬では、なんと真冬にも咲いてくれる優等生だ。 その後、斑入りの品種も植えたら、明るい印象になった。ただし、斑入り品種は白花で、花はやはりブルーのほうが明るく感じるかな? 成長は早いが、枝が細いので簡単に剪定でき、管理は楽な植物だ。 壁面利用に適さないNG植物 NG① プミラ(フィカス・プミラ) 初心者向けの寄せ植えで、よく使用されるアイビーとプミラだが……。 ハッキリ言って失敗したのが、写真の寄せ植えに使用されている、左縁の可愛いプミラ! 寄せ植えのギフトに入っていたプミラを、コンクリート擁壁が醜いので這わせることを試みた。数年は斑入りの葉が美しく成長し、コンクリートを徐々に覆っていった。 ところがその後、斑模様がだんだん無くなってグリーンの葉のみに変化した。 翌年には、壁面を這っていたはずのプミラのつるが、壁面から一斉に空に伸び始めているではないか! ボサボサで、はっきり言って汚らしい! オマケに、この伸び始めたつるの葉はやたらデカイ。このまま放置すると大変なことになりそうなので、養分を断つために壁に張り付いている根元の幹をノコギリで切った。1cmの間隔で切り取って、断面を観察したところ、信じられないが、この木の正体があのミニ観葉のプミラなのだ。 なにしろ、伸びたつるはコンクリート面にべったりと吸盤のような根で張り付いているので、これで枯らすことができるか判らないが、まずは絶滅作戦スタートだ。アイビーなどでも予定外のところにつるが伸びるとややこしいことになるが、プミラも同様。モルタルの上にペンキ塗装している我が家の塀の部分にも伸びて、剥がすと汚らしくなる。つる植物は用心しないとイケナイ。 なぜ厄介なことになったか? 原因は3説考えられた。 原因① 園芸種なので、先祖返りした。 原因② 台木に使われていたオオイタビが暴れたのではないか。 ネットでオオイタビを調べたら、どうやら園芸種であるプミラの母種のようである。当時で10年前に流通していたプミラなので、オオイタビを台木にした接ぎ木苗だったのだろうか。 原因③ プミラは、株が小さい頃につく幼葉と、成熟した株につく成葉の2種あり、普段観賞しているのは幼葉。例えば、マルバユーカリなども幼木は丸い葉の幼葉で、成木になると長い葉のユーカリになる。株が成熟して成葉になったのかもしれない。 NG② ヘデラ(アイビー) 上記のプミラと共に、よく「植えてはイケナイ植物」で取り上げられがちなアイビー。寄せ植えには重宝するし、葉は可愛いものの、地植えにすると大変なことになる。この擁壁にもかなり距離のある他所から侵入して、未だに駆除に苦労している。 つる性植物でも、バラやクレマチスはつるから根が出て壁に付着することはないが、ヘデラやプミラはコンクリートでも木の幹でも付着するので厄介だ。この写真は剪定に行った知人宅の様子。ハナミズキの木に登ってしまい、その幹に付着して、なかなか取れずに、そぎ取るのに半日もかかってしまった。アイビーは余程広いスペースに植えるか、あるいは鉢植えで楽しむのが無難だ。 アーチ&トレリスに適したつる植物 ① つるバラとクレマチスの組み合わせ 我が家でも、多種のつるバラとクレマチスをアーチで育ててきたが、特に思い出に残っているシーンとともに、育ててきた品種をご紹介しよう。 ‘コーネリア’のアーチ仕立て(写真右)。つるが柔らかく作業がしやすい。 ‘バロン・ジロン・ドゥ・ラン’とクレマチス。 クレマチス‘ワルシャワ・ニキ’とつるバラ‘ロジャー・ランベリン’。 ② モッコウバラ アーチやトレリスは、植物が成長すると隠れて見えなくなってしまう。高価な製品を使用するのはもったいない気もするが、とても重宝するガーデニングアイテムだ。 ベンチの後方に見事に咲くモッコウバラ。 花後は、伸びると隣家に迷惑なので、剪定する。そうすることでアーチに絡めているのが分かるようになる。モッコウバラは成長が早く、常緑で、目隠しにもなるので、フェンス仕立てよりアーチにするほうが収まりがよい。 その後、こんなに巨大に育って見事になったものの、後方にある隣家へやたら侵入して手に負えなくなったため処分。モッコウバラは、しっかり剪定しよう。 ③ ハーデンベルギア オージープランツで、日本にもすっかり定着したハーデンベルギア。早春に咲いてくれて、常緑で、比較的育てやすい植物。 そもそもはフェンスに絡めていたのだが、成長力旺盛で、数年後には1年で数メートルも伸び、いろいろな所で咲いてくれる楽しみがある。なんにでも絡みつく性質なので、暴れるといえば暴れるが、つるが細く手でもちぎれる程度なので、花後に剪定すれば、比較的管理しやすい。 雨どいとケーブルテレビの配線に絡みついたハーデンベルギア。まあ、開花中はきれいだが、花後には配線を一緒に切らないようにしっかり処理しよう(昔、切った経験あり!)。 左/2025年3月20日の満開の様子。右/花が散り始めた10日後に伐採。 一度伐採してから1年後。さらに今年の春もケーブルと雨どいを隠すほど盛大に茂り、見事な花を1カ月ほど楽しませてくれた。10日ほどで散り始めたので、配線に絡まるつるを伐採。この手入れのサイクルを覚えていれば、うまく付き合っていける。 フェンスに適したつる植物 ① トケイソウ 最近、温暖化のせいか、日本でも越冬する様子を見かけるようになったトケイソウ。時計のような花でインパクトがある。夏から秋にかけて、たくさんの花を咲かせる。 トケイソウの素晴らしい所は、成長の早さだ。広い面積のフェンスの緑化には最適。上写真は4月に草丈10cm程度の苗を植え付けたもの。9月には幅5m以上にまで成長。毎年、たくさんの花を咲かせてくれる。 ② ワイヤープランツ guentermanaus/Shutterstock.com 昔、メルボルンの住宅街でワイヤープランツを金属ネットに絡めてきれいに刈り込んでいる塀を見たことがあった。とても美しかった。 我が家でもフェンスに絡めてみた。数年はよかったが、ある年に爆発したように変貌し、恐ろしくなって処分した。処分する作業中に、こんな可愛い花が咲いているのを発見。 ワイヤープランツにも花が咲く。 こまめにトリミングする自信のある方にはおすすめだが、「爆発」に要注意。 しかし、プミラもワイヤープランツも、ポット苗は可愛いのに、いきなり化けるので驚く。 緑のカーテンに適したつる植物 ① ゴーヤ 一昔前に、緑のカーテンが大流行したが、我が家では毎年、緑のカーテンといえばゴーヤだ。西向きの部屋があり、近年のような猛暑には欠かせない。毎年、プランター2個に植えているが、適度に収穫もできて、ゴーヤチャンプルーを楽しんでいる。緑のカーテンには、雲南百薬とか、フウセンカズラとかも試したことがあるが、やはりゴーヤが丈夫な緑のカーテンができるのでおすすめ。 ② アサガオ アサガオも、古くから日本で緑のカーテンに利用されてきた。綺麗だが、単独ではやや弱く、最近はゴーヤとミックスで使用している。 番外編 やっかい⁉︎可愛い⁉︎ つる性の雑草 「雑草という草はない」と、牧野富太郎先生はおっしゃっておられます。最後に、やっかいだが意外と可愛い花のつる性植物を! 可愛い花ですね。でも、油断していると、数日で3mくらいあるボトルブラシの上まで伸びて花を咲かせている。可哀そうな名前のヘクソカズラ。 これも綺麗な花を咲かせるが、15m以上にも伸びるクズ(葛)。1週間で1mは伸びて、侵入してくる。恐ろしい生命力。 あまり見かけないが、これも暴れ者のつる性雑草のマルバルコウソウ。 つる性植物を生かして「狭い庭」を緑豊かに! このように、つる性植物にはじつにたくさんの種類があり、それぞれに個性がある。狭い庭でも壁面や空間を立体的に活用し、緑豊かな美しい景観を作り出す魅力がある一方で、予想外の成長や管理の手間といった落とし穴も潜んでいる。私の園芸生活30年を振り返ってみても、つる性植物の力を借りて多くの楽しみを得てきたと同時に、その特性を理解することの重要性を痛感している。 私自身も改めてつる性植物と向き合うことで、また新たな活用法やアイデアが浮かんできた。ぜひ皆さんも、つる性植物の多様な特性をよく知った上で上手に庭に取り入れ、新たな空間の広がりやガーデニングの楽しみを見つけてください。
-
樹木

ミモザ(アカシア)は庭木におすすめ! 黄色い花が魅力のミモザの育て方や種類を解説
ミモザ(アカシア)の基本情報 植物名 ミモザ(アカシア)学名 Acacia英名 Mimosa和名 アカシア、ギンヨウアカシア科名 マメ科属名 アカシア属原産地 オーストラリア形態 常緑性高木 ミモザ(アカシア)は、オーストラリア原産の常緑性高木。ヨーロッパでは、ミモザといえばフサアカシアのことをいうが、日本では、ミモザはマメ科アカシア属の植物の総称で、ギンヨウアカシアやフサアカシアなども含まれる。 ギンヨウアカシア(Acacia baileyana)は、一般的に日本ではミモザとして知られているが、もともとアカシアは、実に多くの品種が世界中に分布するといわれる。しかし、多くがオーストラリア原産で、現地ではワトル・ツリー(wattletree)と呼ばれている。ボンボリ状の可愛らしい黄色の花と、ミモザという響きも素敵で、近年、庭木としても人気だ。マメ科植物なので、比較的痩せた土地でも育つのも魅力。 ミモザ(アカシア)の花の季節はいつ? 花や葉の特徴 園芸分類 庭木、花木開花時期 2〜4月樹高 5〜10m耐寒性 普通耐暑性 強い花色 黄色 「春は黄色い花からやって来る」といわれるが、我が家で真っ先に咲くのがギンヨウアカシアだ。毎年、バレンタインデーには開花する。早春の青空にふわふわイエローの可憐な花が舞い、葉も銀葉で明るく美しく、春を感じて心ウキウキさせてくれる魅力的な花だ。 アカシアというと、「♪アカシアの雨に打たれて……」という流行歌を思い出す方がおられるかもしれないが、この歌のアカシアはニセアカシア(Robinia pseudoacacia)で、北アメリカ原産のマメ科ハリエンジュ属の落葉高木。和名は「ハリエンジュ」といい、ミモザとは異なるので、ミモザ・アカシアの仲間ではない。 僕もかれこれ25年ほど、さまざまなミモザの品種を育ててきたが、多くは成長が早く、数年で丈高くなり、風や雪で枝が折れたり、夏の蒸し暑さで枯れてしまったものだ。 成長が早いと木の寿命も短くなりがちで、花後には剪定をして小型に保ったほうが寿命は長く保てるという。翌年の花芽が7月頃には上がってくるので、剪定は花の直後にしないと、花芽を落とすことになる。 ミモザとアカシアの違いとは 厳密に言うと、ミモザとアカシアは異なる。どちらもマメ科の植物ではあるが、ミモザはオジギソウ属、アカシアはアカシア属に分類される。 ただ、日本でいうミモザはアカシア属に分類され、前述のようにギンヨウアカシアやフサアカシアも含まれるので、この記事では日本式を基準に書いていくこととする。 ちなみに本来のミモザ(オジギソウ属)とアカシア(アカシア属)には、ミモザは触るとお辞儀するように葉を閉じるという特徴があるが、アカシアは触れられても葉が閉じることはない、という違いがあり、それで見分けることができる。 ミモザ(アカシア)の名前の由来 ミモザという名前は、ギリシャ語で「真似る人」という意味の「mimos」に由来している。本来のミモザはオジギソウ属であり、葉に触れるとお辞儀するように動くその動作が、古代ギリシャの劇「ミモスmimos」の劇中に出てくる動きに似ていたことから、その名がついたということだ。 なお、「パントマイム」という言葉は、ギリシャ語の「pantos=すべて」と「mimos」の合成語が語源となっている。 その後、オーストラリア原産のアカシアがヨーロッパに渡来した際、ミモザ(オジギソウ)と見間違えられたことから、アカシアが「ミモザ」と呼ばれるようになったということだ。 ミモザ(アカシア)の花言葉 ミモザの花言葉は、国によって異なる。 日本では、「優雅」「友情」。イタリアでは、「感謝」。フランスでは、「思いやり」「豊かな感受性」。 特にイタリアでは3月8日を「ミモザの日」として、男性から女性へ日々の感謝と敬意の気持ちを込めてミモザの花を贈る、という素敵な習慣がある。ここでいう「女性」は、恋人や妻に限らず、母や祖母、同僚や友人も含めてである。女性たちは、贈られたミモザを飾って楽しむだけでなく、その日は日常から離れて外食やお出かけを楽しむのだ。 ミモザ(アカシア)の代表的な種類 ミモザ(アカシア)には1,000を超える種類がある。ここでは代表的な5種を紹介しよう。 ギンヨウアカシア tamu1500/Shutterstock.com 我が家の庭にもあるギンヨウアカシアは、名前のとおり銀色の葉が美しく、日本でよく出回っている種類。葉の長さが短めなのが特徴で、樹高も低め。コンパクトで育てやすいといえる。 パールアカシア パールアカシア(Acacia podalyriifolia)は、丸い葉と丸いふわふわの花が特徴のミモザ。 上の写真はパールアカシアの実生で、成長が早く4年目で樹高が4mほどになった。一度、夏に枯れたが、残った枝を挿し木にしたら成功して、この木は2代目だ。亜熱帯のクイーンズランド州の南東部に分布しているが、耐寒性があり、雪が降っても枯れることはなかった。ただし、雪の重みで枝が折れることがあるので注意が必要だ。 丸く平たいシルバーリーフがきれいだ。 三角葉アカシア こんな三角葉アカシアという品種もある。名前のとおり三角形の葉が特徴で、シャープなイメージも持ち合わせる。樹高は低めで、他のミモザより花が咲く時期が若干遅い。 プルプレア種 また、新芽が銅葉(紫色ともいわれる)の、プルプレア種も魅力的だ。葉の形はギンヨウアカシアと同じで、銅葉は成長すると銀色に変わる。さらに冬が終わる頃には緑色に変化するので、季節とともにさまざまな色を楽しめる。花の数はあまり多くはない。 ちなみに、「プルプレア」はラテン語で紫という意味だ。 フサアカシア FatimeBarut/Shutterstock.com フサアカシア(Acacia dealbata)は、ギンヨウアカシアより葉が長く緑色なのが特徴。葉は触ると柔らかくて、鳥の羽根やレース編みのようにも見える。樹高が高く10mを超えることもあるので、スペースの考慮とこまめな剪定が必要だ。ヨーロッパでは、「ミモザ」というと、このフサアカシアをさすことが多く、「フランスミモザ」とも呼ばれる。 ミモザ(アカシア)の栽培12カ月カレンダー 開花時期:2〜4月植え付け・植え替え適期:4〜5月、9〜10月肥料:4〜5月剪定:5〜6月 ミモザ(アカシア)の栽培環境 日当たり・置き場所 ミモザは日光が大好きだ。日当たりのよい場所で育てると花付きもよくなる。冬でも気温がマイナス5℃を下回らない地域であれば、地植えもできる。 水はけも大事。そして風通しのよい場所も好む。だが、ミモザの枝は柔らかいので、雨や風で倒れやすくもある。地植えにするときは、幹を支柱などで支えるなどの工夫をしたり、鉢植えの場合は、梅雨や台風のときには安全な場所へ移動させるなど対策はしたほうがいい。 温度 ミモザは、冬でも最低気温マイナス5℃くらいまでは耐えることができる。それを下回ると冬越しは難しいだろう。 夏は25〜30℃くらいが適温だが、水切れには注意が必要だ。 ミモザ(アカシア)の育て方 ミモザの育て方や手入れ方法を解説しよう。 用土 ミモザはあまり土質を選ばない。水はけさえよければ、庭土や市販の培養土でもきちんと育つ。もし用土を自分で配合する場合は、赤玉土6、腐葉土3、軽石1の割合をおすすめする。 水やり ミモザは地植えの場合、植えてから1年くらいは土の表面が乾いたらたっぷりの水やりをしたほうがいいが、根が定着した後は水やりの必要はない。自然の雨に任せるので十分。 鉢植えの場合は、土が乾いたらたっぷりの水をあげるとよい。特に夏はとても乾きやすいので、鉢底から流れ出るくらい十分に水をあげよう。 肥料 ミモザに肥料が必要だとしたら、開花後の4月から5月頃。花が咲き終わったら、長い時間をかけてゆっくり効果を発揮する化成肥料や油粕を使うとよい。 ミモザには自分で窒素を吸収する力があるので、肥料は窒素成分が少ないものをあげるように。 ただ、育ちが悪いなどでないかぎり、必要以上に肥料を与える必要はない。 植え付け ミモザの植え付けの適期は春(4〜5月)と秋(9〜10月)。植え付ける際は前述の日当たりなどを考慮し、慎重に場所を選ぶことが重要。ミモザは移植が苦手だからだ。 市販の苗を購入したら、根鉢のサイズの倍くらいの大きさと深さの穴を掘って植え付けて、水をたっぷりあげる。 植えてすぐは風などで倒れやすいので、支柱を添えるのもおすすめだ。 ミモザは成長が早くどんどん大きくなるので、基本的に地植えが向いているが、鉢植えの場合は、深さのある鉢を選び、植え替えのたびに少しずつ鉢の大きさをサイズアップしていこう。 剪定 ミモザは生育旺盛。放っておくとグングン高さが増して5mは超える高木になる。美しい樹形のミモザに保つためには、そして、細い枝が伸び過ぎて強風で折れてしまうのを防ぐためにも、定期的な剪定が必要だ。 剪定時期は花が咲き終わった5〜6月頃。伸びた枝は切り戻し、混み合っている枝や葉も剪定して、バランスを取るのが重要。 遅くとも7月までに剪定作業は終わらせたい。なぜなら、7月頃からは次の花芽がつき始めるからだ。その後剪定すると、翌年の花つきに影響が出てしまうのだ。 夏越し 耐暑性は強い。夏でも地植えの場合、水やりはしなくても大丈夫。7月から8月にかけて、翌年の花芽がつき始める。 冬越し マイナス5℃を下回らなければ越冬可能。下回る場合は、鉢植えでの管理が必要だ。 ミモザ(アカシア)の増やし方:挿し木、種まきのすすめ ミモザの増やし方には、挿し木や種まきがある。 ミモザは、日本ではあまり長寿ではなく、大きくなるし、夏に突然枯れてしまうことが多いので、梅雨時期に挿し木苗をつくっておくとよいかもしれない。 挿し木苗の作り方は、ミモザの枝を、10〜15cmほど切り出す。その枝の下から半分ほど葉を取り除いて、切り口を斜めに切ったら2〜3時間、コップなどに入れた水に浸す。その後、挿し穂の切り口に発根剤を塗布したら、挿し木用の培養土をポットなどに1/3程度入れたら、割り箸などで穴を開けてゆっくりと植える。表土が乾いたら水を忘れずに。根が出るまで1~2カ月は、なるべく動かさないのがポイント。 また、花後にマメ科特有の鞘に入った種子ができるので、採取して播いて苗を育てるのも楽しい。タネは熱湯に一晩浸けておくと発芽しやすい(オーストラリアの植物は山火事を経験して発芽するものが多い。詳しくは、『オージーガーデニングのすすめ「発芽させる6つの方法」』参照)。 ミモザ(アカシア)のトラブル-害虫、根腐れ- ミモザの害虫被害で最も多いのは、イセリアカイガラムシによる被害。イセリアカイガラムシは、ほかのカイガラムシと同じように、一気に大量発生する。幹につくと樹液を吸って株を弱らせてしまう。 また、カイガラムシの排泄物が葉に付着すると、カビが発生して葉が黒いすすのような粉で覆われるすす病になることも。こうした被害を防ぐためにも、1匹でもイセリアカイガラムシを見つけたら、地道にこそげとるか、薬剤を散布するなど、早めの対処が必要だ。 ミモザの葉が落ちてしまったという場合には、根詰まりによって水が行き届かない乾燥や、逆に水のやり過ぎによる根腐れが原因として考えられる。冬の寒さが厳しい地域では、低温による影響もあるかもしれない。適正な管理で未然に防ぐことができる。 春はミモザ(アカシア)の花粉症に注意 ミモザの咲く春先、この時期は日本ではスギ花粉が飛び散っているが、僕はアカシア(ミモザ)花粉症なのである。あのボンボリのような花は、見るからに花粉がいっぱいではないか! 僕が最初に花粉症になったのは、メルボルン駐在中である。多くの日本人がワトル・ツリーと呼ばれるアカシアの花粉症で悩まされたのだ。 オーストラリアのミモザのシーズン。 Photo/ taewafeel /Shutterstock.com ガーデン都市と呼ばれるメルボルンの花粉の量は、きっと東京の比ではないと思う。家々の庭にはたくさんの花が咲き乱れ、花粉を撒き散らしているのだ。春先から夏にかけて、芝刈りをした夜はもう、花粉症の症状で眠れないほど苦しんだ。アカシアは花も葉も美しいが、花粉症の方は庭で育てるのは要注意かも知れない。 種まきをして発見した感動 長いこと園芸をやっていると、さまざまな感動があるが、僕は新しい植物の神秘を発見した時に感動する。咲いて当たり前の花が咲いても感動はあまりないが、植物の未知の世界に遭遇し、未知が既知のものとなる瞬間に感動がある。このミモザ(オーストラリア原産のアカシア)は普通、偶数羽状複葉であるが、中には三角葉や平葉のアカシアがある。 数年前に、パールアカシア(Acacia podalyriifolia)という、平たい葉っぱの少し変わったアカシアの種子を入手して播いたら、普通のアカシアのような偶数羽状複葉の芽が出てきた。「あれ? 品種が違ったのかな?」と思いつつそのまま育てていたら、ある時、異変に気がついた。なんと羽状複葉の根元が平葉になっているではないか! ユーカリにも幼木の時は丸い葉で、成木になると普通の長い葉になる品種があるが、パールアカシアも成長過程で葉のカタチが変化するようだ。不思議大陸の植物は本当に面白い。 3月8日はミモザの日(国際女性デー) Alena Gridushko/Shutterstock.com 3月8日は国際女性デーとして知られている。国際女性デーは、女性の権利を守り、ジェンダー平等の実現を目指すために、国連により1977年に定められた。 なぜ3月8日かというと、それは1904年3月8日にニューヨークで女性労働者が婦人参政権を求めて起こしたデモに由来する。 また、イタリアでは、3月8日を「ミモザの日」として、男性から女性へ感謝の意を表してミモザの花束を贈る風習があった。3月8日はミモザの花が咲き誇る時期であり、ミモザは国際女性デーのシンボルとなった。 ミモザ(アカシア)を飾る〜剪定枝を活用したスワッグや、リース、ドライフラワーの作り方〜 ところで、このミモザは、最近流行のスワッグの材料にもぴったりだ。つぼみの状態も可愛い。ユーカリやメラレウカと一緒に束ねるのがオススメだ。そうだ、この原稿執筆の手を休めて、スワッグを作ろう…と、庭からつぼみのついたパールアカシアやオージープランツの枝を切ってきて、束ねて、ほんの数分で仕上がったのが上写真だ。庭にオーストラリアの木々があると、ユーカリの香りと共に、おしゃれなインテリアが思い立ったときすぐ楽しめる。 ミモザで作ったリースも、この時期花屋などの店頭で多く見られる。玄関先に、自分で手作りしたリースやスワッグを飾るのも、お客様を出迎えるのに華やかでいい。ドライフラワーにするだけでも、絵になって可愛い。 ミモザのスワッグやリース、ドライフラワーの作り方は、ガーデンストーリーの下記記事をぜひご参考に。 また、伐採したアカシアの木は、オーストラリア・レンガのアクセントに埋め込んで使用している。こうして考えてみると、いろいろと活用方法があるものだ。庭に植えて季節を感じるばかりでなく、生活に活用できるオージープランツ、ぜひ育ててほしい。
-
樹木

美しくたくましい植物「ソテツ(蘇轍)」《我が人生と共に生きた植物》
日本や海外でたくましく育つソテツ お寺でもよく見かけるソテツ。Moonpixel/Shutterstock.com 私にとって、トロピカルなイメージがあるソテツは、九州南部から南西諸島、台湾、中国南部に自生し、園芸植物として世界中で育てられている。TVの時代劇でも庭の植え込みには必ずといってよいほど登場したり、各地には樹齢数百年の大株が存在したりする。また、お寺や学校、公共施設などのエントランスで育つ立派な株立ちも思い出す。日本では古くから盆栽などでも人気の植物であるが、国内のガーデニングの世界では、あまり話題にならないようだ。 最近旅で出会った、箱根の老舗旅館の巨大ソテツ。 宮﨑を象徴する絶景、日南海岸にもソテツが育つ。kan_khampanya/Shutterstock.com 昨今のガーデニングの潮流で、スタイリッシュで育てやすく手間のかからない植物が選ばれるドライガーデンの流行から、ソテツの人気が高まるのではないかと私は期待している。 イギリス、ロンドンの植物園Kew Gardenでもソテツは人気。 アメリカのジョージア州で、住宅街にも見られるソテツ。洋風建築に映えますね。Sabrina Janelle Gordon/Shutterstock.com ソテツは「生きている化石」と呼ばれ、中生代、つまり恐竜が出現した時代から姿形が変わらない植物なのだ。私の好きなシダ同様に、2億5000万年前から風雪に耐え、大自然の中で研ぎ澄まされて最適な形で生き残った自然の芸術作品なのだ。 私とソテツの出会いは小学生の頃 COULANGES/Shutterstock.com 私が初めてソテツに出会ったのは小学生のときで、親戚の家にソテツの盆栽があり、子どもながらに「カッコイイ!」と思った。 私は、中学生の頃はサボテンに興味を持ち、高校生の頃は観葉植物に興味を持ち始めていたが、ソテツに関しては、何と18歳のときに苗を3本買い、以来半世紀以上も人生をほぼ共にしてきた「我が人生思い出の植物」なのだ。 2005年に上から撮ったソテツ。 私がソテツで魅力的に感じるのは、たくましい葉の美しさと共に、新芽が萌え出るときのエネルギーだ。それは爆発のように凄い! なんとも生命力を感じる瞬間だ! 毎年6~7月に新芽が勢いよく伸び出て、まるで爆発するようなエネルギッシュな成長が感動的だ。下の写真は、実家から我が家に来て10年目、2005年の写真。樹齢約37年。 左から、2005年6月30日、7月6日、7月19日と、凄い成長を遂げた。 同じく2005年に上から撮った写真。 18歳のとき、ソテツの苗木を植木市でなんとなく購入 2008年9月。 このソテツは、私が18歳のときに大学の「不合格発表」を見に行った帰り道、通りがかった植木市でなんとなく購入したものである。もう半世紀以上も前のことである。結局、半世紀以上、このソテツとは人生を共にしたことになる。 あの日、第1志望の大学から突き放され、浪人が決まった。このとき、何故ソテツを購入したのか? 1本50円で、根もなく葉もなく、イモみたいに転がされて売られていた。 「え? これが本当に育つの?」と尋ねると、店のオッチャンは「ソテツは生命力が強いから育つんだよ」と答えた。こんな姿から生命を吹き返すなんて思えなかったが……。 私は衝動的に、このソテツを3本購入した。 2005年に植え付けて順調に成長。狭くなったので南側に移植した。2017年7月のこと。 たぶん入試に失敗し、絶望のどん底に突き落とされた自分の姿と、このソテツの惨めな姿が重なって足が止まったのだろう。 そのオッチャンの「強い生命力」という言葉に、若き日の失意の私は揺さぶられたのである。 我が家の一等地に移植後、2024年2月にはこんな立派になった。 2023年8月。 あれから、なんと56年が過ぎた。大学を卒業して実家を離れてから、四半世紀ほどは、実家に戻ったときにしか見なかった。45歳のときにオーストラリアから帰国して現在の家に住むようになり、実家から移植した。 3本購入したうちの1本は、実家で枯れてしまった。実家から連れ帰ったソテツは、うまく掘り上げられず、根鉢も崩れてしまい、もうダメかなと思ったが復活した。まさに「強い生命力」を実感したのである。我が家に来てから、既に30年近く。我が家でも大きくなり、1回移植した。そして、日当たりのよい我が家の一等地に余裕を持って植えたつもりだが、成長が遅いとはいうものの、30年でかなり成長。巨大化し、庭で育てる限界を感じるようになった。 庭の終活、ソテツをよそへ移植 ソテツを掘り上げるには1週間かかった。大人4人でようやく抱えられる重さだった。 おそらく、いずれいつかは、この家を処分することになるが、ご近所を見ても、家を取り壊すときは庭の植木も根こそぎブルドーザーで処分してしまう。 ソテツ以外にも、自分が大切に育ててきた樹木がブルドーザーで処分されるのは耐えがたい。庭の終活を考えるようになって、幸い大きくなったこのソテツや、ジャカランダ、木生シダのディクソニア、コルディリネなどを引き取っていただける広い庭が見つかった。 移植場所は、広い敷地のレンタルガレージの一角、日当たりのよい場所だ。2024年4月に移植して無事に根づき、第2の人生をスタートした。 そして、1本は初めて花を咲かせた。長寿のソテツ、50歳超えは、これから人生の花が開くのだ。ソテツは雌雄別株で、この丸い花は雌花。雄花は長い形だ。 これが雄花。Opachevsky Irina/Shutterstock.com ソテツの寿命は数百年ともいわれる。新天地は、どんなに巨大化しても十分なスペースがある。56年前は小さなイモのようだったソテツが、こんなに育ち、狭い庭から脱出して、広い土地で伸び伸びと葉を広げる姿に、なんだかホッとした。 本当に長い間、人生を共にしたソテツである。辛いことがあったり、くじけそうになったりしたときに、ソテツを見ると元気が出るのだ。私の人生の良きライバルでもある。 立派に育てよう! ソテツの育て方 さて、どんな荒れ地でも育つといわれるソテツだが、育て方に触れておこう。 日当たりのよい場所を好む。 水やりは控えめに乾燥気味に育てる。 地植えの場合には施肥は必要ないが、鉢植えの場合は春と秋に緩効性肥料を与える。 植え替えや移植は春が適期で、鉢植えの場合は2~3年に1回、鉢増しをする。根詰まりを起こしやすいので注意。 寒さに比較的弱く、寒冷地では冬は屋内に入れる。 ソテツ栽培の注意点 成長が遅く、1年で数センチしか育たない。 種子だけでなく、葉や根にも毒性がある。 雌雄異株で花の形が異なる。 ソテツの増やし方「実生と株分け」 実生で増やす注意点 実生(種まき)も可能だが、発芽するまで数カ月から数年かかることもあるそうだ。植物園勤務時代に挑戦したことがあるが、失敗した。種子を植えるときは、半分は地上に出すそうだ。また、温度と湿度を保つ必要があり、私は挑戦したものの失敗。おそらく、湿度管理ができなかったのが原因だと思う。 株分けで増やす方法 株が大きくなると根元から子株が出るので、株分けをする。あまり小さいと育ちにくいので、幹が直径5cmになるのを目安にするとよい。 子株からの成長過程 昨春、移植する際に掘り上げたら、写真のようにたくさんの子株ができていたので植えてみた。 ① 掘り上げ前の親株。② 次々と子株が出てくる。③ たくさんの株ができた。④ 鉢に植えておいた。 56年前に、植木市で1本50円の芋のような苗を3本購入したときのことを思い出した。あのときの株は、葉もなくてもっと小さかったかもしれない。あれから半世紀以上が経ち、子株からまた新しい株が誕生した。 この子株も、50年後には巨大化するのだろうか。新天地に移植した2本のソテツが100歳を超え、きっと立派に育っているであろう未来を想像した。 3カ月後には、こんなに新芽が出た。 私が18歳の青春の頃から人生を共にした、“青春のソテツ”が、何故か石川達三の小説『青春の蹉跌(せいしゅんのさてつ)』と重なる。 『青春の蹉跌』の主人公は、夢と野望を抱くがやがて破滅していくという青春だったが、私の“青春のソテツ”は違うのだ!(ちなみに蹉跌とは、物事が見込みと食い違って、うまく進まない“失敗”の状態になること) あれから長い歳月が流れた。結局、私は浪人しても、第1志望校に行くことはなかった。もしかするとアノ大学に行っていたら、エリートコースに乗って、『青春の蹉跌』の主人公のような破滅の人生を歩んだかもしれない……なんて負け惜しみを言ってみたりする。 私は、夢と野望よりも、余裕のあるロマンと微笑みに満ちた人生がスキだ。今、老後を好きな美しくたくましい植物たちに囲まれ、ピアノとバイオリン&ビオラを奏でて、植物三昧&音楽三昧。自分では幸せと思える日々を送っている。これが、私の“青春のソテツ”。 ソテツは、ずっと私の人生を見守っていてくれた。 田中一村の晩年の作品に「不喰芋と蘇鐵」があるが、その作品をイメージして撮った写真。光に透けて葉が美しく引き立つ。 そして、ソテツはボクの好きな画家、田中一村の絵を思い出させる。 本当に美しくて、たくましいソテツだ。こんなソテツを見ると、加齢で弱音を吐く自分が愚かに思える。残りの人生をソテツのように、美しくたくましく生きよう!
-
一年草

【冬のガーデニング】定番花パンジー&ストックで栽培上手を目指そう!
冬は「のんびり」ガーデニングを推奨 長年ガーデニングを続けてきて、常日頃、水やりをはじめとした世話に追われていると、時に、「のんびり」ガーデニングを素敵に楽しみたいと思うことがある。その絶好の機会は、雑草など生えず、樹木も成長を止める冬である。そんな「のんびり」ガーデニングを楽しみたい冬に、何を植えようかと悩まないよう、例年、パンジーとストックを「冬の定番」としてかれこれ30年近く育ててきた。 キモッコウバラ(左奥)やロベリア(右)が咲く時期でも、パンジーの花付きは衰えていない。 なぜパンジーとストックなのか? それは10月中旬から5月の連休までと長い期間咲き続けてくれる優等生だからだ。比較的、苗も安く入手でき、余裕のあるときは実生(種まき)で育てたりするのも楽しい。ほかの季節はオージープランツをはじめ、比較的マニアックな手のかかる植物を育てている反動からか、冬はパンジーとストックをのんびり育てることに落ち着いた訳である。 平凡なパンジーとストックを冬の定番にして30年になると言うと、なんだか「進歩の無い人」と思われるかもしれない。しかし、毎年の定番という花の存在は、ホッと安らぎを感じさせてくれるのである。 パンジーとストックを定番にした理由 日々のガーデニングをSNSで情報発信していると、つい新しい情報や背伸びした内容をアップしたくなるものだが、やはり、自分が癒やされ、くつろげる自然体のガーデニングが一番である。30年前を振り返れば、私はガーデニング初心者だった。そのときに「初心者でも育てられる植物」がパンジーとストックだったのだ。それに加え、毎年定番の草花を育てるメリットは、「育て方」を毎年経験し、熟知するので失敗がなく、安心していられることだ。 また、この30年でパンジーもストックも品種の性質が向上しているのを年々実感している。昔から親しまれているオールドパンジーやストックこそ、私にとって親しみがある冬の定番なのである。 私のパソコンで過去30年間の写真の中から、パンジーとストックを検索したら、約1,000枚がヒットした。年間にすると50枚だから、11月から4月の6カ月間に、ひと月9枚近くの写真を撮った計算になる。そんな写真をご紹介しながら、冬の定番草花のパンジーとストックの魅力をお伝えしたいと思う。 パンジーの基礎知識 Ermak Oksana/Shutterstock.com 学名/Viola和名/三色スミレ英名/Pansy科名・属名/スミレ科スミレ属原産地/ヨーロッパ 私が子どもの頃、つまり60年くらい前には、パンジーは「三色すみれ」と呼ばれていた。江戸時代に日本に伝わったとされるが、60年前の当時は、春の花であり、販売されるのも3〜4月だったと記憶している。20年ほど前であっても12月頃から販売されていて、その後、年々販売開始が早まり、ご存じのとおり今では10月から園芸店に開花苗が並んでいる。ただし、今年のような猛暑の中では早く購入しすぎても徒長するので、やや寒さを感じる時期まで待ったほうが賢明だ。実生の場合は8月にタネを播けば、12月には開花するといわれるが、今年のような猛暑では難しいかもしれない。 パンジーとビオラの区別についてだが、一時、花径が何センチ以下はビオラといわれたが、最近はミックス品種も多く、学名も両者ともViolaだ。原産地はビオラのほうが北部ヨーロッパとされ、寒さにも強いといわれている。 ストックの基礎知識 学名/Matthiola incana和名/アラセイトウ英名/Stock科名・属名/アブラナ科アラセイトウ属原産地/地中海沿岸 ストックも、江戸時代に日本に入り、房総半島で切り花として栽培された。私自身もストックは「切り花」のイメージが強く、我が家で庭で育て始めたのは30年くらい前からである。パンジーと開花時期がほぼ同じで、育つ環境も似ているので管理しやすい。草丈があるので、パンジーと寄せ植えしてもバランスがよく、扱いやすい。 パンジーとストックの庭での活用実例 我が家はパンジーもストックも、ごく平凡な一般的な品種を育てている。写真をご紹介しながら説明していこう。 【単植】 1鉢に1~2品種のみをシンプルに植えると、花が引き立って豪華。鉢自体が庭のアクセントになる。 【寄せ植え】 シルバーレースはパンジーを引き立てる。 パンジーは他の植物とも合わせやすく、寄せ植えにおすすめ。 左上/黒花をヒューケラと合わせて大人の雰囲気に。右上/常緑低木のカルーナと暖色の同系色でまとめた。左下/一年草のアリッサムとの組み合わせは無難だが失敗がない。右下/サラダ用のミックスリーフと寄せ植え。なかなか渋い。 パステルカラーのネメシアなどとも相性がよい。 【庭風景】 小型の安定感のある鉢に植えると、塀の上など狭い場所に飾ることもできる。 次に、庭風景に映える組み合わせやディスプレイの例をご紹介しよう。 左/数鉢のパンジーを足元に置き、デンドロビウム・キンギアナムを豪華に引き立てる。右/シダのあるワイルドな庭もパンジーが入ると優しい景色に。 パンジーとストックを一緒に植えると高低差が出てバランスがとりやすい。 ストックもパンジーも雪が降っても問題なく、寒さに強い。 パンジーとストックの育て方 種まきから育てたパンジー。ある年の8月下旬の様子。 パンジーもストックも、育て方はほぼ同じ。種子から育てて年内に開花させる場合は8月が播種のタイミングといわれてきたが、猛暑の昨今、このスケジュールではかなり厳しい。発芽適温は15~20℃、最高気温が25℃を超えない時期がよいとされているので、今年のような猛暑で10月でもまだ暑い場合は、年内の開花は諦めたほうがよい。苗から育てる場合、10月には出回っているが、暑いと徒長するので十分に涼しくなってから購入したほうが無難だと思う。そして、本格的な寒さがやってくる頃までにはしっかり根付かせたいので、地域にもよるが、紅葉の見頃を迎える11月下旬から12月上旬が買い時ではないだろうか。 我が家は、毎年、ケース買いをしている。 【植え付け時期】 植え付けは、パンジーは6号鉢に1株、標準プランターで3~4株と余裕をもって植えるとよい。地植えは20~30cm間隔に。 ストックは、やや密に植えないと見栄えがよくないので、8号鉢に3株、標準プランターで5~6株程度でよいだろう。寄せ植えの場合は、これより若干密に植えるとよい。地植えは20cm程度の間隔。 【用土】 あらかじめブレンドされている培養土が簡単。植え付け時に長期間効く緩効性肥料を施しておくとよい。 【置き場所】 日当たりがよく、寒風は当たらないような場所がよい。 【肥料】 鉢植えの場合は、2週間に1回程度、液肥を与える。 【水やり】 鉢植えの場合、表面が乾いたらたっぷりと与える。 【花がら摘み】 特にパンジーのように種子を作る草花は、花がら摘みをマメにすることが長く咲かせるコツ。種子ができてしまうと養分が取られ、子孫を残せることに安心して新しいつぼみを作らなくなる性質がある。花がら摘みを都度することで、子孫を残そうと新しい花が次々に咲く。 今年の冬は基本に戻って、冬の定番花パンジーとストックを育てて、園芸の醍醐味を味わってみませんか? 基本的な草花は、丁寧に育てると見違えるほど立派に育つものです。ぜひチャレンジしてください。
-
おすすめ植物(その他)

日本最北の離島 利尻島・礼文島の花を愛でる旅案内【36種の花図鑑】
予習しなくても次々感動に出会える旅 Rainer Lesniewski/Shutterstock.com 北海道の北部、稚内の西方の日本海に位置する礼文島と利尻島は、高山植物の宝庫として有名です。両島の厳しい寒さと短い夏という環境は、本州の高山の気候と似ており、特に礼文島には多くの貴重な高山植物が育ち、花の浮島とも呼ばれています。正直なところ、「世界でも礼文島でしか咲かない“レブンアツモリソウ”は、6月にしか見られない」くらいの知識しかないなか、漠然と日本に残る貴重な高山植物たちに会いたい! とツアーに参加しました。 礼文島。makieni/Shutterstock.com 特に事前に予習することもなく、北海道の新鮮な海の幸も楽しめるラクチンなツアーで出かけたのです。2泊3日の短い旅でしたが、たくさんの「思いがけない」草花に遭遇。目から鱗の3日間! その感動を、ガーデンストーリーの読者の方にもお伝えしたいと思います。 朝9時に羽田を出発し、13時半には利尻空港に到着。島へは、新千歳空港で乗り換えたのですが、てっきり小型プロペラ機で向かうのだと思い込んでいたら、なんと165席もあるボーイング737という立派なジェット機。それも満席で、驚くと共に、少し安心しました。 礼文島から望む利尻山。applevinci/Shutterstock.com 利尻空港では、利尻富士が迎えてくれました。「利尻富士」と愛称で呼ばれる利尻山は、日本百名山の中では最北に位置し、標高は1,721m。まるで海面から浮かんでいるように裾野を広げ、島のどこからでも眺められました。また、その雄大な美しい姿は礼文島からも見ることができ、今回の旅の中で最も印象に残る景色でした。 初日に出会った利尻の植物14種 早速、バスが向かったのは、富士野園地。ここは、吉永小百合さん主演の映画「北のカナリアたち」のロケ地で有名な場所ですが、エゾカンゾウが咲き乱れる野原…というイメージにはほど遠く、まだ時期が早いため、チラホラ咲いている程度でした。野生の花を見る旅は時期が難しいですね。エゾカンゾウは他で写真を撮れたので、後ほどご紹介します。 富士野園地は、海の見えるのどかな草原でした。マムシがいないので、草原でのロケも安全とか……。かろうじて、遠くにエゾカンゾウが咲いているのが見えました。 姫沼を一周、散策中も雄大な利尻富士が眺められ、可憐な花を咲かせるエンレイソウ、シロバナエンレイソウ、ノビネチドリなどを見ることができました。 延齢草、延根千鳥、舞鶴草 写真左上から時計回りに、エンレイソウ、シロバナエンレイソウ、ノビネチドリ、マイヅルソウ。 初日最後の訪問地は、島最南端の仙法志御崎(せんほうしみさき)公園。海抜ゼロメートルから見る利尻富士が有名です。 利尻富士 ここでは、エゾタカネツメクサ、イワベンケイソウ、ハマカンザシ、チシマフウロ、エゾカンゾウ、ハマナス、シロヨモギなど、たくさんの有名な高山植物や海浜植物に出会うことができました。 蝦夷高嶺爪草 エゾタカネツメクサ エゾタカネツメクサ(蝦夷高嶺爪草)は、高山の砂礫地や岩場にマット状に生育する性質で、本州の高山で見られるタカネツメクサの母種とされています。楚々として可愛いですね。 岩弁慶草 イワベンケイソウ まさか利尻島で多肉植物のイワベンケイソウ(岩弁慶草)に出会うとは。多肉植物は寒さに弱いイメージでしたので、後ほど触れるイワレンゲ同様、ここで見られることが驚きでした。 浜簪 ハマカンザシ 和名ではハマカンザシ(浜簪)と呼ばれるアルメリアにも出会いました。アルメリアが利尻島で自生しているとは驚きでした。 千島風露 チシマフウロ チシマフウロ(千島風露)といえば、フウロソウ(ゲラニウム)もイングリッシュガーデンがブームの頃から人気の植物ですね。アルメリアと共に、フウロソウも利尻が原生地なのも驚きでした(驚きが続きます)。ほかにも、園芸品種でお馴染みの、オダマキやアサギリソウも、原種は利尻・礼文にあったのです。まさに植物の宝庫です。 蝦夷萱草 エゾカンゾウ エゾカンゾウ(蝦夷萱草/エゾゼンテイカ)は、本州でも有名なニッコウキスゲと見た目はさほど違いを感じませんでした。しかし、僕の好きな、ヘメロカリスの原種に、こんな日本最北の離島で会えたのも驚きと感動でした。 浜茄子 ハマナス ハマナス(浜茄子)はハマハシ(浜梨)ともいいます。「知床旅情」で一躍有名になったハマナスです。バラ科の植物でJapanese Roseともいわれています。寒さに強いのですね。 白蓬 シロヨモギ 海岸にはシルバーリーフのシロヨモギ(白蓬)が地面に張り付くように群生していました。できることなら園芸に使用してみたい植物です。 黒百合 クロユリ 初日の宿泊先、知床温泉のホテル周辺にも利尻の代表的な花が植えられていました。 それは、僕の大好きな憧れの黒花、クロユリです。以前、自宅の庭で育てた黒花10選でもご紹介しましたが、いつしか絶えてしまいました。 礼文草 レブンソウ レブンソウ(礼文草)には、紫やピンクの花があり、同属の仲間に「リシリゲンゲ(利尻紫雲英)」もあります。通販などでも苗が売られているようですが、当然のことながら、ほかの地域では夏越しが難しそうです。 深山(礼文)苧環 ミヤマオダマキ(現地名:レブンオダマキ)。礼文島で咲くオダマキの正式名称は、一般的にミヤマオダマキです。 ミヤマオダマキは、日本各地の高山に分布する種で、礼文島でもその美しい姿を見ることができます。礼文島では、特に“レブンオダマキ”と呼ばれることもありますが、これはミヤマオダマキの変種や品種という扱いになります。 ミヤマオダマキは、ガーデンプランツとしても多種育てられている西洋オダマキの仲間です。利尻の街中でたくさん見かけました。 地元の日本酒「最北航路」。 驚きの連続でしたが、温泉に入って、ウニ、サーモン、ホタテ、ホッケ等々海鮮類がぎっしりの夕飯を食べて、満足な1日でした。 2日目に出会った礼文の植物12種 Terence Toh Chin Eng/Shutterstock.com 2日目は、海の幸が中心の朝食でスタートです。午前中は生憎の小雨で真冬並みの寒さでしたが、午後からは天気が回復しました。朝、フェリーで礼文島に渡りました。 早速北上し、今回のツアーのメインイベントである礼文島にしかない固有種のレブンアツモリソウの群生地へ。バスを降りて少々歩きましたが、小雨はさほどではなかったものの、冷たい強風が吹き、まるで真冬のような寒さでした。 礼文敦盛草 レブンアツモリソウ レブンアツモリソウ(礼文敦盛草)の開花は、6月に限られています。この日をめがけてタイミングを合わせたツアーでしたので、寒空の下で無事出会うことができました。ぷっくりとしたクリーム色の可愛らしい花です。この日、花が小雨に濡れていましたが、かえって情緒がありました。 延根千鳥 ノビネチドリ この群生地には、ラン科のノビネチドリ(延根千鳥)も咲いていました。和名は、根が横に伸び、花の形が鳥の飛ぶ姿に似ていることに由来しているそうです。このノビネチドリは、その後もあちこちで見かけました。 春咲山芥子 ハルザキヤマガラシ 黄色い花を見つけましたが、ハルザキヤマガラシ(春咲山芥子)という名でした。ヨーロッパ原産の多年草です。貴重な植生環境の場所にも入りこんで繁茂し、問題になっているようです。 次は、すぐ近くの澄海岬(スカイ岬)へ。透明度の高い青い海で有名な観光スポットで、歌手の中島みゆきさんが「銀の龍の背に乗って」のPVの撮影を行ったことでも有名です。残念ながら青空は見えませんでした。 しかし、途中の小路ではネムロシオガマや、エゾイヌナズナ、エゾシシウド、ハクサンチドリなどを見ることができました。 根室塩竈 ネムロシオガマ ネムロシオガマ(根室塩竈)は、根室という名がついているとおり、北海道本土でも海岸を中心に見られます。葉がシダのように繊細できれいな宿根草です。 蝦夷犬薺 エゾイヌナズナ エゾイヌナズナ(蝦夷犬薺)は一見、アリッサムに似ています。イヌナズナといえば、普通は黄花ですが、エゾイヌナズナは白花で、アリッサムとも同じアブラナ科です。 蝦夷猪独活 エゾシシウド エゾシシウド(蝦夷猪独活)は、草丈100~150cmの大型多年草で、海岸近くに群生していました。イノシシが食べそうな花なので、この名前が付いたそうです。 白山千鳥 ハクサンチドリ ハクサンチドリ(白山千鳥)は、石川県の白山に多く見られるので、この名前がついたそうです。本州では標高が高い山に登らねば見られない高山植物が、一度にまとめて見られるのが、礼文島訪問の魅力ですね。 岩弁慶 イワベンケイ イワベンケイ(岩弁慶)は多肉植物扱いされることもあり、最近はサプリでも有名ですが、もともとは高山植物だったのですね。 礼文岩蓮華 レブンイワレンゲ イワレンゲは多肉植物でお馴染みですが、メキシコ原産だと思っている方も多いのでは? 一般的なイワレンゲは、本州の関西地方以西の海岸に育ち、あまり耐寒性がないと思っていました。見た目はイワレンゲとあまり変わらないレブンイワレンゲ(礼文岩蓮華)、こんな寒い礼文島に自生しているとは、本当に驚きです。 蝦夷延胡索 エゾエンゴサク エゾエンゴサク(蝦夷延胡索)は、生薬に使用されるヤマエンゴグサと似ていますが、苞の形が異なります。 千島風露 チシマフウロ 利尻でも出会った礼文のチシマフウロ(千島風露)。フウロソウ科フウロソウ属の多年草です。別名は、エゾフウロ、エゾノフウロ、トカチフウロ、ハクサンフウロなどがあります。チシマフウロは、園芸用に栽培されることもあります。 チシマフウロとセンダイハギのコラボ。 深山金鳳花 ミヤマキンポウゲ 北海道から本州中部の高山の草原に生えるミヤマキンポウゲ(深山金鳳花)は、特に湿り気のあるゆるやかな斜面では大群落をつくることもあります。初夏の高山の草原を彩る花の代名詞ともされています。 礼文苧環10種の礼文の植物を一気見! 昼頃から天気が回復しました。昼食も海鮮です。これからご紹介する植物の中には、すでに登場しているものもありますが、あちらこちらで咲いていた様子を景勝地も交えてお伝えしたいと思います。 桜草擬 サクラソウモドキ サクラソウモドキ(桜草擬)は、サクラソウ科サクラソウ属の多年草です。別名は、チシマサクラソウ、エゾサクラソウなどがあります。栽培も比較的容易です。日当たりと水はけのよい場所で、よく育ちます。 礼文苧環 ミヤマオダマキ(レブンオダマキ) レブンオダマキは礼文島のみに生息するミヤマオダマキの変種とされ、花色は青紫色または白色です。北海道本島にはミヤマオダマキが生息し、花色は白、紫、ピンクです。 今回の旅行で、野山に限らず街中の住宅の庭にもレブンオダマキが植えられているのを見ました。各所で一番多く見かけた花の一つです。関東地方でも西洋オダマキはガーデニングで一般的ですが、利尻・礼文島に原種がたくさん咲いていたのは驚きです。 根室塩竈 ネムロシオガマ ネムロシオガマ(根室塩竈)は、別名エゾシオガマとも呼ばれています。ネムロシオガマは、絶滅危惧種に指定されています。 礼文小桜 レブンコザクラ 一見、日本桜草かと思いましたが、レブンコザクラ(礼文小桜)は、礼文島の代表的な花の1つであり、花期は5月下旬~6月上旬。礼文島の高山地帯では一面をピンク色に染めるほど咲き誇ります。 桃岩は、北海道礼文町にある景勝地です。日本海の断崖絶壁に突き出た巨大な岩で、その形が桃に似ていることから名付けられました。 舞鶴草 マイヅルソウ マイヅルソウ(舞鶴草)は山野草としてはポピュラーですね。本州の高山地帯に分布し、ブナ林などの林床に生えています。栽培も比較的容易で、日当たりと水はけのよい場所でよく育ちます。 蝮草 マムシグサ マムシグサ(蝮草)は、サトイモ科テンナンショウ属の多年草です。別名は、ヘビノダイハチ、ヤカゴンニャク、ムラサキマムシグサ、アオマムシグサ、ヤクシマテンナンショウなどがあります。 日本全国の山野に生え、やや湿った場所に多く見られます。茎には紫褐色の模様があり、マムシの皮膚の模様に似ていることからマムシグサという名が付けられました。 延根千鳥 ノビネチドリ ノビネチドリ(延根千鳥)は、ラン科ノビネチドリ属の多年草です。別名は、ネジバナ、ネジバナソウ、ネバナなどがあります。 朝霧草 アサギリソウ アサギリソウ(朝霧草)は、2000年のガーデニングブームの頃、人気があり、原産地はイギリスかヨーロッパかと思っていました。まさか、礼文島に自生しているとは! 見つけたときは、またまた驚きです。日本全国の山地や亜高山帯に分布しているようです。 白毛菊葉鍬形 シラゲキクバクワガタ シラゲキクバクワガタ(白毛菊葉鍬形)は、ゴマノハグサ科の多年草です。別名にキクバクワガタ、ゴマノハグサモドキなどがあります。 礼文島のみならず北海道の高山帯に分布し、岩場や海岸の岩礫地などに生えます。草丈は5~25cmほどで、全体に白い毛で覆われています。 礼文島の地蔵岩は、北海道礼文島の元地海岸(もとじかいがん)に位置する高さ約50mの奇岩です。2つの切り立った岩が手を合わせているように見える姿から地蔵岩と呼ばれています。近くにあるメノウ海岸は、その名のとおりメノウの原石が拾えることで知られるほか、夕日の絶景スポットとしても人気です。地蔵岩は、礼文島の三大奇岩(猫岩・桃岩・地蔵岩)の1つとしても知られています 蝦夷薄雪草 エゾウスユキソウ エゾウスユキソウ(蝦夷薄雪草/レブンウスユキソウ)は、北海道礼文島にのみ分布する固有種で、高山帯の草地や岩場に生えます。 利尻紫雲英 リシリゲンゲ リシリゲンゲ(利尻紫雲英)は、マメ科オヤマノエンドウ属の多年草です。リシリシウンエイとも呼ばれます。 姫石楠花 ヒメシャクナゲ ヒメシャクナゲ(姫石楠花)は、ツツジ科ヒメシャクナゲ属の常緑小低木です。別名は、ニッコウシャクナゲ(日光石楠花)です。 蝦夷伊吹虎の尾 エゾイブキトラノオ エゾイブキトラノオ(蝦夷伊吹虎の尾)は、タデ科イブキトラノオ属の多年草です。 日本最北端の離島の植物に触れる旅を終えて 以上約36種の植物をご紹介しましたが、現地では、夏の時期は咲く花が2週間ごとに代わるといわれ、短い期間しか見ることのできない花も多いようです。その年の気候によっても開花時期は異なり、高山植物を見る旅のタイミングは難しいものですが、巡り合えたときの感動と驚きは格別ですね。 ガーデニングを愛する私たちは、日常的にさまざまな品種改良された植物に接していますが、今回の旅を通して、最近、ガーデニングで人気の園芸植物のじつに多くの原種が利尻・礼文島に存在していることを知ることができました。 利尻島 Robert Harding Video/Shutterstock.com その原種が大自然の野に凛として咲く姿は、園芸品種とは異なった生命力にあふれ、パワーのある純粋な美しさでした。今回の花旅は、本当に驚きの連続でしたが、日本列島にこんなにも多くの高山植物が咲く大自然が残っていることに感動し、この自然を大切に後世に残せたらと、純粋な気持ちになりました。
-
ガーデンデザイン

【庭のリニューアル事例】オージー&イングリッシュ・ガーデンに変身
イングリッシュガーデン+オージープランツの融合に挑戦 今年4月から約1カ月半かけて、庭の一部をリニューアルしました。じつは「庭の終活」の一環なのですが、「庭の終活」については別の機会に詳しく書くことにして、今回は、僕の独自路線のオージー&イングリッシュ・ガーデンを試みたリニューアルについてレポートしたいと思います。華やかなイングリッシュ・ガーデンとワイルドなオージープランツとが融合すると、果たしてどうなるでしょうか? まずは、リニューアル後の様子です。これらの植物は、すべて鉢植えです。つまり、寄せ置きガーデンなのです。庭の終活で処分した巨大化したソテツやジャカランダの跡地を利用しました。今後の庭の終活を考え、大きくなる植物の地植えは避け、26年もののニューサイランと、胞子から育てて28年もののディクソニアの2鉢も、もともと地植えしていた株を鉢上げして移動しました。 2階から写したビフォア。 植えて6年のジャカランダは、樹高5m。樹齢60年のソテツは、株張り3m。もともとは、こんな緑のグラデーションが楽しめる鬱蒼としたトロピカルプランツのコーナーでした。 ソテツとジャカランダを移動すべく作業中の様子。なんせ、自分の背丈以上の巨大株、掘り上げるのが大変でした! この苦労話は、また次回レポートします。 木生羊歯のディクソニアとニューサイランも鉢上げした現在の姿。 想像力を働かせて試行錯誤するリニューアル作業 リニューアル前の様子です。ずいぶん暗い雰囲気で、通路の行き来に不便を感じていました。 まず、ジャカランダ、ソテツ、ニューサイラン、ディクソニアを抜き去って、すっかり空いたスペースに、今回の庭のリニューアルに活躍してくれそうな鉢植えを集めてみました。実際に鉢を並べ始めたのは5月の連休明けです。それまでは、この鉢を置くためのスペースを空けるのに時間がかかりました。 これはリニューアル途中の写真ですが、ちょうど20年前の同じ時期の写真があったので、下の写真と見比べてみましょう。 これが、同じ場所の20年ほど前です。園芸雑誌のガーデニングコンテストでグランプリを受賞し、副賞でハワイ旅行をゲットしたときの応募写真です。 正直、この20年の風景の違いは、あたかも20年歳をとった己の姿を見るようで、ショックでした。庭は主の鏡といいますから……。20年前の写真はコンテスト応募のために作り込んだ庭ですので、現在の自分の好きな植物を並べた庭と比較するものではないかもしれません。しかし、一つ明らかなことは、背景の違いです。20年前は、背景に公道の街路樹の緑が生い茂り、それが庭を引き立ててくれていましたが、今はその街路樹が枯れてしまい、近隣の家々が写り込んでしまっています。 私自身、庭のデザインをするときには、写り込ませたくない外部のものは、できるだけ植物で遮断するよう意識してきたのですが、今回はそれができていませんでした。 そこで、翌日には改良した写真を撮ってみました。少しはよくなりました。 背景になる位置に、大株のグレヴィレア・バンクシーと、銅葉ネムノキの‘サマーチョコレート’を配置しているので、もう少し季節が進んで茂ってくれば、背景の景色を遮断してくれると思います。 写真の撮り方でもずいぶん印象が変わりますが、ある程度近くで撮ったほうが、花の美しさはよく分かりますね。 これが、さらに修正を加えた冒頭と同じ位置から撮った写真です。着手から約1カ月半が経過していて、ほぼ完成に近づいた時期には、ジギタリスやデルフィニウムの花がかなり終わってしまい、ちょっと残念でした。2024年はバラも初夏の花も、見頃が短かったですね。 オージー&イングリッシュ・ガーデンの植物たち オージープランツをPick up! 今回のリニューアルに使用した植物をご紹介しておきたいと思います。 まずは、手前のオージープランツたちです。意外とジギタリスやデルフィニウムとも似合うと思いませんか? ファッショナブルな庭木として近年注目が高いグレヴィレアを4種入れています。左上から、時計回りに‘ロビンゴードン’、エレガンス、‘ココナッツアイス’、‘ピーチ&クリーム’。絶妙な花色の違いを楽しめます。 グレヴィレアの育て方は、下記の記事を参考に。 カンガルーポーも2種使用しました。右写真の2枚は、今年初めて見る色で、紫がかるカッコイイ色です。 カンガルーポーの育て方は、こちらを参考に。 米粒のように小さい花蕾が周囲の個性的な植物との繋ぎ役になってくれるライスフラワー(写真左)とニューサイランに寄り添い咲くワックスフラワー。 今回鉢上げした大物の木生シダ、ディクソニアと、ニューサイランです。ニューサイランの手前にはプルメリアを配置して、5月中旬には新芽が出てきました。8月頃にはプルメリアも咲くでしょう。 左からアガベ・アテナータ、ディクソニア、デルフィニウム、ユッカ・ロストラータ、バンクシアと、右後方は、コルディリネ‘レッドスター’。ドライ系の植物も使用してモダンな感じにしています。こうして、栽培環境が異なる植物を組み合わせることができるのは、鉢植えで集合させているからなのです。 ドライ系では、アロエベラも。 オージー&イングリッシュ・ガーデンの植物たち イングリッシュガーデン系をPick up! 手前に咲く紫の花は、カンガルーポー。 さて、イングリッシュガーデンの雰囲気を発揮してくれる植物をご紹介します。まずは、ジギタリスとデルフィニウムが咲く風景から。 存在感のあるジャーマンアイリスや、香りのよいジャスミンも使用しました。 今回は薔薇が少ないですが、20年前から我が庭に華を添えてくれる‘クィーンエリザベス’も健在です。 リニューアルを終えて思うこと 今回、「庭の終活」を念頭に、まずは、巨大化したソテツやジャカランダをお嫁に出し、このまま放置して育つにまかせていては掘り上げもできなくなりそうなディクソニアとニューサイランを鉢上げすることから始まったリニューアル。 10月にタネを播き自家製苗を作っています。デルフィニウムの栽培記事は下記から。 一念発起のおかげでスペースが空いたので、苗がたくさんできたデルフィニウムとジギタリス、そして手持ちのオージープランツの鉢植えを動員して、私が得意とする“寄せ置きガーデン”の手法で、オージー&イングリッシュ・ガーデンづくりを試みたところ、忙しい時期ではありましたが、とても楽しかったです。 2020年にプチリニューアルした別のエリア。 ふと思いついて20年前の同じ場所の写真と見比べて、一瞬ショックを受けたものの、よくよく見れば、今の庭のほうが、数段進化していると自負しております。この20年間を振り返ると、サラリーマンを卒業し、14年間はプロのガーデナーとして活動、植物園の相談員を10年近くしたり、また、『はじめてのオージープランツ図鑑』(青春出版社)を出版する機会にも恵まれました。 オージープランツマストバイ7選 この記事が掲載されている「ガーデンストーリー」サイトにも、毎月、原稿を書かせていただき、かれこれ6年(この記事でなんと100本!)。読者の皆様にも支えられ、刺激をもらい、勉強をさせていただきました。今回は、庭の一部のリニューアルでしたが、いつか残りのエリアも、今の自分が反映された庭にアップデートしたい! という願望が湧いてきています。改めて、ガーデニングって楽しいし、人生をかけられるクリエイティブな趣味だと思った次第です。 G'day, mate. 我が主の作った、オージー&イングリッシュ・ガーデンはいかがでしたか? ボクはヨークシャーテリアなのでイングリッシュ系だけれど、主の喋る英語も訛りのあるオージーイングリッシュだよ。See Ya!
-
寄せ植え・花壇

【初心者でも簡単!】ミニ観葉植物で作る「苔玉(こけだま)」
初心者向け! 観葉植物で苔玉を作ってみよう 外出はちょっと避けたいこの時期は、涼しい部屋でフレッシュな緑を楽しめる苔玉作りにチャレンジしてみませんか? 手のひらに乗るくらいの可愛いサイズ感なので、場所を選ばないのも魅力です。 苔玉の作り方はいろいろありますが、今回は初心者向けに、室内のテーブルでもできる方法をご紹介します。苔玉に使うのは、2種の観葉植物。観葉植物は室内でも育てやすく入手もしやすいので、苔玉作りにおすすめです。上の写真はこの方法で実際に作った苔玉で、製作から約2カ月経ったもの。 観葉植物で作る苔玉の材料 【材 料】 苔玉 小ぶりの観葉植物の苗(今回はネフロレピスとシマトネリコ) ハイゴケ 1シート ケト土 赤玉土 マグァンプK ハイゴケ 苔玉用糸(今回は「華の糸」) 皿 水 使用する道具 ハサミ ビニール袋 使い捨てビニール手袋 45ℓのゴミ袋 粘着テープ 寄せ植えにしたネフロレピスとシマトネリコ。 写真左がネフロレピス、右がシマトネリコ。ネフロレピスとシマトネリコは、どちらもホームセンターや園芸店の「ミニ観葉」のコーナーなどで販売されています。ハイゴケもホームセンターなどで入手できます。 ハイゴケ。 ケト土(けとつち)とは、湿地や沼地に生えるマコモやヨシなどの水辺植物が水底に堆積し、分解してできる黒色の土です。繊維分を多く含み、粘着性が強く保水性にも優れています。苔玉や盆栽、ビオトープに向いている土です。苔玉や石付盆栽などの接着剤としても使用されます。大袋のほか、苔玉用として小袋に分けた製品もネットで見かけます。 苔玉をのせる皿は、家にある不要のモノでOK! なんでもよいのですが、グリーン系の皿のほうが調和しやすく落ち着きます。ハサミはクラフトバサミなどお手持ちのもので。苔玉を形作るために使用する糸は、黒い木綿糸を使う場合もありますが、私のおすすめは「華の糸」というグリーンの針金です。手芸店で入手できます。 テーブルの上が汚れないよう、45ℓのゴミ袋を敷いて四方をテープで留めておくと、ストレスなく作業できます。 苔玉の作り方 ケト土の準備 ケト土(左)と赤玉土。両手で包み込んで大きな球ができるくらいの量を用意してください。 1.ケト土と赤玉土を7:3で混ぜ、マグァンプKも少量加えます。 ケト土と赤玉土、マグァンプKをビニール袋に入れ、水を少しずつ加えながらよく混ぜ、丸くした状態。混ざったら、さらによく捏ねて粘り気を出します。 水を加える量は、耳たぶぐらいの柔らかさが目安です。 2.ビニール袋の上に1の土を置き、ボール状にした後に、直径20cm程度まで薄く広げます。 観葉植物を包む 3.シマトネリコとネフロレピスをポットから出し、根鉢はそのままに周囲の余分な土を取り除いて形を丸く整えたら、2の土の上にのせます。 4.ビニール袋ごと根鉢を包んで握り、団子状にします。崩れないようにしっかり握りましょう。 ハイゴケで包むときのポイント ここからの作業は、ハイゴケを崩さずに、上手に苔玉を包むためのステップです。作業するときは、おにぎりをラップで包んで握るように、ハイゴケをビニール袋ごと包む状態のほうがやりやすいので、その準備をします。 5.ハイゴケを裏返しにします。裏返し方は、まずハイゴケの表面にビニール袋を被せ、ビニール袋の上に崩れ防止の新聞紙をのせ、ひっくり返します。 根が下の状態の苔の表面にビニール袋を被せ、さらにその上に新聞紙をのせて…。 新聞紙が下になるようにひっくり返します。 ハイゴケの裏側(根がある面)に台紙がついた状態。 こうすることで、ハイゴケの形を崩さずに裏返して、ビニール袋の上にのせることができます。 ハイゴケで包む 6.裏返したハイゴケに観葉植物をのせます。 ハイゴケの台紙として敷かれていた紙をはがし、4の観葉植物を置きます。 7.最初はビニール袋ごと苔玉をくるみ、しっかり握り固めて苔と土を密着させます。その後、ある程度形が整ったらビニール袋を剥がし、手に持って直接苔玉を握り、形を整えます。 ハイゴケの下に敷いておいたビニール袋で、ハイゴケと土玉をくるんで握ります。 ビニール袋をはがして仕上げ。 糸をかけて完成 8.最後に、華の糸で苔を固定させます。 苔玉全体に糸をかけ、ハイゴケをしっかり固定します。 糸が見えにくいので、端にテープを貼って目印を作っておきましょう。テープがついたスタートの糸端を上にして、苔玉全体にグルグルと均等に巻き(垂直や放射状など球になるのをイメージして)、最後にテープを貼った糸端を一緒にねじって留めます。 最後にスタート部分の糸とねじり合わせて留めます。 9.皿の上に苔玉をのせて、飛び出した苔を切り落として整え、完成です。 苔玉の管理方法 皿の色が変わると雰囲気も一変。 完成した苔玉は、直射日光の当たらない明るい室内に置き、苔が乾いたら霧吹きで湿らせます。霧吹きに加え、数日に1回程度、苔玉部分をバケツの水に浸け、湿らせるとよいでしょう。緩効性肥料を土に混ぜてあるので、半年程度は施肥の必要はありません。その後は、2週間に1回程度を目安に液肥を与えます。 バケツに水を張り、苔玉部分を沈めて水やりを。 苔玉をのせる皿によって、ずいぶん雰囲気が変わります。いろいろ試して気分を変えるのも楽しいですね。 シマトネリコとネフロレピスの育て方 今回寄せ植えに選んだシマトネリコは、亜熱帯から熱帯に育つモクセイ科の半常緑樹です。明るい屋内でも、半日陰の屋外でも育てられる丈夫な樹木で、近年、日本でもシンボルツリーや観葉植物として人気です。 5~6月に花が咲くので、花後に剪定しましょう。 ネフロレピスはシダの仲間なので耐陰性が強く、直射日光の当たらない明るい場所で育てます。耐寒性が弱いので冬は屋内に入れ、レースのカーテン越しに日が当たるような場所で育てます。乾燥を嫌うので、こまめに霧吹きをすると綺麗に育ちます。 あなたのお部屋にも外の緑に負けない、爽やかなグリーンの苔玉を作って飾ってみませんか? 以前、クリスマスローズの苔玉作りもご紹介したことがありますので、ぜひこちらにも挑戦を。いろいろな植物で、苔玉作りをお楽しみください。























