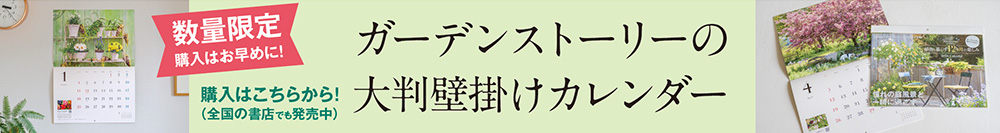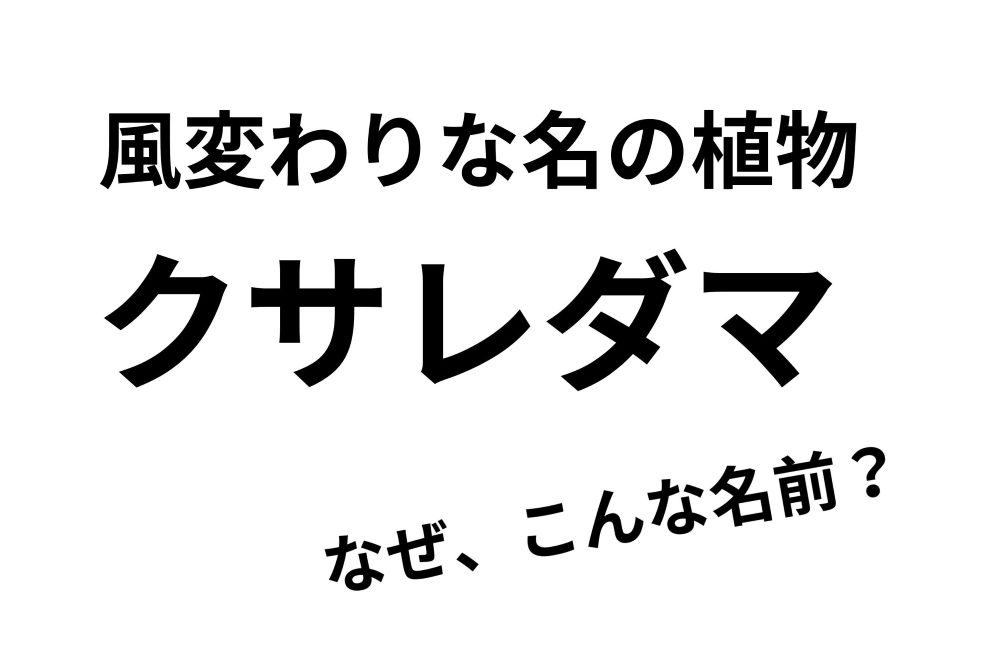花の女王と称され、世界中で愛されているバラ。数多くの魅力的な品種には、それぞれ誕生秘話や語り継がれてきた逸話、神話など、多くの物語があります。数々の文献に触れてきたローズアドバイザーの田中敏夫さんが、バラの魅力を深掘りするこの連載で今回取り上げるのは、フランス最後の王、ルイ=フィリップの庭園丁アンリ・アントワーヌ・ジャックが育種したバラたち。彼が手がけた美しいバラと、花にまつわるエピソードをご紹介します。
目次
アンリ・アントワーヌ・ジャック
アンリ・アントワーヌ・ジャック(Henri Antoine Jacques)は、王族であるルイ=フィリップ、オルレアン公(Louis-Philippe, duc d’Orléans:1773- 1850)が所有するヌイイ城(Château de Neuilly;パリの西郊外、セーヌ河沿いに所在)の庭園丁でした。広大な庭園の中には規模は大きくないもののバラ園があり、ジャックはバラの管理に加え、育種にも携わっていました。今回は、このアンリ・アントワーヌ・ジャックが生み出したバラをご紹介します。
ルイ=フィリップ、フランス最後の王

ルイ=フィリップはブルボン王家につながる王族のひとりでした。啓蒙主義の教育を受けたことが影響したのでしょう、革命派のジャコバン・クラブのメンバーとして共和制に与したこともありましたが、いざとなると出自である王党派の顔が露骨に出て共和制支持者の不興を買うなど、その豹変ぶりが疎んじられた時期もありました。
ナポレオンの没落後、フランスの政権が復古王制、共和制とめまぐるしく変転していた時代、彼は共和制支持者が多い資本家たちを後ろ盾に、1830年から1848年にかけてルイ=フィリップ1世として王位に就きました(7月王政)。
ルイ=フィリップが王位に就いていた時代は絶対王政ではなく立憲君主制に近い政体でしたが、1848年の二月革命の勃発により共和制が復活した際、フランスの王制は終焉を迎えました。こうしてルイ=フィリップはフランス最後の王となりました。
園芸家としてのアンリ・アントワーヌ・ジャック
ジャックは『オールドローズ~黎明期の育種家たち』でご紹介したデズメとともに、フランスにおける最も先駆的な育種家のひとりとして知られています。
1782年、ジャックは園芸一家に生まれ、長じてから兵役につきましたが、それを終えた後、大トリアノン宮殿のガーデナーとなり経験を積み重ねていました。その造園技能をナポレオン一世に称賛されたことから、彼の心酔者となったようです。人生の目標は、ナポレオンが住まう館の庭園丁となることだったと伝えられています。
1818年、ジャックは、ルイ=フィリップ、オルレアン公が保有するパリ郊外のヌイイ城(Château de Neuilly)の庭園丁となったことは冒頭で触れた通りです。
ルイ=フィリップは熱心な植物愛好家でもありました。ジャックはルイ=フィリップの意を受け、シクラメン、ロベリア、プリムラ、ヴェロニカなどの蒐集、改良などを行いました。また、ジャックは1827年に設立されたパリ園芸協会の創立メンバーのひとりでした。この協会は、1885年にはフランス園芸協会へと発展することになります。
ルイ=フィリップがフランス王であった時代は、ジャックがバラ育種に熱心に取り組んだ時期と重なっています。彼の育種したバラは主に、ヨーロッパ原産のロサ・センペルヴィレンス(R. Sempervirens)を交配親にしたシュラブやランブラー。原種の特徴である小輪花を豪華絢爛と咲かせるランブラーを作り出すことに熱心に取り組みました。

アンリ・アントワーヌ・ジャックが生み出した代表的な品種
ジャックが育て、ルイ=フィリップが愛でたランブラーたちを、いくつかご紹介しましょう。
アデライド・ドルレアン(Adélaïde d’Orléans)- 1826年

花色はクリーム色または純白。豪華な房咲き、柔らかな枝ぶりのランブラーとなります。大株になると、じつに見事です。
古い記述やイラストでは、つぼみは紅に近いピンク。開花するとクリーム色から白へ移ってゆくとされています。現在、‘アデライド・ドルレアン’として出回っているものの中には、つぼみのときから純白であるものもあり、花形はよく似ているものの、オリジナルとは違う品種ではないかと思われています。
原種ロサ・センペルヴィレンスを用いた交配種であることは明確ですが、詳細な情報は伝えられていません。
ルイ=フィリップの妹アデライド(Adélaïde d’Orléans :1777-1847)に捧げられました。

アデライドは、オルレアン公である兄ルイ=フィリップが1794年、フランス共和制議会から”反革命”の烙印を押されて亡命を余儀なくされた後、1801年にアメリカへ亡命しました。アメリカの富裕な商人と結婚し4人の子供をもうけましたが、ルイ=フィリップがナポレオン失脚後の王制復古の機運により1814年にフランスへ帰国した折、アメリカの家族の許を離れ、兄と暮らす道を選択しました。
生まれながらの聡明さと長い海外生活から、母国語であるフランス語のほか、英語、イタリア語、ドイツ語に堪能で、兄ルイ=フィリップを政策上でもよく支えました。
この品種が彼女へ捧げられた時、フランスは王制復古派の勢力が優勢で、それゆえに安寧な毎日を送っていた時期でした。4年後の1830年、ルイ=フィリップはフランス国王となります。彼は1848年に王位を追われてしまいましたが、アデライドはそれ以前に生涯を終えたため、兄の零落を見ることはありませんでした。
フェリシテ・ペルペチュ(Félicité-Perpétue)- 1828年

多弁、つぼ咲きの小さな花が、ひしめくような房咲きとなります。
ピンクに色づいていたつぼみは、開花すると淡いピンクが入ることがありますが、次第に純白へと変化します。丸みのある、深い葉色。細く、柔らかな枝ぶり。樹高450〜600cmまで枝を伸ばすランブラーです。耐病性に優れ、多少の日陰にも耐え、花を咲かせます。トゲも少なく、取り扱いが容易です。温暖地域では葉をつけたまま冬季を越すことができるほどの強健種ですが、逆に冷涼地域での生育には難しい面があるようです。
ロサ・センペルヴィレンスといずれかのノワゼットとの交配により生み出されたといわれています。
キリスト教の教えを守って殉教した聖フェィチタス(St. Felicitasu)と聖ペルペトゥア(St. Perpetua)にちなんで命名されました。
ジャックは、生まれてくる子供にちなんでこのバラに命名しようとしていましたが、双子の娘が生まれたため、同時に殉教した聖人、フェリシテ(Félicité)と ペルペチュ(Perpétue)にちなんで命名したという説もあります(”A Rose Odyssey” by J.H. Nicolas, 1937)。

2人の聖人は、3世紀初頭、ローマ帝国によるキリスト教者迫害時代、カルタゴで捕らえられ棄教を迫られましたが肯んぜず、猛獣の餌食となって殉教しました。裁判官に「今、あなたは私たちを裁いていますが、今に神様があなたを裁かれるでしょう」と語ったと伝えられています。
フローラ(Flora)- 1830年
小輪の花が数十輪も集う房咲きとなります。花弁が密集した、オールドローズのケンティフォリアのような花形が優雅です。しばしば、花心に緑芽が生じます。
クリムゾンに色づいていたつぼみは、開花するとライラック・ピンクの花色へと変化しますが、花弁の縁に濃い色が残ることが多く、微妙で繊細な色合いとなります。深い緑、とがり気味のつや消しの葉、細く、柔らかな枝ぶりのランブラー。
センペルヴィレンス交配種であることは明らかですが、詳細は不明のままです。
「センペルヴィレンス交配種の中では最も強健で、最高の品種のひとつだ…」(Charles Quest Riston, “Climbing Roses of the World”)とまで賞賛される品種です。センペルヴィレンス交配種では、‘フェリシテ・ペルペチュ’が最も広く植栽されていると思われますが、このライラック・ピンクの美しい品種も、もっと愛されてもよいように思います。
レーヌ・デ・ベルジュ(Reine des Belges)- 1832年
小輪、カップ形の花が房咲きとなります。白地に刷毛ではいたようにピンクが入っていたつぼみは、開花すると純白となります。センペルヴィレンス交配種に特徴的な深緑のつや消し葉、細い枝ぶり、樹高350〜500㎝に達するランブラーとなります。
ルイ=フィリップの長女、ルイーズ=マリー・テレーズ・シャルロット・イザベル・ドルレアン(Louise-Marie Thérèse Charlotte Isabelle d’Orléans;1812-1850)に捧げられました。

ルイーズ=マリーは1832年、ベルギー国王レオポルド1世(1790-1865)と婚礼の式を挙げました。この品種の命名は、ご成婚のお祝いの意味があったものと思われます。3男1女に恵まれましたが、後に王位を継いだ次男レオポルド2世の悪政を見ることなく世を去ったのは、ある意味幸運だったのかもしれません。
英語の翻訳名「クィーン・オブ・ザ・ベルジャンズ(Queen of the Belgians)」と呼ばれることもあります。また、1867年におそらくコシェにより育種されたとされる、まったく同名のピンクのHPがあり、市場での混乱を招いています。
プリンセス・マリー(Princesse Marie)- 1829年

小輪、すこし閉じ気味の愛らしい花形、花束のように密集して開花するさまは、じつに見事です。濃いピンクに色づいていたつぼみは、開花するとラベンダー気味の明るいピンク、やがて淡い色合いへと移ろい、終わりにはほとんど白色へ。そのため、株全体は花色がグラデーションとなります。
深い緑色の葉、500cmに達することもある大型のランブラーとなります。
ルイ=フィリップの次女、マリー・クリスティーヌ・カロリーヌ・アデライード・フランソワーズ・レオポルディーヌ・ドルレアン(Marie Christine Caroline Adélaïde Françoise Léopoldine d’Orléans;1813-1839)に捧げられました。

マリー・クリスティーヌは、芸術、文芸にすぐれた才能を発揮しました。上に表示したマリー・クリスティーヌの肖像画の作者であるアリ・シェフェールに師事し、とくに彫像にすぐれた才能を発揮しました。ルイ=フィリップが王位に就いていた時代、テュイルリー宮殿内に専用のアトリエを持ち、制作にいそしんでいましたが、作品は王女の“手慰み”と呼ぶレベルをはるかに超えた高みに達していました。
作品の多くは政争の混乱の際、破壊されてしまいましたが、“祈るジャンヌ・ダルク像”など数点が残されています。

1837年、姉ルイーズ=マリーの夫であるベルギー王レオポルド1世の甥にあたるヴュルテンベルク公アレクサンダー・フォン・ヴュルテンベルク(Friedrich Wilhelm Alexander von Württemberg)と結婚しましたが、2年後の1837年、結核が悪化して若くして死去しました。
ジャックと最初のブルボン・ローズ、イル・ド・ブルボン
ジャックは、ブルボン・ローズがヨーロッパにもたらされたときに深く関わったことでも知られています。
イングランドのバラ研究家トーマス・リバースは、著作『ローズ・アマチュアズ・ガイド(Rose-Amateur’s Guide)』(1843年刊)の中で、ブルボン・ローズの由来について、フランスの園芸家ブレオンが伝えた話を紹介しています。
「ブルボン島(註:現在のインド洋レウニオン島)では、住民は一般的に自分の住居を2種のバラの生け垣で囲うが、それは、一つはコモン・チャイナ・ローズ(註:‘オールド・ブラッシュ’のこと)、もう一つはレッド・フォー・シーズンズ(註:赤花のオータム・ダマスク)だった。
サン・ブノワ(St. Benoist)の所有者であるペリション氏は、そんな生け垣の中に樹形やシュートが他と著しく異なる小さな若苗が生えているのを見つけ、それを自分の庭に植えてみることにした。その若苗は翌年花開いたが、それは上述の2品種とは明らかに違う、新しい品種と思われた。けれども、そのことはブルボン島の中でのみ知られていることだった。…1817年、ブレオン氏は、フランス政府派遣の植物園管理者として島を訪れた。そして、この品種を多数育成し、株と種を本国(フランス)、パリ近郊のヌイイ館の庭園師であったジャック氏へ送った。ジャック氏はこれをフランス国内のバラ育成者へ出荷した…ブレオン氏はこの品種をブルボン島のバラ(Rosier de l’Ile de Bourbon)と名付けた」
もう一つの説として、同書の中でリバースが伝えているのは次のようなものです。
「あるフランスの海軍士官は、ブルボン島の住民であった故エドワールド氏の夫人にインドへの航海の際、珍しいバラを持ち帰ってほしいと依頼された。その帰途、海軍士官はこのバラを持ち帰り、夫人はそれを夫の墓前へ植え付けた。そして、このバラはロズ・エドワールド(Rose Edouard)と呼ばれ、(その結実が)フランス本国へブルボン島のバラ(Rosier de l’Ile de Bourbon)として送られた…」
リバース自身は、後者の説は真実味が欠けると述べ、先に記述した自然交配説に重きを置いています。しかし、最近の理解は、むしろ後者のほうが正しいのではないかというものです。
すなわち、ジャックは‘ロズ・エドワールド’の実生から育った株にブルボン島のバラと命名して市場へ提供したのだろうというものです。
しかし、疑問は完全に解消されたとはいえません。
現在、‘ロズ・エドワールド’の名で流通している品種は明るいピンク、しかし、‘ロジエ・ド・リル・ド・ブルボン’は、販売している農場により、明るいピンクであったり、赤花と呼んでいいほど濃い色合いのものであったりと変化が大きく、はたしてそれらが本当に同じものなのかという疑問があります。
はじめの説に従うと、ブルボン・ローズが”赤花”である理由に説明がつきますし、ピンクのほうが本来のものであれば、後者の説に説得力があります。
この謎はいつ解けるのでしょうか。


(註)ジャックのフル・ネームについては、Antoine A. JacqueとするものとHenri Antoine Jacqueとするものがあります。この記事ではHenri Antoine Jacqueを正としました。
おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)
優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。
新着記事
-
ガーデン&ショップ

「第4回東京パークガーデンアワード夢の島公園」ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート
2025年12月中旬、第4回目となる「東京パークガーデンアワード」の作庭が、夢の島公園(東京・江東区)でスタートしました。 作庭期間の5日間、書類審査で選ばれた5人の入賞者はそれぞれ独自の方法で土壌を整え、吟…
-
イベント・ニュース

冬に咲くチューリップ!? 今だけ見られるアイスチューリップの名景色、特徴、入手方法を一挙紹介
冬の澄んだ空気の中、思いがけず出会うチューリップの花。枯れ色の多い季節に、春のような色彩がふっと現れる――それが「アイスチューリップ」です。冬にもかかわらず、色鮮やかな花を咲かせるアイスチューリップが…
-
宿根草・多年草
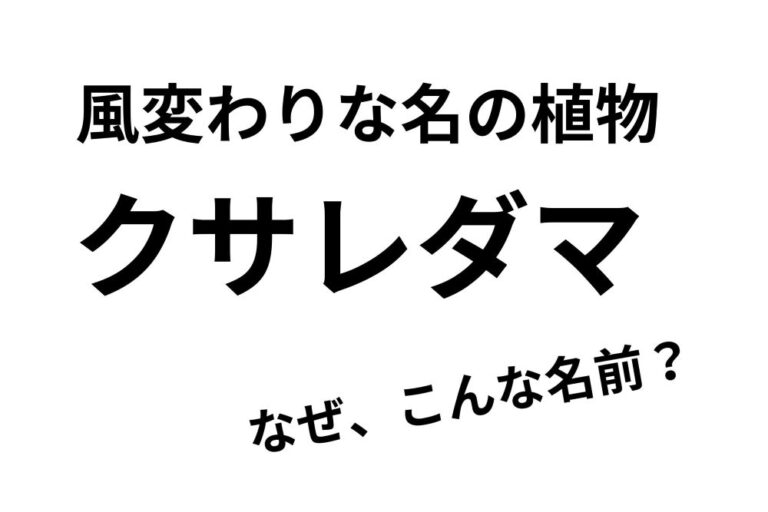
これ何だ?「クサレダマ」|風変わりな名前をもつ植物たち
「クサレダマ」——。まるで妖怪か、あるいは妖怪が振り回す武器のような名前だと思いませんか。そんな禍々しい名のものをぶん投げられたら、ひどいことになりそうな予感。でも、じつはクサレダマは「腐った玉」でも…