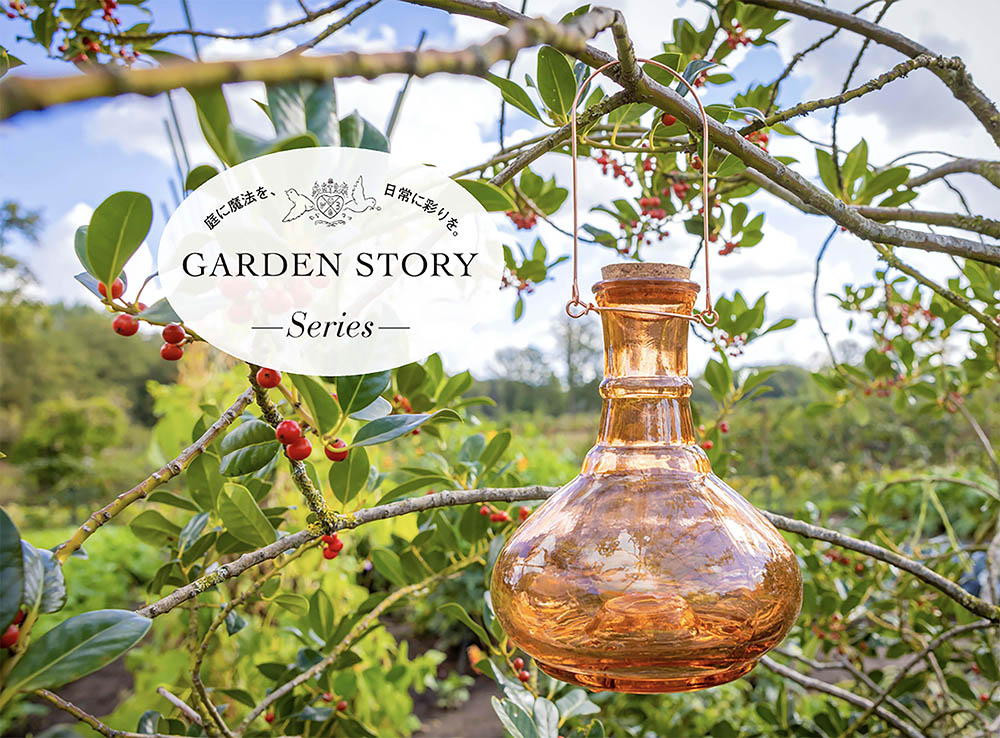- TOP
- 花と緑
- 観葉・インドアグリーン
- 【決定版】パキラの育て方完全ガイド! 初心者も安心のコツから風水効果・種類まで徹底解説
【決定版】パキラの育て方完全ガイド! 初心者も安心のコツから風水効果・種類まで徹底解説

Robert MacMillan/Shutterstock.com
代表的な観葉植物として人気のパキラは、環境適応力が強く丈夫で育てやすいため、園芸初心者の方にも非常におすすめです。また、風水的には運気を上げる縁起の良い植物としても知られ、おしゃれなインテリアとして住まいの雰囲気を高めてくれます。この記事では、基本情報から枯らさずに育てるための詳細なコツ、運気を高める風水効果、日本で流通している代表的な種類まで、パキラに関するあらゆる情報を詳しく解説します。あなたのお部屋にパキラを迎えて、素敵なグリーンライフを始めましょう。
目次
パキラの基本情報

植物名:パキラ
学名:Pachira
英名:Guiana Chestnut、Money Tree
和名:カイエンナッツ
別名:発財樹
科名:パンヤ科
属名:パキラ属
原産地:中南米
形態:木本植物、常緑高木
パキラは耐陰性に優れるため、室内に飾って楽しまれることが多い植物です。形態は低木から高木に分類され、学名をPachiraで、パンヤ科パキラ属の木本植物です。原産地は中南米で、メキシコから中米の熱帯アメリカにかけて分布しています。株が成熟し、適した環境で育つと、パンヤ科らしい可憐な花が咲きます。カイエンナッツともいわれ、現地では炒って食用にされることも。熱帯域に自生しているため耐暑性は強く、日本の夏の暑さも平気ですが、その反面、耐寒性は弱く、耐えられる最低気温は5~10℃前後です。
パキラの花や葉の特徴

園芸分類:観葉植物
開花時期:6〜7月
草丈・樹高:10cm〜20m
耐寒性:弱い
耐暑性:強い
花色:赤、白
パキラは熱帯のジャングルの川沿いなどに自生しています。樹の高さは最大で約20m。成長すると幹がとっくり状にずんぐりと太くなり、葉の軸を長く伸ばして、その先端に5~7枚の小さな葉をつけます。葉は長楕円形で皮革質の光沢のある緑色で、やや厚めです。
比較的乾燥に強いのですが、雨期には水没するような場所に自生しているため、多湿な土壌でも育ちます。園芸店などで水耕栽培のようにして販売もされているのは、そのため。
園芸分類では観葉植物に分類されます。とても丈夫で育てやすいため、初心者にもおすすめの植物です。
パキラの花言葉や名前の由来

パキラの名前は、原産地「ギアナ地方」(南アメリカ大陸の北東部から太平洋に面した地方)での呼び方からきています。「カイエンナッツ」「発財樹(MoneyTree)」という別名を持ち、前者はパキラの実の名前から、後者は「新しい芽が次々と出てくるパキラをたくさん売ったら大金持ちになった」という言い伝えを由来としています。
花言葉は「快活」「勝利」。別名と同じく、パキラを売ってお金持ちになったという言い伝えや、生命力が強くて丈夫な様子からきています。
パキラの風水効果

パキラは、室内に観葉植物として置くことで、風水的にもよい効果をもたらすといわれています。葉の形からよい気を発し、悪い気を鎮めてくれるのだとか。得たい運気の流れが活発なところに置くと効果があるそうで、方角としては、金運や商売繁盛の運気を強めたい場合は西、または北西に、仕事運を強めたい場合は東、北西、南西に飾るとよいとされています。また調和をもたらしてほしい場合は、人通り(出入り)の多い場所に飾りましょう。
パキラの代表的な種類
パキラには20種類ほどの品種があるといわれていますが、日本で流通している種類はそれほど多くありません。主な4種をご紹介します。
パキラ・グラブラ


日本で最も流通している品種の一つ。花は白、実は緑色。濃い緑の葉を茂らせます。定番品種で、花屋やホームセンターで入手できます。
次に紹介するパキラ・アクアティカと似ていますが、葉の形がより尖っているのがグラブラの特徴です。
パキラ・アクアティカ

アクアティカも日本で広く流通している品種の一つ。淡いピンクから黄色の花弁に、雄しべの先端赤く色づく特徴的な花を咲かせ、実は赤茶。グラブラよりも葉が丸みを帯びています。
園芸店などで、幹の部分がおしゃれに編まれて販売されていることも多い品種です。
‘ムーンライト’
葉にライムグリーンの斑模様が入っている珍しい品種。太くしなやかに曲がった太い幹が特徴です。
‘ミルキーウェイ’
「ミルキーウェイ=天の川」の名が示すように、星の煌めきをイメージさせる美しい斑入り葉が楽しめる希少品種。他の品種と同様にて気温を保ち、葉焼けに注意して葉色を保ちましょう。
パキラの栽培12カ月カレンダー
開花時期:6月〜7月
植え替え適期:5月〜9月
肥料:4月〜9月
入手時期:通年
植え付け時期:通年
パキラの育て方

パキラはとても丈夫な植物ですが、適した環境で健やかに育てることで、長期にわたってより丈夫で枝ぶりのよい姿が楽しめます。ここでは育て方のポイントをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
パキラの栽培環境
日当たり・置き場所

【日当たり/屋外】日当たりと風通しがよい場所で育てます。
【日当たり/屋内】週に2〜3回は窓際や屋外など日当たりのよい場所に移動しましょう。
【置き場所】
外で育てる場合、春から秋にかけては明るくて風通しのよい場所に置くようにしましょう。夏は、午後からは日陰になる場所へ。
ある程度の耐陰性もあるため、屋内で通年育てることもできます。その場合はひょろひょろと伸びる「徒長」が起きやすくなるので、週に2、3回は窓際などの明るい場所や、屋外の日当たりのよい場所に移動しましょう。エアコンの風は苦手なので、風が直接当たらない場所で管理します。
また、室内から屋外に急に移動すると、環境の違いについていけず葉を落としたり、急に直射日光に当ててしまうと葉焼けを起こすことがあります。屋外に出す際は、徐々に明るさに慣らすようにしましょう。
温度

熱帯原産の植物なので比較的高い温度を好み、16〜25℃が栽培適温です。寒さに弱いので、春〜秋はベランダなどの屋外で育てている株も、冬は室内に取り込みましょう。室温が10℃を下回ると落葉して活動が止まり、休眠状態になります。
パキラの育て方のポイント
用土

用土は水はけのよいものが適しています。観葉植物用に配合された用土も販売されているので、それを使うのもいいですし、室内管理でもう少し乾きやすい土がよいということであれば、観葉植物用の用土に赤玉土と鹿沼土を2:1:1程度の割合で配合するなどして、生育環境に合わせて調整するのがよいでしょう。
観葉植物用の用土には腐葉土やピートモスなどの有機質が使われており、場合によってはコバエなどが発生することがあります。気になる場合は、赤玉土や軽石、化粧砂など無機質の用土で表面を覆うことで、発生をある程度抑えることができます。
また、前述のようにパキラは水への耐性も高いことから、水に浸したセラミスやハイドロボールなど無機質の用土に植え付けて栽培することも可能です。
水やり

水やりのタイミングと水の量は、季節によって調整するとよいでしょう。生育期は、用土が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。乾燥にも強いので、用土が乾ききってしまったあとでも大丈夫。
生育が緩慢になる冬や、葉が落ちてしまったときなどは、水やりを控えめにしましょう。鉢の大きさにもよりますが、乾かし気味に管理し、水やりの間隔は2週間から1カ月に1回程度でかまいません。また定期的な葉水(霧吹きなどで葉に水をかける)を行い、埃を落として葉を清潔に保ち、病害虫を予防しましょう。
肥料
肥料はあまり必要としませんが、緩効性肥料や液体肥料を生育期に少量与えると生育が早くなります。ただし、適正量を超えると肥料焼けを起こして根が傷んでしまい、最悪の場合枯れてしまうこともあるので、肥料の容器などに書かれた規定量と頻度を守って与えるようにしましょう。
パキラの詳しい育て方

パキラは成長速度が早く、環境が適していると大きくなりすぎて手に負えなくなってしまうことがあります。反対に、パキラを大きくしたいのに適切な管理ができていないと生育が緩慢になることも。ここでは、思い描くサイズ感や枝ぶりにするためのお手入れの方法について解説します。
選び方

パキラは、園芸店に行くと小さい苗から大きく育った大型のものまで、さまざまなサイズが並んでいます。価格もそれに応じて変わるので、自分の好みに合ったものを選んで購入しましょう。また選ぶ際は、葉が青々としてよく茂り、幹のしっかりしたものがおすすめです。
種まき

パキラは種子から育てることができる観葉植物です。種子から育てた株は「実生株(みしょうかぶ)」となり、自然樹形が楽しめて、個性的な花が咲くことも期待して育てる人もいます。ただし、開花までは最低でも5年はかかるとされており、難易度は高いでしょう。
パキラの種子は、実生株から採取するか、まれに園芸店や通販で入手できることもありますが、採取して半月〜1カ月程度で発芽力を失ってしまうため、新鮮な状態の種子を購入することが大切です。
種子を入手したら、下記の手順で土に植えましょう。
1. 水没検査をする
種を水の入った容器に入れて、種を1〜2日間吸水させます。この段階で水の底に沈んだ種は発芽する可能性があるので、沈んだ種を選別します。
2. 水苔で包む
選別した種は、発芽するまで湿らせた水苔で包みます。20℃程度の暖かい場所に、種が乾燥しないように管理しながら置いておくと、早くて2日ほどで発芽が始まります。
3. 発芽したら殻をむく
発芽が進むと殻が割れてくるので、手で取れそうな場合は丁寧に殻をむきます。発芽したての芽(=胚)が2〜3cmになるまで育てます。
4. 鉢に植え付ける
胚が2〜3cmになったら、赤玉土の入った用土(前出の「用土」の項目参照)に植え付けます。赤玉土を敷き詰めて十分に湿らせ、その上に胚を半分ほど埋まるように植え付けて、葉が出てくるまで上から水苔を被せておきます。
その後、胚が育ち双葉が出て発根し、双葉が芽生えたら、日当たりのよい場所へ鉢を移動させましょう。
剪定・切り戻し

パキラが大きく育ちすぎたり、屋内管理で徒長してだらしない姿に乱れてしまったときは、切り戻す剪定をしましょう。その際、枝の根元にある成長点より2cmほど上の位置で切り取ると、成長点から新しい枝が出てきて更新ができます。幹や枝の表面にある、節のように膨らんでいる茶色い部分が成長点です。
パキラは挿し木で増やすことができ、また切った枝を水につけておくと根が出てくるので、そのまま水耕栽培で育てたり、鉢植えにすることもできます。その際は、切り取った枝の葉の先を切り落としておくと、その後の生育が順調に進みます。
植え替え・鉢替え

パキラは根の生育も早いため、定期的な植え替えが必要となります。植え替えをしないと根詰まりが起き、生育が緩慢になってしまうので、大きく育てたい場合は1〜2年に1回、一回り大きな植木鉢に植え替える「鉢増し(はちまし)」をしましょう。コンパクトに育てたいのであれば、植え替えの時に鉢のサイズは変えずに植え直します。根の周りの古い土を1/3程度落とし、傷んで黒ずんだ根を取り除いた後、新しい土を補充してください。
植え替え直後は微細な土の粒がたくさんあり、そのままにしていると土が目詰まりする原因に。鉢底から流れ出る水が透明になるまで、たっぷりと水やりをしてください。
増やし方

パキラの増やし方には、主に挿し木と種子繁殖があります。
挿し木の適期は5~9月。挿し木用の土は、バーミキュライトや鹿沼土、挿し木専用の用土も市販されているので、それらを使うのもよいでしょう。挿し木用のトレーにまとめて挿したり、ポリポットに1本ずつ挿してもよいでしょう。水を切らすと発根が遅くなるので、水切れさせないように管理を。1カ月ほどで新芽と根が出てくるでしょう。
また種子繁殖(実生)に挑戦する場合は、まれに園芸店やネットショップで入手できたり海外から種子を輸入するのも一案ですが、入手はやや困難です。
夏越し
外で育てる場合、日本の真夏の直射日光下では葉焼けを起こすことがあるので、午後からの強い直射日光を避けるために日陰になる場所に置くとよいでしょう。そうした置き場所がない場合は、西側に簡易なフェンスを設けたり、遮光するシェドを設置するか、株が大きくて強い日光にも耐えるオリーブなどの鉢植えを置くなど、日差しを遮る工夫をするのがおすすめです。
室内で育てる場合、暑すぎると高温障害も起きるので、夏場に閉め切った部屋に置きっぱなしにすることはやめましょう。
冬越し
耐寒性は弱いので、屋外で育てている場合も冬は室内に取り込みましょう。冬も生育させたい場合は最低15〜16℃以上、葉が落ちるのを防ぐためには最低10℃以上の室温が必要です。室温が10℃を下回ると落葉して活動が止まり、休眠状態になります。
パキラのよくあるトラブルと対処法
病害虫

パキラは病害虫に強く、栽培適地で健康に育っている株であれば、あまり心配することはありません。ただ空気の乾燥する時期や屋内管理で風通しが悪いときなどは、ハダニやアブラムシ、カイガラムシなどの害虫が発生することがあります。葉色が悪くなったり、葉の色が抜け落ちる、あるいは葉の基部などに白い物が付いていたりしたら害虫が潜んでいる可能性があるので、葉裏などもしっかり観察しましょう。
害虫を見つけた場合は早めの対処が肝心です。早期であれば葉水などで害虫を洗い流したり、捕殺したりしましょう。ある程度広がっている場合は、スプレー式の適用のある薬剤を噴霧するのもよいでしょう。その際は、葉裏もお忘れなく。
葉焼け
パキラは、強い直射日光があたり続けると葉焼けしてしまうことがあります。葉焼けとは、葉が強い光を浴びて、葉先から茶色や白色に変色してしまうこと。
それまで室内に置いていた株をいきなり直射日光に当てると葉焼けを起こすこともあるので、屋外に出す際は、最初は直射日光が当たらない場所で1週間ほど明るさに慣らしながら徐々に移動させるようにしましょう。
一度葉焼けしてしまうと元には戻らず、そのままにしておくと株全体が枯れることもあります。対処法としては、置き場所を変えるなどの工夫をし、葉焼けした葉を切り取って新しい葉が出るのを待ち、元気な葉だけ残すようにしましょう。
根腐れ
根腐れとは、土が常に湿った状態で根っこから酸素が吸収できなくなり、呼吸ができなくなって腐ってしまうことです。葉が黄色くなる、幹がブヨブヨとやわらかくなる、などの変化が見られたら、その症状はかなり進行しており、そのまま放置していると、やがて株全体が弱り、枯れてしまいます。
根腐れの症状が初期の場合、鉢受けの水を捨てて土を乾燥させ、日当たりと風通しのよい場所に移動させてしばらく水やりを控えることで、復活の可能性はあります。
根腐れを防ぐためにも、水やりの頻度は前述のように「用土が乾いてから」を守るようにしましょう。
パキラを育てて素敵な空間を楽しもう

パキラの特徴から具体的な育て方まで幅広く解説しました。パキラは育てやすく風水的にも縁起がよいとされ、大変人気のある植物です。サイズや樹形もさまざまで、自分のお気に入りのものを選ぶ楽しさもあります。部屋にグリーンがあるとみずみずしい空間になり、緑が日々の生活に癒やしを与えてくれますよ。この記事を参考にして、ぜひ素敵にパキラを育ててみてください。
Credit
文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!
- リンク
記事をシェアする
新着記事
-
育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR
今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…
-
ガーデン&ショップ

【秋の特別イベント】ハロウィン色&秋バラも開花して華やぐ「横浜イングリッシュガーデン…PR
今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、10月31日(金)まで「ハロウィン・ディスプレイ」…
-
イベント・ニュース

まちづくりを支える花とみどり…みつけイングリッシュガーデン、一人一花運動、中之条ガーデンズの事例 〜…
40年以上の歴史を持つ老舗業界専門雑誌『グリーン情報』最新号から最新トピックスをご紹介! 2025年9月号の特集は、「まちづくりを支える花とみどり」。そのほかにも、最新のイベント紹介はじめ園芸業界で押さえて…