鎌倉時代に成立したとされる『平家物語』の冒頭に登場する沙羅双樹とはどのような植物なのか、興味がある方も多いのではないでしょうか。仏教に深いかかわりを持ち、インドでは聖なる木として人々に大事にされている沙羅双樹について深掘りするとともに、日本におけるサラノキ(沙羅の木)の特徴やよく似た樹木、名所、代替によく使われるナツツバキ(夏椿)の育て方などについて、幅広くご紹介します。
目次
沙羅双樹の基本情報

植物名:サラノキ
学名:Shorea robusta
英名:Sal tree
和名:サラノキ(沙羅の木)
その他の名前:沙羅双樹
科名:フタバガキ科
属名:コディアエウム属
原産地:インド
分類:常緑性高木
沙羅双樹とは、本来は木の名前ではなく、サラノキ(沙羅の木)が2本対になっている状態のことをいいます。サラノキの学名は、Shorea robusta(ショレア・ロブスタ)。フタバガキ科コディアエウム属の常緑高木です。原産地はインドで、暑さに強く寒さに大変弱い性質を持っています。自然樹高は30mほど。
サラノキは仏教の三大聖樹の1つで、残りの2つは無憂樹(ムユウジュ)、印度菩薩樹(インドボダイジュ)です。サラノキは若返りや復活を意味する「生命の木」として、大切に扱われています。一方、日本では「サラノキ」のことを「ナツツバキ」と認識していることがほとんどです。この謎については、のちほど紐解いていきます。
サラノキの花や葉の特徴

園芸分類:樹木
開花時期:3~7月
樹高:30m前後
耐寒性:弱い
耐暑性:強い
花色:クリーム色
サラノキの原産地での開花期は3〜7月で、一番の見頃は4月頃です。花色はクリーム色がかった白で、小さな花を密に咲かせます。ジャスミンに似た、甘く爽やかな香りを持っています。葉はつやのある楕円形で、長さ10〜25cmにもなる大きな葉が特徴です。幹は頑丈で、現地では建築用木材として加工されたり、樹脂が香料として使われたりと、生活に馴染みのある樹木の1つです。
サラノキ(沙羅の木)を沙羅双樹と呼ぶ理由

沙羅双樹という名前は、お釈迦様の入滅の際に、沙羅の木が対になった場所が選ばれたことにちなみます。2本の対の沙羅の木の間に横たわったとする伝えや、2本ずつ4カ所に8本植えられていたという伝えがあり、いずれも対に並んでいる様子が名前に含められて広まったようです。お釈迦様が入滅すると、嘆き悲しんだ沙羅の木は白い花を咲かせてお釈迦様を覆い尽くしたという言い伝えも残されており、それによって聖木として扱われてきました。
沙羅の木を含む三大聖樹とは
仏教では、沙羅の木、無憂樹、印度菩提樹を三大聖樹としています。沙羅の木については前述のとおりなので、ここでは無憂樹、印度菩提樹について簡単にご紹介しましょう。
無憂樹

学名はSaraca indica(サラカ・インディカ)で、マメ科サラカ属の中木。原産地はインドで、暑さに強く寒さに弱い性質を持っています。花色は黄〜オレンジで、小さな4弁花が集まって咲きます。お釈迦様はこの木の下で4月8日に生まれたと伝えられ、この日を灌仏会(かんぶつえ)や降誕会(こうたんえ)と呼んでいます。「阿輪迦の木」(あそかのき・あしょかのき)という別名も持っており、「憂いがない」という意味のサンスクリット語「アショカ」に由来しています。インドでは「憂いのない出産・誕生・結婚をかなえる幸福の木」とされています。
印度菩提樹

学名はFicus religiosa(フィカス・レリジオーサ)。クワ科フィカス属の高木で、原産地はインド。暑さに強く寒さに弱い性質を持っており、日本では観葉植物として流通しています。葉は縦長の楕円形で、先端が少し尖っているのが特徴です。花や実はつくものの、ほとんど外からは見えません。お釈迦様がこの木の下で49日間瞑想し、2月8日に悟りを開いたと伝わっており、この日を「成道会(じょうどうえ)」と呼んでいます。ちなみに、ボダイジュやセイヨウボダイジュ、ナツボダイジュなどはシナノキ科で、印度菩提樹とは別種です。
日本で沙羅の木とされる大半はナツツバキ(夏椿)
サラノキは寒さを苦手とするため、日本の気候では温室でない限りは育てられません。しかし仏教では聖木とされているため、代わりに花姿が似ているナツツバキを植栽して沙羅の木と呼ぶようになりました。ここでは日本の沙羅の木、ナツツバキについてご紹介します。
ナツツバキの基本情報

植物名:ナツツバキ
学名:Stewartia pseudocamellia
英名:Japanese stewartia
和名:ナツツバキ(夏椿)
その他の名前:サラノキ(沙羅の木)、シャラノキ
科名:ツバキ科
属名:ナツツバキ属
原産地:日本、朝鮮半島
分類:落葉性小高木
ナツツバキの学名はStewartia pseudocamellia (ステワルティア・プセウドカメリア)。ツバキ科ナツツバキ属の小高木。原産地は日本、朝鮮半島で、暑さにも寒さにも強い性質を持っています。花の形がツバキに似ており、6〜7月に開花するためナツツバキ(夏椿)と呼ばれてきました。花色は白で、5〜6cmほどの5弁花。一日で散る一日花です。自然樹高は10mほどですが、剪定によって樹高をコントロールすることができます。冬には葉を落とす落葉樹です。
お寺によく植えられているのは、日本の寒さに耐えられないサラノキの代わりとして、葉や花姿が似ているナツツバキを植えたためとされています。そのため、日本ではナツツバキが沙羅双樹だとして広く認識されるようになりました。また、僧侶がナツツバキを間違えて沙羅の木と呼んだことが由来、という説もあります。
ほかのツバキとの違い

ナツツバキは、ツバキ、サザンカ、ヒメシャラと見た目がそっくりなため、これらの違いがよく分からないという人も多いのではないでしょうか。ここで、見分け方についてご紹介します。
ツバキの花色は赤、ピンク、白、複色。種類によって咲く時期に幅があり、12月〜翌年4月で、花の終わりには花首がポトリと落ちます。常緑樹で、葉は肉厚で艶やかです。
サザンカは、性質はほとんどツバキと似ていますが、花の終わりに花首が落ちるツバキとは異なり、花弁をバラバラに散らします。また主に冬に咲くことや、枝に産毛があること、葉が小さいことも見分けるポイントです。
ヒメシャラの開花期は5〜7月。花色は白か淡いピンクで、小さめの花を咲かせます。花も葉もナツツバキより小ぶりなため、「小さい沙羅の木」という意味でヒメシャラ(姫沙羅)と呼ばれるようになりました。落葉小高木で、常緑のツバキやサザンカと違って冬は落葉します。
ナツツバキの育て方
サラノキの代わりとして寺社などで育てられてきたナツツバキ。日本では「沙羅の木」といったらナツツバキを指すことが多いため、ここでは、ナツツバキの育て方について解説していきます。
適した栽培環境

日当たり・置き場所
【日当たり/屋外】日当たり・風通しのよい場所を好みます。半日陰の環境でも十分育ちますが、暗すぎると花つきが悪くなるので注意。また、西日が強く当たる場所では、夏の強い日差しによって葉が傷みやすくなるので、避けたほうがよいでしょう。
【日当たり/屋内】屋外での栽培が基本ですが、寒冷地では鉢栽培にし、真冬は屋内に取り込むほうが無難です。
【置き場所】乾燥に弱く、適度に水はけ・水もちのよい土壌を好みます。
植え付け・植え替え

植え付け適期は、12月〜翌年2月です。
植え付けの2〜3週間前に、直径・深さともに50cm程度の穴を掘ります。掘り上げた土に腐葉土や堆肥、緩効性肥料などをよく混ぜ込んで、再び植え穴に戻しておきましょう。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。
土づくりをしておいた場所に、苗の根鉢よりも1回り大きな穴を掘り、根鉢をくずさずに植え付けます。最後に、たっぷりと水を与えます。
水やり

水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために枝葉全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてください。根付いた後は、地植えの場合は下から水が上がってくるのでほとんど不要です。ただし、乾燥を嫌うので、雨が降らない日が続くようなら水やりをして補います。
真夏は、気温の高い昼間に与えると、すぐに水の温度が上がって株が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に行うことが大切です。
また、真冬は、気温が低くなる夕方に与えると凍結の原因になってしまうので、十分に気温が上がった日中に行うようにしましょう。
施肥

順調に生育していれば追肥はほぼ不要です。しかし、木の生育に勢いがないようであれば緩効性肥料を樹木の周囲にまき、クワなどで軽く耕して土に馴染ませて様子を見守ってください。
剪定

剪定適期は、落葉して休眠している12月〜翌年2月です。自然樹高は10mに達しますが、家庭で栽培するなら管理をしやすくするためにも5m以内にとどめ、剪定によって樹高をコントロールしましょう。成長スピードはやや遅いほうです。もともと枝数が少なく、繊細な枝ぶりが美点といえるので、強い切り戻しをせずに自然に整う樹形を楽しむ剪定を心がけます。
まず樹高の半分より下の位置で幹から出ている下枝は、すべて元から切り取ります。次に、幹の内側に向かって伸びる枝を切り、さらに込み合っている部分があれば、不要な枝を元から切って風通しをよくしましょう。枝はどこで切ってもいいわけではなく、必ず分岐点まで遡って切り取ってください。剪定した部分から雑菌が入って病気を誘発したり、木の水分を失ったりするのを防ぐために、切り口には必ず癒合剤を塗っておきましょう。癒合剤は園芸店などで手に入ります。
注意する病害虫

【病気】
発生しやすい病気は、さび病です。
さび病は、カビによる伝染性の病気で、葉にくすんだオレンジ色の斑点が現れます。この楕円形の斑点はイボ状に突起するのが特徴で、症状が進むと破れ、中から粉のように細かい胞子を飛ばします。放置すると株が弱り、枯死することもあるので注意。発病した葉は見つけ次第切り取って処分し、適用のある薬剤を散布して防除します。
【害虫】
発生しやすい害虫は、チャドクガなどです。
チャドクガは蛾の幼虫で、イモムシのような姿で多数の細かい毛に覆われています。体長は20〜30mmで、ツバキ科の植物によく発生します。葉裏などに幼虫が大発生することがあり、見た目がよくないだけでなく、毒があるので見つけ次第駆除しましょう。チャドクガの毛に触れるとかぶれて皮膚炎を起こすので、駆除の際には注意が必要です。毛が皮膚につかないように長袖、長ズボン、手袋を着用して作業し、枝ごと切ってビニール袋に入れて処分してください。
タイやカンボジアで沙羅の木として扱われる花

日本ではナツツバキが沙羅の木の代わりとなっているのと同様に、タイやカンボジアでは、ホウガンノキが沙羅の木として広まっています。一層ややこしくなってきましたが、これは仏教が伝わる際に、沙羅の木をホウガンノキと誤認したことが由来のようです。
ホウガンノキは、学名はCouroupita guianensis(コウロウピタ・ギアネンシス)。サガリバナ科ホウガンノキ属の常緑高木です。原産地は南アメリカで、寒さに弱いので日本では温室のある植物園でしか見ることができません。開花期は3〜5月で、花は朱色。肉厚な花弁が特徴的で、芳香を持っています。花は一日花で、のちに15〜20cmの実がつきます。
平家物語に登場する沙羅双樹の意味合い

『平家物語』の有名な冒頭部、「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす……」。この一文を学校で学んだ方は多いことでしょう。「どんなに勢いに乗っている人でも、必ず衰える時がやってくる」という意味ですが、この沙羅双樹の花の色とは何を示しているのでしょうか。これはお釈迦様が入滅する際に沙羅双樹が白化したという言い伝えをもとに、「沙羅双樹の花の色」は死や滅亡を暗喩して、盛者必衰に結びつけたものとされています。
国内でサラノキ・ナツツバキが楽しめるスポット

サラノキは日本での栽培は難しいのですが、温室設備の整った植物園などでは実物を見ることができます。
●滋賀県「水生植物公園 みずの森」(滋賀県草津市下物町1091番地)では、ロータス館のアトリウムにて展示。
●京都府立植物園(京都市左京区下鴨半木町)の日本最大級の温室では、サラノキのほか印度菩提樹や無憂樹、ホウガンノキ、ナツツバキも見学できます。
●夢の島熱帯植物館(東京都江東区夢の島2-1-2)は夢の島公園内の熱帯博物館で、サラノキ、印度菩提樹、無憂樹が見られます。
日本の沙羅の木・ナツツバキのおすすめスポットもご紹介しましょう。
●妙心寺東林院(京都市右京区花園妙心寺町59)は、1531年に細川氏綱が父を弔うために建立しました。本堂前庭には十数本のナツツバキがあり、見頃に合わせて特別公開しています。
●普門寺(大阪府高槻市富田町4丁目10-10) は、行基菩薩開創のお寺で、1300年の歴史があります。6月頃がナツツバキの見頃です。紅葉寺としても知られています。
サラノキは三大聖樹の一つ!スポットを訪れて見てみよう

仏教では聖樹として知られるサラノキ。日本では苗の流通も少ないうえ、温室でない限り育たないことからナツツバキを代用し、沙羅の木に見立てて大切に育ててきました。そのため一般的にも沙羅双樹イコールナツツバキとして定着していますが、本来は違う植物です。国内でも本家のサラノキを見ることができる、温室設備の整った植物園もあるので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
Credit
文 / 3and garden

スリー・アンド・ガーデン/ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。2026壁掛けカレンダー『ガーデンストーリー』 植物と暮らす12カ月の楽しみ 2026 Calendar (発行/KADOKAWA)好評発売中!
- リンク
記事をシェアする
おすすめアイテム

壁掛け時計&温度計(GARDEN STORY Series)
優雅な曲線とリリーモチーフで飾られた、デコラティブな壁掛け時計&温度計。片面は時刻を読みやすいステーションクロック、もう片面は植物の管理に役立つ温度計になっています。アンティークな外観は、フェンスや壁のデザインポイントとなるアイテムとしても。
新着記事
-
ガーデン&ショップ

「第4回東京パークガーデンアワード夢の島公園」ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート
2025年12月中旬、第4回目となる「東京パークガーデンアワード」の作庭が、夢の島公園(東京・江東区)でスタートしました。 作庭期間の5日間、書類審査で選ばれた5人の入賞者はそれぞれ独自の方法で土壌を整え、吟…
-
ガーデンデザイン
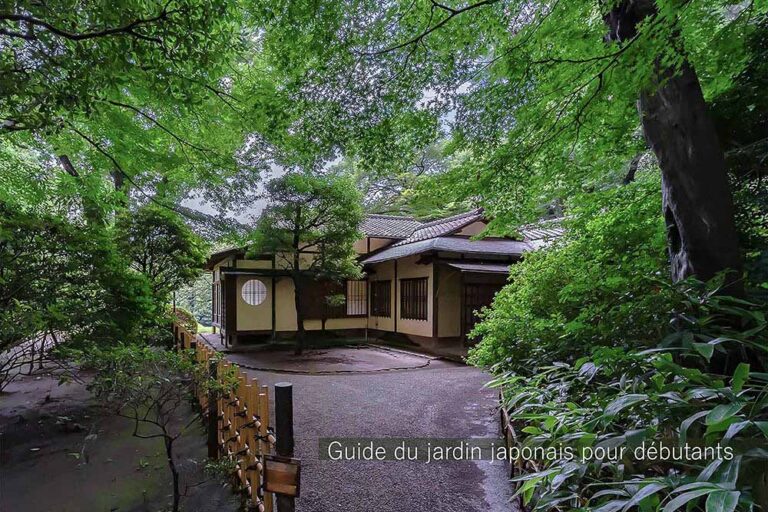
【日本庭園 超・入門】なぜ日本庭園には“飛び石”があるのか? 茶の湯が育んだ「露地」の美学
日本庭園の象徴ともいえる「飛び石」。じつはこれ、茶室へと続く小径「露地(ろじ)」から始まった、茶の湯の美学が詰まった装置であることをご存じでしょうか。単なる足場としての役割だけでなく、俗世から離れて…
-
花と緑

季節の花の3択クイズ! 冬に芳香を放つロウバイ(蝋梅)は次のうちどれ?【Let’s Try! 植物クイズ】Vol.32
冬の寒空の下、どこからかかぐわしい香りが漂ってきたら、近くにロウバイ(蝋梅)が咲いているかもしれません。年末や新年の頃に香りのよい花を咲かせるロウバイは、生け花や茶花にも広く利用され、庭木としても人…

































