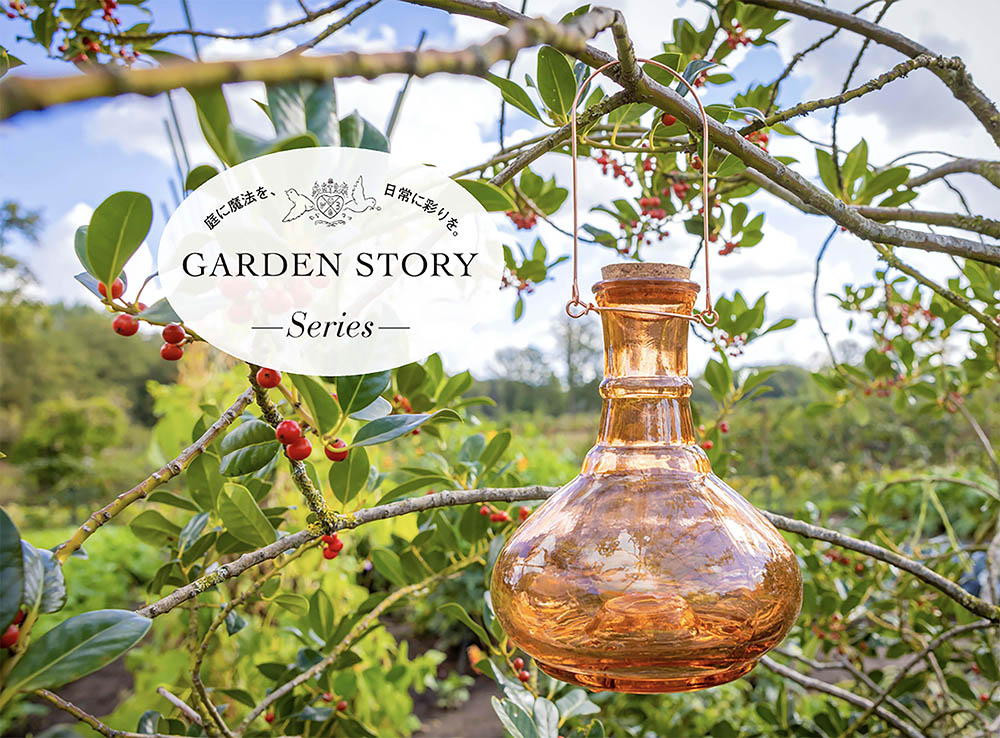【雑草は役立つ?!】雑草で冬の大地の乾燥を守り、手間いらずの土壌改良&害虫対策

抜いても抜いても生えてくる雑草。終わりの見えない草むしりに疲れてしまっているガーデナーもいるかもしれません。しかしじつは、野花や雑草は豊かな庭づくりを手助けしてくれる存在であることを知れば、神経質に除去する必要もなくなります。メドウ(野原)のような有機無農薬のガーデンでバラを育てる持田和樹さんは、庭づくりに雑草を活用することで、ローメンテナンスなガーデンを実現。そんな持田さんが、土壌や環境を整える雑草の力と、庭づくりに取り入れる際のポイントをご紹介します。
目次
ローメンテナンスな庭づくりをサポートする雑草

皆さんは、庭や畑に生えてくる野花や雑草と、どうお付き合いしているでしょうか? ほとんどの方が雑草を見つけたら育たないように抜いてしまい、雑草=厄介者として扱っていることと思います。
ですが、もしそんな野花や雑草が、皆さんお困りの害虫対策に貢献してくれる優れものと知ったら、彼らに対する見方が変わるはず。今までの雑草取りの苦労からも解放され、むしろ野花や雑草が庭づくりや家庭菜園の大きな味方になってくれるでしょう。
実際に私が手がけている菜園やローズガーデンは、隣町にあるため週に1度しか手入れができません。そんな困難な状況だからこそ、あえて野花や雑草を取り入れ、自然の働きを生かすことで、ローメンテナンスかつローコストで有機無農薬栽培に成功しています。


秋に芽生える野花は、冬の寒さや乾燥から土を守る大地の衣

秋に入り、気温が20℃前後に下がってくると、春に花が咲く野花の多くが発芽適温になります。この季節、地面に目をやると、小さな可愛い芽生えがあちらこちらで起きていることに気がつきます。こうした秋に芽生える野花の多くが、春に開花し、夏には種子をつけるサイクルです。

まだ寒さが残る3月頃には、青空のように美しいイヌフグリやハート形の種子が可愛いナズナ、群生すると赤紫色の花の絨毯をつくるホトケノザなどが、春の訪れを真っ先に感じて咲き始めます。また関東の平地では、すでに11月から春の野花が咲き始め、冬の間でも暖かな日には野花が咲く姿を目にすることもあります。
こうした秋に芽生える野花の大きな特徴は、あまり背丈が大きくならないということ。多くは冬の寒さから身を守るため草丈は低く、この時期育つ花や野菜の光合成の邪魔になりにくいのです。春になれば伸びてくるので、ある程度の草刈りや除草は必要ですが、夏の旺盛に伸びる雑草とは大きく異なり、あまり神経質に除草する必要はありません。むしろ、冬は寒さや乾燥から大地を守る役割を担ってくれるので、活用しない手はありません。
草抜きで砂漠化⁉ 土を潤す植物の役割

皆さんも、乾燥する冬は肌荒れを防ぐために、加湿をしたりボディクリームを塗って肌を保護・保湿しているのではないでしょうか? 洋服を重ね着し、寝るときは布団をかけて暖かくして眠りますね。
それと同じようなことが、自然にも言えます。土という地肌を乾燥から守るのは、落ち葉や枯れ草であり、秋に芽生える野花や雑草なのです。
特に積雪のない地域では、生きた野花や雑草は、湿度調整を自動でしてくれる天然の加湿器。植物が生えていないところの土は、日光や風で風化しガサガサになっていますが、植物が生えているところは冬でもしっとりと潤っています。そして雨が降らない日が続いていても、冬の早朝に散歩すると朝露が草についていることにも気が付きます。朝露もまた、土を潤す重要なファクターです。

朝露ができる仕組みは、次のとおりです。晴れた日の夜間には、「放射冷却」現象が強まります。植物の表面は熱を放射しやすく、葉や茎の表面から熱が奪われて周囲の空気よりも温度が下がると、空気中の水分が結露して朝露がつきます。さらに植物の葉や茎は、広い表面積、微細な毛や凹凸のある構造、放射冷却を促す性質など、朝露を形成し集めるのに適した条件を備えています。このように、植物は乾燥した環境でも水分を得られるよう進化してきたのです。
土壌の微生物にも必要な水
植物にとって欠かせない水ですが、植物の生育に欠かせない微生物の多くも、活動のためには適度な水分が不可欠です。ほとんどの土壌微生物は直射日光が苦手で、紫外線、乾燥、高温といった影響を避けるために、土壌の深部など保護された環境に生息しています。土壌微生物の活動を守るためには、土壌の保湿や適度な日陰を保つことが重要。その環境を整える手助けをしているのも、植物なのです。
人間にとっては雑草が生えていないほうが、綺麗で手入れが行き届いているように見えるかもしれません。しかし、生物・生態学的な視点で見ると、何も生えていない土は、植物にとってあまりよくない環境なのです。一生懸命している雑草取りが、もしかしたら砂漠化を招くことになっているかもしれません。
草花が紡ぐ食物連鎖と生命のリレー
じつは早春に咲く野花は、害虫対策にもとても重要。雑草扱いして抜いてしまうのはもったいないことなのです。なぜなら、春を感じ冬の寒さから目覚めるのは草花だけでなく、虫などの小さな生き物たちも同じだからです。
こうして目覚めた生き物は、まだ食糧の少ない環境の中で生きていかなくてはなりません。早春に咲く野花には、貴重な蜜を求めて小さな虫たちがやってきます。その虫たちを糧にクモなどの捕食者が増え、その捕食者をさらに上位のトカゲやカエル、鳥などが食べて、生き物全体が食物連鎖により育まれていきます。

ここで重要なポイントは、年間を通して生き物が豊かに育つ環境を整えること。庭では夏にかけて徐々に害虫が増えてきますが、その前段階である冬の目覚めから春にかけて生まれてくる小さな生命を育むことで、春から夏にかけての害虫を抑制することができるのです。
害虫を抑制するために虫たちを育てるのは、一見矛盾するように思われるかもしれません。しかし多くの場合、この生き物たちを育む生命のリレー、食物連鎖のバランスが崩れているからこそ、害虫に悩まされるのです。
1つの野花がもたらすたくさんの恩恵

例えば、4月頃になると咲き始めるカラスノエンドウ。このカラスノエンドウに、たくさんのアブラムシが群がっている姿をよく目にします。
アブラムシが大好物のテントウムシは、カラスノエンドウに群がるアブラムシを食べて繁殖し、アブラムシが出す甘露が大好きなアリは、アブラムシの周りに集まり周辺の害虫を抑制したり、命を終えた生き物を食べて土に還したり、アリの巣を作ることで土の中に水と空気の通り道を作ったりと、植物が生育しやすい環境を整える大きな助けになります。
また、カラスノエンドウ自体にも甘い液を分泌する蜜腺があり、アリを惹きつけ防御をしていると考えられています。アリは蜜腺の甘い液を餌として利用する一方で、カラスノエンドウに付く害虫やその卵を排除する手助けをします。一方、カラスノエンドウの草の汁を吸うアブラムシですが、彼らもじつはカラスノエンドウの生育の手助けをしているのではないかと私は考えています。植物は、葉や茎、根の成長にエネルギーを使う「栄養成長」と、花や果実、種子の形成にエネルギーを集中させる「生殖成長」とに生育の段階が分かれています。そして、この生育の切り替えに昆虫の食害が影響を与えているという研究が多くあります。
カラスノエンドウを観察していると、あえて茎の成長をアブラムシに止めさせて、種子を作る準備を手伝わせているかのようです。真実は定かではありませんが、私にはカラスノエンドウがアブラムシやアリ、テントウムシに食事を与え、まるで自分で自分を育てているかのように見えます。食べる食べられるという関係の中で、お互いが助け合いながら住みやすい環境を整えているように感じられるのです。
結果的に、庭にカラスノエンドウがあることで、アブラムシを食べるテントウムシを増やし、庭や菜園を守り土壌を豊かにするアリを呼び込むことができます。バラを育てている私は実際に、5月のバラが咲く前、4月の段階でカラスノエンドウを活用してテントウムシやアリを増やすことで、害虫対策をしています。季節ごとの現象は決して独立したものではなく、連鎖的に繋がっていくため、自然の流れや繋がりを分断せず好循環させることで、自ずと害虫は減っていきます。1つの事柄の背景には、まるで織り糸のようにさまざまな生き物や環境要因が折り重なっています。そして、庭や菜園をどのように織り上げるかは、私たち次第。自然を排除するのではなく、自然と共生する庭づくりや家庭菜園は、私たちに多くの恵みを与えてくれます。労力削減になるのはもちろん、心の面でもゆとりができ、感謝の気持ちを持って自然をじっくり味わうことができるようになります。

カラスノエンドウのような野草は、小さな虫たちと共生しているため、虫たちに合わせた小さな素朴な花を咲かせるものが多いです。園芸品種のような華やかな見た目ではなくても、野花や雑草には食物連鎖を支える大きな役目があるのです。見た目や雑草という先入観に囚われ、野の草花が持つこうした役割に気付かずにいるのは、とてももったいないこと。改めて自然の持つ可能性と豊かさに目を向けることで、新たな発見や気づきが得られることでしょう。
野花や雑草の取り入れ方のバランス
野花や雑草を庭づくりに取り入れる際に難しいのは、その取り入れ方のバランス。自然の仕組みを生かしたガーデニングであっても、一番やってはいけないことは、じつは放置です。近年、雑草を取り入れた自然栽培という栽培方法があり、私もこれに近いことをしていますが、自然が一番いいからといって、放置することがよい訳では決してありません。
面白い植物の実験に、1日3回手で撫でたナズナと、全く撫でなかったナズナの成長を記録したものがあります。実験の結果はというと、撫でたほうが愛情を注いでいるから成長した…かと思いきや、全く成長せず、小さいまま花が咲きました。一方、全く手で撫でなかったナズナはグングン元気に成長し、歴然とした差が現れました。
植物は生態系を支える一次生産者で、常に食べられる危険性があるがゆえに、草食動物に食べられないよう刺激が多い場所では小さくなったのかもしれません。いつも人が歩く場所では、確かに草は小さくなっていますよね。
人が手を入れなければ雑草は旺盛に伸び、育てている植物に覆い被さって光合成の邪魔をしてしまいます。ですから適度な草刈りや除草は欠かせません。もっとも秋に生える野草は、背丈が低く大人しいものがほとんどです。野花や雑草の特徴を把握し、それぞれを程よく残して庭に取り入れることで、生態系を豊かにし、害虫抑制を図ってみてはいかがでしょうか?
雑草抑制のために草花の種まきを

何の手入れもしなければ、庭や畑はもちろん雑草だらけになってしまいます。そこで私が取り組んでいることは、草花の種子を播くこと。さまざまな草花の種子がありますが、私はあらかじめ春に咲く秋まきのものを購入しておき、9月後半から10月の間に播いています。草花が雑草の成長を抑制しつつ花を咲かせるので、雑草取りの労力も減りますし、適度に野花が入り交じる花畑のような美しい仕上がりに。花の蜜を求めて多くの生き物が集まるため、生態系も整います。花畑を作ることで、結果的にバラや菜園の害虫や雑草を抑制してくれるのです。
種まきをしても環境に合わない草花は自然と絶え、環境に合うものが残ります。咲いた花は種子を採取し、また秋に種まきすることで、コストを削減できます。さらに植物には適応能力があり、育った環境の学習が次世代に引き継がれるため、自家採種した種子はより環境に適応して強い株になり、少しずつ育てやすくなっていきます。
こうして残った環境に合う植物は、ほとんど手がかかりませんし、元気よく育って見事な美しい花を咲かせてくれます。ありふれた草花であっても、生き生きと咲いている姿は見応え十分で、見る人を感動させてくれます。創造という無限の可能性に触れることができるガーデニング。自然や宇宙の目には見えない摂理とも繋がり、内なる自分自身とも向き合う神聖な行為だと、私は感じています。

四季折々に咲く草花や、季節ごとに移り変わる景色、生き物の営み、鳥のさえずりや虫たちの美しい演奏、土や草花の香り……五感を通して感じるすべてに癒やしがあります。小さな虫の赤ちゃんが懸命に生きて少しずつ育っていく姿を見ていると、私も嬉しい気持ちになりますし、いつも害虫が増えすぎないように整えてくれる生き物たちには「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えています。
私は害虫や益虫を区別せず、全ての生き物に感謝しています。自然界では、それぞれが影響し合い、依存しています。だからこそ、無駄な生命はなく尊い命なのです。
自然の恵みを分かち合う

植物を育てていれば、病害虫対策は尽きることのない悩みです。しかし、本来は癒やしを求めて植物を育てているはずなのに、病害虫対策に神経をすり減らしてストレスに感じてしまうのでは本末転倒。
ガーデニングや菜園では、私たち人間が楽しむために植物を育てますが、植物は本来、誰の所有物でもなく、生きとし生けるもの全てと恵みを分かち合う存在だと思います。いま地球規模で起きている環境問題も、地球や自然を人間の所有物だと思い込み、他の生命を顧みず好き勝手に独占してきた結果ではないでしょうか。
だからこそ、多少虫に食べられたとしても目くじらを立てず、恵みを分かち合う存在として温かく見守る気持ちを持つことが、いま起きている地球規模の危機を救うきっかけになると、私は信じています。

Credit
文&写真(クレジット記載以外) / 持田和樹

アグロエコロジー研究家。アグロエコロジーとは生態系と調和を保ちながら作物を育てる方法で、広く環境や生物多様性の保全、食文化の継承などさまざまな取り組みを含む。自身のバラの庭と福祉事業所での食用バラ栽培でアグロエコロジーを実践、研究を深めている。国連生物多様性の10年日本委員会が主宰する「生物多様性アクション大賞2019」の審査委員賞を受賞。
- リンク
記事をシェアする
新着記事
-
育て方

【バラ苗は秋が買い時】美しいニューフェイス勢揃い&プロが伝授! 秋バラの必須ケア大公開PR
今年2回目の最盛期を迎える秋バラの季節も、もうすぐです。秋のバラは色も濃厚で香りも豊か。でも、そんな秋のバラを咲かせるためには今すぐやらなければならないケアがあります。猛暑の日照りと高温多湿で葉が縮れ…
-
ガーデン&ショップ

【スペシャル・イベント】ハロウィン色で秋の庭が花やぐ「横浜イングリッシュガーデン」に…PR
今年のハロウィン(Halloween)は10月31日(金)。秋の深まりとともにカラフルなハロウィン・ディスプレイが楽しい季節です。「横浜イングリッシュガーデン」では、9月13日(土)から「ハロウィン・ディスプレイ」…
-
ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る「第3回 東京パークガーデンアワード」都立砧公園【秋の到来を知らせる9月…
新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第3回コンテストが、都立砧公園(東京都世田谷区)を舞台にスタートし、春の花が次々と咲き始めています。…