縁側は機能的な和の空間! その役割や5つのメリットを解説します

Blanscape/Shutterstock.com
縁側(えんがわ)といえば、日本家屋では定番の造りでしたが、近年の住宅では見かけることが少なくなりました。しかしながら、縁側は家の中と外とを繋ぐ役割や利便性もしっかりと考えられた魅力的な構造です。ここでは、そのよさが再認識されつつある縁側の特徴や種類、メリットとデメリットなどについて詳しく解説します。
目次
縁側とは

縁側とは家の縁(へり)に沿って床板を張り、通路として拡張した部分のことをいいます。ベランダやバルコニー、ウッドデッキなどと意匠的には似た点がありますが、日本家屋での縁側は空間を区切るものではなく、一般的には部屋や家自体の内外を曖昧にする空間として認識されています。ここではその特徴や起源、種類などについて解説します。
縁側の特徴と種類

縁側の特徴は、まず通路としての役割にあります。家の縁(へり)に沿って造られ、部屋の中を通らずに他室へ移動することができます。縁側の外に向かった面には壁はなく、外の景色を近くに感じることができる造りとなっています。雨戸や引き戸などで仕切られていて、外部との繋がりを調整できる縁側を「くれ縁」、仕切る物がない縁側は、雨が降ると濡れることがあるため「濡れ縁」と呼ばれています。縁側の中で、縁がまちに対して板を直角に敷き並べたものを、とくに「切目縁(きりめえん)」と呼びます。以前は縁側のことを「縁(えん)」と呼んでいたので、このような呼び方になっているようです。
縁側の起源

床板が広く貴族の間で一般的になった平安時代では母屋と別棟である「庇(ひさし)の間」が設けられ、そことを繋ぐ廊下が縁側の起源とされています。現存する最古の縁側と呼べる造りがあるのは、奈良時代に建立された法隆寺東院の伝法堂といわれています。
大正時代になると庶民の家でも縁側が造られるようになり、昭和初期の日本家屋では縁側を設けることが一般的となりました。
縁側とウッドデッキの違いは?

縁側とウッドデッキの明確な違いの定義はありませんが、一般的に縁側が家屋と繋がる形で軒を出して造られるのに対し、ウッドデッキは家屋から独立して造られることが多く、そのため家から続く軒などがないものも多く見られます。とはいえウッドデッキのような造りでも縁側と称することもありますし、同じような用途での活用が可能です。
モダンな縁側が増えている

もともと日本家屋に連なって造られた縁側ですが、さまざまな建築様式の建物に設けることができます。現在は洋風リビングに合うような素材で造られた縁側や、和洋をうまく折衷し、2階のリビングと外壁の間をモダンな縁側にしたり、庭に面した部分をテラスのように広い縁側にしたりする建築も見受けられます。
縁側の役割

もともとの縁側の役割は別棟へ行くための通路でしたが、今はそれ以外のさまざまな用途に使われています。1つ目は家の内外を繋ぐ出入り口としての役割です。リビングに繋がる縁側の場合、玄関から入ることなく、利便性のよい使い方ができます。2つ目は交流の場としての役割です。室内に上げるほどではない立ち話や、ちょっとしたコミュニケーションの場として、気軽に招き入れることができる縁側はとても便利です。3つ目は憩いの場としての役割です。縁側は部屋の中と同様に、くつろぎながら外の景観や日差しを感じることができるスペースにもなります。
縁側があるメリット

縁側があることで生活が豊かになるポイントがたくさんあります。ここでは、具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。
コミュニケーションが取りやすくなる

接客の際に室内に招くのは、家主と訪問者の双方が少し気負ってしまうことがありますよね。縁側であれば訪問者は靴を脱がないですむ気軽さや半屋外という認識から、気軽にコミュニケーションを取りやすくなります。また広い縁側であればくつろぎや休憩スペースとなり、家族や友人などが集まりやすい空間として有効活用ができます。
夏は涼しく冬は暖かく室温を調整

部屋の内側と外側の間に軒のある縁側という空間を挟むことで、夏は直射日光が室内に入るのを防ぐ緩衝地帯となり、また居室部分に繋がる縁側では、引き戸を開放すれば風通しがとてもよくなって室温の上昇を抑え、閉じれば外気の侵入を防ぐことができます。
部屋を広く見せられる

居室部分と段差のない縁側にすることで一体感が生まれ、縁側までをひと部屋のように使うことができます。より一体感を持たせるためには、縁側との仕切り部分の引き戸を1カ所に収納して開口できるようにしたり、居室部分の床材と縁側部分の床材を同じにする方法もあります。
四季の移ろいを五感で感じ楽しめる

縁側を庭に面して造ることで、庭の植物や借景から四季の移ろいを感じることができます。ガーデニングが趣味であれば、腰掛けてのんびりできる縁側は絶好の観賞スペースとなります。
縁側は室内とは違い、日差しや風をダイレクトに感じることができます。春は新芽の息吹を感じ、夏は夕涼みをしたり、花火をしたり……。秋はゆっくりと腰掛けてお月見や虫の音を楽しむことも。縁側があることで、五感を使って季節の変化を楽しむことができます。
人によってさまざまな使い方ができる

縁側の用途は自由で、人によってさまざまな使い方ができます。前述のように、コミュニケーションの場やバーベキューなど飲食して楽しむ場、または収穫した野菜を選別する作業場にも。庇があれば、洗濯物や布団、乾物を干すこともできます。広縁なら子どもの遊び場としても申し分ないでしょう。用途はまさに無限大といえます。
縁側をつくるデメリット
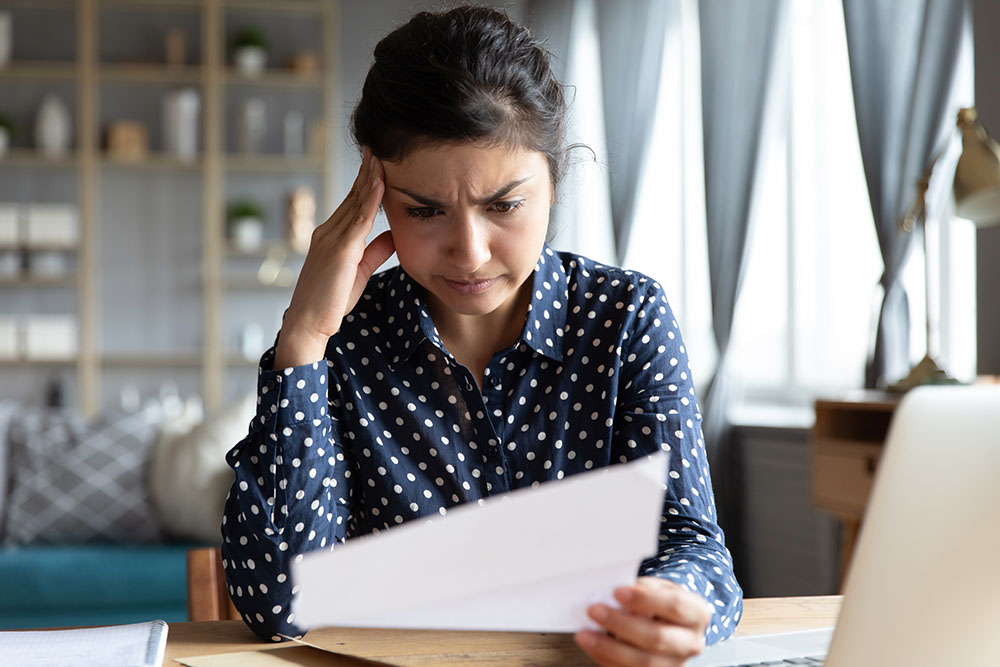
生活を豊かにしてくれる縁側ですが、作る場合にはその分費用がかさむなどのデメリットも存在します。ここでは、それらのデメリットについて解説したいと思います。
縁側分のスペースが必要

縁側を造る場合、まず縁側のスペース分、部屋として使用できる面積が減ってしまうデメリットが挙げられます。家の広さにもよりますが廊下としての活用を考えると、幅は最低1mほど必要になります。設計段階から縁側を検討している場合は、部屋面積との兼ね合いを含めながら縁側のサイズを考えていきましょう。庭の広さに余裕があれば、増築という選択肢もあります。ただ後付けの場合はコストが高くなり、また建築基準法の建ぺい率・容積率の関係で縁側の増築許可が必要になる場合もありますので、希望がある場合は、まず施工会社に確認してみましょう。
庭のこまめなお手入れが必要

縁側のよさの一つに、庭の景観が楽しめるということが挙げられます。縁側があることで常に庭を意識し、自然の移ろいを感じることができるのです。しかし庭の手入れを怠ってしまうと、生え放題の雑草や枯れた木々を逆に意識させられることになり、楽しみが半減してしまいます。そのため、庭のこまめな手入れは必須。植木の管理や雑草への対処が大変であれば、管理しやすい最低限の植物を植え、他の場所は砂利を敷くなどして手間を省き、ストレスなく縁側が活用できるようにしましょう。
プライバシー・防犯面の心配

縁側はコミュニケーションが取りやすく、気軽に交流できる場所である反面、プライバシーや防犯面での心配があります。また壁などの遮るものがないため、外から家人の動きが見えてしまいます。そのため縁側の設置位置を考慮したり、目隠しとなる塀を造ったりするなどの工夫が必要となります。
縁側を造るときの注意点

ここまで、縁側を造るメリット、デメリットをご紹介してきました。それらを加味した上で、ここでは縁側を設ける際の注意点について解説したいと思います。
縁側がある家を建てるとき

新築の際に縁側を組み込もうと考えている場合、一番大切なのは、そこで何がしたいか、何を見たいか、どんな風に活用したいかを具体的にイメージすることです。庭が眺めたいのであれば庭に面した造りになるでしょうし、洗濯物や乾物を干すなどの作業場を兼ねての活用を考えているのであれば、日当たりのよい南に面しているとよいでしょう。ただ漠然と造ってしまうと、庭が見たかったのに縁側からは塀しか見えなかった。あるいは防犯面のことが全く考えられていないため、結局安心して使うことができなかったなど、残念な結果となってしまいます。その場でやりたいことが具体的であればあるほど建築士も設計しやすくなり、希望のイメージに近い縁側となることでしょう。まずは暮らしをイメージし、その内容を建築士に伝えることが大切です。
縁側をリフォームで造る場合

後付けでも広縁や濡れ縁を設けることができます。費用は広縁で一部屋100万円程度、濡れ縁で20万円程度から可能です。場合により増築と判断されれば、固定資産税がかかる場合もあるため注意が必要です。前述しましたが、建築基準法の問題で許可が必要になる場合があるため、設置したい場所に十分なスペースがあるかどうか、また、許可が下りるかどうかを専門家に確認しましょう。
今風の縁側で充実した暮らしを

近年の生活様式の変化により、家での過ごし方も変わってきたのではないでしょうか。野菜栽培やガーデニングなど、自宅の庭の見直しをする人も増えてきています。小休止する場所として、また庭を眺めながらのんびりする憩いの場所として、縁側は生活をとても充実したものにしてくれることでしょう。みなさんも縁側を取り入れた暮らしを考えてみてはいかがでしょうか。
Credit

文/3and garden
ガーデニングに精通した女性編集者で構成する編集プロダクション。ガーデニング・植物そのものの魅力に加え、女性ならではの視点で花・緑に関連するあらゆる暮らしの楽しみを取材し紹介。「3and garden」の3は植物が健やかに育つために必要な「光」「水」「土」。
冬のおすすめアイテム

ウッドストレージ(薪台) -GARDEN STORY Series-
薪ストーブやキャンプに欠かせない薪を、スタイリッシュに収納できるラック。薪を置くキャンバス布は取り外して取っ手付きキャリーバッグになるので、移動もラクラクです。キャンバス布は外して丸洗い可能。雨や土埃で汚れても気軽に清潔を保てます。
新着記事
-
ガーデン&ショップ

都立公園を新たな花の魅力で彩る画期的コンテスト「第4回 東京パークガーデンアワード」夢の島公園でスタ…
新しい発想を生かした花壇デザインを競うコンテストとして注目されている「東京パークガーデンアワード」。第4回コンテストが、都立夢の島公園(東京都江東区)を舞台に、いよいよスタートしました。2026年1月、5人の…
-
樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR
大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…
-
クラフト

節分から春へ! 無病息災を願う節分飾りを「小鳥へのギフト」に変える<2way>のお守りリース作り プチ…
家族の無病息災を願う「節分」。今年は豆まきだけでなく、飾って楽しめる特別なリースを作ってみませんか? 材料はスーパーのヒイラギと、100均の落花生などを用意して、総額700円。 魔除けとして飾ったあとは、小…































