「ビカクシダ」は「コウモリラン」とも呼ばれ、ここ数年、インテリアグリーンとしても爆発的な人気を誇る珍奇植物。そして、虫をほふる奇怪な生態の「食虫植物」。両者ともフォトジェニックな姿がSNSを席巻し、そのブームは今なお拡大中! この話題の二大植物の牽引役ともいえる2店舗を、天下一植物界2022にてGS編集部が特別取材。貴重なインタビューは永久保存版です!
目次
ビカクシダと食虫植物のブースを訪問する前に軽く予習
ビカクシダとは

園芸店によっては「コウモリラン」という名でも売られていますが、ランではなく、その名の通りシダの仲間で、主にインドネシアや太平洋の島々など、熱帯の環境下で、木の幹に着生しながら生息しています。観葉植物としての楽しみ方は、鉢植えで育てることも可能ですが、最も人気なのは、樹上に着生している姿に似せた「板付け」。水苔に植え付け、それを釘やヒモを使って土台となる板(主にコルク)にしっかりと固定する着生植物特有の栽培方法です。シダ類は直射日光が苦手なので、室内で育てる観葉植物としても最適。多くの人が壁に掛けたり吊したりして、室内でビカクシダ栽培を楽しんでいます。
ビカクシダは、和名・学名ともに鹿の角という意味を含んでおり、葉が大ぶりのものを1株飾れば、その名のごとく鹿角のオブジェを飾ったかのようにお部屋がゴージャスに見える効果があり、小ぶりのものでも、ちょっと奇怪で可愛い感じがお部屋をオシャレに魅せる…このように、とてもインテリア性に富んだ観葉植物です。
手間をかけ、自分流に株を育て上げていく、そんなところも人気なのかもしれませんね。インスタグラムでもハッシュタグで検索すると28万件以上ヒットし、亜熱帯感がひしひしと伝わるものや、スタイリッシュな“映え”を意識したものなど、素敵な写真が目白押し! ビカクシダ初心者の私にとっては、この天下一植物界でどんな出会いがあるのかワクワクします。
食虫植物とは

食虫植物というと、奇々怪々な形をした植物が虫を捕らえ、それを栄養分にして生きている、何やらちょっとホラーな姿を想像してしまいますが、実際は少し違っていて、決して虫だけを糧に生きているわけではなく、他の植物同様、ちゃんと光合成をしながら成長していく能力も備わっています。蝶番みたいなところで虫を捕らえるハエトリソウ(写真)や、消化液の入った壺のような場所に虫を誘い、落下したところをじわりじわりと溶かしていくウツボカズラなどが有名ですね。
種類にもよりますが、奇怪な見た目に反して栽培方法は簡単な品種が多いため、最近はホームセンターの園芸コーナーなどでもよく見られるようになりました。
とはいえ、どこか謎めいた存在であることは確か。私も食虫植物というと前述の2種類しか知らないため、今回の天下一植物界でどんな出会いがあるのか、とても楽しみです。おそらくそこには、自分の想像を上回る異色な世界が広がっている予感が…。
ビカクシダブース【vandaka plants】を訪ねる
『vandaka plants』とは
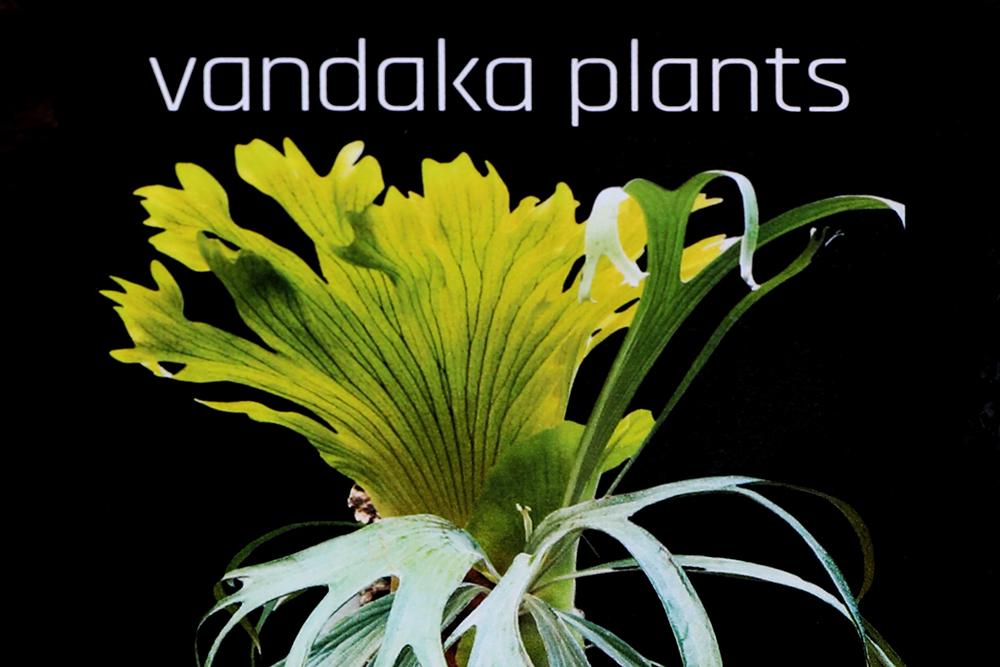
グリーンとインテリアアート2つの融合体ともいえるビカクシダ。熱狂的な愛好家も多く、コロナ禍のおうち時間効果も加わり、ここ2〜3年で幅広い層に爆発的に人気が広がりました。そんなムーブメントの牽引役も担っているのが、全国のビカクシダマニアから熱い信頼を寄せられている専門店『vandaka plants』。京都のショップですが、東京にもショップを兼ねたギャラリーを構えていて、東西の拠点から全国に向け、ビカクシダの魅力を発信しています。植物を愛し、旅を愛する代表の高橋宏治さんが手がける『vandaka plants』のエキゾチックな天下一植物界ブースを訪ねました。
ブースのビジュアル的なインパクトに魅せられる

サボテンマニアの私が、この天下一植物界でまず最初に向かったブース、じつは多肉ブースではなく、ビカクシダ専門店の『vandaka plants』のブースでした。なんていうのかな、あの謎めいた葉っぱに呼び寄せられたというか、引力を感じたのです。自宅近所の園芸店で、コウモリランの商品名で売られているビカクシダは幾度となく見たことがありますが、ここにあるものは、町の園芸店のそれとはまったく別物です。私が知っているそれは、苔玉に植えられて、ワイヤーのようなもので吊されたものだったのですが、『vandaka plants』のブースにあるものはほとんどが前述の「板付け」というスタイルで飾られていて、ブース全体のビジュアル的なインパクトにかなりやられました。見る人を取り囲むように飾られたビカクシダを眺めていると、まだ行ったことのない亜熱帯のジャングルとはこういう感じなのだろうな、と想像を掻き立てられます。

胞子のガチャ。この中にあるのがビカクシダの素、ってこと? でも、こんなギミックすらもオシャレでカッコよく見えてしまいます。

板や木片が無造作に置いてありますが、これは株を着生させるためのコルクの板。たかだか木片なのですが、ここに雄々しいビカクシダが着生し、それが拙宅のリビングに飾られている様を思い浮かべると、その部屋にいる自分がディーン・フジオカにでもなったかのような・・・そんな妄想が無限に広がります。いやホント、帰りが飛行機でなかったら完全に買っていました。
『vandaka plants』代表の高橋宏治さんにお話を伺いました

多種多様な品種をしっかりと作り込んでいるのがうちの持ち味
K:本日はよろしくお願いします。まずさっそくですが、今回天下一植物界に出展した経緯を教えていただけますか?
高橋(以下T):第1回の時より出展させていただいておりまして、コロナによるイベント中止が続いて、今回が3年ぶり2回目の出展となりました。中止になってしまった第2回目の企画段階から、こちらの会場の屋上部分を、世界のさまざまな植物を取り扱っている『花宇宙』さんと占領して、面白い展示をしたいと計画していました。それが今回実現できて、大変嬉しく思っています。
K:それにしても、ビカクシダって、思いのほか見事な、というか、ダイナミックなものなのですね。私はビカクシダ初心者なので、知らないことだらけなのですが、ビカクシダの値段の幅って、どんなところで決まるのでしょうか?
T:希少性と大きさ、また管理期間の長さといったところですね。
K:やっぱり大きければ大きいほど高価になる感じですか?
T:そうですね。ただ、品種によっては小型のものもあるんで、逆にそれが希少性が高かったりして、価格も大きなものを凌駕することがあります。

K:ビカクシダの栽培法についてですが、鬱蒼とした熱帯ジャングルにいるイメージなので、燦々と降り注ぐ直射日光はやはり苦手な植物なのですか?
T:そうですね。このブースがそうであるように、直射日光は避けたほうがいいです。インスタグラムでもよく見られるように、「アマテラス」に代表されるような植物育成ライトだけでも育つといえば育つのですが、室内栽培で健康に美しく育てるには、やはり風が必要なんですね。本来、屋外で生育している植物ですから、風に当てて、明るく、でも直射日光は当たらない、そんな環境がいいですね。
K:ここに木の皮がありますが、これに植え付ける感じなのですね?
T:これはコルクの木の表皮でして、これに、土の代わりに水苔をつけて植え付けます。なので、一般的な植物が土が古くなったら植え替えを行うように、水苔が古くなったらまた新しい水苔に替えて、新しい木の土台に植え替える必要があります。

K:なるほど、植木鉢への植え替えと違って、板付けは作業にひと手間ふた手間かかるところがまた趣深いですね。上手に育てられたとして、どのくらいまで生きる植物なのですか?
T:寿命か…あまり考えたことはないですねぇ。けっこう長いこと生きるのは確かです。そもそもシダ植物なので、花も咲きませんし、まさにご覧のこの状態を、この葉っぱの姿を長い時間かけて楽しむ、という感じですね。シダなので、古くからこの形で、それこそ古代から続いてる植物なので、そんなところに想いを馳せるのもおもしろさの一つです。
K:そう聞くと、なにやら時空を超えたロマンを感じますね! 今回の出展で、来場されたお客様に『vandaka plants』のブースで、ここを一番見てほしい! というところがありましたら教えていただけますか?
T:多種多様の品種を揃えて、しっかりと作り込んで販売しているところがうちの持ち味かと思います。たくさんの品種を直接見て選ぶ楽しさを味わっていただきたいと思います。

きっかけは、旅先で出会った野生のビカクシダ
K:葉の形のバリエーションも多く、緑の色調もそれぞれ味わいがあって、結構種類が多いのですね。ここでの出会いを期に、ビカクシダにハマる人も多いのではないかと思います。ちなみに、高橋さんがビカクシダに惹かれたきっかけを教えていただけますか?
T:20年以上前に、旅先で出会った野生のビカクシダの造形美に衝撃を受け、その魅力にはまりました。
K:野生って、カットした木ではなく、生えている木に着生しているやつですよね? 写真でしか見たことありませんが、生で見たら凄いんだろうなぁ。
T:生の迫力は凄いですよ! ビカクシダに限らず、原生地はユニークな植物の宝庫なので、植物が好きなら一生に一度は見る価値があると思います。
K:高橋さん企画で、ぜひツアーを(笑)。さて、こうして皆さんにその魅力を伝える側になられたわけですが、そんな高橋さんの手がけたビカクシダは、東京の『vandaka plants GALLERY TOKYO』でも見ることができるそうですね。こちらのギャラリーについて教えていただけますか?
『vandaka plants GALLERY TOKYO』
T:現在『vandaka plants』は、東京と京都に2店舗ありまして、日本橋馬喰町にある東京店のほうが、『vandaka plants GALLERY TOKYO』です。馬喰町界隈には、アートギャラリーも多く、最近はおしゃれな店も随分と増えており、東京店のある「BAKUROCACTUS」も、各階にアートギャラリーなどが入った面白いビルです。アートピースのようにビカクシダを見せるという、園芸店とは違うアプローチの仕方が、ビカクシダの面白さ、すばらしさをお伝えできるのではないかと考えて、壁一面ビカクシダで覆うなど、展示方法も工夫していますので、ぜひ遊びに来てください。
K:ありがとうございます。近日中に、そちらのほうも取材させてください。
T:もちろんです、お待ちしています。
K:このように東西からビカクシダの魅力を発信されているわけですが、今までビカクシダと関わってきた中で、最も印象に残っているエピソードがあれば教えていただけますか?
T:そうですね、たくさんあって一つに絞れませんが、仕入れ先でもあるタイのバンコクで定宿にしているホテルがあるのですが、毎回利用しているうちに、仕入れたものの持ち帰れなくて置いていったビカクシダを、仲のよい従業員さんが世話してくれるようになり、それらが徐々にホテルを占領していってしまい、エントランスと屋上がビカクシダだらけのホテルになってしまっていること、などでしょうか。旅先での思い出は数え切れませんよ。
K:そのホテル、見てみたい(笑)。ビカクシダマニアにとっては夢のようなホテルですね! では最後になりますが、ガーデンストーリー読者の皆さんに、何かメッセージをいただけますか? 読者の中には、ビカクシダについて今回初めて知る、あるいは興味を持ったという方も多いと思います。

T:ビカクシダの魅力は、個性豊かな種類がたくさんあることに加え、育て方によってもいろんな表情を見せてくれるところです。また観葉植物の中でも成長が早いところや、壁に掛けて管理ができるので、インテリアとしても楽しめるところなど、そういったたくさんの魅力を、読者の皆さんにぜひ知ってもらえたら嬉しいですね。そして、皆さんがそれぞれのライフスタイルに合わせて、ビカクシダを楽しんでいただけたらと思います。
K:本日はお忙しいなか、ありがとうございました!

いかがでしたか? ビカクシダ。今回の私がそうであったように、皆さんにも興味を持っていただけると嬉しいです。インタビューにもあるように、私は近日中に、『vandaka plants GALLERY TOKYO』にお邪魔して、改めてビカクシダの魅力を再発見したいと思います。いずれその模様もご紹介しますので、どうぞお楽しみに!
「vandaka plants」のさらに詳しい情報はこちら
Instagram https://www.instagram.com/vandakaplants_official/
【KYOTO SHOWROOM】
住所:京都府京都市上京区三軒町48-15
電話:080-4014-2855 メール:info@vandaka-plants.com
【GALLERY TOKYO】
Instagram https://www.instagram.com/vandakaplants_gallerytokyo/
住所:東京都中央区日本橋馬喰町2-4-1 BAKUROCACTUS 4F
電話:03-6683-9120 メール:info@vandaka-plants.com
※京都、東京、両ショップ共、営業日、及び時間はwebサイト内のカレンダーにてご確認ください。
食虫植物ブース【関西食虫植物愛好会】を訪ねる
『関西食虫植物愛好会』とは

最近はホームセンターの園芸コーナーで見かける機会も多くなった食虫植物。私もかつて、あの大きな口で虫をバクっとやるハエトリソウを育てたことがあります。まさにホームセンターで購入したのですが、見る見るうちに成長し、やがては千手観音像の幾多の手のごとく増えて、その栽培が結構楽しかったのを覚えています。
と、そんな経緯もあることから、興味津々でブースを訪ねましたが、こちらのブースは屋号が「愛好会」なので、サークルの集まりなのかなと思いきや、販売している商品は全てホームセンターで売られているものよりも本格的で、見たこともないような品種も多数。お話を伺ったメンバーの南あこさんからは、食虫植物の知られざる実態をいろいろと教えていただきました。
ふざけた感じのネーミングセンスが楽しい食虫植物
南さんにお気に入りの1株を伺ったところ、ピックアップされたウツボカズラ「ネペンテス・エトセトラ」のネーミングに笑ってしまいました。「石原さ●み風プルプルリップ」って(笑)。確かに壺の口部分は、虫が滑りやすいようにプルプルになっていますが、このド直球のネーミングセンスには脱帽です。


ここにある株は、私の知っているホームセンターのそれとは違い、どれも皆立派でバラエティー豊か。例えば、この赤い粘着質のある部分で虫を捕らえる品種は「モウセンゴケ」というのですが、観賞用にあつらえたものというよりは、いかにも現地に自生しているものをそのまま持ってきました! というようなリアリティーが、どの株からも感じられました。そのどれもが健康そうなので、かなりアグレッシブに虫を捕ってくれそうな気がします。

「関西食虫植物愛好会」の南さんにお話を伺いました

食虫植物のコワイところは、沼にはまっちゃうところなんです(笑)
K:いやぁ、このブースだけアマゾンの秘境ですね(笑)。まず最初に、今回このイベントに出展した経緯を教えていただけますか?
南(以下M):関西食虫植物愛好会は、天下一植物界の前身であるBORDER BREAK!!当初から参加させていただいています。食虫植物はまだまだニッチなジャンルではありますが、ここ10年ほどでホームセンターなどで簡単に手に入るようになり、確実に身近な存在になってきました。イベントは、食虫植物の沼にどっぷりハマった私たちにとって、食虫植物の知名度を上げるためはもちろん、私たちのような趣味家や、多様な植物を愛する人のためにもとても素晴らしい機会だと思い、今回も楽しんで参加させていただいています! ちなみに、私たちは企業というより、愛好会組織なんです。
K:というと、大学のサークル的な?
M:それよりはもっと踏み込んで、自生地保全、普及活動、研究発表、植物園とのタイアップ企画などの活動もさせていただいていますが、もっと自由に愛好者同士で集まろうよ! 基本はニッチなジャンルだからこそ趣味の同じ仲間を見つけて楽しくワイワイ集まろうよ! という趣旨がベースにはあるので、そこを意識してこの名前がついています。
K:なるほど、ゆえに名称も「愛好会」なのですね。そんな皆さんが、今回の出展で来場されたお客様に、ここを一番見てほしい! というところがありましたら教えていただけますか?
M:食虫植物というと「ハエトリソウ」「ウツボカズラ」といった有名どころを想像し、鬱蒼とした薄暗いジャングルに生息しているイメージを持っている方が大半かと思います。でも本当は、山上にある開けた湿地とかで、太陽を燦々と浴びて育っている食虫植物が大半なんです。名前のインパクトと反比例して可愛らしい花を咲かせたり、水の中に漂っていたり、昆虫と共生したりと、知れば知るほど想像を超えてくる彼らの生態には他の植物にはない面白さがあり、ハマッたら抜け出せないと思います! なので、一番見てほしいのは、ズバリ、商品全てですね。

K:おっと! 全部ときましたか(笑)。まぁ確かに、指を入れたら指が溶けちゃうんじゃないかとか、そんなちょっと怖いイメージを持っている人は多いかもしれないですね。かく言う私も、ホームセンターでハエトリソウに出会うまではそうでしたが、イメージがちょっと変わりました。そんな食虫植物と南さんが出会い、惹かれるようになったきっかけは何だったのですか?
M:幼少期に植物図鑑で知ったウツボカズラと私が実際に出会ったのは、大人になってから行った植物園の食虫植物展でした。実際の姿を見て、なぜこんな形になったのか? どうやって虫を食べるのか? 食べた虫はどうなるのか? どのくらい消化液は強いのか? といった疑問で頭がいっぱいになりました。確かに私もそのときは、生態系ピラミッドを崩すかのような存在に、ちょっと恐怖を覚えたのも事実です。でも怖いもの見たさといいますか、植物園を出る頃にはもう、ウツボカズラの虜でしたね。そして、手に入れたい一心で、植物園の帰りに園芸店をいくつもハシゴして、ウツボカズラをはじめ、その他の食虫植物も大量買いしたんです。そう、食虫植物のこれがコワイところなんです。沼にはまっちゃうんです(笑)。

その後、育て方などを調べていくうちに関西食虫植物愛好会と出会い、現在に至っています。そこで知ったのは、食虫植物っていうくらいだからけっこう強いと思うけれど、じつは意外と儚くて、保護も視野に入れねばならない希少な存在なのだということ。そして気が付けば10年以上経っていて、今はYouTubeで食虫植物の話をしたりと、ありがたいことに面白さを広める側に立たせていただいています。

食虫植物はいけばなの世界でも馴染みが深い植物
K:いやさすが、食虫植物への愛情と熱気がバシバシ伝わってきます! ところで南さん、お名刺を拝見したところ、いけばなの教授、とのことですが、いけばなと食虫植物、何か相通ずるものがあるのですか?
M:じつは、いけばなにとって、食虫植物は昔から馴染み深い植物なんです。私が入門していますいけばな小原流では、二世家元の小原光雲先生が「小原流盛花瓶花傑作選集」という昭和9年発行の本で、すでにウツボカズラを使用した作品を活けておられて、イラストと記録が残っているんですよ。
K:昭和9年って、90年近くも前じゃないですか! そんな昔に食虫植物でいけばなとは、驚きました。小原流は、なかなか攻めていたのですね(笑)。でも、何やら不思議な作品ができそうですね。
M:いけばなでは、ウツボカズラやサラセニア、イビセラという品種が使われることが多いです。私も花展などで自分が活ける場合、ウツボカズラやサラセニアを使っています。流通数が少なく、まだまだ数を揃えることが難しい植物なので、普段の練習やお稽古の時の花材として「今日の材料はウツボカズラよー」なんてことはさすがに言えないのですが(笑)。

大きな花展であれば、会場で食虫植物を見つけることができます。私は花展が終わったら、挿し木や株分けをして、延々とリユースしています。栽培としての姿だけでなく、切り花や作品としてもたくさんの方に目をとめて興味を持っていただき、食虫植物というジャンルがもっと大きく確立できれば嬉しいですね。
食虫植物はお子様の夏休みの自由研究にもぴったり!
K:今回、食虫植物がいけばなで使われているのを初めて知った人は多いと思いますよ。さて、いけばな教授の南さんではなく、プロの生産者・販売業者さんとして南さんが食虫植物と関わってきた中で、一番印象に残っているエピソードがあれば教えていただけますか?
M:いろんなイベントに参加させていただいていますが、だんだんと「あ、前もイベントの時に来てくれてはったなー」みたいに、顔馴染みになってきたお客様が増えた時は、やっぱり嬉しいですね。販売の流れが落ち着いた頃に「一年前のイベントで買ったコレが今こんな感じでー」と話しかけてくださったり、その際に写真でめっちゃ育ってるのを見せてくださったりと、いろいろ共有できるのも嬉しいです。そして仲良くなって植物園や自生地に遊びに行く…そんな関係になれるのが愛好会としての生産販売者冥利に尽きるなと思っています。
K:一期一会といいますからね、同じ趣味の輪を広げるには、イベントは最高の場所ですね。さて最後に、ガーデンストーリーは、グリーンと共に日々の生活を楽しむためのコンテンツをお届けしているWebメディアでして、そんな読者の皆さんに、何かメッセージをいただけますか?
M:食虫植物には、小さな子供から大人まで、人間を虜にする不思議なパワーがあります。お子様の夏休みの自由研究にも使えて、みんなの目をオッと釘付けにするような話題にもなる不思議な魅力を持った植物です。温度管理が! 湿度管理が! 虫をあげなきゃ! といろいろ思いがちですが、皆さまの暮らしにスッと溶け込める食虫植物がじつはたくさんあります。1人でも多くの方と食虫植物たちの魅力を分かち合うことができれば嬉しいです。ぜひこの夏、食虫植物をおうちにお迎えしてみませんか?

K:今日はお忙しいなか、ありがとうございました。おかげで食虫植物という存在がとても身近なものになりました。
取材前のリサーチで、まず名称の段階でインパクト大の『関西食虫植物愛好会』。当日現地に向かう飛行機の中でも「さぞかし変わった人たちなんだろうなぁ…」と思っていたら、その予想は、まぁ当たってはいましたが(笑)、とにかく、ただひたすら真っ直ぐに食虫植物を愛する南さんでした。
『関西食虫植物愛好会』のさらに詳しい情報はこちら
ビカクシダに食虫植物、噛めば噛むほど味わい深い亜熱帯の植物の魅力に興味津々
いや、なかなかに新しい発見ずくめのビカクシダに食虫植物でした。植物というのは、人類の祖先が水から上がる前に既に地球上に存在していた、いわば生命の大先輩。他の木に着生したり、虫を食べたり、生き残るために遂げた進化には、人間の進化よりも長い時を費やしたのではないかと想像すると、ビカクシダにも食虫植物にも、地球レベルのロマンを感じずにはいられません。
『関西食虫植物愛好会』の南さんの言葉を借りますが、いかがでしょう? この夏、そんなロマンをおうちに迎え入れてみては?
天下一植物界各ブース情報や、主催者長谷圭祐氏のインタビューなど、イベント全体像を網羅したVol.1は下記リンクより。
●【天下一植物界Vol.1】話題の多肉、塊根、熱帯草が目白押し!
Credit

文/写真:編集部員K
フリーランスのロックフォトグラファーを経て2022年4月にガーデンストーリー編集部に参加。サボテンに魅せられて以来5年、仕事でサボテンに関われることを神に感謝している。
おすすめアイテム

バードハウス Green -GARDEN STORY Series-
まるで英国の田舎町にありそうなガーデンシェッドを思わせる、小さな家の形をしたバードハウス。鉢植えやジョウロ、寝そべる犬など、ミニチュアのような細かな装飾が施され、オブジェとしても心惹かれる愛らしさがあります。 入り口の穴は直径27mm。シジュウカラやヤマガラなどの小型野鳥が安心して出入りできるサイズです。
新着記事
-
ガーデン&ショップ

「東京パークガーデンアワード@夢の島公園」でガーデン制作に挑む! 5人のガーデンデザイナーの庭づくりに…
都立夢の島公園(東京都江東区)にて現在開催中の「第4回 東京パークガーデンアワード」。今回も、個性あふれる気鋭のガーデンデザイナー5人が選出され、2025年12月、それぞれの思いを込めたガーデンが制作されまし…
-
樹木

【憧れの花14種】毎年植え替えなくていい? 「ラックス」と「シュラブ」で叶える、手間なし…PR
大雪や寒風、冬の寒波で、春の庭仕事・庭準備がなかなか進まない、毎年の植え替えが負担……。そんな方にこそおすすめしたいのが、一度植えれば毎年春を彩ってくれる植物たちです。特に、驚異的な強さと輝く花姿を兼…
-
観葉・インドアグリーン

手軽にできる苔(コケ)栽培! 癒やしの“苔植物”の基礎知識と枯らさない管理術
特有の趣があり、世界中で親しまれている植物「苔(コケ)」。日本庭園の苔むした風景には、静かで奥深い風情があり、盆栽の株元にあしらったり、芽出し球根の寄せ植えの表土に貼って景色をつくったりと、さまざま…


































