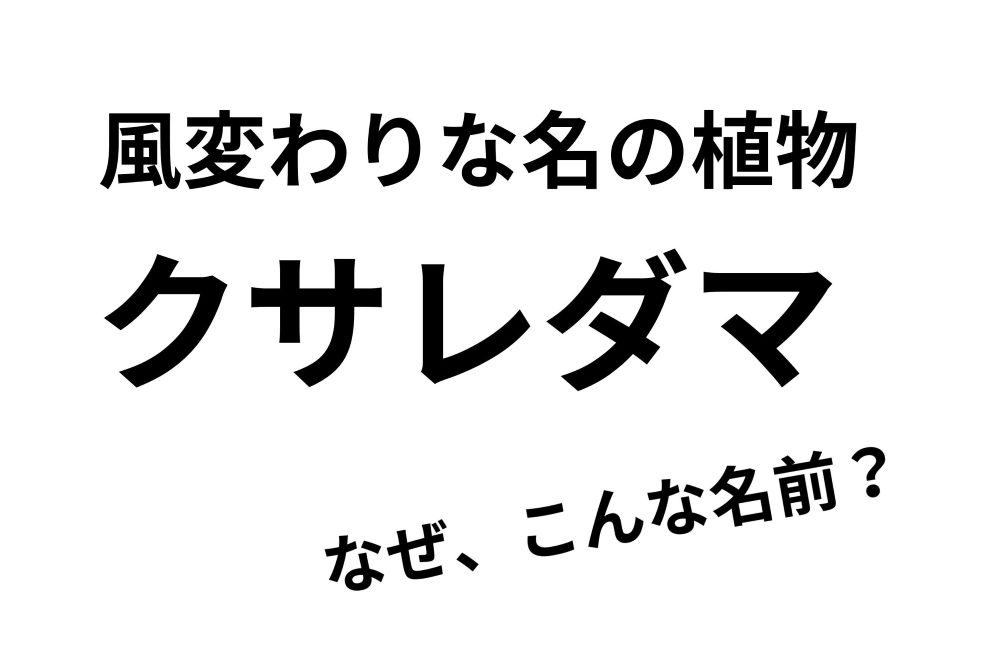- TOP
- ガーデン&ショップ
ガーデン&ショップ
-
フランス

【一度は行きたい】花好きを魅了するフランス「シュノンソー城」王妃たちの庭園を巡る旅
フランス王妃たちの庭園、花々が溢れるシュノンソー城 フランスの中央部を流れるロワール川の支流、シェール川のほとりに位置するルネサンス様式の優美な古城シュノンソー。古くは王室の居城であり、歴代女城主によって守られてきたことから、貴婦人たちの城とも呼ばれてきました。 フランス国王アンリ2世の王妃カトリーヌ・ド・メディシスと美貌で知られた寵妃ディアーヌ・ド・ポワティエのこの城をめぐる確執は有名です。そして現在のシュノンソー城では、歴史的な面影に新たな見どころが加わり、さらに魅力的になった庭園が見逃せません。 シェール川の水景を生かしたディアーヌの庭 ディアーヌの庭全景。 16世紀中葉、アンリ2世は最愛の寵妃ディアーヌ・ド・ポワティエに、王室所有であったシュノンソー城を与えます。ディアーヌはルネサンス様式の城をさらに整備し、美しい庭園をつくらせました。洪水対策として川面よりも高い位置につくられ、石壁で囲まれた構造を当時のままに残す12,000㎡ほどの「ディアーヌの庭」には、穏やかなシェール川の水景を生かした景観設計がなされています。外の景観を取り入れ、建物と調和したエレガントな庭園です。 ディアーヌの庭のポイントにはスタンダード仕立てにしたムクゲなども使われている。中央は芝生とミネラル素材で形づくられたアラベスク模様。 城から庭を見下ろした時に最もよく映える、芝生の上に描かれた端正な幾何学模様は、19~20世紀の著名な造園家アシール・デュシェンヌ(1866-1947)によるものです。 カトリーヌの庭 カトリーヌの庭。バラやラベンダーが使われたクラシカルで優雅なフォーマル・ガーデン。 城の建物を挟んで反対側には、アンリ2世が逝去するとすぐ、ディアーヌからシュノンソー城を奪回した王妃カトリーヌ・ド・メディシスがつくらせた「カトリーヌの庭」があります。かつては川向こうまで広がっていた庭園ですが、現在残る部分は約5,500㎡と、こぢんまりとした親密な雰囲気のあるルネサンスの整形式庭園です。 カトリーヌの庭正面のシェール川の向こう側にも森が広がる。 イタリアの庭園芸術の流れを汲んで、城の建築と一体化したシンメトリーな整形式のデザインは、城の景観を見事に引き立てています。庭園に動きを与える中央の噴水を囲み、リズムよく配置された壺などの彫刻を用いた装飾も、やはりイタリアの影響を受けたもの。 カトリーヌの庭から見たシュノンソー城。ロワールの古城の中でもひときわ優雅。 こうした整形式庭園の構成要素は、17世紀のフランス絶対王政の時代に、ル・ノートルによって完成されるフランス整形式庭園に引き継がれていきます。 スタンダード仕立てのバラや、ラベンダーなどが多用された植栽には、シュノンソー城らしい女性的でロマンチックな雰囲気が醸し出されているように感じます。 城内の窓から見た、穏やかに流れるシェール川と、川に面したカトリーヌの庭。城の周りは御伽話の世界にトリップしそうな、こんもりとした森に囲まれています。 ラッセル・ページの庭 ラッセル・ページ記念庭園。シンプルな洗練された緑の空間に、ラランヌの羊の彫刻が点在してユーモラス。 カトリーヌの庭から少し離れると、かつてカトリーヌが動物小屋や鳥小屋を作らせていた、現在はさまざまな木々が主体となった「緑の庭」があります。その先には、20世紀を代表するイギリスの造園家ラッセル・ページ(1906–1985)へのオマージュの庭があります。 全体にシンプルなシンメトリー構成のラッセル・ページの庭。庭を囲む壁に沿って、イギリス風のボーダー植栽が。 現代の造園家によって十数年前につくられたもので、城の建築に隣接した歴史的庭園空間とは異なり、モダンな美意識が感じられる、グッとシンプルに洗練された庭です。ページのモットーであった「自然と建築の調和」に則りつつ、シンプルな緑を生かした構成に、フランスの彫刻家フランソワ=グザビエ・ラランヌによるアート作品が彩りを加え、現代アートと庭園の融合を楽しめる空間でもあります。 フローリストの庭 フローリストの庭。 さらに、現在のシュノンソーの城と庭園の新たな魅力になっているのが「フローリストの庭」です。かつてルネサンス期には、実用のためのハーブ園やポタジェ(菜園)はあったにしても、 花々はあくまでも庭園の装飾要素、またはポタジェの一部であったに過ぎなかったようです。 訪れた9月はダリアが盛り。城内のアレンジメントの花々が花畑でも見られるので、散策するのもとても楽しい。 現在のシュノンソー城のポタジェはまさに「花のポタジェ」で、敷地内のレストランでも利用されるさまざまな栽培野菜とともに、リンゴの木やバラで仕切られた12区画の植栽エリアは、城内のフラワーアレンジメントに切り花として使うための季節の花々を提供する花畑になっています。ここで栽培された食用花は敷地内のレストランのシェフが料理に利用することもあれば、フローリストたちが野菜をアレンジに使うこともあり、さらなるクリエイティビティの可能性に貢献する庭にもなっているといいます。 庭の中には19世紀の農家を移築したフローリストのアトリエがあります。ここではワークショップなども行われるとのこと。 訪れた時には盛りは過ぎていてあまり目立っていませんでしたが、フランスのポタジェの野菜の定番であるアーティチョークは、じつはカトリーヌがフランスにもたらしたものの1つだそうで、そうした歴史的背景も考慮した城内のフラワーアレンジメントによく登場するのだとか。 フラワーガーデンと城内を飾るアレンジメント 城内のフラワーアレンジメントはどれも素敵で、この部屋ではランとケイトウ、ヨウシュヤマゴボウ、枝垂れるアマランサスなど、花器からこぼれるようなアレンジが。ヒストリカルな室内の雰囲気をさらに盛り上げている。 「フローリストの庭」が作られたのは2015年頃からと近年のことで、シュノンソー城は、ロワールの古城の中では唯一、自前のフローリストチームを抱える城でもあります。ヨーロッパ・ジュニア・チャンピオンで国家優秀職人賞を受賞した経歴をもつフローリスト、ジャン=フランソワ・ブーシェ氏率いる3名のフローリストチームが、城内19の各部屋を飾るフラワーアレンジメントを毎週作り変えています。 この時期、フローリストの庭で煙のような穂をつけていたグラス類の隣には、赤や黄色のケイトウやカンナも開花。 フローリストの庭では、毎年6万本以上の切り花用の植物が栽培されていますが、材料としてはそれだけではとても足りないそうで、毎朝アレンジメントの状態をチェックして、花材の発注をしたり、市場が休みの月曜の朝は、自然の中にグラス類などの花材を探しに出るのだとか。ブーシェ氏によれば、野生の素材はアレンジに命を与える点が素晴らしいのだということですが、これも自然に囲まれた城という環境ならではの贅沢でしょうか。 城内のアレンジメントは、シンメトリーを基本とした優雅でゴージャス、非常にオーナメンタルで、家具類やタペストリー、美術品のコレクションが飾られたルネサンスの城の各部屋に華を添え、次はどんなデコレーションに出会えるかと、歩を進めるのが楽しくなってくるほど。 また、非常に華やかなアレンジの中にも、シャンペトルな自然の雰囲気、季節感が強く感じられるのは、フローリストたちの美意識に加えて、庭や近隣の自然に結びついた素材の力も大きいのかもしれません。 大輪のダリアにヨウシュヤマゴボウが動きを添えるアレンジメント。 城の中も外も、見どころが尽きないシュノンソー城。オランジュリーはレストランとサロン・ド・テになっており、食事もゆっくりできます。花々に囲まれ、昔日の貴婦人になった気分で、一日ゆったりと過ごしてみたい場所です。 庭園内のかつてのオランジュリーはレストランとサロン・ド・テになっています。優雅な気分で食事やお茶を楽しめます。
-
フランス

【フランスのバラの楽園へ】アンドレ・エヴが遺した「香りのナチュラルガーデン」を訪ねて
アンドレ・エヴのバラの庭へ アンドレ・エヴ(André Eve 1931-2015年)はフランスの著名なバラの育種家です。数々の名花を作出し、またモダンローズの全盛だった1980年代から、現在に続くオールドローズの人気復興に貢献した人物としても知られます。彼が作り育てたプライベートなバラの庭、また現在も後継者たちが見事な育種を行うバラのナーセリー、アンドレ・エヴ社の育種場兼展示ローズガーデンなどの素晴らしいバラの庭は、フランスのロワレ地方にあります。 ロワレのバラ街道。loskutnikov/Shutterstock.com この地域は、バラの生産が盛んであると同時に、見所の多い植物園や庭園を擁する土地であることを生かし、近年には「ロワレのバラ街道」なる、フランスのバラと庭園を訪ねる観光ルートが立ち上げられているほどです。 バラの最盛期である6月初めに、このバラの庭を訪れる幸運に恵まれました。 1969年発表の‘シルヴィ・ヴァンタン’。Alexandre Prevot/Shutterstock.com アンドレ・エヴは、ベルサイユ園芸学校で造園を学んだのち、造園家として活躍するうちにバラ園芸に魅せられて育種家となります。彼が作出した最初のバラは、1969年発表の‘シルヴィ・ヴァンタン’でした。70年代から80年代には、どちらかというと派手めなモダンローズが流行の傾向にありましたが、そうした中でオールドローズの魅力をいち早く再発見したのも彼でした。 バラと宿根草のナチュラル・ローズガーデン アンドレ・エヴのナーセリーは、育種家ジェローム・ラトゥーらに引き継がれ、現在もフランスきってのバラのナーセリーであり、メゾン・ディオールのためのバラ‘ジャルダン・ド・グランヴィル’などの名作を次々に作出し続けています。 2016年に社屋を移転したシリュール=オ=ボワの地では、創設者のエスプリを大切に作庭された「アンドレ・エヴの庭(Le jardin André Eve ® )」で、100近いオリジナル品種のバラとともに、オールドローズをはじめとするバラのコレクションが、宿根草や灌木類、小型の果樹など、バラの「コンパニオン」と呼ばれる草花とともに植え込まれ、洗練されたナチュラル感溢れるバラの風景を作り出しています。 バラを活かす庭デザインの秘訣 白樺などナチュラル素材を仕切りに用いて自然な雰囲気を心がけたボーダー植栽。 さまざまな姿形で咲き誇るバラたちで賑やかな庭に入って気がつくのは、まずその香りです。バラの季節の雨上がりの庭、一歩足を踏み入れた途端に、繊細なバラの香りに包まれ、さらに園路を散策しながら一つひとつのバラの香りを呼吸すれば、もうそれは至福の心持ちに。ようやく我に返って、バラ栽培に重要な日当たりを確保するため、敢えて大木は避けた空間がのびのびと広がっているのを気持ちよく眺めます。 バラと宿根草、灌木類がミックスされた植栽がポイント。 美しいばかりでなく、無農薬の自然な栽培に向く耐病性・耐久性の高いバラを目指したアンドレ・エヴの庭は、デザインにも洗練された素朴さ、ナチュラル志向が表れています。構成はフォーマルな左右対称ではない自然風。よくイギリス風のコテージガーデンに見られるような、きれいに刈り込まれた芝生のライン、または白樺などの木材で区切られたバラと宿根草の植栽の間には、緑地になった曲線の園路が設けられ、ゆったりと散策しながら間近で植栽された植物を観察できます。 パーゴラも丸太を利用し、全体のトーンをナチュラルに統一。 また、丸太のパーゴラやアーチ、壁面に盛大に這い上るつるバラの姿がそれは見事です。 それぞれのバラの個性を魅せつつ、ヒューケラやホスタ、デルフィニウムやシャクヤクなど、バラと共存しやすいコンパニオン・プランツを組み合わせて、全体として自然な風景が創り出されているのが大きな魅力の1つ。庭づくりの参考になる見所が随所にありました。 庭を案内してくださったアンドレ・エヴ社のドニーズ・フランソワさんによると、バラを庭に植え風景を創るときのポイントの1つは、3本以上同じ品種をまとめて植えること。ボリュームを出すことによって、そのバラの存在感が遺憾なく発揮される、その目安が3本以上なのだそう。 芝地に緩やかな曲線をベースに配置された植栽グループ。 1本ずつぽつんぽつんと植えるのでは、この存在感が出にくいのです。また、多少空間がありすぎるように見えても、成長は早いので、それぞれに必要な間隔はあらかじめ空けておくこと、アーチなどに這わせる際の注意点など、具体的にバラを庭に取り込むために役立つアドバイスが満載です。 「結婚の部屋」バラ育種の現場 「結婚の部屋」ビニールハウスで、案内してくださったフランソワさん。 さらに興味深かったのが、実際に新品種開発のための交配を行っている場所の見学です。そこは、将来の新品種の父と母となるべく選出されたバラのポットが並ぶ、フランス語で「結婚の部屋」と呼ばれるビニールハウスです。 不純物が混じらないように、あらかじめ父となるバラの開花前に雄しべを取っておき、母となるバラの雌しべの開花の準備ができたところで人工交配が行われます。秋まで待って、成熟した実から種子を採取し、12月まで冷蔵ののち播種して隣の「育児所」ビニールハウスで栽培していくという、とてもベーシックな方法で育種が行われています。 「育児所」となるビニールハウスの中。札に示されている写真のバラを両親として生まれた新種のバラたちの花姿を見比べると、色も形も性質もさまざまあって興味深い。 面白いのはその子どもたち。ひとつとして同じ姿形がない、じつに変化に富んだバラが生まれるのです。育種家は、それぞれのバラの姿形や香り、花数や返り咲き性の高さなどを日々つぶさに観察し、新品種候補のバラが選ばれます。 同じ両親を持つバラの子どもたち。見た目からそれぞれに全く違うのが面白い 。 現代の新品種作出時の最重要項目としては、姿形や香り、返り咲き性もさることながら、強い耐病性や乾燥への耐性などが欠かせません。農薬などを使わない自然栽培に向き、天候不順にも適応できる耐久性を併せ持ったバラが求められるのは、現在の庭園の在り方の流れを反映しているといえるでしょう。 庭に隣接した野外の販売コーナー。 3万粒ほどの種子を播き、9年ほどをかけた栽培ののちに、実際に新品種としてデビューするのは、年間に3~5点とごく僅か。自然の驚異と育種家のバラへの情熱と深い造詣に裏打ちされた日々の努力、生み出される新品種のバラそれぞれの姿が、ますます魅力的に見えてきます。 ガーデニングをしていても、バラは敷居が高い、難しいと感じている方は結構いらっしゃるのではないかと思います。じつは私もその一人なのですが、やっぱり挑戦してみたいと思わせられて、カタログを眺めてはあれこれ想像の翼を広げる日々です。
-
フランス

年間75万人が訪問するフランス「モネの庭」 なぜ人々は心奪われる? 復元された魔法の庭
ジヴェルニー「モネの庭」の魅力を深掘り 5月になるとバラの香りに包まれるモネの家。 睡蓮の連作などで知られる印象派の画家クロード・モネ(1840-1926年)の庭は、フランス、ノルマンディー地方の入り口、人口500人ほどの小さな村ジヴェルニーにあります。ひっそりとした佇まいを想像したくなりますが、じつは年間75万人もの人々が訪れる、モン・サン=ミシェルに次ぐ、ノルマンディー地方第2の大人気観光スポットです。 家の前には赤とピンクのペラルゴニウムが、かつてのモネの庭と同じように群れ咲いています。 さらには日本にも「モネの庭」が再現されているほどで、庭好きさんはもとより、多くの人々を魅了するこの魅力とは、どんなものなのでしょうか。モネの庭の2025年の様子をお伝えします。 画家の夢の庭 「水の庭」の太鼓橋。4~5月には紫と白のフジの花が咲き継ぐ見どころです。 画家モネが、家族とともにジヴェルニーの家に移り住んだのは1883年、彼が43歳の頃。戸外の自然の風景を描き続けてきたモネにとって、川の流れや林、牧草地に囲まれたこの地の自然は格好の画題となります。そして新たな情熱となったのが、庭づくりでした。方々に写生旅行は続けながらも、園芸雑誌を熟読し、園芸仲間と情報や種苗を交換し合って没頭した庭づくりは、50歳になる頃にはさらに大々的に進められます。 食堂はクロームイエロー、台所はブルーと白など、大胆な色づかいの内装もモネ自身が考えたものだそうで、とても可愛らしい空間になっています。壁を飾る浮世絵を見ると、モネのコレクションの様子が分かります。 ようやく画家として認められて財を成し、借家だった家と土地を買い取れるまでになったのです。庭師を何人も雇い、珍しい種苗を取り寄せて、理想の庭をつくり上げます。かつて農家だった建物とその敷地は、鮮やかな色彩が溢れる夢のような庭となり、亡くなるまでの43年間をここで過ごした画家の終の住処となったのです。 「花の庭」と「水の庭」 「花の庭」5月の中央園路の様子。アーチにはつるバラが咲き、その足元にはアリウムをはじめパープル系の花々が。 モネの庭は、大きく雰囲気の異なる2つの庭で構成されています。まず家の裏に広がるのは「クロ・ノルマン」(クロは囲まれた土地の意味)と呼ばれた「花の庭」。家屋の中央から庭の正面を貫く幅広い中央園路が印象的です。かつては並木道だったそうですが、モネは家の近くにある一対のイチイの大木を残して、すべて取り去ってしまい、モネの庭のシンボル的な存在でもある、バラが絡むアーチが続く明るいトンネルを作りました。 同じ中央園路の4月の様子。まだ閑散とした早春の庭では、チューリップをはじめとする春先の球根花たちが大活躍。 幾何学形の花壇がリズムよく並ぶ全体の構成はポタジェ(菜園)のようですが、これでもか、というほどにぎっしりと、さまざまな草花が植栽された花の園です。 「水の庭」の5月、白花のフジが咲き残る緑色の太鼓橋の上は、いつも人がいっぱいです。 そして道路を挟んだ向こう側のエリアは、後になって土地を買い足し、近くを流れるエプト川支流の流れを変えて、睡蓮の池とフジに縁取られた緑の太鼓橋をポイントにした、日本風の「水の庭」をつくりました。 「花の庭」の5月、枝垂れるスタンダード仕立てのバラと、足元のアイリスなどが満開に。 モネ没後、最後の直系の遺族だった息子の死に際して、残されていた作品や家と庭はフランス芸術アカデミーに遺贈されます。その頃の庭はすでに、手入れもされず元の形は失われかけていたのですが、1970年代から1980年代にかけて最初の復元プロジェクトが始まります。そして、庭を描いた作品や写真、モネの手紙や種苗の注文書などの資料をもとにした復元作業によって、輝くような本来の姿を取り戻しました。元どおりというばかりでなく、世界中から訪れる観光客に配慮して、一年中見どころがあるようにと、復元を超えて季節をくまなくカバーするような植栽計画がなされています。 「花の庭」花々が咲き継ぐ春から秋へ 4月の「花の庭」の様子。注意深く見ると、しっかりと区画分けされた花壇のそれぞれがテーマカラーを持っています。 現在のモネの庭の開園は、毎年4月初めから10月末まで。季節の花々が主役の庭ゆえに、冬季は閉園になります。4月といえばフランスではまだ早春ですが、庭を訪れてみると、スイセンやフリチラリア、色とりどりのチューリップをはじめとする、華やかなスプリングエフェメラルたちの饗宴に、思わず目を奪われます。この時期はまだ花壇の構造もはっきりと見えているので、それぞれの花壇ごとに色調がまとめられているのがよく分かるのですが、全体を眺めようとすると、それはまるでパレットに並べた絵の具の色彩が一度に目の中に飛び込んでくるようで、圧倒されます。 リンゴや洋ナシなどの果樹の花々は、この時期ならではのフランスの田舎らしい早春の風景。 そして5月、ひと月経つか経たないかの間に、すっかり様変わりした庭の、満開に近づくバラの下にアイリスやシャクヤクが咲く花風景は、まさにゴージャス。自然な風景を好んだモネのバラの好みは、白やピンク系のオールドローズ、白モッコウバラや野バラなど。当時から栽培されている品種だけでなく、例えば当時は存在しなかったイングリッシュローズ、デヴィッド・オースティンの‘コンスタンス・スプライ’など雰囲気の合う現代のバラも植栽に加えられています。 バラが咲き出す5月の風景。たった1カ月の違いで、緑も花もどんどん育ってまったく違う様相に。 そして夏から秋にかけては、ダイナミックにダリアやヒマワリが咲き、オレンジのナスタチウムが中央の園路を覆うというように、また違った花風景が展開します。いつの季節も豊かに咲き乱れる花々に囲まれて、うっとりと幸せな気持ちになってしまう、魔法がかかっているかのようです。 庭のそこかしこから、思いがけない花風景が広がって、息をつく暇もないほど。でも気持ちはウキウキ、そしてゆったりと庭を散策。 日本を意識してつくられた「水の庭」 「水の庭」4月の様子。睡蓮は夏になってからが出番なので、まだ姿は見えないけれど、池の周りにも変化に富んだ色彩の華やかな植栽が施されています。 幾何学構成の花壇の花々があふれ、その色彩に埋もれてしまいそうな「花の庭」に比べると、「水の庭」は、常に微妙な変化を見せる水面と空と植物とが織りなす、ぐっと落ち着いた空間です。 モネは浮世絵のコレクターで、家のなかには収集した浮世絵がたくさん飾られていたそうですが、池の外周を囲う竹林や、緑にペイントされた太鼓橋にフジの花や睡蓮の花という、和を感じる植物のチョイスには、当時流行したジャポニスムの影響が見られます。 「水の庭」の4月は、ヤエザクラや早咲きの紫のフジなどの花木が春らしい彩りを添える。 自然風景のなかにある、特に光や色彩、天候や時刻による変化を捉えようとしたモネにとって、睡蓮池の水景は刻々と表情を変える光、水、空気までもを捉えるための、描き飽きることのないモチーフとなりました。晩年には白内障を患い、視力を失いつつあるなかで描き続けた睡蓮の連作は、抽象絵画の先駆けとして現代美術への扉を開くことになります。 5月の池の周りでは、ボルドー色の紅葉の隣に紅のツツジが華やかに咲き、少し進むと白花と紫の爽やかな組み合わせが。 モネの息子から遺贈された作品はマルモッタン美術館に所蔵され、この庭とアトリエで制作された最後の大作はフランス政府に寄贈されて、現在パリのオランジュリー美術館に特別に誂えられた展示室で観ることができます。 池の外周を囲む竹林で一気に雰囲気が変わります。近年ではフランスの庭でも竹を使うところは多いですが、当時はまだ珍しかったそう。また、垣根にも竹垣を用いるなど、和風へのこだわりが感じられます。 画家の庭の魅力 芸術家の庭は、造園家が設計するのとはまた違った自由な着想が魅力であることが多いのですが、モネの庭もその1つ。シンプルな構成のうえに、画家としての色彩感覚と、たっぷりの植物愛をこめて配置された過剰なまでの花々。庭師たちの手間暇惜しまない維持管理が、モネの庭を特別なものにしているのでしょう。また、モネの愛したノルマンディーの絶え間なく変化する空と光と空気感も、この空間を輝かせている重要な要素なのだと思います。 ジヴェルニーの村を散策するのもおすすめ ジヴェルニー印象派美術館のカラフルな庭園。Alex_Mastro/Shutterstock.com 小さな村のなかには、土産物を売る店やら、かつて芸術家たちが集ったレストランなどが幾つかあるほか、モネの家と庭からほど近くには、庭付きのジヴェルニー印象派美術館があります。印象派の歴史やその後の展開を紹介する美術館ですが、地元の星付きシェフがプロデュースする付属のレストランには庭に面したテラス席もあり、人混みを離れて緑のなかで昼食を楽しむにもおすすめです。繁忙期には予約したほうがよいでしょう。また、食事のあとに村を散策する時間があれば、教会やモネのお墓を訪れることもできます。 モネの庭から徒歩15分程度の場所にある、ロマネスク様式のサント=ラデゴンデ教会。モネの墓もここにある。Alex_Mastro/Shutterstock.com ジヴェルニー印象派美術館(英語) https://www.mdig.fr/en/レストラン・オスカーOscar(英語) https://www.mdig.fr/en/plan-your-visit/restaurant/ ジヴェルニーへの行き方 ・公共交通機関利用の場合は、パリのサン=ラザール駅より電車で50分ほど、最寄りのヴェルノン=ジヴェルニー駅下車、のちバス(所要30分ほど)かプチ・トランかタクシーでジヴェルニーの村へ移動。繁忙期には混み合ってすぐにバスに乗れないこともあるので、時間には余裕を持って移動するのがよさそう。 ・車の場合はパリから1時間強。駐車場は村のなかのモネの家と庭の向かい側の他にも、外側に大駐車場があります。 ・入場券は現地でも購入できますが、入口には常に長蛇の列ができているので、個人で見学に行く場合は事前にオンライン予約購入が無難です。オンライン購入済みの場合の入口は団体入口になりますので要注意です。 ・パリからの日帰り観光バスツアーも多く出ているので、そちらを利用することもできます。
-
フランス

フランスの園芸愛好家たちに愛されるガーデニングフェア「サン=ジャン=ド=ボールギャール城」をレポート
愛され続ける老舗ガーデニングフェア 白いテントやパラソルの内外に植物の苗がわんさかと並べられています。 パリから南西に30kmほどの田園地帯に位置する17世紀の城館サン=ジャン=ド=ボールギャールのガーデニングフェアは、2024年の春に創立40周年という節目の年を迎えました。歴史的ポタジェで知られる個人所有のお城の庭園内で行われるという場所の魅力に加え、毎回フランス内外から200以上の種苗業者やガーデニング関連の出展者が一堂に集まる場となっており、各地の生産者と交流しながら新種や希少種を発見したり、幅広い品揃えを実際に自分の目で確かめて、質のよいこだわりの苗を購入できるなど、魅力がぎゅっと詰まっています。 植物の性質などを細やかに記した手書きのプレートがついていたり、植物選びを助ける配慮がいろいろあるのが嬉しい。 今回のフェアの注目テーマにも謳われていたのがグラウンドカバー植物ですが、日陰の庭の強い味方のシダ類はいつも人気。 ベルギーから来ているダリアなどの春植え球根も毎年人気のスタンドです。 私自身、毎年このフェアに行くのを楽しみにしているのですが、周りのガーデニング愛好家の方々も同様で、約束せずとも現地で何人も友人知人に出会ってしまうのも面白いところです。この日たまたま出会った友人夫婦は、冬の間ダメになってしまったテラスの植栽の植え替えのために、シュウメイギクやエリゲロンなどの花苗を買い込んでいて、帰ったらすぐ植え替えると言っていました。ちなみに、選ぶのは奥様、植え替え作業は旦那様担当だそうで、なんとなくフランスっぽい役割分担です。 買った苗は、会場内ではカートで運んだり、持参のエコバッグで持ち運ぶ姿が多く見られます。 樹木などは、スタンドから駐車場まで専用車で直接配送もありと、苗木類を購入持ち帰りするためのサービスも至れり尽くせり。 ガーデニングのトレンドをキャッチ 毎年必ず見かける定番の樹木や多年草のほかに、目新しい植物に出会えるのがガーデニングフェアの大きな魅力。さまざまな視点から選出される受賞植物のセレクションにも注目です。 今年の受賞プランツの一部。アガベは大きすぎてプレゼンテーション台に乗らなかったようで、パレットの上に置かれたまま。逆に存在感が出ています。 ヤナギのトピアリーに注目 フランスのポタジェ(菜園)ではレイズドベッドの仕切りなどに、ヤナギの枝を編んだものが使われているのをよく見かけます。昔ながらの手法で、ナチュラルでリュステックな雰囲気が素敵ですが、作り込むのはなかなか大変そう。アール・ド・ヴィーヴル(生活芸術)賞に選出され、フェアで注目を集めていたのが、“ヤナギのトピアリー”と呼んだらよさそうな仕立てもの。 発根能力が高く、しなやかな枝をもつヤナギの性質を生かした鉢植えで、このまま1つ、または幾つかをテラスにアクセントとして飾る、あるいは並べて仕切りにするなど、いろいろ活用できそう。実際にこの鉢を抱えて帰路についている人もたくさん見かけました。どんな風に使うのかしら。 充実のガーデニングツール スチール製の大きなガゼボ。足元には同素材のコンテナーが付属しており、庭にもテラスにも同じように設置できるようになっています。 フェアの楽しみとしては、植物苗ばかりでなく、庭仕事を支えるガーデニングツールや、庭デザインのポイントにもなるアウトドアファニチャーにも注目したいところ。ファニチャーに関しては、木材などの自然素材を生かしたナチュラル感の高いものと、スチール素材のエレガント系が主流です。 木製の柵やバードハウス各種。ガーデンチェアはスタンダードな形をポップな色合いにしてみたり、遊び心を感じる製品もたくさん。 こちらはシンプルながら愛嬌を感じる、スチール板の動物たち。庭に置いたら楽しそう。 実用的な支柱なども、シンプルかつエレガントに使える素材と形が揃っています。 そして、今回特に気になったのが、オーストリアの企業が作っている銅やブロンズ(銅合金)製のガーデニングツールです。 ブロンズの輝きが美しいスコップなどのガーデンツール。土壌や植物を守る効果もあり、環境保護の面からも理想的な伝統の道具でもあります。 これらは昔ながらの風合いの金属色が美しいばかりでなく、じつは鉄と異なり、酸化して錆びることがないので、土に鉄サビを残さず土壌のバランスを崩しません。そのうえ静電気をほとんど帯びないのでシャベルからの土離れがよく、根の周りを丁寧に扱うのにも向いています。また微量ながら銅には天然の抗菌作用があり、病原菌やカビの繁殖を抑えるなど、いくつもの利点があるそうです。さらには、叩き直して修復することもできるので一生ものになる、かなりお高くはあるのですが、世代を超えて使い続けられるとなれば、お値段以上に値打ちのある投資になるかもしれない、永遠の定番です。 HAWSのジョウロなども定番人気の商品です。写真の中には皆さんにも見覚えのあるものが見つかるのでは。 さて、ブロンズの手作り伝統ガーデンツールはオーストリア製ですが、ガーデニング用品のスタンドを覗いてみると、イギリス製のガーデングッズも安定的な人気の様子。日本の皆さんがご存じのグッズも写真の中に見えているのではないでしょうか。 気になるランチタイムは 左端でちょっとボケて写っているのが、手に持ったマカロン。昔風のアーモンド・マカロンです。しっかり甘いけれど美味しかった! ところで、ガーデニングショーでもフード事情は気になりますよね。広い敷地を歩き続ければお腹も空いてきます。ということで、すでに朝のおやつタイムに、こちらのフードスタンド名物の昔風のマカロンをいただいてみました。 通常のマカロンの2倍くらいはありそうなサイズ。アーモンド感がたっぷりでかなり甘くて、昔風といえば納得の、素朴に美味しいマカロン。毎年これを必ず買って帰るというファンもいるそうです。ほかにもヌガー、カヌレやパン・デピスと呼ばれるハチミツ風味のお菓子など、どちらかといえば伝統的なお菓子が揃っています。 左/丸焼き豚プレートは、丸い木のランチボックスにて提供されます。明るい光も何よりのご馳走。右/ちなみにランチをいただく場所から見えるお城のメインの館には、現在も城主のご家族がお住まいなのだそう。 肝心のランチは、サンドイッチなどの軽食を売るフードトラックで調達して、ポタジェの草地やベンチでいただくか、あるいは、大テントとテラス席を備えた期間限定レストランでいただくか。いずれにしてもカジュアルな2択となるのですが、天気さえよければ、どちらも気持ちがよくておすすめです。今回は早めに着いたので、無事レストランのテラス席をゲットして、比較的優雅な外ランチを楽しむことができました。私が選んだのは、丸焼き豚ローストにポテトの付け合わせ、グリーンサラダとシードル、ついでにエクレアも。どれもシンプルに美味しくて、お腹いっぱい、大満足です。 リンゴの花咲く早春のポタジェへ 17世紀からの歴史的庭園でもある整形式のポタジェ(菜園)は、リンゴや洋ナシが花ざかりの早春の風景。 ランチの後はゆるりとお城のポタジェを散策し、名残惜しいスタンドをもう一度確認し、まだスイセンの群生が美しい草地を通って、帰路へ。パリからは車で1時間弱の距離ながら、林に囲まれたお城の敷地に入れば、御伽話の世界に迷いこんだ感じすらしてきます。フランスではお城の敷地を利用してガーデニングショーが行われることが多いですが、それぞれフランスらしさに溢れる自然と歴史文化がミックスされた環境の使い方がじつに上手だなあと、いつも感心しています。 スイセンがそこかしこで咲き続け、シャクヤクはまだ葉っぱが出てきたばかりといった感じ。 定番の植物たちや出展者のブースには安心感がありながら、新たな出会いもあり、毎年期待を裏切りません。今回は、早春の爽やかな花風景も一緒にお伝えしながらのフランスからのガーデニングフェア報告でした! 皆さんも、春からのガーデニングをご一緒に楽しみましょう。 お城の敷地に入るとこんな様子で、ナチュラル感いっぱいの花と緑の風景が広がります。
-
フランス

パリのアーバン・ガーデンショー「ジャルダン・ジャルダン2024」
知られざる歴史遺産、ヴィラ・ウィンザー 19世紀に建築されたヴィラ・ウィンザーは、第二次大戦後、ド・ゴールが大統領になる前に住んでいた邸宅で、その後はウィンザー公爵夫妻が暮らしたことでも有名です。海外人気ドラマシリーズ「ザ・クラウン」で見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれません。邸宅と庭園ともにこれまで一度も一般公開されてこなかった場所ですが、来年からの一般公開に向けて、現在修復整備が進められています。 それに先駆けてのガーデンショー・イベントというのも興味深いところでしたが、最終日にようやく多少の晴れ間があったものの、設営期間から連日雨が続き、傘をさしつつガーデンショーエリアを見て歩くのがやっとという異例の事態でした。改めて青空の下で庭園と邸宅を散策できる日を楽しみに取っておくことにしています。 変わらぬテーマはアーバン・ガーデン 大都市パリという立地と特徴を生かした変わらぬテーマは、日々の暮らしを豊かに、街の緑化に貢献するサスティナブルでスタイリッシュなアーバン・ガーデンです。大手造園会社や著名庭園デザイナーの見応えたっぷりの緑の空間とともに、グランプリの審査対象となるショーガーデンのカテゴリーは3つ。小さな12㎡のミニ・アーバンガーデン、さらに小さい6㎡のアーバン・ポタジェ(菜園)、4㎡のアーバン・バルコニーがあり、決して広くはないことが多いパリのアパルトマンのバルコニーやテラス、中庭のガーデニングのアイデア探しにも楽しいショーです。 小さなポタジェと花咲くアーバン・バルコニー賞を受賞「カレモン」 「カレモン」のタイトルは、フランス語で正方形を表す「カレ」から。キューブ形の木製コンテナーをさまざまに組み合わせたポタジェのデザイン。カテゴリー別の受賞ガーデンには、トロフィーの代わりに、おしゃれなステンレス鋼のシャベルが贈られます。 景観デザイン・グランプリ受賞「感覚の庭・癒やしの庭」 設計:マティルド・ティルマン 「庭と健康」協会が出展したセラピー・ガーデン「感覚の庭・癒やしの庭」。木材などの自然素材を用いたナチュラルテイストの構造物と、感覚を呼び起こすような色彩や香りをもつ植物が、さまざまに異なる雰囲気のコーナーを作る豊かな植栽が魅力。ガーデンの設置工事は設計者とともに協会会員のボランティアが行ったのだそうで、ほのぼのとした雰囲気も魅力。 「読書のための庭、植物の図書館」 設計:ガリー設計事務所 カルチャーという言葉が栽培と文化の2つの意味を含むように、植物を栽培するガーデニングと、同様に精神を耕す読書のための、人に知恵を与え心を解放する小さな緑の空間がコンセプト。ロックな雰囲気が楽しい。 人気のシャネル・ガーデン、今年はアイリスの庭 ショーガーデンの中でも定番で人気を集めているのが、シャネルによる花の庭。メゾンのパルファンの原料となっている植物の1つにフォーカスしてデザインされます。その洗練されたスタイリッシュな佇まいの空間は、いつも注目の的。 今年のテーマのアイリスは、スミレを思わせるような、またそれだけではない重層的な香りが特徴で、シャネル5番や19番といった伝説的なパルファンや、近年大ヒットしているコメットなど多くのシャネルのパルファンに使われています。香り成分が含まれるのは花でも葉でもなく、地中の根茎部分。その栽培の歴史は古代エジプトに遡りますが、フランスでは18世紀にイタリア、トスカーナ地方から伝わったアイリス(IRIS PALLIDA)が、香水を構成する香料の中でも最も貴重なものの1つとなりました。 香料成分を得るためには、栽培に3年、香料抽出作業前の乾燥に3年の合わせて6年という長い年月がかかり、また3kgの香料を得るために1トンの乾燥させ粉状にした根茎が必要だといいます。非常に多くの時間と人手がかかるため、フランスでは1970年代には栽培農家が消滅し、イタリアでも2000年代には同様の状況になってしまいました。モロッコやトルコなどでは別の品種のアイリスの栽培と香料製造が続いていますが、シャネルでは、かつての香料のクオリティを担保するために、南仏の香水の街グラース近くの専属契約農家で自家栽培を行うようになったのだそうです。 シャネルの庭は、ガイドスタッフとともにグループで見学します。スタッフの女性たちの長靴姿も、シックかつ可愛い。 アウトドア・プロダクトの新アイデアも 会場ではガーデンまわりのアウトドア・ファニチャーを見たり、ガーデニング・グッズやウェア、樹木や草花、ハーブなどの苗のスタンドを見て回るのも楽しみの1つ。買い物だけでなく、特にアウトドア・ファニチャー類は、これから製品化されるプロトタイプの展示も多く、新たなアイデアに触れることができるのもショーのよいところです。 上写真は、カラーステンレス製のオブジェ。何かと思えば、なんと新しいお墓のモデルとのこと。箱形のオブジェの中の空間に小枝や木の葉を重ねれば、コンポストボックスも兼ねるのだとか。動植物の形などカットワークになった部分は、故人の想い出になるよう自宅に飾ることもできるのだそうです。 移動が楽な車輪付きのベンチなどもおしゃれなカタチ。 永遠の憧れ、バスケットのピクニック・セットのブース。 パリ近郊でオーガニック栽培されている旬の花、シャクヤクの販売ブース。長蛇の列ができていました。 初夏のガーデンショーでは、芳しい香りのなか、満開のバラの花々を直接見て選べるのも嬉しい。 全体を見回すと、環境への配慮を前提にした都会の小さな庭やテラスをスタイリッシュに楽しむためのアイデアやグッズが、さらにフォーカスされてきた様子のガーデンショー、ジャルダン・ジャルダン2024。個性的なショーガーデンを囲むガーデン業界の専門家たちの集いの場であるのと同時に、さまざまなセミナーやワークショップも開催されました。 自然な様相の池を中心にブランコなどを設えたワイルド感のあるデザインも人気でした。 パリの人々にとっても、バルコニーで育てるハーブ苗や新鮮な切り花を買うことができる、グリーンな週末のアミューズメントの場。蜜源植物を植えるとか、少ない水やりの工夫など、都会のグリーンで自然のためにできることを知り、ガーデニングへの関心を高める機会にもなっていました。 ホワイトとグリーンを基調に、アーチを使って立体感を出した緑の空間は、流行を超えた上品さが魅力。 過去のJARDINS JARDINの記事もチェック!
-
フランス

【パリ近郊の庭を訪ねて】ナチュラルに楽しむ小さな花束の庭
森の佇まいと選りすぐりの花々 お宅のリビング側から庭を見下ろす。春の球根花からダリアへと季節ごとに植え替える植栽のエリア。 フジの花が満開で、スイセンやチューリップの盛りが過ぎた晩春の週末。パリ近郊で素敵な庭づくりをしている英理子さんのお宅にお邪魔しました。 折り紙&ペーパーフラワー作家としても活躍する英理子さんが、フランス人のご主人と2人のお子さんと暮らす家は、パリから電車で30分ほどの長閑(のどか)な住宅地にあります。これまでも、季節を変えて何度も伺っている大好きな庭です。 ヘビイチゴやステラリア・パルストリスが混じるグラウンドカバーは、野原そのままのナチュラルな雰囲気を庭に運びます。 この地に引っ越してきて、自分で庭づくりを始めてから15年ほどが経つという英理子さん。この庭は、森の一角を思わせるナチュラルな佇まいのを背景に、季節ごとに彩りを変える彼女のこだわりの花々が、絶妙なハーモニーを織りなしているのが魅力です。 今回訪れた際にも、ちょうどイングリッシュ・ローズの名花‘ガードルード・ジーキル’の初花が咲いていました! 初めて伺ったのは、ちょうどバラの季節。フランスの個人庭には珍しく、イングリッシュ・ローズの数々が見事に咲いているのが印象的でした。 ジャルダン・ブクティエ(花束の庭) 春の花の植栽、選び抜かれたチューリップはそれぞれがビジュー(宝石)のよう。 さて今回は、曇りからにわか雨を経て時々晴れ、気温はひと桁台という花冷えの4月下旬の日曜日。球根花は終わりかけで、バラの盛りは3週間後くらいか、でもスズランはもう花盛りですよ、というタイミングでしたが、たくさん植え込まれたさまざまな種類のスイセンやチューリップは、好き好きに開き切った、その姿にも味わいを感じます。 スズランの群生の前に佇む後ろ姿は庭ネコのたまちゃん。 「そう、庭で見る分にはまだいいのだけれども、ブーケにするには咲き始めがいいの」と言う英理子さん。大好きだというスイセンは、いろいろな園芸種を毎年400球ほどは植え込むそうです。今年は雨が多かったせいか、庭づくりを続けてきて初めてというほどの激しいナメクジ被害があったそうで、花の部分をつぼみのうちに食べられたスイセンが多数出てしまったと、残念そうでした。ちなみにナメクジは捕獲処分。薬剤などは使わないナチュラルガーデニングが基本です。 チューリップは、庭の風景を保ちつつ、少々切り花にしてブーケにも使えるように、同じ種類を20、30球と植え込んでおくとのこと。そう、この庭の植物選びの原則の1つに、切り花として使える花々というのがあり、実際、いつも季節の花でささっと素敵なブーケを作ってくださるのです。庭の自然をそのまま運ぶようなブーケは、もちろんパリの友人の間でも評判です。 晴れ間の出てきた庭で恵理子さんにお茶をご馳走になりながらお話を伺いました。気持ちのよいひととき。 庭の奥でちょうど花盛りだったビバーナムは、やはり15年ほど経つ大株だそうですが、これもブーケにも使おうと思ってチョイスしたとのこと。切り花のための庭をカッティング・フラワー・ガーデンと呼んだりしますが、フランス語ではジャルダン・ブクティエ(花束の庭)やジャルダン・フローリスト(フローリストの庭)といいます。 森の佇まいを運ぶ野の花々 木々の足元を彩る黄色のドロニクムも森からやってきたワイルドフラワーです。 選りすぐりの栽培種のチューリップやスイセンが植え込まれたエリアは、カラフルな宝石箱のよう。それを引き立てるのが、フワフワとそこかしこに生えているヒナギクだったり、儚げなワスレナグサの群生。森の一角にいるように、よく林縁に生えている黄色のドロニクムも木陰に揺れています。野の花と園芸種の共演は、まさに庭空間ならではの技ではないでしょうか。 この時期、スズランも庭のあちこちで満開になってきていて、摘むのが追いつかないほどだとか。スズランは、もともと群生していた場所もあれば、義理のお母様からいただいたひと鉢が一面に広がった斜面もあり、いずれにしてもこの土地に合うようです。フランスでは5月1日にスズランを贈る習慣がありますが、ここでは毎年少し早く最盛期を迎えます。 スズランの群生に混じって、可愛らしい八重のオダマキがつぼみをつけていたり、庭の中には、ほっこりする風景がたくさんあって飽きません。種まきで増やしたもの、あるいは種が飛んで自然に増えたものなど、それぞれの様子をよく観察しつつ、そのままそっとしておいたり、場所を移動させたりと、丁寧にお手入れされているのがよく分かります。 小さな庭のいいところ 毎年春には数々のスイセンとチューリップが彩るエリアは、季節が終わるとダリアに植え替え、夏から秋にかけては、選りすぐりのダリアが花盛りになります。ダリアの球根は季節が終わると掘り上げられて、また春の準備に。季節に沿って花が溢れる小さな庭は、じつは大変な手間に支えられています。 スペースが限られているので好きな植物がすべて植えられるわけではない、慎重に取捨選択しなければならないのだけれども、逆に自分にとってはそれがよいのだと思う、と言う英理子さん。植栽の選定は自分の「好き」が基準ではあるけれども、土地に合うのか、気候に合うのかということも大事です。特に、ここではまだ急激な変化は起きていないけれども、夏の暑さや水不足などの気候変動に対応するには、環境に適応できるということがより大事になりそう、と庭友さんたちの間でも話題になっているとか。 庭のスズランを摘んでブーケに。素晴らしくいい香りです。 それぞれの植物の気に入った場所を見極めて定植したり、移動したりと、植物それぞれとの対話の中で作られてきた庭空間では、草花が皆ハッピーなのか、居るだけで気持ちが和んできて、いつまでも佇んでいたくなります。抜け感のあるお洒落はパリジェンヌが得意とするところですが、この庭の、リラックスする柔らかなワイルド感は、それに通じるところがあるような気がします。 庭の中心のガーデンテーブル。お茶の時間には自然と家族が集まって過ごす和やかな場所に。 森を思わせる野の花々と、こだわりの園芸植物たちが、恵理子さんの振るタクトを見ながらそれぞれに歌い、そのリズムが柔らかなイル=ド=フランスの光と空気に溶け込んでいくような素敵なナチュラル・ガーデンです。
-
フランス

【パリの庭】パリ市の四大植物園「パルク・フローラル」に咲くダリア
パリ市の植物園「パルク・フローラル」 ご紹介する「パルク・フローラル(花公園)」は、パリ市の四大植物園(*)の一つで、文字どおりにさまざまな植物コレクションを保有しています。1969年に同地で行われた国際園芸博覧会を契機につくられたもので、広さは30ヘクタールほど。全体的には、森林公園のような松やオークの林を抜ける散歩道の所々に、ダリア園や芍薬園などがあり、華やかな花のコレクションを見ることができます。アイリスやシダ、アスチルべなどのオーナメンタルな植物に加え、パリ盆地の自生植物や薬用植物などのコーナー、錦鯉が泳ぐ広い園池など、変化に富んだ見所もあり、どの季節も、大人も子どもも楽しめるような工夫がされています。 *四大植物園=パリ市の植物園としては、ほかに同じヴァンセンヌの森にあるエコール・デュ・ブルイユの樹木園、バラ園で有名なバガテル公園、セール・ドートゥイユがあります。 秋の森に群生するシクラメン。 色彩溢れる華やかなダリアにうっとり ダリア園の入り口、緑の中のはっとする華やかさ。 さて、今日のお目当ては、なんといってもダリア園。ダリアは7、8月から10月下旬の初霜の降りる頃までと花期が長く、少し寂しくなってくる秋の庭に華やかな色彩を添えてくれる人気者です。近年は花屋さんでも、オシャレな色合い、花姿の異なるさまざまなダリアを見かけるなぁと思っていましたが、最盛期のダリア園は、入り口に立っただけで、その華やかさに圧倒されます。 カラフルな色合いに加え、草丈は20cmほどの矮小種から2mを超すものまで。また小さな花や大きな花、一重や八重咲き、ポンポン咲き、カクタス咲き……などなど。あらゆる種類のダリアが咲き乱れる様子は、これぞ眼福です。 国際ダリア・コンクール パリのパルク・フローラルでは、野生種・園芸種を合わせて400種を超えるダリアを栽培しており、毎年8月末〜9月初めには、国際ダリア・コンクールが行われています。これには、フランス国内から60ほどの生産家がエントリー、ドイツやオランダ、リトアニア、日本など外国の生産家も参加し、一般投票と専門家の審査を経て、新栽培種の受賞品種が選ばれます。 左/Dahlia 'Hellios' (写真内手前)右/Dahlia Gryson's Yellow Spider 一般審査の参加者は、3つの好きなダリアに投票することができます。専門家の審査では、花ばかりでなく茎や葉も合わせた全体の花姿や色彩、さらに耐病性などのテクニカルな部分も対象になります。大賞、ジャーナリスト特別賞、一般審査賞、子ども審査員賞などに選ばれたダリアの一部をご紹介すると、ニュアンスカラーのバラ色のDahlia 'Dutch Delight'、黄色〜オレンジからカフェオレ色に変化するDahlia 'Hellios'、菊のような繊細なカクタス咲きで爽やかなイエローのDahlia Gryson's Yellow Spiderなど。 左/Dahlia Comet 右/Dahlia Staburadze またDahlia Cometはパステルトーンのオレンジのポンポン咲き。より柔らかでエレガントなDahlia Staburadze、シックな深いレッドのDahlia 'King Arthur'など、受賞作品は、色も形もじつにさまざま。この多様性こそがダリアの尽きない魅力と、改めて実感します。 ダリアの魅力〜多様性 もともとはメキシコやコロンビアの暖かい高地に自生するダリアは、18世紀にヨーロッパに持ち込まれ、フランスに導入されたのはフランス革命が勃発した1789年。当初は根を食用にする野菜として扱われたものの、あまり美味しくはなかったようで、ジャガイモを超える人気の食用植物にはなりませんでした。しかし、花の華やかさや、初霜まで続く花期の長さが重宝されて、庭のオーナメンタルな植物として人気となりました。植物愛好家であったナポレオン皇妃ジョゼフィーヌもマルメゾンの庭園にダリアを取り入れ、ダリアは19世紀のフランスで人気を博しました。 再び人気上昇中のダリア かつては希少な品種が高額取り引きされるなど、歴史的にも花形だったダリアですが、一時期のフランスでは、田舎の祖父母のポタジェの花のような、ちょっと時代遅れのイメージになっていました。しかし近年は現代の感性に応える色や形のバリエーションに加え、茎の強度が増し、庭での植え込みやブーケの素材として使いやすく進化してきました。また、花がら摘みが不要なように、花後には再びつぼみのような姿になるローメンテナンスなダリアも現れるなど、生産家による品種改良の努力が続けられてきた結果もあってか、ここ数年来ダリアの人気は再び上昇しています。 野生種のコーナーの一角、ポンポン咲きのダリア。 パルク・フローラルのダリア・コレクションでは、年々増える多彩な園芸品種のダリアのかたわらに、全部で40種類前後存在する野生品種のダリアの1/3ほどが栽培されています。すでに草丈は低いものから人の背丈くらいのものまで、花形も一重も八重も多種の形態がありますが、比較的クラシックなそれらのダリアに比べて、栽培種ではさらに、複雑なカラーコンビネーションで、銅葉やダークな色合いの茎までコーディネートされて、まるでオートクチュールのデザインのような完成度の高さ。 ミルキーなオレンジやカフェ・オレ・カラー、シックなレッドなど、オシャレなカラーリングにも目移りが止まりません。ダリア園を一巡りしてみると、帰りにはすっかりダリアマニアになってしまいそうです。 庭デザインにもアレンジにも大活躍 花の姿だけでなく、葉や茎も含め、さらに群生した際の姿のよさ、管理のしやすさなど、改良を重ねた園芸種のダリアの多様性は、華のある風景づくりの強い味方です。家に飾るブーケにもできる、双方向に活躍するダリアは、自宅の庭の花としても魅力的。ちなみに、ダリアの切り花は長時間の輸送には向いていないのですが、逆に地消地産といったローカルな花のサーキュラーエコノミーにうってつけであることは、サステナブル志向になってきた花屋でダリア人気が再燃している理由の一つでもあります。 さて、パルク・フローラルのダリアは、季節が終わると掘り上げられて、来春の植え付けまで大切に保管されます。また来年にはどんな新しいダリアに出会えるのか、今から楽しみになっています。
-
フランス

【フランスの庭】ル・プリウレ・ドルサン修道院の庭〜魅惑のモナステリー・ガーデン〜
中世の修道院の庭 ヨーロッパで景観への見晴らしがよい開かれた大規模な整形式庭園が発達するのは、ルネサンス期以降。中世の修道院に設けられた庭には、閉じられた空間の中に、修道士たちが自らを養う野菜や果樹のポタジェ(菜園)やベルジェ(果樹園)、また病人を癒やすためのハーブガーデン(薬草園)などがつくられていました。祈りとともに、自らの手を使って働くことは大切な修行の一環であり、庭仕事は修道士の日常の仕事の一部。自給自足という機能面と、修道院という場に相応しい、静けさと調和に満ちた美しく整った空間が、中世の修道院の庭だったといいます。 現代の感性で再現されたモナステリー・ガーデン 庭に続く、修道院の建物のエントランスのしつらいも、ウェルカム感いっぱいで期待が膨らみます。 残念ながら、現代までそのまま残る中世の修道院の庭はありません。今から30年ほど前の作庭にあたっては、装飾写本などに描かれた当時の庭の様子や文献調査から、かつての修道院の庭で行われていたように、植栽には伝統的な有用植物や象徴的な植物を選び、整形式のプランでポタジェ(菜園)、ベルジェ(果樹園)、クロワートル(回廊)がつくられ、現代のモナステリー・ガーデンが誕生しました。 ポタジェ(菜園)とサンプル(薬草園) 見学コースの始まりは、建物に一番近いポタジェから。正方形の木枠で縁取られたポタジェでは、昔からの伝統野菜が花々とともに植栽され、元気に育っています。きっちり端正に整備された構造物とのコントラストで、生き生きと茂る植物のオーガニックな動きの勢いがますます感じられます。また「プレシ Plessis」と呼ばれる小枝などを組んで作られた柵やトレリスが素敵な、魅惑のポタジェ風景が広がります。 こんなに可愛いポタジェには、なかなかお目にかかれません。ポタジェの奥は「サンプル」と呼ばれる薬用ハーブの植栽コーナーです。病人を癒やすのは中世の修道院の重要な責務であり、このハーブガーデンには、かつて王令で薬草として栽培を推奨されたハーブの数々、カモミールやメリッサ、セージ、ミント、イチョウヨモギ、アンジェリカやバーベナなども植栽されています。 プロムナード(散歩道)からベルジェ(果樹園)へ リンゴや洋ナシが規則正しく植えられたベルジェの様子。 何度でも見て回りたくなるポタジェを抜けて、芝地に並木が植栽されたプロムナードへ。緑だけのスッキリと整ったシンプルに美しいこの空間に入ると、不思議とスッと心落ち着く感じがしました。 続いて、芝地にリンゴや洋ナシといった果樹が植えられたベルジェも、穏やかな空気が流れる場所。果樹の周りを囲むように設けられたプレシ(小枝の柵)のベンチや王様の椅子を思わせるシーティングが、シンプルな空間にアクセントを添えています。 通路には、異なる空間の重なりの奥に、常にフォーカルポイントが作られていて、深い奥行きを感じさせます。 それぞれの庭のコーナーは生け垣やプレシでしっかり囲まれつつも、他の空間への見通しのポイントがそこかしこに設けられていて、こちらへ、彼方へと誘われるように、歩を進めることになります。 ラビリンス(メイズ 迷宮) さまざまな植物に彩られたラビリンス。 さらに進んでいくと、さまざまなエスパリエ仕立ての果樹や小枝の柵で構成された、ラビリンスに入り込みます。カゴ形の構造物の中に植えられたルバーブや、白を基調にした花々が揺れる仕切りの奥に、ベンチで囲まれた大きな果樹が見えるのですが、目に映るままに進んでも、意外と行きつけない、まさに迷宮になっています。 幾何学的なボリュームで構成された空間ですが、よく見ると足元の素材は木材を利用。長もちはしないかもしれませんが、温かな雰囲気です。 この迷宮は、キリスト教での“行き着くことが難しい「救済」への道”を示すものでもあるのだとか。迷路を構成する生け垣の片隅には、日陰になった休息スペースもあって、花や果樹を愛でつつ、迷うことを楽しみながら、ゴールに向かう構成です。 さまざまな小さな庭 ラビリンスの中心には、円形の洋ナシのパーゴラを被った丸いベンチが。 ラビリンスの中心には、その形を反映するように円形に刈り込まれた洋ナシと、風に揺れる花々の植栽が。イチゴやフランボワーズ、スグリなどの赤い実の小道や、残念ながらバラの季節は過ぎてしまっていたのですが、バラ園であるマリアの庭など、さまざまな小さな庭の空間が続きます。 いずれもが共通して、整形式のプランと構造に木材や小枝などの自然の素材が使われており、それでいてテーマによってそれぞれ全く異なる雰囲気を持った空間となっています。エリアが変わるたびに、ハッとするような発見の感覚があって、楽しさが尽きません。 クロワートル(回廊) クロワートルの庭の中心には、生命の象徴である水が流れています。 さまざまな小さな庭の連続の中、大きな空間を占めるのがクロワートルと呼ばれる、全体のほぼ中心に当たる庭です。修道院建築の中に必ず含まれる中庭を囲むクロワートルは、祈りと瞑想の場であり、天国を予示する象徴的な場でもあったそうです。ここでは石造りの修道院の建築の代わりに、クマシデの生け垣がクロワートルを形づくっています。その中心には静かに水が流れる噴水があり、四方は小さな葡萄畑になっています。 じつは、現在修復されている修道院の建物も、最盛期の1/10ほどだそうで、かつては石造りの建物として存在したクロワートルが、静かな散策の緑のプロムナードとなって庭に再現されているのは、デザインとしても面白いところ。 緑の生け垣の壁にくりぬかれた円形窓からの風景。どのディテールも魅力的。 作庭から30年ほどが経つという、ル・プリウレ・ドルサンの庭。現在は4人のガーデナーが維持管理を担っている3haほどの庭園は、非常によく手入れされており、本当に気持ちよく寛いで散策できます。中世の修道院の庭のさまざまな特徴を、現代の美意識でデザインに生かしたこの庭には、人の手仕事と植物たちの美しい調和が溢れていて、まさに天国のような心休まる空気が流れていました。 庭園にはショップとカフェも。昼時にはテラスか室内で、ホームメイドの塩味系のキッシュやタルトとフレッシュな庭のレタスのサラダ、ドリンクとデザートの軽いランチセットがいただけます。
-
フランス

【フランスの庭】ヴェルサイユ庭園の最新スポット「調香師の庭」
花の宮殿、グラントリアノン グラントリアノン。Andy Sutherland/Shutterstock.com ヴェルサイユ宮殿には、グラントリアノン、プチトリアノンの2つの離宮と庭園があります。ルイ14世は「ヴェルサイユ宮殿を宮廷のために、マルリー宮殿を友人たちのために、グラントリアノンを自分のために作った」といわれます。王は堅苦しい宮廷儀礼を離れたプライベートな時間を過ごすために、1668年、陶器のトリアノンと呼ばれた美しい宮殿を建てさせました。しかし、外壁を覆うデルフト陶器の脆弱さゆえに陶器のトリアノンは20年と持たず、早々に大理石のトリアノンと呼ばれる、現在まで残るイタリア風の建物に建て替えられることになります。 プチトリアノン。Ivan Soto Cobos/Shutterstock.com さて、王が親密な時間を過ごしたトリアノンの庭は、どんな様子だったのでしょうか。 当時、トリアノンの庭園の花の植栽は、その時々の王の希望に合わせて素早く変えられるよう、また、すべての花を最高の状態で見せられるよう、植木鉢に植えて花々を組み替える方法で行われていました。別名「花の宮殿」とも呼ばれたトリアノンの庭園には、香りのよい花々が大量に咲き乱れ、その強い芳香に気絶する招待客も出るほどだったとか。 ヴェルサイユと香水文化 盛夏の「調香師の庭」は、香りにまつわる植物たちが旺盛に育つ、ナチュラルかつのどかな雰囲気。 衛生面ではまだ発展途上であったともいえる17世紀、ルイ14世の時代の宮廷では、不都合なにおいを隠す目的もあって、ムスクなどの動物性の強い芳香が好んで使われていたそうです。庭園や宮殿を飾る花々も、ヒヤシンスや月下香など、芳香の強いものが好まれました。そうした背景から、17世紀から18世紀にかけて、イタリアから伝わった香水が大流行したフランスの宮廷は、数々の名調香師を生んだ、香水産業の揺り籠となったのでした。また、当時は香水を使うことができるのは王侯貴族などに限られていたゆえに、香水の香りは、豊かさと高貴さの象徴でもあったのです。 香りの花々が育つ「調香師の庭」 ダマスクローズ越しの「調香師の庭」の風景。 そうしたヴェルサイユの宮廷と宮殿、香水文化の歴史からインスパイアされて生まれたのが、新たにつくられた「調香師の庭」です。かつて「Sillage de Reine」でマリー・アントワネットの香水を復元するなどヴェルサイユと縁の深い香水のメゾン、フランシス・クルジャンがスポンサーとなってつくられた、香水の歴史に捧げられた庭園です。 シャトーヌフのオランジュリー。かつてルイ15世が、ここでコーヒーやパイナップルを栽培させたのだそう。 植物学に興味を寄せていたルイ15世がかつて造らせた、シャトーヌフのオランジュリー。「調香師の庭」は、その建物近くにある9,000㎡ほどの敷地につくられました。トリアノンの庭師たちと協力し300種以上の香水の素材となる精油に使われるさまざまな植物が集められた庭は、雰囲気の異なる3つのゾーンで構成されています。通常は非公開の場所ですが、ガイド付きであれば見学することができます。では、3つのゾーンをそれぞれ見ていきましょう。 <好奇心の庭> ルイ15世がパイナップルやコーヒーを栽培させたというシャトーヌフのオランジュリーにまっすぐ向かう通路を中心軸に、左右対称の整形式に整備されています。数百種の芳香に関連する植物が植栽された「調香師の庭」は、いわば香りのポタジェ。実際、少し前までこの敷地にはヴェルサイユの宮殿内にレストランを持つアラン・デュカスのポタジェがあったのだそう。 多数のバラの中で、わずかに咲き残りの花が見られたダマスクローズ。香水の原料の主となる香りのバラです。 この庭には、当時の植物系の香水の素材として花形的存在だったアイリスやバラ、昔から使われ続けているさまざまな香りのハーブ類、香水製造にまつわる文脈で「ミュエット(無言)」の花と呼ばれる月下香やスミレなどが植えられています。 チョコレートコスモスは、深いチョコレート色がおしゃれなばかりでなく、香りもチョコレート! また、花そのものが素晴らしい芳香を持つものだけでなく、直接的には香水の材料となる香りが抽出できず、人工的に再構成するしかない種類の花、チョコレートやパイナップルといった珍しい香りの草花など、幅広く香りに関する花々が集められています。 葉からパイナップルの香りがするハーブ、パイナップルセージ。 セージをはじめ、香りのハーブの植栽エリアも充実。 庭園全体は、17世紀のトリアノンの庭の香りのエスプリをイメージしながら、一年を通して何らかの花が咲くようにといった配慮がされています。また、ボルドーとチョコレート色、イエローからオレンジへのグラデーションというように、色彩をポイントに構成された植栽からは、オーナメンタルな庭としての心配りが大事にされているのが分かります。 晩夏もまだ花盛りのラベンダーは、青紫色の植栽コーナーの主役。 私が訪れた8月中旬は、庭の季節としては花から結実へと向かう、暑さで疲れも出ていそうな時期でした。庭の花形であるバラは、さすがに少々の花が残る程度でしたが、そこかしこで勢いよく育った草花のダイナミックな姿がワイルドで、フランスの田舎の夏休みを思わせるような、ナチュラルで心休まる風景になっていました。 かなりワイルドな、でもなぜかほっとする風景。 オランジュリーの前と通路の両脇は、レモンやビターオレンジ(橙)などの柑橘類の植木鉢で飾られています。ビターオレンジも、実は精油のネロリやプチグランの原料となり、香水の材料として活躍する柑橘です。ちなみに、さまざまな動物系の強い芳香を嗅ぎすぎたためか、芳香アレルギーになってしまった晩年のルイ14世が、唯一受け付けることができたのは柑橘系の香りだったのだそうです。 オランジュリーからの中央通路に並ぶ柑橘類を中心にしたコンテナーと植木鉢の列。 <木々の下の庭> 緑がワサワサ茂るワイルドな果樹園。 <好奇心の庭>の隣の果樹園エリアとの間には細長い桜並木があり、春には庭園の一番の見どころになりますが、8月の果樹園で目を引くのは、モモやリンゴ、洋ナシがたわわに実る果樹のほうです。かなりワイルドな感じの果樹園を抜けると、奥にはさらに、壁に囲まれた小さな<秘密の庭>が待っています。 奥に進むと、さらに壁に囲まれた扉を発見。 小さな<秘密の庭> 敷石のステップが緩やかな曲線を描き、庭の奥へと気持ちを誘う<秘密の庭>。中に立ち入って植栽などを観察することはできなかったのですが、ひっそりと静かに瞑想するのによさそうな静かな空間は、現在のところ庭師の実験ガーデンとなっているのだそう。 <秘密の庭>を覗いたところ。 見学の最後には、ワークショップスペースでアイリスの根やバラの花、パチュリの葉や茎、バニラの実など、精油の抽出には植物のさまざまな部分が使われることを学び、香りを実際に体験することができます。精油となった芳香をそれぞれの言葉で表現し、また実際の植物の香りやイメージと、精油になった香りとのギャップを発見するのは、大人にとっても子どもにとっても面白い体験。視覚と嗅覚とイマジネーションをフル活用することで、庭と植物の楽しみ方がさらに広がります。 屋根付きのワークショップコーナーでは、ガラス瓶の蓋の裏に用意された調香の基本となる香りを体験。実際に香りを嗅いで言葉にする体験は、新鮮な発見になります。 ドライのバラの花やアイリスの根などに混じって、真ん中の瓶はドライになったパチュリの茎と葉っぱ。 香水の歴史を庭のインスピレーションとして新たな空間を作った「調香師の庭」は、ヴェルサイユ庭園ならではの興味深い試みです。
-
フランス

パリのサステナブル・ガーデンショー「ジャルダン・ジャルダン2023」
パリのガーデニングの最新情報を知るイベント 日本と同様、6月はバラ、シャクヤク、アジサイと、次々に花が咲きあふれる季節。フランスでもガーデンイベントが集中する時期です。 2023年はコロナ明け2年ぶり開催だったパリのアーバン・ガーデンショー、ジャルダン・ジャルダン。18回目を迎える今年は例年のリズムを取り戻し、6月最初の週末(2023年6月1~4日)にチュイルリー公園の一角で開催されました。 テーマは「豊穣でレスポンシブルなリソース・ガーデン」 今年のテーマは「環境に負荷をかけない」「人にも他の生き物にも寛容な、資源としての庭」また、「人が原点回帰して元気を取り戻せるような庭」といったイメージで、エコロジーやサステナビリティを強く意識したガーデニングという今日的なメッセージがダイレクトに伝わってくるものでした。 庭のオーナメンタルなアクセントにもなる個性的なデザインのトレリス。 これまでも、都市緑化・アーバンガーデニングに的を絞った構成が、小規模なガーデニングショーならではのピリリと気の利いた存在感を放ってきましたが、今年はさらに自然環境・生物多様性保護に貢献する、現在と未来へ向けてのアーバン・ガーデンのあり方を模索する示唆に富んだ内容になってきました。 フレンチ・ガーデンの伝統を表現する幾何学的なトピアリーをアクセントにした端正な庭も健在。 大(50~200㎡)小(15㎡)合わせて三十数個のショーガーデンと、80ほどのガーデニング関連の出展者たちのプレゼンテーションに共通している、サステナビリティやエコロジーへの配慮は、もはやパリのアーバン・ガーデニングのマストになったといえるでしょう。 人と自然に優しいガーデンのかたち 「責任感があり、自然にも人にも優しい豊穣な庭」というキーワードをもとに展開された庭は、都市のヒートアイランド現象の蓄熱を抑える緑の働きや、土壌の大切さ、水の大切さを振り返るようなコンセプトのものが多く、積極的にリサイクルやリユースを利用したデザインや、温暖化に対応した水を大量に必要としない丈夫な植物にスポットを当てたドライガーデンなどが見られました。また、ワイルドフラワーと、オーナメンタルかつ食用にもなるハーブなどのエディブルな要素を分け隔てなくランダムに植栽に取り入れつつ、懐かしい田舎の庭を思わせるようなガーデンなど、全体的にはナチュラルな雰囲気ながら、さまざまなスタイルの庭が提案されています。 フェ・ドモワゼル(ドモワゼルの妖精)の庭(Demoiselle VRANKENがスポンサー)。 そのなかで、メインガーデンのデザイン大賞に輝いたのは、庭づくりの匠、フランク・セラによる作品でした。フランスの田舎の祖父母の家の庭をイメージした、レトロで新しいナチュラル・ガーデンです。エディブルな植物とワイルドフラワーが交じりあって彩る、丸太で構成された小道を通って庭に入り、中央の池の上を渡っていくと、涼しい日陰の小さな小屋や、ひっそりメディテーションしたくなるようなシーティングスペースが待っています。 ナチュラルな田舎の風景を思わせる、ワイルドフラワーが彩る丸太の小道を通って、池を渡り、小さな小屋へ。 ポタジェの野菜やハーブを収穫して皆で賑やかに食事したり、植物に囲まれてゆったりとくつろいで英気を養う…人の暮らしと自然が温かに共存するこの庭で、池の水は生命の象徴として取り入れられていました。 スモール・アーバンガーデン大賞が新設 涼やかなシェードの下に、食事が楽しめるテーブルコーナー、ゆったりくつろぐためのコクーンのようなシーティングと、アイデアが盛りだくさんの小さなガーデン。 また、新たに創設されて注目を集めたのが「スモール・アーバンガーデン大賞」です。15㎡という狭小な敷地は、一般的なパリのバルコニーやテラスなどにもすぐ応用できるリアリティのある面積。「小さな空間に大いなるアイデア」という選考基準をもとに、書類審査された9つのガーデンが、実際に会場に設置されました。木材などの自然素材、リサイクルやリユースの素材を上手に使って、狭い中にもそれぞれの個性が生きる素敵なスモール・ガーデンが並びます。 「スモール・アーバンガーデン大賞」に選ばれた「出現 Apparaître」。 大賞に選ばれたのは「出現 Apparaître」というタイトルがついたガーデン。リサイクルのガラス素材などがうまく組み合わされて、透明感と反射の加減で空間を広く軽やかに見せる工夫がなされています。 「スモール・アーバンガーデン大賞」に選ばれた「出現 Apparaître」。木材とガラス材を多用した空間の構成が面白い作品。植栽はシンプルに、ワイルドなグリーンで。 今年のシャネルはオレンジ・ガーデン さて、見逃してはならないのが、毎年楽しみにされているシャネルのガーデンです。ハイブランドの世界観を表現するガーデンは、いつも上品かつスタイリッシュ。今年はシャネルのパルファンの5つの基本の香りの中から、ビターオレンジ(橙、Citrus aurantium)をメイン・テーマにしたガーデンです。 ビターオレンジの若苗が、南仏のオレンジ畑の風景を彷彿とさせます。 イル=ド=フランスをはじめ、フランスのほとんどの地方では露地栽培が不可能なオレンジの木ですが、シャネルのパルファンのために、温暖な南仏の契約農家で、環境に配慮した無農薬栽培で大切に育てられた花が採取されているそうです。 ブース内ではビターオレンジから作られる香料ネロリとプチグランを嗅ぎ比べたり、香料や香水の製造過程について学べます。 かつては盛大だった南仏のビターオレンジの栽培も、化学的な香料の発展で現在は大幅に減少してしまっています。シャネルでは契約農家とともに、700本のビターオレンジを新たに植樹して無農薬栽培のオレンジ畑をつくっています。畑の造成は、南仏で昔から使われている石壁制作の技術を専門学校の生徒たちに伝授する機会にするなど、伝統技術の継承の場にもなっています。 子どもたちのためのワークショップの特設スペースもとってもおしゃれで、参加できる子どもが羨ましい。 ガーデニンググッズもカッコよくサステナブルに 大手ガーデンセンターによるガーデニング超初心者さん向け定植体験ブース。バジルやラベンダーなど、たくさんの植物の中から好きな苗を選んで植木鉢に定植。家に持ち帰れます。 ガーデニンググッズにも、やはりリサイクル、リユースといったサステナビリティを大切にしたデザインが見られ、会場のさまざまな製品のプロトタイプのトレンドになっていました。最新のリサイクル技術などを取り入れ、かつ自然な素材や伝統的な技術にも目を配った、エコロジカル・ガーデニングに欠かせないお洒落なプロダクトを発見するのも、会場での楽しみの一つ。 こちらは軽さがポイントのテキスタイル製のアウトドア用コンテナーシリーズのプロトタイプ。10年以上の耐久性があり、かつ何度かのリサイクルが可能な素材が使われています。 最近はすっかり一般化してきた素焼きのオヤ(Ollya)。水やり回数を抑えることができる優れもの。 パリのハチミツ業者のブース。時期により蜜源は変わるが、写真は世界的なハチミツコンクールで入賞したものだそうで、さすがに一際味が濃くて美味しい。 また、庭といえば、養蜂を趣味にする人も多いフランス。パリのハチミツ業者も出店。農薬などの使用がほとんどないパリのほうが、農業地帯よりもよいハチミツが採れる、のだそうです。時期によって蜜源が異なるので、味も軽いものから複雑で深いものまであり、中には世界ランキングでも評価の高い美味なパリ産ハチミツも。 憧れのクラシカルな温室 そして、ヨーロッパらしさが溢れているのが、おしゃれな温室です。大小さまざまなサイズ展開で、展示されている色に限らず、カスタムメイドもできます。庭に温室があれば、寒さに弱い植物の冬囲いや播種にも便利ですし、または、お茶を飲むスペースなど、部屋が一つ増えたようにも使えます。お値段は張りますが、いつかは欲しい、憧れの温室です。 無農薬有機栽培の野菜・ハーブ苗 無農薬栽培で育てられた伝統野菜や希少品種の野菜苗たち。 さて、サステナビリティへのこだわりは、苗販売にも行き届いていて、無農薬・有機栽培で育てられたじつに多彩な野菜の種子と、この季節すぐ植えられる苗も揃っています。話を聞くと特に伝統野菜に力を入れているそうで、例えば、フランスの家庭のポタジェ(菜園)で栽培するのに一番人気のトマトなどは、それだけでも何十種類もあります。 自家栽培の固有種、伝統種の野菜や花の種がよりどりみどり。 食文化が豊かなフランスでは、野菜や果物の品種にもこだわって栽培する人が多い様子。私も一般的なガーデンセンターではほぼ見つからないカクテル・キュウリの苗を発見、お買い上げできて大満足でした(翌日さっそくポタジェに定植、収穫できる夏になるのが楽しみです!)。 すべてはご紹介できなかったのですが、会場では、こだわりのガーデナーもガーデニング初心者も、誰もが満足できる展示・物販がどこかに用意されています。しかもフランスの6月は、野外にいるだけで気持ちのよい季節でもあり、大変満足度の高いイベントになっています。 セイヨウボダイジュの並木はカフェサロンに早変わりして、くつろぐ来訪者たち。 さらに、会場のチュイルリー公園は、花が咲き始めたセイヨウボダイジュの並木道が美しい、彫刻作品なども充実した有数の歴史的庭園。ちょうどバラの季節でもあり、会場を出てからも、美しい庭の世界の延長をうっとり楽しむことができるのも、いいところ。今後も注目していきたいイベントです。 チュイルリー公園、花が咲き始めたセイヨウボダイジュの並木や、バラが植栽されたクラシカルな美しい庭園空間が広がります。
-
フランス

【フランスの庭】ル・ヴァストリヴァル、プリンセスの庭
プリンセスの庭の始まり 庭づくりの始点となった、コテージガーデンの雰囲気がある建物周辺と、針葉樹にクレマチスが這うフォレスト・ガーデンへの入り口(写真右)。 前回ご紹介したヴァロンジュヴィル=シュル=メールの近隣に位置するこの庭は、第2次世界大戦後の1950年代に家族と共にフランスに移り住んだモルダヴィア(現モルドバ民主共和国)のプリンセス、グレタ・ストュルザ(Greta Sturdza 1915-2009)によってつくられました。かつて作曲家のアルベール・ラッセルの住居だったという、荒れ放題になっていた小さな家と12ヘクタールの土地を気に入って購入した彼女は、ここを「四季を通じていつでも美しい庭にする」と決意します。 ガーデニング成功のカギ フォレストガーデンは、さまざまな樹木や草花の協奏曲のよう。よく見ると、植栽の足元はみな枯れ葉でマルチングされています。 家の周辺からマツやカシなどが生える林の方に向かって、ぼうぼうの草地を整備するために、プリンセス自ら生い茂ったシダを抜きとるところから始まった庭づくり。まったくの独学ながら、それまでに住んだモルダヴィアとノルウェーでの経験から体得していたことが、彼女の庭づくりの大きな指針となりました。それは、若木の定植を丁寧に行うことと、マルチングを欠かさないこと、この2つです。枯れ葉やコンポストなど、現場にある自然の材料で行うマルチングは、土壌を保護しながら豊かにし、乾燥を抑え、冬には防寒にもなる優れものです。 さりげなく庭の片隅に積み上げた枯れ葉などは、そのままコンポストになる。 美しき調和、庭風景の秘密 高木からグラウンドカバーまで、それぞれの層がしっかり確保され、重なるように景観が作られている。 そして、絵画のような圧倒的な美空間を構成する秘密は、プリンセス・ストュルザが自ら開発したという、高木からグラウンドカバーまでの植物層を明確に分けつつ重ねる構成と、透かし型の剪定です。 雨が多く湿度が比較的高い、また海沿いの強風が吹き付ける土地柄から、庭園での倒木の危険を避け、樹冠に風と光を通すための樹木の剪定は必要不可欠でした。 剪定で形作られたシャクナゲの大木の幹は、独特な美しい造形を見せている。 樹冠部分を十分に透かし、枝の重なりを段々状に整えるような剪定によって樹形が作られます。そのことで、庭の構成に美的なタッチが加わり、さらに生まれるグラウンドカバーから灌木類、中木、高木へときれいな層の重なりのグラデーションが、この庭ならでは。どこから見ても美しい光景を描き出しています。また、しっかり剪定された樹木がある層の下に密に植栽されたグラウンドカバーの植物は、マルチングと併せて、雑草の繁殖を防ぐという意味からも有用です。 和庭園で行われている透かし剪定ともまた違った、オリジナルな剪定により形作られた樹木が庭のデザインのポイントになっている。 四季の美をつかさどる植栽コレクション 森に自生する丈夫な花、ドロニクを群生させた一角は、春らしいナチュラルな華やかさ。 植栽の選定もこの庭らしい魅力が現れているポイントです。プリンセス・ストュルザの植物選びは、徹底した自らの審美眼と、自然に寄り添うものでした。庭好きの例に漏れず、彼女の植物へ向けられた情熱には並々ならぬものがありました。シャクナゲ、ツツジ、ビバーナム、アセビ、ミズキ、ウツギ、アジサイ、マグノリアなどは土地柄によく合い、彼女の美意識にもかなって、それぞれたくさんの品種が植えられ、庭園に彩りを加えています。 さまざまな針葉樹も庭のデザインポイントに。 例えば園内に700本以上が植えられている、大型のものでは10m以上にもなるシャクナゲは、開花時期の異なるさまざまな品種を選ぶことで、12月(Christmas cheer)から翌年9月(Polar Bear)まで次々に咲き継ぎます。花や葉の造形的な美しさとともに芳香も放ち、庭の四季を彩ります。 オレンジベースのツツジと銅葉のヤグルマソウ。 プリンセス・ストュルザは、気に入った品種はどんどん取り入れ、何年かかけて観察し、必要があれば場所を変え、結果、自分の望む庭のイメージに合わないものは容赦なく撤去するというスタイル(他の庭園愛好家に分けるなどして)で、庭の植物を選定していきました。この地の自然の気候の中でよい状態で生き残る丈夫さを必須条件とし、温室などの設置はしていません。 フォレストガーデンを抜けて、開かれた傾斜地へ続くエリア。さまざまな雰囲気の植栽の島々が芝地に連なっている。このエリアでは維持管理だけでなく、現在もプリンセスが育成した庭師たちにより新しい作庭が続けられている。 特定の植物を多品種網羅するという植物学的な意味でのコレクションではなく、野生種も希少な栽培種も含め、あくまで彼女の審美眼に沿って長年選ばれてきたことで、庭のための魅惑的な植物が膨大にコレクションされました。 こちらも、フォレストガーデンを抜けて、開かれた傾斜地へ続くエリア。 コレクションには希少な植物が多数含まれていますが、希少性よりも大切なのは、自らの庭のイメージと全体の調和です。オークやシラカバ、ヒイラギなどの自生の樹木は積極的に生かしながら、エキゾチックすぎる竹類やユーカリや木生シダなどは、ノルマンディーらしい風景にならないとして取り入れていません。逆に、冬の庭の見所となる針葉樹類の珍しい品種などは積極的に取り込んでいます。 オーナメンタルな樹木を積極的に利用。 また、「四季を通じて美しい庭」というコンセプトにとって“冬にも美しい庭”を実現することが特に重要な部分です。落葉樹の葉がすべて落ちた冬季に、開けた空間で何を見どころとするか。それは、常緑樹の姿や装飾的な風合いを持つ樹木の幹の色や形、質感などで、それらが冬の庭を魅力的にするということをフランスでいち早く広めたのも、プリンセス・ストュルザの功績の一つといえるでしょう。 プリンセスの贈り物 ノルマンディーの地での庭づくりに当たっては、95歳で亡くなる2009年まで、庭のコンセプト作り、植栽のプランニングばかりでなく、芝刈りや雑草取り、花がら摘み、樹木の剪定に至るまで、ガーデニング全般をプリンセス自らが率先して行っていました。 こちらはハンカチの木やシラカバがアクセントに使われ、グリーン〜ホワイトのグラデーションが爽やか。 また、庭園を公開し始めてからは、見学者の案内も自らが中心となって行ったプリンセス・ス トュルザ。彼女はお気に入りの植物について熱意を込めて見学者に語り、惜しみなく知識をシェアし、フランスの園芸愛好家たちや造園・園芸界に多大な影響を残すことになります。雇った庭師の数はそう多くなかったといいますが、そこは庭主自らが実際の庭仕事を知るガーデナーだったからこそ。実用的でローコスト・ローメンテナンスのナチュラル・ガーデニングを実現させるための知恵が、そこかしこに組み込まれている庭にもなったのです。 現在は遺族が所有する12ヘクタールのこの庭園は、プリンセス自らが庭仕事をレクチャーした4人の庭師たちによって維持管理が続けられています。ノルマンディーの地にやってきた北方のプリンセスの審美眼と植物への情熱、弛まぬ努力が生んだ、四季を通して美しい珠玉の庭園。機会があれば季節を変えて、何度でも訪れてみたいものです。 春先は美しい新緑に魅了されるこのエリア、秋には日本とはまた違った紅葉の風景が見られるはず。
-
フランス

【フランスの庭】ノルマンディー珠玉の庭園「モルヴィルの庭」を訪ねて
ノルマンディー地方の名園「モルヴィルの庭」 クリビエ邸の近くに位置する「オレンジの庭」コーナーは、イエロー〜オレンジ色の植栽に美しく彩られたアンチームな空間。 ノルマンディー地方、英仏海峡を望む断崖絶壁のあるヴァロンジュヴィル=シュル=メールの村は、冬も比較的に温暖かつ降雨量が多いという庭づくりに恵まれた環境ゆえか、フランスでも選りすぐりの名園が集まる場所として知られています。 その中でも、いつか訪れてみたいと思い続けていた庭が、フランス造園界の貴公子と呼ばれたパスカル・クリビエ (Pascal Cribier)が40年以上をかけてつくり続けた自邸モルヴィルの森の庭です。 フランス造園界の貴公子パスカル・クリビエ アメリカ原産の球根花カマッシアは、この地にもよく合い、手がかからずに美しく、クリビエもお気に入りだったとか。背景には満開のビバーナム。 パスカル・クリビエ(1953- 2015)は、モデル、仏ナショナル・チームに所属するカートのレーサーなど、造園家としては異色の経歴の持ち主。アートと建築を学んだのち、パートナーのエリック・ショケが1972年にモルヴィルの森の土地を購入したことがきっかけで、独学で庭づくりを始めます。富裕層が主な顧客であったことから造園界の貴公子と評され、また、施主との意見が合わないとさっさとプロジェクトから手を引くこともあったため、自由分子と呼ばれることも。 庭づくりにあたっては、自然に対峙しその意を汲みつつ、細部にわたって自身の美意識を貫きました。ルイ・ベネシュとともに手がけたチュイルリー公園の大規模改修プロジェクトなど、数多くの優れた庭園デザインが国内外に残っています。 モルヴィルの森の庭 かつては放牧地と森だった、急傾斜で断崖絶壁の海へと下っていく10ヘクタールの土地は、クリビエにとって実験の庭となります。急斜面ゆえに、トラクターなどを乗り入れることができず、庭づくりはクリビエとショケ、そして2人を支えた地元出身の庭師ロベール・モレルの3人によって、すべて手作業で行われました。3人亡き後の現在は、クリビエの弟ドニ・クリビエが庭園を継承し管理に当たっています。 下枝は残しつつ大胆に透かし剪定された独特のフォルムの松。 海への眺め、空への眺め 下枝は残しつつ大胆に透かし剪定された独特のフォルムの松。 樹齢40年以上の見事な姿で来訪者を魅了するクリビエらが植えた松の木々は、日本庭園とはまた違った形で厳しく剪定された、独特のフォルムが印象的。剪定は真向かいの海からの強風による倒木を避けるために必須であったとともに、独自のフォルムを形作る手段ともなりました。また空への眺めを確保し、光を通すために積極的に木々の枝を透かす剪定手法が、独自の美的な景観を作り出しています。 クリビエ邸の居間の窓からの海に向かう見事な眺望も、もともとあったものではなく、彼らが切り開いて作り出した景観。一刻一刻変わる海と空の光の表情は、一日見続けても飽きません。 自宅窓から海へ向かう眺めは、天候によって、また時間によって、さまざまに表情を変える。 悪条件もチャームポイントに すり鉢状の渓谷に続く芝地。しっかり形作られたオークの木がアクセントになっている。 丸みをつけつつ刻まれた溝は、手作業で作られた排水のための手段だが、見た目も美しく面白い効果を出している。 夏には野の花が溢れる草原を越えると、オークの大樹がある、すり鉢状に傾斜した芝地に至ります。粘土質の土壌ゆえに水はけが非常に悪いという条件を改善するために、手作業で刻まれた溝が、そのままデザインのアクセントとなっているのも見事なセンスで感動します。 植物へのこだわりから生まれるデザイン モルヴィルの庭では、在来の植物も栽培種の植物も、それぞれの特性に合う場所を選んで共存しています。植物の特性と土地の条件を見極めて適材適所に配置することは、その植物がしっかり育つためにも、その後のローメンテナンスのためにも必須。実地で庭づくりを学んだクリビエの植物への造詣は深く、「庭づくりをより完璧なものにするために」と協力を依頼された植物学者も驚くほどだったといいます。植物をよく知ることが、庭のデザインにとっても非常に重要だということを体得していたのでしょう。 海に向かって芝地を下る途中にあるカツラの木。枯れ葉の香りからカラメルの木とも呼ばれるが、フランスでは珍しい。 例えば、日本では方々に自生するシャクナゲやツツジ、カメリアなどは、フランスでは希少で栽培の難度が高い花木です。しかし、多雨に加えて酸性が強い土壌を利用して積極的に庭に取り入れた結果、いまでは見事に育った姿が見所の一つになっています。 日本には自生するお馴染みのカメリア。フランスでは難度の高い希少な花木として大人気。 カメリアやツツジがラビリンスのような一角を作っていたり、また、森の中にポツポツと植えられたカメリアが既存の森の植物たちと自然に調和した風景も魅力的。一見、自然のままに残したように見える森エリアの散策路には、自らのお気に入りのグラス類をさりげなく補植してボリュームを調整するなど、細かに手が入っています。 シラカバの枝葉を透かして柔らかい光が降り注ぐヒイラギのラビリンスは、オリジナルかつポエティック。 また、ヒイラギの生け垣とシラカバの木々を合わせたラビリンスは、シンプルな組み合わせながら詩的で素敵な空間に。合わせて植栽されたマンサクが咲く早春の情景をイメージして作られた場所だそうで、その頃にはさらに素晴らしい景観が見られるのだろうと想像します。 シャクナゲやカメリアなど、日本でも馴染み深い花木たちが、ノルマンディーの地でも愛されている。 庭の管理をラクにおしゃれにするデザイン 庭の至る所で出合うスカート型剪定の生け垣。 また、敷地のスペースや、車も通る道路の区切りに使われている生け垣の裾広がりの形にも注目です。スカート型剪定と呼ばれる、クリビエが好んで生け垣に使った形ですが、優雅な雰囲気を醸しつつ、じつはこれで下方の枝にも光が当たりやすくなり、また生け垣の下に生える雑草抜きをしなくて済むという、優れモノなのだそう。用の美の精神が至る所に行き渡ったクリビエのデザインの一例です。 庭園入り口近くのコーナー。デザイン性に富んだ果樹と灌木・多年草を合わせた植栽。 それぞれの植物への深い理解と愛情をもって、地の利も不利も生かしきって、自然と人為が美しく協調したクリビエの現代の庭。変奏曲を奏でるように美しくさまざまな表情を見せるそのデザインの根底には、自然と対峙し、完璧な美の世界を完成するために、どこまでも自らの意志を貫き、コントロールしようとする、フランスのフォーマル・ガーデンの伝統が滔々と流れているように感じられたのが印象的です。
-
フランス

【フランスの庭】パリのナチュラルガーデン「カルチエ現代美術財団の庭」
街中に季節を映す緑のショーケース 美術館の前に来ると、ショーケースのような高い透明なガラスの壁に囲まれた、自然の草地のような緑の風景が現れます。緑の空間の向こうには、ジャン・ヌーベル設計のガラス張りのシンプルモダンな美術館がそびえています。建築のボリュームはかなり大きいにもかかわらず、素材の透明感と緑の存在で、軽やかな心地よい空間になっているのはさすがです。 庭園には美術館の入場券がないと入れないのですが、ガラスの壁の外側からも、庭の様子が街に向かって展示されているかのようによく見えるので、近くを通行する人々も季節を映す緑を感じることができる設計になっています。 毎年この季節は、スノードロップ、スノーフレイク、水仙やクロッカスなどのスプリングエフェメラルが春の訪れを告げるように咲く姿が、じつにチャーミング。 早咲きの桜はいつも3月を待たずに満開になって、春先の庭に彩りを添えています。 街に自然を呼び込む庭「テアトラル・ボファニカム」 自然な草地といった雰囲気の庭園内。 庭の中に入ると、まるでごく自然な草地に来たよう。いわゆる雑草と呼ばれる、イラクサ(ネトル)など野生の植物たちにも居場所が提供されている、かといって放置された草地とは違う、庭らしく人の手が入った調和の取れたナチュラルな風景が広がります。 奥の小屋は映画監督アニエス・ヴァルダの作品「猫の小屋」(2016年)。 4,500㎡ほどのこの庭がつくられたのは、美術館の建物が建設されたのと同時期の1990年代前半。財団からのオーダーにより、ドイツ人アーティスト、ローター・バウムガルデンによって、アート作品として制作されたものです。中世の薬草書に由来する「テアトラル・ボファニカム Theatrum Bofanicum」という名がつけられたこの庭のコンセプトは、都市に自然を呼び戻すこと。それは植物のみならず、そこに集まる鳥や昆虫などを包括する生物多様性を回復しようとするプロジェクトでした。 18世紀には作家シャトーブリアンが住んだ大邸宅と古い庭園の跡地だった場所の由来を生かして、既存の大木などはできる限り残し、植栽にはイル=ド=フランスの気候に合った在来種を選んでつくられた庭には、鳥の声も心地よい、じつに自然な景観が育っています。 戻ってきた生物多様性 現在、この庭には200種ほどの植物が存在しますが、アーティストが気候に合った在来種を中心に選んで1994年に植栽した当初の181種のうち、いまも残るのは3割ほど。つまり当初のリストにはなかった多くの植物が、鳥や風に連れられ庭に招かれて、その一員となっています。 植栽の中には、フランスでも全国的に数が減少している在来種が多く含まれています。例えばジャイアント・ホグウィード(Heracleum mantegazzianum)は、樹液に触れると重篤な光線過敏を引き起こす危険な野草ですが、家畜に危険だという理由でフランスの田園風景からはほぼ消えてしまったその姿を残すために、植栽リストに入っているのだそう。 また、パリの街では巣作りができる場所が減ってしまい、生息する野鳥の種類も数も激減していますが、この庭は行き場をなくした野鳥たちの避難場所にもなっています。2012年と2016年に実施された自然史博物館の調査でも、保護を必要とするような希少な昆虫類、野鳥たちや、都会ではすっかり姿が見られなくなったコウモリの生息が確認されるなど、見かけがナチュラルというだけでなく、実際に生物多様性を迎え入れる場となった庭の姿が確認されています。 自然の庭を守る庭師 時とともに少しずつ植栽が変化し、庭を棲処とする生物たちが増えていくのをずっと見守ってきたのが、専属庭師のメタン・セヴァンさん。庭の始まりの時期からアーティストとともにその手入れをし、作庭意図を完璧に引き継いで管理を担ってきました。この庭の手入れは、除草剤や殺虫剤などの化学薬品は一切使わないナチュラルな方法で行われ、剪定した木や枯れ葉などを含む緑の廃棄物は園内でリサイクルすることによって外にゴミを出さない、灌水は夏場に長期にわたって雨が降らない時期の必要最低限に抑える、など環境に配慮したエコロジカルな管理が行われています。こうした環境への配慮は現在では当たり前になってきていますが、この庭が生まれた90年代前半には、まだまだ先駆的なアイデアでした。 運よく庭で作業をしているセヴァンさんを見かけたら、気さくに庭のいろいろなことを教えてくれます。例えば、手作業で行われる除草でも、すべて除去してしまうということではなく、それぞれがちょうどよく共存できるように、勢いの強すぎるものは数を減らし、あるいは場所を移すなどして、生物多様性に配慮しつつバランスを取っているのだそうです。 通常は雑草扱いだけれど、貧血予防などの薬効もあるネトルが白い花を咲かせていました。通常は葉っぱに触ると棘がチクチクしますが、花の時期は不思議と痛くありません。 温暖化時代への対応 手前右は、新たに加わったコルクガシ。倒木を避けるため切り倒さざるを得なかった古木も昆虫ハウスになって、新しい庭の景観を作ります。 作庭当初から30年近くが経ち、既存の老齢の大木も永遠の命というわけではないので、倒木の危険が出てくれば切り倒し、新たな植樹をせざるを得ません。また、パリ市内では気候温暖化の影響で、より暑さや乾燥に強い植栽が求められるようになってきています。庭の作者であるアーティストの意向を常に汲みつつも、セヴァンさんは環境の変化に対応した手入れの工夫を重ねています。新たに植樹する樹木には、地中海沿岸原産のコルクガシなど当初のリストにはなかった温暖化対応のチョイスが加わりました。長く庭を見守ってきたレバノン杉の大木は、倒木の危険から切り倒さざるを得ませんでしたが、昆虫ハウスという別の形で庭に生かされることになりました。 長年の間に少しずつ姿を変えながらも、心休まる空間とそこに宿るエスプリは変わらない自然の庭、そこには一人の人間が長く一つの庭を見守ってきたからこそ生まれる調和があるように思われます。 アートと庭の親和性 エントランスにはパトリック・ブランの垂直庭園、彼の初期の頃の作品です。 現代アート作品には、しばしば今の時代のその先を予感させるような先見的な眼差しが読み取れます。バウムガルデンの生物多様性の庭も、現在は当たり前になってきたエコロジカル、サステナブルな庭づくりを30年前から実現しているという点で先駆的だったといってよいでしょう。 階段状になった草地とカフェ広場。思い思いにくつろぐ人々。 アートから着想された、人も他の生物も心地よく居られる、心安らぐ調和に溢れた自然の風景が魅力の庭は、今日も庭に招かれた植物や動物たち、散策する大人も子どもも、みんな優しく迎え入れています。
-
フランス

【フランスの庭】皇妃ジョゼフィーヌの夢の棲みか マルメゾン城の庭園
皇妃ジョゼフィーヌの夢の棲みか 城館正面。Kiev.Victor/Shutterstock.com ナポレオンとジョゼフィーヌがマルメゾンの土地と城館を購入したのは、2人の結婚から3年目の1799年。まだナポレオンが皇帝として戴冠する前です。ナポレオンの遠征中にジョゼフィーヌがこの地所に一目惚れして購入を決め、ナポレオンが後から承認したという流れだったそうで、最初からジョゼフィーヌのイニシアチブの強さを感じさせます。当時のフランスきってのファッションリーダーだった彼女は、帝政スタイルの室内装飾で自分の好みに合わせて城館と庭園を整えさせました。このマルメゾン城の書斎ではナポレオンにより数々の重要な国事決定がなされ、また多くの華やかなレセプションが行われました。 現在は博物館となっているマルメゾン城内。Kiev.Victor/Shutterstock.com マルメゾンのイギリス風景式庭園 絵画のようなイギリス風景式の庭園が広がる。 当時は塀に囲われた部分のみでも70ヘクタールあったという庭園の姿にも、時代の流れとジョゼフィーヌのこだわりが反映されているのは言うまでもありません(現在残る部分は6.5ヘクタール)。フランス18世紀後半のイギリス式庭園の大流行を受けて、マルメゾン城の主庭にはイギリス風の自然な風景を取り入れた庭園がつくられました。大きな木々の間を静かに流れる小川にはピトレスクな橋が架かり、古代風の彫刻などがフォーカルポイントとなって、絵画のように構成された自然風景の中を、緩やかに曲線を描く園路が続きます。鳥のさえずりを聞きながら緑の中を散策すれば、自然と心が落ち着いてくることに気づくでしょう。フランスの庭園といえば、ベルサイユの庭園のようなフォーマルガーデンがイメージされるかもしれませんが、18世紀以降はイギリス風の自然風景式庭園が数多くつくられています。 オールドローズガーデンの様子、円形のガーデンシェッドがポイントに。 ライムツリーの並木越しに、オールドローズガーデンを眺める。 英国風庭園の一角、人工の岩石や古代風彫刻などが絵画的なシーンを演出。 アプローチはフォーマルスタイル、カマイユーの植栽 Kiev.Victor/Shutterstock.com 一方、城館へのアプローチとなる前庭部分は、メイン・ガーデンとコントラストをなすフォーマルスタイルで構成されています。正面玄関に向かう通路脇は、毎シーズン変わる華やかなボーダー植栽で彩られます。このボーダーは、やはり当時の流行だったカマイユー植栽という、1色の濃淡を主調とする植栽デザインで構成されています。 赤を主調にしたカマイユーの植栽。 ジョゼフィーヌの植物への愛 大温室はもうないが、かつてジョゼフィーヌが収集したバナナの木やベゴニア、ユーカリ、フェイジョアなど、ゆかりのある植物が並ぶ。 マルメゾンでは、イギリス式庭園の絵画的な自然風景、カマイユーのボーダー植栽や、季節のよい時期に飾られるオレンジやレモンの木のコンテナなどから、現在でも当時の姿を十分に偲ぶことができます。しかし、マルメゾンの庭の最大の特徴は、なんといってもジョゼフィーヌが主導した多彩かつ希少な植物コレクションでした。 気候が温暖でさまざまな熱帯植物が繁茂する、植物にとっての楽園のような土地、マルティニーク諸島の貴族の出だったジョゼフィーヌにとって、植物や動物の存在は身近に欠かせないものだったのでしょう。大きな温室を作らせ、海外からもたらされた希少な亜熱帯植物などをどんどん収集しました。遠い南の植物たちの姿に、故郷を懐かしく思い描いていたのかもしれません。とはいえ、そこには常に科学技術の進歩への関心がありました。彼女は、世界中の植物学者や研究者との情報交換ネットワークを築いていたといいます。 ダリアのコレクションも豊富。 モダンローズの母、皇妃ジョゼフィーヌ さらに、ジョゼフィーヌの庭園を歴史の中で不朽のものとしたのは、何よりもまず世界各地から250種を集めたというバラのコレクションでした。英仏戦争の戦火の下、ジョゼフィーヌが取り寄せた英国からのバラ苗は、英仏海峡を越えてマルメゾンに届けられたといい、バラへの想いは戦闘下のいずれの国をも無事に行き来することができたようです。 マルメゾンの庭ではさまざまな品種のバラを栽培していたため、自然交配による新品種が生まれ、それは人工交配によって新品種を生むモダンローズ開発の発端となりました。ジョゼフィーヌが現代に続くモダンローズの母と呼ばれる所以です。また、彼女は生きたバラの花を愛でるばかりでなく、その姿をとどめるため、画家を雇ってコレクションの植物を描かせました。それが、ジョゼフィーヌの宮廷画家として歴史に名を残すことになったピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ(1759-1840)です。 花の画家ルドゥーテのバラ図譜 ロサ・ケンティフォリア Pierre-Joseph Redouté, Public domain, via Wikimedia Commons 写真などはない当時、植物の姿を残す方法は、植物標本とするか、細密な植物画を描くかでした。ルドゥーテの描いたマルメゾンのバラの数々は、そうした意図のもと『バラ図譜』として出版され、植物画の金字塔として大変な人気を博しました。というのも、彼が描いた数々のバラの姿の正確さや精彩さ、それに加わる優美さは、単なるテクニカルな植物画を超えた美術作品としての魅力を放ち、ルドゥーテの『バラ図譜』によって、植物画は芸術としての領域を切り拓くことになったのです。 ●「バラの画家」ルドゥーテ 激動の時代を生きた81年の生涯(1) 幻のオールドローズガーデン ルドゥーテの『バラ図譜』に描かれたオールドローズの姿から、私たちはジョゼフィーヌがマルメゾンの庭で愛でたバラの数々を知ることができます。では、マルメゾンのバラ園は、一体どんな姿だったのでしょうか? じつは、独立したバラ園としてのガーデンが構想されるようになったのは19世紀に入ってから(ライレローズのバラ園など)で、ジョゼフィーヌの当時のマルメゾンのバラは、バラ園としてまとまった形のデザインの中で栽培されていたわけではありませんでした。鉢植えで栽培され、寒い時期には温室で管理して、よい季節には庭園を飾ったバラもあれば、城館の室内を飾るため、あるいは衣裳の飾りや髪飾りとして使うために栽培されているバラもあるなど、さまざまだったようです。マルメゾンのバラは希少なコレクションとして存在するばかりでなく、生活の中にその美しい姿と香りが溢れていたことでしょう。 現在の庭園には、2014年にジョゼフィーヌ没後200年を記念して作庭されたオールドローズガーデンがあります。ここは、彼女のコレクションだったオールドローズの品種を集めた庭で、バラの季節にはジョゼフィーヌの愛でた数々のバラを堪能することができます。 オールドローズガーデンの様子。花期は短いが、バラの香りでいっぱいに。 ワイルドフラワーメドウ(花咲く草原) ワイルドフラワーのメドウガーデン。 最後に、城館内からもよく見えるワイルドフラワーメドウにご案内しましょう。自然といっても整った印象が強い英国式庭園の一角に広がる、ワイルドフラワーメドウの飾らない自然さは心和むとともに、とても印象的。現代のサステナブルな庭づくりを反映しているのかな、と思ったら、じつはジョゼフィーヌの時代に彼女の希望によりつくられていたものを再現しているのだそう。素朴なワイルドフラワーが咲く草原もまた、彼女が幼い頃に親しんだマルティニークの自然を思わせる風景だったのでしょう。 嫡子ができないことを理由に離婚した際、ナポレオンはジョゼフィーヌにマルメゾンを与え、美しい庭園の自然と花々に囲まれて、彼女は亡くなるまでをこの地で過ごします。曇り空の多いイル・ド・フランスにあって、遠い故郷へ想いを馳せることのできる植物が溢れるマルメゾンの庭園は、どれほどにか彼女の心を癒やしたことでしょう。
-
フランス

【フランスのバラ園】王妃の賭けから生まれたパリのバガテル公園、知られざる魅力
バガテルの誕生 マリー・アントワネットとアルトワ伯爵の賭け 現在のバガテル公園に繋がる城と庭園がつくられる契機となったのは、18世紀、王妃マリー・アントワネットの気まぐれから始まった、ルイ16世の弟アルトワ伯との賭けでした。1775年、フォンテーヌブロー城からの帰り道で、王妃はバガテルの土地を購入したばかりだった当時20歳のアルトワ伯に、100日で城を建てることができたならば10万リーヴル払うとの賭けを提案します。この遊び心の挑戦に、では2カ月後には拙宅での雅宴にご招待しましょう、と受けて立ったアルトワ伯。なんと64日間で小さな城(シャトー)と建物周りの庭園を完成させ、見事この賭けに勝利しました。 バガテル城、別名「アルトワ伯のフォリー」をフランス式フォーマル・ガーデンから眺める。 こうして誕生したのが、当時は「アルトワ伯のフォリー」と呼ばれたバガテルのシャトー(城)です。アルトワ伯の依頼を受けた建築家ベランジェは1日でプランを描き上げ、工事には900人を動員、パリ中の工事現場から建築資材などを集め、掛け金の10倍以上の予算を費やして完成させたといわれます。 「フォリー」とは、18世紀当時、大抵は庭園内や緑に囲まれた田舎に造られた、住居目的ではなく、休憩や食事、遊興などに使われる趣向を凝らした建物でした。アルトワ伯のフォリーは、破格の特急工事にもかかわらず、当時の最新流行だった新古典主義様式の建築の傑作の一つに数えられる出来栄えで、ラテン語で「小ぶりだが、非常によく構想された」という銘が建物に掲げられているほどです。 このシャトーは混乱のフランス革命期を経た今も現存するものの、保存状態が悪く立ち入りはできない状況。ですが、再オープンできるよう、目下修復工事が進められているところです。 18世紀の最新流行、アングロ=シノワ庭園 庭園の構成は伝統に従い、城の周りはフォーマル・ガーデン、そして、イギリス風景式庭園の影響を受けてアングロ=シノワ様式といわれる、フランスの18世紀に大流行したスタイルの庭園もつくられました。この庭園づくりで活躍したのが、スコットランド人の造園家で植物学者のトーマス・ブレイキー。自然の風景のように樹木が所々に配置された広い芝生を巡る園路が緩やかな曲線を描き、要所のフォーカルポイントには、彫刻などのほか、世界のさまざまな文明からインスパイアされたデザインの庭園建築「ファブリック(英:フォリー)」が配置されました。エキゾチックな中国風(シノワ風)の東屋や橋、オベリスクや人工洞窟などはその中でも定番ですが、そうしたファンタジックな装飾で彩られた庭園は、非日常感溢れる「おとぎの国」になぞらえられました。元来舞台装置のようにハリボテ的な素材が使われた当時のファブリックのつくりは脆弱で、残念ながら時の流れとともにその姿は失われてしまっています。 18世紀後半のフランスで流行したアングロ=シノワ様式と呼ばれる、自然の風景の中を散策する庭園。絵画のような理想の自然美、調和が表現される。 中国風デザインのファブリックの一つ「パゴダ」から庭園を眺める。 パリのイギリス貴族の邸宅と庭園に 拡張されたイギリス風景式庭園。 19世紀の第二帝政期下、パリ育ちのイギリス貴族で美術収集家でもあったハートフォード侯爵の手に渡ったバガテルの城と庭園は、大きな変化を迎えます。侯爵は南北の土地を買い足し、バガテルはほぼ現在の姿に近い24ヘクタールに拡大されます。平屋だった城に2階部分を増築するとともに、拡大した公園の北側には大きな池を囲む形のイギリス風庭園を、南側の庭園部分にはオランジュリーなどを作らせました。また、皇帝夫妻とも懇意だった侯爵は、皇太子が馬術のレッスンを受けるための特別の馬術場を設けます。パリ市内に近い南側には、ロココ調の豪華な鋳鉄の門のある正面入り口が新たに設けられました。 現在はバラ園を一望できる皇后のキヨスク(東屋)。現在のバラ園の場所には、かつては馬場があった。侯爵と懇意だった皇帝夫妻はしばしばバガテルを訪れ、皇后ウージェニーはこのキヨスクから皇太子が馬に乗るのを眺めた。 余談になりますが、このバガテルを引き継いだ子息リシャール・ウォーレスも名高い美術収集家。珠玉の個人コレクションの名にふさわしいロンドンのウォーレス・コレクションは、未亡人がイギリス政府に収集品を寄贈してできた美術館です。 公共公園とバガテルのバラ園の誕生 20世紀初頭のバガテルに、当時の遺産相続人が城の家具調度を売り払い、土地を分割分譲しようとする危機が訪れます。この危機に際し、パリ市が散逸しかけた城と庭園を買い上げ、1905年、バガテル公園は公共の都市公園となりました。 バラ園はスタンダード仕立てやトレリス仕立てのつるバラなどで構成されるフォーマル・スタイル・ガーデン。構造の中心となるのは、木材のアメリカンピラーとフェストン(花綱)を飾るバラの花々。 そのイニシアチブを取った造園家ジャン=クロード=ニコラ・フォレスティエが公園整備を行った際に、馬術場は現在のバラ園へと生まれ変わりました。バラ園を見下ろす東屋は、皇后が皇太子の乗馬の様子を見守った場所だったのだそうです。ライレローズの創設者として知られるグラブロー氏の惜しみない協力を得て、約9,500本のバラ、1,100品種を保持するバラ園が誕生して程ない1907年、現在は世界中のロザリアンが注目するイベントとなったバラ新品種の国際品評会が始まります。この種のバラのコンクールとしては、世界で最初の品評会でした。 バラ園の奥には、バラの季節が終わる頃に最盛期を迎える菖蒲園がつくられている。 フォレスティエは、バラをはじめとしたさまざまな植物コレクションを擁する庭園としてバガテル公園を構想しており、バラ園のみならず、アイリスガーデン、クレマチスや牡丹などの多年草ガーデンなどがつくられます。 19世紀ハートフォード侯爵の頃につくられた「庭師の家」。煉瓦造りはブーローニュの森の周りの建物に合わせたのだそう。コテージガーデンのような花が溢れる初夏の風景。 「庭師の家」の続きには、アスターなどさまざまな宿根草の「展示庭園」。春夏には連続するフジのアーチが見事。 変化し続けるバガテル、地中海ガーデン ロココ調のメインエントランスからは、常緑樹で冬でも緑溢れる落ち着いた園路が続く。 公園のメインエントランスであるロココ調の正面門からは、19世紀のパリの公園といった雰囲気の、大きく育った常緑樹に覆われたエレガントな園路が奥に向かって延びています。その先に進んでいくと、歴史的な面影が感じられる広い芝生面に大きな樹木の植栽、水のしつらいと、洞窟や滝などの風景式庭園とはまた違った、より明るくワイルド感のあるコーナーに行き当たります。 地中海性気候の植物で構成された地中海ガーデン。パリでも気候温暖化に適応する植栽が模索されている。 ここは、1999年末にフランスで各地の森林や庭園に甚大な倒木被害を引き起こした大嵐の際、バガテルでも多数の倒木があってすっかり様相が変わってしまった場所に、新たにつくられた地中海植物のガーデン。被害で空いてしまったスペースには、地中海植物の象徴的な存在であるオリーブやツゲの木々、エニシダやラベンダーなどが溢れ、現代的なナチュラル感とともに、植物コレクションの幅を広げる新しい庭空間に生まれ変わりました。 幾層もの歴史の面影を残しながら、常に変化し続けるバガテル公園。バラの季節はもちろん、いつ訪れても変化に富んだ穏やかな散策が楽しめる、とっておきの庭園です。 公園の中では孔雀や鴨が至る所を自由に優雅に闊歩しています 。